≪第76号アリアCD新譜紹介コーナー≫
その2 4/22〜
マイナー・レーベル新譜
歴史的録音・旧録音
メジャー・レーベル
国内盤
映像
|
4/25(金)紹介新譜
マイナー・レーベル新譜
ACADEMIA DE MUSICA DE SANTA CECILIA DE LISBOA
(リスボン・サンタ・セシリア音楽アカデミー)
|

AMSC 01
\2400
【旧譜 再入荷】 |
ルイ・パイヴァ前作 南欧のブクステフーデ ファロ大聖堂のオルガン
ディートリヒ・ブクステフーデ(1637-1707):
わが愛する神に BuxWV179/前奏曲ト短調
BuxWV163
カンツォネッタ ト長調 BuxWV172/トッカータ
ト長調 BuxWV165
天におられるわれらの神 BuxWV207/トッカータ
ト長調 BuxWV164
カンツォーナ ハ長調 BuxWV166/前奏曲ト長調
BuxWV162
フーガ ロ長調 BuxWV176/イエス・キリスト、われらの救い主
BuxWV198
フーガ ハ長調 BuxWV174/暁の星の何と美しいことか
BuxWV223
今こそ主をたたえよ、わが魂よ BuxWV212
今こそ主をたたえよ、わが魂よ(1,2,3)BuxWV213(ヘ長調に移調して演奏) |
ルイ・パイヴァ(オルガン)
|
|
録音:2007年7月2-5日、ファロ大聖堂、ファロ、ポルトガル
使用楽器:1710-1720年、ハンス・ハインリヒ・クーレンカンプ製
(2007年、ディナルテ・マシャド修復完了)
ポルトガル南部の港湾都市ファロ。その大聖堂のオルガンの修復完了に合わせて制作されたCD。なぜ南欧ファロのオルガンでブクステフーデなのか?それは、オルガン製作者であるハンス・ハインリヒ・クーレンカンプが北ドイツの偉大なオルガン製作家アルプ・シュニトガー(1648-1719)の弟子であり、また、修復が完了した2007年が北ドイツのリューベックで活躍しシュニトガーのオルガンをたいへん気にっていたブクステフーデの没後300年に当たっていたからとのことです。
外装に規格番号の表示がございません。
|
ALMAVIVA
|
|
|
現代スペイン女性作曲家たちのハープ作品集
ラウラ・ベガ(1978-):
私を覆う夜を超えて [Mas alla de la noche
que me cubre...]
マリア・ホセ・アレナス(1983-):マクトゥーブ
II [Maktub II]
メルセデス・サバラ(1963-):
雪の上の雪 [Nieve sobre nieve]/降りしきる雪
[Incesante nieve]
ロサ・マリア・ロドリゲス・エルナンデス:ルスエロ
[Luzeulo]
ディアナ・ペレス・クストディオ(1970-):オルフェオ・ジップ
[L'Orfeo.zip]
コンスエロ・ディエス(1958-):存在と時間
[Ser y Tiempo]
ドロレス・セラノ・クエト(1967-):裂かれた道
[Caminos rasgados]
マリサ・マンチャド(1956-):
アンヘラのための7つの小品 [Siete piezas
para Angela]
マリア・ルイサ・オサイタ(1938-):幻想曲
[Fantasia]/思い出 [Recuerdos]
イルミナダ・ペレス・フルトス(1972-):
ハープのタペストリーの上で [Sobre el
tapiz del arpa]
カルメ・フェルナンデス・ビダル(1970-):灰色の霧
[Brume Grisatre] |
クリスティナ・モンテス・マテオ(ハープ) |
|
録音:データ記載なし
クリスティナ・モンテス・マテオは1984年スペインのセビリャに生まれ、セビリャのマヌエル・カスティリョ音楽院、ロンドンの王立音楽アカデミーで学び、シュターツカペレ・ベルリン・オーケストラ・アカデミーのメンバーとしてダニエル・バレンボイムの指導を受けたハープ奏者。日本ハープコンクール他数々の国際コンクール入賞。2013年現在バレンシア州立管弦楽団(ロリン・マゼール音楽監督)のメンバー。
|
| |


DS 0130
\2400 →\2190
【未案内旧譜】 |
トゥリーナ(1882-1949):室内楽作品集
弦楽四重奏曲ニ短調「ギター風」Op.4(1911)
セレナード Op.87(1934)
闘牛士の祈り Op.34(1925)
ピアノ五重奏曲ト短調 Op.1(1907)(*) |
ブレンノ・アンブロジーニ(ピアノ(*))
グリニッジ弦楽四重奏団
マイケル・トマス、
ブライアン・ブルックス(ヴァイオリン)
ジェーン・アトキンズ(ヴィオラ)
テュモシー・ヒューズ(チェロ) |
|
録音:1999年6月、セント・ピーター・イン・チェインズ教会、ロンドン、イギリス
発売:2001年
前ディストリビューターからも未案内だった旧譜商品。ピアノ五重奏曲
Op.1はフランク流の循環形式による力作。弦楽四重奏曲
Op.4は先輩アルベニス(1860-1909)から「(フランク流を脱して)スペイン的な音楽を目指すべき」という助言を受けたトゥリーナが自己のスペイン的様式を確立した作品と言われています。
|
 ALTHUM ALTHUM
|
|
|
16&17世紀イベリア半島のオルガン音楽/アロウカ修道院のオルガン
ディエゴ・デ・コンセイサン(17世紀;ポルトガル):バタリャ[戦争]第5旋法
アントニオ・デ・カベソン(1510-1566;スペイン):パヴァーヌとそのグロサ
アントニオ・カレイラ(1530頃-1594頃;ポルトガル):
アヴェ・マリア(4声)/4声の歌とグロサ
セバスティアン・アギレラ・デ・エレディア(1561-1627;スペイン):
作品第8旋法(アルト:エンサラダ)/ティエント・デ・ファルサス第6旋法
セバスティアン・ドゥロン(1660-1716):ティエント第1旋法−左手のガイティリャ
マヌエル・ロドリゲス・コエリョ(1555-1635;ポルトガル):
テント第2番第1旋法「デ・ラ・ソ・レ」
フランシスコ・コレア・デ・アラウホ(1575-1654;スペイン):
ソプラノ声部のメディオ・レヒストロによるティエント第8旋法
ジュアン・カバニリェス(1644-1712;スペイン):
パッサカリア第3番第3旋法/イタリア風クラント
ペドロ・デ・アラウジョ(1610-1684;ポルトガル):
2つのソプラノ声部のメイオ・レジストロによる(作品)第2旋法
ファンタジア第4旋法
不詳(18世紀初頭、アントニオ・マルティン・イ・コルの曲集から;ポルトガル)
バタリャ・ファモザ[有名な戦争] |
ルイ・パイヴァ(オルガン) |
|
録音:2013年7月18-20日、アロウカ修道院、アロウカ、ポルトガル
使用楽器:1739年、ドン・マヌエル・ベント・ゴメス・フェレイラ製(2009年、ゲアハルト・グレツィング修復)
「ラッパ奏法」(水平方向に突き出したラッパ管でトランペットやトロンボーンのような音を出す)や音栓分割(一段の鍵盤の高音部・低音部で異なる音色にする)の使用といった独特の発展を遂げたイベリア半島(スペインとポルトガル)のオルガン音楽と、その発展をもたらしたイベリア式バロック・オルガンの響きを堪能できる一枚。メディオ・レヒストロ(スペイン語)/メイオ・レジストロ(ポルトガル語)は音栓分割、ティエント(スペイン語)/テント(ポルトガル語)およびグロサは変奏曲の一形式。
ポルトガル第二の都市ポルト近郊のアロウカにある修道院のオルガンは典型的なイベリア・バロック・タイプの楽器。様々な音栓から生み出される音色は極めて個性的で、小鳥のさえずりを模した効果音(ペダル機能)まで現れます。現代ポルトガルを代表するオルガン奏者の一人でありイベリアの歴史的オルガン演奏の第一人者であるルイ・パイヴァによる演奏はまさに文句なし。絶品です。「オルガンは地味で単調で…」という先入観は、これらの音楽、この楽器、そしてこの奏者にはまったく当てはまりません。
収録時間約70分。スペイン・ポルトガル料理のフルコースを満喫した気分になれます。(株式会社サラバンド代表取締役
金田敏也)
ルイ・パイヴァ(1961年生まれ)はリスボン高等技術学校電気工学を修了、リスボン国立音楽院でジョアキム・シモンイス・ダ・オラにオルガンを、クレミルデ・ロザド・フェルナンデスに通奏低音を師事、さらにバルセロナ(スペイン)でモンセラト・トゥレンに、サラゴサ(スペイン)でホセ・ルイス・ゴンサレル・ウリオルに教えを受けたポルトガルのオルガンおよびチェンバロ奏者。1989年から2011年までリスボン国立音楽院教授、2014年現在リスボン・サンタ・セシリア音楽アカデミー学長を務めています。
■ハードカヴァー・ブック仕様。本体・外装の規格番号表示は「A
006」となっておりますが、弊社では「ALTHUM
006」として管理いたします。(代理店)
|
| |

ALTHUM 004
\2400
【旧譜 再入荷】 |
フェルナンド・デ・アルメイダ(1600頃-1660):
聖木曜日のレスポンソリウム集
オリーヴ山で/わが魂は悲しむ/そこでわれらは彼を見た/わが友が
極悪の商人ユダは/弟子のうちの一人が/われは子羊のごとく
民の長老らは
平日のミサ; キリエ/サンクトゥス/ベネディクトゥス/アニュス・デイ |
カペラ・パトリアルカル
モニカ・サントス、
モニカ・モンテイロ(ソプラノ)
カロリナ・フィゲレド、
カタリナ・サライヴァ(アルト)
ジョアン・モレイラ、
アンドレ・バレイロ(テノール)
マヌエル・レベロ、
ティアゴ・シルヴァ(バス)
セルジオ・シルヴァ(オルガン)
ジョアン・ヴァス(指揮) |
|
録音:2011年1月17-19、24日、聖ニコラウ教会、リスボン、ポルトガル
フェルナンド・デ・アルメイダはポルトガルの作曲家・キリスト騎士団修道士。ドゥアルテ・ロボ(1565頃-1646)に師事しトマルのキリスト教修道院楽長を務めました。最近までほとんど顧みられることがなかったものの、その厳格な対位法や修辞的表現法は彼がポルトガル音楽史において重要な人物の一人であったことを裏付けています。
カペラ・パトリアルカルは16世紀から19世紀のポルトガル音楽を演奏するために2006年に創設された声楽アンサンブル。指揮者のジョアン・ヴァスはポルトガルにおける歴史的オルガン演奏の第一人者です。
ハードカヴァー・ブック仕様。本体・外装の規格番号表示は「A
004」となっておりますが、弊社では「ALTHUM
004」として管理いたします。(代理店)
|
| |
|
|
フェルナンド・ロペス=グラサ(1906-1994):子供のための歌
あの雲、他 [Aquela nuvem e outras] (全22曲)
ティアの歌集 [As Cancoezihnas da Tila]
(全11曲)
子供たちのためのクリスマス [Natal para
as criancas] (全10曲) |
リスボン・サンタ・セシリア音楽アカデミー児童合唱団(独唱、斉唱、合唱)
イネス・メスキタ、
ジョアナ・アルヴェス(ピアノ)
アナ・パウラ・ロドリゲス、
アントニオ・ゴンザルヴェス、
アルトゥル・カルネイロ(指揮) |
|
録音:2005-2007年、スタジオ・ナモシェ、リスボン、ポルトガル
ハードカヴァー・ブック仕様。本体・外装の規格番号表示は「A
007」となっておりますが、「ALTHUM 007」として管理いたします。(代理店)
|
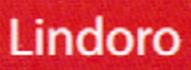 LINDORO LINDORO
|
|
|
Raclerie Universelle 17世紀フランスのギター音楽
フランチェスコ・コルベッタ(1615-1681):組曲イ短調
前奏曲,アルマンド,クラント,サラバンド,ジグ,パサカーユ
アンリ・グルネラン(1625-1700):組曲ニ短調
前奏曲,アルマンド,クラント,サラバンド,ジグ,パサカーユ
フランソワ・ル・コック(確認できる活躍期:1685-1729):シャコンヌ
不詳:ニ調の小品集
Mariez Moy,La Vielle,La Bonita,L'Otonera,La
Forlane
ロベール・ド・ヴィゼ(1650頃-1732頃):
組曲ト長調; 前奏曲,アルマンド,クラント,サラバンド,ジグ
アポロンの入場(アルマンド)/「ロラン」のロジスティーユ
マスカラード/ヴィラネル/パサカーユ
フランチェスコ・コルベッタ:ラ・ストゥアルダ(サラバンド)/アルマンド |
イスラエル・ゴラーニ(バロックギター) |
|
録音:2012年3月14-17日、プロテスタント教会、テルカプレ、オランダ
17世紀後半のフランスで隆盛を極めたバロックギターのための音楽で構成されたアルバム。タイトルは「普遍的な掻き鳴らし」や「掻き鳴らされる音の世界」と訳せばよいのでしょうか。
イスラエル・ゴラーニはテルアヴィヴ大学で音楽学を修めた後、フレッド・ヤーコプス(アムステルダムのスウェーリンク音楽院)とエリザベス・ケニー(ロンドンの王立音楽アカデミー)にリュートとテオルボを師事。数多くのアンサンブル、オーケストラ、プロジェクトに参加しながらバロックギターも習得し、2010年のユトレヒト古楽祭でバロックギター奏者としてソロ・デビューしました。
|
| |
|
|
16世紀グラナダの楽師たち
[I. 宗教的領域]
フアン・デ・ウレデ(確認できる活躍期:1451-1482頃没):
Pange lingua (5声), Quinta Boz (Baso).
Morales (*)
フランシスコ・ゲレロ(1528-1599):O Maria
(4声)
クリストバル・デ・モラレス(1500頃-1553):Veni
Domine (4声)
フランシスコ・ゲレロ:Ave Maria (4声)
クリストバル・デ・モラレス:Inter vestibulum
(4声)
フランシスコ・ゲレロ:Dixit Dominus Petro
(5声) / Benedictus (4声)
ロドリゴ・デ・セバリョス(1525/1530頃-1581):Agnus
Dei (5声) (*)
[II. 大学]
フランシスコ・ゲレロ:Christe potens rerum
(5声) (*)
ペドロ・ゲレロ(1520頃-?):O beata Maria
(4声)
ジョスカン・デプレ(1450/55頃-1521):
Lauda Sion [Je ne me puis tenir d'aimer]
(5声)
ペドロ・ゲレロ:Quinque prudentes virgines
(4声)
オルランドゥス・ラッスス(1532-1594):O
invidia, nemica di virtute (5声)
ピエール・サンドラン(1490頃-1560以後):Doulce
memoire (4声)
トマ・クレキヨン(1505/1515頃-1557):Prenez
pitie
フランシスコ・ゲレロ:O quam super terram
(5声) (*)
[III. 家庭的な場]
ニコラ・ゴンベール(1495頃-1560頃):J'ay
conge prins (4声)
フランシスコ・ゲレロ:Mi ofensa es grande
(5声)
ジャック・アルカデルト(1507頃-1565):Il
ciel che rado (4声)
フィリップ・ヴェルドロ(1480/1485頃-1530/1532頃、1552以前):
Madonna no so dir tante parole (5声)
不詳:S'io fusse certo di levar per morte
(4声) (*)
オルランドゥス・ラッスス:Susanne ung jour
(5声)
トマ・クレキヨン:Pane me ami duche
[IV. 都市の道路や広場で]
フランシスコ・ゲレロ:Todos aman (5声)
/ Si el mirar (5声)
フィリップ・ド・マンシクール(1510頃-1564):Yo
te quiere matare (4声) (*)
トマ・クレキヨン:Pour ung plaisir (4声)
クレメンス・ノン・パパ(1510/1515頃-1555/1556頃):
Ne scauroit on trouver bon messaigier
de France (4声) (*)
フランシスコ・ゲレロ:No me podre quexar
(5声)
ループス・ヘリンク(1494頃-1541):Ung
jeune moine (4声) (*)
フランシスコ・ゲレロ:Subiendo amor (5声)
/ Adios mi amor (5声)
アンサンブル・ラ・ダンスリー
フェルナンド・ペレス・バレラ(コルネット[ツィンク]、コルネタ・ムダ、サックバット、
チリミア・テノル、クルムホルン、リコーダー)
フアン・アルベルト・ペレス・バレラ(コルネット[ツィンク]、コルネタ・ムダ、チリミア、
バホンシリョ、クルムホルン、リコーダー)
ルイス・アルフォンソ・ペレス・バレラ(サックバット、クルムホルン、リコーダー)
エドゥアルド・ペレス・バレラ
(バホン[ドゥルツィアン]、バホンシリョ、チリミア、クルムホルン、リコーダー)
マヌエル・ケサダ・ベニテス(サックバット) ホセ・メンデス・ガルバン(リコーダー)
|
|
録音:2012年12月16-20日、サクロモンテ修道院教会、グラナダ、スペイン
グラナダのマヌエル・デ・ファリャ図書館の写本975番所収の楽曲(*)を中心に、16世紀のグラナダで活躍した楽師たち(管楽合奏団)のレパートリーを取り上げたアルバム。タイトルの「Yo
Te Quiere Matare」(マンシクールの収録曲名)を直訳すると「私はあなたを殺してしまいたい」になりますが、殺伐とした音楽は一つもありませんのでご安心ください。
ラ・ダンスリーは1998年に創設されたスペインのピリオド管楽器アンサンブル。
|
| |
|
|
バロック音楽に反映されたラテンアメリカの音楽
アントニオ・ベルターリ(1605-1669):シャコンヌ
ハ長調
ホセ・マリン(1618-1699):声とギターのための51のトノ
から
乙女よ、あなたの移り気に [Nina, como
en tus mudanzas]
不詳(17世紀):
修道士グレゴリオ・デ・スオラの写本 から
マリサパロス [Marizapalos]
ヤコプ・ヘルマン・クライン(1688-1748):
チェロと通奏低音のための6つのソナタ
Op.4 から ソナタ イ短調
不詳(17世紀):ペルーのトルヒリョの写本(マルティネス・コンパニョン写本)から
ランチャス・パラ・バイラル [Lanchas
para Baylar]
ラ・セロサ [Tonada La Selosa] (ランバイエケの村のトナダ)
エル・コンゴ [El Congo] (歌踊りのトナダ)
アントニオ・ヴァレンテ(1530-1585)−不詳:
ナポリのガイヤルド−トルベリーノ−いかれたハラベ
[Jarabe Loco] |
ロス・テンペラメントス
スワンティー・タムス・フライアー(ソプラノ、リコーダー)
アンニカ・フォーグルプ(リコーダー)
ウゴ・ミゲル・デ・ロダス・サンチェス(バロックギター)
ネストル・ファビアン・コルテス・ガルソン(バロックチェロ)
ナディーネ・レンメルト(チェンバロ) |
|
録音:2013年11月20-23日、聖コスマス&ダミアン教会、ルンゼン、ドイツ
スペイン、およびスペイン領だったことのあるオランダと南イタリアからヨーロッパに流入した中南米の音楽をテーマとするアルバム。ホセ・マリンはスペイン、アントニオ・ベルターリとアントニオ・ヴァレンテはイタリア、ヤコプ・ヘルマン・クラインはオランダの作曲家。
中南米起源とされるシャコンヌに始まりメキシコの民俗舞曲ハラベで閉じられる絶妙なプログラムです。
タイトルの「De la Conquista y otros Demonios」を直訳すると「征服の悪魔と他の悪魔」になりそうですが、あまり考えずに楽しむほうが良さそうです(最近の当レーベルはアルバム・タイトルに凝り過ぎ?)。
ロス・テンペラメントスはドイツのブレーメン芸術大学古楽アカデミー卒業生により2009年に結成されたアンサンブル。
|
| |
|
|
ガエターノ・ブルネッティ(1744-1798):
弦楽三重奏のためのディヴェルティメント
第4集(1784)
第1番イ長調 (L.145)/第2番変ロ長調
(L.146)/第3番ハ短調 (L.147)
第4番ハ長調 (L.148)/第5番変ホ長調
(L.149) |
カルメン・ベネリス
ラウル・オレリャナ(ヴァイオリン)
パブロ・アルマサン(ヴィオラ)
ギリェルモ・マルティン(チェロ) |
|
録音:時期の記載なし、闘牛博物館図書室、ロンダ、マラガ県、スペイン
ガエターノ・ブルネッティはイタリアのファーノに生まれ、ピエトロ・ナルディーニに師事した後1762年頃スペインのマドリードに移住。1770年に国王カルロス3世の王太子(アストゥリアス公)付き音楽教師に就任。1788年、王太子がカルロス4世として即位するとともに王の私設楽団のヴァイオリニストとなり、さらに1795年に王宮楽団が創設されるにあたってその指揮者に就任しました。450を超える作品を残したとされていますが、生前・没後とも出版された作品は少なく、演奏・録音される機会も多くありません。
当盤は好評を博した「弦楽四重奏曲集」(NL
3011)に続くカルメン・ベネリスによるブルネッティ第2弾。
カルメン・ベネリスは2005年に創設されたスペインのピリオド楽器アンサンブル。ヴィオラのパブロ・アルマサン(・ハエン)とチェロのギリェルモ・マルティン(・ガミス)を核として演奏曲目ごとにメンバーを補強する形をとっています。
今回参加のラウル・オレリャナは南米チリ出身、ミラノ市立音楽院古楽科でエンリコ・ガッティに師事したヴァイオリン奏者。音楽、演奏ともにすばらしく、同時代のイタリア人で同様にマドリードで活躍したボッケリーニも真っ青といったところ。
実際にブルネッティの再評価を進めてくれそうな一枚です。
その「弦楽四重奏曲集」 |
|
|
ガエターノ・ブルネッティ(1744-1798):弦楽四重奏曲集
イ短調 Op.2 No.4 (L.153)/ト長調 Op.3
No.6 (L.161)
変ロ長調 Serie 8 No.7 (L.196)/ニ長調
Serie 8 No.10 (L.199) |
カルメン・ベネリス
ミゲル・ロメロ・クレスポ、
ラファエル・ムニョス=トレロ・サントス(ヴァイオリン)
パブロ・アルマサン・ハエン(ヴィオラ) ギリェルモ・マルティン・ガミス(チェロ) |
| 録音:時期の記載なし、聖復活病院内行事サロン、ウトレラ、セビリャ県、スペイン |
|
| |


MPC 0709
\2400 →\2190
【旧譜 再入荷】 |
キアラ・バンキーニ(ヴァイオリン)
ジャン=フィリップ・ラモー(1685-1767):
クラヴサン合奏曲集(クラヴサン・アン・コンセール) |
キアラ・バンキーニ(ヴァイオリン)
マリアンネ・ミュラー(ヴィオラ・ダ・ガンバ)
フランソワーズ・ランジュレ(チェンバロ) |
|
録音:1999年11月、ヌーシャテル芸術歴史博物館、フランス
使用楽器:1632年、ヨハネス・ルッカース製(チェンバロ)
女性ピリオド楽器奏者のトリオによる当レーベルのベストセラー盤が再生産されました。
|
MUSICAS FESTIVAS DE FERNANDO LOPES−GRACA
|


MFFLG 1-2
(2CD)
\3600 →\3290
【旧譜 再入荷】 |
フェルナンド・ロペス=グラサ(1906-1994):お祝いの音楽
[CD 1]
お祝いの音楽(1962-1994)
第1番「テレザ・マルガリダの5歳の誕生日に」
第2番「シルヴィアの3歳のお誕生日に」
第3番「ジョゼ・ペドロの最初のクリスマスに」
第4番「“カナリト”の誕生に」
第5番「ネニタの結婚式に」
第6番「“カザ・ドス・ガロス”の開館式に」
第7番「テレジタ・マシャドの結婚式に」
第8番「ロメオの結婚式に」
第9番「マリア・アリナの20歳の誕生日に」
第10番「ヌノ・バロゾの19歳の誕生日に」
第11番「わが兄弟ジョゼの80歳の誕生日に」
第12番「フランシネ・ベノイトの90歳の誕生日に」
第13番「わが兄弟の最初の曾孫ルイス・ゴンサロの
最初のクリスマスのおもちゃ」
第14番「イヴォ・マシャドの結婚式に」
[CD 2}
お祝いの音楽
第15番「カタリナの3歳の誕生日に」
第16番「ジョアン・エスプリト・サントの15歳の誕生日に」
第17番「若い友人たちの集いに」
第18番「ミゲル・ボルジェス・コエリョの18歳の誕生日に」
第19番「わが兄弟の曾孫ジョルジ・ミゲルの3歳の誕生日に」
第20番「ヴァスコ・コンサルヴェスの70歳の誕生日に」
第21番「ジョゼ・ペドロとパウラの結婚式のために」
第22番「親愛なるジャシント・ジモンイス博士の66歳の誕生日に」
第23番「わが同僚にして友人アルヴァロ・クニャルの80歳の誕生日に」
9つの短い舞曲 |
アントニオ・ロザド(ピアノ) |
|
録音:2012年11月23-26日(CD 1)、2013年4月5-8日(CD
2)、CGDホール、リスボン経済経営高等学校(ISEG)、リスボン、ポルトガル
20世紀ポルトガルを代表する作曲家フェルナンド・ロペス=グラサがその長い生涯において親類や友人の誕生日や結婚式等を祝うために作曲したピアノ作品の出版に合わせて制作されたCD。アントニオ・ロザドはリスボン音楽院を卒業後、16歳でパリ音楽院に入りアルド・チッコリーニに師事、1980年にデビューしたポルトガルのピアニスト。彼はロペス=グラサのピアノ・ソナタ全集も録音しています(Numericaレーベル、NUM
1124 入手不能)。
本体、外装に規格品番表示がございません。ご了承ください。
|
OS MUSICOS DO TEJO
|
|
|
ファドの種 ポルトガル歌曲とファドの遠い関係を探って
不詳:私は、不運にも [Foi por mim, foi
pela sorte](*)
ラファエル・コエリョ・マシャド(1814-1887):
甘美な希望はついえた [Fenece doce esperanca](*)
アントニオ・ダ・シルヴァ・レイテ(1759-1833):メヌエット
フランシスコ・シャヴィエ・バプティスタ(17??-1797):
私の人生は常に悲しみと苦しみばかり
[He somente a minha vida sempre penar
e sofrer](*)
ジョゼ・メスキタ(確認できる活躍期:1793-1795):
優しい鳥たち [Ternas Aves](*)
アントニオ・ダ・シルヴァ・レイテ:
アンダンティーノ/フランシスコ・ジェラルド氏のトッカータ
マルコス・ポルトゥガル(1762-1830):愛しい夫が
[Cosi dolce amante sposo](*)
アントニオ・ダ・シルヴァ・レイテ:
この世の栄光を軽んじ [Desprezar do mundo
a gloria](*)
愛が私に褒美をくれた [Amor concedeum'um
premio] (デュエット)(*)
マヌエル・ジョゼ・ヴィディガル(確認できる活躍期:1796-1826):
メヌエット第6番/メヌエット第3番
V・J・コエリョ(19世紀前半):小鳥 [Avezinha]
アントニオ・ジョゼ・ド・レゴ(1783頃-1821):
バレイロの涼しい海辺 [Frescas praias
do Barreiro](*)
D・ジョゼ・アクニャ(?-1828):オリュンポスの神々
[Deuses do Olimpo](*)
ジョゼ・マウリシオ(1752-1815):
私が自然に何をしたのか [Que fiz eu a
natureza](*)
カルロス・セイシャス(1704-1742):
ソナタ ハ短調(PM No.16)から 第1楽章(チェンバロ独奏)
D・ジョゼ・アクニャ:愛の絆 [Os lacos
d'Amor](チェンバロ伴奏)(*) |
オス・ムジコス・ド・テジョ
アナ・キンタンス(ソプラノ(*))
リカルド・ロシャ(ポルトガルギター)
マルコス・マガリャンイス(チェンバロ、指揮) |
|
録音:2006年7月23-26日、市立アウグスト・カブリタ・コンサートホール、バレイロ、ポルトガル
ポルトガルの伝統歌謡ファドへの流れを作ったと考えられる、18世紀中盤から19世紀初頭にかけてポルトガルで書かれた「都会の中産階級向け歌曲」を選び出し、ポルトガルギターを交えて演奏するという興味深い企画。オス・ムジコス・ド・テジョはマルコス・マガリャンイスにより2003年に創設されたピリオド楽器アンサンブル。ポルトガル音楽ファンの方でしたら
Naxosから発売されたフランシスコ・アントニオ・デ・アルメイダ(1702-1755)のオペラ「ラ・スピナルバ」ですでにご存じかもしれません。
アナ・キンタンス(1975年生まれ)はリスボン国立音楽院で学んだソプラノ。ピリオド・モダーンを問わずすでに多くの名だたるオーケストラとの共演、オペラハウスへの出演を果たしています。
リカルド・ロシャ(1974年リスボン生まれ)は現代を代表するポルトガルギター奏者の一人。
マルコス・マガリャンイスは1972年リスボンに生まれ、リスボン高等音楽学校でクレミルデ・ロザド・フェルナンデス、シェティル・ハウグサンに、パリ音楽院でケネス・ギルバート、クリストフ・ルセ、ケネス・ワイスに師事したチェンバロ奏者・指揮者。 ブックレットにポルトガル語の解説と英語・フランス語訳、ポルトガル語歌詞と英語訳・フランス語訳を収録。
本体・外装ともに規格品番表記がございませんが、弊社は「MT
001」として管理いたします。ご了承ください。(代理店)
|
| |
|
|
ルイザ・トーディのアリア集
フローリアン・レオポルト・ガスマン(1729-1774):
オペラ「職人の恋」 [L'Amore Artigiano]
(1778)から 序曲(管弦楽)
ベルナルディーノ・オッターニ(1736-1827):
オペラ「アルミーニオ」 [Arminio] (1781)から
ロスモンダのアリア
「あなたが心に同情を覚えるなら」 [Se
pieta tu senti al core]
ニッコロ・ピッチンニ(1728-1800):
オペラ「迫害された匿名の女」[L'Incognita
Perseguitata] (1770)から
ジャネッタのレチタティーヴォとアリア「羊飼いたちよ、私も一緒に」
[Pastorelle, anch'o con voi]
ジョヴァンニ・パイジエッロ(1740-1816):オペラ「アンドロマカ」(1797)から
アンドロマカのレチタティーヴォとアリア「哀れな王子よ」
[Povero Prence]
ニッコロ・ピッチンニ:オペラ「迫害された匿名の女」から
ジャネッタのアリア
「お父さん、ああ、どこにいるの?」
[Genitore, ah, dove siete?]
アントニオ・サッキーニ(1731-1786):オペラ「オリンピーアデ」(1778)から
メガークレのアリア「もしも君が探すなら、こう言うなら」
[Se cerca, se dice]
ニッコロ・ピッチニーニ:オペラ「ディドーネ」
[Didone] (1791)から
ディドーネのレチタティーヴォとカヴァティーナ
「ああ、私が何を言った?不幸な人よ」
[Ah, che dissi, infeice?]
ニッコロ・ピッチンニ:
オペラ「インドのアレッサンドロ」 [Alessandro
nell'Indie](1778)から
クレオフィーデのレチタティーヴォとアリア
「それでポーロは死んだのだ」 [Poro
dunque mori]
ダヴィド・ペレス(1711-1779):
オペラ「デモーフォンテ」 [Demoofonte]
(1772)から
ディルチェアのアリア「私はあなたに期待する、愛する夫よ」
[In te spero, o sposo amato]
アントニオ・サッキーニ:オペラ「オリンピーアデ」から
アルジェーネのアリア「もう何も見つからない」
[Piu non si trovano] |
ジョアナ・セアラ(ソプラノ)
オス・ムジコス・ド・テジョ(管弦楽)
マルコス・マガリャンイス(指揮)
|
|
録音:2008年9月12-16日、カルトゥジオ教会、カシアス、ポルトガル
18世紀終盤に活躍したポルトガル出身の名リリック・ソプラノ、ルイザ・トーディ。1753年ポルトガルのセトゥバルにルイサ・ロザ・デ・アギアルとして生まれ、14歳で舞台デビュー、16歳の時にナポリ出身のヴァイオリン奏者フランチェスコ・サヴェーリオ・トーディと結婚、17歳でオペラ・デビュー。1777年にポルトガルを出てから20年にわたってイギリス、フランス、イタリア、ドイツ、ロシア等ヨーロッパ各地で大活躍。1799年、ナポレオン戦争を避けナポリを去り、13ヶ月をかけて1810年ポルトガルに帰国。1801年ポルトに居を構え歌手活動を再開しましたが、1803年に夫が死去、1809年のナポレオン軍のポルト侵攻の際に「Ponte
das barcasの悲劇」に巻き込まれ貴重な宝石類を失い、さらに1813年頃から視力が弱まり10年後に完全には完全に失明する不幸に見舞われ、1833年リスボンで貧窮のうちに亡くなりました。
当盤はルイザ・トーディがヨーロッパ各地で歌った数々のオペラからアリアを選び彼女のキャリアを回想しようという企画。
「ルイザ役」を歌うのは、リスボンに生まれロンドンのギルドホール音楽学校で学び2004年にオペラ・デビューしたソプラノ、ジョアナ・セアラ。バロックから古典派にかけてのレパートリーを得意としています。ブックレットにポルトガル語の解説と英語・フランス語訳、イタリア語歌詞とポルトガル語・英語・フランス語訳を収録。
|
PRIMETIME
|


PMT 0613
(2CD)
\4200 →\3790 |
「辺境のマイナー楽器」のイメージを吹き飛ばす
「クラシカル・ポルトガルギターの名盤」と自信を持って申し上げます。(代理店)
ペドロ・カルデイラ・カブラル/ポルトガルギターの迷宮&アンソロジー
[CD 1] ポルトガルギターの迷宮(*)
不詳(16世紀):マタシンス
ペドロ・デ・エスコバル(1465頃-1536):ヴィランセテ/カンティガ
不詳(16世紀):ルッジェーロのグロザ
ディエゴ・オルティス(1510-1570):レセルカダ
I/レセルカダ II
ジョン・ダウランド(1563-1626):憂鬱なガイヤルド
アントニー・ホルボーン(1550頃-1602):パヴァーヌ第4番
ジョン・ダウランド:蛙のガイヤルド
ロバード・ジョンソン(1582頃-1633):アルマン
ロベール・バラール(1575-1650):村のブランル
ドメニコ・スカルラッティ(1685-1757):ソナタ
K.322
カルロス・セイシャス(1704-1742):ソナタ
37
ジョアン・パウロ・ペレイラ(確認できる活躍期:1840-1860):
ワルツ ヘ短調/ワルツ ト短調
不詳(1850頃):マズルカ
ペドロ・カルデイラ・カブラル(1950-):イチイのバラード/アストリアナ
[CD 2] アンソロジー
アロンソ・ムダラ(1520頃-1580):ファンタジア
ジル・デュラン・デ・ラ・ベルジェリ(1554-1605):愛しの人よ、もしあなたの心が
ガスパル・サンス(1640頃-1710):パヴァーヌ
サンティアゴ・デ・ムルシア(1682頃-1740):前奏曲/カンシオン
ジュゼッペ・アントニオ・ブレシャネッロ(1690頃-1758):ソナタ
ドメニコ・スカルラッティ:ソナタ K.11
マテオ・アルベニス(1755-1831):ソナタ
フェルナンド・ソル(1778-1839):練習曲
Op.6 No.23/練習曲 Op.35 No.10
アントニオ・ラウロ(1917-1986):ベネズエラのワルツ
ペドロ・カルデイラ・カブラル:
アーモンドのバラード/玩具/岩山の迷宮/未完の円 |
ペドロ・カルデイラ・カブラル(ポルトガルギター)
ダンカン・フォックス(コントラバス(*)) |
|
録音:データ記載なし
ポルトガルの伝統歌謡ファドの伴奏楽器と位置付けられていたポルトガルギターをクラシカルなソロ楽器にまで高めたペドロ・カルデイラ・カブラル。彼の2つのコンサート・プログラムを収めたCDが発売されました。
ポルトガルギターはいわゆるギターではなくリュート系で、6コース・スチール複弦の撥弦楽器。どこか哀感を帯びた甘美な音色を特徴としています。ポルトガルでは単に「ギター(ギタラ)」と言えばこの楽器を指すそうです。
ペドロ・カルデイラ・カブラルは1950年リスボンの音楽一家に生まれリスボン国立音楽院で学んだギター、ポルトガルギター、リュート、ヴィオル奏者。彼はポルトガルにおける古楽演奏の第一人者でもあり、ピリオド楽器と古楽唱法によるアンサンブル「ラ・バタッラ」および「コンセルト・アトランティコ」を主宰する他、ルネサンス・バロック音楽のポルトガルギター用編曲に長年取り組んでいます。
録音したCDは十数枚あり、当盤同様に2つのコンサート・プログラムを収めたCD「ポルトガルギターの記憶&18世紀のギターに」(2003年、Tradisomレーベル、ポルトガル)もすばらしい内容だったのですが残念ながら廃盤のため入手できません。
カルデイラ・カブラルの編曲・演奏による楽曲の数々はポルトガルギターのために書かれたオリジナル作品としか思えないほど違和感がなく、この楽器独特の魅力を備えた逸品に仕上がっています。なかでもすばらしいのはやはりセイシャス。カルデイラ・カブラルの自作曲もファド風あり、ピアソラ風あり、技巧を極めた現代音楽風ありでとことん楽しめます。
「辺境のマイナー楽器」のイメージを吹き飛ばす「クラシカル・ポルトガルギターの名盤」と自信を持って申し上げます。(株式会社サラバンド代表取締役
金田敏也)
Primetimeは配給元と表示されており、実質的には自主制作商品と思われますのでお早目の入手をお勧めいたします。なお、外装に規格品番表記がございませんのでご注意ください。(代理店)
|
<国内盤>
 AEON AEON
|


MAECD0977
(国内盤・2枚組)
\3700+税 |
モートン・フェルドマン チェロのための作品集
〜偶然と反復の音世界〜
モートン・フェルドマン(1926〜1987):
① 半音階平原の模様
(Patterns in achromatic field/1981)
②プロジェクション1(Projection I/1950)
③コンポジション:八つの小品
(Composition - 8 little pieces/1950)
④交叉点 IV(Interjection IV/1951)
⑤持続II(Duration II/1960) |
アルヌ・ドフォルス(チェロ)
大宅裕(ピアノ) |
まるで一面に広がる草原に、風が模様をつくってゆくよう。じわり感じ入る、フェルドマンの音世界。
ケージと並ぶニューヨーク楽派の大立者が残した後期の大作に、初期の出発点をしめす掌編をいくつか。画期的なクセナキス盤(MAECD1109)で注目されるドフォルス、堂々の2枚組!
前衛芸術とひとくちに言っても本当にさまざまですが、このアルバムは極度に玄人好みな内容でありながら、まったく同時に何より素晴しい現代音楽へのイントロダクションにもなるであろう、周到なプログラム構成。
さすがは現代系レーベルaeon、切り口が絶妙です。モートン・フェルドマンのチェロ作品集——フェルドマンといえば、前衛音楽畑ではケージ、ベリオ、ブーレーズ...といった名前と並ぶ超ビッグネームでありながら、コンサヴァティヴなクラシック演奏家が意外にとりあげない=音盤があるようでない作曲家。1950
年代にジョン・ケージと意気投合し、五線紙を全く使わない図形楽譜や、演奏してみるまでどんな音楽ができるかわからない“偶然性の音楽”といった、その後の前衛音楽の世界に浸透してゆくさまざまな作曲技法が彼の作品に端を喫しており、極度なまでに長い反復を伴う、とほうもなく演奏時間が長い作品が多いことでも有名ではありますが、本盤ではそうした長大系フェルドマンの名品「半音階平野の模様」がひとつと、彼がケージと出会って間もなく、フェルドマンがフェルドマンたりえてゆく最初の過程で残した小品がいくつか、チェロとピアノという多くのクラシック・ファンにとっても身近な(むしろ「多くの方が好きな」と言ってしまってもよいかもしれません)楽器で織り上げられてゆきます。
2枚のCD のうち、「半音階平野の模様」は実にCD1枚にも収まりきらず、次のCD2まで浸食するほどの長さがある長大な作品(演奏時間90
分近く)で、さまざまな音型が一定期間つづく安定したリズムのなかで続いてゆくところが多く、現代畑で活躍するオランダ語圏ベルギーの天才奏者アルノ・ドフォルスが繰り出す音のテクスチュアの魅力、同じくベルギーを活躍の場にしている大宅裕のピアノの音色とあいまって、じっくり傾聴しつづけるだけでなく、音環境の演出素材として流しつづけても苦にならない、穏やかで心地よい音響体験の場にもなってくれる——そうした作品のあとに、フェルドマンが自己を確立しはじめた時期の小品(チェロの鳴らし方の工夫一覧のような演奏時間3
分あまりの「交叉点IV」なども、不思議体験の入口として絶妙かもしれません)がいくつかあるというあたりで、本盤は「聞き深めれば面白い、けれどなんとなく感じているだけでもOK」な、前衛音楽への糸口となってくれるアルバムに仕上がっているわけです。
フェルドマンという大御所を知り、20 世紀の前衛音楽の基本的ルールを極上解釈でひとわたり味わえる企画。日本語解説とあわせ、ぜひご体感を。 |
<映像>
 ALTHUM(映像) ALTHUM(映像)
|

ALTHUM 01-12
(DVD PAL)
\4200
【旧譜 再入荷】 |
ルイ・パイヴァ参加 マフラ国立宮殿教会堂の6台のパイプオルガン
アントニオ・レアル・モレイラ(1758-1819):
マフラ王宮教会堂のためのシンフォニア(6台のオルガンのための)(1-6/D)
ディエゴ・デ・コンセイサン(17世紀):メイオ・レジストロ第2旋法(5)
カルロス・セイシャス(1704-1742):ソナタ
イ長調(4)
ルイ=ニコラ・クレランボー(1676-1749):
組曲第2旋法 から クラン・ジュによる奇想曲(6)
イスフリート・カイザー(1712-1771):序曲(3)
ジョアン・ヴァス(1963-):
アヴェ・マリス・ステラ
(グレゴリオ聖歌による合唱と6台のオルガンのための)(C/1-6/D)
マルコス・ポルトゥガル(1762-1830):オルガンのためのソナタ(1)
ジュゼッペ・アントニオ・パガネッリ(1710-1763):アリアII(2)
ジョアン・ジョゼ・バルディ(1770-1816):
退却行進曲(2)
ミサ(独唱、合唱と6台のオルガンのための)から
グローリア(T/B/C/1-6/D)
[ボーナス・トラック]
TVショー「Camara Clara」(2010年5月9日、RTP2チャンネルで放映)
ディナルテ・マシャド(オルガン製作家、修復責任者)、
ジョアン・ヴァス(オルガン奏者、修復アドバイザー)、
ルイ・ヴィエイラ・ネリ(音楽学者、修復顧問委員長)へのインタビューを含む |
|
フェルナンド・ギマランイス、
カルロス・モンテイロ(テノール(T))
ディエゴ・ディアス(バリトン(B))
リスボン・カンタート・シンフォニック合唱団(男声合唱(C))
ジョアン・ヴァス(福音書オルガン(1))
ルイ・パイヴァ(使徒書オルガン(2))
アントニオ・エステイレイロ(アルカンタラの聖ペドロ礼拝堂のオルガン(3))
アントニオ・ドゥアルテ(秘跡礼拝堂のオルガン(4))
セルジオ・シルヴァ(受胎礼拝堂のオルガン(5))
イザベル・アルヴェス(聖バルバラ礼拝堂のオルガン(6))
ジョルジ・アルヴェス(指揮(D)) |
|
収録:2010年5月15日、ライヴ、国立宮殿教会堂、マフラ、ポルトガル
使用楽器:
(1)建造:1807年、シャヴィエル・マシャド・エ・セルヴェイラ
改修:1820年頃、同/修復:1999年、ディナルテ・マシャド
(2)建造:1807年、ジョアキン・アントニオ・ペレス・フォンタネス
改修:1820年頃、シャヴィエル・マシャド・エ・セルヴェイラ
修復:2000年、ディナルテ・マシャド
(3)建造:1806年、ジョアキン・アントニオ・ペレス・フォンタネス
修復:2004年、ディナルテ・マシャド
(4)建造:1806年、シャヴィエル・マシャド・エ・セルヴェイラ
改修:1820年頃、同/修復:2004年、ディナルテ・マシャド
(5)建造:1807年、シャヴィエル・マシャド・エ・セルヴェイラ
改修:1820年頃、同/修復:2010年、ディナルテ・マシャド
(6)建造:1806年、ジョアキン・アントニオ・ペレス・フォンタネス
改修:1820年頃、シャヴィエル・マシャド・エ・セルヴェイラ
修復:2010年、ディナルテ・マシャド
|
1711年、世継ぎに恵まれなかったポルトガル国王ジョアン5世(1689-1750、在位:1706-1750)と王妃マリア・アナが「子を授かったら修道院を建立する」と神に誓約したところ、間もなく王女バルバラが誕生。誓約通り国王は1717年、首都リスボンの北西約40kmの町マフラに巨大な王宮兼修道院の建築を開始し、13年後に完成しました。
王宮兼修道院は王政消滅(1910年)の後国立宮殿として利用され、現在ではポルトガルの観光名所の一つにもなっています。宮殿の教会堂の6台のオルガンは1792年から1806-1807年にかけて建造され、1998年から2010年にかけて修復されました。
当DVDはポルトガル国営放送(RTP)がその修復完成を祝う演奏会の模様を収録したテレビ番組を商品化したものです。オルガン6台が合奏する楽曲では、各オルガン奏者が指揮者を映し出すモニターを見ながら弾いています。PAL方式で価格も高めですが、オルガン、教会建築、ポルトガルに興味のある方には是非ともお勧めしたい、実に興味深い映像作品です。カラー写真を多数掲載したポルトガル語・英語併記の解説書を備えたハードカヴァー・ブック仕様。
■PAL方式のため、一般的な日本製DVDプレーヤーでは再生できません。PAL対応のDVDプレーヤーが必要です。ご注意ください。
■本体・外装の規格番号表示は「A 01-12-DVD」となっておりますが、「ALTHUM
01-12」として管理いたします。(代理店) |

4/24(木)紹介新譜
マイナー・レーベル新譜
AEOLUS
|

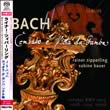
AE-10206
(SACD HYBRID)
\2700 →\2490 |
J.S.バッハ:ヴィオラ・ダ・ガンバ・ソナタ集
ヴィオラ・ダ・ガンバとチェンバロのためのソナタ第1番ト長調
BWV.1027
ヴィオラ・ダ・ガンバとチェンバロのためのソナタ第2番ニ長調
BWV.1028
ヴィオラ・ダ・ガンバとチェンバロのためのソナタ第3番ト短調
BWV.1029
ソナタ ト短調 BWV.1030b
|
ライナー・ツィパーリング(ヴィオラ・ダ・ガンバ)
ザビーネ・バウアー(チェンバロ、クラヴィオルガン) |
18世紀オーケストラの名チェロ&ガンバ奏者ライナー・ツィパーリングのバッハ!
18世紀オーケストラのメンバー、カメラータ・ケルンの創設メンバーでもあるオランダの名ガンバ奏者、ライナー・ツィパーリング。Aeolusの「J.S.バッハ:ソナタ・シリーズ」第1弾として、ヴィオラ・ダ・ガンバ・ソナタ集が登場!ツィパーリングは、通常の「ヴィオラ・ダ・ガンバとチェンバロのためのソナタ」BWV.1027〜1029の3曲に加え、BWV.1030b(原曲はフルート・ソナタ
ロ短調)の、ヴィオラ・ダ・ガンバ版を収録(ジョナサン・マンソンとトレヴァー・ピノックのコンビでも録音していた試みである)。
チェロ&ヴィオラ・ダ・ガンバ奏者として18世紀オーケストラ、カメラータ・ケルン、リチェルカール・コンソートなど、200以上のレコーディングに参加するベテラン、ライナー・ツィパーリングと、カメラータ・ケルンで共に活動し長年の室内楽パートナーでもあるザビーネ・バウアーによる格別なるバッハ。ちなみに、BWV.1028のニ長調ソナタではクラヴィオルガン(オルガンにチェンバロを組み込んだ楽器)を使用している。古楽ファン大注目のシリーズがスタートです!

旧譜/名盤!
ライナー・ツィパーリングの無伴奏チェロ |

flora
0202
(2CD)
\3600→¥2990 |
バッハ:無伴奏チェロ組曲 BWV.1007-1012 |
ライナー・ツィパーリング(Vc) |
|
録音:2002年8月、ブラ・シュ・リエンヌ
アンナー・ビルスマにチェロを、ヴィーラント・クイケンにヴィオラ・ダ・ガンバを師事、18世紀オーケストラ、カメラータ・ケルン等
のメンバーを務めるツィパーリング。
師匠ビルスマを思わせる大胆さもかいま見せる、みごとな演奏です。
使用楽器は1786年ヴィンツェ ンツォ・トルシアーノ・パノルモ製/1750年ルドヴィクス・グェルサン製5弦ピッコロ・チェロ。
|
|
 COBRA RECORDS COBRA RECORDS
|
|
|
コンチェルト・パルランド
ドヴァリョーナス:悲歌的小品 《湖畔にて》
シチェドリン:
ヴァイオリン、トランペットと弦楽のための
《コンチェルト・パルランド》*
プロコフィエフ:5つのメロディー Op.35bis(管弦楽伴奏版)
チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲 Op.35(カデンツァ:イザイ) |
フィリップ・グラファン(ヴァイオリン)
マーティン・ハレル(トランペット)*
ミハイル・アグレスト(指揮)*
BBC交響楽団*
ロベルタス・シャーヴェニカス(指揮)
リトアニア国立フィルハーモニー管弦楽団 |
フィリップ・グラファンのチャイコフスキー!"イザイによるカデンツァ"世界初録音!
16歳でパリ音楽院を卒業したフランスの天才ヴァイオリニスト、フィリップ・グラファン!
これまでも、Hyperion、Avie、Onyxなどで様々なレア・レパートリーを開拓・披露してきたグラファンがCobra
Recordsで魅せてくれるのは、ロディオン・シチェドリンによるグラファン委嘱作「コンチェルト・パルランド」のイギリス初演ライヴ(世界初録音)。
プロコフィエフの5つのメロディーはピアノ伴奏ではなく、管弦楽伴奏による世界初録音(オーケストレーションはプロコフィエフとシチェドリン)。そして注目は、名曲「チャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲」のイザイによるカデンツァ世界初録音!
ヴィルトゥオーゾ・ヴァイオリニストでもあったウジェーヌ・イザイのカデンツァは、元々が超絶技巧のオンパレードであるチャイコフスキーのカデンツァを更なる超絶カデンツァへと姿を変えている。
Hyperionのロマンティック・ヴァイオリン・コンチェルト・シリーズのスタートを飾った「サン=サーンス:ヴァイオリン協奏曲全集」や、Avieに録音し大きな話題となった「エルガー:ヴァイオリン協奏曲(初稿版)」など、グラファンの誇る偉大なコンチェルト・レパートリーに新たに加わるチャイコフスキーとシチェドリン。グラファンのレア・レパートリー探求に注ぐ止めどない情熱と、それを実現する驚異的なテクニックを体感する。
※録音:2008年2月22日、BBCメイダ・ヴェール・スタジオ1*、2012年4月2日、リトアニア国立フィルハーモニー・ホール

フィリップ・グラファンあれこれ
気に入ったアルバムが何枚かあって、気づいたらそれらが同じ演奏家によるものだったというときのショックはでかい。もちろんいい意味で。
フィリップ・グラファン。
16歳という若さでパリ音楽院を首席で卒業してしまったという底知れぬ才能の持ち主。
昔HYPERIONからワルターのヴァイオリン・ソナタが出ていてわりと気に入っていたが、同じHYPERIONから出てる結構お気に入りの超マイナー・ヴァイオリン曲アルバムもグラファンだと知って、こういうマイナー作品が好きな奇才なんだなあ、と思った覚えがある。
その後AVIEから出て印象的だったエルガーの初稿版によるヴァイオリン協奏曲の世界初録音もグラファンだった。
で、きわめつけはAVIEのモーツァルトのコンチェルト集。今井信子目当てで買ったはずなのに、ヴァイオリンが素敵でとても気に入ったのだが・・・それがまたグラファンだった。
世界的知名度を得るようになるにはまだ数年かかるのだろうが、まあそんなものがなくてもすごい人はすごい。 |
|
|
| |
|
|
まだまだフィリップ・グラファン!
マルッティネンの協奏曲集!
マルッティネン:
ヴァイオリン協奏曲 Op.13, MV.63
ピアノ協奏曲第1番 Op.154, MV.65
チェロと管弦楽のための幻想曲 Op.154,
MV.84(世界初録音) |
フィリップ・グラファン(ヴァイオリン)
ラルフ・ファン・ラート(ピアノ)
マルコ・ユロネン(チェロ)
アリ・ラシライネン(指揮)
トゥルク・フィルハーモニー管弦楽団
ハンヌ・リントゥ(指揮)
タンペレ・フィルハーモニー管弦楽団 |
「チャイコフスキー&シチェドリン(COBRA
0040)」に続く、フィリップ・グラファンのレア・コンチェルトは、20世紀フィンランドの作曲家、タウノ・マルッティネン(1912−2008)のヴァイオリン、ピアノ、チェロの協奏的作品を収録。ピアノのラルフ・ファン・ラート、チェロのマルク・ユロネンも、それぞれ近現代の作品に造詣の深い名手で、フィンランドのリーディング・オーケストラ、トゥルク・フィル、タンペレ・フィルとともに、フィンランドの芸術を、見事に奏でている。
※録音:2012年9月13日−15日、タンペレ・ホール(チェロ幻想曲)、2013年5月27日−29日、コンサート・ホール・トゥルク(ヴァイオリン協奏曲、ピアノ協奏曲) |
| |
|
|
レヴォリューションズ 〜
シェーンベルク、ヴェーベルン、ベルク:弦楽四重奏曲集
シェーンベルク:弦楽四重奏曲ニ長調
ヴェーベルン:弦楽四重奏のためのロンド
ベルク:弦楽四重奏曲 Op.3
ヴェーベルン:弦楽四重奏のための6つのバガテル
Op.9
J.S.バッハ:マタイ受難曲より コラール
《汝の行くべき道と》 |
キロガ弦楽四重奏団 |
スペインの新世代クヮルテット、新ウィーン楽派を弾く!
ガリシア地方の大ヴァイオリニスト、マヌエル・キロガ(1892−1961)の名を冠するスペインのクヮルテット、キロガ弦楽四重奏団(Cuarteto
Quiroga)。2007年にスペイン国営放送の文化賞を授与された新世代アンサンブルが弾く、シェーンベルク、ヴェーベルン、ベルクによる「新ウィーン楽派」の弦楽四重奏曲集が登場。前作「ステイトメンツ(COBRA
0035)」でも聴かせてくれたヴェーベルンから更に踏み込んだ、「革命(Revolution)」と「進化(Evolution)」の新ウィーン楽派作品集。
18世紀製作のグランチーノ・ランドルフィ、1682年製作のニコラ・アマティのヴァイオリンの音色と存在感も健在。
※録音:2012年12月12日−14日、ウェストフェスト90教会(スキーダム、オランダ) |
 FRA BERNARDO FRA BERNARDO
|
|
|
オリジナル楽器によるブルックナー交響曲第1番!
ブルックナー:交響曲第1番ハ短調 WAB.101(リンツ稿) |
フィリップ・フォン・シュタインエッカー(指揮)
ムジカ・セクロルム |
国内代理店登場により再紹介。ちょっとだけ安くなった。
2013年12月にベートーヴェンの「第九」で新日本フィルと共演を果たし、才気あふれる演奏で話題を呼んだ、ドイツの逸材フィリップ・フォン・シュタインエッカー。
指揮者、チェリストとして急成長を見せているフィリップ・フォン・シュタインエッカーは、ヨーロッパのピリオド・アンサンブルやマーラー室内管のメンバーを集め、南チロル、ボルツァーノを活動の拠点とするピリオド・オーケストラ、ムジカ・セクロルムを創設。
ムジカ・セクロルムとのオリジナル楽器によるブルックナーの「交響曲第1番」では、瑞々しくクリアなサウンド、弦楽器と管楽器の絶妙のバランス、丁寧なアナリーゼが印象的。モダン、ピリオドの枠を越えた好演奏を披露してくれている。
ムジカ・セクロルムを率いるフィリップ・フォン・シュタインエッカーはドイツ出身。チェリストとしてマーラー室内管やルツェルン祝祭管で活躍し、イングリッシュ・バロック・ソロイスツとオルケストル・レヴォリューショネル・エ・ロマンティックでは首席チェロ奏者を務めるなど、モダンとピリオドの両面で豊富な経験を積み、近年では指揮者としても活発な活動を展開している。

新日本フィルとの「第9」公演で個性的な演奏を披露し、賛否両論となったシュタインエッカー(シュタイネッカー)。
ドイツ・ハンブルクに生まれ、第1回メリゴーOAE指揮者コンクール優勝。アバド、ラトル、ハーディングが称賛する注目の若手指揮者として知られていたが、ほかにもガーディナー、ユロフスキ、ノリントンなどのアシスタントを務めてきた。
近年はモダン・オケとピリオド・オケ両方を操り、特に最近は自分で創設したオケ’ムジカ・セクロルム’で自在な演奏を繰り広げているという噂だった。
そのシュタインエッカーがいよいよポピュラーな交響曲で我々にその真価を見せるときが来た。
ブルックナーの1番。爽快さと個性を前面に押し出し、新たなブルックナー像を打ち立てる。
おそらく2年後には多くのクラシック・ファンがその名を語るようになるだろう。店主のこういう勘は当たる。(初紹介時のコメント)
|
|
 MELODIYA MELODIYA
|
|
|
ミハイル・クーゲル&ボリス・ベレゾフスキー
グリンカ:ヴィオラとピアノのためのソナタ
ニ短調(未完)、アルバムの一葉
ルビンシテイン(クーゲル校訂):ヴィオラとピアノのためのソナタ
ヘ短調 Op.49
グラズノフ:ヴィオラとピアノのためのエレジー
Op.44
ストラヴィンスキー:無伴奏ヴィオラのためのエレジー
エルンスト(クーゲル編):シューベルトの《魔王》による大奇想曲
Op.26
エルンスト(クーゲル編):《夏の名残のバラ(庭の千草)》による序奏、主題と変奏 |
ミハイル・クーゲル(ヴィオラ)
ボリス・ベレゾフスキー(ピアノ) |
クーゲルとベレゾフスキーのデュオ!Melodiyaの新録音はヴィオラとピアノ!
1975年のブダペスト国際音楽コンクールで第1位に輝き(第2位はバシュメット)、モスクワ音楽院やエルサレムのルービン音楽アカデミーの教授を歴任した旧ソ連〜ロシアの伝説的ヴィオリスト、ミハイル・クーゲル(1946−)と、1990年チャイコフスキー国際コンクールの覇者にして当代屈指の名ピアニスト、ボリス・ベレゾフスキーのデュオによる新録音がメロディア(Melodiya)から登場!
ユーリ・バシュメットやユーリ・クラマロフと並び、旧ソ連、ロシアが輩出した世界的ヴィオリストの1人と称されるクーゲル。
自らの校訂によるルビンシテインのソナタや、ヴィオラ版への編曲によるエルンストの2作品など、ソロ楽器としてのヴィオラの存在感を高めた功績は非常に大きい。
そしてピアノはベレゾフスキー。クーゲルとのデュオによるロシアン・プログラムでの、際立つピアニズムを堪能したい。
※録音:2002年、2012年&2013年(ディジパック仕様) |
<マイナー・レーベル歴史的録音・旧録音>
 FRA BERNARDO FRA BERNARDO
|


fb 1312522
(2CD)
\3600 →\3290 |
クレメンス・クラウス&ウィーン・フィル
ハイドン:オラトリオ《天地創造》 |
クレメンス・クラウス(指揮)
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
ウィーン国立歌劇場合唱団
トルーデ・アイッパーレ(ソプラノ)
ユリウス・パツァーク(テノール)
ゲオルク・ハン(バス・バリトン) |
1943年3月28日にウィーンで収録されたハイドンの「天地創造」の放送用録音、クレメンス・クラウスとウィーン・フィルの名演が「フラ・ベルナルド(fb/fra
bernardo)」レーベルから登場。
クラウス&ウィーン・フィルはもちろんのこと、アイッパーレ、パツァーク、ハンといった名歌手たちの共演による「天地創造」は、名演の誉れが高い。音質面にも要注目。 |
 MELODIYA MELODIYA
|


MELCD 1002170
(6CD/特別価格)
\7800 →\7290 |
ヴォーン・ウィリアムズ:交響曲全集
海の交響曲(交響曲第1番)*/ロンドン交響曲(交響曲第2番)/
田園交響曲(交響曲第3番)/交響曲第4番ヘ短調/
交響曲第5番ニ長調/交響曲第6番ホ短調/南極交響曲(交響曲第7番)/
交響曲第8番ニ短調/交響曲第9番ホ短調 |
ゲンナジー・ロジェストヴェンスキー(指揮)
ソヴィエト国立文化省交響楽団
エレーナ・ドフ=ドンスカヤ(ソプラノ)
ソヴィエト国立室内合唱団
タチアナ・スモリャコワ(ソプラノ)
ボリス・ヴァシリエフ(バリトン)
レニングラード音楽協会合唱団
リムスキー・コルサコフ音楽大学合唱団 |
ロジェストヴェンスキーのヴォーン・ウィリアムズ!ソヴィエト国立文化省響との《交響曲全集》が登場!
ゲンナジー・ロジェストヴェンスキーが、80年代から旧ソ連崩壊まで率いたソヴィエト国立文化省交響楽団とのヴォーン・ウィリアムズの交響曲全集(!)がメロディア(Melodiya)から登場!
改訂稿、異稿を網羅したブルックナーの交響曲全集や、ショスタコーヴィチ、グラズノフの交響曲全集など、多くの凄演を世に送り出したロジェストヴェンスキーとソヴィエト国立文化省響のコンビ。
ロジェストヴェンスキー、旧ソ連のオーケストラ、イギリスのヴォーン・ウィリアムズ、しかも9つ全ての交響曲という異色の組み合わせへの興味は高まるばかり。
旧ソ連崩壊の足音が聞こえてくる中、レニングラード音楽院大ホールに響いたヴォーン・ウィリアムズのシンフォニー。これは要注目!
1988年−1989年の録音。 |
| |
|
|
本家から登場
ベルマンが繰り広げる超絶のリスト
リスト:超絶技巧練習曲集 S.139 |
ラザール・ベルマン(ピアノ) |
20世紀ロシアの巨星、ラザール・ベルマンのメロディア音源を代表する驚異の名演、1963年に録音されたフランツ・リストの「超絶技巧練習曲集S.139」が遂に本家メロディアから復刻!
超絶技巧の化身となったベルマンが繰り広げる超絶のリストは、「超絶技巧練習曲集S.139」の最高峰に君臨し続ける名演です。メロディアからの復刻であり、音質面にも期待したいところ。
1963年の録音。ディジパック仕様。
VENEZIA盤も紹介しておきましょう
リスト:超絶技巧練習曲
1963年モスクワでのスタジオ録音
VENEZIA CDVE00020(3CD)\1800→\1690
ふう。ようやくこの日が来た。
ベルマンの新譜が出るたびにこの録音が入っていないか確認する習慣が、ようやくこれで終わる。
あらゆるピアノ録音の中で、まちがいなく五本の指に入る、復刻要望の大きかった録音。
「ベルマンの1963年の『超絶技巧』がすごい」と聞いて手元のCDを見ると「1959年」・・・「それじゃないんだよなあ、63年のがすごいんだよ」といわれて歯ぎしりをしながら近くのCDショップに駆け込んで「1963年のベルマンの『超絶技巧』をください!」と叫ぶも、「それ、今、廃盤です」と店員につれなく対応されてしまったあなた。
もう大丈夫。
その「ベルマンの1963年の『超絶技巧』」、出ます。
店主もかれこれ30年前、そのLPを買い(正確には買ったのは兄だが)、何日も開いた口がふさがらなくてずーっと口を開けたまま聴いていた。こんな音楽があるのか、こんな演奏があるのか、こんなピアニストがいるのか。当時は「超絶技巧」の全曲盤はこれとアラウくらいしかなかったから、他に比較の仕様がなかったのだが、その後どんな演奏を聴いても結局この「ベルマンの1963年の『超絶技巧』」が刷り込みになってしまって、どうしても満足できなかった。多くの多くのピアノ・ファンがそう言うように、この演奏が絶対的な聖典となってしまったのである。
しかしこの録音、ここ数年(20年前はまだあった)、MELODIYAの音源がらみのゴタゴタで廃盤になってから、ずっとずっとずっとお蔵入りのままだったのだ。
その国宝的音源が、今回ようやくようやく、VENEZIAから発売になる。
で、何度も言っているがVENEZIAは本当に初回限定プレスになることが多い。アリアCDでも何年分かの在庫は取るつもりだが、それでも入手するならどうかどうかお早めに。(発売当時のコメント) |
|
|
| |
|
|
ミェチスワフ・ヴァインベルク(1919−1996)
ワインベルク:
シンフォニエッタ第1番 Op.41
シンフォニエッタ第2番 Op.74
交響曲第7番 Op.81(弦楽とハープシコードのための)* |
エフゲニー・スヴェトラーノフ(指揮)
ソヴィエト国立交響楽団
ルドルフ・バルシャイ(指揮)*
モスクワ室内管弦楽団* |
戦火を逃れるため、生まれ故郷のポーランドから、旧ソ連へと亡命したものの、反ユダヤ運動のため、演奏禁止、逮捕など苦難に遭ったミェチスワフ・ヴァインベルク(1919−1996)。
亡命時からの理解者だったショスタコーヴィチ、近年の録音の増加などにより、再評価が進むヴァインベルクの管弦楽作品から、ユダヤの民族色が濃厚な「シンフォニエッタ第1番」、第1番と対極に位置するかのような「シンフォニエッタ第1番」、冒頭のハープシコードが印象的な「交響曲第7番」をスヴェトラーノフとバルシャイの指揮で。
1966年(Op.41)、1962年(Op.74)、1967年(Op.81)の録音。ディジパック仕様。 |
| |


MELCD 1002227
(2CD)
\4200 →\3790 |
プロコフィエフ:ピアノ協奏曲全集
ピアノ協奏曲第1番変ニ長調
ピアノ協奏曲第4番変ロ長調 op.53
ピアノ協奏曲第5番ト長調 Op.55
ピアノ協奏曲第2番ト短調 Op.16
ピアノ協奏曲第3番ハ長調 Op.26 |
ウラディーミル・クライネフ(ピアノ)
ドミトリー・キタエンコ(指揮)
モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団 |
ロシアン・ピアノ・スクールの4大流派の1つ「ネイガウス・スクール」の名ピアニストであり、1970年の第4回チャイコフスキー国際ピアノ・コンクールでは第1位に輝いたウラディミール・クライネフ。
チャイコフスキー国際コンクール優勝後の1976年から83年にかけて、キタエンコとモスクワ・フィルとのコンビで収録されたクライネフのプロコフィエフのピアノ協奏曲全集。
クライネフは1991年から92年にかけてキタエンコ&フランクフルト放送響ともプロコフィエフのピアノ協奏曲全集を録音しており、音色や解釈の変化など、聴き比べも興味深い。
1976年−1983年の録音。ディジパック仕様。 |
<メジャー・レーベル>
<国内盤>

4/23(水)紹介新譜
マイナー・レーベル新譜
 2L 2L
|

2L 104SABD
(Blu-ray Audio +
SACD HYBRID)
\4000 |
われらこの国を愛す
1. 国王の歌(Kongesangen)
作者不詳(17世紀-18世紀の旋律)(スチャン・オーレスキョル(1974-)編曲)
2. ボヤール(ルーマニア貴族) の入場行進曲(Bojarenes
inntogsmarsj)
ヨハン・ハルヴォシェン(1864-1935)
(フランク・ウィンタボトム(1861-1930)編曲)
3. 険しい山と丘の間を海に向けて(Mellom
bakkar og berg)
イーヴァル・オーセン(1813-1896)
(スティーグ・ノルドハーゲン(1861-1930)編曲)
4. ノルウェー・ラプソディ第1番(Norsk rapsodi
nr.1)イ長調
ヨハン・ハルヴォシェン(1864-1935)
(スティーグ・ノルドハーゲン(1861-1930)編曲)
5. われらはひとつの国(Vi ere en nasjon,
vi med)
ヘンリク・ヴェルゲラン(1808-1845)
(スヴァイン・ヘンリク・ギスケ(1973-)編曲)
6. ノルウェー芸術家の謝肉祭(Norsk kunstnerkarnaval)Op.14
ヨハン・スヴェンセン(1840-1911)(ダン・ゴッドフレイ(1868-1939)編曲)
7. 神に祝福されし、われらが素晴らしき祖国(Gud
signe vart dyre fedreland)
C・E・F・ヴァイセ(1774-1842)(オイヴィン・ヴェストビ(1947-)編曲)
8. 忠誠行進曲(Hyldningsmarsj)Op.56-3
(《十字軍の王シーグル(Sigurd Jorsalfar)》組曲から)
グリーグ(1843-1907)(オイヴィン・ヴェストビ(1947-)編曲)
9. ノルウェーの息子たちよ(Sonner av Norge)(Henrik
Anker Bjerregaard)
クリスチャン・ブルム(1782-1861 ノルウェー)(ライド・ギリエ(1965-)編曲)
10. オラヴ皇太子栄誉行進曲(Kronprins Olavs
Honnormarsch)
オスカル・ボルグ(1851-1930)(ビョルン・メレンベルグ(1941-)編曲)
11. ノルウェーの旗は赤と白と青に(Norge
i rodt, hvitt og blatt)
ラーシュ=エーリク・ラーション(1908-1986)
(スヴァイン・ヘンリク・ギスケ(1973-)編曲)
12. 国王ホーコン七世栄誉行進曲(Kong Haakon
den Vlldes Honnormarsch)
オスカル・ボルグ(1851-1930)(ビョルン・メレンベルグ(1941-)編曲)
13. 美しきかな祖国(Fagert er landet)
メルヒオール・ヴルピウス(c.1570-1615)(ペッテル・ヴィンロート(1980-)編曲)
14. ヴァルドレス行進曲(Valdresmarsj)
ヨハネス・ハンセン(1874-1967)
15. われらこの国を愛す(Ja, vi elsker dette
landet)
リカルド・ノルドローク(1842-1866)(オイヴィン・ヴェストビ(1947-)編曲) |
インガル・ベルグビ(指揮)
ノルウェー軍音楽隊
スコラ・カントールム
トゥーネ・ビアンカ・スパッレ・ダール(合唱指揮) |
ノルウェー憲法制定200周年記念、ノルウェー軍音楽隊&スコラ・カントールムによる「われらこの国を愛す」これぞブルーレイ・オーディオ!響きの奥行き、自然な空気感がそのまま録音された2
Lの超優秀録音!
録音:2013 年 ヤール教会(ベールム、ノルウェー)、ウラニエンボルグ教会(オスロ)/制作&バランスエンジニアリング:モッテン・リンドベルグ/エンジニア:ビアトリス・ヨハンネセン
[DXD (24bit/352.8kHz) 録音][Blu-ray:
5.1 DTS-HD MA (24bit/192kHz), 2.0 LPCM (24bit/192kHz),
mShuttle: MP3 & FLAC, Re-gion ABC][SACD
DXD (5.1 surround 2.8224 Mbit/s/ch, 2.0 stereo
2.8224 Mbit/s/ch)/CD 2.0 stereo (16 bit/44.1
kHz)]
ノルウェーは、2014 年、憲法制定200 周年を迎えます。各市町村では一年を通じさまざまな祝祭行事が予定され、5
月17 日の憲法記念日、オスロの中央駅から王宮に向かうカール・ヨハン通りで行われる子供たちと青年たちが主役のパレードもいっそう華やかで活気にみちたものになりそうです。
ノルウェーを代表するレコードレーベルのひとつ
2L も、この記念すべき年を祝い、アルバムを制作しました。『われらこの国を愛す』。アルバムのタイトルは、グリーグの親友、リカルド・ノルドロークの作曲した「ノルウェー国歌」からとられました。
グリーグとならぶナショナル・ロマンティシズム期を代表する作曲家ハルヴォシェンが管弦楽のために作曲し、ウィンドオーケストラのための編曲がスタンダード・レパートリーになった《ボヤールの入場行進曲》と《ノルウェー・ラプソディ第1
番》。グリーグの親友、スヴェンセンの《ノルウェー芸術家の謝肉祭》。古くから伝わる『ノルウェー乾杯「勇者の国ノルウェーのために」』を作家ヘンリク・ヴェルゲランが「子供たちの国歌」に作った《われらはひとつの国》。ヨハネス・ハンセンの《ヴァルドレス行進曲》もノルウェー各地のバンドによって演奏されています。
録音に参加したのは、ノルウェー王国軍の擁するプロフェッショナル・バンドのひとつ、フランスのウィンド作品集『凱旋路』(2L086SABD)が人気のノルウェー軍音楽隊と、オスロの混声合唱団、『聖母讃歌』(2L095SABD)をリリースしたスコラ・カントールムです。ウィンドバンドによる演奏、合唱とバンドの演奏。ノルウェー王国の音楽による歴史書とも呼べるアルバムを、ノルウェーを代表するアンサンブルが敬愛の心とともに美しく彩ります。
5.1 DTS-HD MA と 2.0 LPCM の音声を収録した
Blu-ray Disc Audio と SACD Hybrid 盤をセットにしたアルバムです。Blu-ray
Disc Audio にはインデックスを除き映像は収録されていません。SACD
Hybrid 盤はSACD ブレーヤーとCD プレーヤーで再生できますが、Blu-ray
Disc Audio はCD やDVD のプレーヤーでは再生できないので、Blu-ray
プレーヤーもしくは Blu-ray 対応の機器をお使いください。 |
AURORA
|
|
|
瞑想 — シェル・モルク・カールセン(1947-):宗教作品集
キリストの瞑想(Christus-Meditationen)
Op.120
(1997)(オルガンのための)
ソナタ《エフタの娘(Daughter of Jephthah)》
Op.152B
(チェロ独奏のための)
黙示録の瞑想(Offenbarungs-Meditationen)
Op.155
(2006/07)(オルガンのための) |
インゲル=リーセ・ウルスルード(オルガン)
[ウラニエンボルグ教会のクーン・オルガン]
フリーダ・フレドリッケ・ヴォーレル・
ヴェールヴォーゲン(チェロ) |
オルガニスト、カールセンによる「瞑想」
録音:2013 年9 月2 日-4 日 ウラニエンボルグ教会(瞑想)、10
月28 日 ノルウェー・オペラハウス(ソナタ)(オスロ)/80’09
ノルウェー作曲家協会のレーベル Aurora は、シェル・モルク・カールセンの作品集をこれまでに2
枚制作してきました。新しいアルバムでは、オルガニスト、教会音楽家として活躍するカールセンの『聖書』に題材を採った作品が紹介されます。イエス・キリストの生涯に題材を採った7
つの曲から構成される《キリストの瞑想》と『ヨハネの黙示録』に拠る、ロマンティシズムの伝統に則った《黙示録の瞑想》。オルガンのための《瞑想》は両曲ともベルゲン大聖堂の委嘱により作曲され、マグナル・マンゲシュネスが初演した作品です。新しいアルバムのオルガニストはインゲル=リーセ・ウルスルード(1963-)。彼はノルウェー音楽アカデミーの教授を務め、即興演奏のマスタークラスを定期的に開催。彼女が首席オルガニストを務めるオスロのウラニエンボルグ教会は響きの豊かさで知られ、Aurora、Simax、2L
のアルバムの録音場所として使われています。
この教会にオルガンが設置されたのは1884
年。数度の修復と追加が行われ、2009 年にクーン・オルガン工房の手で現在の姿に整備されました。《エフタの娘》はチェロ独奏のための作品です。
「わたしがアンモンとの戦いから無事に帰るとき、わたしの家の戸口からわたしを迎えに出て来る者を主のものといたします。わたしはその者を、焼き尽くす献げ物といたします」(『旧約聖書』「士師記」(11
節)新共同訳による)。
イスラエルの指導者エフタの主への祈りと、主への誓いを果たすための犠牲となった娘への「悲歌」から出発し、「歴史を通じ、苦しまねばならなかった無実の者たちすべての永遠の嘆きの余韻」として完成しました。
《ソナタ》は、2006 年のチェロと管弦楽のための協奏曲(Op.152)をチェロ独奏のために改訂した作品です。フリーダ・フレードリケ・ヴォーレル・ヴェールヴォーゲン(1988-)は、ノルウェー国立音楽アカデミーのオーゲ・クヴァルバインとトルルス・モルク、ケルン音楽大学のフランス・ヘルメション、ストックホルムの王立音楽大学のトゥールレイフ・テデーエンに師事、アンサンブル・アレグリアの首席チェロ奏者を務め、ノルウェー室内管弦楽団にも定期的に参加しています。デクストラ・ムジカから貸与された1823
制作のニコラ・デュポのチェロを弾いています。 |
 HMF HMF
|
|
|
マイ・フェイヴァリット・ダウランド
1. レディ・ハドソンのパフ[P 54] 2. 靴屋の女房[P
58]
3. ミア・バルバラ[P 95] 4. サー・ジョン・スミスのアルマンド[P
47]
5. ファンシー[P 6] 6. サー・ジョン・ラングトンのパヴァーヌ[P
14]
7. デンマーク王のガイヤルド[P 40] 8. カエルのガイヤルド[P23a]
9. ラクリメ[P 15] 10. ラクリメのためのガイヤルド[P
46]
11. ファンタジー[P 1a] 12. 別れ[P 3] 13.
Forlorne Hope Fancye[P 2]
14. エセックスの伯爵、ロバート閣下のガイヤルド
[P 42a]
15. コイ・ジョイ [P 80] 16. ミセス・ヴォーのジグ[P
57]
17. ミセス・ウィンターのジャンプ[P 55]
18. クリフトン卿夫人閣下のスピリット[P45]
19. ウォルシンガム[P 67] 20. ファンシー
[P 5] 21. パヴァーヌ [P 18]
22. The most sacred Queene Elizabeth, her
Gaillard [P 41]
23. Semper Dowland semper dolens [P 9] |
ポール・オデット
(リュート/
8 コース、
マルコルム・プリオール(2008年)、
Sixtus Rauwolf モデル(1590頃)) |
リュートの神様、ポール・オデット、珠玉のダウラウンド・アルバム
録音:2012 年1 月/75’23
リュート界の巨匠、ポール・オデット。オデットは、ダウランドについて、40
年以上前、初めてリュートを手にして、初めて作品を奏でた時からたちまち魅了された作曲家だ、と語ります。ちなみに、オデットは学生の頃ロックバンドでギターを弾いており、友人の勧めでクラシック・ギターも始め、そのレッスンでルネッサンス音楽(ギターに編曲されたもの)と出会い、リュートを手にとるようになったといいます。オデットは、ダウランドについて、「楽器に非常に適したスタイルで書かれており、しかも、奏者は、ただ作品を弾いているのではなく、偉大な芸術の中に取り込まれているような感覚になり、また、何百回と作品に触れてもなお汲めども尽きぬ深さと魅力に満ちている」、と語っています。リュートを手にした時からオデットがずっと敬愛しつづけている作曲家、ダウランドの魅力を、心行くまでゆったりと味わうことのできる1
枚です。
ダウランドの楽譜は、自筆譜はほとんど残っておらず、写譜に頼らざるを得ませんが、それもどれが信頼できるものなのか、また、ダウランドはよく自作に手を入れており、どの段階が決定稿なのかわからない、などという問題がありますが、オデットは、ほぼすべてダウランドの息子ロバートが1610
年に出版した「Varietie of Lute Lessons」の楽譜に依拠しています。 |
 SIMAX SIMAX
|
|
|
グーロ、初の協奏曲アルバム
ブルッフ(1838-1920):ヴァイオリン協奏曲第1番
ト短調 Op.26
プロコフィエフ(1891-1953):ヴァイオリン協奏曲第2番
ト短調 Op.63 |
グーロ・クレーヴェン・ハーゲン(ヴァイオリン)
ビャッテ・エンゲセット(指揮)
オスロ・フィルハーモニック管弦楽団 |
ノルウェー注目の女性ヴァイオリニスト、グーロ、初の協奏曲アルバムはブルッフとプロコフィエフ
録音: オスロ・コンサートホール/49’14
グーロ・クレーヴェン・ハーゲン(1994-)は、ノルウェーの新しい世代の楽家のひとり。プロフェッショナルの道を歩み始めたヴァイオリニストたちのアルバム『9人のヴァイオリニストのための9つのソロ曲』(Aurora
ACD5067)にも起用され、グレン=エーリク・ハウグランの《自分が自分の味方をしないで、誰が味方をするだろう》を弾きました。ノルウェー民俗音楽の故郷として知られるハリングダールとグーブランスダールの間に位置するヴァルドレスに生まれ、2001
年にオスロのバラット・ドゥーエ音楽学校に入学、2012
年の秋からベルリンのハンス・アイスラー音楽大学のアンティエ・ヴァイトハースの下で学んでいます。
17歳の時、ユッカ=ペッカ・サラステの指揮するオスロ・フィルハーモニックの2010/2011
年のシーズンにチャイコフスキーの協奏曲を弾いてコンサート・デビュー。内省と直感の感じられる音楽作りと輝かしい音色がオスロのコンサートホールの聴衆を熱狂させ、翌シーズン、フィルハーモニックが行ったツアーに帯同しています。2010
年ノルウェー・ソリスト賞、2013 年スタトイル賞を受賞。彼女の弾くヴァイオリンは、デクストラ・ムジカから貸与された「ベルゴンツィ」ヴァイオリン。フリッツ・クライスラーの弾いた楽器です。
この録音は、グーロの初めての協奏曲アルバム。ブルッフが1868
年に完成させ、彼の代表作とも言われる協奏曲第1
番。プロコフィエフの円熟したスタイルを反映した、抒情的、直截的な音楽の第2
番の協奏曲。彼女の「心」が一番親しみを感じるという2
曲が選ばれています。
ビャッテ・エンゲセット(1958-)指揮オスロ・フィルハーモニックの公演。エンゲセットは、バラット・ドゥーエ音楽学校で教えるヴァイオリニスト、ヘンニング・クラッゲルードが信頼を置く指揮者のひとりです。
旧譜
『9人のヴァイオリニストのための9つのソロ曲』 |


AURORA
ACD 5067
\2500 →\2290 |
9人のヴァイオリニストのための9つのソロ曲
(1)グレン=エーリク・ハウグラン:
自分が自分の味方をしないで、誰が味方をするだろう
(2007)
グーロ・クレーヴェン・ハーゲン(Vn)
(2)シュンネ・スコウエン:アリスに別の入口を
(2010)
クリストフェル・トゥン・アンデシェン(Vn)
(3)マルクス・パウス:橋の上の婦人たち
ソノコ・ミリアム・シマノ・ヴェルデ(Vn)
(4)ストーレ・クライベルグ:灰 (2010)
ヴィクトリア・プッテルマン(Vn)
(5)シェティル・ヴォスレフ:ヴァイオリン・ソロ
II (2009)
サラ・チェン(Vn)
(6)ギスレ・クヴェルンドク:鏡の国のアリス
(2008)
ミリアム・ヘルムス・オーリエン(Vn)
(7)ヤン・エーリク・ミカルセン:ヴァイオリンのための小品
(2011)
メリンダ・チェンキ(Vn)
(8)ダーグフィン・コック:彫像−ある魂がかつて歌った歌を再発見するため
(アッラン・ペッテション) (2009)
マデレーネ・ベルグ(Vn)
(9)オラヴ・アントン・トンメセン:
一枚の絵をめぐり『月明かりの海辺の接吻』(ムンク
1914 年)(2010)
アン・ホウ・セーテル(Vn) |
|
新時代ノルウェーのヴァイオリニストたちによる新時代のヴァイオリン音楽
74’09”
今日のノルウェーでは新しい世代のヴァイオリニストたちが次々と音楽シーンに登場してきています。当アルバムに登場する9人のヴァイオリニストは、1990
年から1996 年の間に生まれ、オスロのバラット=デゥーエ音楽学校に学びました。
9 人が演奏する曲を書いたのは、グレン=エーリク・ハウグラン(1961-)、シュンネ・スコウエン(1950-)、マルクス・パウス(1979-)、ストーレ・クライベルグ
(1958-)、シェティル・ヴォスレフ(1939-)、ギスレ・クヴェルンドク(1967-)、ダーグフィン・コック(1964-)、オラヴ・アントン・トンメセン(1946-)
らノルウェーのベテランと新進の作曲家。北欧の若い音楽家たちからの委嘱がひっきりなしというヤン・エーリク・ミカルセン(1979-)
の曲も注目されます。
これら9 曲は、ほとんどがこのディスクで演奏するヴァイオリニストのために書かれ、ベルゲン国際フェスティヴァルあるいはヴァルドレスで6
月に行われる室内楽フェスティヴァルで初演されました。 |
|
| |
|
|
ファッテイン・ヴァーレン — モダニズムへの道程
ファッテイン・ヴァーレン(1887-1952):
弦楽四重奏曲 Op.0
ヴァイオリンソナタ Op.3
ピアノ三重奏曲 Op.5 |
アイナル・ヘンニング・スメビ(ピアノ)
トール・ヨハン・ボーエン(ヴァイオリン)
ペール・クリスチャン・スカルスタード(ヴァイオリン)
ベネディクト・ロワイエ(ヴィオラ)
ヨハンネス・マッテンス(チェロ) |
録音:2012 年7 月4 日-6 日、10 月11 日-13
日 ソフィエンベルグ教会(オスロ)/制作:
スティーヴン・フロスト, 録音: ジェフ・マイルズ/52’33
ノルウェーのヴァーレンは、1900 年前期の音楽に新生面を開いた作曲家のひとり。謙虚、控えめでありながら、強い信念をもって独自の道を歩みました。新録音によるヴァーレン作品集『モダニズムへの道程』は、初期の室内楽作品が紹介されます。クラシカル=ロマンティックな作風から、一般に使われるのとは異なるヴァーレン独自の「実験的モダニズム」へと、「ゆったりと」移行する時代の3
曲です。クリスチャニア(現オスロ)でカタリヌス・エリングの下で作曲法を学んでいたころ作曲され、この作品がマックス・ブルッフの目に留まったことからベルリン音楽院への門戸が開かれたという、作品番号のない弦楽四重奏曲。そして、北欧音楽の研究家、イギリスのジョン・ホートンが「部分的には調的な語法から完全に解放された十二音技法へと推移する過程を記録する強烈な個性の作品」(ジョン・ホートン『北欧の音楽』大束省三・訳)と述べたヴァイオリンとピアノのためのソナタ(1916
年)とピアノ三重奏曲(1917 年から1924 年)。三重奏曲は、作品集(PSC3116)にも含まれていた作品です。
ピアニストのアイナル・ヘンニング・スメビ(1950-)はノルウェー国立音楽アカデミーの教授。古典と「今日」の音楽、グリーグとセーヴェルーの音楽を主なレパートリーにコンサート活動を行い、ヴァーレンの音楽はピアノ作品全曲を録音しています。ヴァイオリニストのトール・ヨハン・ボーエン(1971-)は国立音楽アカデミーで学んだ後、アメリカでカミラ・ウィックスとセルジウ・ルカに師事しています。ピリオド楽器とモダン楽器を演奏。手稿譜を調査、研究したイザイの『弦楽のための三重奏曲集』(PSC1295)が代表的録音です。ペール・クリスチャン・スカルスタード(1972-)はオスロ弦楽四重奏団の創設メンバー。ノルウェー室内管弦楽団でも演奏しています。ヴィオラのベネディクト・ロワイエは、パリ生まれ。パリ音楽院、オスロのアカデミー、ザルツブルクのモーツァルテウムに学び、フランス、ノルウェー、スウェーデンなど各地で活動。ボーエンの創設したアンサンブル、フラガリア・ヴェスカのトヴェイト作品集(PSC1222)にも参加しました。
チェロのヨハンネス・マッテンス(1977-)はオスロ・フィルハーモニックの団員。室内楽奏者としても活躍しています。彼が主宰するアンサンブルのエリオット・カーター室内楽作品集(2L54SACD)は、欧米で高い評価を獲得した一枚です。 |
WAON RECORDS
|
|
|
ジャン=フィリップ・ラモー(1683-1764):
クラヴサン曲集[クラヴサン曲集(1706)]
1. プレリュード 2. アルマンド 3. 第2アルマンド
4. クーラント 5. ジーグ 6. 第1サラバンド&第2サラバンド
7. ヴェニシエンヌ 8. ガヴォット
9. メヌエット[クラヴサン曲集(1724)]
10. アルマンド 11. クーラント 12. ロンドー形式のジーグ
13. ロンドー形式の第2ジーグ 14. 鳥のさえずり
15. 第1リゴドン、第2リゴドンとドゥブル
16. ロンドー形式のミュゼット 17. タンブーラン
18. 村人たち19. 優しい嘆き 20. 女神たちの対話
21. つむじ風[新クラヴサン曲集(1729-30)]
22. トリオレ 23. 未開人 24. 異名同音 |
三和睦子(チェンバロ) |
|
|
ワオンレコードのハイ・レゾ音源ソフト、ハイレゾリューション・オーディオ・データ、パソコンで再生する新しいオーディオ。CDをはるかに凌駕するハイサンプリングと高ビット深度が、溢れる音楽の熱情とともに広大な音場の空気感までを再現します。
CD,SACD,DVD プレーヤーでは再生できません。
使用楽器:アンリ・エムシュ 1751年製(オリジナル/フレデリック・ハース氏所蔵)
A=405Hz,録音:2012年7月1-3日、フランワレ教会(ベルギー、ナミュール市郊外)
(2DVD-ROM) High Resolution Audio Data、176.4kHz/
24bit WAVE、96kHz/ 24bit、ダウンコンバートデータ、同時収録、STEREO・WAVE、PC-AUDIO
(DVD-ROM) High Resolution Audio Data、2.8224MHz
DSDIFF、STEREO・DSDIFF、DSD-AUDIO
ヨーロッパと日本で活躍する実力派、三和睦子の新譜。2010
年にリリースした日本では初めてとなるソロCD「J.S.
バッハ:トランスクリプション集」はレコード芸術で特選盤および優秀録音に選ばれました。今回の作品は、フランス・バロックの粋、ラモーのクラヴサン曲集。各曲の性格を巧みに描き分けながら、情感たっぷりに奏でています。ラモーも弾いたのでは、といわれているアンリ・エムシュのオリジナルの名器を用いており、楽器の音色も注目ポイント。リッチで鮮烈な音色に圧倒されます。
【再生上の注意】
ワオンレコードのオリジナルマスターをあまさず収めたこの高音質音源をお楽しみ頂くには、DVD-ROM
を読み込み可能なディスクドライブを接続したパソコンと、適切なソフトウェア、オーディオ・インターフェース機器をご用意いただく必要があります。通常のCD、SACD、DVD
プレーヤーでは再生できません。 |
<マイナー・レーベル歴史的録音・旧録音>
 OPUS蔵 OPUS蔵
|
|
|
ジネット・ヌヴー〜ソナタと小品集
・グルック:「オルフェオとエウリディーチェ」〜メロディ(ヴィルヘルミ編曲)
・パラディス:シチリア舞曲(ドゥシキン編曲)
ブルーノ・ザイドラー・ヴィンクラー(ピアノ)/録音:1938
年、ベルリン
・R.シュトラウス:ヴァイオリン・ソナタ
変ホ長調 Op.18
・タルティーニ:コレルリの主題による変奏曲(クライスラー編曲)
グスタフ・ベック(ピアノ)/録音:1939
年、ベルリン
・ラヴェル:ツィガーヌ
・ショパン:夜想曲第20番 嬰ハ短調(遺作)(ロディオノフ編曲)
・スーク:4つの小品Op.17
・ディニーク:ホラ・スタッカート(ハイフェッツ編曲)
・ファリャ:歌劇『はかなき人生』〜スペイン舞曲(クライスラー編曲)
ジャン・ヌヴー(ピアノ)/録音:1946
年、ロンドン |
ジャネット・ヌヴー(ヴァイオリン) |
ヌヴーのスタジオ録音を集めた2 枚!彼女の戦前のベルリンでのR.
シュトラウスのソナタと戦後の傑作ショーソンの「ポエム」など名演揃い!
原盤:SP Electrora HMV
これまでオーパス蔵のSP やLP の復刻は一部の例外を除いて安原暉善の手によるものでした。今回は初めての試みでCD
全部の復刻が広川陽一氏によるものです。
実はまだオーパス蔵が誕生する前に安原氏が広川氏にSP
の音をきちんと取り出す手順を指導しており、その後広川氏がさらに自分なりに技術を発展させております。言ってみれば師匠と弟子の関係にあるわけで、広川の音には安原のDNA
が入り込んでいます。弟子の音をお楽しみいただければ幸いです。(復刻者:広川陽一)
今回のCD には、彼女がまだ10 代だった貴重な戦前のSP
録音と、LP 時代から有名だった戦後のSP の名演奏を、広川氏のコレクションから御自身の復刻でまとめたものです。ヴァイオリンのオーパス蔵の評判に相応しいオーパス蔵のリアリスティックな音質で復刻されています。グルックの「メロディ」とパラディスの「シシリエンヌ」が1938
年4 月13 日、ベルリンにおけるヌヴーの記念すべき最初のセッション録音です。 翌年1939
年3 月、同じくベルリンでリヒャルト・シュトラウスのヴァイオリン・ソナタを録音しました。シュトラウスは今年(2014
年)生誕150 年を迎えましたが、1939 年は生誕75
年にあたり、おそらくはその記念録音だったのでしょう。ヌヴーの本格的な録音は戦後すぐにロンドンで始まりました。協奏曲はシベリウス、ブラームスが残されましたが(OPK
2064)、ここでは小品を集めております。(OPUS
蔵 相原了) |
| |
|
|
ジネット・ヌヴー「ポエム」&ヨーゼフ・ハシッド全録音
・ショーソン:詩曲Op.25
ジャネット・ヌヴー(ヴァイオリン)
イサイ・ドブロウェン(指揮) フィルハーモニア管弦楽団
・ラヴェル:ハバネラ形式の小品
・スカルラテスク:バガテル
・ドビュッシー:ヴァイオリン・ソナタ ト短調*
ジャネット・ヌヴー(ヴァイオリン) ジャン
ヌヴー(ピアノ)
録音:*1948年、その他は1946 年、ロンドン
・ドヴォルジャーク:ユモレスク(クライスラー編曲)
・チャイコフスキー:メロディ~ 懐かしい土地の思い出より
・サラサーテ:プライェーラ(スペイン舞曲集第5番)
・サラサーテ:サパテアード(スペイン舞曲集第6番)
・マスネ:タイスの瞑想曲
・アクロン:ヘブライの旋律
・クライスラー:ウィーン奇想曲
・エルガー:気まぐれ女
ヨーゼフ・ハシッド(ヴァイオリン) ジェラルド・ムーア(ピアノ)
録音:1940 年、ロンドン |
原盤:SP HMV/仏 VSM-LP (ショーソン、ドビュッシー)
ヌヴーの録音したショーソンの「ポエム(詩曲)」とドビュッシーのヴァイオリン・ソナタはSP
では発売されませんでした。恐らく最終の承認が出る前にヌヴーの乗る飛行機が墜落したためでしょう。遺族の承認を得て発売されたのは1957
年ですが、このときは既にLP の時代になっておりSP
原盤から復刻されたLP として発売されました。
ヌヴーの録音の中でも名演と評される「ポエム」を抜きにすることは許されません。そこでここでは「ポエム」とドビュッシーのソナタをフランス盤LP
から復刻しました。ヌヴーと同時代の才能あるヴァイオリニストにハシッドがいます。ただ彼は今で言う統合失調症を発し、ロボトミー手術の後26
歳で亡くなったためほとんど知られていません。彼は16
歳のとき1940 年にロンドンで録音を行いましたが、これらは素晴らしい演奏です。
ここでは前年の試し録音を除く発売された録音をまとめました。ヌヴー、ハシッドという若くして亡くなった2
人の演奏をお聴きください。(OPUS 蔵 相原了) |
<国内盤>
りゅーとぴあ
|
|
|
グレンツィング・オルガンの魅力 〜J.S.バッハとスペイン音楽〜
セバスチャン・アギュイレーラ・デ・エレディア(ca.1565-1627):エンサラータ
パブロ・ブルーナ(1611-1679):第2 旋法の過ったティエント
同:第6 旋法によるティエント“ウト・レ・ミ・ファ・ソル・ラ”
アントニオ・コレア・ブラーガ(17世紀頃):バッターリャ
J.S.バッハ:幻想曲 ト長調 BWV572
同:コラール“最愛なるイエスよ、我らここに集いて”BWV731
同:コラール“目覚めよと呼ぶ声がして”BWV645
同:前奏曲とフーガ ト長調 BWV541 |
山本真希(オルガン) |
ホールの座席300席を撤去して行われたこだわりの超優秀録音!!各紙で絶賛された、りゅーとぴあのオルガン録音
録音:2011 年10 月24-26 日、りゅーとぴあ新潟市民芸術文化会館、コンサートホール/DDD
りゅーとぴあの自主制作盤。新潟市民芸術文化会館のコンサートホールに備え付けられたグレンツィング・オルガンを用いたオルガン名曲集!演奏は、2006
年より同ホールの専属オルガニストを務める山本真希で、スペイン製グレンツィング・オルガンの艶やかな音色を余すところなく引き出した選曲となっております。
この録音で興味深いのは、最適な音響を得るためホールの座席300
席を撤去しておこなわれたことです。パイプの前後感やホールの空気感まで表現され、またオルガンの澄み切った音色を捉えた超優秀録音です。
なお、当盤はCD のみのリリースとなります。絶賛されているサン=サーンスの交響曲第3
番(CD:RYUT 0001、SACD:RYUTSA 0001)とあわせてお楽しみください。
山本真希(オルガン)
大阪府出身。神戸女学院大学音楽学部、同大学専攻科で学んだ後、ドイツ国立フライブルグ音楽大学大学院修了。ドイツ国立シュトゥットガルト音楽・演劇大学ソリスト科に在籍し、最優等の成績でオルガンソロに合格。ドイツ国家演奏家資格を取得。あわせてフランス、ストラスブール音楽院で学ぶ。オルガンを井上圭子、サットマリー、ボッサート、ラウクヴィック、モントーの各氏に師事。第1
回、ドイツ・ランデスベルク国際オルガンコンクール第3
位。日本オルガニスト協会会員。2006 年4 月、りゅーとぴあ新潟市芸術文化会館専属オルガニストに就任。主催公演での演奏、オルガン事業の企画制作、オルガン講座のレッスンおよびオルガンの保守管理にかかわる業務などを担当し、オルガン音楽の普及と発展につとめている。

|

4/22(火)紹介新譜
マイナー・レーベル新譜
 DACAPO DACAPO
|


6.220574
(SACD-Hybrid)
\2200→\1990 |
サカリ・オラモ(指揮)&ウィーン・フィル!!
ペア・ノアゴー:交響曲 第1番&第8番
1-3.交響曲 第1番「sinfonia austera」
(1953-1955/1956改編)/
4-6.交響曲 第8番(2010-2011)
※4-6…世界初録音 |
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団/
サカリ・オラモ(指揮) |
録音 2013年5月16-17日 ウィーン,コンチェルトハウス…1-3,
2013年5月25-26日 ウィーン,コンチェルトハウス,ライブ録音…4-6
ノアゴー(1932-)は、現代デンマークで最も人気を誇る作曲家の一人。彼独自の手法である「無限セリー」や、多彩なパーカッションを用いた作品などで知られます。世界初録音を含むこのアルバム、演奏はなんと、サカリ・オラモが指揮するウィーン・フィルハーモニー。
北欧における最も新しい交響曲がウィーン風の響きを纏って演奏されるその素晴らしさと不思議な感覚。これは得難い体験であり、またウィーン・フィルの新たな側面を知るためにも最適なアルバムと言えるでしょう。
世界初録音となる交響曲第8番は、彼のこれまでの作品と比べても、かなり古典的で研ぎ澄まされた筆致を持つもので、彼が至った境地を垣間見ることができるはずです。 |
| |


8.226114
\2000→\1890 |
ポール・ヒリアー(指揮)&ロンドン・シンフォニエッタ
ペレ・グドムンセン=ホルムグレーン:Mixed
Company
1.Run(2012)/2.Turn Ⅱ(2012)/3.Song(2010)/
4.Play(2010/2012改編)/5.Sound I(2011)/
6.Sound Ⅱ(2012)/7.Company(2010)
※世界初録音 |
テアトル・オブ・ヴォイセス/
ロンドン・シンフォニエッタ/
ポール・ヒリアー(指揮) |
録音 2012年10月6日 コペンハーゲン 王宮図書館,ブラック・ダイアモンド,クィーンズ・ホール
ライブ収録
先鋭的な作風で知られるグドムンセン=ホルムグレーン(1932-)。このアルバムは彼の作品集「Mixed
Company」の世界初録音盤となります。演奏するのはロンドン・シンフォニエッタとテアトル・オブ・ヴォイセス、指揮はおなじみポール・ヒリアーです。
作品は、4世紀前のダウランドの作品からインスパイアされたフレーズが様々に形を変えながら、新しい音楽を形作っていくというもので、息を飲むような複雑なハーモニーに彩られた旋律は、「過去へのオマージュ」と「新しい世界の発見」という相反する2つの喜びを聴き手にもたらすものです。 |
| |

8.226561
\2000 |
ファジー-記憶の中のチャイム
1-3.ノートル・ダム三部作(2002-2006)/
4.B-ムーヴィーズ(1997)/
5.記憶の中のチャイム(1987)/
6-8.Tre tilbageblik(2004)/
9.Stjerner over Kobenhavns Forbrandingsanstalt
(1975) |
グレーテ・クロフ(オルガン)/
ティーネ・レーリング(ハープ)/
ジャネッテ・バランド(サクソフォン) |
録音 2008年 コペンハーゲン大聖堂,クラウス・ビリス…1-3,
2012年12月2日 フレデンクベルク,ファジー・スタジオ…4,
1987年 フレデンクベルク,ファジー・スタジオ…5,
2012年11月28-29日 ゲントフテ,CLスタジオ…6-8,
1975年 フレデンクベルク,ファジー・スタジオ…9
“ファジー”とは、現代デンマークのミュージシャン。彼は1939年に生まれ、若い頃は「イェンス・ヴィルヘルム・ペデルセン」の本名を名乗っていましたが、いつしかこちらのニックネームの方が有名になった人です。
彼は荒々しい髪と髭を持ち、即興演奏に優れ、また電子音楽の分野でも素晴らしい作品を書いています。
彼の造りだす音は、実験的であり、機知に富み、また幾許かの郷愁を帯びています。
このアルバムでは、その「懐かしさ」が前面に押し出されており、オルガンやハープ、サクソフォンの響きが極めて幽玄な音を醸し出しています。 |
| |

8.226572
\2000 |
デュオ・カポウ!-バースト
1.ニルス・マルティンセン(1963-):バースト(1990)/
2.シモン・ステーン=アナセン(1976-):
アルトサックスとパーカッションのための「スタディ」(1998)/
3.イェクスパー・ホルメン(1971-):
アルトサックスとパーカッションのための「オイル」(2003)/
4.モルテン・レイドホフ(1978-):
Pyr, ami spy, ram isp yra mis(2003)/
5.ニルス・レンスホールト(1978-):
飲めば本当の私が出来上がる(2002)/
6.カスパー・ジャルナム(1971-2011):
Der Totenschlager und der Rattenfanger(2001) |
クラウス・オーレセン(サクソフォン)/
ヘンリク・クナルボルク・ラーセン(パーカッション) |
録音 2009年12月21-22日 オーフス王立音楽アカデミー
デンマークの作曲家たちによる、サックスとパーカッションのための作品のコレクションです。標準的な形式の中に組み込まれた様々な感情の発露・・・絶望と憂鬱、鬱積した思い、もつれ、叫びなど、時には異様とも思える音のぶつかり合い。
聴き手は、これらの錯綜した音の中から幾つもの可能性を見出す楽しみにふけることができるはずです。 |
| |

8.226578
\2000 |
ルネ・グレロプ:dust encapsulated
1.リコーダー,ヴァイオリン,とアコーディオンのための「オブジェクト」(2008)/
2.パーカッションとエレクトロニクス・ライヴのための「dust
encapsulated #1」(2008-2009)/
3.フルート,クラリネット,ヴァイオリン,チェロとピアノのためのdust
encapsulated #2(2009)/
4-10.ピアノのための「7つの楽章のソナタ」(2011)/
11.シンフォニエッタ・ディヴェルティメント(2010-2011) |
ニール・ブラムスネス・テイルマン(ピアノ)/
マティアス・エリス=ハンセン(パーカッション)/
ギャマン(アンサンブル)/
アスラス・シンフォニエッタ・コペンハーゲン/
ピエール・アンドレ=ヴァラーデ(指揮) |
録音 2012年12月 コペンハーゲン,ガルニソン教会…1,
2013年3月19日 コペンハーゲン王立音楽アカデミー…2.4-10,
2013年5月25日 コペンハーゲン歌劇場,オーケストラ・リハーサル室…3,
2013年4月3日 モンテカルロ.芸術の春音楽祭
エンパイア・ホール ライヴ録音…11
「幼い頃から音楽を学び、自分が作曲家になることを確信していた」というルネ・グレロプ(1981-)。彼は常に新しい響きを求め、音楽に独自の世界を語らせようとします。
ここでは5つの作品の世界初演録音を聴くことができます。強いエネルギーを帯びたこれらの音は、空気中に拡散されてこそ、新たな命を得るものと言えるでしょう。 |
 NAIVE NAIVE
|
|
|
リーズ・ドゥ・ラ・サール最新盤
シューマン(1810-1856):
子供の情景 op.15
アベッグ変奏曲 op.1
幻想曲 ハ長調 op.17 |
リーズ・ドゥ・ラ・サール(ピアノ) |
世界を翔ける麗しきピアニスト、リーズ・ドゥ・ラ・サール最新盤はシューマン!音楽への喜びが迸るアベッグ変奏曲
録音:2013 年12 月
世界を翔ける活躍ぶり、そして来日も重ね、人気・実力ともに急上昇のリーズ・ドゥ・ラ・サール。最新盤はシューマンの3
作品。アベッグ変奏曲は、シューマンの最初期の作品のひとつで、シューマンが法学の勉強をやめ、音楽に本格的に取り組み始めたころのもの。音楽を書くことへの純粋な喜びのようなものを感じるとリーズは語っており、彼女の演奏も非常に素直に華麗にこの作品を紡いでいます。「子供の情景」も、彼女の深くあたたかみのあるタッチで紡ぐ第1曲から、シューマンの世界に引き込まれます。ひとつひとつのメロディーを慈しみながら、リズムのセンスも非常に優れていて、推進力のあるシューマンを展開しています。幻想曲も、ほとばしるようなシューマンの情感たっぷり。ピアニストとして、女性として、ますます深みを増していることを感じさせる出来栄えです。

リーズ・ドゥ・ラ・サール旧譜
ただのカワイ子ちゃんだと思っているとガブっと食いつかれる。
1988年生まれの美貌と才能に恵まれたピアニスト、リーズ・ドゥ・ラ・サール。13才から国外コンサートに招かれているとか、既に数々のコンクールで一等を獲得しているとか、そんなことは二の次。とにかくこれらのCDで聞ける演奏にただただ驚くばかり。その鮮烈な感性、圧倒的な技巧、豊かな表現力・・・まさに才能の塊。「フランスの至宝」と呼ばれるのは分かるような気がする。 |
|
|
<マイナー・レーベル歴史的録音・旧録音>
 TAHRA TAHRA
|
|
|
衝撃、ターラ最後のリリース!
さよならTAHRA!
「ターラ・ストーリー」
(1)ラモー:6声のコンセール第6番 初出
(2)シューベルト:交響曲第8番ロ短調D759「未完成」
(3)ブルックナー:交響曲第7番ホ長調WAB.107〜第1楽章 初出
(4)ベートーヴェン:交響曲第7番イ長調op.92〜第1楽章
(5)ベートーヴェン:交響曲第5番ハ短調op.67〜第2楽章 |
(1)ヘルマン・シェルヘン(指揮)
フランス国立放送管弦楽団
(2)ヘルマン・シェルヘン(指揮)
北西ドイツ・フィルハーモニー
(3)ヘルマン・アーベントロート(指揮)
メクレンブルク・シュターツカペレ・シュヴェリーン
(4)ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(指揮)
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
(5)ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(指揮)
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 |
ヒストリカルの雄ターラ最後のリリース「ターラ・ストーリー」シェルヘン、アーベントロート、フルトヴェングラー、スタートを飾ったのと同じ3巨匠の演奏で振り返るレーベルのあゆみ
(1)収録:1964 年3 月6 日/パリ、ORTFスタジオ (2)収録:1960
年2 月11日 (3)収録:1951年 (4)収録:1943
年10 月31 日-11 月3 日 (5)収録:1954年2
月-3月/ADD、モノラル、76’56”
フランスのTahra レーベルは、2014 年2 月13
日にレーベルの顔であるルネ・トレミヌ氏が亡くなられたのを機に、ヒストリカルの雄として22
年間に655 のタイトルを世に送り出したその活動に終止符を打つことになりました。
「Tahra Story」と銘打たれた最後のアルバムには、1992
年の初心に立ち返り、当時と同じく3 人の巨匠シェルヘン、アーベントロート、そしてフルトヴェングラーのライヴ演奏が選ばれ、このうち、シェルヘンによるラモーと、アーベントロートによるブルックナーとが初出音源となります。
ブックレットの構成は、レーベルの共同運営者で、トレミヌ氏の公私に亘るパートナーのミリアム・シェルヘン氏のレーベル終了のあいさつに始まり、レーベルのあゆみが綴られたあと、最後にトレミヌ氏自身によるエッセイ「ターラのすばらしいひととき」も掲載しています。また、フルトヴェングラー未亡人との2
ショットや、大切にしていた家族との写真の数々も収められています。 |
<映像>

|
![]()