 ALTUS ALTUS
|


ALTSA 276/7
( 2SACDシングルレイヤー)
\8500 →\7990 |
ウィーン芸術週間 1960 ベートーヴェン:交響曲全曲演奏会
Disc 1
・交響曲第1番ハ長調 op.21(録音:1960
年6 月7 日)
・交響曲第2番ニ長調 op.36(録音:1960
年5 月29日)
・交響曲第3番変ホ長調 op.55『英雄』(録音:1960年5
月29日)
・交響曲第4番変ロ長調 op.60(録音:1960年5
月31 日)
・交響曲第5番ハ短調 op.67『運命』(録音:1960年5
月31 日)
・交響曲第6番ヘ長調 op.68『田園』(録音:1960年6
月2 日)
Disc 2
・交響曲第7番イ長調 op.92(録音:1960年6
月2 日)
・交響曲第8番ヘ長調 op.93(録音:1960年6
月4 日)
・交響曲第9番二短調 op.125『合唱』(録音:1960年6
月7 日)*
・《コリオラン》序曲 作品62( 録音:1960年6
月4 日)
・《エグモント》序曲 作品84( 録音:1960年5
月31 日)
・《プロメテウスの創造物》序曲 作品43(
録音:1960年6 月2 日) |
オットー・クレンペラー(指揮)
フィルハーモニア管弦楽団
ウィルマ・リップ(ソプラノ)
ウルズラ・ベーゼ(コントラルト)
フリッツ・ヴンダーリヒ(テノール)
フランツ・クラス(バス)
ウィーン楽友協会合唱団* |
※通常のCDプレーヤーでは再生できません。
SACDの長時間収録のメリットを生かし2SACDに!LP
制作で使用したアナログ・マスターをDSD 化野太い音質で登場!
クレンペラーの偉大さの証明!1960 年ウィーン芸術週間ベートーヴェン・ツィクルス・ライヴ、チェトラ盤以来最高の音質で登場。
「第九についてもこれに匹敵する演奏はない」(ハインリッヒ・クラリーク)
「しかしなんという緊張と迫力。なんという剛健さ、なんという構造の明快さ、そして賛歌のごときエクスタシー」(エクスプレス紙) と絶賛された伝説のツィクルスです。
ライヴ録音:ムジークフェラインザール/ライヴ、モノラル
クレンペラーはベートーヴェンの交響曲全曲をツィクルスで演奏することにこだわりがあり、フィルハーモニアとも3
回目のそして海外で初めての挙行となったのがこの1960
年ウィーン芸術週間でありました。この圧倒的大成功をおさめたこの演奏会を当時聴いていた外山雄三氏は「指揮はクレンペラーですばらしかった。フィルハーモニアというのも我々がレコードで聴くのと全く同じ音ですよ。非常に艶がある。ツヤツヤしている。あんな艶のあるオーケストラは聴いたことがない。それにアンサンブルが完璧です。クレンペラーは非常に偉大な人格だから、かれの人間でもって非常にすばらしい演奏になるのです」(レコード芸術S35
年8 月)と激賞されておりました。実際今きいても異常な緊張感と迫力にあらためてクレンペラーの偉大さを思い知らされました。
肝心の音質も過去に出たものと比べてみましたが、そうとう優れております。演奏の凄さが音質の良さも手伝い感銘度のかなり高いディスクにしあがっております。 |
| |
ムラヴィンスキー&レニングラードフィル、レニングラードスタジオ録音、
音質刷新 新マスタリング初SACD
化!
|
レニングラードスタジオが収録したムラヴィンスキー幻の音源は、2005
年12 月にALTUS よりBOX セットで発売されました。
そこには一カ月後に日本公演を控えた同団の入念なリハーサルとムラヴィンスキー入魂のリハーサルも含まれていましたが、今回演奏会部分をSACD
シングルレイヤー化。
国の威信をかけた日本公演へのエネルギーと真摯さがさらにまざまざと蘇りました。
数あるムラヴィンスキーの記録のなかでも、音質、迫力No.1。人間業の限界に挑戦しています。 |

ALTSA 185
(SACD シングルレイヤー)
\4200 |
ベートーヴェン&ブラームス:交響曲
ベートーヴェン:交響曲第4番
変ロ長調 Op.60
ブラームス:交響曲第4番 ホ短調
Op.98 |
エフゲニー・ムラヴィンスキー(指揮)
レニングラード・フィルハーモニー交響楽団 |
この完成度は全く比類がない!それがきちんと保管され、望みうる最上の状態で復刻されたのは、ファンにとってはまことにありがたい。(平林直哉)
ライヴ録音:1973 年4 月28 日、レニングラード・フィルハーモニー大ホール/ステレオ、ライヴ録音、新マスタリング
ALT-114(8CD) 発売時(2005 年12
月26 日)
初出だった名演奏の待望の初SACD
化!伝説の来日直前の演奏。すごい緊張感で聴き手を金縛り!音の良さに大変驚きました。これほどの演奏を聴いてしまうと大変で、まさに麻薬のようでございます。あの日本公演の超絶的名演の原点がここにあります。
※通常のCDプレーヤーでは再生できません。 |
| |

ALTSA 186
(SACD シングルレイヤー)
\4200 |
ブルックナー:交響曲第9番 ニ短調 |
エフゲニー・ムラヴィンスキー(指揮)
レニングラード・フィルハーモニー交響楽団 |
ビクター時代からの名盤復活!私はこのブルックナーを高く評価する。これほど透明で激しく力強く描いた演奏は希有である。(平林直哉)
ライヴ録音:1980 年1 月29&30日、レニングラード・フィルハーモニー大ホール/ステレオ、ライヴ録音、新マスタリング
旧ビクター音産から発売され名盤の誉れ高かった演奏ですが、オリジナル音源から新たにデジタルトランスファーされ、新マスタリングにより、見違えるような音質に仕上がりました。その音質の素晴らしさゆえにムラヴィンスキーのヴァイオリン両翼配置の美しさと強力な金管、浮きあがる木管など実に美しくしかも克明に再現されます。素晴らしいの一言でございます。
※通常のCDプレーヤーでは再生できません。 |
| |

ALTSA 191
(SACD シングルレイヤー)
\4200 |
ショスタコーヴィチ:交響曲第5番 ニ短調 Op.47 |
エフゲニー・ムラヴィンスキー(指揮)
レニングラード・フィルハーモニー交響楽団 |
ムラヴィンスキーの数ある『革命』の中でも、あの特別な73
年の日本公演に匹敵する音質、演奏内容といえる(平林直哉)
セッション録音:1973 年5 月3
日、レニングラード・フィルハーモニー大ホール/ステレオ、セッション録音、新マスタリング
さすがオリジナルテープからのデジタルトランスファーだけあってすばらしい音質!演奏はまさに完璧の一言で、ムラヴィンスキーらしい異様な緊張感と迫力で一気に聴かせます。聴いていて恐ろしくなるほど。それにしてもいつ聴いてもムラヴィンスキーはすばらしい!平林直哉氏の資料に基づいた解説も大いに参考になります。
※通常のCDプレーヤーでは再生できません。 |
| |

ALTSA 192
(SACD シングルレイヤー)
\4200 |
デジタルトランスファーの効果絶大!
チャイコフスキー:交響曲第5番
ホ短調 Op.64
プロコフィエフ:『ロメオとジュリエット』組曲第2番
Op.64 より
(モンタギュー家とキャピュレット家/
少女ジュリエット/僧ローレンス/
別れの前のロメオとジュリエット/
アンティーユ諸島から来た娘たちの踊り/
ジュリエットの墓の前のロメオ) |
エフゲニー・ムラヴィンスキー(指揮)
レニングラード・フィルハーモニー交響楽団 |
ムラヴィンスキーのチャイコフスキー5 番に対する解釈はまさに微動だにしない、盤石なものである。これだけ徹底し突き詰めた表現は聴けば聴くほど驚異である。また、プロコフィエフは音質の良いこの演奏があれば十分だろう。(平林直哉)
ライヴ録音:1982 年11 月6 日、レニングラード・フィルハーモニー大ホール/ステレオ、ライヴ録音、新マスタリング
このチャイコフスキーとプロコフィエフもすばらしい音質。これもオリジナルテープから丁寧なデジタルトランスファーの効果絶大!盤鬼平林氏は17
種あるムラヴィンスキーのチャイ5
のうち、当盤とグラモフォン60
年盤があれば!と激賞の様子でございます。
※通常のCDプレーヤーでは再生できません。 |
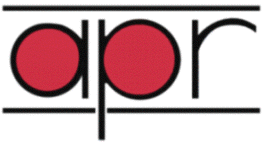 APR APR
|


APR 6014
(2CD/特別価格)
\2800 →\2590 |
トバイアス・マッセイとその弟子たち
トバイアス・マッセイ 〜
マッセイ:
《組曲形式による練習曲》Op.16より
第1番、第8番、
《サリー州の丘にて》Op.30より
第1番、第4番
(録音:1932年11月16日)
アイリーン・シャーラー 〜
シューマン:
ピアノ・ソナタ第2番ト短調
Op.22より
第1楽章、第3楽章、第4楽章
(録音:1924年3月4日)
ショパン:前奏曲第23番ヘ長調
Op.28(録音:1925年10月28日)
シューベルト:即興曲変イ長調
Op.90-4(録音:1930年5月12日)
ライエ・ダ・コスタ 〜
リスト:
ヴェルディの《リゴレット》による演奏会用パラフレーズ
S.434
(録音:1930年6月13日)
グリュンフェルト:ウィーンの夜会
Op.56(録音:1930年6月13日)
エセル・バートレット 〜
J.S.バッハ(ルンメル編):愛しきイエスよ、われらはここに
BWV.731
(録音:1929年12月23日)
デニス・ラッシモンヌ 〜
J.S.バッハ:2声のインヴェンション
BWV.772-786
(録音:1941年9月23日)
モーツァルト:幻想曲とフーガ
ハ長調 K.394(録音:1941年6月13日)
アーネスト・ラッシュ 〜 グリーグ:ハリング(録音:1955年10月25日)
アドルフ・ハリス 〜
ドビュッシー:《12の練習曲》より
第9番、第10番
(録音:1938年2月3日−5日)
ハリエット・コーエン 〜 トゥリーナ:魅惑の踊り(録音:1945年7月16日)
ユーニス・ノートン 〜オネゲル:コンチェルティーノ
〔ユージン・オーマンディ(指揮)、ミネアポリス管弦楽団〕
(録音:1935年1月15日)
ニーナ・ミルキーナ 〜
スカルラッティ:
ソナタ ト長調 Kk.125、ソナタ
イ長調
Kk.208、
ソナタ ニ短調 Kk.396、ソナタ
ニ長調
Kk.29(録音:1958年6月)
ブルース・シモンズ 〜 シューベルト:即興曲変ロ長調
Op.142-3
(録音:1950年代)
レイ・レフ 〜 シューマン:ノヴェレッテ嬰へ短調
Op.21-8(録音:1952年)
エガートン・ティドマーシュ
〜
J.S.バッハ:《パルティータ第5番》より
前奏曲
モシュレス:練習曲ホ長調
Op.70-4(録音:1923年7月&8月)
デジレ・マキューアン 〜
ブラームス:ワルツ変イ長調
Op.39-15
J.S.バッハ:《イギリス組曲第3番》より
ジーグ ト短調(録音:1923年3月)
ラエ・ロバートソン 〜
パーセル:前奏曲ハ長調、ハイドン:アレグロ・コン・ブリオ、
イエンゼン:あこがれ(録音:1925年)
ドロシー・ハウエル 〜
ヘンデル:クーラント、バック:前奏曲ハ短調、
ヘラー:前奏曲嬰ハ短調 Op.81-10(録音:1925年)
マーガレット・ポーチ 〜
ヘラー:練習曲ハ短調 Op.46-5、
ブリューワー:ロンリー・ストレンジャー(録音:1923年7月&8月)
ヒルダ・ディードリッヒ 〜
モーツァルト:幻想曲ニ短調
K.397(録音:1925年)、
ボロディン:尼僧院にて(録音:1923年7月&8月)
シューマン:満足(録音:1925年)、
スウィンステッド:優雅なワルツ(録音:1925年)
トバイアス・マッセイ 〜
マッセイ:前奏曲、《Six Monothemes》より
第5番、第6番
(録音:1923年4月) |
トバイアス・マッセイ(ピアノ)
アイリーン・シャーラー(ピアノ)
ライエ・ダ・コスタ(ピアノ)
ハリエット・コーエン(ピアノ)、他 |
トバイアス・マッセイ・スクール・シリーズ!完結盤はトバイアス・マッセイとその弟子たち!
19世紀後期〜20世紀前期の英国ピアノ界における名教師、トバイアス・マッセイ(1858−1945)の弟子たちの名演を復刻する「APR」の大好評シリーズ「トバイアス・マッセイ・スクール」。
アイリーン・ジョイス、ハリエット・コーエン、アイリーン・シャーラー、マイラ・ヘス、モーラ・リンパニー、エセル・バートレット&レイ・ロバートソンのデュオと続いてきたシリーズの最終巻は、トバイアス・マッセイの自作自演などの希少音源を集めた「トバイアス・マッセイとその弟子たち」!
AFMCレーベルの音源から復刻となる名教師トバイアス・マッセイのピアニズム、ハリエット・コーエンなどマッセイ門下の名ピアニストたちの貴重な演奏、そして最近発見されたアイリーン・シャーラーの未発売音源などが収録された「トバイアス・マッセイとその弟子たち」は、シリーズ最終巻に相応しい充実の内容。
名エンジニア、マーク・オーバート=ソーンのリマスタリングによる音質向上にも要注目。APRの「トバイアス・マッセイ・スクール」シリーズ、ここに完結! |
 AQUARIUS AQUARIUS
|
|
|
ダヴィド・オイストラフ 初期録音集
J・S・バッハ(1685-1750):ヴァイオリン協奏曲第2番ホ長調
BWV1042
サン=サーンス(1835-1921):序奏とロンド・カプリチョーソ
イ短調 Op.28
ベートーヴェン(1770-1827):ヴァイオリン協奏曲ニ長調
Op.61 |
ダヴィド・オイストラフ(ヴァイオリン)
モスクワ国立フィルハーモニー交響楽団
レフ・シテインベルク(指揮) |
|
録音:1938年
ダヴィド・オイストラフ(1908-1974)が第1回ウジェーヌ・イザイ・コンクール(現エリザベート王妃国際音楽コンクール)で優勝した翌年の録音。
伴奏オーケストラはレフ・シテインベルクが創設したモスクワ国立交響楽団(1943-)やモスクワ・フィルハーモニー管弦楽団(1951-)とは別の団体。
|
| |
|
|
不謹慎ながら、出演者はさすがに豪華
コンスタンチン・イグームノフ追悼演奏会
[第1部]
J・S・バッハ(1685-1750):前奏曲とフーガ
ト短調 BWV578(*)
ラフマニノフ(1873-1943):
ピアノ三重奏曲第2番ニ短調「悲しみの三重奏曲」Op.9
から 第1楽章(+)
リスト(1811-1886):「巡礼の年
第3年」から
エステ荘の糸杉に(#)
ラフマニノフ:前奏曲嬰ト短調
Op.32 No.12(#)/メロディー
ホ長調 Op.3 No.3(#)
[第2部]
ラフマニノフ:
ひそかな夜の静寂の中で
Op.4 No.3(**)
ああ、いやだ、お願い、行かないで
Op.4
No.1(**)
何と苦しいことか Op.21
No.12(**)
チャイコフスキー(1840-1893):
語るな、おお、わが友よ
Op.6 No.2
穏やかな星はぼくらに光を注ぎ
Op.60 No.12
恐ろしいひととき Op.28
No.6
ただ憧れを知る人だけが
Op.6 No.6
セレナード Op.63 No.6 |
|
アレクサンドル・ゲディケ(オルガン(*))
レフ・オボーリン(ピアノ(+))
ダヴィド・オイストラフ(ヴァイオリン(+))
スヴャトスラフ・クヌシェヴィツキー(チェロ(+))
スヴャトスラフ・リヒテル(ピアノ(#))
パーヴェル・リシツィアン(バリトン(**))
ナジェージダ・オブーホヴァ(メゾソプラノ(無印))
マトヴェイ・サハロフ(ピアノ(**/無印))
ヴァレンティーナ・ソロヴィヨヴァ(司会) |
|
録音:1949年4月4日、ライヴ、モスクワ音楽院大ホール、モスクワ、ロシア、ソヴィエト
ロシアのヴィルトゥオーゾ・ピアニストでモスクワ音楽院の名ピアノ教師としても名高いコンスタンチン・イグームノフ(1873-1948)の没翌年に彼を偲んで開かれた演奏会のライヴ録音。レフ・オボーリンはイグームノフ門下生。
|
| |
|
|
ビゼー(1838-1875):オペラ「ジャミレ」(ロシア語訳版)(*)
[ボーナス・トラック]
ビゼー:愛の歌(#)
グノー(1818-1893):メジェ(アラビアの歌)(+)
サン=サーンス(1835-1921):「ペルシャのメロディー」から
孤独な女(+) |
リュドミーラ・レゴスターエヴァ(メゾソプラノ(*/+/#):ジャミレ(*))
アントン・トカチェンコ(テノール:ハルン(*))
ヴラディーミル・ザハロフ(バリトン:スプレンディノ(*))
モスクワ放送合唱団&交響楽団(*)
アレクサンドル・オルロフ(指揮(*))
ゲオルギー・オレントリヘル(ピアノ(+/#)) |
| 録音:1937年(*)/1950年(+)/1953年(#) |
| |

AQVR 372-2
(2CD)
\2500 |
アレクサンドル・セローフ(1820-1871):オペラ「悪魔の力」(1871)から
抜粋 |
アレクセイ・イヴァーノフ(バリトン:ピョートル)
ナターリア・ソコロヴァ(ソプラノ:ダーシャ)
エリザヴェータ・アントノヴァ(アルト:スピリドノヴナ)
ヴェロニカ・ボリセンコ(メゾソプラノ:グルーニャ)
ニコライ・シェゴリコフ(バス:エリョームカ)
アレクサンドル・ホッソン(テノール:ヴァーシャ)
ヴェニアミン・シェフツォフ(テノール:アガフォン)
マリア・クズネツォヴァ(ソプラノ:ステパニーダ)
ボリショイ劇場の歌手たち
ボリショイ劇場合唱団&管弦楽団
キリル・コンドラシン(指揮) |
|
録音:1952年
ルビンシテインら西欧派とバラキレフら国民楽派の両方を痛烈に批判しワーグナーを擁護したロシアの音楽評論家兼作曲家セローフ。
オペラ「悪魔の力」は未完で遺されましたが未亡人らの手により完成され彼の代表作の一つとなりました。
初出音源と表示されています。
ボーナス・トラックとしてコンドラシン指揮による同オペラから3トラック(録音:1947、1948年)とオペラ「ユディト」(1863)から3トラック(録音:1947年)が収録されています。
|
| |
|
|
アレクサンドル・セローフ(1820-1871):オペラ「ログネーダ」(1865)から
抜粋 |
ダニール・デミャーノフ(バリトン:ヴラディーミル)
ソフィア・キセリョヴァ(メゾソプラノ:ログネーダ)
ニーナ・クラーギナ(メゾソプラノ:イジャスラフ)
アントン・トカチェンコ(テノール:ルアリト)
フセーヴォロト・チュチュニク(バス:ドブリーニャ・ニキチッチ)
アレクセイ・コロリョフ(バス:さすらいの老人)
パーヴェル・ポントリャーギン(テノール:スコモロフ)
レヴォン・ハチャトゥロフ(バリトン:司祭)
コンスタンチン・ポリャーエフ(バス:狩人)
モスクワ放送合唱団&管弦楽団
アレクサンドル・オルロフ(指揮) |
| 録音:1945年 |
| |


AQVR 374-2
(2CD)
\2500 →\2290 |
リムスキー=コルサコフ(1844-1908):
オペラ「見えざる都市キテジと聖女フェブローニャの物語」 |
アレクサンドル・ヴェデルニコフ(バス:ユーリー・フセーヴォロドヴィチ公)
ヴラディーミル・イヴァノフスキー(テノール:フセーヴォロド・ユーリエヴィチ公子)
ナターリア・ロジェストヴェンスカヤ(ソプラノ:フェヴローニャ)
ドミートリー・タルホフ(テノール:グリーシュカ・クテリマ)
イリヤ・ボグダーノフ(バリトン:フョードル・ポヤーロク)
リディア・メリニコヴァ(メゾソプラノ:少年)
ボリス・ドブリン(バス:グースリ弾き)
パーヴェル・ポントリャーギン(テノール:熊使い)
レオニード・クチトロフ(バス:ベジャイ)
セルゲイ・クラソフスキー(バス:ブルンダイ)
ニーナ・クラーギナ(メゾソプラノ:アルコノスト)
モスクワ放送合唱団&管弦楽団
サムイル・サモスード(指揮)
|
|
録音:1955年1月19日、ライヴ、モスクワ音楽院大ホール、モスクワ、ロシア、ソヴィエト
初出音源と表示されています。
|
| |
|
|
ヴィターリー・キリチェフスキー オペラ・アリア&歌曲集
チャイコフスキー(1840-1893):
オペラ「チェレヴィチキ」第3幕
から ヴァクーラの歌(*)
オペラ「イオランタ」から
ヴォデモンのロマンス(*)
リムスキー=コルサコフ(1844-1908):
オペラ「五月の夜」第1幕
から レフコの歌(#)
オペラ「五月の夜」第3幕
から レフコの歌(#)
オペラ「皇帝の花嫁」第3幕
から ルイコフのアリア(+)
イッポリトフ=イヴァーノフ(1859-1935):
オペラ「裏切り」から イラークリのアリア(+)
オペラ「ノルランドのオーレ」から
オーレのアリア(+)
プッチーニ(1858-1924):
オペラ「ラ・ボエーム」第1幕
から ロドルフォのアリア「冷たい手を」(*)
ベートーヴェン(1770-1828):遥かなる恋人に(**)
モーツァルト(1756-1791):クローエに(++)
ヴァルラーモフ(1801-1848):ああ、口づけしないで
キュイ(1835-1918):燃やされた手紙/ツァールスコエ・セローの彫像/貴方と君
ダルゴムイシスキー(1813-1869):オペラ「ルサルカ」第3幕
から 王子のアリア
マイアベーア(1791-1864):おいで、美しい漁師の娘よ
ドリーブ(1836-1891):こんにちは、シュゾン
グノー(1818-1893):舟歌
ブラーホフ(1822-1885):いいえ、私はあなたを愛していない
リッカルド・バルテルミ(1869-1937):船乗りの歌 |
ヴィターリー・キリチェフスキー(テノール)
ボリショイ劇場管弦楽団(*/+/#)
ヴァシーリー・ネボリシン(指揮(*/+/#))
ナウム・ヴァリテル(ピアノ(**))
ゲオルギー・オリントリヘル(ピアノ(++))
セミョーン・ストゥチェフスキー(ピアノ(無印))
|
|
録音:1947年(*/**)/1948年(+)/1950年(#/++)
1949年3月22日、ライヴ、モスクワ音楽院小ホール、モスクワ、ロシア、ソヴィエト(無印)
ヴィターリー・キリチェフスキー(1899-1986)はレニングラードのミハイロフスキー劇場およびマリーンスキー劇場、モスクワのボリショイ劇場で活躍したソヴィエト・ロシアのテノール。ロシア作曲家以外の歌曲もロシア語訳で歌われています。
|
| |
|
|
エレーナ・クルグリコヴァ ロシア歌曲集
ロシア伝承曲:
永遠の菩提樹/丸顔の娘/タタールの虜/私は石の上に座り
ヴァーニャはソファーに腰掛けていた/プロチャージナヤ/子守歌
ああ、愛しい人よ
バフメチエフ(1807-1901):指輪
ロシア伝承曲:
言っておくれ、美しい人よ/そうだ、時ごとに
あなたに教えていいかしら、ヴァーニャ/別れ/渡し場のドゥーニャ
ほこりっぽい場所で/叫び/私は庭にいた
チャイコフスキー(1840-1893):子守歌
ヴァルラーモフ(1801-1848):ああ、口づけしないで/私は生きて悲しみ
[ボーナス・トラック]
チャイコフスキー:それが何だと?(*)/なぜ?(*)
リムスキー=コルサコフ(1844-1908):心の優しさの表れで(+) |
エレーナ・クルグリコヴァ(ソプラノ)
ボリス・アブラモヴィチ(ピアノ(無印))
E・スミルノヴァ(ピアノ(*))
アブラム・マカーロフ(ピアノ(+)) |
|
録音:1950年4月2日、ライヴ、科学者の家、モスクワ、ロシア、ソヴィエト(無印)
1953年(*)/1947年(+)
エレーナ・クルグリコヴァ(1907-1982)はボリショイ劇場で活躍したソヴィエト・ロシアのソプラノ。
|
| |


AQVR 377-2
\1700→\1590
|
レオニード・ピアティゴルスキー ロシアの管弦楽作品集
イッポリトフ=イヴァーノフ(1859-1935):
トルコ行進曲 Op.55/組曲第3番「トルコの断章」Op.62
組曲第4番「トルクメニスタンの草原で」Op.65
組曲第5番「ウズベキスタンの音画」Op.69
イリア・サーツ(1875-1912):
メーテルリンクの戯曲「青い鳥」への付随音楽からの組曲(*) |
モスクワ放送合唱団女声パート(*)
リュドミラ・エルマコヴァ(合唱指揮(*))
モスクワ放送交響楽団
レオニード・ピアティゴルスキー(指揮) |
|
録音:1949年(*以外)/1962年(*)
レオニード・ピアティゴルスキー(1900-1973)はウクライナ出身のユダヤ系ソヴィエト・ロシアの指揮者。イッポリトフ=イヴァーノフの管弦楽組曲は第1番「コーカサスの風景」の好評に合わせて連作されましたが、第3〜5番が演奏されることは稀です。
イリア・サーツはタネーエフに師事したウクライナ出身ユダヤ系ロシアの作曲家。初出音源と表示されています。
|
| |


AQVR 378-2
(2CD)
\2500 →\2290 |
スヴェトラーノフ初出音源
ボロディン(1833-1887):オペラ「イーゴリ公」 |
アレクセイ・イヴァーノフ(バリトン:イーゴリ公)
ニーナ・ポクロフスカヤ(ソプラノ:ヤロスラーヴナ)
ヴィターリー・オルレーニン(テノール:ヴラディーミル・イーゴリェヴィチ)
ニコライ・シェゴリコフ(バス:ヴラディーミル・ヤロスラーヴィチ)
アレクセイ・クリフチェニア(バス:コンチャーク)
ヴェロニカ・ボリセンコ(アルト:コンチャーコヴナ)
チホン・チェルニャーコフ(テノール:オヴルール)
セルゲイ・コルティピン(バス:スクラー)
ニコライ・ザハロフ(テノール:イェローシカ)
ラリーサ・ニキーチナ(ソプラノ:ヤロスラーヴナの乳母)
ヴァレンティーナ・クレパツカヤ(ソプラノ:ポロヴェツ人の娘)
ボリショイ劇場合唱団&管弦楽団
エフゲニー・スヴェトラーノフ(指揮) |
|
録音:1958年11月8日、ライヴ、ボリショイ劇場、モスクワ、ソヴィエト
2013年に発売された Russian Disc盤(RDCD 00922-923)のちょうど2ヶ月後に同じボリショイ劇場で録られた音源で、ヤロスラーヴナ以外のキャストは同一。初出音源と表示されています。
|
| |

AQVR 379-2
(2CD)
\2500 |
チャイコフスキー(1840-1893):オペラ「スペードの女王」 |
ディミテル・ウズノフ(テノール:ゲルマン)
ナターリア・ソコロヴァ(ソプラノ:リーザ)
アレクセイ・イヴァーノフ(バリトン:トムスキー伯爵、ズラトゴル)
ピョートル・セリヴァーノフ(バリトン:エレツキー侯爵)
エフゲーニャ・ヴェルビツカヤ(メゾソプラノ:伯爵夫人)
エレーナ・グリボヴァ(メゾソプラノ:ポーリーナ、ミロヴゾル)
ヴェーラ・フィルソヴァ(ソプラノ:プリレーパ)
チホン・チェルニャーコフ(テノール:チェカリンスキー)
フィリップ・フォーキン(バス・スーリン)
イヴァン・イオノフ(テノール:チャプリツキー)
ニコライ・チムチェンコ(バス:ナルーモフ)
エレーナ・コルネーエヴァ(メゾソプラノ:家庭教師)
ナジェジダ・コシツィナ(ソプラノ:マーシャ)
ボリショイ劇場合唱団&管弦楽団
ボリス・ハイキン(指揮)
|
|
録音:1957年1月20日、ライヴ、ボリショイ劇場、モスクワ、ロシア、ソヴィエト
ブルガリアのテノール、ディミテル・ウズノフ(1922-1985)がボリショイ劇場に客演した際のライヴ録音。彼だけブルガリア語で歌っています。初出音源と表示されています。
|
| |

AQVR 380-2
(2CD)
\2500 |
チャイコフスキー(1840-1893):オペラ「エフゲニー・オネーギン」 |
セルゲイ・シャポシンスキー(バリトン:オネーギン)
セルゲイ・レメシェフ(テノール:レンスキー)
オリガ・ゴロヴィナ(メゾソプラノ:ラーリナ)
ヴェーラ・クドリャフツェヴァ(ソプラノ:タチアーナ)
アレクサンドラ・メシチェリャコヴァ(アルト:オリガ)
クセニア・コミッサロヴァ(メゾソプラノ:乳母)
イリヤ・ザハレヴィチ(バス・グリョーミン)
ヴァレーリー・ライコフ(バス:中隊長)
ドミートリー・シリヴェストロフ(バス:ザレツキー)
ヴラディーミル・ヨルチェンコ(テノール:トリケ)
レニングラード・マールイ・オペラ劇場合唱団&管弦楽団
グリゴリー・ドニアフ(指揮) |
|
録音:1954年10月28日、ライヴ、マールイ・オペラ劇場、レニングラード(サンクトペテルブルク)、ロシア、ソヴィエト
初出音源と表示されています。
|
| |
|
|
ヴラディーミル・ブンチコフ オペラ&オペレッタ・アリア&デュエット集
ドニゼッティ(1797-1848):
「ラ・ファヴォリータ」第3幕
から アリフォンゾのアリア(*)
ヴェルディ(1813-1901):「仮面舞踏会」第1幕
から レナートのアリオーソ(*)
ヴェルディ:「仮面舞踏会」第3幕
から レナートのアリア(*)
レオンカヴァッロ(1857-1919):
「道化師」から シルヴィオとネッダのデュエット(O/*)
カールマーン(1882-1953):
「伯爵夫人マリーツァ」第1幕
から タッシロのチャルダーシュ(+)
プランケット(1848-1903):「コルヌヴィルの鐘」第1幕
から 侯爵のアリア
プランケット:「シュルクーフ」
第1幕 から シュルクーフのアリア(#),
第3幕 から イヴォンヌとシュルクーフのデュエット(L/**)
レハール(1870-1948):「メリー・ウィドー」第3幕
から Song of the swing(++)
J・シュトラウスII(1825-1899):
「ジプシー男爵」第1幕 から
バリンカイのクプレ(++)
レハール:「青いマズルカ」第1幕
から アドラールの歌(##)
レハール:「微笑みの国」第2幕
から 殿下のアリア
ジャン・ジルベール(1879-1942):「踊り子カーチャ」から
デュエット(V)
カールマーン:「悪魔の騎手」第1幕
から
シャードルのチャルダーシュ
カールマーン:「サーカスの女王」
第1幕 から フェドーラとミスターXのデュエット(V)
第?幕 から ウィーンの歌 |
ヴラディーミル・ヴンチコフ(バリトン)
オルガ・ピョートロフスカヤ(ソプラノ(O))
リディア・カザンスカヤ(ソプラノ(L))
ヴェーラ・クラソヴィツカヤ(ソプラノ(V))
モスクワ放送交響楽団
オニシム・ブロン(指揮(*))
アレクサンドル・コヴァーレフ(指揮(+))
ゲンナジー・カーツ(指揮(#))
エフゲニー・アクロフ(指揮(**))
アレクサンドル・オルロフ(指揮(++))
グリゴリー・ストリャーロフ(指揮(##))
レオニード・ピアティゴルスキー(指揮(V/無印)) |
|
録音:1946-1948、1950-1953年
ヴラディーミル・ブンチコフ(1902-1995)はスタニスラフスキー&ネミローヴィチ=ダンチェンコ記念音楽劇場やモスクワ放送専属歌手として活躍したソヴィエト・ロシアのバリトン。すべてロシア語訳による歌唱。
|
| |
|
|
ニコライ(1810-1849):オペラ「ウィンザーの陽気な女房たち」から
抜粋 |
ゲオルギー・アブラーモフ(バス:サー・ジョン・ファルスタッフ)
ヴラディーミル・ザハロフ(バリトン:フルート氏)
ゾーヤ・ムラトヴァ(ソプラノ:フルート夫人)
ニコライ・オゼロフ(バス:ライヒ氏)
ニーナ・アレクサンドリースカヤ(メゾソプラノ:ライヒ夫人)
オリガ・アマートヴァ(ソプラノ:ライヒ嬢)
セルゲイ・フォミチョフ(テノール:フェントン)
モスクワ放送合唱団&管弦楽団
アレクサンドル・オルロフ(指揮) |
|
録音:1937年
役名はドイツ語版に拠っていますがロシア語訳での歌唱です。
|
ARCO DIVA
|

UP 0158-2
(2CD + DVD PAL)
\5000 |
ズデニェク・オタヴァ/オペラ・アリア集
[CD 1 & 2]
モーツァルト、ロッシーニ、ドニゼッティ、ヴェルディ、レオンカヴァッロ、
プッチーニ、チャイコフスキー、スメタナ、ドヴォルジャーク、フィビフ、
コヴァロヴィチ、ノヴァーク、クレイチのオペラからのアリア |
ズデニェク・オタヴァ(バリトン)
様々な共演者 |
[DVD]
ズデニェク・オタヴァ−歌手のプロフィール
オーディオ・ボーナス:
スメタナ、ドヴォルジャーク、フェルステル、チャイコフスキー、ヴェルディ、
ビゼーのオペラからのアリア
ドヴォルジャーク、フェルステル、ヴィツパーレク、ノヴォトニーの歌曲 |
ズデニェク・オタヴァ(1902-1980)はチェコのブルノに生まれたバリトン。1929年から1972年まで40年以上プラハ国民劇場に所属し160以上の役を歌った他、声楽教師としても活躍しました。
※PAL方式DVDの再生にはPAL対応プレーヤーが必要です。 |
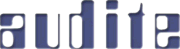 AUDITE AUDITE
|


AU 21427
(5CD)
\7000 →\6290 |
アマデウス四重奏団RIAS レコーディング第3集
モーツァルト:後期弦楽四重奏曲、弦楽五重奏曲集
CD-1
(1)弦楽四重奏曲第14番 ト長調
K.387(27’10”)
(2)弦楽四重奏曲第15番 ニ短調
K.421(24’23”)
(3)弦楽四重奏曲第16番 変ホ長調
K.428(24’00”)
CD-2
(4)弦楽四重奏曲第18番 イ長調
K.464(32’57”)
(5)弦楽四重奏曲第19番 ホ長調
K.465(25’46”)
(6)弦楽四重奏曲第21番 ニ長調
K.575(19’57”)
CD-3
(7)弦楽四重奏曲第22番 変ロ長調
K.589(20’45”)
(8)弦楽四重奏曲第23番 ヘ長調
K.590(22’00”)
(9)クラリネット五重奏曲
イ長調 K.581(28’48”)
CD-4
(10)弦楽五重奏曲第3番 ハ長調
K.515(31’04”)
(11)弦楽五重奏曲第4番 ト短調
K.516(30’37”)
CD-5
(12)弦楽五重奏曲第5番 ニ長調
K.593(23’08”)
(13)弦楽五重奏曲第6番 変ホ長調
K.614(21’46”) |
アマデウス四重奏団
【ノーバート・ブレイニン(第1ヴァイオリン)、
ジークムント・ニッセ(第2ヴァイオリン)、
ピーター・シドロフ(ヴィオラ)、
マーティン・ロヴェット(チェロ)】
(9)ハインリヒ・ゴイザー(クラリネット)、
(10)-(13)セシル・アロノヴィッツ(ヴィオラ) |
アマデウス四重奏団の絶頂時に収録された貴重なRIAS
初出音源、第3 集はモーツァルト!!
録音:1950 年6 月10 日(1)、1951
年4 月23
日(4)(8)、1952 年12 月16 日(9)、1953
年9
月19 日(10)(11)(12)、1953 年12
月2 日(5)(6)(7)、1955
年5 月9 日(2)、1957 年11 月29
日(13) 以上、ジーメンスヴィラ、ベルリン、ランクヴィッツ、1950
年10 月30 日(3)、RIAS フンクハウス、7
スタジオ、ベルリン/モノラル
高音質復刻で評判を呼ぶドイツaudite
レーベルからリリースされているRIAS
音源によるアマデウス四重奏団の初出音源集、注目の第3
弾はモーツァルトです!
当RIAS 音源によるモーツァルトは1950
年代に収録されたもので、1948
年に結成した当団の意欲と新鮮な解釈に満ちておりますが、すでに魅力である優美な演奏は結成初期からのものだということがわかります。
DG 音源が有名なモーツァルトですが、当演奏はまるで絹のような音色、抜群のアンサンブル能力、そして絶妙なニュアンスが表現されております。
演奏の素晴らしさもさることながら、audite
レーベルの見事な復刻にも注目で、モノラルながら非常に鮮明な音質で蘇りました。なお、これらRIAS
盤は録音の際に各楽章編集なしのワンテイクで収録したとのことですので、セッション録音でありながらライヴを思わせる生き生きとした演奏となっております。
第1 弾ベートーヴェン(AU 21424)、第2
弾シューベルト(AU
21428)とあわせてお楽しみください。
アマデウス四重奏団
ノーバート・ブレイニン(第1
ヴァイオリン)、ジークムント・ニッセ(第2
ヴァイオリン)、ピーター・シドロフ(ヴィオラ)、マーティン・ロヴェット(チェロ)の4
人のメンバーはイギリスに亡命していたことにより出会い、1948
年に結成することとなったアマデウス弦楽四重奏団。
音楽はドイツ、オーストリアの作品を得意とし、特にベートーヴェン、モーツァルトの解釈は今でも定評があります。とりわけ第1
ヴァイオリンのノーバート・ブレイニンの音色は非常に優美でアンサンブルに華やかさを添えます。そして、それぞれのパートを際立たせ、まるで交響曲と思わせるスケールの大きな演奏も魅力の弦楽四重奏です。

|
| |


AU 21420
(3CD)
\4500 →\4090 |
ピラール・ローレンガー、RIAS録音集
|
ピラール・ローレンガー(S) |
ベッリーニ:「ノルマ」—清き女神よ
プッチーニ:「トゥーランドット」—ご主人様、お聞きください
アルトゥール・ローター(指)
ベルリン放送交響楽団,RIAS室内合唱団
録音:1959 年3 月2 日、ジーメンス荘
ヘンデル:「エジプトのジューリオ・チェーザレ」—私の運命に涙するでしょう
グラナドス:「ゴイエスカス」—マハと夜鶯
アルトゥール・ローター(指)ベルリン放送交響楽団/
録音:1959 年3 月24日、ジーメンス荘
プッチーニ:「蝶々夫人」—ある日見ることでしょう,「ボエーム」—私はミミと呼ばれています
A.スカルラッティ:すみれ
アルトゥール・ローター(指)ベルリン放送交響楽団/
録音:1960 年2 月16 日、ジーメンス荘
モーツァルト:「魔笛」—私には感じられる,「ドン・ジョヴァンニ」—ひどい人ですって
ヴェルディ:「エルナーニ」—エルナーニ、私を奪い去って
ヴェルディ:「トラヴィアータ」—不思議だわ
フェルディナンド・リヴァ(指)ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
録音:1961 年4 月11 日、ベルリン高等音楽院
ロドリーゴ:4 つの愛のマドリガル
フリート・ヴァルター(指)RIAS管弦楽団/
録音:1961 年11 月1 日、ジーメンス荘
ニン:20 のスペイン民謡—アストゥリアスの女,ムルシアの布
レオス:三連の歌曲(ガルシア・ロルカの詩による)
グリーディ:カスティーリャの6
つの歌—
お前のハシバミの実はほしくない,私にどう思ってほしいの,サン・フアンの朝
グラナドス:昔風のスペインの歌曲集—控えめなマホ,トラララと爪弾き,マハの流し目
トルドラ:6 つの歌—母さん、一対の目が,小唄,君を知ってから
ヘルタ・クルースト(P)/録音:1960
年1
月27 日、RIAS放送局
ヴェルディ:ジプシー女,星に,ストルネッロ,煙突掃除夫,私は平安を失い
ベッリーニ:フィリデの悲しげな姿
モーツァルト:
満足 K.349,おいで、いとしのツィターよ
K.351,子供の遊び K.598,静けさは微笑みながら
K.152
ヘルタ・クルースト(P)/
録音:1962 年12 月28
日、ジーメンス荘
ヘンデル:カンタータ「決して心変わりせず」
HWV140
不詳:三人のムーアの娘たちが
ミラルテ:私の髪の影に
ダサ:アンティオコスは病気だった
ベルムド:ネロはタルペイヤから
ナルヴァエス:何を使って洗いましょう
ヴァスケス:ポプラの林から
ムダラ:ダビデ王は悲しんだ
ルイス・デ・ミラーン:ドゥランダルテ
ピサドール:ドン・サンチョ王よご用心,サン・フアンの朝
ヴァルデラバーノ:ああ、なんてこと
ジークフリート・ベーレント(G)、リヒャルト・クレム(VdG)/
録音:1960 年10 月5 日、RIAS放送局
9 つのスペイン古謡とロマンセ:
ソロンゴ,三枚の葉,チニータスのカフェ,トランプの王様,アンダ・ハレオ,
四人のラバひき,ドン・ボイソのロマンセ,かわいい巡礼たち,ラ・タララ
ジークフリート・ベーレント(G)/
録音:1959 年12 月21 日、RIAS放送局 |
ベルリンで絶大な人気を誇ったスペインのソプラノ、ピラール・ローレンガーの若き日の録音!
177' 17
ピラール・ローレンガー(1929—1996)は、スペイン、アラゴン州サラゴサ生まれのソプラノ。1958
年、ベルリン・ドイツオペラと契約し、1960、1970
年代、この劇場の看板歌手として活躍しました。ことにロリン・マゼール時代(1965—1971)には、ローレンガーとマゼールによるオペラはたいへんな人気を博しました。
ここに収録されているのはローレンガーがベルリンを拠点とした初期の録音です。元々美声のローレンガーですが、30
歳そこそこという若さのローレンガーの声は実に瑞々しく、しかもまだ素朴さを残していて、なんとも言えない魅力があります。
アリアや歌曲の他、お得意のスペイン歌曲を多数収録。後年に録音があるものが大半ですが、ベッリーニ「ノルマ」の“清き女神よ”
のようにこれが唯一の録音と思われるものも含みます。ちなみにこの“清き女神よ”は楽譜にはないハープが活躍する珍しい演奏です。
名匠アルトゥール・ローターや、ドイツの偉大なギタリスト、ジークフリート・ベーレントなどが伴奏を務めているのも注目です。 |
BENO BLACHT SOCIETY
|

SBB 011-13-02
(2CD)
\4200 |
スメタナ(1824-1884):オペラ「ダリボル」(1867)
録音:1946年、チェコスロヴァキア放送スタジオ、プラハ、チェコスロヴァキア |
ベノ・ブラフト(テノール:ダリボル)
ズデンカ・フルンチージョヴァー(ソプラノ:ミラダ)
スタニスラフ・ムシュ(バリトン:ヴラディスラフ)
エドゥアルト・ハケン(バス:ベネシュ)
シュチェパーンカ・イェリーンコヴァー(ソプラノ:イトカ)
オルドジフ・コヴァーシュ(テノール:ヴィーテク)
テオドル・シュルバーシュ(バリトン:ブディボイ)
プラハ国民劇場合唱団&管弦楽団
ヤロスラフ・クロンプホルツ(指揮) |
[ボーナス・トラック]
スメタナ:オペラ「ダリボル」第2幕
から
録音:1952年 |
ベノ・ブラフト(テノール:ヴィーテク)
マリア・タウベロヴァー(ソプラノ:イトカ) |
 BERLIN CLASSICS BERLIN CLASSICS
|

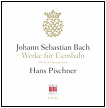
BC0300570
(10CD)
\4500→\4090 |
東ドイツの大偉人 ハンス・ピシュナー
当然共演者もすごい
J.S.バッハ:ハープシコードのための作品集
| CD1 |
2声のインヴェンションと3声のシンフォニア
BWV.772-801 |
録音:1968年 |
| CD2-5 |
平均律クラヴィーア曲集全曲 BWV.846-893 |
録音:1962年、1965年 |
| CD6 |
イタリア協奏曲 BWV.971
半音階的幻想曲とフーガ
BWV.903
フランス風序曲 BWV.831 |
録音:1971年、1972年 |
| CD7 |
ゴルトベルク変奏曲 |
録音:1968年 |
| 2つのヴァイオリンと通奏低音のためのソナタ
BWV.1037 |
ダヴィド・オイストラフ(ヴァイオリン)
イーゴリ・オイストラフ(ヴァイオリン)
録音:1957年(モノラル) |
| CD8 |
チェンバロ協奏曲第1番ニ短調 BWV.1052
チェンバロ協奏曲第5番ヘ短調
BWV.1056
チェンバロ協奏曲第2番ホ長調
BWV.1053 |
ベルリン交響楽団
クルト・ザンデルリング指揮
録音:1963年 |
| CD9 |
2台のチェンバロのための協奏曲第2番ハ長調
BWV.1061
2台のチェンバロのための協奏曲第3番ハ短調
BWV.1062
2台のチェンバロのための協奏曲第1番ハ短調
BWV.1060 |
イゾルデ・アールグリム(チェンバロ)
シュターツカペレ・ドレスデン
クルト・レーデル指揮
録音:1965年 |
| CD10 |
3台のチェンバロのための協奏曲第1番ニ短調
BWV.1063
3台のチェンバロのための協奏曲第3番ハ長調BWV.1064
4台のチェンバロのための協奏曲
BWV.1065 |
イゾルデ・アールグリム(チェンバロ)
ズザナ・ルージイチコヴァ(チェンバロ)
ロベール・ヴェイロン=ラクロワ(チェンバロ)
シュターツカペレ・ドレスデン
クルト・レーデル指揮
録音:1965年 |
| フルートとヴァイオリンとチェンバロのための協奏曲
BWV.1044 |
エルヴィン・ミルツコット(フルート)
マックス・ミハイロフ(ヴァイオリン)
ベルリン室内管弦楽団
ヘルムート・コッホ指揮 |
|
1914年ブレスラウ生まれのハンス・ピシュナー。東ドイツ放送の音楽部長、ドイツ民主共和国の文化大臣を務め、1963年にベルリン国立歌劇場の総監督となったという偉人。
バッハをはじめとするハープシコード奏者としても知られ、厳しくも暖かい演奏で多くの録音が親しまれている。 |
BOMBA
|
BOMBA-PITER(サンクトペテルブルク)とは別のモスクワのレーベル。
2012年にご案内した "Russian
Performing
School" シリーズの発売元です。 |
|
|
偉大なるチェリスト ヤコフ・スロボトキン(1920-2009)
ピアノはフリエール、ギンズブルグ!
ヴェーバー(1786-1826):チェロ・ソナタ
イ長調(*)
メンデルスゾーン(1809-1847):
チェロとピアノのための協奏的変奏曲ニ長調
Op.17(+)
グリーグ(1843-1907):チェロ・ソナタ
イ短調 Op.36(#)
ハイドン(1732-1809):チェロ協奏曲第2番ニ長調
Hob.VII:b(**) |
ヤコフ・スロボトキン(チェロ)
ヤコフ・フリエール(ピアノ(*))
ナウム・ヴァリテル(ピアノ(+))
グリゴリー・ギンズブルク(ピアノ(#))
ソヴィエト国立交響楽団弦楽パート(**)
アレクサンドル・ガウク(指揮(**)) |
|
録音:データ記載なし、モノラル
20世紀後半のソヴィエト・ロシアを代表するチェロ奏者の一人であるヤコフ・スロボトキン(1920-2009)。1932年に音楽天才児のためのプロジェクトで選抜され、1935年に演奏活動を開始。1936年モスクワ音楽院に入学、1941年に卒業しモスクワ・フィルハモニーのソリストとなりました。1943年ドヴォルジャークのチェロ協奏曲のソヴィエト初演を務め、1947年にはフィンランドを訪れ作曲家シベリウスと共演、以後も親交を保ちチェロ曲の献呈も受けました。
いわゆる「西側」ではスロボトキンの名声はあまり知られていませんでしたが、没後の2011年にMelodiyaから彼の協奏作品録音のCDが発売されたことで注目されるところとなり、さらなる音源のCD化が待たれていました。
|
| |


BOMB 033-665
\2300 →\2090
【未案内旧譜】 |
イサーク・シュヴァルツ(1923-2009):
指揮はアルヴィド・ヤンソンス、エミン・ハチャトゥリアン
交響曲ヘ短調(*)
映画音楽「カラマーゾフの兄弟」からの組曲(+)
3つの正教会聖歌(#) |
レニングラード・フィルハーモニー管弦楽団(*)
アルヴィド・ヤンソンス(指揮(*))
ソヴィエト国立映画交響楽団(+)
エミン・ハチャトゥリアン(指揮(+))
聖ダニロフ修道院男声合唱団(#) |
|
録音:1958年(*)/1968年(+/#) 発売:2010年
イサーク・シュヴァルツはウクライナに生まれ、ショスタコーヴィチの支援を得てレニングラード音楽院で学んだ作曲家。100本を超える映画音楽や管弦楽曲、合唱曲等を書きました。
|
 BONGIOVANNI BONGIOVANNI
|
|
|
ヴィルジニア・ゼアーニ ライヴ録音集 第4集
ヴェルディ:「シチリアの晩鐘」,「オテッロ」
プッチーニ:
「ボエーム」,「トスカ」,「蝶々夫人」,
「ジャンニ・スキッキ」,「
つばめ」,「トゥーランドット」
チャイコフスキー:「エフゲニ・オネーギン」(イタリア語)
マスネ:「ウェルテル」(イタリア語)
からのアリア、場面 |
ヴィルジニア・ゼアーニ(S) |
録音:1962-1975 年/DDD、78' 55
第1 集(GB 1060)、第2 集(GB
1112)、第3
集(GB 1172)に続くヴィルジニア・ゼアーニのライヴ録音集の第4
集。ゼアーニは1925 年、ルーマニアのソロバストルの生まれ。1947
年にイタリアに移り、1950 年代から1970
年代まで、幅広く活躍しました。また夫でバスのニコラ・ロッシ=レメーニとのおしどり夫妻っぷりも話題でした。ジャケット写真でも分る通り、彼女はたいそうなルーマニア美人でもあります。
この第4 集はプッチーニを中心に、チャイコフスキー:エフゲニ・オネーギン」からタチアーナの手紙の場面や、マスネの「ウェルテル」など、ゼアーニの卓越した劇的表現力を楽しめます。
なお録音状態はあまりよくありませんので、ご承知おきくださいますようお願いいたします。
史上最高の美女ゼアーニ
これまでアンナ・モッフォ、ライナ・カバイヴァンスカ、ヒルデ・ギューデン、アンジェラ・ゲオルギュウ、リーザ・デラ・カーザ、アンナ・ネトレプコ・・・、と絶世の美人歌手を多く見てきたが、このゼアーニを超える美貌の人には出会えない。歌手を容貌で語るな、とどんなにきつくお叱りを受けても、もうこればっかりは仕方がない。このゼアーニの録音ならなんでも集めてしまう。
|
|
|
| |
|
|
ペドロ・ラヴィルヘン/ライヴ録音集
ヴェルディ:
「トロヴァトーレ」,「仮面舞踏会」,「シチリアの晩鐘」,
「運命の力」,「アイーダ」,「オテッロ」
プッチーニ:「トスカ」,「外套」,「トゥーランドット」
ビゼー:「カルメン」
レオンカヴァッロ:「道化師」
ジョルダーノ:「アンドレア・シェニエ」からのアリア、場面
ララ:グラナダ
フレイレ:アイ、アイ、アイ! |
ペドロ・ラヴィルヘン(T) |
テノール・マニアなら聞き逃すことなかれ!知る人ぞ知るスペインの名テノール、ラヴィルヘン!貴重なライヴ録音がどっさり!!
録音:1968-1979 年/78' 18
ペドロ・ラヴィルヘンは、1930
年、スペインのコルドバ近郊のブハランセに生まれたテノール。アルフレード・クラウス(1927
年生まれ)とほぼ同世代。
たいへん輝かしく立派な声の持ち主で、情熱的な歌い口と相まってヴェルディのヒロイックな役では素晴らしい歌を聞かせてくれます。1970
年代前後に活躍した多数の優れたテノールの中にあってもラヴィルヘンは間違いなくトップクラスの実力を誇る歌手ですが、片脚に障害があり活動が制限されたため実力に比してあまりにも低い知名度しか得られませんでした。ちなみにラヴィルヘンは1973
年に藤原歌劇団公演の「カルメン」でホセを歌って大成功を収め、年配のオペラファンの間では伝説的人物です。録音も極めて少ないので、ここでのライヴ録音は、音質こそあまりよくないものの、いずれも貴重です。 |
 チェコ放送ラジオサービス チェコ放送ラジオサービス
|
|
|
リヒャルト・シュトラウス(1864-1959):
ヴァイオリン・ソナタ変ホ長調
Op.18(*)
ハンス・プフィツナー(1869-1949):
ヴァイオリン・ソナタ ホ短調
Op.27(+) |
ルボミール・チェルマーク(ヴァイオリン)
ヤロスラフ・スミーカル(ピアノ) |
|
録音:1985年(*)、1994年(+) ライセンサー:チェコ放送ブルノ支局
ルボミール・チェルマークは1945年チェコのブルノに生まれ、ブルノ音楽院、ヤナーチェク音楽アカデミーで学んだヴァイオリン奏者。1969年にブルノ弦楽四重奏団を創設し、同年より1977年までブルノ国立フィルハーモニー管弦楽団コンサートマスターを務めました。
1990年(?)以来2014年現在マルチヌー室内管弦楽団のソリスト兼芸術監督を務めています。
|
| |
|
|
ダニエラ・ショウノヴァー=ブロウコヴァー/声楽リサイタル
ヴィーチェスラフ・ノヴァーク(1870-1949):
連作歌曲「愛についての憂鬱な歌」Op.38(PR/JH)
モーツァルト(1756-1791):オペラ「コシ・ファン・トゥッテ」K.588
第2幕 から
フィオルディリージのアリア(MP/PC)
ヤン・ヤクプ・リバ(1765-1815):眠れ、幼き御子よ(PR/SB)
スメタナ(1824-1884):
オペラ「くちづけ」第1幕
から ヴェンドゥルカの子守歌(ST/FV)
オペラ「売られた花嫁」第2幕
から マジェンカのアリア(NT/PV)
ポンキエッリ(1834-1886):
オペラ「ラ・ジョコンダ」第2幕
から ラウラのアリア(*/NT/JC)
ヴェルディ(1813-1901):
オペラ「ドン・カルロ」第1幕
から エリザベッタのアリア(PR/JS)
ドヴォルジャーク(1841-1904):
オラトリオ「聖ルドミラ」Op.71
から ルドミラのアリア(2曲)(+/PR/AB)
劇的カンタータ「幽霊の花嫁」Op.69
から
少女のアリア「神の悲嘆」(PR/FV)
ヴェルディ:レクイエム から
リベラ・メ(一部)(#/PR/FV)
ドヴォルジャーク:劇的カンタータ「幽霊の花嫁」Op.69
から
少女のアリア「聖母マリア様に」(PR/FV) |
ダニエラ・ショウノヴァー=ブロウコヴァー(ソプラノ)
ドラホミーラ・ドロプコヴァー(アルト(*))
レオ・マリアン・ヴォディチカ(テノール(+))
プラハ放送合唱団(#)
プラハ放送交響楽団(PR)
ムジチ・デ・プラーガ(MP)
プラハ・スメタナ劇場管弦楽団(ST)
プラハ国民劇場国民劇場管弦楽団(NT)
ヨセフ・フルンチーシュ(指揮(JH)
ピエール・コロンボ(指揮(PC))
スタニスラフ・ボグニア(指揮(SB))
フランチシェク・ヴァイナル(指揮(FV))
ペトリ・ヴロンスキー(指揮(PV))
ヨセフ・ハロウプカ(指揮(JC))
ヤン・シュティフ(指揮(JS))
アントニオ・デ・バヴィエル(指揮(AB)) |
|
録音:1976-1990年
ダニエラ・ショウノヴァー=ブロウコヴァーは1943年チェコのプラハに生まれ、1970年から2003年までプラハ国民劇場に所属して活躍したソプラノ。
|
| |
|
|
ヴィレーム・プシビル/チェコ・オペラ・リサイタル
スメタナ(1824-1884):「ダリボル」、「二人のやもめ」、「売られた花嫁」、「口づけ」、
ドヴォルジャーク(1841-1904):「ドミトリー」、「ルサルカ」、
フィビフ(1850-1900):「シャールカ」から |
ヴィレーム・プシビル(テノール)
ヤルミラ・クラートカー、
インドラ・ポコルナー、
キタ・アブラハーモヴァー(ソプラノ)
ルドルフ・アスムス(バスバリトン)
ヨセフ・クラーン(バス)
ブルノ国立オペラ合唱団&管弦楽団
フランチシェク・イーレク、
ヴァーツラフ・ノセク、ヤン・シュティフ(指揮) |
| 録音:1968、1971、1972、1973、1981、1982年、チェコ放送ブルノ支局スタジオ、ブルノ、チェコ |
| |

CR 0686-2
(2CD)
\3600 |
ヨハン・シュトラウスII(1825-1899):オペレッタ「ジプシー男爵」(チェコ語訳版)
録音:1953年 |
ラディスラフ・ムラース(バスバリトン:カールマーン・ジュパーン)
マグダ・シュパコヴァー(ソプラノ:アルセナ)
オルドジフ・コヴァーシュ(テノール:シャーンドル・バーリンカイ)
ヤロスラヴァ・プロハースコヴァー(ソプラノ:サッフィ)
ルドミラ・ハンザリーコヴァー(アルト:ツィプラ)
フランチシェク・ヴォボルスキー(テノール:ホモナイ伯爵)
ボジェク・ルヤン(バリトン:カルネロ伯爵)
チェコスロヴァキア放送プラハ合唱団
イジー・ピンカス(合唱指揮)
プラハ放送管弦楽団
ヴラチスラフ・アントニーン・ヴィプレル(指揮) |
[ボーナス・トラック]
ヨハン・シュトラウスII:オペレッタ「ジプシー男爵」(チェコ語訳版、抜粋)
録音:1962年 |
ベノ・ブラフト(テノール:シャーンドル・バーリンカイ)
イヴァナ・ヴクソヴァー(アルト:ツィプラ)
ミラン・カルピーシェク(テノール:ホモナイ伯爵)
ミラダ・シュブルトヴァー(ソプラノ:サッフィ)
アントニーン・ヴォタヴァ(バリトン:カルネロ伯爵)
ヴラディミール・イェデナーツティーク(バス:カールマーン・ジュパーン)
チェコスロヴァキア放送プラハ合唱団
プラハ放送管弦楽団
ヴラスチスラフ・アントニーン・ヴィプレル(指揮) |
 CRYSTAL CLASSICS(Blu-rayオーディオ) CRYSTAL CLASSICS(Blu-rayオーディオ)
|
Crystal Classics Blu-ray Auido本格始動!
|


N 80006
(2Blu-ray Audio/
特別価格)
\7000 →\6290 |
ケーゲル/
ベートーヴェン:交響曲全集
交響曲第1番ハ長調Op.21/
交響曲第3番変ホ長調Op.55《英雄》/
交響曲第2番ニ長調Op.36/交響曲第4番変ロ長調Op.60/
交響曲第6番ヘ長調Op.68《田園》/
交響曲第5番ハ短調Op.67《運命》/
交響曲第8番ヘ長調Op.93/交響曲第7番イ長調Op.92/
交響曲第9番ニ短調Op.125《合唱付き》 |
ヘルベルト・ケーゲル(指揮)
ドレスデン・フィルハーモニー管弦楽団
アリソン・ハーガン(ソプラノ)
ウテ・ヴァルター(コントラルト)
エバーハルト・ビュヒナー(テノール)
コロシュ・カヴァトシュ(バス)
ベルリン放送合唱団
ライプツィヒ放送合唱団 |
その前にCDで出してくれ!(店主)
ケーゲルのベートーヴェン全集ついにBlu-ray
Audioで登場!次世代高音質フォーマットDTS
HD 24bit/96kHz で、伝説のベートーヴェンが蘇る!
強烈な個性と繊細な音作りで驚異的な人気・カリスマを誇ったドイツの指揮者、ヘルベルト・ケーゲル。ケーゲルの遺した膨大な録音の中でも、特に代表盤として君臨するのが、首席指揮者としてドレスデン・フィルを振った1982年〜83年録音のベートーヴェン。CDとしても発売された交響曲全集だが、特に注目を浴びたのが、デジタル・リマスタリングを施し、サラウンド化されたSACDによる全集であり、ケーゲルの真骨頂である細部の表情の変化までがくっきりと刻印された録音として長く評価されていたが、現在は廃盤となってしまっている。
そんな伝説的録音が、ついに次世代の超高音質フォーマット、Blu-ray
Audio(Pure Audio Blu-ray)で登場。音声フォーマットは、5.1chとSACD盤と同じ4.0chの2種類のサラウンド(ともにDTS
HD)と、ステレオ(PCM)の3種類を収録。かつてのSACD盤を上回るウルトラ・ハイ・クオリティ・サウンドで、伝説のベートーヴェンが蘇る。
録音:1982年−1983年
5.1 DTS HD Master Audio 24bit/96kHz/4.0
DTS HD Master Audio 24bit/96kHz/2.0
PCM
24bit/96kHz
※Blu-ray Audio Discは、Blu-ray対応機器でのみ再生可能です。
※当タイトルは音声のみの収録となっており、映像は収録されておりません。予めご了承下さい。 |
| |

N 80008
(Blu-ray Audio)
\4500 |
J.S.バッハ:クリスマス・オラトリオ BWV.248 |
ルート・ツィーザク(ソプラノ)
モニカ・グループ(アルト)
クリストフ・プレガルディエン(テノール)
クラウス・メルテンス(バス)
ラルフ・オットー(指揮)
フランクフルト・ヴォーカル・アンサンブル
コンチェルト・ケルン |
ドイツの名合唱指揮者、ラルフ・オットーと自身が創設した合唱団、フランクフルト・ヴォーカル・アンサンブルによる大バッハのクリスマス・オラトリオ。ドイツの荘厳な響きを新時代の超高音質ディスクで浮き彫りにする。
録音:1991年1月9日−16日、フランクフルト
5.0 DTS HD Master Audio 24bit/96kHz/2.0
PCM 24bit/96kHz
※Blu-ray Audio Discは、Blu-ray対応機器でのみ再生可能です。
※当タイトルは音声のみの収録となっており、映像は収録されておりません。予めご了承下さい。 |
| |

N 80007
(Blu-ray Audio)
\4500 |
J.S.バッハ:ブランデンブルク協奏曲 BWV.1046〜1051(全曲) |
ヘルムート・ヴィンシャーマン(指揮)
ドイツ・バッハゾリステン |
ドイツの名指揮者ヘルムート・ヴィンシャーマンは、お得意のバッハから、ブランデンブルク協奏曲の全曲録音がBlu-ray
Audioで登場。2010年にも来日公演を果たし、90歳ながら素晴らしいバッハを聞かせてくれたヴィンシャーマンは、宮本文昭なども師事した名オーボイストでもあり、このブランデンブルク協奏曲でも管楽器のコントロールは見事なもの。
5.1 DTS HD Master Audio 24bit/96kHz/2.0
PCM 24bit/96kHz
※Blu-ray Audio Discは、Blu-ray対応機器でのみ再生可能です。
※当タイトルは音声のみの収録となっており、映像は収録されておりません。予めご了承下さい。 |
| |

N 80004
(Blu-ray Audio)
\4500 |
モーツァルト:ピアノ協奏曲集
ピアノ協奏曲第9番変ホ長調 《ジュノム》
K.271
ピアノ協奏曲第12番イ長調 K.414
ピアノ協奏曲第13番ハ長調 K.
415
ピアノ協奏曲第18番変ロ長調
K.456
ピアノ協奏曲第21番ハ長調 K.467
ピアノ協奏曲第23番イ長調 K.488
|
リンダ・ニコルソン(フォルテピアノ)
ニコラス・クレーマー(指揮)
カペラ・コロニエンシス |
フォルテピアノの第一人者リンダ・ニコルソンは、ヒロ・クロサキと共演した「モーツァルト:ヴァイオリン・ソナタ全集」がレコード・アカデミー賞を受賞し、日本でも馴染み深い存在となった鍵盤楽器奏者。1954年にドイツのケルンで結成されたピリオド・オーケストラ、カペラ・コロニエンシスとのコンビによるピリオド楽器でのモーツァルト。ニコルソンのフォルテピアノから生まれる軽やかな響きで聴くモーツァルトが、ピュア・オーディオで味わえる。
録音:1989年、1990年
5.0 DTS HD Master Audio 24bit/96kHz/2.0
PCM 24bit/96kHz
※Blu-ray Audio Discは、Blu-ray対応機器でのみ再生可能です。
※当タイトルは音声のみの収録となっており、映像は収録されておりません。予めご了承下さい。 |
| |

N 80005
(Blu-ray Audio)
\4500 |
フンパーディンク:歌劇 《王子と王女》 |
クラウス・フローリアン・フォークト(テノール)
ユリアーネ・バンゼ(ソプラノ)
クリスティアン・ゲルハーヘル(バリトン)、他
インゴ・メッツマッハー(指揮)
ベルリン・ドイツ交響楽団
ベルリン放送合唱団
ベルリン少女合唱団
|
ワーグナーと深い親交をもち、「ヘンゼルとグレーテル」で知られるドイツの作曲家、エンゲルベルト・フンパーディンク(1854−1921)。1897年のメロドラマを題材とし1910年に作曲された「王子と王女」。メッツマッハー&ベルリン・ドイツ響に、フローリアン・フォークトやバンゼ、ルハーヘルなど世界屈指の名歌手たちが参加した録音もBlu-ray
Auidoで登場。
録音:2008年12月15日&17日
5.1 DTS HD Master Audio 24bit/96kHz/2.0
PCM 24bit/96kHz
※Blu-ray Audio Discは、Blu-ray対応機器でのみ再生可能です。
※当タイトルは音声のみの収録となっており、映像は収録されておりません。予めご了承下さい。 |
| |

N 80003
(Blu-ray Audio)
\4500 |
ガーシュウィン作品集
ガーシュウィン:
ピアノ協奏曲ヘ長調*†
パリのアメリカ人†
キューバ序曲‡
《アイ・ガット・リズム》
による変奏曲+‡
《ポーギーとベス》 より メロディー†
ラプソディ・イン・ブルー*† |
セシル・ウーセ(ピアノ)*
ネヴィル・マリナー(指揮)†
シュトゥットガルト放送交響楽団†
アラン・マークス(ピアノ)+
ハンス=ディーター・バウム(指揮)‡
ベルリン放送交響楽団‡ |
フランスのセシル・ウーセ、アメリカのアラン・マークスがソリストとしてドイツの2つのオーケストラと共演。フランスやドイツのテイストが加わったガーシュウィンもまた面白い。マリナーのタクトも見事に、「パリのアメリカ人」や「キューバ序曲」などのオーケストラ作品もしっかりと収録した、ガーシュウィン作品集です!
録音:1991年11月、シュトゥットガルト†/1992年、ベルリン‡
5.1 DTS HD Master Audio 24bit/96kHz/2.0
PCM 24bit/96kHz
※Blu-ray Audio Discは、Blu-ray対応機器でのみ再生可能です。
※当タイトルは音声のみの収録となっており、映像は収録されておりません。予めご了承下さい。 |
| |

N 80002
(Blu-ray Audio)
\4500 |
ウィーン宮廷礼拝堂の音楽
アイブラー:シバの人々は来る、奉献唱
モーツァルト:
アヴェ・ヴェルム・コルプスKV618、われら御身の保護のもとに
サリエリ:聖霊よ来り給え、深い淵からの叫び
M.ハイドン:ハレルヤ、復活の日
ヘルベック:子らよ、共に歌え
フックス:しもべたちよ、主を褒め称えよ
フンメル:グラドゥアーレ「Quod
quod in
orbe」Op.88
ラントハルティンガー:手に向かいて歌え
シューベルト:
マニフィカトD.486、サルヴェ・レジナ
ヘ長調Op.47
D223、
いま天にいます者をあがめD488、心に悲しみを抱きてOp.46
D136
ブルックナー:ミサ曲第1番ニ短調 |
レンネケ・ルッテン&
アニカ・ソフィー・リトレウスキ(ソプラノ)
ウタ・クリスティーナ・ゲオルク(メゾ・ソプラノ)
フランツィスカ・ラブル(アルト)
ダニエル・ベーレ&
ドミニク・ヴォルティグ(テノール)
ヨハネス・マルティン・クレンツル&
カイ・シュティーフェルマン(バリトン)
WDR放送合唱団、ケルンWDR放送管弦楽団、
ヘルムート・フローシャウアー(指揮) |
神聖ローマ皇帝マクシミリアン1世の在位中、1498年に設立されたウィーン宮廷礼拝堂のための音楽集。
モーツァルトやサリエリ、ミヒャエル・ハイドンたちが捧げた数々の音楽がウィーン宮廷の偉大なる存在感を示す。
録音:2006年12月7日−14日&2010年12月6日−11日、ケルン
5.1 DTS HD Master Audio 24bit/96kHz/2.0
PCM 24bit/96kHz
※Blu-ray Audio Discは、Blu-ray対応機器でのみ再生可能です。
※当タイトルは音声のみの収録となっており、映像は収録されておりません。予めご了承下さい。 |
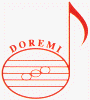 DOREMI DOREMI
|
|
|
マルタ・アルゲリッチ Vol.2 |
(1)リスト:練習曲ヘ短調「軽やかさ」
[1957年8月ブゾーニ国際コンクール・ライヴ]
(2)プロコフィエフ:ピアノ・ソナタ第3番イ短調Op.28
[1960年3月16日NDR ハンブルク(放送用セッション)]
(3)同:ピアノ・ソナタ第7番変ロ長調Op.83
[1960年3 月16 日NDRハンブルク(放送用セッション)]
(4)同:トッカータOp.11 [1960年3月16日NDRハンブルク(放送用セッション)]
(5)ラヴェル:夜のガスパール
[1960年3月16日NDRハンブルク(放送用セッション)]
(6)同:ソナチネ [1960年9月8日WDRケルン(放送用セッション)] |
マルタ・アルゲリッチ(Pf) |
この指さばきと集中力はまさに神。アルゲリッチ19歳の貴重な放送用セッション、初めて日の目を見る
MONO
ファンを狂喜させたDoremi のアルゲリッチ・シリーズ、第2
弾の登場です。今回は彼女が1960
年3 月16 日にハンブルクのNDR
で放送用に行ったセッション録音で、初CD
化。さらに同年9
月8 日にケルンのWDR で行った放送用セッション録音も含まれているのが嬉しい限り。いずれも初出音源。
プロコフィエフとラヴェルは難曲として名高いですが、当時19
歳だったアルゲリッチの若さと才気ほとばしる演奏で完全に征服、ゾクゾクさせられる凄さ。技巧の冴えはもちろんながら、しっとりと潤いのある美音、圧倒的な集中力がまさに神業、アルゲリッチにしかできぬ至芸です。
プロコフィエフの名作「ピアノ・ソナタ第7
番」も初めて聴くような新鮮さに満ちています。また「ピアノ・ソナタ第3
番」はアルゲリッチとしては他に録音のないレパートリーのため超貴重。これも予想以上のすさまじさ。
ラヴェルも驚くべき名演。リズム感の良さ、輝く音色で釘づけにさせられます。ことに「夜のガスパール」のすさまじさは驚異的で、19
歳の少女の芸とは信じ難い成熟度。ますますアルゲリッチに魅かれてしまう、必携の一枚と申せましょう。
第1弾 |
|
|
アルゲリッチのデビューの年のモーツァルト!
マルタ・アルゲリッチVol.1
モーツァルト:
(1)ピアノ協奏曲第21番ハ長調K467
(2)ピアノ・ソナタ第8番イ短調K310
(3)ピアノ・ソナタ第13番変ロ長調K333
(4)ピアノ・ソナタ第17番ニ長調K576 |
マルタ・アルゲリッチ(P)
(1)ペーター・マーグ(指)
ケルン放送交響楽団 |
アルゲリッチのデビューの年に収録されたモーツァルト、珍しいピアノ・ソナタも収録
録音:(1)1960 年9 月5
日、ケルン (2)(3)1960
年4 月26 日、ミュンヘン (4)1960
年7 月23
日、ケルン
歴史的に偉大な演奏家の貴重な録音をリリースしているカナダのDOREMI
レーベルが、「生ける伝説」現代最高のピアニスト、マルタ・アルゲリッチのシリーズをスタートさせました。
第1弾は1960年にケルンとミュンヘンの放送局スタジオで録音された音源。どの曲も正規盤ではリリースはなく、貴重な音源です。1960年といえばドイツ・グラモフォンからデビューレコードをリリースした年。アルゲリッチ19
歳、ショパン・コンクールで優勝する前の演奏で、若いアルゲリッチの瑞々しい感覚が発揮され、輝く才能に溢れた生き生きとした演奏を聴かせてくれます。
モーツァルトのピアノ協奏曲第21
番。前作20
番とは対極的で、調性もハ長調という明るく伸びやかな歌心溢れた作品。美しい旋律で有名な第2
楽章では、アルゲリッチの感性に訴えかけてくる演奏に心を動かされます。
またアルゲリッチのモーツァルトのピアノ・ソナタは、2
台ピアノや4 手のためのソナタの録音はありますが、通常のピアノ・ソナタの録音は正規盤ではありませんでしたし、アルゲリッチはモーツァルトの録音自体多くありません。それは師であったグルダが最も得意としていた作曲家でもあり、アルゲリッチは以前「彼の演奏がある限り私は弾かない」と語ったほど。ここに収録されている3
曲のソナタは、モーツァルトの純粋な音楽世界を、アルゲリッチのインスピレーションが赴くまま自由奔放な演奏で聴くことができます。 |
|
 FRA BERNARDO FRA BERNARDO
|


fb 1312522
(2CD)
\3600 →\3290 |
クレメンス・クラウス&ウィーン・フィル
ハイドン:オラトリオ《天地創造》 |
クレメンス・クラウス(指揮)
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
ウィーン国立歌劇場合唱団
トルーデ・アイッパーレ(ソプラノ)
ユリウス・パツァーク(テノール)
ゲオルク・ハン(バス・バリトン) |
1943年3月28日にウィーンで収録されたハイドンの「天地創造」の放送用録音、クレメンス・クラウスとウィーン・フィルの名演が「フラ・ベルナルド(fb/fra
bernardo)」レーベルから登場。
クラウス&ウィーン・フィルはもちろんのこと、アイッパーレ、パツァーク、ハンといった名歌手たちの共演による「天地創造」は、名演の誉れが高い。音質面にも要注目。 |
GRAND SLAM
|
|
|
怪物クナの面目躍如、メロディアLP 復刻登場!
(1)ブラームス:交響曲 第3番
ヘ長調 Op.90
ワーグナー:
(2)歌劇「タンホイザー」より序曲とヴェヌスベルクの音楽
(3)歌劇「さまよえるオランダ人」序曲
ボーナス・トラック:
(4)ワーグナー:楽劇「パルジファル」第1幕前奏曲よりリハーサル風景 |
ハンス・クナッパーツブッシュ(指揮)
(1)ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
(2)(3)ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
(4)ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団 |
怪物クナの面目躍如、ブラームス第3、メロディアLP
復刻登場!貴重なリハーサル付き!
録音:(1)1944 年9 月9 日、バーデン・バーデン
(放送録音) (2)(3)1953 年5
月6、7 日、ウィーン、ムジークフェラインザール(セッション録音) (4)1962
年11 月、ミュンヘン、バヴァリア・スタジオ(放送録音)/モノラル
使用音源:① Melodiya D-06429/30 ②③
London(U.S.A.) LL 800 ④ Private
archive
■制作者より
クナッパーツブッシュが指揮したブラームスの交響曲第3
番は今や複数の音源が知られていますが、その中でも戦時中の放送録音(ベルリン・フィル、1944
年)は最高と評価されているものです。今回はその演奏の初出LP(メロディア)から復刻、怪物クナの真骨頂を堪能出来ます。余白には当シリーズ未復刻のワーグナーの序曲2
曲のほか、ボーナス・トラックには貴重なリハーサルが付きます(邦訳付き)。リハーサルではクナの貫禄のある声がファンにはたまりませんが、あることに対して文句を言っているのも、いかにもクナらしいです。(平林直哉) |
| |
|
|
ブルックナー:交響曲第5番 変ロ長調(改訂版) |
ハンス・クナッパーツブッシュ(指揮)
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 |
クナッパーツブッシュ&VPO のブルックナー第5!2トラック・38センチのテープより復刻! 仰天の音質!
録音:1956 年6 月3-6 日、ウィーン、ゾフィエンザール/使用音源:
Private archive (オープンリール・テープ、2トラック、38
センチ)/ステレオ
■制作者より
クナッパーツブッシュ&ウィーン・フィルのステレオによるブルックナーの交響曲第5
番は、当シリーズでも一度復刻しています(GS
2047 / 2010 年、4 トラック・19
センチのテープを使用(現在廃盤))。今回は2
トラック、38 センチのオープンリール・テープを素材としていますが、驚くべきはその音質です。澄み切った空気感、瑞々しい音色、絹の肌触りのような柔らかさは腰を抜かすほどで、ウィーン・フィルの蜜のしたたるような美音がいやというほど味わえます。この演奏は言うまでもなく評判の悪い改訂版を使用したものですが、その欠点を全く忘れさせてくれます。ワルター指揮、コロンビア響のマーラーの「巨人」(GS
2105)では「レーベル設立以来の最高音質か?」と思っていましたが、今回のブルックナーはそれ以上かもしれません。制作者自身も、音のチェックをしながら、その艶やかな音に酔いしれていました。(平林 直哉) |
| |
|
|
記念すべき世界初出LP より復刻!
ブルックナー:交響曲第8番 ハ短調(ハース版) |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(指揮)
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 |
フルトヴェングラーのブルックナー交響曲第8番(VPO、1944)
録音:1944 年10 月17 日、ウィーン、ムジークフェラインザール/モノラル
使用音源: Unicorn (U.K.) UNIC-109/10/放送用録音/マグネトフォン・コンサート)
■制作者より
拙著『フルトヴェングラーを追って』(青弓社)でも触れている通り、1968
年にイギリス・ユニコーン・レーベルが設立された際、フルトヴェングラー夫人からユニコーンの関係者に2
つのテープが手渡されました。それらは、ブルックナーの交響曲第8
番とベートーヴェンの同第3 番「英雄」(ともに1944
年、ウィーン・フィル)で、これをもとにのちにLP
が作成されました。
「英雄」は1953 年に発売されたウラニア盤と同一演奏ですが、ブルックナーの方はこのユニコーン盤が世界初発売です。その記念すべきLP
の中でも最初期にプレスされ、最も音質が安定していると言われるもの(深緑色のレーベル)を復刻の素材としました。
解説書には1947 年にウィーンの文筆家F.
ヴィルトガンスによって書かれた「フルトヴェングラーおよびその他の人々」の邦訳を掲載しています。第二次大戦後、フルトヴェングラーをはじめ、ナチスとの関係を取りざたされた音楽家は裁判にかけられました。その後、彼らの多くは1947
年前後に無罪が確定し、間もなくウィーンの楽壇にも復帰を果たします。ところが、ヴィルトガンスの論評によると、当時のウィーンにはこうした復帰を必ずしも歓迎しない意見も根強かったと伝えています。戦後の余韻が色濃く残っていた頃の、貴重な文献のひとつと言えるでしょう。
なお、本演奏では第3 楽章の一部にカットはあるものの、全曲にわたって「ハース版」に準拠していますので、他の多くのディスクと同じく「ハース版」と表記しています。(平林 直哉) |
 GUILD HISTORICAL GUILD HISTORICAL
|
|
|
マルコム・サージェント 〜
シベリウス・レコーディングス
1956〜1958
シベリウス:交響曲第1番ホ短調
Op.39*
交響幻想曲《ポホヨラの娘》Op.49
交響曲第5番変ホ長調 Op.83 |
マルコム・サージェント(指揮)
BBC交響楽団 |
英国の名指揮者マルコム・サージェントのシベリウス!
ジョン・バルビローリ、トーマス・ビーチャム、エイドリアン・ボールトらと並び、戦後の英国指揮者界を代表する4人の名指揮者うちの1人、サー・マルコム・ジャージェントのシベリウス録音が、Guild
Historicalから登場!
ボールトから首席指揮者の任を引き継いだ1950年代の、交響曲第1番と交響曲第5番。BBCプロムスの名物指揮者として人気を誇ったサージェントの、名録音の1つが、レイノルズ・マスタリングでよみがえる!
※リマスター:ピーター・レイノルズ&レイノルズ・マスタリング/マスター・ソース:シャールヴェヒター・コレクション/
録音:1956年8月27日キングスウェイ・ホール(モノラル)*/1958年8月25日−26日、キングスウェイ・ホール(ステレオ) |
GUILD LIGHT MUSIC
|
|
|
軽音楽の黄金時代 〜
バイ・スペシャル・リクエスト:フェイス&ファーノン
スタイン:ライド・スルー・ザ・ナイト/
フェイス:ケアフリー/伝承曲:ツバメ/
ララ:グラナダ/マルチェッティ:ファッシネイション/
ロジャーズ:もうすぐ17歳/
バーリン:ザ・ガール・オン・ザ・ポリス・ガゼット/
ファーノン:セヴンス・ヘヴン/
ノーブル:タッチ・オヴ・ユア・リップス/他 |
パーシー・フェイス(指揮)&
ヒズ・オーケストラ
ロバート・ファーノン(指揮)&
ヒズ・オーケストラ
デンマーク国立放送管弦楽団
クイーンズ・ホール・ライト・
オーケストラ、他 |
ライト・ミュージックの全盛期を回顧する名物シリーズの第117集は、北米の映画音楽やライト・ミュージックを牽引した2人のコンポーザー=コンダクター、パーシー・フェイスとロバート・ファーノンの演奏を集めたスペシャル・リクエスト。
1948年−1962年の録音。アラン・バンティングのリマスタリング。 |
| |
|
|
軽音楽の黄金時代 〜
コントラスト:1960年代から1920年代への回帰
Vol.1
ケイパー:オン・グリーン・ドルフィン・ストリート
モドゥーニョ:チャオ・チャオ・バンビーナ
アンダーソン:サテンを着た少女
ストット:フォーカス・オン・ファッション
ミラー:ロマネスク・タンゴ
ピーター:ムーンビーム
リンデマン:そりの鈴/他 |
シリル・オーナデル(指揮)
スターライト・シンフォニー
パーシー・フェイス(指揮)&
ヒズ・オーケストラ
リロイ・アンダーソン(指揮)&
ヒズ・オーケストラ
ワルター・ストット(指揮)
テレキャスト・オーケストラ/
ロバート・ファーノン(指揮)&
ヒズ・オーケストラ、他 |
ライト・ミュージックの全盛期を回顧する名物シリーズの第118集。
多様なコレクションを擁するライト・ミュージックの名曲を、1960年代から1920年代へと年代ごとに遡って収録されるシリーズの第1弾。移り変わるライト・ミュージックの歴史、コントラストを感じることができるだろう。
1929年−1962年の録音。アラン・バンティングのリマスタリング。 |
 HAENSSLER HAENSSLER
|
|
|
巨匠ヘルムート・リリングの名盤復活シリーズ!
ブラームス:ドイツ・レクイエムOp.45 |
ドナ・ブラウン(ソプラノ)
ジル・カシュマイユ(バリトン)
ヘルムート・リリング(指揮)
シュトゥットガルト・ゲヒンガー・カントライ
シュトゥットガルト・バッハ・コレギウム |
録音:1991 年/DDD、73’15”
2014 年5 月に81 歳を迎えた巨匠ヘルムート・リリング。今もなお精力的に演奏活動を続けるリリングですが、当盤は往年の名演奏から、現在では入手が難しくなってしまった名盤の再発売です。
1991 年に収録されたドイツ・レクイエムは、宗教曲の合唱指揮者としても名高いリリングならではの各パート、声部まできめ細かな解釈が魅力の演奏です。

|
 HERITAGE HERITAGE
|


HTGCD261
\1600 |
ライオネル・ターティス(Vla)の芸術
J.S.バッハ(ターティス編):シャコンヌBWV.1004
1924年11月25日録音/
ブラームス:ヴィオラソナタOp.120-1
ハリエット・コーエン(pf)
1933年2月17日録音/
ディーリアス(ターティス編):ヴァイオリンソナタ第2番
ジョージ・リーブス(pf)
1929年10月7日録音/
バックス:ヴィオラソナタ
アーノルド・バックス(pf) 1929年5月27日録音 |
| |

HTGCD262
\1600 |
シューマンと仲間たち
シューマン:子供の情景Op.15/
ゲーゼ:水彩画Op.19より、牧歌よりOp.34/
ヘラー:夢の絵Op.79より/
ブラームス:4つのバラードOp.10/
キルヒナー:夜の絵Op.25より
1991年11月録音 |
ディルク・イェレス(pf) |
| |

HTGCD263
\1600 |
音楽劇「イスカリオテのユダ」
散文詩:トーマス・ブラックバーン
音楽:ピーター・ディキンスン |
| |


HTGCD264
(2CD)
\3200 |
ヤナーチェク:ピアノ曲全集
2003年12月録音 |
マルティーノ・ティリモ(pf) |
| |

HTGCD266
\1600 |
パヌフニク:
交響曲第9番「希望の交響曲」
ファゴット協奏曲
1987年10月録音 |
ロバート・トンプソン(Fgt)
アンジェイ・パヌフニク指揮、
BBC交響楽団 |
| |

HTGCD267
\1600 |
晩祷
1960年録音 |
ケンブリッジ・キングズ・カレッジ合唱団 |
| |


HTGCD268
\1600 |
クラリネット・クラシックス
モーツァルト:クラリネット五重奏曲K.581
ブダペスト弦楽四重奏団 1938年4月録音/
バルトーク:コントラスツ
ベラ・バルトーク(pf)
ヨゼフ・シゲティ(Vln)
1940年5月録音/
ドビュッシー:第1狂詩曲
ジョン・バルビローリ指揮、
ニューヨーク・フィルハーモニック
1940年12月録音/
ブラームス:クラリネットソナタ第2番
ナディア・ライゼンバーグ(pf)
1945年12月録音/
ベートーヴェン(ベリソン編):
モーツァルトの「ドン・ジョヴァンニ」による変奏曲
ナディア・ライゼンバーグ(pf)
1946年9月録音/
ウェーバー:協奏的大二重奏曲Op.48より第3楽章
ナディア・ライゼンバーグ(pf) 1946年7月録音 |
ベニー・グッドマン(Cla) |
| |


HTGCD269
\1600 |
ノエル・ミュートン=ウッド(pf)の芸術
ウェーバー:ピアノソナタ第1番、第2番/
ショパン:タランテラOp.43 1941年録音
シューベルト:流れにて/
ベートーヴェン:遥かな恋人に
1953年録音 |
ピーター・ピアーズ(Ten)
デニス・ブレイン(Hrn) |
| |


HTGCD270
\1600 |
ハヴァーガル・ブライアン:歌劇「虎」より
シンフォニック・ダンス
ジョン・フォウルズ:パスクネィド・シンフォニー第1番 |
レオポルト・ハーガー指揮、
ルクセンブルグ放送交響楽団 |
| |

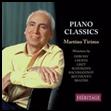
HTGCD271
\1600 |
マルティーノ・ティリモ(pf)名演奏集
リスト:ため息/
ドビュッシー:亜麻色の髪の乙女/
アルベニス:カスティーリャ/
シューマン:夕べに/
ショパン:ショパン華麗なる大円舞曲/
バルトーク:子供のためにより/
ドビュッシー:ミンストレル、雪が踊っている/
シューベルト:4つの舞曲D.145-6、D.145-2、D.365-2D、779-13/
ショパン:幻想即興曲/
ドビュッシー:月の光/
ブラームス:ワルツOp.39-12/
ラフマニノフ:前奏曲Op.32-12/
ベートーヴェン:エリーゼのために/
ショパン:ノクターン(遺作)/
ドビュッシー:ゴリウォーグのケークウォーク、沈める寺/
リスト:リゴレット・パラフレーズ |
マルティーノ・ティリモ(pf) |
 HUNGAROTON HUNGAROTON
|


HCD 41011
(3CD)
\4800 →\4390 |
アニー・フィッシャーの芸術
CD1
(1)モーツァルト:ピアノ協奏曲第20番ニ短調K.466
(2)同:ピアノ協奏曲第21番ハ長調K.467
(3)同:ロンド ニ長調K.382
CD2
(4)ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第3番ハ短調Op.37
(5)モーツァルト:幻想曲とフーガ
ハ長調K.394
(6)シューベルト:即興曲ヘ短調Op.142の1
CD3
(7)シューベルト:ピアノ・ソナタ第21番変ロ長調D.960
(8)リスト:ピアノ・ソナタ
ロ短調 |
アニー・フィッシャー(Pf)
エルヴィン・ルカーチ(CD1)
ヘリベルト・エッセル(CD2)(指)
ブダペスト交響楽団 |
祝・生誕百年。アニー・フィッシャー絶頂期の絶品協奏曲集
録音[CD1 ; 1965年3 月7-11 日(1)(2)、4
月5
日(3)、CD2 ; 1966年6 月2-5 日(5)、1965
年4
月5 日(6)、3 月28-31 日(7)、CD3
; 1968年3
月28-31日(8)、1953 年1 月9 日⑧/フンガロトン・スタジオ]/ADD
今年2014 年に生誕百年を迎えるアニー・フィッシャー。それを祝い、長く入手困難となっていた音源を3
枚組にしてお手頃価格でご提供いたします。
リストのソナタを除くと、いずれもフィッシャー50
代初めの演奏で、得意のモーツァルトとベートーヴェンの協奏曲を聴かせてくれます。モーツァルトの伴奏指揮は日本でもお馴染みのエルヴィン・ルカーチ。フィッシャーの独奏ともども音楽を楽しんでいるのが伝わってくる、聴いていて幸せな気持ちになれるアルバムです。
一方ベートーヴェンは力強く颯爽とした快演。さらに、シューベルトの大作、ピアノ・ソナタ第21
番とリストのピアノ・ソナタ ロ短調も充実の名演。虚飾の一切ない、切りつめられたピアニズムながら、これほど豊かな音楽を引き出し、聴き手を魅きつけてしまうのはフィッシャーならではの魔術。まさに奇跡のピアノ演奏と申せましょう。 |
![]()