 III millennio(テルツォ・ミレンニオ) III millennio(テルツォ・ミレンニオ)
|
|
|
聞け、天よ イタリア・ルネサンス&バロックの教会音楽
クリストファノ・マルヴェッツィ(1547-1599):
「ラ・ペッレグリーナ」(1589)から シンフォニア
ジョヴァンニ・ジョヴェナーレ・アンチーナ(1545-1604):
「聖母マリアの調和の神殿」(1599)から
神を称えよ [Laudate Dio]
ディエゴ・オルティス(1510頃-1570頃):変奏論(1553)から
2つのレセルカダ
セラフィーノ・ラッツィ(1531-1613):
宗教的ラウダ集第1巻(1563)から 美しき処女
[Vergine bella]
ジローラモ・フレスコバルディ(1583-1643):
トッカータ集第2巻(1637)から トッカータ第1番
セラフィーノ・ラッツィ:
宗教的ラウダ集第1巻 から おお、マリア、暁の星よ
[O Maria diana stella]
ジョヴァンニ・バッティスタ・フォンターナ(?-1630頃):
ソナタ集(1641)から ソナタ第3番
不詳:常に喜ぶ [Iudundare iugiter] (ピエ・カンツィオネス(1582)から)
カルロ・カルヴィ(1610頃-1670):ギター曲集(1646)から
フィレンツェのアリア
ハインリヒ・プフェンダー(1590-1631):
モテット集(1625)から 聞け、天よ [Audite
coeli]
クラウディオ・モンテヴェルディ(1567-1643):
聖母マリアの夕べの祈り(1610)から あなたは美しい
[Pulchra es]
サロモーネ・ロッシ(1570頃-1630):
シンフォニアとガリアルダ集第1巻(1607)から
シンフォニア
クラウディオ・モンテヴェルディ:
「倫理的・宗教的な森」(1640)から 主をたたえよ
[Laudate Dominum]
ジローラモ・フレスコバルディ:
トッカータ集第1巻(1616)から フォリアによるパルティータ
アドリアーノ・バンキエーリ(1568-1634):新教会ペンシエーロ集(1634)から
天から雷が [Intonuit de carlo] (二人の天使の対話によるコンチェルト)
ジュリオ・チェーザレ・バルベッタ(1540-1603):
リュート曲集(1585)から モレスカ第4番「ラ・ベルガマスカ」
オリヴィエロ・バリス(1540-1616):
愛と魂のカンツォネッタ集(1607)から
聖なる処女 [Vergine sacra]
フランチェスコ・カヴァッリ(1602-1676):
「聖なる花輪」(1625)から 主に向かいて歌え
[Cantate Domino]
ミヒャエル・プレトリウス(1571-1621):
「シオンの音楽」(1605)から アーメン
[Amen] |
ラ・ロシニョル
相川英美(ソプラノ)
ロベルト・クインタレッリ(男性アルト、リコーダー)
マッテオ・パリアーリ(フラウト・トラヴェルソ、リコーダー)
フランチェスコ・ズヴァデッリ(歌、オルガン、チェンバロ)
ドメニコ・バローニオ(リュート、コラショーネ、バロックギター) |
|
録音:2013年11月、サーラ・ムジカーレ・ジャルディーノ、クレーマ、クレモナ県、イタリア
2010年以来停滞していたテルツォ・ミレンニオ・レーベルが活動を再開、看板アーティストであるラ・ロシニョルの新録音が登場しました。
ラ・ロシニョルは1987年に創設された声楽とピリオド楽器のアンサンブル。イタリア在住の日本のソプラノ相川英美(あいかわえみ)が参加しています。
|
| |
|
|
ロベルト・カラヴェッラ(1959-):
オラトリオ「天使が処女マリアに」
(独唱、合唱、弦楽合奏、オルガンと朗読のための;2012) |
メルセデス・ロビエド(ソプラノ:天使 I)
マリア・デ・ロス・アンヘレス・ノバウ(ソプラノ:天使
II)
ラウラ・レアル(アルト:天使 III)
ダニロ・バルド(テノール:天使 IV)
アントネラ・マガニ(メゾソプラノ:マリア)
マリオ・マルティネス(テノール:ガブリエル)
ピエーラ・デリ・エスポスティ(朗読:創造主)
シモンピエトロ・クッシーノ(チェロ)
アントニオ・ルチアーニ(ピアノ)
ロベルト・カラヴェッラ(サントゥール)
サンタフェ州ポリフォニー合唱団
サンタフェ州交響楽団
セルヒオ・シモノビチ(指揮) |
| 録音:2012年12月21-23日、聖フランシスコ修道院教会、アメナバル、サンタフェ州、
アルゼンチン |
| |

CDS 0154
\2300
【未案内旧譜】 |
パオロ・ヴィヴァルディ(1964-):
貴婦人、騎士、武具、愛 − オルランド・フリオーソの歌による
Le donne, i cavallier, l'arme, gli amori
/ O degli uomini inferma e instabil mente!
La battaglia / Quantunque il simular
/ Ove il sole cade
Se l'ntricati rami e l'aer fosco, basato
sul raag Bhairav
Di voce in voce / Chi mette Il pie sull'amorosa
pania
Piccola suite della pazzia d'Orlando
/ Pensier che'l cor m'aggiaeci et ardi
Verso le porte di Damasco / Il volo dell'Ippogrifo
/ Cerere
Assai piu larga piaga e piu profonda
/ Marfisa / Ad ascoltar v'aspetto |
アンサンブル・ブラダマンテ
パオロ・ヴィヴァルディ(ディレクター) |
| 録音:2002年2月4-9日、ハウス・レコーディング・スタジオ、ローマ、イタリア |
ACADEMIA DE MUSICA DE SANTA CECILIA DE LISBOA
(リスボン・サンタ・セシリア音楽アカデミー)
|

AMSC 01
\2400
【旧譜 再入荷】 |
ルイ・パイヴァ前作 南欧のブクステフーデ ファロ大聖堂のオルガン
ディートリヒ・ブクステフーデ(1637-1707):
わが愛する神に BuxWV179/前奏曲ト短調
BuxWV163
カンツォネッタ ト長調 BuxWV172/トッカータ
ト長調 BuxWV165
天におられるわれらの神 BuxWV207/トッカータ
ト長調 BuxWV164
カンツォーナ ハ長調 BuxWV166/前奏曲ト長調
BuxWV162
フーガ ロ長調 BuxWV176/イエス・キリスト、われらの救い主
BuxWV198
フーガ ハ長調 BuxWV174/暁の星の何と美しいことか
BuxWV223
今こそ主をたたえよ、わが魂よ
BuxWV212
今こそ主をたたえよ、わが魂よ(1,2,3)BuxWV213(ヘ長調に移調して演奏) |
ルイ・パイヴァ(オルガン)
|
|
録音:2007年7月2-5日、ファロ大聖堂、ファロ、ポルトガル
使用楽器:1710-1720年、ハンス・ハインリヒ・クーレンカンプ製
(2007年、ディナルテ・マシャド修復完了)
ポルトガル南部の港湾都市ファロ。その大聖堂のオルガンの修復完了に合わせて制作されたCD。なぜ南欧ファロのオルガンでブクステフーデなのか?それは、オルガン製作者であるハンス・ハインリヒ・クーレンカンプが北ドイツの偉大なオルガン製作家アルプ・シュニトガー(1648-1719)の弟子であり、また、修復が完了した2007年が北ドイツのリューベックで活躍しシュニトガーのオルガンをたいへん気にっていたブクステフーデの没後300年に当たっていたからとのことです。
外装に規格番号の表示がございません。
|
 ACTE PREALABLE ACTE PREALABLE
|
|
|
ヴィトルト・マリシェフスキ(1873-1939):室内楽作品集
Vol.1
弦楽五重奏曲ニ短調 Op.3(*)
弦楽四重奏曲第2番ハ長調
Op.6(+) |
フォー・ストリングス四重奏団
ルツィナ・フィエドゥキェヴィチ(第1ヴァイオリン)
グジェゴシュ・ヴィテク(第2ヴァイオリン)
ベアタ・ラシェフスカ(ヴィオラ)
ウーカシュ・トゥジェルツ(チェロ)
ヴォイチェフ・フダラ(チェロ(*)) |
|
録音:2013年12月8日(*)、12月20-21日(+)、市立総合中等学校、ボイショヴィ、ポーランド
前回新譜「ヴァイオリンとピアノのための作品集」(AP
0285)で好評を博したマリシェフスキの室内楽作品録音がシリーズ化されます。
ヴィトルト・マリシェフスキはペテルブルク音楽院でリムスキー=コルサコフに師事したポーランド人作曲家。1913年オデッサ音楽院の創立者となり初代院長に就任、ダヴィド・オイストラフ、エミール・ギレリスらを輩出しました。1921年、ソヴィエト政権の迫害によりポーランドに出国。ロシアにおける彼の名誉・功績はすべて消し去られ、オデッサ音楽院創立者も他人にすり替えられてしまいました。
ポーランドではワルシャワ音楽協会総裁、第1回ショパン国際ピアノ・コンクール委員長、ワルシャワ音楽院教授等の要職を歴任。作風は「古典的ネオ・ロマンティシズム」と称され、門下生である作曲家ヴィトルト・ルトスワフスキは後年、彼の講義を絶賛していました。
フォー・ストリングス四重奏団は2004年にルツィナ・フィエドゥキェヴィチによりカトヴィツェのポーランド放送交響楽団のメンバーを中心に創設されたアンサンブル。
旧譜
ヴィトルト・マリシェフスキ:ヴァイオリンとピアノのための作品集 |
|
|
ヴィトルト・マリシェフスキ(1873-1939):ヴァイオリンとピアノのための作品集
ヴァイオリン・ソナタ
ト長調 Op.1(1902)
4つの小品 Op.20(1923) |
レゼクスプロラテュール
アンナ・オルリク(ヴァイオリン(*))
ユゼフ・コリネク(ヴァイオリン(+))
ヨアンナ・ワヴリノヴィチ(ピアノ) |
|
録音:2013年、ポーランド放送スタジオ、ポーランド
ヴィトルト・マリシェフスキはペテルブルク音楽院でリムスキー=コルサコフに師事したポーランド人作曲家。1913年オデッサ音楽院の創立者となり初代院長に就任、ダヴィド・オイストラフ、エミール・ギレリスらを輩出しました。
1921年、ソヴィエト政権の迫害によりポーランドに出国。ロシアにおける彼の名誉・功績はすべて消し去られ、オデッサ音楽院創立者も他人にすり替えられてしまいました。ポーランドではワルシャワ音楽協会総裁、第1回ショパン国際ピアノ・コンクール委員長、ワルシャワ音楽院教授等の要職を歴任。
作風は「古典的ネオ・ロマンティシズム」と称され、門下生である作曲家ヴィトルト・ルトスワフスキは後年、彼の講義を絶賛していました。
|
|
| |
|
|
ヨアンナ・ブルズドヴィチ(1943-):
弦楽四重奏曲第1番「ラ・ヴィータ」(*)
連作歌曲「高熱の世界」(+)
連作歌曲「世界」(純真な詩集)(#) |
ネオ弦楽四重奏団(*)
カロリナ・ピョントコフスカ=ノヴィツカ(第1ヴァイオリン)
パヴェウ・カピツァ(第2ヴァイオリン)
ミハウ・マルキェヴィチ(ヴィオラ)
クシシュトフ・パヴウォフスキ(チェロ)
リリアナ・グルスカ(メゾソプラノ(+/#))
トマシュ・ヨチ(ピアノ(+/#)) |
|
録音:2013年12月、ライヴ、マゾフシェ文化芸術センター、ワルシャワ、ポーランド(+)
2014年3月、スタニスワフ・モニュシュコ音楽アカデミー・コンサートホール、グダンスク、ポーランド(*/#)
ヨアンナ・ブルズドヴィチはポーランドのワルシャワに生まれ、ショパン音楽アカデミーを卒業後フランス政府給費留学生としてパリでナディア・ブーランジェ、オリヴィエ・メシアン、ピエール・シェフェールに師事、その後ベルギーを本拠に活躍している作曲家。
アニエス・ヴァルダ(1928-)監督作品をはじめとする映画音楽の分野でも知られています。
|
| |
|
|
ヴィトルト・マリシェフスキ(1873-1939):ヴァイオリンとピアノのための作品集
ヴァイオリン・ソナタ ト長調
Op.1(1902)
4つの小品 Op.20(1923) |
レゼクスプロラテュール
アンナ・オルリク(ヴァイオリン(*))
ユゼフ・コリネク(ヴァイオリン(+))
ヨアンナ・ワヴリノヴィチ(ピアノ) |
|
録音:2013年、ポーランド放送スタジオ、ポーランド
ヴィトルト・マリシェフスキはペテルブルク音楽院でリムスキー=コルサコフに師事したポーランド人作曲家。1913年オデッサ音楽院の創立者となり初代院長に就任、ダヴィド・オイストラフ、エミール・ギレリスらを輩出しました。
1921年、ソヴィエト政権の迫害によりポーランドに出国。ロシアにおける彼の名誉・功績はすべて消し去られ、オデッサ音楽院創立者も他人にすり替えられてしまいました。ポーランドではワルシャワ音楽協会総裁、第1回ショパン国際ピアノ・コンクール委員長、ワルシャワ音楽院教授等の要職を歴任。
作風は「古典的ネオ・ロマンティシズム」と称され、門下生である作曲家ヴィトルト・ルトスワフスキは後年、彼の講義を絶賛していました。
|
| |
|
|
ユゼフ・ヴィエニャフスキ(1837-1912):ピアノ作品集
Vol.1
2台のピアノのための幻想曲
Op.42(*/+)/タランテッラ
Op.4(*)
サロン用ワルツ Op.7(+)/幻想曲とフーガ
Op.25(*)
タランテッラ第2番 Op.35(+)/夜想曲
Op.37(*)/奇想ワルツ
Op.46(+)
夢 Op.45 No.1(*)/演奏会用ワルツ第3番(四手連弾のための)Op.3(*/+) |
ヴァ・イ・ヴェ・ピアノ・デュオ
ヴァレンティーナ・セフェリノヴァ(ピアノ(*))
ヴェネーラ・ボイコヴァ(ピアノ(+)) |
|
録音:2013年7月19-20日、ポーランド放送スタジオS2、ワルシャワ、ポーランド
パリ音楽院で学んだユゼフ・ヴィエニャフスキは兄ヘンリク(ヴァイオリン奏者・作曲家)のピアノ伴奏者を10年近く務めた後独立した道を歩み始め、ドイツのヴァイマールでリストにピアノを、ベルリンでアドルフ・マルクス(1795-1866)に作曲を学び、パリ、モスクワ、ブリュッセルでヴィルトゥオーゾ・ピアニスト、作曲家およびピアノ教授として活躍しました。
作品は兄ほどには認められませんでしたが、近年ポーランドにおいて録音が増えてきており国際的にも再評価されそうな勢いです。Vol.1:AP
0184。
|
| |
|
|
ヨハン・クリストフ・ケスラー(1800-1872):ピアノ作品集
24の前奏曲 Op.31
24の練習曲 Op.20(1827)から
Vol.1(Nos.1-12) |
マグダレナ・ブジョゾフスカ(ピアノ) |
|
録音:2013年5月19日、7月18日、11月24日、ラドム、ポーランド
ヨハン・クリストフ・ケスラーはリヴィウ(ウクライナ)、ワルシャワ、ウィーンで活躍したドイツのピアニスト・作曲家。ウィーン時代に出版された「24の練習曲
Op.20」はリストに愛奏され高く評価されました。1829年にワルシャワに赴いたケスラーは青年ショパンと親交を結び「24の前奏曲
Op.31」を献呈。10年後、ショパンは同じ調性パターン(5度ずつ上昇)で書いた「24の前奏曲
Op.28」をケスラーに献呈しています。
ケスラーは終生ポーランドの作曲家・演奏家を支援したポーランド音楽の恩人とも言える人物です。
|
| |
|
|
ナジ・ハキム(1955-):ヴァイオリン作品集
ヴァイオリンとオルガンのための奇想曲(2005)(*)
サルヴェ・レジナ(ヴァイオリンとオルガンのための;2004)(*)
エドヴァルド・ムンクの「海辺の若者たち」による
無伴奏ヴァイオリンのための幻想曲(2010)(+)
ヴァイオリンとピアノのためのソナタ(2000)(#)
ヴァイオリンと弦楽合奏のための協奏曲(2002)(**) |
アグニェシュカ・マルハ(ヴァイオリン)
ナジ・ハキム(オルガン(*)、ピアノ(#))
ゼノン・ブジェフスキ・ワルシャワ弦楽合奏団(**)
アンジェイ・ゲンプスキ(指揮(**)) |
|
録音:2012年7月、主の復活教区教会、グダンスク、ポーランド(*)
2012年2月、フリデリク・ショパン音楽大学コンサートホール、ワルシャワ、ポーランド(+)
2009年10月、舞踏会ホール、フルサング宮、デンマーク(#)
2011年2、6月、ポーランド放送スタジオS2、ワルシャワ、ポーランド(**)
レバノンのベイルートに生まれたフランスの作曲家・オルガン奏者ナジ・ハキム。1975年パリに移住し国立電気通信大学で学ぶかたわらジャン・ラングレ(1907-1991)にオルガン演奏と即興法を師事、さらにパリ音楽院で学び抜群の成績で卒業。1985年パリのサクレ・クール教会のオルガン奏者に就任。1993年にはオリヴィエ・メシアンの後継としてサント・トリニテ教会のオルガン奏者となり2008年まで務めました。
彼はオルガン以外の楽器のための作品も数多く書いていますが、ヴァイオリン作品をまとめて聴ける機会はほとんどないのでこの録音は貴重と言えるでしょう。
|
| |
|
|
フェリクス・フルドラン(1880-1923):歌曲集
小さな聖体拝領者たち [Les
petites communiantes]
夜のアルジェ [Alger le soir]/蝶
[Le
papillon]
柳並木で [Le long des saules]/雪のように降る花
[Il neige des fleurs]
蜂 [Les abeilles]/謝肉祭
[Carnaval]/屏風の花
[Fleurs de paravent]
古い風車 [Le vieux moulin]/オアシス
[L'oasis]/エーデルワイス [Edelweiss]
アイスランドの船乗り [Marins
d'Islande]/そこで
[La-bas]
恋する瞳の美女 [La belle
aux yeux d'amour]
バイユーのレース編みの女
[La dentelliere
de Bayeux]
かもめ [Les mouettes]/聖ドロテア
[Sainte
Dorothee]
コサックの騎手 [Chevauchee
Cosaque]
ノルウェーの歌 [Chanson Norvegienne]/別れの手紙
[Lettre d'adieu]
雪のクリスマス [Noel de neige]
Op.60 |
リリアナ・グスカ(ソプラノ)
ピオトル・エイスモント(ピアノ) |
|
録音:2013年、録音スタジオ、スタニスワフ・モニュシュコ音楽アカデミー大学、グダンスク、ポーランド
フェリクス・フルドランはフランスのニースに生まれ、パリのエコール・ニーダーマイヤーで学んだ後、パリ音楽院でアレクサンドル・ギルマンとシャルル=マリー・ヴィドールにオルガンを師事。作曲家になることを決意しマスネの弟子となり、43歳で亡くなるまでに20を超える舞台作品や約100曲の管弦楽作品等を書き上げました。
|
| |
|
|
ツィプリアン・バジリク(1535頃-1600以後):作品全集 ポーランド・ルネサンスの歌
Nabozna piosnka [Pius Song)
Panie Boze wszechmocny [O
God, the heathen
are come into thine /
Deus venerut gentes (Psalm
LXXIX)]
Piesn o niebezpieczenstwie
zywoya [Song
about dangers oh human life]
W Tobie, Panie, nadzieje
mam
[In thee, O Lord, do I
put my trust
/ In Te Domine speravi (Psalm
LXX)]
Piesn z Ewanjelijej wyjeta
[Song of the
Gospel removed]
Wszytcy sa blogoslawieni
[Blessed is
every one / Beati omnes (Psalm
CXXVII)]
Dobrotliwosc Panska [Lord's
Goodless]
Oratio Dominica [Our Father]
Piesn nowa, w ktorej jest
dziekowanie
[The New Song, in which
we thank Almighty]
Piesn nowa krzescijanska
[The Christian
Song]
Z glebokosci, grzechow moich
[Out of the depths / De
profundis (Psalm
CXXIX)]
Zaniechaj towarzystwa z ludzmi
zlosciwemi
[Abstain from the company
of malevolent
people]
Piesn ranna, gdy slonce wschodzi
[Song
of the morning, when the sun
rises]
Pozegnanie krzescijanskie
na kazdy dzien
[Farewell Christian every day]
Benedicto Mense |
シェラツ・カンティレーナ合唱団
スブティリオル・アンサンブル
アンサンブル・アルス・ノヴァ
ヤツェク・ウルバニャク(指揮) |
|
録音:2012年9月、ウルスラ会修道院教会、シェラツ、ポーランド
ツィプリアン・バジリクはポーランドの作曲家・詩人・著作家・翻訳家・宗教改革者。シェラツの中産階級の家に生まれ、1550年頃クラクフのヤグエウォ大学に入学し神学を学びました。1557年に貴族に列せられバジリク姓を賜り、国王ジグムント2世アウグストの書記官を務めた後、1558年にヴィリニュス(リトアニア)の宗教改革派の大貴族である「黒髪の」ミコワイ・ラジヴィウの宮廷に仕え、音楽家、後に翻訳家として活躍。翻訳家として高く評価された彼は宗教改革派の著作のポーランド語訳にも取り組み、またカルヴァン派の印刷所の経営も行いました。
彼の音楽作品としてはルネサンス期のクラクフで印刷された譜面によって15曲の聖歌が現在に伝わっており、当盤にはそれらすべてが収められています。ポーランドにおける古楽のパイオニア、ヤツェク・ウルバニャク(1949年生まれ)が3つの団体を仕切った演奏です。
|
| |
|
|
アレクサンデル・タンスマン(1897-1986):ピアノ作品集
5つの即興曲(1922-1926)
6つのアラベスク(1930)
8つのノヴェレッテ(1936) |
エルジビェタ・ティシェツカ(ピアノ) |
| タンスマンが子供や10代のピアノ学習者のために書いた親しみやすいピアノ曲集シリーズ4作(「ピアノを弾く子供たち」(AP
0205)、「幸せな時間」(AP 0246)、「子供たちのために」(AP
0255)、「ピアノ演奏の上達」(AP
0270))で好評を得たエルジビェタ・ティシェツカがタンスマンの本格的ピアノ作品を弾いた一枚。 |
| |
|
|
ベートーヴェン、ショパン、ドビュッシー:ピアノ作品集
ベートーヴェン(1770-1827):ソナタ第8番ハ短調「熱情」Op.13
ショパン(1810-1849):
練習曲ホ長調 Op.10 No.3/練習曲ハ短調
Op.10 No.12
子守歌 変ニ長調 Op.57/スケルツォ第2番変ロ短調
Op.31
ドビュッシー(1862-1918):
前奏曲集第2巻 から ヒースの荒野/版画
から 塔,雨の庭 |
カタジナ・ピェトロン(ピアノ) |
|
録音:2013年9月14日、スタジオ・フルスト、スレユヴェク、ポーランド
カタジナ・ピェトロンはワルシャワ音楽大学でピアノ(エルジビェタ・タルナフスカに師事)、楽理、合唱指揮を修め、2014年現在ポーランド科学カデミー技術研究所博士課程に在籍中の女性。著作「自己表現と声の働き」を出版、また音楽雑誌のCDレビューも担当しています。
ピアニストとしてはヴロツワフの国際ピアノ・マスターコースでアンジェイ・ヤシンスキの指導を受け勉強を終え、ワルシャワを本拠に演奏活動を展開しています。
|
ALMAVIVA
|
|
|
現代スペイン女性作曲家たちのハープ作品集
ラウラ・ベガ(1978-):
私を覆う夜を超えて [Mas alla
de la noche
que me cubre...]
マリア・ホセ・アレナス(1983-):マクトゥーブ
II [Maktub II]
メルセデス・サバラ(1963-):
雪の上の雪 [Nieve sobre nieve]/降りしきる雪
[Incesante nieve]
ロサ・マリア・ロドリゲス・エルナンデス:ルスエロ
[Luzeulo]
ディアナ・ペレス・クストディオ(1970-):オルフェオ・ジップ
[L'Orfeo.zip]
コンスエロ・ディエス(1958-):存在と時間
[Ser y Tiempo]
ドロレス・セラノ・クエト(1967-):裂かれた道
[Caminos rasgados]
マリサ・マンチャド(1956-):
アンヘラのための7つの小品
[Siete piezas
para Angela]
マリア・ルイサ・オサイタ(1938-):幻想曲
[Fantasia]/思い出 [Recuerdos]
イルミナダ・ペレス・フルトス(1972-):
ハープのタペストリーの上で
[Sobre el
tapiz del arpa]
カルメ・フェルナンデス・ビダル(1970-):灰色の霧
[Brume Grisatre] |
クリスティナ・モンテス・マテオ(ハープ) |
|
録音:データ記載なし
クリスティナ・モンテス・マテオは1984年スペインのセビリャに生まれ、セビリャのマヌエル・カスティリョ音楽院、ロンドンの王立音楽アカデミーで学び、シュターツカペレ・ベルリン・オーケストラ・アカデミーのメンバーとしてダニエル・バレンボイムの指導を受けたハープ奏者。日本ハープコンクール他数々の国際コンクール入賞。2013年現在バレンシア州立管弦楽団(ロリン・マゼール音楽監督)のメンバー。
|
| |


DS 0130
\2400 →\2190
【未案内旧譜】 |
トゥリーナ(1882-1949):室内楽作品集
弦楽四重奏曲ニ短調「ギター風」Op.4(1911)
セレナード Op.87(1934)
闘牛士の祈り Op.34(1925)
ピアノ五重奏曲ト短調 Op.1(1907)(*) |
ブレンノ・アンブロジーニ(ピアノ(*))
グリニッジ弦楽四重奏団
マイケル・トマス、
ブライアン・ブルックス(ヴァイオリン)
ジェーン・アトキンズ(ヴィオラ)
テュモシー・ヒューズ(チェロ) |
|
録音:1999年6月、セント・ピーター・イン・チェインズ教会、ロンドン、イギリス
発売:2001年
前ディストリビューターからも未案内だった旧譜商品。ピアノ五重奏曲
Op.1はフランク流の循環形式による力作。弦楽四重奏曲
Op.4は先輩アルベニス(1860-1909)から「(フランク流を脱して)スペイン的な音楽を目指すべき」という助言を受けたトゥリーナが自己のスペイン的様式を確立した作品と言われています。
|
 ALTHUM ALTHUM
|
|
|
16&17世紀イベリア半島のオルガン音楽/アロウカ修道院のオルガン
ディエゴ・デ・コンセイサン(17世紀;ポルトガル):バタリャ[戦争]第5旋法
アントニオ・デ・カベソン(1510-1566;スペイン):パヴァーヌとそのグロサ
アントニオ・カレイラ(1530頃-1594頃;ポルトガル):
アヴェ・マリア(4声)/4声の歌とグロサ
セバスティアン・アギレラ・デ・エレディア(1561-1627;スペイン):
作品第8旋法(アルト:エンサラダ)/ティエント・デ・ファルサス第6旋法
セバスティアン・ドゥロン(1660-1716):ティエント第1旋法−左手のガイティリャ
マヌエル・ロドリゲス・コエリョ(1555-1635;ポルトガル):
テント第2番第1旋法「デ・ラ・ソ・レ」
フランシスコ・コレア・デ・アラウホ(1575-1654;スペイン):
ソプラノ声部のメディオ・レヒストロによるティエント第8旋法
ジュアン・カバニリェス(1644-1712;スペイン):
パッサカリア第3番第3旋法/イタリア風クラント
ペドロ・デ・アラウジョ(1610-1684;ポルトガル):
2つのソプラノ声部のメイオ・レジストロによる(作品)第2旋法
ファンタジア第4旋法
不詳(18世紀初頭、アントニオ・マルティン・イ・コルの曲集から;ポルトガル)
バタリャ・ファモザ[有名な戦争] |
ルイ・パイヴァ(オルガン) |
|
録音:2013年7月18-20日、アロウカ修道院、アロウカ、ポルトガル
使用楽器:1739年、ドン・マヌエル・ベント・ゴメス・フェレイラ製(2009年、ゲアハルト・グレツィング修復)
「ラッパ奏法」(水平方向に突き出したラッパ管でトランペットやトロンボーンのような音を出す)や音栓分割(一段の鍵盤の高音部・低音部で異なる音色にする)の使用といった独特の発展を遂げたイベリア半島(スペインとポルトガル)のオルガン音楽と、その発展をもたらしたイベリア式バロック・オルガンの響きを堪能できる一枚。メディオ・レヒストロ(スペイン語)/メイオ・レジストロ(ポルトガル語)は音栓分割、ティエント(スペイン語)/テント(ポルトガル語)およびグロサは変奏曲の一形式。
ポルトガル第二の都市ポルト近郊のアロウカにある修道院のオルガンは典型的なイベリア・バロック・タイプの楽器。様々な音栓から生み出される音色は極めて個性的で、小鳥のさえずりを模した効果音(ペダル機能)まで現れます。現代ポルトガルを代表するオルガン奏者の一人でありイベリアの歴史的オルガン演奏の第一人者であるルイ・パイヴァによる演奏はまさに文句なし。絶品です。「オルガンは地味で単調で…」という先入観は、これらの音楽、この楽器、そしてこの奏者にはまったく当てはまりません。
収録時間約70分。スペイン・ポルトガル料理のフルコースを満喫した気分になれます。(株式会社サラバンド代表取締役
金田敏也)
ルイ・パイヴァ(1961年生まれ)はリスボン高等技術学校電気工学を修了、リスボン国立音楽院でジョアキム・シモンイス・ダ・オラにオルガンを、クレミルデ・ロザド・フェルナンデスに通奏低音を師事、さらにバルセロナ(スペイン)でモンセラト・トゥレンに、サラゴサ(スペイン)でホセ・ルイス・ゴンサレル・ウリオルに教えを受けたポルトガルのオルガンおよびチェンバロ奏者。1989年から2011年までリスボン国立音楽院教授、2014年現在リスボン・サンタ・セシリア音楽アカデミー学長を務めています。
■ハードカヴァー・ブック仕様。本体・外装の規格番号表示は「A
006」となっておりますが、弊社では「ALTHUM
006」として管理いたします。(代理店)
|
| |

ALTHUM 004
\2400
【旧譜 再入荷】 |
フェルナンド・デ・アルメイダ(1600頃-1660):
聖木曜日のレスポンソリウム集
オリーヴ山で/わが魂は悲しむ/そこでわれらは彼を見た/わが友が
極悪の商人ユダは/弟子のうちの一人が/われは子羊のごとく
民の長老らは
平日のミサ; キリエ/サンクトゥス/ベネディクトゥス/アニュス・デイ |
カペラ・パトリアルカル
モニカ・サントス、
モニカ・モンテイロ(ソプラノ)
カロリナ・フィゲレド、
カタリナ・サライヴァ(アルト)
ジョアン・モレイラ、
アンドレ・バレイロ(テノール)
マヌエル・レベロ、
ティアゴ・シルヴァ(バス)
セルジオ・シルヴァ(オルガン)
ジョアン・ヴァス(指揮) |
|
録音:2011年1月17-19、24日、聖ニコラウ教会、リスボン、ポルトガル
フェルナンド・デ・アルメイダはポルトガルの作曲家・キリスト騎士団修道士。ドゥアルテ・ロボ(1565頃-1646)に師事しトマルのキリスト教修道院楽長を務めました。最近までほとんど顧みられることがなかったものの、その厳格な対位法や修辞的表現法は彼がポルトガル音楽史において重要な人物の一人であったことを裏付けています。
カペラ・パトリアルカルは16世紀から19世紀のポルトガル音楽を演奏するために2006年に創設された声楽アンサンブル。指揮者のジョアン・ヴァスはポルトガルにおける歴史的オルガン演奏の第一人者です。
ハードカヴァー・ブック仕様。本体・外装の規格番号表示は「A
004」となっておりますが、弊社では「ALTHUM
004」として管理いたします。(代理店)
|
| |
|
|
フェルナンド・ロペス=グラサ(1906-1994):子供のための歌
あの雲、他 [Aquela nuvem
e outras] (全22曲)
ティアの歌集 [As Cancoezihnas
da Tila]
(全11曲)
子供たちのためのクリスマス
[Natal para
as criancas] (全10曲) |
リスボン・サンタ・セシリア音楽アカデミー児童合唱団(独唱、斉唱、合唱)
イネス・メスキタ、
ジョアナ・アルヴェス(ピアノ)
アナ・パウラ・ロドリゲス、
アントニオ・ゴンザルヴェス、
アルトゥル・カルネイロ(指揮) |
|
録音:2005-2007年、スタジオ・ナモシェ、リスボン、ポルトガル
ハードカヴァー・ブック仕様。本体・外装の規格番号表示は「A
007」となっておりますが、「ALTHUM
007」として管理いたします。(代理店)
|

ARS PRODUKTION
|


ARS 38113
(SACD Hybrid)
\2500 →\2290 |
リーツ、グロス:チェロ協奏曲集
ユリウス・リーツ(1812-1877):チェロと管弦楽のための幻想曲
Op.2
ヨハン・ベンヤミン・グロス(1809-1848):チェロ協奏曲ロ短調
ユリウス・リーツ:チェロ協奏曲
Op.16 |
クラウス=ディーター・ブラント(チェロ)
ラルパ・フェスタンテ
リッカルド・ミナージ(指揮) |
|
録音:2011年8月25-31日
メンデルスゾーン、シューマンと同世代で彼らと交友のあった二人のドイツ人作曲家のチェロ協奏曲。世界初録音。
ユリウス・リーツはベルリンに生まれた作曲家・指揮者・チェロ奏者。デュッセルドルフ、ライプツィヒ、ドレスデンで楽壇の要職を歴任。教育者として、またメンデルスゾーンの多くの作品とバッハの「マタイ受難曲」「ミサ
ロ短調」の校訂者としても名を残しています。
ヨハン・ベンヤミン・グロスはエルビング(現ポーランドのエルブロング)に生まれた作曲家・チェロ奏者。1835年より「皇帝付き室内楽士」の称号を得てサンクトペテルブルク(ロシア)の宮廷楽団員を務めながらチェロ音楽の作曲と教育活動を続けましたが、コレラのため38歳の若さで亡くなりました。
クラウス=ディーター・ブラントはムジカ・アンティクァ・ケルン、ウィーン・アカデミー、ラルパ・フェスタンテ等のピリオド楽器オーケストラで首席を務めてきたドイツのチェロ奏者。当レーベルでは一貫して知られざる作品の録音に取り組み、「室内楽珍曲集シリーズ」(ARS
38067, 38071, 38096)、「アーベル、グラーフ:チェロ協奏曲集」(ARS
38068)をリリースしています。ラルパ・フェスタンテは1983年ミヒ・ガイクによりミュンヘンで創設されたピリオド楽器オーケストラ。
美しいんです
ヨハン・ベンヤミン・グロス:作品集(全曲世界初録音) |
|
|
「ロマンチックなバラード」
ヨハン・ベンヤミン・グロス(1809〜1848):作品集(全曲世界初録音)
(1)チェロ・ソナタ ロ短調
op.7
(2)薬屋の主人は恋がたき(詩:グルッペ)op.35-3
(3)フリードリッヒ・バルバロッサ(詩:リュッケルト)op.35-5
(4)バラード op.26-4
(5)愛のかなしみ(詩:ハイネ)op.35-4
(6)ヘブライの歌より(詩:バイロン)op.35-6
(7)チェロとピアノのためのセレナーデ
ハ長調
op.32
(8)第3 集より(詩:リュッケルト)op.35-1
(9)弦楽四重奏曲 ヘ短調
op.37-3 |
金子陽子
(ピアノ/ウィーン製1838年頃の
フォルテピアノ”グロス”)
ミヒャエル・ダーメン(バリトン)
クリストフ・コワン
(チェロ/ 1720 年頃製
アレッサンドロ・ガリアーノ製のチェロ)
モザイク弦楽四重奏団
(エーリヒ・ヘーバルト、
アンドレア・ビショッフ、
アニタ・ミッテラー、
クリストフ・コワン) |
忘れ去られた作曲家、ヨハン・ベンヤミン・グロス世界初録音による作品集。コワンと金子陽子の魅力のデュオ充実の弦楽四重奏曲!
録音:2009 年9 月
チェリスト、そして作曲家として19
世紀の重要な人物、ベンヤミン・グロスの作品集。音楽史や事典で彼のことが扱われることはほとんどありませんが、43
の主にチェロのための作品(4
つのチェロ協奏曲、ソナタ1
曲ほか)、4 つの弦楽四重奏曲や何曲かの歌曲をのこしています。ベルリン、そしてライプツィヒでチェロ奏者として活躍しながら、メンデルスゾーン、シューマン、クララ・シューマンらと一緒にロマン派の渦の中心点にいました。クララ・シューマンとは自作のソナタを共演したことがあるといいます。1848
年に教師・チェロ奏者として活躍したサンクト・ペテルブクルクの地でコレラにかかり客死しました。
作品はどれもロマン派ならではの抒情と情熱に満ちたもの。チェロ・ソナタ
ロ短調ではコワンが渋く滋味あふれる音色で旋律をうたい、金子のピアノが熱く華麗にコワンの奏でる旋律を彩ります。歌曲でも、詩の魅力が存分に活きた曲作りが見事。弦楽四重奏曲では濃厚メロディと熱を帯びた和声、ロマンの魅力に溢れています。モザイク・クヮルテットの熟練のアンサンブルが光ります。
|
|
| |


ARS 38148
(SACD Hybrid)
\2500 →\2290 |
ロシアの管弦楽曲をピアノで トランスクリプション&パラフレーズ集
フロリアン・ノアック(1990-)編曲/
チャイコフスキー(1840-1893):組曲「白鳥の湖」
情景/ワルツ/モデラート/ロシアの踊り
ラフマニノフ(1873-1943):オペラ「アレコ」からの組曲
序奏/女たちの踊り/男たちの踊り
リムスキー=コルサコフ(1844-1908):交響組曲「シェエラザード」Op.35
海とシンドバッドの船/カランダール王子の物語/若い王子と王女
バグダッドの祭り−海−船は青銅の騎士のある岩で難破−終曲
リャードフ(1855-1914):魔法にかけられた湖
Op.62
チャイコフスキー:幻想序曲「ロミオとジュリエット」 |
フロリアン・ノアック(ピアノ) |
|
録音:2014年1月、インマヌエル教会、ヴッパータール、ドイツ
録音時点で23歳、ベルギーの新星フロリアン・ノアックがその編曲の才をもあらわにした驚きのディスク。絢爛なオーケストレーションで知られる「シェエラザード」をも四手ではなく二手用に書き換え、弾ききってしまいます。
フロリアン・ノアックは12歳でエリーザベト王妃シャペル・ミュジカルの天才児コース受講者に選ばれ、15歳でベルギー国内の8つのコンクール優勝。16歳でケルン音楽大学に入りロシアのピアニストで作曲家のヴァシーリー・ロバノフに師事、ここでロシア音楽への理解を深めたと思われます。
ノアックのロシア管弦楽曲のピアノ編曲スコアは出版されており、ドミートリー・バシキーロフ、シプリアン・カツァリス、ボリス・ベレゾフスキーといった技巧派ピアニストたちにも採用されています。
|
| |

ARS 38149
(SACD Hybrid)
\2500 |
プレヴィン、ショスタコーヴィチ、ベラウアー:チェロとピアノのための作品集
アンドレ・プレヴィン(1929-):チェロ・ソナタ(1993)
ショスタコーヴィチ(1906-1975):チェロ・ソナタ
ニ短調 Op.40
ヨハネス・ベラウアー(1979-):パッサカリア(2012) |
マティアス・バルトロメイ(チェロ)
クレメンス・ツァイリンガー(ピアノ)
|
|
録音:2014年2月10-13日
マティアス・バルトロメイは1985年ウィーンに生まれたチェロ奏者で、父はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団首席チェロ奏者のフランツ・バルトロメイ。ウィーン音楽大学で学んだ後ザルツブルク・モーツァルテウム大学に進み2010年に卒業。2011年以来2014年現在ウィーン・コンツェントゥス・ムジクスとカメラータ・ザルツブルクのソリスト(首席奏者)を務めています。このCDがデビュー盤となります。
プレヴィンのソナタは彼がモーツァルテウム大学卒業試験の際に演奏した曲。ヨハネス・ベラウアーはクラシックとジャズの両分野で活躍する作曲家。
|
| |

ARS 38150
(SACD Hybrid)
\2500 |
ピアノのための幻想曲集
シューベルト(1797-1828):幻想曲ハ長調「さすらい人」Op.15
D.760
カール・フィリップ・エマヌエル・バッハ(1714-1788):幻想曲嬰ヘ短調
シューマン(1810-1856):幻想曲ハ長調
Op.17 |
ダナエ・デルケン(ピアノ) |
|
録音:2014年1月13-15日
デビューCD「ヤナーチェク:ピアノ作品集」(ARS
38130)が弊社(代理店)にとって意外にも(ごめんなさい)好セールスだったダナエ・デルケンのセカンドCD。
ダナエ・デルケンは1999年ドイツのヴッパータールに生まれたピアニスト。両親はドイツ人とギリシャ人で音楽一家ではありませんでしたが、4歳のときに友達の弾くピアノに興味を覚え、5歳になって
Marina Kheifetzのもとでレッスンを開始、半年後にはコンクールで入賞するという神童ぶりを発揮しました。
1999年3月、ユーディ・メニューインに才能を見出され援助の申し出を受けるもメニューインが数日後に急逝。2002年の終わり、11歳のときに参加したカール=ハインツ・ケンマーリングのマスタークラスにおいて彼に誘われ入門し2012年に彼が亡くなるまで師事。2014年現在ラルス・フォークトに師事しています。
|
| |


ARS 38526
(2CD)
\2500→ \2290
|
クララ&ローベルト・シューマン:ロマンス
ヴァイオリン/ヴィオラとピアノのための作品集
ローベルト・シューマン(1810-1856):
オーボエ(ヴァイオリン)とピアノのための3つのロマンス
Op.94
クララ・シューマン(1819-1896):
ヴァイオリンとピアノのための3つのロマンス
Op.22
ローベルト・シューマン:
クラリネット(ヴァイオリン)とピアノのための幻想小曲集
Op.73
ヴァイオリン・ソナタ第1番イ短調
Op.105
おとぎの絵本(ヴィオラとピアノのための)Op.113(*)
ヴァイオリン・ソナタ第2番ニ短調
Op.121
ヴァイオリン・ソナタ第3番イ短調
WoO.2 |
ゲオルク・ハーマン(ヴァイオリン(*以外)、ヴィオラ(*))
ベアータ・ベック(ピアノ) |
|
録音:2013年2月5-7日、4月12-28日、パウル・バドゥラ=スコダ・スタジオ
ゲオルク・ハーマンは1960年ウィーンに生まれ、ウィーン音楽大学でアルバン・ベルク弦楽四重奏団のメンバーであるクラウス・メッツル(ヴァイオリン)、ハット・バイエルレ(ヴィオラ)に師事したヴァイオリンおよびヴィオラ奏者。長年にわたりウィーン室内管弦楽団首席ヴィオラ奏者を務めており、またアンサンブル・ウィーン東京のメンバーだったこともあってたびたび来日しており、その演奏、録音や教育活動を知る日本のファンは多いことでしょう。
ベアータ・ベックは1986年ウィーン生まれのピアニスト。2007年以来ゲオルク・ハーマンとデュオを組んでいます。
|
BOMBA
|
BOMBA-PITER(サンクトペテルブルク)とは別のモスクワのレーベル。
2012年にご案内した "Russian
Performing
School" シリーズの発売元です。 |

BOMB 033-276
\2300
【未案内旧譜】 |
レオニード・デシャトニコフ(1955-):室内オペラ「貧しいリーザ」 |
ユリア・コルパチョーヴァ(ソプラノ)
エンドリュ・グドヴィン(テノール)
ヴァディム・ニキーチン(朗読)
オレシア・テルティチナヤ(フルート、ピッコロ、アルトフルート)
デニス・ビュストロフ(オーボエ)
ヴィラディスラフ・ペーシン、
ユーリー・ウシチャポフスキー(ヴァイオリン)
アレクセイ・ボゴラート(ヴィオラ)
タラス・トレペリ(チェロ)
アレクセイ・イヴァーノフ(コントラバス)
ミハイル・ラデューケヴィチ(ギター)
アレクセイ・ゴリボリ(ピアノ、音楽監督) |
|
録音:2006年 発売:2007年
レオニード・デシャトニコフはウクライナに生まれレニングラード音楽院で学んだ作曲家。映画音楽とオペラで名声を得ています。
|
 CASTELLO CASTELLO
|
約4年ぶりのご案内。
ポーランドのコンサート・エージェント「Castello
Grupa Tworcza」(Castello Creative
Group)が所属アーティストを起用して立ち上げたレーベル。 |
|
|
シマノフスキ(1882-1937):歌曲集
クルピエ地方の12の歌 Op.58
スウォピェフニェ(ユリアン・トゥビムの詩による5つの歌)Op.46bis
ヤン・カスプロヴィチの詩による3つの断章(賛歌)Op.5 |
イザベラ・マトゥワ(ソプラノ)
マリア・リゼフスカ(ピアノ) |
|
録音:2008年10月、コシュキエフ城、クラクフ、ポーランド
イザベラ・マトゥワ(1980年生まれ)はクラクフ音楽アカデミーで学んだポーランドのソプラノ。
|
| |
|
|
シューベルト、シューマン、ピアティゴルスキー、ダンチョフスキ:
チェロとピアノのための音楽
シューベルト(1797-1828):アルペッジョーネ・ソナタ
イ短調 D.821
シューマン(1810-1856):おとぎの絵本
Op.113
グレゴール・ピアティゴルスキー(1903-1976):パガニーニの主題による変奏曲
デジデリウシュ・ダンチョフスキ(1891-1950):ポロネーズ |
バルトシュ・コジャク(チェロ)
ユスティナ・ダンチョフスカ(ピアノ) |
|
録音:2009年9月、ヴワディスワフ・ジェレンスキ中等音楽学校コンサートホール、クラクフ、ポーランド
デジデリウシュ・ダンチョフスキはポーランドのチェロ奏者・教師・作曲家。彼の孫にあたるのがヴァイオリニストのカヤ・ダンチョフスカ(1949-)で、彼女の娘が当盤のピアニストであるユスティナ。
ユスティナ・ダンチョフスカは1981年ポーランドのクラクフに生まれ、バーゼル音楽アカデミーでクリスティアン・ジメルマン、チューリヒ音楽大学でコンスタンチン・シチェルバコフに師事。
バルトシュ・コジャクは1980年ポーランドのザコパネに生まれ、ワルシャワのショパン音楽大学でカジミェシュ・ミハリクとアンジェイ・バウエルに、パリ音楽院でフィリップ・ミュレールに師事。作曲家ペンデレツキからの信頼厚く、彼のコンサート・シリーズの常連となり新作初演にも参加。カヤ・ダンチョフスカの好意によりデジデリウシュ・ダンチョフスキが所有したチェロを貸与されています。
|
| |
|
|
ヴィヴァルディ(1678-1741):ヴァイオリン協奏曲集「四季」 |
アンナ・タルノフスカ(ヴァイオリン)
タルヌフ室内管弦楽団
スタニスワフ・クラフチンスキ(指揮) |
|
録音:1996年、クラクフ、ポーランド
アンナ・タルノフスカはクラクフ音楽アカデミーでカヤ・ダンチョフスカに師事し1993年に卒業したポーランドのヴァイオリニスト。モダーン楽器での演奏。
|
| |
|
|
ヴィヴァルディ、J・S・バッハ:ヴァイオリン協奏曲集
ヴィヴァルディ(1678-1741):
「ラ・ストラヴァガンツァ」Op.4
から(*)
第1番変ロ長調 RV383a/第8番ニ短調
RV249/第9番ヘ長調 RV284
シンフォニア ト長調 RV146
J・S・バッハ(1685-1750):
ヴァイオリン協奏曲第1番イ短調
BWV1041(+)
2つのヴァイオリンのための協奏曲ニ短調
BWV1043(#/+) |
パヴェウ・ヴァイラク(ヴァイオリン(*)、指揮)
アダム・モクルス(ヴァイオリン(+))
ユスティナ・パヴウォフスカ(ヴァイオリン(#))
タルヌフ室内管弦楽団 |
|
録音:2011年8月24-26日、高等神学校講堂、タルヌフ、ポーランド
パヴェウ・ヴァイラクは2014年現在クラクフ・フィルハーモニー管弦楽団コンサートマスター。アダム・モクルスは2003年から2009年までチェンストホヴァ・フィルハーモニー管弦楽団コンサートマスター。ユスティナ・パヴウォフスカは2009-2010年カロル・シマノフスキ・アカデミー交響楽団コンサートマスター。モダーン楽器での演奏。
|
| |
|
|
シューマン(1810-1856):ヴァイオリン・ソナタ第2番ニ短調
Op.121
プロコフィエフ(1891-1953):ヴァイオリン・ソナタ第1番ヘ短調
Op.80 |
マリア・スワヴェク(ヴァイオリン)
ピオトル・ルジャンスキ(ピアノ)
|
|
録音:データ記載なし
マリア・スワヴェクは1988年ポーランドのグダンスクに生まれ2011年にクラクフ音楽アカデミーを卒業したヴァイオリニスト。ピオトル・ルジャンスキは1989年クラクフに生まれ当盤録音時点でクラクフ音楽アカデミー在学中のピアニスト。
|
| |
|
|
古い聖歌と新しい聖歌
トマス・ルイス・デ・ビクトリア(1548-1611):Ave
Maria
グレゴール・アイヒンガー(1564-1628):Ave
Regina coelorum
グレゴリオ聖歌:Ubi caritas
フェリーチェ・アネーリオ(1560-1614):Christus
factus est
ミコワイ・ゴムウカ(1535-1609):Wszyscy,
ktorzy po ziemi chodzicie
シャモトゥーのヴァツワフ(1524-1560):Alleluja.
Chwalcie Pana Boga
トマス・タリス(1505-1585):If
ye love
me
マレク・ヤシンスキ(1949-2010):Ave
Maria
クシシュトフ・グジェシュチャク(1965-):Antyfona
(Ave Regina coelorum)
オラ・イェイロ(1978-):Ubi
caritas
アントン・ブルックナー(1824-1896):Christus
factus est
パヴェウ・ウーカシェフスキ(1968-):Jubilate
Deo
ミハウ・ジェリンスキ(1965-):Laudate
Dominum
フィリップ・ストップフォード(1977-):If
ye love me |
レジェ・アルティス室内合唱団
アグニェシュカ・トレラ=ヨヒメク(指揮)
|
|
録音:2012年5月、聖スタニスワフ司教殉教者教会、ウヘルツェ・ミネラルネ、ポーランド
レジェ・アルティス室内合唱団は2005年ポーランドのクラクフに創設。ルネサンスから現代に至る無伴奏合唱音楽に取り組んでいます。(上記の作曲者生没年は外装に記載されたものをそのまま写しました。)
|
| |


CASTELLO 010
(1CD + 1DVD PAL)
\3000 →\2690 |
アレクサンダー・ガブリリュク ライヴ
ショパン(1810-1849):
ピアノ協奏曲第1番ホ短調
Op.11
ピアノ協奏曲第2番ヘ短調
Op.21
[アンコール]
モーツァルト(1756-1791):ロンド
ニ長調
K.485
リムスキー=コルサコフ(1844-1908):くまばちの飛行 |
アレクサンダー・ガブリリュク(ピアノ)
AUKSO管弦楽団
マレク・モシ(指揮) |
|
録音&録画:2010年7月2日、「たそがれのヴァヴェル城」音楽祭、ライヴ、ヴァヴェル城旧王宮、クラクフ、ポーランド
アレクサンダー・ガブリリュクは2000年、16歳の時に臨んだ浜松国際ピアノ・コンクールで優勝して以来日本でもおなじみのウクライナ出身のピアニスト。これはポーランドの古都クラクフのヴァヴェル城で開催される音楽祭のオープニング・コンサートに彼が出演した際に収録されたCD+DVD。
※PAL方式DVDの再生にはPAL対応プレーヤーが必要です。
|
| |

CASTELLO 016
(1CD + 1DVD PAL)
\3000 |
ヴァヴェル・ロイヤル・コレクション
ショパン(1810-1849):ピアノ三重奏曲ト短調
Op.8
ユリウシュ・ザレンプスキ(1854-1885):ピアノ五重奏曲ト短調
Op.34(*) |
ダニエル・スタブラヴァ(ヴァイオリン(*))
マリア・ゾフィア・スタブラヴァ(ヴァイオリン)
エヴァ・シュチェパンスカ=フファスト(ヴィオラ(*))
クシシュトフ・サドゥオフスキ(チェロ)
ピオトル・コシンスキ(ピアノ) |
|
録音&録画:2010年8月16-17日、オルシャの戦いの間、ヴァヴェル城旧王宮、クラクフ、ポーランド
ユリウシュ・ザレンプスキはポーランドのピアニスト・作曲家。ウィーンで学びピアニストとしてヨーロッパ各地で活躍、リストに作曲の才能を認められ指導を受けましたが、結核のため31歳の若さで亡くなりました。ピアノ五重奏曲は彼の代表作。ポーランドの古都クラクフのヴァヴェル城での収録。
※PAL方式DVDの再生にはPAL対応プレーヤーが必要です。
|
 CLASSICAL RECORDS CLASSICAL RECORDS
|
|
|
ラフマニノフ:悲歌 ピアノ作品集
ラフマニノフ(1873-1943):
悲歌 Op.3 No.2/前奏曲嬰ハ短調
Op.3 No.2
前奏曲変ロ長調 Op.23 No.2/前奏曲ト短調
Op.23 No.5
前奏曲ト長調 Op.32 No.5/前奏曲ロ短調
Op.32 No.10
チャイコフスキー(1840-1893)/ラフマニノフ編曲:子守歌
ラフマノノフ:
楽興の時 ロ短調 Op.16 No.3/絵画的練習曲変ホ短調
Op.39 No.5
ソナタ第2番ロ短調 Op.36(第2版) |
ユーリー・ディジェンコ(ピアノ) |
| ユーリー・ディジェンコは1966年ウクライナに生まれモスクワ音楽院でヴィクトル・メルジャーノフに師事したピアニスト。 |
| |
|
|
シューベルト、シューマン、リスト:ピアノ作品集
シューベルト(1797-1828):4つの即興曲
Op.90 D.899
第1番ハ短調,第2番変ホ長調,第3番変ト長調,第4番変イ長調
シューマン(1810-1856):
3つの幻想的小品 Op.111/ウィーンの謝肉祭の道化
Op.26
リスト(1811-1886):スペイン狂詩曲 |
カテリーナ・ザイツェヴァ(ピアノ) |
| カテリーナ・ザイツェヴァはロシに生まれアメリカ合衆国ノース・テキサス大学でホアキン・アチュカロに師事したピアニスト。 |
| |
|
|
ナジェージダ・ピサーレヴァ・プレイズ・シューマン ピアノ作品集
シューマン(1810-1856):
ソナタ嬰ヘ短調 Op.11/4つの小品
Op.32/3つの幻想的小品
Op.111 |
ナジェージダ・ピサーレヴァ(ピアノ) |
まあ、このルックスならとりあえず「注目」にしておかないとね。
ナジェージダ・ピサーレヴァ(ナージャ・ピサレヴァ)はモスクワに生まれ、モスクワ音楽院でセルゲイ・ドレンスキーに師事し2010年に卒業、さらにベルリン芸術大学でクラウス・ヘルヴィヒに師事したピアニスト。
父はピアニストのアンドレイ・ピサーレフ(1962年生まれ)。
2013年に来日。
 
|
 CORNETTO CORNETTO
|
|
|
王宮のリコーダー
アルカンジェロ・コレッリ(1653-1713):ソナタ
Op.5 No.9
ジョヴァンニ・バッティスタ・フォンターナ(?-1631):
ヴァイオリンまたは類似の楽器のためのソナタ集(1641)から
第2番
ジャック=マルタン・オトテール(1684-1763):
フラウト・トラヴェルソ、その他の楽器と通奏低音のための曲集第1巻
Op.2 から
組曲第4番
ゲオルク・フィリップ・テレマン(1681-1767):
無伴奏フルートのための12の幻想曲
から
第7番
ヨハン・ショップ(1590-1667):
「t'Uitnemend Kabinett」(1646-1649)から
涙のパヴァーヌ
ヤコプ・ファン・エイク(1590頃-1657):
「笛の楽園」(1644)から
Prins Robberts
Masco
シャルル・デュパール(1667-1740):6つのクラヴサン組曲
から 第2番
ゲオルク・フィリップ・テレマン:
「音楽の練習」(1739-1740)から
ソナタ
ニ短調 TWV41:d4 |
アストリッド・アンダーソン(リコーダー)
アン・レジェーン(ヴィオラ・ダ・ガンバ)
コーリー・ジェイマソン(チェンバロ)
リカルダ・ホルニヒ(テオルボ) |
|
録音:2013年6月18-20日、7月12日、福音教会、シュトゥットガルト=メンヒフェルト、ドイツ
アストリッド・アンダーソンはデンマークに生まれ1989年アメリカ合衆国に移住、インディアナ大学とジェイコブ音楽学校で学んだ後チューリヒ音楽大学(スイス)でマティアス・ヴァイレンマンに師事したリコーダー奏者。
|
| |
|
|
アレクサンダー・マリア・シュナーベル(1889-1969):ピアノ五重奏曲ハ長調
Op.17
ハリンリヒ・リーチュ(1860-1927):ピアノ五重奏曲ニ長調 |
マリンコニア=アンサンブル・シュトゥットガルト
ラミール・トルンペルマン(第1ヴァイオリン)
ユリウス・カルヴェッリ=アドルノ(第2ヴァイオリン)
マルクス・エルテル(ヴィオラ) ヘルムート・ショインヒェン(チェロ)
ギュンター・シュミット(ピアノ) |
|
録音:2013年、フィルハーモニー・グスタフ=ジーグレ=ハウス、シュトゥットガルト、ドイツ
ピアノと弦楽のための珍しい作品を紹介するマリンコニア・シリーズ第4弾。
アレクサンダー・マリア・シュナーベルはラトヴィアのリガに生まれた作曲家。音楽専業では生活できずポーランド、ドイツへと活動の場を移しましたが、1943年にブライトコプフ社のアーカイヴが戦災で焼失し彼の出版譜・手稿譜の多くが失われ、また5年をかけて作曲した交響曲の手稿譜を移動中に紛失したことで意欲を失い作曲と音楽著作をやめてしまった悲運の音楽家です。
ハリンリヒ・リーチュはボヘミア北西部のソコロフ(ファルケナウ)に生まれた作曲家・音楽学者。ウィーンで法学を学んだ後エドゥアルト・ハンスリック(1825-1904)、グイード・アドラー(1855-1941)に音楽史を、ローベルト・フックス(1847-1927)らに音楽理論を師事。ハンスリック、アドラーの後継者としてウィーン大学教授を務めた後プラハ音楽大学教授に就任、またプラハ・ドイツ室内楽教会を創設しました。
マリンコニア=アンサンブルは忘れ去られた楽曲の復興を目的としてチェロ奏者・音楽学者ヘルムート・ショインヒェンにより1980年代に創設されたアンサンブル。
|
| |
|
|
ブラジウス&ヴィリー・ペル:ワルツ、ポルカ&行進曲集
ブラジウス・ペル(1855-1919):
パッサウへのあいさつ(行進曲)(*)
パッサウの美しい山々で(ワルツ・パラフレーズ)(+)/パッサウ防衛行進曲
愛の思い(ガヴォット)(*)/第16連隊行進曲
バイエルンの森の音楽(ワルツ)(*)/パッサウへのあいさつ(行進曲)(**)
パッサウ防衛隊(行進曲)(#)
ヴィリー・ペル(1888-1971):
ハッケンザック行進曲(1952)/ファンファーレ第1番変ホ長調
アントレ=ファンファーレ第2番「カストラ・バターヴァ」
パッサウ・コンサート協会行進曲(1922)(*) |
シュタットカペレ・パッサウ(無印/+/**)
ゴットフリート・ヴェルフル(指揮(無印))
ゼップ・バルストルファー・ヴァルドラーカペレ(#)
ゼップ・バルストルファー(指揮(+/#/**))
パッサウ・コンサート協会管弦楽団(*)
マルクス・エーバーハルト(指揮(*)) |
|
録音:2013年9月12-14日、パッサウ市立音楽学校、パッサウ、ドイツ(無印)
2013年6月8日、フロイデンハイン城、パッサウ、ドイツ(*)
1966年(+)、1968年(#)、1969年(**)、バイエルン放送のアーカイヴから、モノラル(+/#/**)
ドイツ、バイエルンの都市パッサウのローカル音楽家二代の作品集。ブラジウス・ペルは軍楽隊長からパッサウ市の音楽監督に出世した人物。
息子ヴィリー(ヴィルヘルム)・ペルは父に倣って軍楽隊に所属した後パッサウ市立音楽学校教員に転職、1919年市のコンサート協会の創設者の一人となり、1945年まで代表を務めました。
1929年には「パッサウ市カペルマイスター」の称号を贈られています。(*)をのぞき吹奏楽による演奏。アルバム・タイトルにある「ポルカ」が収録楽曲に見当たらないのが謎です。
|
| |
|
|
ニコラウス・レーナウと音楽
ニコラウス・レーナウ(1802-1850):愛の祭(抜粋)
フリードリヒ・シュミット(1802-1873):葦の歌
第1(*)(#)
レーナウのシュヴァーベンの詩人サークルへの参加について
ニコラウス・レーナウ:ルムリンゲンの礼拝堂
フリードリヒ・シュミット(1802-1873):葦の歌
第3(*)(#)
シュヴァーベンの詩人サークルにおけるレーナウとレーナウの音楽活動について
ヨゼフィーネ・ラング(1815-1880):遥かな人に(*)
エミリー・ツムシュテーク(1796-1857):葦の歌
第2 Op.6 No.2(*)
ハイデルベルクにおけるレーナウとメンデルスゾーンとの最初の出会いについて
フリードリヒ・シュミット:静かな信頼(*)(#)
ハイデルベルクにおけるレーナウの音楽活動とアメリカへの旅について
ニコラウス・レーナウ(ベートーヴェンによる):アメリカ国民行進曲(+)(#)
レーナウの「ファウスト」について
リスト(1811-1886):メフィスト・ワルツ第1番(+)
レーナウのピアノ演奏について
ダニエル・シュレジンガー(1799-1839):アンダンテ・ヴァリエ
Op.8(+)(#)
レーナウのベートーヴェン崇拝について
ベートーヴェン(1770-1827):ピアノ・ソナタ第12番
Op.26 から 葬送行進曲(+)
レーナウのカール・エーファースとの交友について
カール・エーファース(1819-1876):願い(*)
レーナウのヨゼフ・デッサウアーとの交友について
ヨゼフ・デッサウアー(1798-1876):森で(*)(#)
レーナウのハンガリー崇拝とメンデルスゾーン、ヒラーとの出会いについて
フェルディナント・ヒラー(1811-1885):三人のジプシー(*) |
ミヒャエル・シュモール(バス(*))
マルグリット・エーム(ピアノ(*)、監修)
クリストフ・エーム=キューンレ(ピアノ(+))
ペーター・ベートゲ(朗読(無印)) |
|
録音:データ記載なし 制作:2013年
ハンガリー生まれのオーストリアの詩人でベートーヴェン崇拝者であったニコラウス・レーナウ(1802-1850)の生涯と音楽の関わりを綴るドキュメンタリー。(#)は初録音曲。
|
DIGRESSIONE
|
|
|
アントニオ・ジャコメッティ(1957-)/
ヴェロニカ・ヴィスマーラ(作詩):shakti,
la grande madre
Introduzione / Intuire la
sua presenza
/ Percepirla pienamente
Accettarne gli aspetti piu
fisici / Viverla
liberandosi dalle paure
Sentirne il potere creativo
/ Rapportarsi
con il maschile "interno"
Rapportarsi con il maschile
"esterno"
/ Gestire l'energia creatrice
interiore
Liberarsi e donare Luce /
Trascendere
ogni archetipo / Preprarsi al
distacco
Sperimentarne l'unita |
ヴェロニカ・ヴィスマーラ(声、ヴォーカル・ハーモニー)
ダニエラ・ゴッツィ(フルート)
ステファノ・ボルギ(クラリネット)
サンドロ・トッリアーニ(ソプラノサクソフォン、テナーサクソフォン)
ジョヴァンニ・ファルツォーネ(トランペット)
フランチェスコ・コンティ(ピアノ、キーボード)
アントニオ・ジェコメッティ(打楽器)
フランチェスカ・ティラーレ(ハープ)
シモーネ・モール(エレクトリックギター、シタール)
エヴァ・フェウド・シュー(チェロ)
ロレンツォ・ピエロボン(ヴァオーカル・ハーモニー、ディジェリドゥー) |
| 録音:2010年9月-2011年2月、フレクエンツェ・スタジオ、モンツァ、イタリア |
| |
|
|
ユリシーズ−到着、横断、出発の地
フランチェスコ・トラヴェルシ:
Amor mi fa sovente(テューバ、声と管弦楽のための)(*)
フランチェスコ・アントニオーニ:Soror(フルートと弦楽六重奏のための)(+)
ヴィート・パルンボ:Hoquetus(トロンボーンのための)(#)
ブルーノ・モレッティ:Kadir(テューバと管弦楽のための)(**) |
ドメニコ・ジッジ(テューバ(*/**))
ミケーレ・ロムート(トロンボーン(#))
サルヴァトーレ・ヴェッラ(フルート(+))
パオラ・アルネザーノ(声(*))
アンサンブル'05(#以外) |
録音:2011年9月1日、インターナショナル・サウンド・スタジオ、コンヴェルサーノ、バーリ県、イタリア(*/**)
2011年8月8日(+)、29日(#)、P・グラッシ劇場、チステルニーノ、ブリンディジ県、イタリア(+/#) |
DISCMEDI
|
|
|
ベル・カント
マリオラ・カンタレロ&シモン・オルフィラ オペラ・アリア&デュエット集
モーツァルト(1756-1791):「ドン・ジョヴァンニ」から
Crudele!... Non mi dir
(*) / Madamina,
il catalogo e questo (+)
La ci darem la mano (*/+)
ロッシーニ(1792-1868):
「セミラーミデ」から Bel
raggio lusinghier
(*)
「セビリャの理髪師」から
La calunnia
(+)
「セミラーミデ」から Se la
vita ancor...
(*/+)
ドニゼッティ(1797-1848):
「ルクレツィア・ボルジア」から
Vieni
la mia vendetta (+)
「アンア・ボレーナ」から
Piangete voi...
Al dolce guidami (*)
「ルクレツィア・ボルジア」から
Soli noi
siamo (*/+)
「愛の妙薬」から Quanto amore
(*/+) |
マリオラ・カンタレロ(ソプラノ(*))
シモン・オルフィラ(バスバリトン(+))
ガリシア王立フィルハーモニー管弦楽団
オルベル・ディアス(指揮) |
|
録音:データ記載なし
年齢も近いスペインの実力派歌手マリオラ・カンタレロ(1978年グラナダ生まれ)とシモン・オルフィラ(1976年メノルカ島生まれ)による熱気溢れるベルカント・アルバム。
|

DISCOS ABADIA DE MONTSERRAT
|
スペイン・カタルーニャ、バルセロナ近郊の聖地モンセラト修道院の自主レーベル。
オルガンとヴァイオリンによるキリストの「生誕」と「復活」をテーマとしたアルバム。
演奏しているのは実際の修道女と修道士。
まだ手元に届いていないのだが、人生を変えるとしたらこういうアルバムだと思う。
手に入りにくく、しかもいつまで入手できるか微妙なアイテムなので、どうかどうかお早めに。
.
ここで DAM 5019 の一部が聴けます・・・
. |
|
|
オルガンとヴァイオリンが奏でるメロディー(Vol.1)
ジョー・アケプシマス(1940-):暁の光よ
ルター派の賛美歌:
われらすべてを救いに来たもう御身(エアフルト賛美歌集(1524)から)
ルシアン・デス(1921-2007):もうすぐ夜が明ける
伝承曲:来たれ、神聖なる救世主よ
J・S・バッハ(1685-1750):主の栄光を称えよ
ジョゼフ・ジェリノー(1920-2008):さあ来たれ、世の救い主よ
ジョー・アケプシマス:救い主を求めるあなたがた
グレゴリオ聖歌(タミエ修道院):待降節の賛歌
グレゴリオ聖歌:クリスマスの賛歌
ディディエ・リモー(1922-2003):今日、この世に
ジュゼプ・マリア・ビンセン:天の喜び
不詳(16世紀):声のかぎり神に歌わん
ジョン・フランシス・ウェード(1710-1786):神の御子は今宵しも
フランツ・グルーバー(1787-1863):きよしこの夜
ルシアン・デス:天の御子
ジョー・アケプシマス:神よ、人の生の源よ
ポール=ジャン=ジャック・ラコーム(1838-1920):貧者たちの夜
アダン(1803-1856):オー・ホーリー・ナイト
ジョー・アケプシマス:あなたはどなたか、謙遜なる王よ
ヴェロニカ・ヨン:愛のシスター |
ヴェロニカ・ヨン(ヴァイオリン)
ジョルディ・アウグスティ・ピケ(オルガン) |
|
録音:2010年10月25-27日、モンセラト修道院バジリカ聖堂、モンセラト、スペイン
タイトルにはうたわれていませんが、キリストの生誕をテーマとしたアルバムです。時季外れのご案内になってしまい申し訳ありませんが、モンセラトの清澄な空気を感じさせるサウンドは季節を問いません。
ヴェロニカ・ヨンは韓国のオーケストラで活躍後、1986年に修道女となったヴァイオリン奏者。
ジョルディ・アウグスティ・ピケはモンセラト修道院修道士でオルガン奏者・音楽学者。1997年から2001年までエスコラニア(モンセラト修道院少年聖歌隊)の楽長を務め、その後数々の著作を発表しています。
ディスクには配給元である DISCMEDIの規格品番「DM
4894-02」が表示され、両規格品番が併記されている外装でもそちらのほうが目立つのですが、弊社では「DAM
5019」として管理いたします。(代理店)
|
| |


DAM 5021
\3200→\2990 |
オルガンとヴァイオリンが奏でるメロディー(Vol.2)
プロヴァンスのクリスマス・キャロル/R・ジェフ編曲:ああ、眠っているあなた
ジャック・ベルティエ(1923-1994):逃れるなかれ/御身の暁を輝かせよ
ジョー・アケプシマス(1940-):イエスよ、御身はわが心を燃やした
不詳:キリストはまことに復活せり
オデット・ヴェルクリュイス(1925-2000):アレルヤ!
ドイツ伝承曲/ルイ・リエバール(1908-2010):地上に夜明けが訪れれば
ルシアン・デス(1921-2007):愛の精神
ジョー・アケプシマス:彼が友らに言った時
ルシアン・デス:神の御心
J・エレラ/ジャン=ポール・レコ編曲:生けるキリスト
ジャック・ベルティエ:われらは御身に歌う、復活せしキリストよ
ジョゼフ・ジェリノー(1920-2008):汝の心を開け
不詳:新たな一日が明ける(賛美歌集「ダヴィデの竪琴」(1708)から)
ルシアン・デス:神は統べる
グレゴリオ聖歌:過ぎ越しのいけにえを称えよ
ルシアン・デス:アレルヤ、この日こそ
グレゴリオ聖歌:サルヴェ・レジナ |
ヴェロニカ・ヨン(ヴァイオリン)
ジョルディ・アウグスティ・ピケ(オルガン) |
|
録音:2011年11月13-15日、モンセラト修道院バジリカ聖堂、モンセラト、スペイン
こちらもタイトルにはうたわれていませんが、キリストの復活をテーマとしたアルバムです。
|
GZ DIGITAL MEDIA
|
|
|
バールタ降臨!
シューベルト(1797-1828):ピアノ・ソナタ第4番イ短調
Op.164 D.537
フンメル(1778-1837):チェロ・ソナタ
イ長調
Op.104(*)
録音:データ記載なし |
イジー・バールタ(チェロ(*))
ノルベルト・ヘレル(ピアノ)
|
スプラフォンやハイペリオンへの録音でおなじみのチェコのチェロ奏者イジー・バールタがGZレーベルに登場。
ノルベルト・ヘレルはガブリエラ・デメテロヴァーとのデュオで当レーベルに録音したモーツァルトのヴァイオリン・ソナタ集(L
10639-2)で知名度を上げたチェコのピアニスト。モダーン楽器使用。 |
HEVHETIA
|
|
|
あふれるクリスタル ツィンバロムのための現代音楽
ヴラジミール・ボケス(1946-):
エニケーのチャールダーシュ
[Csardas EnikQnek]
(2004)
イシュトヴァーン・ラーング(1933-):
コンチェル・ドゥオタンテ
[Concer duotante](2010)(*)
テオ・ブラントミュラー(1948-2012):
5つの夜の絵 [Bilder der
Nacht] (2004/2005)
ハンス・ヨアヒム・ヘスポス(1938-):サントゥール
[Santur] (1972)
ルイージ・マンフリン(1961-):
あふれるクリスタル II [Overflowing
Crystals
II] (2009)(*)
ユライ・ハトリーク(1941-):エニケーのために
[Fur EnikQ] (2009-2011)
瞳の涙/難しい決断/穏やかな光/ヘッセへのオマージュ |
エニケー・ギンゼリ(ツィンバロム)
アンドラーシュ・フェイェール(トロンボーン(*)) |
|
録音:データ記載なし
ハンガリーを中心とする地域の民族楽器ツィンバロムのために書かれた作品集。ボケスとハトリークはスロヴァキア、ラーングはハンガリー、ブラントミュラーとヘスポスじゃドイツ、マンフリンはイタリアの作曲家。
エニケー・ギンゼリはスロヴァキアの首都ブラチスラヴァで生まれ(たぶんハンガリー系)、ブラチスラヴァ音楽院、フランツ・リスト音楽院(ブダペスト、ハンガリー)で学んだ後、ザール音楽大学(ザールブリュッケン、ドイツ)を2005年に卒業したツィンバロム奏者(女性)。中世から現代に至る幅広いレパートリーを持つヴィルトゥオーゾであり、特にソロおよび他の楽器とのアンサンブルに精力的に取り組む彼女は多くの作曲家を触発し、数々の新作を捧げられています。
|
HUDOBNE CENTRUM(MUSIC CENTER
SLOVAKIA)
|
|
|
ミラン・パリャ ヴァイオリン/ヴィオラと管弦楽のための音楽
ユライ・ベネシュ(1940-2004):
冬の音楽 [Musica d'inverno]
(ヴァイオリンと管弦楽のための;1992)(*)
エフゲニー・イルシャイ(1951-):アシラの歌
[Ashira Songs](*)
フランチシェク・グレゴル・エンメルト(1940-):
ヤコブの戦い [Jacob's Fight]
(ヴィオラと室内弦楽合奏のための;2009)(+)
アリフレト・シュニトケ(1934-1998):
モノローグ [Monologue] (ヴィオラと室内管弦楽のための;1989)(+) |
ミラン・パリャ(ヴァイオリン(*)、ヴィオラ(+))
チェコ・ヴィルトゥオージ
オンドレイ・オロス(指揮) |
|
録音:2009年10月18日、11月28日、スタディオン・ブルノ、ブルノ、チェコ 発売:2010年
現代音楽を得意とするスロヴァキアのヴァイオン&ヴィオラ奏者ミラン・パリャ(1982年生まれ)と同じくスロヴァキアの指揮者オンドレイ・オロス(1983年生まれ)がチェコのオーケストラと共演。ベネシュはスロヴァキア、イルシャイはロシア生まれのスロヴァキア、エンメルトはチェコの作曲家。
|
| |
|
|
セルゲイ・コプチャーク
最後の言葉 バスと器楽アンサンブルのための現代スロヴァキア音楽
イリヤ・ゼリェンカ(1932-2007):
3つの言葉(バス、ボンゴ、フルート、マリンバとチェロのための;2006)
ミロ・バーズリク(1931-):コラールによるカノン変奏曲
(弦楽四重奏曲、バスバリトンとチェンバロのための;2011)
ヴラジミール・ボケス(1946-):出発
Op.85
(S・D・シムコの詩によるバスと室内アンサンブルのための6つの歌;2011)
テーブルの上に残されたノート/出発/冬の音楽
ゲオルク・トラクルへのオマージュ/一月/証言
ロマン・ベルゲル(1930-):テネブレ(バスと室内アンサンブルのための;2011) |
セルゲイ・コプチャーク(バス)
クアサルス・アンサンブル
イヴァン・ブッファ(指揮) |
|
録音:2012年3月1-3日、4月28日、スロヴァキア放送小コンサートホール、ブラチスラヴァ、スロヴァキア
発売:2012年
イリヤ・ゼリェンカが2006年に書いた歌曲「3つの言葉」とは「}ivot
pomaly kon ci / Life slowly ends
/ 人生は
ゆるやかに 終わる」の3語のこと。ゼリェンカはこの作品を親友であるスロヴァキアの名バス歌手セルゲイ・コプチャーク(1948年生まれ)に献呈しましたが、その初演を待たず翌2007年に亡くなりました。
2008年にオペラのステージから引退した後も親友の遺言のようなこの作品をずっと気にかけていたコプチャークは、2011年のメロス=エトス音楽祭のプロジェクトにおいて歌うことを決意。「3つの言葉」と同様にバスと器楽アンサンブルのためにスロヴァキアの現役作曲家が書いた新作とともに録音しました。
|
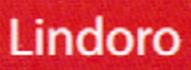 LINDORO LINDORO
|
|
|
Raclerie Universelle 17世紀フランスのギター音楽
フランチェスコ・コルベッタ(1615-1681):組曲イ短調
前奏曲,アルマンド,クラント,サラバンド,ジグ,パサカーユ
アンリ・グルネラン(1625-1700):組曲ニ短調
前奏曲,アルマンド,クラント,サラバンド,ジグ,パサカーユ
フランソワ・ル・コック(確認できる活躍期:1685-1729):シャコンヌ
不詳:ニ調の小品集
Mariez Moy,La Vielle,La
Bonita,L'Otonera,La
Forlane
ロベール・ド・ヴィゼ(1650頃-1732頃):
組曲ト長調; 前奏曲,アルマンド,クラント,サラバンド,ジグ
アポロンの入場(アルマンド)/「ロラン」のロジスティーユ
マスカラード/ヴィラネル/パサカーユ
フランチェスコ・コルベッタ:ラ・ストゥアルダ(サラバンド)/アルマンド |
イスラエル・ゴラーニ(バロックギター) |
|
録音:2012年3月14-17日、プロテスタント教会、テルカプレ、オランダ
17世紀後半のフランスで隆盛を極めたバロックギターのための音楽で構成されたアルバム。タイトルは「普遍的な掻き鳴らし」や「掻き鳴らされる音の世界」と訳せばよいのでしょうか。
イスラエル・ゴラーニはテルアヴィヴ大学で音楽学を修めた後、フレッド・ヤーコプス(アムステルダムのスウェーリンク音楽院)とエリザベス・ケニー(ロンドンの王立音楽アカデミー)にリュートとテオルボを師事。数多くのアンサンブル、オーケストラ、プロジェクトに参加しながらバロックギターも習得し、2010年のユトレヒト古楽祭でバロックギター奏者としてソロ・デビューしました。
|
| |
|
|
16世紀グラナダの楽師たち
[I. 宗教的領域]
フアン・デ・ウレデ(確認できる活躍期:1451-1482頃没):
Pange lingua (5声), Quinta
Boz (Baso).
Morales (*)
フランシスコ・ゲレロ(1528-1599):O
Maria
(4声)
クリストバル・デ・モラレス(1500頃-1553):Veni
Domine (4声)
フランシスコ・ゲレロ:Ave Maria
(4声)
クリストバル・デ・モラレス:Inter
vestibulum
(4声)
フランシスコ・ゲレロ:Dixit
Dominus Petro
(5声) / Benedictus (4声)
ロドリゴ・デ・セバリョス(1525/1530頃-1581):Agnus
Dei (5声) (*)
[II. 大学]
フランシスコ・ゲレロ:Christe
potens rerum
(5声) (*)
ペドロ・ゲレロ(1520頃-?):O
beata Maria
(4声)
ジョスカン・デプレ(1450/55頃-1521):
Lauda Sion [Je ne me puis
tenir d'aimer]
(5声)
ペドロ・ゲレロ:Quinque prudentes
virgines
(4声)
オルランドゥス・ラッスス(1532-1594):O
invidia, nemica di virtute (5声)
ピエール・サンドラン(1490頃-1560以後):Doulce
memoire (4声)
トマ・クレキヨン(1505/1515頃-1557):Prenez
pitie
フランシスコ・ゲレロ:O quam
super terram
(5声) (*)
[III. 家庭的な場]
ニコラ・ゴンベール(1495頃-1560頃):J'ay
conge prins (4声)
フランシスコ・ゲレロ:Mi ofensa
es grande
(5声)
ジャック・アルカデルト(1507頃-1565):Il
ciel che rado (4声)
フィリップ・ヴェルドロ(1480/1485頃-1530/1532頃、1552以前):
Madonna no so dir tante parole
(5声)
不詳:S'io fusse certo di levar
per morte
(4声) (*)
オルランドゥス・ラッスス:Susanne
ung jour
(5声)
トマ・クレキヨン:Pane me ami
duche
[IV. 都市の道路や広場で]
フランシスコ・ゲレロ:Todos
aman (5声)
/ Si el mirar (5声)
フィリップ・ド・マンシクール(1510頃-1564):Yo
te quiere matare (4声) (*)
トマ・クレキヨン:Pour ung
plaisir (4声)
クレメンス・ノン・パパ(1510/1515頃-1555/1556頃):
Ne scauroit on trouver bon
messaigier
de France (4声) (*)
フランシスコ・ゲレロ:No me
podre quexar
(5声)
ループス・ヘリンク(1494頃-1541):Ung
jeune moine (4声) (*)
フランシスコ・ゲレロ:Subiendo
amor (5声)
/ Adios mi amor (5声)
アンサンブル・ラ・ダンスリー
フェルナンド・ペレス・バレラ(コルネット[ツィンク]、コルネタ・ムダ、サックバット、
チリミア・テノル、クルムホルン、リコーダー)
フアン・アルベルト・ペレス・バレラ(コルネット[ツィンク]、コルネタ・ムダ、チリミア、
バホンシリョ、クルムホルン、リコーダー)
ルイス・アルフォンソ・ペレス・バレラ(サックバット、クルムホルン、リコーダー)
エドゥアルド・ペレス・バレラ
(バホン[ドゥルツィアン]、バホンシリョ、チリミア、クルムホルン、リコーダー)
マヌエル・ケサダ・ベニテス(サックバット) ホセ・メンデス・ガルバン(リコーダー)
|
|
録音:2012年12月16-20日、サクロモンテ修道院教会、グラナダ、スペイン
グラナダのマヌエル・デ・ファリャ図書館の写本975番所収の楽曲(*)を中心に、16世紀のグラナダで活躍した楽師たち(管楽合奏団)のレパートリーを取り上げたアルバム。タイトルの「Yo
Te Quiere Matare」(マンシクールの収録曲名)を直訳すると「私はあなたを殺してしまいたい」になりますが、殺伐とした音楽は一つもありませんのでご安心ください。
ラ・ダンスリーは1998年に創設されたスペインのピリオド管楽器アンサンブル。
|
| |
|
|
バロック音楽に反映されたラテンアメリカの音楽
アントニオ・ベルターリ(1605-1669):シャコンヌ
ハ長調
ホセ・マリン(1618-1699):声とギターのための51のトノ
から
乙女よ、あなたの移り気に
[Nina, como
en tus mudanzas]
不詳(17世紀):
修道士グレゴリオ・デ・スオラの写本
から
マリサパロス [Marizapalos]
ヤコプ・ヘルマン・クライン(1688-1748):
チェロと通奏低音のための6つのソナタ
Op.4 から ソナタ イ短調
不詳(17世紀):ペルーのトルヒリョの写本(マルティネス・コンパニョン写本)から
ランチャス・パラ・バイラル
[Lanchas
para Baylar]
ラ・セロサ [Tonada La Selosa]
(ランバイエケの村のトナダ)
エル・コンゴ [El Congo]
(歌踊りのトナダ)
アントニオ・ヴァレンテ(1530-1585)−不詳:
ナポリのガイヤルド−トルベリーノ−いかれたハラベ
[Jarabe Loco] |
ロス・テンペラメントス
スワンティー・タムス・フライアー(ソプラノ、リコーダー)
アンニカ・フォーグルプ(リコーダー)
ウゴ・ミゲル・デ・ロダス・サンチェス(バロックギター)
ネストル・ファビアン・コルテス・ガルソン(バロックチェロ)
ナディーネ・レンメルト(チェンバロ) |
|
録音:2013年11月20-23日、聖コスマス&ダミアン教会、ルンゼン、ドイツ
スペイン、およびスペイン領だったことのあるオランダと南イタリアからヨーロッパに流入した中南米の音楽をテーマとするアルバム。ホセ・マリンはスペイン、アントニオ・ベルターリとアントニオ・ヴァレンテはイタリア、ヤコプ・ヘルマン・クラインはオランダの作曲家。
中南米起源とされるシャコンヌに始まりメキシコの民俗舞曲ハラベで閉じられる絶妙なプログラムです。
タイトルの「De la Conquista
y otros Demonios」を直訳すると「征服の悪魔と他の悪魔」になりそうですが、あまり考えずに楽しむほうが良さそうです(最近の当レーベルはアルバム・タイトルに凝り過ぎ?)。
ロス・テンペラメントスはドイツのブレーメン芸術大学古楽アカデミー卒業生により2009年に結成されたアンサンブル。
|
| |
|
|
ガエターノ・ブルネッティ(1744-1798):
弦楽三重奏のためのディヴェルティメント
第4集(1784)
第1番イ長調 (L.145)/第2番変ロ長調
(L.146)/第3番ハ短調 (L.147)
第4番ハ長調 (L.148)/第5番変ホ長調
(L.149) |
カルメン・ベネリス
ラウル・オレリャナ(ヴァイオリン)
パブロ・アルマサン(ヴィオラ)
ギリェルモ・マルティン(チェロ) |
|
録音:時期の記載なし、闘牛博物館図書室、ロンダ、マラガ県、スペイン
ガエターノ・ブルネッティはイタリアのファーノに生まれ、ピエトロ・ナルディーニに師事した後1762年頃スペインのマドリードに移住。1770年に国王カルロス3世の王太子(アストゥリアス公)付き音楽教師に就任。1788年、王太子がカルロス4世として即位するとともに王の私設楽団のヴァイオリニストとなり、さらに1795年に王宮楽団が創設されるにあたってその指揮者に就任しました。450を超える作品を残したとされていますが、生前・没後とも出版された作品は少なく、演奏・録音される機会も多くありません。
当盤は好評を博した「弦楽四重奏曲集」(NL
3011)に続くカルメン・ベネリスによるブルネッティ第2弾。
カルメン・ベネリスは2005年に創設されたスペインのピリオド楽器アンサンブル。ヴィオラのパブロ・アルマサン(・ハエン)とチェロのギリェルモ・マルティン(・ガミス)を核として演奏曲目ごとにメンバーを補強する形をとっています。
今回参加のラウル・オレリャナは南米チリ出身、ミラノ市立音楽院古楽科でエンリコ・ガッティに師事したヴァイオリン奏者。音楽、演奏ともにすばらしく、同時代のイタリア人で同様にマドリードで活躍したボッケリーニも真っ青といったところ。
実際にブルネッティの再評価を進めてくれそうな一枚です。
その「弦楽四重奏曲集」 |
|
|
ガエターノ・ブルネッティ(1744-1798):弦楽四重奏曲集
イ短調 Op.2 No.4 (L.153)/ト長調
Op.3
No.6 (L.161)
変ロ長調 Serie 8 No.7
(L.196)/ニ長調
Serie 8 No.10 (L.199) |
カルメン・ベネリス
ミゲル・ロメロ・クレスポ、
ラファエル・ムニョス=トレロ・サントス(ヴァイオリン)
パブロ・アルマサン・ハエン(ヴィオラ) ギリェルモ・マルティン・ガミス(チェロ) |
| 録音:時期の記載なし、聖復活病院内行事サロン、ウトレラ、セビリャ県、スペイン |
|
| |


MPC 0709
\2400 →\2190
【旧譜 再入荷】 |
キアラ・バンキーニ(ヴァイオリン)
ジャン=フィリップ・ラモー(1685-1767):
クラヴサン合奏曲集(クラヴサン・アン・コンセール) |
キアラ・バンキーニ(ヴァイオリン)
マリアンネ・ミュラー(ヴィオラ・ダ・ガンバ)
フランソワーズ・ランジュレ(チェンバロ) |
|
録音:1999年11月、ヌーシャテル芸術歴史博物館、フランス
使用楽器:1632年、ヨハネス・ルッカース製(チェンバロ)
女性ピリオド楽器奏者のトリオによる当レーベルのベストセラー盤が再生産されました。
|
 MAP MAP
|


MAPCL 10004
\2500 →\2290
(CD-R) |
ヨハン・ダーヴィト・ハイニヒェン(1683-1729):未出版のドレスデン・ソナタ集
2つのオーボエと通奏低音のためのトリオ・ソナタ変ロ長調
2つのオーボエと通奏低音のためのトリオ・ソナタ
ト長調
2つのオーボエ、ファゴットと通奏低音のためのトリオ・ソナタ変ロ長調
オーボエと通奏低音のためのソナタ
ト短調(*)
2つのオーボエと通奏低音のためのトリオ・ソナタ
ヘ長調
ファゴットと通奏低音のためのソナタ
ニ長調
2つのオーボエと通奏低音のためのトリオ・ソナタ
ハ短調 |
アンサンブル・サン・スーシ
ジュゼッペ・ナリン(オーボエ、リーダー)
ニコロ・ノッティ(オーボエ)
パオロ・トニョン(ファゴット)
ファビアーノ・メルランテ(テオルボ、アートリュート、バロックギター)
マッシミリアーノ・ヴァルージオ(チェロ、ヴィオラ・ダ・ガンバ)
ミケーレ・ガッロ(コントラバス)
マルコ・ヴィンチェンツィ(チェンバロ) |
|
録音:2013年7月22-24日、ベルトルディ別邸、セッティモ、ペスカンティーナ、ヴェローナ県、イタリア
ヨハン・ダーヴィト・ハイニヒェンはドイツ、ザクセン地方ヴァイセンフェルス近郊に生まれた作曲家・音楽理論家。ライプツィヒのトーマス学校でヨハン・クーナウ(1660-1722)にチェンバロとオルガンを師事、後に師の助手となりました。
ライプツィヒ大学では法学を修め卒業後ヴァイセンフェルスで弁護士として活躍しましたが、周囲に楽才を注目され音楽家の道を歩み始めました。1710年、イタリア・オペラを学ぶためヴェネツィアに渡り、ヴィヴァルディらと交友。1717年帰国しドレスデンのザクセン選帝侯宮廷楽長に就任し生涯務めました。
当時の名声と活躍ぶりに反してなぜか後世では忘れられていましたが、近年教会声楽作品からリバイバル・ムードが高まり、その独創的で優れた音楽が再評価されつつあります。
イタリアのピリオド管楽器と通奏低音の名手たちが取り上げた当盤収録曲は(*)を除き世界初録音。CD-Rであるのは残念ですが、古楽ファンなら見逃せない一枚と言えるでしょう。
|
| |


MAPCL 10002
\2500 →\2290
(CD-R) |
ああ、わが恋人たちよ 田舎者とヴィラネッラ−不躾なアモール
ジローラモ・デル・モンテサルド(16-17世紀):
Folia chiamata cosi da spagnuoli
[フォリア「スペイン人」]
〔タブラチュアによる新インヴェンション(1606、フィレンツェ)〕(*)
ティベーリオ・ファブリアネーゼ(16世紀):La
canzon della gallina [雌鶏の歌]
〔ナポリ風の3声のカンツォーネ・ヴィッラネスカ集第1巻(1550、ヴェネツィア)〕
ドメニコ・マリア・フェッラボスコ(1513-1574):Io
mi son giovinetta [私は若い娘]
〔優れた作者たちによる4声のマドリガーレ集第1巻(1542、ヴェネツィア〕
レオナルド・プリマヴェーラ(1540頃-1585):
Mamma nu grosso pollice /
Dormendo mi
sonniava
〔3声のカンツォーネ・ナポリターナ集第1巻(1570、ヴェネツィア)〕
不詳:パッサメッツォ・アンティコ(*)
バルダッサーレ・ドナート(1530頃-1603):Chi
la gagliarda
〔ナポリ風の3声のカンツォーネ・ヴィッラネスカ集第1巻(1550、ヴェネツィア)〕
レオナルド・プリマヴェーラ:
Tre donne belle fanno gran
battaglia
[三人の美女が起こす大戦争]
〔3声のカンツォーネ・ナポリターナ集第1巻(1570、ヴェネツィア)〕
ジャコモ・ゴルザニス(1525頃-1578頃):
Sta vecchia canaruta / Guerra
non ho
da far / Duca vi voglio dir
〔リュートのためのナポリ風アリア集第1巻(1570、ヴェネツィア)〕
ディエゴ・オルティス(1525頃-1570以後〕:レセルカダ第1番〔変奏論(1553、ローマ)〕
ディンチェルト(16世紀):Bon
cacciator
gia mai
〔冠−3声および4声のナポリターナ集(1572、ヴェネツィア)〕
不詳:Cossi esstrema e la doglia
〔聖マルコ図書館の写本(16世紀)〕
ベルンハルト・シュミット(1535-1592):
Io mi son giovinetta [私は若い娘]
(タブラチュアによる器楽版)
〔Zwey Bucher einer neuen
kunstlichen
Tabulatur auff Orgel und Instrumenten
(1577、ストラスブール〕
ミヒャエル・プレトリウス(1571-1621):
Ballet des coqs [雄鶏] 〔テルプシコーレ(1612、ヴォルフェンビュッテル〕
コージモ・ボッテガーリ(1554-1620):
Sola soletta me ne vo [たった一人で私は行く]
〔Arie e Canzoni in musica
di C. B.,
ms(16世紀終盤)〕
ジローラモ・コンヴェルシ(16世紀):
Sola soletta [たった一人で]
〔5声のカンツォーネ集第1巻(1573、ヴェネツィア〕
アントニオ・スカンデッロ(1517-1580):S'io
canto e tu mi spacci per cicala
〔カンツォーネ・ナポリターナ集第2巻(1577、モナコ)〕
ディエゴ・オルティス:レセルカダ第2番
〔変奏論(1553、ローマ)〕
不詳:4つのガリアルダ; Gonella
/ Fantina
/ Comadrina / Fornerina
〔タブラチュアによる様々な種類のバッロ集(1551、ヴェネツヴィア)〕
ジャン・ドメニコ・デル・ジョヴァーネ(1510頃-1592):Si
ben voltasse
〔3声のカンツォーネ・ナポリターナ集第2巻(1566、ヴェネツィア)〕
ヤコプ・ファン・エイク(1590頃-1657):
Boffons [道化師] (パッサメッツォ・モデルノによる変奏曲)
〔笛の楽園(1649-1655頃、アムステルダム〕
ジャン・ドメニコ・デル・ジョヴァーネ:Fontana
che dai acqua [川のほとりの泉]
〔3声のカンツォーネ・ヴィッラネスカ集(1545、ヴェネツィア)〕
ディンチェルト:ヴィラネッラ・ヴィラネッラ
〔3声のカンツォーネ・ナポリターナ集第1巻(1566、ヴェネツィア)〕
バルダッサーレ・ドナート:No
pulice m'entrato
〔ナポリ風の3声のカンツォーネ・ヴィッラネスカ集第1巻(1550、ヴェネツィア)〕
ルッツァスコ・ルッツァスキ(1545頃-1607):I
mi son giovinetta [私は若い娘]
〔優れた作者たちによる4声のマドリガーレ集第1巻(1542、ヴェネツィア〕
アントニオ・スカンデッロ:
Haveva na ga 〔カンツォーネ・ナポリターナ集第1巻(1564、ニュルンベルク)〕
不詳:Ciaccona [シャコンヌ](*) |
シャリヴァリ・アンサンブル
クリスティーナ・クルティ、
シルヴィア・テストーニ(ソプラノ)
レオナルド・コルテラッツィ(テノール)
エマヌエーラ・デ・クレティコ(リコーダー、サックバット)
ダニエーレ・サルヴァトーレ(リコーダー、サックバット、打楽器、三穴笛&太鼓)
ダンテ・ベルナルディ(ドゥルツィアン、サックバット、ボンバルダ、フリスカレットゥ)
ローザ・ディ・イリオ(ボンバルダ)
マルコ・デル・ビアンコ(ヴィオラ・ダ・ガンバ)
ステファノ・ロッコ(リュート、ギター)
エレーナ・ダラ・カーザ(チェンバロ)
ダニエーレ・サルヴァトーレ(指揮) |
|
録音:2009年4月1-4日、ロンコフレッド、フォルリ=チェゼーナ県、エミリア=ロマーニャ州、イタリア
16世紀中盤から17世紀初めにかけての、主にイタリア音楽における粗野な面に光を当てた企画。無名作曲家たちの楽曲が次々に登場します。
シャリヴァリ・アンサンブルは中世・ルネサンス・バロック器楽の研究と実演を目的として1984年に創設されたイタリアのピリオド楽器アンサンブル。〔カッコ内〕は収録曲の出典。(*)ではダニエーレ・サルヴァトーレによるリダクション版を使用。
|
MISTERIA PASCHALIA
|
ポーランドの古都クラクフにおいて毎年カトリックの聖週間〜復活祭の時期に開催される音楽祭「ミステリア・パスカリア」の自主レーベル。
ファビオ・ビオンディ指揮による2つの演目のライヴ録音が発売されています。
在庫限りです。 |


MPC 001
〔旧譜〕
\2500 →\2290
【在庫数:12】 |
ジャン・フランチェスコ・デ・マーヨ(1732-1770):
オラトリオ「重き十字架を背負いしイエス」(1764) |
ロベルタ・インヴェルニッツィ(ソプラノ:マリア)
ルチア・チリッロ(アルト:マグダレーナ)
カルロ・アッレマーノ(テノール:ヨハネ)
エウローパ・ガランテ
ファビオ・ビオンディ(指揮) |
|
録音:ライヴ、2006年4月14日、カロル・シマノフスキ・ホール、クラクフ、ポーランド
ジャン・フランチェスコ・デ・マーヨは作曲家ジュゼッペ・ディ・マーヨ(1697-1771)の息子としてナポリに生まれたイタリアの作曲家。38歳の若さで病死しましたが、20を超えるオペラ、多数のオラトリオ、カンタータ、ミサ曲等を残しました。「重き十字架を背負いしイエス」はキリストの受難を聖母マリア、マグダラのマリア、使徒(福音記者)ヨハネの視点で綴ったオラトリオ。解説書はポーランド語表記のみ。歌詞の記載はございません。
|
| |


MPC 002
〔旧譜〕
\2500 →\2290
【在庫数:8】 |
アレッサンドロ・スカルラッティ(1660-1725):
聖なるお告げのためのオラトリオ
(最も神聖なる受胎告知のためのオラトリオ)(1700-1703) |
ロベルタ・インヴェルニッツィ(ソプラノ:処女マリア)
エマヌエーラ・ガッリ(アルト:天使)
マルタ・アルマハノ(ソプラノ:無垢の心)
マリーナ・デ・リーゾ(アルト:謙遜の心)
マグヌス・スターヴェランド(テノール:不信の心)
エウローパ・ガランテ
ファビオ・ビオンディ(指揮) |
|
録音:ライヴ、2007年4月7日、カロル・シマノフスキ・ホール、クラクフ、ポーランド
解説書はポーランド語表記のみ。歌詞の記載はございません。
|
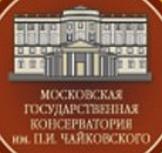 モスクワ音楽院 モスクワ音楽院
|
|
|
アリーサ・ギツバ(ソプラノ)/チャイコフスキー、ラフマニノフ:歌曲集
チャイコフスキー(1840-1893):
待て! Op.16 No.2
フランスの詩による6つの歌
Op.65
セレナード「あなたはどこへ行くのか」,失望,
セレナード「曙の明るい光の中で」,冬が来ても,涙,魅惑の女
セレナード Op.63 No.6
ラフマニノフ(1873-1943):
6つの歌 Op.38
夜ふけに私の庭で,彼女に,ひなぎく,ねずみ捕り,夢,おーい!
夕暮れ Op.21 No.3/立ち去ろう、愛しい人よ
Op.26 No.5
そよぐ風 Op.34 No.4/彼女たちは答えた
Op.21 No.4 |
アリーサ・ギツバ(ソプラノ)
スヴェトラーナ・ボンダレンコ(ピアノ) |
|
録音:2013年2-3月、モスクワ音楽院大ホール、モスクワ、ロシア
アリーサ・ギツバはグルジアのスフミに生まれモスクワのグネーシン音楽大学で学んだソプラノ。2014年現在モスクワのヘリコーン・オペラ劇場およびモスクワ・フィルハーモニー所属の古楽アンサンブル「マドリガル」のメンバー。
|
| |
|
|
アンドレイ・ヤロシンスキー(ピアノ)/
ラフマニノフ(1873-1943):ピアノのための24の前奏曲 |
アンドレイ・ヤロシンスキー(ピアノ) |
|
録音:2013年6月、モスクワ音楽院大ホール、モスクワ、ロシア
アンドレイ・ヤロシンスキー(1986年生まれ)はヴェーラ・ゴルノスターエヴァ(モスクワ音楽院)、アレクサンドル・ソコロフ(同ポストグラデュエイト・コース)に師事し2013年に修了した新進ピアニスト。
すでに NaxosレーベルからCDデビューしていますが、当盤の発売は彼に対するモスクワ音楽院の期待の大きさを示すものと言えるでしょう。
|
 MPMP MPMP
|
|
|
カルロス・セイシャス(1704-1742):鍵盤音楽全集
Vol.5
ソナタ ニ短調 K.23/ソナタ
ニ短調 K.22/ソナタ変ロ長調
K.77
ソナタ変ホ長調 K.33/ソナタ
ハ短調 K.15/ソナタ変ホ長調
K.32
ソナタ イ短調 K.72/ソナタ
イ長調 K.58/ソナタ
ホ短調 K.XI
ソナタ ホ短調 K.XII/ソナタ
ホ長調 K.X/ソナタ
ロ短調 K.80 |
ジョゼ・カルロス・アラウジョ(フォルテピアノ) |
|
録音:2013年10月27-28日、音楽博物館、リスボン、ポルトガル
使用楽器:1763年、エンリケ・ヴァン・カステール製、リスボン音楽博物館蔵
チェンバロ、オルガンに続いてフォルテピアノによるセイシャスが登場。
エンリケ・ヴァン・カステール(Henrique
van Casteel;1722-1790)はフランスのトゥルネに生まれた鍵盤楽器製作家。彼の生涯について伝わっていることはほとんどないのですが、1757年から1767年までリスボンで、その後ブリュッセルで1770年代後半まで製作したことが確認されています。
ジョゼ・カルロス・アラウジョはリスボン高等音楽学校、リスボン国立音楽院でカンディダ・マトスとルイ・パイヴァに学んだポルトガルのチェンバロおよびオルガン奏者。2004年、リスボン高等音楽学校主催カルロス・セイシャス・チェンバロ・コンクール第1位と聴衆特別賞を獲得。リスボン大学文学部で古典哲学を学び、古典ギリシャ語の辞書編纂にも携わるというユニークかつインテリジェンスあふれる人物です。
|
| |
|
|
カルロス・セイシャス(1704-1742):鍵盤音楽全集
Vol.6
ソナタ ハ短調 K.18/ソナタ
ト短調 K.54/ソナタ
ハ短調 K.14
ソナタ ヘ長調 K.39/ソナタ
ハ長調 K.2/ソナタ
イ短調 K.67
ソナタ ハ長調 K.8/ソナタ
イ短調 K.75/ソナタ
イ長調 K.63
ソナタ イ短調 K.66/ソナタ
ハ長調 K.4/ソナタ
ヘ長調 K.40
ソナタ ニ短調 K.VIII/ソナタ
ト長調
K.48 |
ジョゼ・カルロス・アラウジョ(フォルテピアノ) |
|
録音:2014年1月10-12日、アロウカ修道院、アロウカ、ポルトガル
使用楽器:1739-1741年、ドン・マヌエル・ベント・ゴメス・フェレイラ製
(2009年、ゲアハルト・グレツィング修復)
典型的なイベリア・バロック・タイプの楽器である、ポルトガル第二の都市ポルト近郊アロウカの修道院のオルガンによるセイシャス。
このオルガンは ALTHUM 006でルイ・パヴァが弾いているものと同じです(そちらでは1739年製と書かれていました)。
アラウジョはリスボン国立音楽院でパイヴァにオルガンを師事したので、はからずも同一楽器による師弟競演となります。
|
| |
|
|
カルロス・セイシャス(1704-1742):鍵盤音楽全集
Vol.7
ソナタ ト短調 K.XVI/ソナタ
ニ短調 K.VIII/ソナタ
ニ短調 K.28
ソナタ ヘ短調 K.43/ソナタ
イ長調 K.59/ソナタ
III イ短調
ソナタ ハ長調 K.8/ソナタ
イ短調 K.66/ソナタ
IX ホ長調
ソナタ ハ短調 K.11/ソナタ
ハ短調 K.II |
ジョゼ・カルロス・アラウジョ(チェンバロ) |
|
録音:2014年、音楽博物館、リスボン、ポルトガル
使用楽器:1758年、ジョアキム・ジョゼ・アントゥネス(1731-1811)製、リスボン音楽博物館蔵
Vol.1、Vol.3と同じアントゥネス製チェンバロを使用。この楽器はこれまでもクレミルデ・ロザド・フェルナンデス(1987年;Portugalsom,
SP 4317、在庫僅少)、ルイ・パイヴァ(1995年;Philips
Portugal、廃盤)、ホセ・ルイス・ゴンサレス・ウリオル(2001年;Portugaler、廃盤)といったポルトガル鍵盤音楽のスペシャリストたちによるセイシャスの作品の録音に使用されてきた名器です。
ジョゼ・カルロス・アラウジョはリスボン高等音楽学校、リスボン国立音楽院でカンディダ・マトスとルイ・パイヴァに学んだポルトガルのチェンバロおよびオルガン奏者。
2004年、リスボン高等音楽学校主催カルロス・セイシャス・チェンバロ・コンクール第1位と聴衆特別賞を獲得。
リスボン大学文学部で古典哲学を学び、古典ギリシャ語の辞書編纂にも携わるというユニークかつインテリジェンスあふれる人物です。
旧譜
カルロス・セイシャス(1704-1742):鍵盤音楽全集
Vol.1〜6 |
ポルトガルのクラシカル音楽のデータベース作成、楽譜出版、ソフト制作、演奏会企画、演奏団体(MPMPアンサンブル)の運営等を行うMPMP(Movimento
Patrimonial pela Musica
Portuguesa [ポルトガル音楽の継承活動])が擁するCDレーベル。
CDシリーズは「Melographia
Portugueza」と銘打たれています。 |
|
|
カルロス・セイシャス(1704-1742):鍵盤音楽全集
Vol.1
ソナタ ホ短調 K.37/ソナタ
ホ短調 K.35/ソナタ
イ短調 K.65
ソナタ イ長調 K.60/ソナタ
ニ短調 K.25/ソナタ
ニ長調 K.21
ソナタ ト短調 K.50/ソナタ
ト長調 K.46/ソナタ
ハ短調 K.15
ソナタ ハ長調 K.1 |
ジョゼ・カルロス・アラウジョ(チェンバロ)
|
|
録音:データ未詳
使用楽器:1758年、ジョアキム・ジョゼ・アントゥネス(1731-1811)製、リスボン音楽博物館蔵
ジョゼ・カルロス・アラウジョはリスボン高等音楽学校、リスボン国立音楽院で学んだポルトガルのチェンバロおよびオルガン奏者。2004年、リスボン高等音楽学校主催カルロス・セイシャス・チェンバロ・コンクール第1位と聴衆特別賞を獲得。リスボン大学文学部で古典哲学を学び、古典ギリシャ語の辞書編纂にも携わるというユニークかつインテリジェンスあふれる人物です。
|
| |
|
|
カルロス・セイシャス(1704-1742):鍵盤音楽全集
Vol.2
フーガ ハ短調 K.II/ソナタ
ハ短調 K.17/ソナタ
ト短調 K.49
ソナタ II ト長調/ソナタ
ニ短調 K.30/ソナタ
ニ長調 K.20
ソナタ イ短調 K.71/フーガ
イ短調 K.XXII/ソナタ
XII ハ長調
ソナタ ハ長調 K.7/シンフォニア
ヘ長調
K.41/ソナタ ニ短調 K.31
ソナタ イ短調 K.74/ソナタ
ハ長調 K.I |
ジョゼ・カルロス・アラウジョ(オルガン) |
録音:時期未詳、サン・ベント・ダ・ヴィトリア修道院、ポルト、ポルトガル
使用楽器:未詳 |
| |
|
|
カルロス・セイシャス(1704-1742):鍵盤音楽全集
Vol.3
ソナタ ハ短調 K.III/ソナタ
ハ短調 K.14/ソナタ
ト短調 K.51
ソナタ ニ長調 K.V/ソナタ
ニ短調 K.20/ソナタ嬰ヘ短調
K.XIV
ソナタ イ長調 K.XX/ソナタ
イ短調 K.XXIII |
ジョゼ・カルロス・アラウジョ(チェンバロ) |
録音:データ未詳
使用楽器:1758年、ジョアキム・ジョゼ・アントゥネス(1731-1811)製、リスボン音楽博物館蔵 |
| |
|
|
カルロス・セイシャス(1704-1742):鍵盤音楽全集
Vol.4
ポルトガル国立図書館所蔵写本5015番所収のソナタ集
ソナタ ト短調 BNP Ms.5015
I/ソナタ ト長調
BNP Ms.5015 II
ソナタ イ短調 BNP Ms.5015
III/ソナタ変ロ長調
BNP Ms.5015 IV
ソナタ ハ短調 BNP Ms.5015
V/ソナタ ニ短調
BNP Ms.5015 VI
ソナタ ホ短調 BNP Ms.5015
VII/ソナタ
ヘ長調 BNP Ms.5015 VIII
ソナタ ホ長調 BNP Ms.5015
IX/ソナタ
ニ長調 BNP Ms.5015 X
ソナタ イ長調 BNP Ms.5015
XI/ソナタ
ハ長調 BNP Ms.5015 XII |
ジョゼ・カルロス・アラウジョ(チェンバロ)
|
録音:データ未詳
使用楽器:1738年、クリスティアン・ファーター製/1693年、ジョヴァンニ・ジュスティ製 |
| |
|
|
カルロス・セイシャス(1704-1742):鍵盤音楽全集
Vol.5
ソナタ ニ短調 K.23/ソナタ
ニ短調 K.22/ソナタ変ロ長調
K.77
ソナタ変ホ長調 K.33/ソナタ
ハ短調 K.15/ソナタ変ホ長調
K.32
ソナタ イ短調 K.72/ソナタ
イ長調 K.58/ソナタ
ホ短調 K.XI
ソナタ ホ短調 K.XII/ソナタ
ホ長調 K.X/ソナタ
ロ短調 K.80 |
ジョゼ・カルロス・アラウジョ(フォルテピアノ) |
|
録音:2013年10月27-28日、音楽博物館、リスボン、ポルトガル
使用楽器:1763年、エンリケ・ヴァン・カステール製、リスボン音楽博物館蔵
チェンバロ、オルガンに続いてフォルテピアノによるセイシャスが登場。
エンリケ・ヴァン・カステール(Henrique
van Casteel;1722-1790)はフランスのトゥルネに生まれた鍵盤楽器製作家。彼の生涯について伝わっていることはほとんどないのですが、1757年から1767年までリスボンで、その後ブリュッセルで1770年代後半まで製作したことが確認されています。
ジョゼ・カルロス・アラウジョはリスボン高等音楽学校、リスボン国立音楽院でカンディダ・マトスとルイ・パイヴァに学んだポルトガルのチェンバロおよびオルガン奏者。2004年、リスボン高等音楽学校主催カルロス・セイシャス・チェンバロ・コンクール第1位と聴衆特別賞を獲得。リスボン大学文学部で古典哲学を学び、古典ギリシャ語の辞書編纂にも携わるというユニークかつインテリジェンスあふれる人物です。
|
| |
|
|
カルロス・セイシャス(1704-1742):鍵盤音楽全集
Vol.6
ソナタ ハ短調 K.18/ソナタ
ト短調 K.54/ソナタ
ハ短調 K.14
ソナタ ヘ長調 K.39/ソナタ
ハ長調 K.2/ソナタ
イ短調 K.67
ソナタ ハ長調 K.8/ソナタ
イ短調 K.75/ソナタ
イ長調 K.63
ソナタ イ短調 K.66/ソナタ
ハ長調 K.4/ソナタ
ヘ長調 K.40
ソナタ ニ短調 K.VIII/ソナタ
ト長調
K.48 |
ジョゼ・カルロス・アラウジョ(フォルテピアノ) |
|
録音:2014年1月10-12日、アロウカ修道院、アロウカ、ポルトガル
使用楽器:1739-1741年、ドン・マヌエル・ベント・ゴメス・フェレイラ製
(2009年、ゲアハルト・グレツィング修復)
典型的なイベリア・バロック・タイプの楽器である、ポルトガル第二の都市ポルト近郊アロウカの修道院のオルガンによるセイシャス。
このオルガンは ALTHUM
006でルイ・パヴァが弾いているものと同じです(そちらでは1739年製と書かれていました)。
アラウジョはリスボン国立音楽院でパイヴァにオルガンを師事したので、はからずも同一楽器による師弟競演となります。
|
|
MUSICA BOHEMICA
|


MB 004-2
\2400 →\2190
〔旧譜・再プレス〕 |
モーツァルト(1756-1791):レクイエム ニ短調
K.626 |
アンナ・フラヴェンコヴァー(ソプラノ)
カロリーナ・ベルコヴァー(アルト)
マリアン・パヴロヴィチ(テノール)
ロマン・ヴォツェル(バス)
ムジカ・ボヘミカ・プラハ(管弦楽)
プラハ室内合唱団
ヤロスラフ・クルチェク(指揮) |
|
録音:2000年7月、ドモヴィナ・スタジオ、プラハ、チェコ
ムジカ・ボヘミア・プラハにしては意外な通常レパートリー。モダーン楽器使用。
|
MUSICAS FESTIVAS DE FERNANDO LOPES−GRACA
|


MFFLG 1-2
(2CD)
\3600 →\3290
【旧譜 再入荷】 |
フェルナンド・ロペス=グラサ(1906-1994):お祝いの音楽
[CD 1]
お祝いの音楽(1962-1994)
第1番「テレザ・マルガリダの5歳の誕生日に」
第2番「シルヴィアの3歳のお誕生日に」
第3番「ジョゼ・ペドロの最初のクリスマスに」
第4番「“カナリト”の誕生に」
第5番「ネニタの結婚式に」
第6番「“カザ・ドス・ガロス”の開館式に」
第7番「テレジタ・マシャドの結婚式に」
第8番「ロメオの結婚式に」
第9番「マリア・アリナの20歳の誕生日に」
第10番「ヌノ・バロゾの19歳の誕生日に」
第11番「わが兄弟ジョゼの80歳の誕生日に」
第12番「フランシネ・ベノイトの90歳の誕生日に」
第13番「わが兄弟の最初の曾孫ルイス・ゴンサロの
最初のクリスマスのおもちゃ」
第14番「イヴォ・マシャドの結婚式に」
[CD 2}
お祝いの音楽
第15番「カタリナの3歳の誕生日に」
第16番「ジョアン・エスプリト・サントの15歳の誕生日に」
第17番「若い友人たちの集いに」
第18番「ミゲル・ボルジェス・コエリョの18歳の誕生日に」
第19番「わが兄弟の曾孫ジョルジ・ミゲルの3歳の誕生日に」
第20番「ヴァスコ・コンサルヴェスの70歳の誕生日に」
第21番「ジョゼ・ペドロとパウラの結婚式のために」
第22番「親愛なるジャシント・ジモンイス博士の66歳の誕生日に」
第23番「わが同僚にして友人アルヴァロ・クニャルの80歳の誕生日に」
9つの短い舞曲 |
アントニオ・ロザド(ピアノ) |
|
録音:2012年11月23-26日(CD 1)、2013年4月5-8日(CD
2)、CGDホール、リスボン経済経営高等学校(ISEG)、リスボン、ポルトガル
20世紀ポルトガルを代表する作曲家フェルナンド・ロペス=グラサがその長い生涯において親類や友人の誕生日や結婚式等を祝うために作曲したピアノ作品の出版に合わせて制作されたCD。アントニオ・ロザドはリスボン音楽院を卒業後、16歳でパリ音楽院に入りアルド・チッコリーニに師事、1980年にデビューしたポルトガルのピアニスト。彼はロペス=グラサのピアノ・ソナタ全集も録音しています(Numericaレーベル、NUM
1124 入手不能)。
本体、外装に規格品番表示がございません。ご了承ください。
|
NON PROFIT MUSIC
|
| 「国境なき医師団」支援のためのチャリティ・コンサートを企画するスペインの団体「Non
Profit Music Foundation」(非営利音楽財団)傘下のレーベル。 |

NPM 1404
\3100 →\2990
[CD] |
ホルヘ・グルンドマン(1961-):ヴァイオリンとピアノのためのWソナタ集
What Inspires Poetry(ソナタ)
I. About Loneliness and
Nostalgia /
II. About Calm and Serenity
III. About Rain and Storm
Warhol in Springtime(ソナタ)
White Sonata: The Child Who
Never Wanted
to Grow Up(ソナタ)
Why?(ヴァイオリンとピアノのための) |
ビセンテ・クエバ(ヴァイオリン)
ダニエル・デル・ピノ(ピアノ) |
|
録音:未詳
スペインの作曲家・音楽学者ホルヘ・グルンドマンの、Wで始まるタイトルを持つヴァイオリン・ソナタ集。
|
OS MUSICOS DO TEJO
|
|
|
ファドの種 ポルトガル歌曲とファドの遠い関係を探って
不詳:私は、不運にも [Foi por
mim, foi
pela sorte](*)
ラファエル・コエリョ・マシャド(1814-1887):
甘美な希望はついえた [Fenece
doce esperanca](*)
アントニオ・ダ・シルヴァ・レイテ(1759-1833):メヌエット
フランシスコ・シャヴィエ・バプティスタ(17??-1797):
私の人生は常に悲しみと苦しみばかり
[He somente a minha vida
sempre penar
e sofrer](*)
ジョゼ・メスキタ(確認できる活躍期:1793-1795):
優しい鳥たち [Ternas Aves](*)
アントニオ・ダ・シルヴァ・レイテ:
アンダンティーノ/フランシスコ・ジェラルド氏のトッカータ
マルコス・ポルトゥガル(1762-1830):愛しい夫が
[Cosi dolce amante sposo](*)
アントニオ・ダ・シルヴァ・レイテ:
この世の栄光を軽んじ [Desprezar
do mundo
a gloria](*)
愛が私に褒美をくれた [Amor
concedeum'um
premio] (デュエット)(*)
マヌエル・ジョゼ・ヴィディガル(確認できる活躍期:1796-1826):
メヌエット第6番/メヌエット第3番
V・J・コエリョ(19世紀前半):小鳥
[Avezinha]
アントニオ・ジョゼ・ド・レゴ(1783頃-1821):
バレイロの涼しい海辺 [Frescas
praias
do Barreiro](*)
D・ジョゼ・アクニャ(?-1828):オリュンポスの神々
[Deuses do Olimpo](*)
ジョゼ・マウリシオ(1752-1815):
私が自然に何をしたのか [Que
fiz eu a
natureza](*)
カルロス・セイシャス(1704-1742):
ソナタ ハ短調(PM No.16)から
第1楽章(チェンバロ独奏)
D・ジョゼ・アクニャ:愛の絆
[Os lacos
d'Amor](チェンバロ伴奏)(*) |
オス・ムジコス・ド・テジョ
アナ・キンタンス(ソプラノ(*))
リカルド・ロシャ(ポルトガルギター)
マルコス・マガリャンイス(チェンバロ、指揮) |
|
録音:2006年7月23-26日、市立アウグスト・カブリタ・コンサートホール、バレイロ、ポルトガル
ポルトガルの伝統歌謡ファドへの流れを作ったと考えられる、18世紀中盤から19世紀初頭にかけてポルトガルで書かれた「都会の中産階級向け歌曲」を選び出し、ポルトガルギターを交えて演奏するという興味深い企画。オス・ムジコス・ド・テジョはマルコス・マガリャンイスにより2003年に創設されたピリオド楽器アンサンブル。ポルトガル音楽ファンの方でしたら
Naxosから発売されたフランシスコ・アントニオ・デ・アルメイダ(1702-1755)のオペラ「ラ・スピナルバ」ですでにご存じかもしれません。
アナ・キンタンス(1975年生まれ)はリスボン国立音楽院で学んだソプラノ。ピリオド・モダーンを問わずすでに多くの名だたるオーケストラとの共演、オペラハウスへの出演を果たしています。
リカルド・ロシャ(1974年リスボン生まれ)は現代を代表するポルトガルギター奏者の一人。
マルコス・マガリャンイスは1972年リスボンに生まれ、リスボン高等音楽学校でクレミルデ・ロザド・フェルナンデス、シェティル・ハウグサンに、パリ音楽院でケネス・ギルバート、クリストフ・ルセ、ケネス・ワイスに師事したチェンバロ奏者・指揮者。 ブックレットにポルトガル語の解説と英語・フランス語訳、ポルトガル語歌詞と英語訳・フランス語訳を収録。
本体・外装ともに規格品番表記がございませんが、弊社は「MT
001」として管理いたします。ご了承ください。(代理店)
|
| |
|
|
ルイザ・トーディのアリア集
フローリアン・レオポルト・ガスマン(1729-1774):
オペラ「職人の恋」 [L'Amore
Artigiano]
(1778)から 序曲(管弦楽)
ベルナルディーノ・オッターニ(1736-1827):
オペラ「アルミーニオ」 [Arminio]
(1781)から
ロスモンダのアリア
「あなたが心に同情を覚えるなら」
[Se
pieta tu senti al core]
ニッコロ・ピッチンニ(1728-1800):
オペラ「迫害された匿名の女」[L'Incognita
Perseguitata] (1770)から
ジャネッタのレチタティーヴォとアリア「羊飼いたちよ、私も一緒に」
[Pastorelle, anch'o
con voi]
ジョヴァンニ・パイジエッロ(1740-1816):オペラ「アンドロマカ」(1797)から
アンドロマカのレチタティーヴォとアリア「哀れな王子よ」
[Povero Prence]
ニッコロ・ピッチンニ:オペラ「迫害された匿名の女」から
ジャネッタのアリア
「お父さん、ああ、どこにいるの?」
[Genitore, ah, dove siete?]
アントニオ・サッキーニ(1731-1786):オペラ「オリンピーアデ」(1778)から
メガークレのアリア「もしも君が探すなら、こう言うなら」
[Se cerca, se dice]
ニッコロ・ピッチニーニ:オペラ「ディドーネ」
[Didone] (1791)から
ディドーネのレチタティーヴォとカヴァティーナ
「ああ、私が何を言った?不幸な人よ」
[Ah, che dissi, infeice?]
ニッコロ・ピッチンニ:
オペラ「インドのアレッサンドロ」
[Alessandro
nell'Indie](1778)から
クレオフィーデのレチタティーヴォとアリア
「それでポーロは死んだのだ」
[Poro
dunque mori]
ダヴィド・ペレス(1711-1779):
オペラ「デモーフォンテ」
[Demoofonte]
(1772)から
ディルチェアのアリア「私はあなたに期待する、愛する夫よ」
[In te spero, o sposo
amato]
アントニオ・サッキーニ:オペラ「オリンピーアデ」から
アルジェーネのアリア「もう何も見つからない」
[Piu non si trovano] |
ジョアナ・セアラ(ソプラノ)
オス・ムジコス・ド・テジョ(管弦楽)
マルコス・マガリャンイス(指揮)
|
|
録音:2008年9月12-16日、カルトゥジオ教会、カシアス、ポルトガル
18世紀終盤に活躍したポルトガル出身の名リリック・ソプラノ、ルイザ・トーディ。1753年ポルトガルのセトゥバルにルイサ・ロザ・デ・アギアルとして生まれ、14歳で舞台デビュー、16歳の時にナポリ出身のヴァイオリン奏者フランチェスコ・サヴェーリオ・トーディと結婚、17歳でオペラ・デビュー。1777年にポルトガルを出てから20年にわたってイギリス、フランス、イタリア、ドイツ、ロシア等ヨーロッパ各地で大活躍。1799年、ナポレオン戦争を避けナポリを去り、13ヶ月をかけて1810年ポルトガルに帰国。1801年ポルトに居を構え歌手活動を再開しましたが、1803年に夫が死去、1809年のナポレオン軍のポルト侵攻の際に「Ponte
das barcasの悲劇」に巻き込まれ貴重な宝石類を失い、さらに1813年頃から視力が弱まり10年後に完全には完全に失明する不幸に見舞われ、1833年リスボンで貧窮のうちに亡くなりました。
当盤はルイザ・トーディがヨーロッパ各地で歌った数々のオペラからアリアを選び彼女のキャリアを回想しようという企画。
「ルイザ役」を歌うのは、リスボンに生まれロンドンのギルドホール音楽学校で学び2004年にオペラ・デビューしたソプラノ、ジョアナ・セアラ。バロックから古典派にかけてのレパートリーを得意としています。ブックレットにポルトガル語の解説と英語・フランス語訳、イタリア語歌詞とポルトガル語・英語・フランス語訳を収録。
|
 PAVLIK PAVLIK
|


PA 0074-2/9
(3CD/3DVD-Audio)
\6600 →\5990 |
ニコラウス・ズメスカル(1759-1633):15の弦楽四重奏曲
第10番ニ短調/第6番イ長調/第11番ロ短調/第9番ト長調
第12番ト短調/第13番ハ短調/第5番変イ長調/第3番ヘ短調
第1番ト長調/第4番ニ長調/第7番ハ長調&ヘ長調/第2番ロ長調
第8番嬰ニ(変ホ)長調/チェンバロノタメノロンド
ヘ長調(*)
第15番ト短調/第14番ニ長調 |
ズメスカル弦楽四重奏団(*以外)
ミロシュ・ヴァレント、ダグマル・ヴァレントヴァー(ヴァイオリン)
ペテル・ヴルピンチーク(ヴィオラ) ユライ・コヴァーチ(チェロ)
リタ・パップ(チェンバロ(*)) |
|
録音:2009-2011年、ヤセノヴァーおよびブジニーの教会、スロヴァキア
ニコラウス・ズメスカルはスロヴァキアのレシュチニに生まれた高級官僚・作曲家・チェロ奏者。ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンと個人的に交友、ウィーンの音楽界をリードしたパトロンで楽友教会創立者の一人でもありますが、作曲家としては忘れ去られてしまいました。
ブックレットに記載された作品目録によると、当盤に収録された15の弦楽四重奏曲と1つのチェンバロ小品が現存する彼の音楽作品のすべてであることがわかります。
CDとDVD-Audioの両面ディスク仕様。
|
| |
|
|
ヤーン・レヴォスラフ・ベッラ(1843-1936):ピアノ作品全集
ソナタ変ロ長調(第2版)(1885以後)
ソナティナ ホ短調(1873)
スロヴァキア民謡「ドナウ河畔のプレシュポロク」による変奏曲
(1866/改訂:1879)
スロヴァキア民謡「群れが飛ぶ」による変奏曲(1872)
奇想曲(1869)/奇想曲(第2版;1877)/妖精の踊り(1873)
小奇想曲(1876)/聖マルチンのカドリーユ(1862)
クレムニツァ消防隊ポルカ(1869-1881)
人形の休日(ピアノ二重奏のための;1927)(*) |
ペテル・バジツキー(ピアノ)
マルチン・フダダ(ピアノ(*)) |
|
録音:データ記載なし
ヤーン・レヴォスラフ・ベッラはウィーンで活躍したスロヴァキアの作曲家・指揮者。ロマン派的作風を貫きました。ペテル・バジツキーはブラチスラヴァ音楽アカデミーでマリアン・ラプシャンスキーに師事したスロヴァキアのピアニスト。
|
| |
|
|
ウースメフ・アコーディオン・オーケストラ
ハンス・ジマー(1957-)/サムエル・ベズナーク編曲:
パイレーツ・オブ・カリビアン−ア・トリビュート・トゥ・ハンス・ジマー
ハンス・ボル(1923-):バルカンの旅の画集(管弦楽組曲)
山々の夕べ/古い職人小路/港町で
フェリクス・リー:シャローム/メドレー
ヘンリー・マンシーニ(1924-1994)/マリアンナ・ディンカウ編曲:
ピンク・パンサー
アバ/マティアス・ヘネッケ編曲:アバ−ベスト・オブ・メドレー
レナード・バーンスタイン(1918-1990)/ハインツ・エーメ編曲:
ウエストサイド・ストーリー(メドレー)
アドルフ・ゲッツ(1938-):スラヴ狂詩曲
ロッシーニ(1792-1868)/グイード・ヴァーグナー編曲:
「セビリャの理髪師」序曲 |
ウースメフ・アコーディオン・オーケストラ
ヤーン・ハルシネク(コンサートマスター)
アンドレア・カジコヴァ(第1アコーディオン)
ペテル・イェルグシュ・パルニツァ(第2アコーディオン)
フィリプ・オレイニク(第3アコーディオン)
ヤナ・チュカノヴァー(第4アコーディオン)
ヘレナ・ゴリャノヴァ(バスアコーディオン)
サムエル・ベズナク(ピアノ、キーボード、アコーディオン)
モニカ・オレイニコヴァ(クラヴィーア、キーボード)
フランチシェク・レトコ(クラリネット、アルトサクソフォン)
ミロシュ・ミルコヴィチ(ドラムス、ティンパニ、打楽器)
マルチナ・ホラー(指揮) |
|
録音:2012年11月16-18日、初等芸術学校コンサートホール、ノヴェイ・ドゥブニツィ、スロヴァキア
ウースメフ・アコーディオン・オーケストラは1991年スロヴァキアのトレンチアンスケ・テプリツェ初等芸術学校内に創設されたアコーディオン主体のアンサンブル。現在は非営利団体として活動しています。
|
| |
|
|
ジプシー・デヴィルズの「カルメン」
ビゼー(1838-1875)/エルンスト・シャルケジ編曲:
序曲(*)/カルメン組曲 から
闘牛士たち/恋は野の鳥(ハバネラ)
ハバネラの回想/カルメン組曲/セビリャの城壁近くで
諸君らの乾杯を喜んで受けよう(闘牛士の歌)
鈴が打ち鳴らされれば(ジプシーの歌)
カルメン変奏曲 から 諸君らの乾杯を喜んで受けよう
ドヴォルジャーク(1841-1904):オペラ「ルサルカ」からのアリア |
ジプシー・デヴィルズ
シュテファン・バニャク(第1ヴァイオリン) エミル・ハサラ(第2ヴァイオリン、作詞)
シルヴィア・シャルケジオヴァー(チェロ、歌) エルンスト・シャルケジ(ダルシマー)
ゾルターン・グルンザ(クラリネット、タロガトー) ヨゼフ・ファルカシュ(ヴィオラ)
アレクサンドレル・ミホク(コントラバス) ゲスト:マレク・ピロ(ギター&歌(*)) |
|
録音:データ記載なし
ジプシー・バンドの枠に収まらず、クラシック、ジャズ、ロックのミュージシャンとのコラボレーションも盛んに行っているエスノ・ミュージック・オーケストラ、ジプシー・デヴィルズがビゼーの「カルメン」に挑戦。ブックレットは無くジャケットの裏にパウル・グルダ他の賛辞が記載されているのみ。理屈ではなく、まず聴いて楽しめということなのでしょう。ジプシー・デヴィルズの動画。
|
| |
|
|
エフゲニー・イルシャイ(1951-):From Nowhere
with Love
From nowhere with love(ヴァイオリンとピアノのための;2008)(*/#)
Pimpampunchi(無伴奏ヴァイオリンのための;2010)(*)
Soundquake(アコーディオンとピアノのための;2009)(+/#)
Exodus(ピアノと2つのタムタムのための;1996)(#)
Summer garden - snow is falling(ピアノのための;1997)(#)
Bahagobu(アコーディオンのための;2011)(+)
Sonata No.3(ヴァイオリンとピアノのための;2013)(*/#) |
ミラン・パリャ(ヴァイオリン)
ペテル・カティナ(アコーディオン)
エフゲニー・イルシャイ(ピアノ、タムタム) |
|
録音:データ記載なし
スロヴァキアで活躍するロシア人作曲家エフゲニー・イルシャイ。「From
Nowhere with Love」を直訳すると「どこでもない所より愛をこめて」。ジャケットにはイルシャイの絵画作品が使われています。
|
| |
|
|
ヒスパニック・スピリット
エンリケ・グラナドス(1867-1916):詩的ワルツ集
から
序奏−ヴィヴァーチェ/メロディコ/遅いワルツのテンポ
ユーモラスなアレグロ/アドリブ風/プレスト/メロディコ
ホアキン・ロドリーゴ(1901-1999):
アデラ(*)/聖なる羊飼い(*)/ベツレヘムのコピリャナ(*)
3つの小品 から 小さなセビリャナ/恋する羊飼いのコプラ(*)
ミゲル・リョベト(1878-1938):盗賊の歌/アメリアの遺言/聖母の御子
アグスティン・ペレス・ソリアノ(1846-1907)/
ミリアム・ロドリゲス・ブリュロヴァー編曲:
サルスエラ「エル・ギタリコ」から
Suena
guitarrico mio(*)
アグスティン・バリオス(1885-1944):フリア・フロリダ(子守歌)
カルロス・グアスタビノ(1912-2000)/ダニエル・ボルショイ編曲:
渇きの底から(*)/ばらと柳(*)/二人兄弟のミロンガ(*)
アストル・ピアソラ(1921-1992):オブリビオン
ローラン・ディアンス(1955-):タンゴ・アン・スカイ
カルロス・ガルデル(1890-1935)/ミリアム・ロドリゲス・ブリュロヴァー編曲:
想いの届く日(*)
アルド・ロドリゲス・デルガド(1955-):歌と踊り
フェデリコ・モレノ・トロバ(1891-1982)/
ミリアム・ロドリゲス・ブリュロヴァー編曲:
サルスエラ「マラビリャ」から
愛、わが命の命(*)
ヘロニモ・ヒメネス(1854-1923)/ミリアム・ロドリゲス・ブリュロヴァー編曲:
サルスエラ「ラ・テンプラニカ」から
サパテアド(*) |
パヴォル・レメナール(バリトン(*))
ミリアム・ロドリゲス・ブリュロヴァー(ギター) |
|
録音:時期の記載なし、ローマ・カトリック教会、ヘリパ、スロヴァキア
ミリアム・ロドリゲス・ブリュロヴァー(1979年生まれ)はブラチスラヴァ音楽院および舞台芸術アカデミー、カナダのケベック大学およびラヴァル大学で学んだスロヴァキアのギター奏者。「ポピュラー音楽でギターが当たり前のように歌の伴奏をするのと同様、クラシカル歌曲の伴奏をギターで行うのは自然なこと」と考えていた彼女は2007年にパヴォル・レメナール(1974年生まれ、スロヴァキアのバリトン)の歌唱を聴いて「これだ」と確信。二人は意気投合しデュオ活動を開始しました。
|
| |

PA 0121
\2300
|
ユライ・ハトリーク(1941-):繊細な混練 室内楽作品集
アルバムの綴り−繊細な混練(ツィンバロム、オルフ教育楽器と童声のための)
エニケー・ギンゼリ(ツィンバロム)
ユライ・シュシャニーク、ヴラジミール・サヴィチ(打楽器)
スロヴァキア放送児童合唱団(第25曲のみ) ブランコ・ラディチ(指揮(同))
小さい人と大きい人−手を取り合って
(小さいヴィオラ奏者と大きいヴィオラ奏者のための連作二重奏曲断章)
イヴァン・パロヴィチ、ヴェロニカ・プロケショヴァー(ヴィオラ)
ピアノのための4つの間奏曲
クロコダイルとナイル川/小さな蝶エリーゼ/大きな太陽の下で/蝶
フランチシェク・ペルグレル(ピアノ)
ヘッセへのオマージュ(アルト、ヴィオラとツィンバロムのための二部作
心の粘り強さ/格言
ペトラ・ノスカイオヴァー(メゾソプラノ)
イヴァン・パロヴィチ(ヴィオラ) エニケー・ギンゼリ(ツィンバロム)
小さい人と大きい人−手を取り合って(断章)
イヴァン・パロヴィチ、ヴェロニカ・プロケショヴァー(ヴィオラ)
鳥は悲しげに歌う…(左手のための幻想曲風カンツォーナ)
ペトラ・ノスカイオヴァー(メゾソプラノ) フランチシェク・ペルグレル(ピアノ)
Ad matrem... [The Noon]
ブラチスラヴァ市合唱団 マルチナ・メスチツカー(フルート)
フランチシェク・ペルグレル(ピアノ) ラジスラフ・ホラーセク(指揮)
ヘルマン・ヘッセの格言
シュテファン・ブチコ(朗読) |
| 録音:2013年11月16-23日、ドヴォラナ・コンサートホール、舞台芸術アカデミー、
ブラチスラヴァ、スロヴァキア |
| |

PA 0122
(2CD)
\4600 |
ヴァイオリン・ソロ 5
スロヴァキアの作曲家による無伴奏ヴァイオリンのための作品集
リュドヴィート・ライテル(1906-2000):組曲
アンドレイ・オチェナーシュ(1911-1995):心についての詩
イリヤ・ゼリェンカ(1932-2007):4つの小品
ロマン・ベルゲル(1930-):収束
第1番
エフゲニー・イルシャイ(1951-):3
Huslehubky
ユライ・ポスピーシル(1931-2007):組曲
トマーシュ・ボロシュ(1971-):ブロック
ユライ・ハトリーク(1941-):遮られたシャコンヌ
ダニエル・マテイ(1963-):嵐の
[Stromy]
ユリウス・コヴァルスキ(1912-2003):6音システムによるパルティータ
イヴァン・フルショフスキー(1927-2001):ソナタ |
マリアン・パリャ(ヴァイオリン) |
|
録音:2013年12月7-8日、ブルク邸、ポヴァシュスケー・ポドフラディエ、スロヴァキア
スロヴァキアの無伴奏ヴァイオリン作品をすべて録音してしまいそうな勢いのマリアン・パリャ。第5弾の登場です。
|
PICCOLO
|
|
|
プロノモス 21世紀のフルート
日本尺八古典本曲:手向
ドビュッシー(1862-1918)/フリアン・エルビラ編曲:シリンクス
V.P. [Syrinx V.P.]
フリアン・エルビラ(1973-):
建築家の家 [La casa del arquitecto]/ターラ
[Tala]/ラーガ [Raga]
マラン・マレ(1656-1728)/フリアン・エルビラ編曲:
スペインのフォリアによる変奏曲
ヘスス・ナバロ(1980-):白鳥の預言
[Swan's
Prophecy]
日本古謡/フリアン・エルビラ編曲:さくらさくら |
フリアン・エルビラ(プロノモス・フルート) |
|
録音:データ記載なし
使用楽器:スティーヴン・ウェッセル製
スペインのフルート奏者フリアン・エルビラ(1973年生まれ)が自ら10年以上をかけて開発した高機能フルート「プロノモス・フルート(Promonos
Flute)」を演奏。
詳しくはプロノモス・フルートのウェブサイト(スペイン語、一部英語)にて。
|
 PLECTRA MUSIC PLECTRA MUSIC
|


PL 21401
(3CD)
\4800 →¥4390 |
ルベーグ、アルデル:チェンバロ作品全集
ニコラ・ルベーグ(1631頃-1702):
クラヴサン曲集(1677)
組曲ニ調/組曲ト調/組曲イ調/組曲ハ調/組曲ヘ調
クラヴサン曲集第2巻(1687)
組曲 en d la re(*)/組曲
en g re sol
♭/組曲 en a mi la re(*)
組曲 en A mi la re #/組曲
en F ut
fa(*)/組曲 en G re sol ?
ジャック・アルデル(1643頃-1678):
組曲ニ調
ガヴォットとドゥブル(マルク=ロジェ・ノルマン・クープラン(1663-1734)作曲?)
アルデルのクラント/クラント(デイヴィット・モロニー復元) |
カレン・フリント(チェンバロ) |
|
録音:データ記載なし
使用楽器:1627年(*以外)、1635年(*)、アントウェルペン、ヨハネス・ルッカース製
フランス・クラヴサン楽派の創始者とされるジャック・シャンピオン・ド・シャンボニエール(1601/1602-1672)の次世代、ルイ・クープラン(1626-1661)とジャン=アンリ・ダングルベール(1629-1691)の同世代にあたる二人のクラヴサン作曲家を取り上げたアルバム。
ニコラ・ルベーグは低い身分の出身ながらパリで成功を収めた作曲家・オルガンおよびチェンバロ奏者。サン=メリ教会のオルガン奏者を1664年から亡くなるまで38年にわたって務め、1678年からは国王ルイ14世付きオルガン奏者も兼務しました。
ルベーグのチェンバロ(クラヴサン)音楽は師匠だった可能性もあるシャンボニエール、およびルイ・クープランの影響が見られ、たいへん高い水準にあるにもかかわらず、演奏・録音される機会に恵まれていたとは言えません。ジャック・アルデルは楽器製作の家系に生まれ、シャンボニエールに師事した作曲家・チェンバロ奏者。完全な形で残された作品が10曲に満たないこともあり知名度はいまひとつですが、忘れてはならない作曲家です。
カレン・フリントはオバーリン音楽院およびミシガン大学で学んだ合衆国のチェンバロ奏者。ブランディワイン・バロック(古楽アンサンブル)のアーティスティック・ディレクターであり、当レーベルの中心的音楽家です。ルベーグとアルデルのチェンバロ独奏全作品がルッカースのオリジナル楽器で録音されたことの意義は大きいと言えるでしょう。
|
| |


PL 21402
(3CD)
\4800 →¥4390 |
フランソワ・クープラン(1668-1733):
「クラヴサン奏法」(1716)に収められた8つの前奏曲とアルマンド
クラヴサン曲集第2巻(1717)
第6組曲/第7組曲/第8組曲/第9組曲/第10組曲/第11組曲
第12組曲 |
デイヴィット・モロニー(チェンバロ)
|
|
録音:データ未詳
使用楽器:1627年および1635年、アントウェルペン、ヨハネス・ルッカース製
グスタフ・レオンハルト亡き後の古楽界を代表する鍵盤楽器奏者の一人、デイヴィット・モロニーが満を持して取り組むフランソワ・クープランのクラヴサン独奏全作品録音プロジェクト第2作。
デイヴィット・モロニー(1950年生まれ)はスージー・ジーンズ、ケネス・ギルバート、グスタフ・レオンハルトに師事した英国の鍵盤楽器奏者・音楽学者。20年以上本拠としていたパリから2001年アメリカ合衆国に移住し、カリフォルニア大学バークレー校教授兼オルガニストを務めています。
ルッカースのオリジナル楽器2台を使用した演奏。

|
 POLSKIE NAGRANIA(MUZA) POLSKIE NAGRANIA(MUZA)
|
|
|
愛 フォーレ、ベートーヴェン、ラフマニノフ:ピアノ作品集
フォーレ(1845-1924):バラード嬰ヘ長調
Op.19
ベートーヴェン(1770-1827):ソナタ第31番変イ長調
Op.110
ラフマニノフ(1873-1943):ソナタ第2番変ロ短調
Op.36 |
小林倫子(ピアノ)
|
|
録音:2013年4月26日、国立フィルハーモニー・ホール、ワルシャワ、ポーランド
小林倫子は1977年よりポーランド在住の日本人ピアニスト。履歴等については公式サイト:http://rinkokobayashi.com/jp/をご覧ください。
|
PRIMETIME
|


PMT 0613
(2CD)
\4200 →\3790 |
「辺境のマイナー楽器」のイメージを吹き飛ばす
「クラシカル・ポルトガルギターの名盤」と自信を持って申し上げます。(代理店)
ペドロ・カルデイラ・カブラル/ポルトガルギターの迷宮&アンソロジー
[CD 1] ポルトガルギターの迷宮(*)
不詳(16世紀):マタシンス
ペドロ・デ・エスコバル(1465頃-1536):ヴィランセテ/カンティガ
不詳(16世紀):ルッジェーロのグロザ
ディエゴ・オルティス(1510-1570):レセルカダ
I/レセルカダ II
ジョン・ダウランド(1563-1626):憂鬱なガイヤルド
アントニー・ホルボーン(1550頃-1602):パヴァーヌ第4番
ジョン・ダウランド:蛙のガイヤルド
ロバード・ジョンソン(1582頃-1633):アルマン
ロベール・バラール(1575-1650):村のブランル
ドメニコ・スカルラッティ(1685-1757):ソナタ
K.322
カルロス・セイシャス(1704-1742):ソナタ
37
ジョアン・パウロ・ペレイラ(確認できる活躍期:1840-1860):
ワルツ ヘ短調/ワルツ ト短調
不詳(1850頃):マズルカ
ペドロ・カルデイラ・カブラル(1950-):イチイのバラード/アストリアナ
[CD 2] アンソロジー
アロンソ・ムダラ(1520頃-1580):ファンタジア
ジル・デュラン・デ・ラ・ベルジェリ(1554-1605):愛しの人よ、もしあなたの心が
ガスパル・サンス(1640頃-1710):パヴァーヌ
サンティアゴ・デ・ムルシア(1682頃-1740):前奏曲/カンシオン
ジュゼッペ・アントニオ・ブレシャネッロ(1690頃-1758):ソナタ
ドメニコ・スカルラッティ:ソナタ
K.11
マテオ・アルベニス(1755-1831):ソナタ
フェルナンド・ソル(1778-1839):練習曲
Op.6 No.23/練習曲 Op.35 No.10
アントニオ・ラウロ(1917-1986):ベネズエラのワルツ
ペドロ・カルデイラ・カブラル:
アーモンドのバラード/玩具/岩山の迷宮/未完の円 |
ペドロ・カルデイラ・カブラル(ポルトガルギター)
ダンカン・フォックス(コントラバス(*)) |
|
録音:データ記載なし
ポルトガルの伝統歌謡ファドの伴奏楽器と位置付けられていたポルトガルギターをクラシカルなソロ楽器にまで高めたペドロ・カルデイラ・カブラル。彼の2つのコンサート・プログラムを収めたCDが発売されました。
ポルトガルギターはいわゆるギターではなくリュート系で、6コース・スチール複弦の撥弦楽器。どこか哀感を帯びた甘美な音色を特徴としています。ポルトガルでは単に「ギター(ギタラ)」と言えばこの楽器を指すそうです。
ペドロ・カルデイラ・カブラルは1950年リスボンの音楽一家に生まれリスボン国立音楽院で学んだギター、ポルトガルギター、リュート、ヴィオル奏者。彼はポルトガルにおける古楽演奏の第一人者でもあり、ピリオド楽器と古楽唱法によるアンサンブル「ラ・バタッラ」および「コンセルト・アトランティコ」を主宰する他、ルネサンス・バロック音楽のポルトガルギター用編曲に長年取り組んでいます。
録音したCDは十数枚あり、当盤同様に2つのコンサート・プログラムを収めたCD「ポルトガルギターの記憶&18世紀のギターに」(2003年、Tradisomレーベル、ポルトガル)もすばらしい内容だったのですが残念ながら廃盤のため入手できません。
カルデイラ・カブラルの編曲・演奏による楽曲の数々はポルトガルギターのために書かれたオリジナル作品としか思えないほど違和感がなく、この楽器独特の魅力を備えた逸品に仕上がっています。なかでもすばらしいのはやはりセイシャス。カルデイラ・カブラルの自作曲もファド風あり、ピアソラ風あり、技巧を極めた現代音楽風ありでとことん楽しめます。
「辺境のマイナー楽器」のイメージを吹き飛ばす「クラシカル・ポルトガルギターの名盤」と自信を持って申し上げます。(株式会社サラバンド代表取締役
金田敏也)
Primetimeは配給元と表示されており、実質的には自主制作商品と思われますのでお早目の入手をお勧めいたします。なお、外装に規格品番表記がございませんのでご注意ください。(代理店)
|
 RUSSIAN DISC RUSSIAN DISC
|
|
|
ヴァレーリー・キクタ(1941-):21世紀の協奏曲集
オーボエと室内管弦楽のための協奏曲第3番(2001)(*)
4つのフルート、チェンバロと室内管弦楽のための協奏曲
「Volyn' Tunes」(2013年版)(+)
ホルン協奏曲(2008)(#) |
アレクサンドル・レヴィン(オーボエ(*))
モスクワ音楽院学生交響楽団室内キャスト(*)
ヴャチェスラフ・ヴァレーエフ(指揮(*))
セルゲイ・ジュラヴェル(フルート(+))
イリーナ・スタロードゥプ(チェンバロ(+))
キエフ・ソロイスツ(国立室内アンサンブル)(+)
ヴラディーミル・シレンコ(指揮(+))
ヴァレーリー・ジャヴォロンコフ(ホルン(#))
ムジカ・ヴィーヴァ(室内管弦楽団)(#)
アレクサンドル・ルーディン(指揮(#)) |
|
録音:2012年(*)/2013年(+/#)
ヴァレーリー・キクタはウクライナのドネツクに生まれ、モスクワ音楽院でセミョーン・ボガティリョフ(1890-1960)、チーホン・フレンニコフ(1913-2007)に師事した作曲家。
|
 SEDEM(スペイン音楽学会) SEDEM(スペイン音楽学会)
|

CD 31
(DCD 309)
\2500 |
新イスパニアの楽師たち プエブラ大聖堂写本19番所収の音楽
[カンシオン、ビリャネスカとマドリガル
I]
フィリップ・ロジエ(1561頃-1596):
5声のカンシオン(ff.99v-101r)/5声のカンシオン(ff.105v-107r)
オルランドゥス・ラッスス(1532-1594):5声のシャンソン(ff.109v-111r)
フィリップ・ロジエ:5声のカンシオン(ff.98v-99r)
不詳(16世紀):4声のマドリガル「Occhi
miei」
クレマン・ジャヌカン(1485頃-1558):シャンソン「Batalla」(ff.81v-84r)
[ベルソ(ヴェルスス)]
ヒル・デ・アビラ(確認できる活躍期:1574-1597?):
5声のベルソ第6旋法(ff.38v-43r)
[モテット]
フランシスコ・ゲレロ(1528-1599):
5声のモテット「Pie pater
Hieronyme」(ff.118v-120r)
4声のモテット「Iste Sanctus」(ff.128v-130r)
4声のモテット「Gloriose
confessor」(ff.132v-134r)
4声のモテット「Sancta Maria
sucurre」(ff.122v-124r)
不詳(16世紀):5声のモテット「In
sole」(ff.150v-151r)
[ベルソ]
ヒネス・マルティネス(・デ・ガルベス)(確認できる活躍期:1633-1668):
4声のベルソ第1旋法(ff.151v-152r)
[カンシオン、ビリャネスカとマドリガル
II]
ロドリゴ・デ・セバリョス(1525頃-1581):
4声のビリャネスカ「Dime,
manso viento」(ff.145v-146r)
ペドロ・リモンテ(1565-1627):
4声のカンシオン「Mi ausencia」(カンシオン第6番)(ff.72v-73r)
4声のカンシオン「En este
fertil monte」(カンシオン第1番)(ff.65v-66r)
フランシスコ・ゲレロ:
4声のビリャネスカ「Adios,
verde ribera」(ff.139v-140r)
フアン・ナバロ(1530頃-1580):
4声のマドリガル「Sobre una
pena」(ff.84v-86r)
ペドロ・ゲレロ(1520頃-1586以後?):
4声のマドリガル「Por do
caminare」(ff.146v-147r)
[ベルソ]
ヒル・デ・アビラ:4声のベルソ第6旋法(ff.31V-36r)
[イムノ(ヒムヌス)]
エルナンド・フランコ(1530頃-1585):
4声のイムノ「Monstra te
esse Matrem」(ff.54v-55r)
4声のイムノ「Arbor decora」(ff.55v-57r)
ロドリゴ・デ・セバリョス(1525頃-1581):
5声のイムノ「Nobis datus」(ff.63v-65r)
[ベルソ]
不詳(16世紀):4声のベルソ第5旋法(ff.28v-31r)
[カンシオン、ビリャネスカとマドリガル
III]
不詳(16世紀):4声のカンシオン(ff.77v-81r)
トマ・クレキヨン(1505-1557):
5声のシャンソン「Je suis
ayme」(ff.116v-118r)
5声のシャンソン「Belle,
donne moy」(ff.107v-109r)
フィリップ・ロジエ:5声のカンシオン(ff.101v-103r)
[ベルソ]
エルナンド・フランコ:4声のベルソ第4旋法(ff.27v-28r) |
アンサンブル・ラ・ダンスリー
フェルナンド・ペレス・バレラ
(コルネット[ツィンク]、サックバット、リコーダー、クルムホルン)
フアン・アルベルト・ペレス・バレラ
(チリミア、バホンシリョ、コルネット[ツィンク]、リコーダー、クルムホルン)
ルイス・アルフォンソ・ペレス・バレラ
(サックバット、リコーダー、クルムホルン)
エドゥアルド・ペレス・バレラ
(バホン[ドゥルツィアン]、バホンシリョ、チリミア、リコーダー、クルムホルン)
マヌエル・ケサダ・ベニテス
(サックバット) |
|
録音:2012年11月19-22日、ハエン大聖堂参事会室、ハエン、スペイン
新イスパニア(ヌエバ・エスパニャ)とはメキシコシティに首都を置く副王が統治した新大陸スペイン領地域のこと。この地域にはスペインをはじめヨーロッパ人の楽師たちが送り込まれ、宮廷や教会での演奏を受け持ちました。
彼らは地元民に主として管楽器を教え、現地の楽師を養成していきました。プエブラ(・デ・ロス・アンヘレス)は初代副王により1531年に建設された都市(現メキシコ、プエブラ州都)。16世紀後半には司教座が置かれ、1649年には大聖堂が完成、新イスパニアにおけるキリスト教の中心地となりました。
プエブラ大聖堂が所蔵していた写本は当時の新大陸音楽を伝える貴重な資料。当盤では写本19番に収められた、スペインから持ち込まれたルネサンス音楽の管楽アンサンブル・ヴァージョンが取り上げられています。
1998年に創設されたスペインのピリオド管楽器アンサンブル、ラ・ダンスリーのメンバーは校訂譜ではなく写本のファクシミリ版を見ながら演奏。スペイン系民族楽器を交え雰囲気豊かです。
|
 STRADIVARIUS STRADIVARIUS
|

STR 33933
(2CD)
\3600 |
ルイ・シュポーア(1784-1859):旅のソナタ ヴァイオリンとピアノのための作品集
協奏的二重奏曲ト短調 Op.95
協奏的二重奏曲ヘ長調「旅のソナタ」Op.96
協奏的大二重奏曲ホ長調 Op.112
6つの小二重奏曲「悲哀にして滑稽な」Op.127 |
フランチェスコ・パッリーノ(ヴァイオリン)
ミケーレ・フェドリゴッティ(ピアノ) |
| |
|
|
リュック・フェラーリ(1929-2005):
即興の練習(ピアノのための;1977)
失われたリズムを求めて(ピアノとテープのための;1978) |
チーロ・ロンゴバルディ(ピアノ) |
| |
|
|
ヘンデル(1685-1759):愛の音 リコーダー・ソナタ集
リコーダーとチェンバロのためのソナタ
ハ長調
アリア「La cervetta nei lacci
avvolta」ニ短調
(オペラ「アレッサンドロ」HWV21
より、リコーダーと通奏低音のための)
チェンバロのための組曲 HWV426(1720)から
前奏曲ヘ長調
リコーダーとチェンバロのためのソナタ
ヘ長調
2つのリコーダーと通奏低音のための協奏曲ニ短調
(マルコ・スコルティカーリ編曲)
リコーダーとチェンバロのためのソナタ
ト短調
アリア「Lascia ch'io pianga」(オペラ「リナルド」HWV7
より、
ウィリアム・バベル(1689-1723)編曲、チェンバロのための)
リコーダーとチェンバロのためのソナタ
イ短調
デュエット「Son d'Amore」ハ長調
(オペラ「アレッサンドロ」HWV21
より、リコーダーと通奏低音のための)
リコーダーとチェンバロのためのソナタ
ニ短調 |
マルコ・スコルティカーリ(リコーダー)
ダヴィデ・ポッツィ(チェンバロ)
エストロ・クロマティコ |
 TANIDOS TANIDOS
|
|
|
珠玉のスペイン・チェロ音楽 Vol.4 無伴奏チェロ作品集
ガスパル・カサド(1897-1966):無伴奏チェロ組曲(1926)
ロジェリオ・ウゲ・イ・タゲイ(1882-1956):スペイン組曲第1番(1938)
エンリク・カザルス(1892-1986):
組曲ニ短調−パウ・カザルスへのオマージュ(1982)
エドゥアルド・デ・リオ(1974-):よそ者の組曲−ペドロ・コロストラに献呈(1994) |
エドゥアルド・デ・リオ(チェロ) |
|
録音:2014年1月4日、ロドルフォ・アルフテル専門音楽院室内楽ホール、モストレス、
マドリード県、スペイン
好評の「珠玉のスペイン・チェロ音楽」シリーズ、Vol.3に先だってVol.4が発売されました。エドゥアルド・デル・リオはスペインのマドリードに生まれ、1999年以来2014年現在ロドルフォ・アルフテル専門音楽院室内楽科・チェロ科教授を務めているチェロ奏者。
|
| |
|
|
チェロ楽派のパイオニアたち バリエール、ボッケリーニからポッパーへ
2つのチェロのための音楽
ジャン=バティスト・バリエール(1707-1747):
チェロ・ソナタ集第1巻
から 第1番ロ短調
チェロ・ソナタ集第4巻
から 第4番ト長調(*)
ルイージ・ボッケリーニ(1743-1805):チェロ・ソナタ第6番ハ長調
パブロ・ビダル(?-1808):「チェロの技法と訓練」から
練習曲第26番、第27番
ダーヴィト・ポッパー(1843-1913):組曲
Op.16 |
テンポ・ディ・バッソ
アルド・マタ、エドゥアルド・コンサレス(チェロ) |
|
録音:2013年6月、セゴビア専門音楽院コンサートホール
|
THYMALLUS
在庫限り
|
1990年代後半の短期間のみ活動したレーベル。流通在庫のみの供給となります。 |
|
|
ロマンティシズム
シューベルト(1797-1828):ノットゥルノ変ホ長調
Op.148 D.897(*)
シューマン(1810-1856):おとぎ話
Op.132(+)
メンデルスゾーン(1809-1847):弦楽八重奏曲変ホ長調
Op.20(#) |
スカラ座ソロイスツ
ファブリツィオ・メローニ(クラリネット(+))
ステファノ・パリアーリ(ヴァイオリン(*/#))
アレッサンドロ・フェラーリ、
アンドレア・ペコロ、
ロドルフォ・チビン(ヴァイオリン(#))
ダニーロ・ロッシ(ヴィオラ(+/#))
シモニーデ・ブラコーニ(ヴィオラ(#))
エンリコ・ディンド(チェロ(*/#))
ヤコプ・ルートヴィヒ(チェロ(#))
アンナ・マリア・チゴリ(ピアノ(*/+)) |
| 発売:1997年 |
| |
|
|
ナポリ フルートとギターのための音楽
フェルディナンド・カルッリ(1770-1841):
二重奏曲 Op.104 Nos.1-6/二重奏曲
Op.109
マウロ・ジュリアーニ(1781-1841):グラン・ポプリ
Op.126
セルジオ・レンディーネ(1954-):われらは歓喜す
[Exultamus] |
マッシモ・スカッピーニ(フルート)
マッシモ・ラウラ(ギター) |
| 発売:1997年 |
| |
|
|
モーツァルト・イタリアーノ
モーツァルト(1756-1791):
ディヴェルティメント第11番ニ長調
(オーボエ、2つのホルンと弦楽のための)K.251
ヴァイオリン協奏曲第1番変ロ長調
K.207(*)
交響曲第25番ト短調 K.183 |
ジュリアーノ・カルミニョーラ(ヴァイオリン(*))
マントヴァ室内管弦楽団
ウンベルト・ベネデッティ=ミケランジェリ(指揮) |
| 発売:1997年 |
| |
|
|
ベートーヴェンが26歳の時に書いた2作品
ベートーヴェン(1770-1827):
フルート、ヴァイオリンとヴィオラのためのセレナード
ニ長調 Op.25
(1796/1801)(*)
ピアノと管楽のための五重奏曲変ホ長調
Op.16(1796)(+) |
スカラ座ソロイスツ
ブルーノ・カヴァッロ(フルート(*))
ステファノ・パリアーリ(ヴァイオリン(*))
ダニーロ・ロッシ(ヴィオラ(*))
オーボエ(フランチェスコ・デ・ローザ(+))
ファブリツィオ・メローニ(クラリネット(+))
アレッシオ・アッレグリーニ(ホルン(+))
ヴァレンティーノ・ズッキアッティ(ファゴット(+))
マウリツィオ・ザニーニ(ピアノ(+)) |
| 発売:1997年 |
| |
|
|
J・S・バッハの迷宮 トリオ・ソナタ集
J・S・バッハ(1685-1750):
トリオ・ソナタ ニ短調 BWV1036
ヴィオラ・ダ・ガンバ(チェロ)とチェンバロのためのソナタ
ト短調 BWV1029
トリオ・ソナタ ト長調 BWV1039
音楽の捧げ物 BWV1079 から
トリオ・ソナタ
ハ短調 |
高橋眞知子(フルート)
ヘンク・ルビング(ヴァイオリン)
ウィム・ストラッセル(チェロ)
パトリック・アイルトン(チェンバロ) |
| 発売:1997年 |
TRIART
|


TR 005
(2CD)
\4800 →\4390 |
フラデツ・クラーロヴェー・フィル!?指揮はクカル
ブラームス(1833-1897):
ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲イ短調
Op.102(*)
ピアノ協奏曲第1番ニ短調
Op.15(+) |
イジー・ヴォディチカ(ヴァイオリン(*))
ヤン・パーレニーチェク(チェロ(*))
イトカ・チェホヴァー(ピアノ(+))
フラデツ・クラーロヴェー・フィルハーモニー管弦楽団
オンドジェイ・クカル(指揮) |
|
録音:2013年11月、フラデツ・クラーロヴェー・フィルハーモニー管弦楽団ホール、
フラデツ・クラーロヴェー、チェコ
スメタナ三重奏団をソリストに迎えた録音。ヤン・パーレニーチェク(1957年生まれ)はスメタナ三重奏団の創始者であるヨセフ・パーレニーチェク(ピアニスト;1914-1991)の息子で新生スメタナ三重奏団の創設者。イジー・ヴォディチカ(1988年生まれ)は2014年現在ヤナーチェク・フィルハーモニー管弦楽団ソリスト。イトカ・チェホヴァー(1971年生まれ)はスプラフォンにスメタナのピアノ作品全集を録音しています。
|
 VANITAS VANITAS
|
|
|
消え去りゆく瞬間
ヨハン・ヤコプ・フローベルガー(1616-1667):組曲第18番ト短調(Cm)
アルマンド/ジグ/クラント/サラバンド
ディートリヒ・ベッカー(1623-1707):ソナタ
ニ短調 から レント(Vn/Vg/Vl/Or)(+)
ディートリヒ・ブクステフーデ(1637-1707):主よ、われに御身さえあれば
[Herr, wenn ich nur dich
habe](S/Co/Vn/Vg/Vl/Or)
ルイ・クープラン(1626頃-1661):(組曲)(Cm)
アルマンド/サラバンド/クラントI/クラントII/ジグ
ヨハン・ハインリヒ・シュメルツァー(1623頃-1680):
ソナタ第2番(1664、ニュルンベルク)(Vn/Vg/Vl/Or)(+)
フランツ・トゥンダー(1614-1667):
ああ、主よ、御身の愛する天使たちに
[Ach Herr, lass deine lieben
Engelein](S/Co/Vn/Vg/Vl/Or)(*)
ディートリヒ・ブクステフーデ:
トッカータ ト長調 から フィナーレのオスティナート(Co/Vn/Vg/Vl/Or)(+)
J・S・バッハ(1685-1750):
ゴルトベルク変奏曲 BWV988
から アリア,変奏3,12,17,18,21(Cm)(+)
クラウディオ・モンテヴェルディ(1567-1643):
苦悩が甘美であるならば [Si
dolce il tormento](S/Co/Vn/Vg/Vl/Or)(#)
ディートリヒ・ブクステフーデ:コラール(抜粋)(Or*) |
ラ・レベレンシア
パロマ・ガリェゴ(ソプラノ(S))
パベル・アルミカル(ヴァイオリン(Vn)) マヌエル・パスクアル(コルネット[ツィンク](Co))
ホルヘ・ミロ(ヴィオラ・ダ・ガンバ(Vg))、トル・ホルヘン(ヴィオローネ(Vl))
アンドレス・アルベルト・ゴメス
(チェンバロ(Cm)、ポジティヴ・オルガン(Or)、パイプオルガン(Or*)、ディレクター)
|
|
録音:2012年7-9月,使徒サンティアゴ教会(無印)、跣足カルメル会修道院(*)、
ベレン小聖堂(+)、ガレラ邸のパティオ(#)
アンドレス・アルベルト・ゴメスとスペインの映画監督ダニエル・V・ビリャメディアナ(1975-)の出会いから生まれたバロック音楽ドキュメンタリー映画「De
Occulta Philosophia」(2013)のサウンドトラック盤。おそらく映画の撮影に合わせて様々な場所で録音されています。
バロック時代、生まれた楽音は次の瞬間には消え去ってしまいました。そんなことを思いながら聴き通していただきたいプログラムです。
|
WILLIAM RECORDINGS
|
|
|
パヴェル・ステイドル/
…そして君もイタカに行く… ソロ・ギター・リサイタル
カルロ・ドメニコーニ(1947-):ジミ・ヘンドリックスへのオマージュ
ヤナ・オブロフスカー(1930-1987):前奏曲集
から
モデラート/アダージョ/アレグロ・モデラート/フーガ・アンダンテ
アレグロ・ヴィヴァーチェ
ヤナーチェク(1854-1928):「草陰の小径で」より
ふくろうは飛び去らなかった
ヤナ・オブロフスカー:ゴシックのコラールへのオマージュ
ヤナーチェク:「草陰の小径で」より
散りゆく木の葉
ヤナ・オブロフスカー:前奏曲集
から レント
パヴェル・ステイドル(1961-):…そして君もイタカに行く…
ヤナーチェク:「草陰の小径で」より
おやすみ |
パヴェル・ステイドル(ギター) |
| パヴェル・ステイドルは1961年チェコのラコヴニクに生まれ、ミラン・ゼレンカ、シュチェパーン・ラクらに師事したギター奏者。1982年ラジオ・フランス国際コンクール優勝。1987年オランダを本拠に活動しています。 |
 BERLIN CLASSICS BERLIN CLASSICS
|

BC0300576
\2200 |
R.シュトラウス:管楽器のためのソナチネ
第1番「病人の仕事場から」、第2番「楽しい仕事場」 |
アルモニア・アンサンブル
 |

|


V 5347
\2600→\2390 |
ファジル・サイ/
ベートーヴェン:
ピアノ協奏曲第3番ハ短調
Op.37*
ピアノ・ソナタ第32番ハ短調
Op.111
ピアノ・ソナタ第14番嬰ハ短調
Op.27-2「月光」 |
ファジル・サイ(ピアノ)
hr交響楽団(フランクフルト放送響)*
ジャナンドレア・ノセダ指揮* |
2013年録音
いきなり登場!サイのベートーヴェン
ピアノ協奏曲!
びっくり。
しかも指揮はノセダ!
|
 PIANO CLASSICS PIANO CLASSICS
|


PCL0068
\1300 |
ショパン:練習曲集
練習曲Op.10、Op.25、3つの新練習曲 |
ズラータ・チェチエヴァ(pf) |
日本ではまだ無名だがヨーロッパではすでに幅広く活躍しているチェチエヴァのスカルラッティ。
http://www.youtube.com/watch?v=e0IEnbBCXOQ ここで彼女の爽やかな演奏が少し聴ける。

|
| |

PCL0069
\1300 |
アール・ワイルドによる編曲集第1集
マルチェッロ:アダージョ/
J.S.バッハ:プーランクをたたえて/
ショパン:ラルゲット ピアノ協奏曲第2番より/
フォーレ:夢の後に/
ガーシュウィン:誰か私を見守って、7つの超絶技巧練習曲
(以上すべてワイルド編曲)/
ワイルド:ピアノソナタ2000 |
ジョバンニ・ドリア・ミリエッタ(pf) |
SOLSTICE
|

SOCD 300
\2000 |
チン・ウンスク:ピアノのための6つのエチュード、
P.ブーレーズ:アンシーズ (2001年改訂版)
G,リゲティ:ピアノのためのエチュード〜No15‐No18、
O.メシアン:4つのリズムの練習曲 |
ギル・イェジン(ピアノ) |
録音:2013年9月1日‐5日 ベジエの教会(エロー県)
ギル・イェジン:
ギル・イェジンはソウル大学を卒業後、ドイツ、エッセンのホルクバング芸術大学でディプロマを得て卒業。
その間、韓国国際コンクール、ケラー・オスバル・コンクール(ドイツ)第1位、オルレアン国際コンクールで主要4賞(ナディア・ブーランジェ賞、アルベール・ルーセル賞等)を受賞した。早くから現代音楽に取組み、レパートリーを広げ続けている。
「アンシーズ」に取り組んだとき、ブーレーズの音楽の意味とアイデアについて完璧に習得してブーレーズから賞賛された。
最近ではジュネーヴ劇場等で、エッセン・フィル、デュイスベルガー・フィル、ストラスブール・パーカッション・アンサンブル等々と共演している。
デジパック仕様 |
![]()