≪第77号アリアCD新譜紹介コーナー≫
その5 7/15〜
マイナー・レーベル新譜
歴史的録音・旧録音
メジャー・レーベル
国内盤
映像
|
7/18(金)紹介新譜
<メジャー・レーベル>
 DG DG
|


479 2787
(3CD+DVD)
\6000→\5390 |
ティーレマン/ブラームス:交響曲全集+協奏曲DVD
【CD1】
①交響曲第1番ハ短調作品68
②悲劇的序曲 作品81
【CD2】
③交響曲第2番ニ長調作品73
④大学祝典序曲 作品80
【CD3】
⑤交響曲第3番ヘ長調作品90
⑥交響曲第4番ホ短調作品98
【DVD】
⑦ピアノ協奏曲第1番ニ短調作品15
⑧ピアノ協奏曲第2番変ロ長調作品83
⑨ヴァイオリン協奏曲ニ長調作品77 |
マウリツィオ・ポリーニ(ピアノ⑦⑧)
リサ・バティアシュヴィリ(ヴァイオリン⑨)
シュターツカペレ・ドレスデン
指揮:クリスティアン・ティーレマン |
連綿と受け継がれる伝統が最良の形で実を結んだ一期一会のライヴ!
ティーレマン&シュターツカペレ・ドレスデンのブラームス交響曲全集のCDに、ポリーニのピアノ協奏曲、バティアシュヴィリのヴァイオリン協奏曲のDVDが付いた魅惑のセット。
現代望みうる最高の顔合わせによる超王道のブラームス演奏。
ドイツ音楽の伝統の継承者として確固たる地位を築いている巨匠ティーレマンと、良き時代のしなやかな音色を残しつつ現代的な機能性ももつシュターツカペレ・ドレスデンによるブラームス交響曲全集+序曲集のCD3枚に、既にCDでは発売されているポリーニのピアノ協奏曲2曲の映像とCDとは異なる時期の収録によるバティアシュヴィリのヴァイオリン協奏曲を加えた協奏曲3曲のDVD1枚のセットです。
指揮者、オーケストラ、ソリスト、と3拍子揃った究極の4枚組!
収録:2011年6月(⑦)、2012年10月(①⑤)、2013年1月(②③⑧)、2013年4月(④⑥⑨) ドレスデン、ゼンパーオーパー (ライヴ)
|
| |

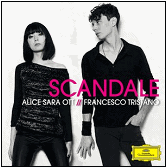
479 3541
\2300→\2090 |
アリス=紗良・オット&フランチェスコ・トリスターノ/
スキャンダル
①ストラヴィンスキー:春の祭典
②R=コルサコフ:
カランダール王子の物語(《シェエラザード》から)
③ラヴェル:ラ・ヴァルス
④トリスターノ:ア・ソフト・シェル・グルーヴ |
アリス=紗良・オット(ピアノ)
フランチェスコ・トリスターノ(ピアノ) |
火花散る、2台ピアノによる奇跡のコラボレーションが輸入盤でも登場!
若手人気ピアニスト2人によるレアなピアノ・デュオ・アルバム。来日公演でも大絶賛を博した二人の火花散るコラボレーションが輸入盤でも入手可能となりました。パリを中心に芸術が華やかだったベル・エポックの時代に一世を風靡したバレエ・リュスをテーマに取り上げたアルバムです。
トリスターノのオリジナル曲も1曲収録しています。
20世紀近代音楽の傑作、バレエ《春の祭典》の1913年の初演は正にスキャンダル。賛成派と反対派の乱闘にまで発展しました。作曲者自身による2台ピアノ版です。
カランダール王子の物語は交響組曲《シェヘラザード》の第2楽章。1888年に作曲され、バレエ・リュスでは1910年に取り上げられています。こちらも作曲者自身による2台ピアノ版です。
ラヴェルのラ・ヴァルスは、「バレエには不向き」とディアギレフに受け取りを拒否され、2人が不仲になるきっかけとなった曲。これもある意味スキャンダル。ルシアン・ガーバンによる2台ピアノ版です。
録音:2013年9月 ベルリン |
| |


479 2465
\2300→\2090 |
《パトリシア・プティボン〜風変わりな美女》
サティ:競馬 /
レオ・フェレ:ジョリ・モーム /
サティ:大リトルネッロ /
プーランク:祭りに出かける若者たちは, パリへの旅,
昨日 /
ロザンタル:夢, 月を釣る者(夢想家) /
サティ:ブロンズの銅像 /
プーランク:ルネ少年の悲しい物語 /
サティ:
ピクニック, そうしようショショット,
ジュ・トゥ・ヴー, カンカン踊り「社交のおえら方」/
フェレ:愛する時 /
サティ:快い絶望 /
フェレ:憂鬱 /
レイナルド・アーン:フォロエ, クロリスに
/
フォーレ:ひそやかに /
プーランク:バベビボビュ /
ロザンタル:
パリ植物園のゾウ, フィドフィド,
動物園の年寄りラクダ /
プーランク:
オルクニーズの歌, 白衣の天使様, ホテル
/
フランシーヌ・コッケンポット:原野のクロッカス
/
フォーレ:ゆりかご |
パトリシア・プティボン(Sp)/
スーザン・マノフ(P),
フラソワ・ヴァレリー(Perc),
クリスチャン=ピエール・ラ・マルカ(Vc),
オリヴィエ・ピィ(Vo),
デヴィッド・ヴェニトゥッチ(アコーディオン), |
彼女の原点に立ち返るような意義深いアルバム
もともとオペレッタとバロック・オペラで独特の存在感を放っていたパトリシア・プティボン。その名前が一躍有名になったのは、2001年にリリースされた「Airs
baroques fran?ais-フランス・バロックアリア集」でした。それからは様々なオペラのタイトル・ロールや、宗教曲を歌い好評を博してきた彼女。今回は「フランス歌曲集」を歌うことで、彼女の原点に立ち返るような意義深いアルバム作りがなされています。
選曲が飛び切り秀逸で、サティやプーランクの軽妙な歌曲や、フォーレの奥ゆかしい歌、めったに耳にすることのないロザンタルのユーモラスな歌曲、そしてレオ・フェレの曲まで自由自在。19世紀末、パリのキャバレーの雰囲気から60年代の憂鬱までを幅広くカバーしています。
ここでプティボンは長年のパートナーであるピアニスト、スーザン・マノフをはじめ、気の置けないゲストたちを集め、親密な世界を作り上げています。フランスの「メロディ」から「シャンソン」への変遷を感じさせる多面的な魅力を持った最高の1枚です。プティボン、セ・シ・ボン! |
| |

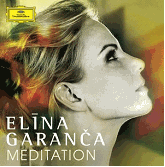
479 2071
\2300→\2090 |
《エリーナ・ガランチャ〜メディテーション》
グノー:聖ツェツィーリアのための荘厳ミサ〜サンクトゥス
/
グノー:悔悟 /
ユージス・プラウリニュシュ:御招霊 /
マスカーニ:カヴァレリア・ルスティカーナ〜
レジーナ・チェリ(復活祭の合唱) とアヴェ・マリア
/
ウィリアム・ゴメス:アヴェ・マリア /
モーツァルト:証聖者の荘厳晩課K.339〜ラウダーテ
/
ビゼー:アニュス・デイ /
プッチーニ:サルヴェ・レジナ /
アダン:オー・ホーリー・ナイト(さやかに星はきらめき)
/
ヴァスクス:静寂の歌〜Dusi dusi, Paldies
tev vela saule /
アレグリ:ミゼレーレ /
カッチーニ:アヴェ・マリア |
エリーナ・ガランチャ(Sp)/
カレル・マーク・チチョン(指揮)
ザールブリュッケン・ドイツ放送フィルハーモニー管弦楽団,
シグヴァルズ・クラーヴァ(指揮)
ラトヴィア放送合唱団, |
彼女のルーツでもある極めて個人的なアルバム
ラトヴィア出身のメゾ・ソプラノ歌手エリーナ・ガランチャ。彼女の父は合唱団の指揮者で、母は声楽歌手&教師という音楽的に恵まれた環境で育ちました。
このアルバムは彼女が幼いころから耳にしていた懐かしい音楽を集めたもの。心の平穏、永遠の憧れ、そして彼女のルーツでもある極めて個人的なアルバムでもあるのです。
ラトヴィアの音楽アカデミーで学び、若き音楽家として合唱団でも歌っていたという彼女は、オペラのアリアだけでなく、宗教作品や合唱曲も得意としていて、このアルバムで共演したラトヴィア放送合唱団の高い技術は、彼女の美質を存分に引き出すことに成功しました。
ここではよく知られたモーツァルトやアダンの「オー・ホーリー・ナイト」などを始め、アレグリの「ミゼレーレ」の新しいアレンジなど絶妙の曲が選ばれ、ラトヴィアの作曲家による作品も2曲収録しています。
指揮は彼女の夫であるチチョン。DGレーベルにおける2枚目の共演となります。 |
 DECCA DECCA
|


478 6771
\2300→\2090 |
ネルソン・フレイレ/シャイー&ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管
ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第5番《皇帝》&ソナタ第32番
ベートーヴェン:
①ピアノ・ソナタ第32番ハ短調作品111
②ピアノ協奏曲第5番変ホ長調作品73《皇帝》 |
ネルソン・フレイレ(ピアノ)
ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団
指揮:リッカルド・シャイー |
祝70歳、円熟の境地のベートーヴェン!
来日記念盤。巨匠ピアニスト、フレイレがシャイー&ゲヴァントハウス管と《皇帝》を録音しました。
ベートーヴェン最後のソナタをカップリングした魅力的な選曲、滋味あふれるタッチで奏でられた馥郁たる一枚です。今年秋の来日公演では、ブラームスの協奏曲第2番を演奏する予定です。
今年3月に久々の来日を果たし、シャイー指揮ゲヴァントハウス管と共にベートーヴェンの《皇帝》を演奏し、その健在ぶりを日本のファンにしめしてくれたブラジル出身のピアニスト、ネルソン・フレイレ。
このアルバムは、日本公演直後に録音された《皇帝》と、ベートーヴェンのソナタ第32番を収録しています。日本公演でも披露したダイナミックなフレージングで、巨匠と呼ばれるにふさわしい、風格のある堂々たる演奏を聴かせてくれます。
録音:2014年2月21-23日 ベルリン、テルデックス・スタジオ(①) 3月5-8日 ライプツィヒ、ゲヴァントハウス(②)
■フレイレ来日公演(ゲルギエフ指揮マリインスキー歌劇場管弦楽団とブラームスのピアノ協奏曲第2番を演奏予定)
10/12 金沢、10/14 東京 |
| |

478 7605
\2300 |
《プメザ・マトキシザ〜Voice Of Hope》
プッチーニ:
ジャンニ・スキッキ〜私のお父さん /
トゥーランドット〜お聞きくださいご主人様
/
モーツァルト:ドン・ジョヴァンニ〜薬屋の歌
/
Thula Baba (Hush, My Baby ) / Malaika (My
Angel ) /
Pata Pata / The Naughty Little Flea / Vedrai,
carino /
Umzi Watsha / Saduva / Holilili / The Click
Song /
Iya Gaduza / Lakutshon’Ilanga (When The
Sun Sets ) /
Freedom Come All Ye |
プメザ・マトキシザ(Sp),
イアン・ファーリントン(指揮)
オーロラ・オーケストラ |
DECCAレーベルに新星のごとく登場!
南アフリカ出身のソプラノ歌手プメザ・マトキシザのデビュー・アルバムです。
彼女は1980年、アパルトヘイトで揺れる南アフリカで生まれ、暴動、混乱を避け、安全な地へ逃れるために、彼女の母に連れられてケープタウンに移住します。その地で偶然耳にしたラジオでオペラの素晴らしさに開眼しました。
最終的に彼女は、アパルトヘイト後のマンデラ政権下、南アフリカの音楽大学に入学し、歌手になるべく勉強を始めました。
その際、南アフリカの作曲家ケヴィン・ヴォランは彼女の特徴的な声の美しさを見出し、彼女のためにロンドン行きの飛行機のチケットを手配、彼女は王立音楽院のオーディションを受けるとともに、コヴェント・ガーデンでヤング・アーティスト・プログラムへ参加することとなりました。
現在の彼女はシュトットガルト歌劇場でスター歌手の座を射止めています。ここでの彼女は、プッチーニやモーツァルトのお馴染みのアリアでその素晴らしい声を披露するとともに、祖国の歌の数々を熱唱。その溢れる才能を惜しげもなく披露しています。【録音】2013年8月,
ロンドン、アビイ・ロード・スタジオ |
| |
478 7646
(4CD)
\3600 |
《ヨナス・カウフマン〜50 Great Arias》
【CD1】
プッチーニ:歌劇「ラ・ボエーム」〜冷たい手を,
ビゼー:歌劇「カルメン」〜おまえの投げたこの花を,
フロトー:歌劇「マルタ」〜かくも淑やかに,
プッチーニ:歌劇「トスカ」〜星は光りぬ,
ヴェルディ:歌劇「ドン・カルロ」〜
僕は彼女を失った!……僕は彼女を目にし、そして彼女の微笑みが,
ウェーバー:歌劇「魔弾の射手」〜
この苦しみは希望を奪い……森を通り、野を越えて,
ヴェルディ:歌劇「椿姫」〜
彼女が離れていては…私の熱い心の…おお、申しわけないことだ,
マスネ:歌劇「マノン」〜ああ、消え去れ、あまりにいとしい面影よ,
ヴェルディ:歌劇「リゴレット」〜
あの娘は攫われてしまった!……突然の危難に遭って,
グノー:歌劇「ファウスト」〜
私を貫いているのはなんという未知の不安なのだろう……おお!清らかな住居よ,
ワーグナー:楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」〜
朝はばら色に輝きて(優勝の歌),
ベルリオーズ:劇的音楽「ファウストの劫罰」〜
広大で奥知れぬ崇高な自然よ(自然への祈願),
マスネ:歌劇「ウェルテル」〜春風よ、なぜ私を目覚めさせるのか/
【CD2】
ワーグナー:歌劇「ローエングリン」〜遥かかなたの国へ,
かわいい白鳥よ!,
モーツァルト:歌劇「魔笛」〜何と美しい絵姿,
童子たちの叡智の教えを,
シューベルト:歌劇「フィエラブラス」〜
どうしてぼくを苦しめるのだ、不幸な運命よ…心の底で,
シューベルト:歌劇「アルフォンソとエストレッラ」〜
もしも、それが既に運び始めるも…そして、その後の私の心が必要とするもの,
ベートーヴェン:歌劇「フィデリオ」〜神よ!ここは何という暗さだ,
ワーグナー:楽劇「ワルキューレ」〜冬のあらしは去り、こころよい月となった,
ワーグナー:舞台神聖祝典劇「パルジファル」〜
アンフォルタス!あの傷!あの傷!,たった一つの武器だけが/
【CD3】
ザンドナイ:歌劇「ジュリエッタとロメオ」〜ジュリエッタよ、私はロメオ,
ジョルダーノ:歌劇「アンドレア・シェニエ」〜
ある日、深くすみ渡った青い空に, 五月の美しい日のように,
チレア:歌劇「アルルの女」〜ありふれた話(フェデリコの嘆き),
レオンカヴァッロ:歌劇「ラ・ボエーム」ミュゼッテ!…愛らしい頭が,
レオンカヴァッロ:歌劇「道化師」〜芝居をするか!…衣裳を着けろ,
マスカーニ:歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」〜
皆さん、ここに居あわせたんだから、一杯やろうじゃありませんか!,
マスカーニ:歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」〜
母さん!母さん、このぶどう酒は強いね,
ボーイト:歌劇「メフィストーフェレ」〜野から牧場から,
最後のときがやってきた,
ジョルダーノ:歌劇「フェドーラ」〜愛さずにはいられぬこの思い,
チレア:歌劇「アドリアーナ・ルクヴルール」〜
心身共にくたくたで, 母の優しく微笑む面影を,
ポンキエッリ:歌劇「リトアニア人」〜こうなれば、この最後のお情けを,
ポンキエッリ:歌劇「ジョコンダ」〜空と海,
レフィチェ:雲の影,
ジョルダーノ:歌劇「アンドレア・シェニエ」〜僕の悩める魂も/
【CD4】
ワーグナー:
楽劇「ワルキューレ」〜父上は私に刀を約束してくださった,
楽劇「ジークフリート」〜あいつが俺の父親でないとは,
歌劇「リエンツィ」〜全能の父よ、私を見護り下さい!,
歌劇「タンホイザー」〜今まで感じなかったほどの,
楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」〜静かな炉端で,
歌劇「ローエングリン」〜
遠い国に、あなたがたの近づき得ぬところに(カット無しオリジナル版),
ヴェーゼンドンクの5つの歌 |
ヨナス・カウフマン(T)/
マルコ・アルミリアート(指揮)
プラハ・フィルハーモニー管弦楽団[CD1]
クラウディオ・アバド(指揮)
マーラー・チェンバー・オーケストラ[CD2]
アントニオ・パッパーノ(指揮)
サンタ・チェチーリア国立アカデミー管[CD3]
ドナルド・ラニクルズ(指揮)
ベルリン・ドイツ・オペラ管弦楽団 |
21世紀の「キング・オブ・テノール」のヨナス・カウフマン。当代随一の人気テノール歌手であり、欧米では、彼が出演するだけでチケットが完売になるほど、確固たる地位と人気を確立しています。
その恵まれた容姿と、抜群の歌唱力、演技力により、世界中のオペラハウスで聴衆を虜にしいます。
このアルバムは、彼がデッカに録音したオペラ・アリア4タイトルを1セットに収めたものです。[CD1]はデッカからのデビュー・アルバム。ドイツ・オペラからイタリア・オペラまで、幅広いジャンルをカバーする表現力の持ち主で、本作でもその実力を見せつけています。
[CD2]は、自身のルーツでもあるドイツ・オペラ・アリア集。「神の子」「王子」「騎士」など劇中に登場する英雄たちの歌を、アバド指揮の好サポートの下でじっくりと歌い上げています。[CD3]は、ドイツものからイタリアものまで幅広いレパートリーをこなすカウフマンならでは選曲で、声そのものの魅力と持ち前の表現力で魅了してくれます。[CD4]は、2009年ミュンヘンでの「ローエングリン」でワーグナー歌手としての地位を確固たるものとしたカウフマン。翌2010年にはバイロイト音楽祭に出演、2012年にはメトロポリタン歌劇場の「ワルキューレ」でもジークムント役を歌い、世界中の歌劇場からオファーが絶えない活躍を続けています。作曲家生誕200年を記念しての録音で、有名な「ローエングリンの名乗り」では、通常カットされる長大な「グラール語り」を完全収録し、女声のために書かれた「ヴェーゼンドンクの5つの歌」にも挑戦しています。
【録音】2007年[CD1], 2008年[CD2], 2010年[CD3],
2012年[CD4] |
<映像>
 DG(映像) DG(映像)
|


73 5149
(BD)
\4600→\4190 |
ボロディン:歌劇『イーゴリ公』(全曲) |
ジャナンドレア・ノセダ指揮
メトロポリタン歌劇場管弦楽団と合唱団
イルダール・アブドラザコフ(イーゴリ公)、
オクサナ・ディーカ(ヤロスラーヴナ)、
アニータ・ラチヴェリシュヴィリ(コンチャーコヴナ)、
ステファン・コツァン(コンチャーク)
セルゲイ・セミシュクール(ヴラヂーミル)、
ミハイル・ペトレンコ(ガーリツキィ公)、他
演出:ディミトリ・チェルニアコフ |

73 5146
(2DVD)
\7600→\6990 |
あまり上演される機会のない作品の、初めて納得のキャストと演出
現在、「だったん人の踊り」(最近では「ボロヴェツ人の踊り」と呼ぶことも多い)のメロディだけが知られるボロディンのオペラ「イーゴリ公」。ほとんどの人は粗筋すらも知らないと思われる作品です。
もともと中世ロシアの叙事詩「イーゴリ軍記」を元にした、東スラヴ人のイーゴリ・スヴャトスラヴィチ公の勇壮な戦いをモティーフに、ボロディンが作曲を始めたものの、完成させることなく逝去。そのためリムスキー・コルサコフとグラズノフが完成版を作成した4幕からなるオペラです。
版の問題などのため、あまり上演される機会のないこの作品、今回初めて納得のキャスト、演出での上演が映像となって発売されます。
ロシアの名バス歌手、イルダール・アブドラザコフによる記念碑的名唱が光るタイトル・ロール。イーゴリ公の心理を夢のように描き出したドミトリ・チェルニアコフの演出。
ジャナンドレア・ノセダが指揮するオーケストラの豪壮な音色。これは文句なし。オペラ好き必見の映像です。
【収録】2014年3月1日, メトロポリタン歌劇場でのライヴ
BD:
Picture format: 1080i / 60i / 16:9 / colour
Audio Format: PCM Stereo / DTS-HD Master
Audio 5.1
Region : All 収録:202分 (オペラ本編:192分/METのバックステージ:約10分)
字幕: English, German, French, Spanish,
Chinese, Korean
DVD:
Picture format: 16:9 / colour / NTSC
Audio format: PCM Stereo / DTS 5.1
Region: All |
| |

73 5162
(3BD)
\8400→\7590 |
《アンナ・ネトレプコ〜ライヴ・フローム・ザルツブルク音楽祭》
ヴェルディ:歌劇『椿姫』(全曲)
収録:2005年8月、ザルツブルク、祝祭大劇場でのライヴ |
アンナ・ネトレプコ(ヴィオレッタ),
ロランド・ヴィラゾン(ジェルモン),
トーマス・ハンプソン(ジョルジョ), 他
ウィーン国立歌劇場合唱団
カルロ・リッツィ(指揮)
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
演出:ヴィリー・デッカー,
衣装:ヴォルフガング・グスマン
照明:ハンス・テルシュテーデ,
振付:アトール・ファーマー
映像監督:ブライアン・ラージ, |
モーツァルト:歌劇『フィガロの結婚』(全曲)
収録:2006年7〜8月、ザルツブルク、モーツァルトハウスでのライヴ |
イルデブラント・ダルカンジェロ(フィガロ),
アンナ・ネトレプコ(スザンナ)
ドロテア・レーシュマン(伯爵夫人),
ボー・スコウフス(アルマヴィーヴァ伯爵)
クリスティーネ・シェーファー(ケルビーノ),
他
ウィーン国立歌劇場合唱団
ニコラウス・アーノンクール(指揮)
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
演出:クラウス・グート,
装置・衣装:クリスティアン・シュミット
映像監督:ブライアン・ラージ |
プッチーニ:歌劇『ボエーム』(全曲)
収録:2012年8月、ザルツブルク、祝祭大劇場でのライヴ |
アンナ・ネトレプコ(ミミ),
ピョートル・ベチャワ(ロドルフォ)
ニーノ・マチャイゼ(ムゼッタ),
ウィーン国立歌劇場合唱団
ダニエーレ・ガッティ(指揮)
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
演出:ダミアノ・ミキエレット,
映像監督:ブライアン・ラージ |
|
73 5157
(4DVD)
\6800→\6190 |
《アンナ・ネトレプコ〜ライヴ・フローム・ザルツブルク音楽祭》
上記と同内容のDVD |
【収録】2005, 2006, 2012年 ザルツブルク音楽祭でのライヴ
ネトレプコがザルツブルク音楽祭に出演したライヴ、3タイトルをセットにしたものです。
運命を表す大きな時計と、赤いドレス。これらが素晴らしい対比をなすシンプルで考え抜かれた演出による2005年の『椿姫』では、彼女の初々しい美貌と卓越した表現力、そしてビリャソンの純朴なアルフレードが夢のような舞台を作り上げたことが話題となった映像。
スザンナ役をまるで小悪魔的な可愛らしさで歌うネトレプコの姿を堪能できる2006年の『フィガロの結婚』では、台本には登場しないはずの天使が大活躍することと、アーノンクールの決して軽快とは言えない重厚な指揮が話題となった映像。
そしてその7年後、結婚、出産など私生活でも充実を重ねた彼女による『ボエーム』ではキッチュで現代的な装置を使った演出ながら、正統的な彼女の歌唱と、ベチャワの美声、そしてガッティのアグレッシブな指揮が話題となった映像。
この3種類のネトレプコの映像を見ることで、彼女の歌手としての成熟を知るとともに、ザルツブルク音楽祭の変遷の一端を確認するという興味深いセットです。もちろんBlu-rayの高画質も素晴らしいものです。 |

7/17(木)紹介新譜
マイナー・レーベル新譜
 BONGIOVANNI BONGIOVANNI
|
|
|
ニコリーニの「双子の姉妹」世界初録音!
ニコリーニ:「双子の姉妹」 |
伊藤佐智馨(S ジャンニーナ)
アロイザ・アイセンベルク(S ジューリア)
イ・ミンホ(Br ル・ブロ氏)
シャラン・ケリー(T アルリーゴ伯爵)
ダヴィデ・ロッカ(Bs トラモンターナ侯爵)
キム・ソンチョン(T ボンベッタ氏)
ミモザ・ラーマ(Ms ジャコメッタ)
イ・ドンヨプ(Br ティンパノ)
ロベルト・トロメッリ(指揮)
アミルカーレ・ザネッラ管弦楽団 |
日本人ソプラノ伊藤佐智馨が主役プレ・ロッシーニ世代の人気作曲家、ニコリーニの「双子の姉妹」もちろん世界初録音!
録音:2012 年4 月28 日、ピアチェンツァ/92’
36”
ジュゼッペ・ニコリーニ(1762—1842)は、チマローザより12
歳下の世代のイタリアの作曲家。1790 年代から活動を始め、19
世紀初頭には人気の高いオペラ作曲家でしたが、1820
年代に30 歳も年下のロッシーニが大人気になると、徐々にオペラの活動から離れ、1830
年代以降は宗教音楽を活動の主に据えます。今日での上演は極めて稀で、オペラのCD
はBongiovanni から発売された「確かめられた嫉妬」(GB2415
2CD)と「水車屋の恋」(GB2443 2CD)があったくらいです。「双子の姉妹」は、1808
年にローマで初演された喜劇オペラ。オリジナルは2
幕仕立てでしたが、後に1 幕に直され、こちらが人気を博しました。ここでも1
幕版が用いられています。
ニコリーニの生地ピアチェンツァでは度々彼のオペラが上演されており、これも2012
年4 月28 日、ピアチェンツァ市立劇場での上演のライヴ録音です。
主役のジャンニーナを、日本人ソプラノ、伊藤佐智馨
(いとうさちか)が歌っています。伊藤は神奈川県出身、ピアチェンツァで学び、イタリアやスペインで活動しています。
ニコリーニ「双子の姉妹」 簡単なあらすじ
トラモンターナ侯爵にはジューリアとジャンニーナという双子の姉妹の姪がいた。侯爵はおバカなジューリアを可愛がる一方、利発なジャンニーナは召使同然に扱っていた。ジューリアはアルリーゴ伯爵と愛し合っているのだが、トラモンターナ侯爵はジューリアを若いパリの侯爵ル・ブロ氏と結婚させることにしてしまった。それを聞いたジャンニーナは、ル・ブロ氏が双子の存在を知らないことを利用して、自分が結婚相手として振舞うことを思いつく。ル・ブロ氏が到着すると、ジャンニーナは首尾よく彼の気持ちを引き付けてしまう。アルリーゴ伯爵はジューリアがル・ブロ氏と結婚するというので立腹する。ル・ブロ氏は、ジューリアからは愛を拒まれ、ジャンニーナからは愛を確かめられ、二人を同一人物と思っているのですっかり混乱してしまう。ようやくトラモンターナ侯爵は事態を飲み込み、ジューリアとアルリーゴ伯爵、ジャンニーナとル・ブロ氏の結婚を認める。 |
| |
GB 2300
(2CD →1CD 価格)
【値下げ再プレス】
\2500
|
「不可触民の男」唯一の録音が値下げして再登場!!
ドニゼッティ:「不可触民の男」 |
アレッサンドロ・ヴェルドゥッチ(アケバレ)
パトリツィア・チーニャ(S ネアラ)
マルツィン・ブロニコウスキ(ザレーテ)
フィリッポ・ピーナ・カスティリョーニ(イダモーレ)
アンドレア・ブラジョット(エンプサーレ)
ナーラ・モンテフスコ(ザイデ)
マルコ・ベルドンディーニ(指揮)
プロ・アルテ・マルケ管弦楽団
メツィオ・アゴスティーニ合唱団 |
ドニゼッティの問題作、インドの悪名高い差別制度を扱った「不可触民の男」唯一の録音が値下げして再登場!!
録音:2001 年4 月、ファエンツァ/録音:2001
年4 月、ファエンツァ
ドニゼッティの問題作の唯一の全曲録音が廉価復活。「不可触民の男」は、1829
年1 月にナポリで初演されたオペラ。不可触民
paria というのは、悪名高いインドのカースト制度でカーストにすら入れられない最下層民ダリットのことで、現代に至るまで非常に過酷な差別に遭っています。これに取材したフランスの作家カシミール・ドラヴィーニュの悲劇を原作とするオペラです。
バラモンの高僧アケバレの娘ネアラは、英雄イダモーレと相愛だが、イダモーレは不可触民の老人ザレーテの行方不明の息子だった。イダモーレと再会したザレーテは、自分たちを弾圧してきた支配層に属するネアラと息子が愛し合っていることに腹を立てる。悩んだイダモーレはネアラに自らの素性を明かすが、彼女の愛は変わらない。二人の結婚式が執り行われていることを知ったザレーテは、乱入しようとして捕らえられ処刑されることになり、イダモーレは皆の前で自分がザレーテの息子だと明かし父と運命を共にする、というもの。
初演はほどほどの成功で、その後埋もれてしまっていました。ドニゼッティはこのオペラの素材の多くを1830
年代の作品に再利用しています。
この唯一の録音では、イタリアを中心に活躍するパトリツィア・チーニャ、ポーランド出身のバリトンでドイツで活躍するマルツィン・ブロニコウスキなど、実力のある歌手が歌って聞き応えのあるものになっています。
なお再発にあたって、解説と伊英対訳はホームページからダウンロードする仕様になっています。 |
 CHALLENGE CLASSICS CHALLENGE CLASSICS
|
|
|
R.ワーグナー(1813-1883):交響曲&管弦楽作品集
1-4. 交響曲 ハ長調
〔録音:2010年6月8, 10日〕
「トリスタンとイゾルデ」より
5.「夜の歌」 6.「イゾルデの愛の死」(ヘンク・デ・フリーハー編曲)
〔録音:2013年4月16日〕
7. ジークフリート牧歌
〔録音:2010年6月10日〕 |
エド・デ・ワールト(指揮)
オランダ放送フィルハーモニー管弦楽団
ファン・デ・オンレープ音楽センター
スタジオ5(すべてセッション録音) |
至高のワーグナー指揮者エド・デ・ワールト最新盤!
77’38”
最高のワーグナー指揮者の一人、エド・デ・ワールトの最新盤。録音機会の少ない交響曲ハ長調が収録されているのも注目です。
ワーグナーの交響曲ハ長調は1832 年の夏、約6
週間にわたって書かれたもので、ワーグナー唯一の完成された交響曲で、ベートーヴェンの影響も色濃く見られる若書きながら、随所に後の劇音楽を思わせる様々な効果に満ちた力作。
エド・デ・ワールトがそれぞれの素材を巧みに響かせ、若きワーグナーの力に満ちた作品を見事にまとめています。
「トリスタンとイゾルデ」からの抜粋の管弦楽編曲は、作曲家でオランダ放送フィルの打楽器奏者でもあるヘンク・デ・フリーハー編曲によるもの。彼は、CC
72338 でワーグナー作品を管弦楽に編曲した「オーケストラル・アドヴェンチャー」の編曲も手掛けています。今回もどのようなアレンジの技量を効かせているか、注目です。
ワーグナーの妻、コジマへのプレゼントであるジークフリート牧歌も、優しさと愛情に満ちた演奏となっています。 |
LES ARTS FLORISSANTS
|
|
|
クリスティ&レザール・フロリサン
ラモー氏の庭園で
ラモー:
「イポリートとアリシ」から
「エベの祭典」第1アントレ「詩」から
「ダルダニュス」から
「優雅なインドの国々」から
カノン「笑いから離れ」
カノン「起きろ、際限なく寝る奴め」
ドーヴェルニュ:
「死に行くエルキュル」から
「ヴェネツィアの女」から
カンプラ:「優雅なヨーロッパ」第2アントレ「フランス」から
モンテクレール:「ジェフテ」プロローグから
ラコ・ド・グランヴァル:カンタータ「何もない」
グルック:「改心した酒飲み」から |
|
ダニエラ・スコルカ(S)
エミリ・ルナール(Ms)
ベネデッタ・マッズカート(A)
ザカリー・ワイルダー(T)
ヴィクトル・シカール(Br)
シリル・コスタンツォ(Bs)
ウィリアム・クリスティ(指揮)
レザール・フロリサン |
ラモー生誕330周年記念公演が、没後250周年にCDに!クリスティと仲間たちによる「ラモー氏の庭園で」
録音:2013 年3 月29、30、31 日、パリ/DDD、81'
03
ジャン=フィリップ・ラモー(1683—1764)は、2013
年が生誕330 周年でした。その2013 年の3 月に、ウィリアム・クリスティ率いるレザール・フロリサンが「ラモー氏の庭園で」と題された、ラモーを中心とした演奏会を催しました。ラモーの他に、ミシェル・ピニョレ・ド・モンテクレール(1667—1737)、アンドレ・カンプラ(1660—1744)、ニコラ・ラコ・ド・グランヴァル(1683—1764)、アントワーヌ・ドーヴェルニュ(1713—1797)、クリストフ・ヴィルバルト・グルック(1714—1787)と、ラモーの前後の世代の作曲家を交えて、17
世紀終わりから18 世紀半ばまでのパリのバロックオペラの多様な面白さを浮かび上がらせています。
この演奏会は、「声の庭園」というシリーズの6
回目に当たるもの。このシリーズでは毎回、クリスティとポール・アグニューによって指導された若く優秀な歌手が起用されています。今回も逸材揃い。ダニエラ・スコルカは1987
年、イスラエルのハイファ生まれのソプラノ。潤いのある美声に品のある情熱が乗った卓越した歌手です。
エミリ・ルナールは、英国タプロー生まれのメッゾソプラノ。しっとりとした落ち着きのある歌が見事。ベネデッタ・マッズカートはイタリアのメッゾソプラノ、アルト。まだ20
代前半という若さですが、大変に注目されています。
ザカリー・ワイルダーは1984 年、米国、サンタモニカ生まれのテノール。現在はパリ在住で、すでにバロック声楽作品でかなり活躍しています。
ヴィクトル・シカールは、1987 年、フランス西部のラ・ロシェル生まれのバリトン。美声で多くのコンクールを征した逸材で、ことにモーツァルトのバリトン役で人気があります。
シリル・コスタンツォは1985 年、トゥーロン生まれ。地理学を学んでから歌手に転向した人で、数年で急速に活躍が広がっています。
クリスティとレザール・フロリサンの演奏については「素晴らしい!」の一言で十分でしょう。長年フランス・バロックオペラの最前線に立ち続けているクリスティならではの高みが楽しめます。
美麗なケースに、CD と解説冊子(歌詞の仏英対訳付き)の他、1966
年生まれのフランスの作家、アドリアン・ゲッツによる「ノルマンディの庭園で」(仏英語)の冊子も収められています。 |
 SUPRAPHON SUPRAPHON
|
|
|
ゼレンカ:聖週間のための預言者エレミアの哀歌
ZWV53 |
ダミアン・ギヨン(テノール)
ダニエル・ヨハンセン(テノール)
トマーシュ・クラール(バス)
ヤナ・セメラードヴァー(指揮)
コレギウム・マリアヌム |
瞑想的にして劇的。天国的に絶美な音世界、ゼレンカの「預言者エレミアの哀歌」第一人者セメラードヴァーら生地チェコ勢による演奏で
収録:2014 年5 月21、22 & 26 日/鎖の下の聖母マリア教会、プラハ/DDD、ステレオ、74’15”
預言者エレミアのものとされる、旧約聖書の「哀歌」は、中世以来、アレグリ、ラッスス、ビクトリア、タリス、ドゥランテ、アレッサンドロ・スカルラッティなど数多くの作曲家たちによって創作のテーマとして扱われてきましたが、なかでも重要な位置を占めるのが、ゼレンカ(1679-1745)作による「エレミアの哀歌」です。
ドレスデン宮廷時代に作曲された「エレミアの哀歌」(1722)は、ゼレンカ初期の傑作のひとつで、プラハで書かれた「墳墓」(SU4068)、レスポンソリウムと並んで、聖週間のための作品です。
「エレミアの哀歌」は、テネブレの典礼(暗闇の礼拝)の一環として演奏されますが、ゼレンカは、瞑想的な様相と力強く劇的な説示とを結びつけることに成功しています。
また、ゼレンカの特異な楽器法の傾向が、たとえば、独奏ヴァイオリン、ファゴット、シャリュモー(今日のクラリネットに似た楽器)を用いた最後の哀歌にはっきりとみてとれます。
なお、ゼレンカは、各日の第一徹夜課の2 つのルソンにのみ音楽を付けているので、この録音では、ドレスデン宮廷において、しばしば演奏されたように、第3
ルソンには「グレゴリオ聖歌」を用いています。
前作(ゼレンカの「墳墓」)に引き続いて、天上の世界をおもわせる絶美の内容に挑むのは、ゼレンカの生地チェコ有数のオリジナル楽器アンサンブル、ヤナ・セメラードヴァー率いるコレギウム・マリアヌム。ダミアン・ギヨンをはじめ、ソリスト陣もきら星のごとき顔ぶれで、アルバムに華を添えています。 |
 NIMBUS ALLIANCE(CD−R) NIMBUS ALLIANCE(CD−R)
|


NI 6257
(CD-R)
\2400 →\2190 |
フェルツマンの、ベートーヴェン!新録音は《ディアベッリ変奏曲》!
ベートーヴェン:
ディアベッリの主題による33の変奏曲ハ長調Op.120
アンダンテ・ファヴォリ ヘ長調WoO.57 |
ウラディミール・フェルツマン(ピアノ) |
旧ソ連での音楽活動禁止、アメリカへの亡命、レーベルの移籍など、幾多の試練を乗り越えた孤高の天才ピアニスト、ウラディミール・フェルツマン。
バッハの主要鍵盤作品の録音、ハイドンのソナタ集、ロマン派から近現代のスクリャービンまで、幅広いレパートリーを誇り、独自のアプローチで聴衆を魅了してきた。
今作の「ディアベッリ変奏曲」もフェルツマンの、情熱溢れる別格の演奏。
2012年9月24日−25日の録音。
※Nimbus Allianceはレーベル・オフィシャルのCD-R盤となります。 |
| |

NI 6261
(CD-R)
\2400 |
リード・トーマス:ピアノ&室内楽作品集
オーボエ、弦楽三重奏とピアノのための《スキャット》
6つのピアノ練習曲
2つのヴァイオリンのための《ダブル・ヘリックス》
ピッコロと金管のためのファンファーレ
《リング・フロウリッシュ・ブレイズ》
ピアノ三重奏のための《ア・サークル・アラウンド・ザ・サン》
イングリッシュ・ホルンと2つのヴァイオリンのための
《ピルグリム・ソウル》
ソロ・ピアノのための《トレース》
ヴァイオリンとピアノのための《トフト・セレナーデ》
独奏ピアノのための《スターライト・リボンズ》(世界初録音) |
ウォールデン・チェンバー・プレイヤーズ
エイミー・ブリッグス(ピアノ)
ジャネット・サング(ヴァイオリン)
ユエン・チン・ユイ(ヴァイオリン)
南メソジスト大学ウィンド・アンサンブル
ジャック・デラニー(指揮)
ロバート・ウォルターズ(イングリッシュ・ホルン)
ステファン・ハーシュ(ヴァイオリン)
スティーヴ・ローズ(ヴァイオリン)
平田真希子(ピアノ)
チャールズ・モーリー(ヴァイオリン)
フランク・ホワン(ヴァイオリン)
ダニエル・シュロスバーグ(ピアノ) |
| アメリカの現代音楽を代表する女流作曲家、オーガスタ・リード・トーマス(b.1964)の録音シリーズ第2弾は、ピアノ&室内楽作品集。今作では、アメリカを拠点に日本でも演奏活動を行う日本人女流ピアニスト、平田真希子の参加もポイント。 |
| |

NI 6256
(CD-R)
\2400 |
コンポーザー=ヴァイオリニスト、ウィリアム・ジンの弦楽四重奏作品集
ジン:
エリー・ヴィーゼル
弦楽四重奏第1番
コル・ニドライ・メモリアル |
ウィハン弦楽四重奏団 |
コンポーザー=ヴァイオリニスト、ウィリアム・ジン(b.1924)の弦楽四重奏作品集。演奏は1985年に結成され、1991年のロンドン国際弦楽四重奏コンクールで第1位を受賞。幅広いレパートリーに定評があるチェコの実力派クヮルテット、ウィハン弦楽四重奏団。
95年の初来日以来、度々来日公演を行っており、来たる2014年11月にも来日公演が予定されている。 |
| |

NI 6264
(CD-R)
\2400 |
ブラックフォード:亡命者の声 |
デイヴィッド・ヒル(指揮)
キャスリン・ウィン=ロジャーズ(メゾ・ソプラノ)
ジェラルド・フィンリー(バリトン)
グレゴリー・クンデ(テノール)
バッハ合唱団、フィルハーモニア管弦楽団
ニュー・ロンドン少年少女合唱団 |
| イギリスの作曲家リチャード・ブラックフォードが、亡命、刑務所、拷問などに、苦しみを受けた人々の言葉を題材として書き上げた劇的なカンタータ。儚い望みを歌い、奏でたメッセージ色の濃い作品となっている。ハイペリオンでも様々な声楽作品を手がけているデイヴィッド・ヒルが指揮を振る。 |
<マイナー・レーベル歴史的録音・旧録音>
 BONGIOVANNI BONGIOVANNI
|
|
|
名バリトン、ブルスカンティーニ唯一のリゴレット!
ヴェルディ:「リゴレット」
録音:1963 年11 月、ローマ |
セスト・ブルスカンティーニ(Br リゴレット)
エミーリア・ラヴァーリャ(S ジルダ)
アルド・ボッティオン(T マントヴァ公)
マッシミリアーノ・マラスピーナ(Bs スパラフチーレ)
エレナ・ツィリオ(Ms マッダレーナ)
アンジェロ・ノゾッティ(Bs モンテローネ)
カルロ・フランチ(指揮)
RAI ローマ管弦楽団,合唱団 |
+ボーナス
ベッリーニ:「夢遊病の女」—お前が分かるぞ、ああ、心地よい地よ
録音:1957 年
ヴェルディ:
「群盗」—カルロ!わしは死んでしまう,見知らぬ男が3ヶ月ほど前にやって来て,
愛情に溢れる父親からの口づけのように
セスト・ブルスカンティーニ(Br マッシミリアーノ)
アドリアーナ・グエリーニ(S アマーリア)
ラルフ・ランベルト(T カルロ)
アルフレード・シモネット(指揮)RAI
ミラノ管弦楽団 |
名バリトン、ブルスカンティーニ唯一のリゴレット!1963
年のSTEREO 録音が完全初出!
録音:1957 年/117’ 00”
これまでまったく流通した形跡のない音源がCD
になりました。1963 年にRAI ローマが収録したヴェルディの「リゴレット」(11
月5 日放送。収録は10 月16 日とされています)。これが素晴らしい名演で、しかもステレオ録音!
1950 年代から1980 年代まで幅広く活躍したバリトン、セスト・ブルスカンティーニ(1919—2003)は、モーツァルトやロッシーニ、ドニゼッティなどで高い評価を得た演技達者なバリトンでした。あまりドラマティックなバリトン役は歌わなかったブルスカンティーニでしたが、リゴレットは得意としていて歌っていました。しかしこれまでまったく録音がありませんでしたので、このCD
は貴重。
ブルスカンティーニのリゴレットは、ヴェルディ・バリトンの押しの強いリゴレットとは異なり、父として道化としての感情を抜群の演技力で歌い上げるもので、聞くものの心に迫るたいへん優れたリゴレットです。マントヴァ公のアルド・ボッティオン(1933—2009)は、1960
年代から晩年まで長く活動したヴェネツィア生まれのテノール。イタリア伝統のスタイリッシュな歌い口で人気を博しました。この録音は新進テノールとして活動の場を広げている頃のもの。エミーリア・ラヴァーリャは軽量級ソプラノで、コロラトゥーラを軽々と歌っています。彼女自身まだ若かったのでしょう、瑞々しい声の初々しいジルダです。
驚いたことに正真正銘のステレオ録音。RAI
では1950 年代末から1960 年代にかけてのステレオ録音がいくつも確認されており、これもその一つだったようです。やや歪っぽいものの、この年代のイタリアでの録音としては上々の音質です。観客入りの放送用録音で、拍手は基本的に幕の終わりだけで途中には入りません。
ボーナスにベッリーニの「夢遊病の女」のアリアと、ヴェルディの「群盗」から3
場面を収録。「群盗」は、RAI がヴェルディの没後50
周年を記念して行った一連のヴェルディ録音の一つで、「群盗」の最初期の録音ですが、これまでCD
にはなっていなかったもの。 |
<国内盤>

7/16(水)紹介新譜
マイナー・レーベル新譜
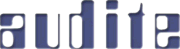 AUDITE AUDITE
|


AU 92691
(SACD HYBRID)
\2600 →\2390 |
トリオ・テストーレが難曲チャイコフスキーとラフマニノフに挑戦!
(1)ラフマニノフ:
ピアノ三重奏曲第1番 ト短調「悲しみの三重奏曲」
(2)チャイコフスキー:
ピアノ三重奏曲 イ短調 Op.50「偉大な芸術家の思い出に」 |
トリオ・テストーレ
【フランチスカ・ピエッチ(Vn)、
ハンス・クリスティア・シュヴァイカー(Vc)、
ヒョンジョン・キム=シュヴァイカー(Pf) |
円熟のピアノ・トリオ、トリオ・テストーレが難曲チャイコフスキーとラフマニノフに挑戦!友人、先輩の死を悼んだ悲しみの作品
録音:2013 年10 月21,22 日/イエス・キリスト教会(ベルリン)/DDD、ディジパック仕様、64’54”
SACD ハイブリッド盤。結成から10 年を過ぎ、ますます円熟のアンサンブルを見せているピアノ三重奏団「トリオ・テストーレ」による最新アルバムは難曲チャイコフスキーとラフマニノフのピアノ三重奏曲です。
チャイコフスキーのピアノ三重奏曲 イ短調
Op.50 は1882 年チャイコフスキー42 歳の時の作品です。この長大な三重奏曲は2
つの楽章から構成されておりますが、変奏曲である第2
楽章は2 つの部分にわかれ、最後の変奏とコーダはそれだけで一部をなす大規模なものとなっております。通称『偉大な芸術家の思い出に』は、ニコライ・ルビンシテインへの追悼音楽から称され、全般的に悲痛で荘重な調子が支配的で感傷に彩られるチャイコフスキー独特の情緒をえがきだしております。高度な演奏技巧が要求されますが、当演奏はトリオ・テストーレの安定感のある堅実なアンサンブルを聴かせてくれます。
一方、ラフマニノフのピアノ三重奏曲第1 番は1892
年に作曲、初演されました。同2 番とともに「悲しみの三重奏曲」と称され、チャイコフスキーの死を悼んで作曲されたと言われております。ピアニストであったラフマニノフらしい、超絶のピアノ技巧と濃厚なロシア情緒に満ち溢れております。
【トリオ・テストーレ】
2000 年に結成された三重奏団。ヴァイオリニストのフランチスカ・ピエッチは11
歳でソロ・デビューを果たした早熟の名手で、1998
年から2002 年までヴッパータール響のコンミスを務めた後、2006
年から2010 年の間ルクセンブルク・フィルのコンミスを務めあげた逸材。チェロを担当するのはソ連の豪傑ペルガメンシコフの愛弟子、ハンス・クリスティア・シュヴァイカー。教育者としてもすでに活躍し、石坂団十郎をはじめ数多くの若手が師事を受けている。トリオの中では最も若手であるヒョンジョン・キム=シュヴァイカーも、2008
年ショパン国際ピアノコンクール in ASIA 第1
位に輝いた韓国期待の実力派。国籍も年代も三者三様のトリオだが、アンサンブルの一体感は折り紙つき。2011
年に室内楽の音楽祭Mai-Klassik を創始。団体名は、使用する弦楽器の制作者の名字がいずれも“テストーレ”
であることに由来している。(ヴァイオリンは1751
年カルロ・アントニオ・テストーレ製、チェロは1711
年カルロ・ジョゼッペ・テストーレ製を使用)

|
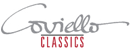 COVIELLO COVIELLO
|
|
|
パリ1937〜「パリ木管三重奏団」を讃えて
(1)ジャン・リヴィエ:小組曲
(2)シャルル・トレネ:君の手をとって
(3)モーリス・フランク:木管三重奏曲
(4)ヘス/トレネ:去りゆく君
(5)フェルー:木管三重奏曲ホ調
(6)ナシオ・ハーブ・ブラウン:アローン
(7)エミール・グーエ:3 つの小品
(8)レイナルド・アーン:牧歌
(9)スタン・ゴレスタン/田園小組曲
(10)ディノ・オリヴィエリ:待ちましょう |
トリオ・レザール
【ステファヌ・エゲリング
(Ob、Eh、Bass-Oboe)、
ヤン・クロイツ
(Cl、バセットホルン、B-Cl)、
シュテファン・ホーフマン
(Fg、コントラファゴット)】 |
木管三重奏団第1号団体に捧げられた花束
録音:2013 年5 月9-12 日/フライブルク・エゲルザール/DDD、59’
59”
オーボエ、クラリネット、ファゴットによる木管三重奏は意外に新しい形態で、名バソン奏者だったフェルナン・ウブラドゥが、オーボエのミルティル・モレル、クラリネットのピエール・ルフェーヴルと1927
年に「パリ木管三重奏団」を結成したのが初。
最小限の編成ながら色彩豊かな新ジャンルのために、同時代の作曲家たちへ新作を委嘱しました。そこで生まれた諸作を集めた好アルバム。
フランス系作曲家のオシャレで効果的な作品から、当時ヒットしていたポップスの編曲まで多彩。注目はレイナルド・アーンのオリジナル作品「牧歌」。アーンならではのメロディアスでセンスあふれる小品ですが、楽譜がどこを探しても見つからず、パリ木管三重奏団による1937
年の録音から採譜したとされます。この1 曲だけでも欲しくなるアルバムです。トリオ・レザールは1990
年、ザールラント音楽院で創立された木管三重奏団。 |
| |
|
|
オーストリアの室内楽
(1)ゲラルド・レッシュ:イタロ・カルヴィーノのよる5つの試み
(2006)
(2)ウェーベルン:ヴァイオリンとピアノのための4つの小品Op.7
(3)同:チェロとピアノのための3つの小品Op.11
(4)フリードリヒ・チェルハ:ピアノ三重奏曲
(2005) |
トリオ 3 : 0
【エヴァ・シュタインシャーデン(Vn)、
デトレフ・ミェルケ(Vc)、
アレクサンダー・ファフタル(Pf)】 |
新ウィーン楽派の伝統を今世紀に受けつぐ室内楽曲集
34’ 49”
3 人のオーストリア人作曲家、アントン・ウェーベルン
(1883-1945)、フリードリヒ・チェルハ (1926-)、ゲラルド・レッシュ
(1975-) を集めています。
それぞれが約半世紀違いに生まれ、ウェーベルン作品が1910
年と14 年、チェルハが2005 年、レッシュが2006
年の作で、約100 年の違いがありますが、どのトラックを聴いても同じような音楽なのに驚かされ、新ウィーン楽派の伝統が脈々と流れているのを実感できる内容となっています。
トリオ3:0は、2006 年にザルツブルクで行われたモーツァルト生誕250
年祭で、新作のピアノ三重奏曲を演奏するために組み合わされた3
名が、数年後に再会して活動を開始。2012 年にこの名称となりました。 |
 HAENSSLER HAENSSLER
|
|
|
ロシア
(1)シュニトケ:3つの宗教曲 (1984)
(2)ラフマニノフ:神の母 (1893)
(3)グバイドゥーリナ:マリーナ・ツヴェターエワ讃歌
(1984)
(4)タネーエフ:ポロンスキーによる合唱曲Op.27より
「星」「陰気な二つの雲が山にかかり」
「ものうげな海の上にあるとき」 (1911)
(5)グリンカ:ヘルビムの歌
(6)チャイコフスキー:
ヘルビムの歌〜聖ヨハネ・クリュソストムスの典礼Op.41より |
マルクス・クリード(指揮)
シュトゥットガルト声楽アンサンブル
中曽和歌子(Sop)
ザビーネ・ツィンツェル(A)
アレクサンドル・ユーデンコフ(Ten)
ミハイル・シャシコフ(Bs)
[ロシア語(教会スラヴ語)歌唱] |
感動的な美しさ。ロシアの合唱曲集
録音:2013 年7 月、11 月/ SWR フンクスタジオ(シュトゥットガルト)/62’
09”
ロシア音楽の魅力のひとつである合唱。ロシア正教は教会内での楽器演奏を禁じているため、聖歌隊教育の歴史がありました。グリンカ、チャイコフスキー、ラフマニノフら大作曲家も個性的な無伴奏宗教曲を残しています。そのほか宗教曲ではありませんが、帝政ロシア末期の1911
年に作られたタネーエフ作品の心洗われるような美しさも必聴。さらに、シュニトケとグバイドゥーリナともに1984
年の作品も興味津々。シュニトケ作品はチャイコフスキーやラフマニノフの宗教曲の系譜上にあり、彼独特の皮肉やグロは全く見られません。非常にピュアで敬虔、ソ連時代にこのような作品が書かれたことは驚きと申せましょう。グバイドゥーリナの作品は対照的に実験的で演劇的。グバイドゥーリナが崇拝しているロシアの女流詩人ツヴェターエワの詩を驚くほど適確に音楽化しています。
クリード率いるシュトゥットガルト声楽アンサンブルはロシアの合唱団とはひと味違う洗練された響きが絶美。アンサンブルが恐ろしく難しいグバイドゥーリナ作品も完璧。 |
The Choir Project
|
合唱ファン狂喜のシリーズ「ザ・コラール・プロジェクト」始動!!
合唱ファン狂喜!ドイツ、ヘンスラー社より興味深いサブ・レーベル「ザ・コラール・プロジェクト」が始動します。このプロジェクトは毎年開催される世界最難関の合唱コンクール「ワールド・コラール・ゲームズ」にて優秀な成績をおさめた団体のディスクをリリースしてゆくというものです。
合唱の形態も4 人のから60 人まで、扱われるジャンルもクラシックにとどまらずポップまであらゆる「合唱」を楽しむことができます。
記念すべき第1弾は2タイトルリリースされ、合唱グループ「Dekoor
Close Harmony」とオーストリアのヴォーカル・アンサンブル「LALA」です。ともに実力派の合唱団で、今後の活躍にも注目と言えましょう。
なお、当コラール・プロジェクトのシリーズは年に3〜5タイトルのペースでリリースしていくとのことです。 |
|
|
ヴォーカル・アンサンブル「LALA」のアルバム
(1)レーガー:「夜の歌」
シューベルト:(2)「夜」、(3)「聖なるかな」
メンデルスゾーン:
(4)「緑の中に」、(5)「憩いの谷」、(6)「森からの別れ」
(7)シューベルト:/(8)ブラームス:「許しておくれ」、
(9)「目覚めよ」、(10)「谷間で」、
(11)「別れの歌」、(12)「静かな夜に」
(13)シューベルト:「墓」
(14)ブルックナー:「タントゥム・エルゴ」第3番
(15)メンデルスゾーン:狩の歌
Preissegger (1951-):
(16)「Gernhabn tuat guat」、(17)「In
Gedankn bin ih bei dir」
(18)マイエル:「Da Adler」
(19)LALA:「LALA-Jodler」
(20)The New York Voices:「Come Home」
(21)LALA:「Fawada」
(22)David Paich:「Rosanna」
(23)Jason Thomas Mraz:「 I’m Yours」
(24)Earth,Wind and Fire:「September」 |
LALA |
合唱ファン狂喜のシリーズ「ザ・コラール・プロジェクト」始動!!
合唱ファン狂喜!ドイツ、ヘンスラー社より興味深いサブ・レーベル「ザ・コラール・プロジェクト」が始動します。このプロジェクトは毎年開催される世界最難関の合唱コンクール「ワールド・コラール・ゲームズ」にて優秀な成績をおさめた団体のディスクをリリースしてゆくというものです。合唱の形態も4
人のから60 人まで、扱われるジャンルもクラシックにとどまらずポップまであらゆる「合唱」を楽しむことができます。記念すべき第1弾は2タイトルリリースされ、合唱グループ「Dekoor
Close Harmony」とオーストリアのヴォーカル・アンサンブル「LALA」です。ともに実力派の合唱団で、今後の活躍にも注目と言えましょう。なお、当コラール・プロジェクトのシリーズは年に3~5タイトルのペースでリリースしていくとのことです。
しっとりと響きわたる澄み切った歌声!ヴォーカル・アンサンブル「LALA」のアルバム
ヴォーカル・アンサンブル「LALA」は4 人のアカペラ・ヴォーカルで教会音楽、フォークソングを得意としております。今回はクラシックからポップスまで幅広いジャンルをレコーディングしました。しっとりと響き渡る澄み切った歌声がヴォーカル・アンサンブル「LALA」の特徴です。 |
| |
|
|
オランダ合唱団Dekoor Close Harmonyのアルバム
(1)We Are Young/(2)Selfless, cold and
composed/
(3)Let Me Take Over/(4)Zombie/(5)A Night
in Tunisia/
(6)Teardrop/(7)Smack Dab In the Middle/
(8)Elijah Rock/(9)Love Psalm/
(10)I Know Where I’ve Been/(11)You’re
theVoice |
Dekoor Close Harmony |
パワフルな歌声が魅力!オランダ合唱団Dekoor
Close Harmonyのアルバム
録音:2011 年9 月、オランダ/DDD、65’35”
「Dekoor Close Harmony」はクリストフ・マック・カーティにより設立された合唱団で、モダン・ジャズからポップスまで実に多様な表現力を持っています。合唱を愛してやまないカーティの思いが伝わってくる心にダイレクトに響き渡る合唱団で、パワフルな歌声が最大の魅力です。 |
 SUPRAPHON SUPRAPHON
|
|
|
ヤナーチェク「1927年9月」オリジナル版による「グラゴル・ミサ」
ヤナーチェク:
・グラゴル・ミサ(1927年9月版/校訂:イジー・ザフラードカ)
アンドレア・ダンコヴァー(ソプラノ)
ヤナ・シーコロヴァー(アルト)
トマーシュ・ユハース(テノール)
ヨゼフ・ベンチ(バス)
収録:2013年8月31日-9月3日/
プラハ、ルドルフィヌム、ドヴォルザーク・ホール
(セッション・ステレオ)
・永遠の福音(1914)
アルジビェタ・ポラーチコヴァー(ソプラノ)
パヴェル・チェルノフ(テノール)
収録:2014年3月27-28日/
プラハ、ルドルフィヌム、ドヴォルザーク・ホール
(セッション・ステレオ) |
プラハ・フィルハーモニー合唱団
ルカーシュ・ヴァシレク(合唱指揮)
トマーシュ・ネトピル(指揮)
プラハ放送交響楽団 |
ネトピルの最新アルバムは得意のヤナーチェク「1927年9月」オリジナル版による「グラゴル・ミサ」世界初録音
DDD、ステレオ、58’13”
チェコの若い世代を代表する指揮者のひとりであるネトピルは、若くして「ヤナーチェクのエキスパート」との呼び声の高い人物。前作「シンフォニエッタ&タラス・ブーリバほか」(SU4131)がグラモフォン誌で高評価を得たことは記憶にあたらしいところですが、最新アルバムで取り上げた「グラゴル・ミサ」は、ネトピルにとって、ヴァイオリンを学びたての時期に触れ、心を奪われた最初のヤナーチェク体験であったとのことで期待がかかります。
作曲の原点といえるモラヴィア民謡と、高度な声楽の扱い、ヤナーチェク独自の特異な語法とがみごとに結実した傑作「グラゴル・ミサ」は、1927
年12 月にブルノで初演されています。初演の翌年には、「グラゴル・ミサ」は作曲者の手によって改訂を施され、いまも通常に演奏されるのは、この最終改訂版の方となっています。
ネトピルによる「グラゴル・ミサ」は、ブルノ初演時の姿を再現したというもので、音楽学者イジー・ザフラードカが校訂した「1927
年9 月オリジナル版」に基づく世界初録音。
ブックレットでネトピルは次のように述べています。
「このオリジナル版を、よく知られている一般的な現行版と比較すると、楽器の編成、構造およびモチーフにおいて、いくつかのまったく根本的な相違に直面します。」
ちなみに、同じくヤナーチェク演奏の大家で、「グラゴル・ミサ」に惚れ込んでいたチャールズ・マッケラスも「作曲者の自筆譜にもとづく原典版」による録音を残していますが、そこでは最初と最後にイントラーダを置く9
楽章構成であったのに対して、現行版同様に8楽章形式のネトピル盤は、この点でもマッケラス盤とも異なる内容ということで、おおいに気になるところです。
カップリングは「永遠の福音」。ヤナーチェクがオペラ「ブロウチェク氏の月への旅」と同時に着手した作品で、第1
次大戦勃発の数カ月前、1914 年の春に完成したこともあり、戦争の影響や、ヤナーチェクの音楽様式にスピリチュアルな志向が反映された内容となっています。こちらは「グラゴル・ミサ」とは対照的にほとんど知られておらず、録音も数えるほどで、ネトピルによる最新録音の登場は、おおいに歓迎されるものとおもわれます。
1975 年チェコ共和国東部のクロメルジーシュに生まれたトマーシュ・ネトピルは、これまでにザルツブルク音楽祭やベルリン・フィル、ドレスデン・シュターツカペレの公演に出演、2013
/ 14 年のシーズンよりあらたにエッセン市の音楽総監督に就任すると同時に、ドレスデン国立歌劇場、パリ国立オペラ座、ウィーン国立歌劇場、またパリ管、ロンドン・フィルといった、欧州各地のオーケストラや劇場への出演が決まっており、オペラ、コンサートの両面で活躍を続けています。 |
<マイナー・レーベル歴史的録音・旧録音>
<メジャー・レーベル>
 イタリア・ユニバーサル イタリア・ユニバーサル
|


482 0959
(18CD)
\9200→\8690 |
カール・リヒター〜バッハ:作品集
CD1
ゴルドベルク変奏曲 BWV 988
CD2
イタリア協奏曲 ヘ長調 BWV 971
半音階的幻想曲とフーガ ニ短調 BWV 903
トッカータ BWV 915
パストラーレ ヘ長調 BWV 590
幻想曲とフーガ ハ短調 BWV 906
CD3
ヴァイオリンとチェンバロのためのソナタ第1,2,3番
BWV 1014-1016
CD4
ヴァイオリンとチェンバロのためのソナタ第4,5,6番
BWV 1017-1019
CD5
フルートとチェンバロのためのソナタ BWV
1020, 1030-1032
CD6
ブランデンブルク協奏曲第1番〜第4番 BWV
1046-1049
CD7
ブランデンブルク協奏曲第5番、第6番 BWV
1050, 1051
オーボエ・ダモーレ協奏曲 イ長調 BWV 1055
(Y1980)
オーボエとヴァイオリンのための協奏曲 ハ短調
BWV 1060 (Y1963)
CD8
チェンバロ協奏曲第1番 ニ短調 BWV 1052
チェンバロ協奏曲第2番 ホ長調 BWV 1053
チェンバロ協奏曲第5番 ヘ短調 BWV 1056
チェンバロと2つのリコーダーのための協奏曲
ヘ長調 BWV 1057
CD9
2台のチェンバロのための協奏曲第2番 ハ長調
BWV 1061
3台のチェンバロのための協奏曲第1番 ニ短調
BWV 1063
4台のチェンバロのための協奏曲 イ短調 BWV
1065
CD10
チェンバロ協奏曲第3番 ニ長調 BWV 1054
チェンバロ協奏曲第4番 イ長調 BWV 1055 (Y1971)
チェンバロ協奏曲第7番 ト短調 BWV 1058
2台のチェンバロのための協奏曲第1番 ハ短調
BWV 1060 (Y1972)
3台のチェンバロのための協奏曲第2番 ハ長調
BWV 1064 (Y1973)
CD11
2台のチェンバロのための協奏曲第3番 ハ短調
BWV 1062
三重協奏曲 イ短調 BWV 1044
3台のチェンバロのための協奏曲第2番 ハ長調
BWV 1064 (Y1981)
CD12
2台のチェンバロのための協奏曲第1番 ハ短調
BWV 1060 (Y1963)
2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調
BWV 1043
音楽の捧げもの BWV 1079
CD13
オルガン協奏曲 BWV 592-596, 597
CD14
トッカータとフーガ「ドリア調」 ニ短調 BWV
538
トッカータとフーガ ニ短調 BWV 565
前奏曲とフーガ 変ホ長調「聖アン」 BWV 552
トリオ・ソナタ第5番 ハ長調 BWV 529
幻想曲とフーガ ト短調 BWV 542
シュープラー・コラール第6曲「主を頌めまつれ」
BWV 650
シュープラー・コラール第1曲「目覚めよと呼びわたる物見の声」
BWV 645
CD15
パッサカリアとフーガ ハ短調 BWV 582
コラール変奏曲「慈しみ深きイエスよ」 BWV
768
カンツォーナ ニ短調 BWV 588
コラール前奏曲「装いせよ、わが魂よ」 BWV
654
管弦楽組曲第3番 ニ長調 BWV 1068
CD16
管弦楽組曲第1,2,4番 BWV 1066, 1067, 1069
CD17〜18
ミサ曲 ロ短調 BWV 232 |
|
| クラムシェル・ボックス仕様、ブックレット(伊・英語併記)を封入。 |
<国内盤>

7/15(火)紹介新譜
マイナー・レーベル新譜
 ENSEMBLE MODERN ENSEMBLE MODERN
|

EMCD 021/22
(2CD)
\4800 |
「彼らは・・・」〜アンサンブル・モデルン国際作曲セミナー
(1)サエド・ハダッド:光の倫理(2004)
(2)マルコ・ニコディイェヴィッチ:対象/空間(2004)
(3)藤倉大:バニシング・ポイント(2004)
(4)トミー・ライサネン:中絶(2005)
(5)アンナ・メレディス:ダウンホール(2005)
(6)シモン・ステーン=アナセン:チェンバード・ミュージック(2007)
(7)今井千景:シムルジェネシス(2009)
(8)伊藤聖子:ゴーイング・フォース・バイ・デイ(2006)
(9)アンソニー・チュン:ハイパー・バトン(2009)
(10)シュテファン・ケラー:スプリング!(2011)
(11)シュタイングリムール・ローロフ:最初の人間(2011)
(12)ヨハネス・クライドラー:カンタータ「今、未来はない」(2008)
(13)シュテファン・バイヤー:信憑性の面で/ある決断(2011) |
アンサンブル・モデルン
(1)(3)フランク・オッル(指揮)
(2)アレホ・ペレス(指揮)
(4)ジョン・B.ヘッジス(指揮)
(5)ライアン・ウィッグルズワース(指揮)
(6)(8)マヌエル・マウリ(指揮)
(7)(9)(10)(11)(12)
ヨハナネス・カリツケ(指揮)
(13)パブロ・ルス・ブロセタ(指揮) |
藤倉大、今井千景、伊藤聖子、他これから羽ばたく作曲家達!アンサンブル・モデルン国際セミナー!
録音:2004年-2013年
アンサンブル・モデルン国際作曲セミナーはダルムシュタット夏季現代音楽講習会と同じく、※アンサンブル・モデルン国際作曲セミナーはダルムシュタット夏季現代音楽講習会と同じく、ンマン、ジョージ・ベンジャミン、ヨハネス・カリツケらが招かれている。ここでは若い作曲家の作品がアンサンブル・モデルンとの緊密なディスカッションとリハーサルによって演奏、発表されるのが最大の特色で、このディスクはこれまでのそうしたライヴを集めたもの。
日本からは藤倉大、伊藤聖子、今井千景が参加、それぞれの出世作、代表作となった。2000
年代に入ってからの前衛若手・中堅世代の作風を俯瞰する上で最適のセット。 |
| |
|
|
「ユークリッド・アビス」
〜インターナショナル・アンサンブル・モデルン・アカデミー
(1)ユーグ・デュフール:ユークリッド・アビス(1996)
(2)フリードリヒ・チェルハ:五重奏曲(2007)〜オーボエと弦楽四重奏のための
(3)シュタイングリムール・ローロフ:コロニース(2013)
(4)チン・ウンスク:ファンタジー・メカニーク(1994,rev.1997) |
ヴィンバイイ・カズィボニ(指揮)
IEMA アンサンブル2012/13
(インターナショナル・アンサンブル・
モデルン・アカデミー) |
チェルハ、デュフールと若手作曲家の室内アンサンブル作品!
録音:2013年
アンサンブル・モデルンは10 年ほど前から「インターナショナル・アンサンブル・モデルン・アカデミー」なる催しを開き、作曲家と演奏家が密に共同作業を行う教育プログラムで自らの前進的な発展を促してきた。このディスクはこれまでの共同作業の中で制作・発表された作品から特に評価の高かった作品をセレクションしたもの。
スペクトル楽派の一人と目されるフランスのデュフール、オーストリアの重鎮チェルハ、アイスランド系ドイツ人の若手ローロフ、韓国出身のウンスク・チンと世代も国籍も様々な作曲家たちの創作の最前線を知ることができる。 |
| |
|
|
「ザール・ベルガーのポートレート/トラヴェリング・ピース」
〜ホルンのための現代作品集
CD1)独奏作品集
(1)ハインツ・ホリガー:
怒り— 夢(cynddaredd brenddwyd)(2001,rev2004)
(2)ミロスラフ・スルンカ:コロニー(2009)
(3)藤倉大:ポヨポヨ(2012)
(4)イェルク・ヴィトマン:エア(2005)
(5)ニーナ・シェンク:ひとつの歌(2012)
(6)ヴァソス・ニコラウ:L.E.A.P.S(2012)
(7)マヤ・ドゥニエツ:フィガロの夢(2012)
(8)デーモン・トーマス・リー:ベント(2008)
(9)今井千景:ドローイング(2012)
(10)ディトマー・ヴィースナー:テープつきの歌(2008)
CD2)室内楽作品集
(11)トーマス・アデス:ソナタ・ダ・カッチア(狩猟のソナタ)(1993)
(12)ザミール・オデー=タミーミ:
フレンチ・ホルンと打楽器のためのデュオ(2011)
(13)キャシー・ミリケン:3ステップ(2010)
(14)ヴィト・ジュラーイ:ウォーム・アップ(2012)
(15)ホーコン・テリン:夢の旋律(2012)
(16)アンソニー・チャン:
ホルン独奏と管弦楽のための「霧のモビール」(2010)
(17)ヴァレンティン・ガーヴィー:
金管四重奏曲「セロニアス・モンクのレッツ・コール・ディスの変奏曲」(2012) |
ザール・ベルガー(Hrn)
(7)マヤ・ドゥニエツ(Pf)
(11)クリスティアン・ホンメル(Ob)
ウエリ・ヴィゲト(Cemb)
(12)ライナー・レーマー(Perc)
(13)ジャグディシュ・ミストリー(Vn)
エヴァ・ベッカー(Vc)
(14)小川留美(Perc)
デヴィッド・ハラー(Perc)
(15)ホーコン・テリン(Cb)
(16)マティアス・ピンチャー(指揮)
フランクフルト放送交響楽団
(17)ヴァレンティン・ガーヴィー(Trp)
サヴァ・スイトヤノフ(Trp)
ウーヴェ・ディエルクセン(Trb) |
藤倉大の「ポヨポヨ」を初めとする現代ホルン作品集!
録音:2010-2012年(16)ダルムシュタット・ライヴ
ザール・ベルガーはイスラエル出身のホルン奏者でエルサレム音楽院で学んだ後、渡独、ベルリンでマリー=ルイーズ・ノイネッカーらに師事した。現在はソリストとして多くのオーケストラに招かれ、また若手作曲家とのコラボレーション、現代の巨匠的作曲家の作品の再演など、現代音楽に並々ならぬ意欲を見せている。このアルバムは全てベルガーの委嘱によって書かれた作品で現代のホルン音楽を知る上で極めて貴重な内容。藤倉大、トマス。アデスら若手・中堅から重鎮ハインツ・ホリガーまで聴き応え十分。特にホルン・マニアは必携! |
| |


EMCD 017
【再プレス・価格変更】
\2900 →\2690 |
エルネスト・ブールの名盤クセナキス&ベートーヴェンが復活です!
(1)クセナキス:「アラックス」〜3群の同一編成のアンサンブルのための
(2)ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲ニ長調Op.61 |
エルネスト・ブール(指揮)
アンサンブル・モデルン
(1)ハンス・アイスラー新音楽グループ&
アンサンブル・ケルン
(2)トマス・ツェートマイヤー(Vn) |
録音:(1)1985 年9 月15 日ケルン音楽大学(初演)、(2)1987
年10 月26 日ケルン・フィルハーモニー・ホール(ライヴ)
現代音楽を得意としていた指揮者エルネスト・ブールの秘蔵音源が取り扱い再開です。但し価格が改定になりましたので、ご注意ください。
このCD はクセナキスとベートーヴェンをカップリングしたブールの二つの側面を知るのに最適の一枚。クセナキスの《アラックス》は3
群のオーケストラが絡み合い分岐し衝突しまた合流するプロセスの中で時に官能的ともいえるほど鮮やかで色彩的な音響が立ち上がります。対してトマス・ツェートマイヤーをソリストに迎えてのベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲はいわゆる新即物主義による無駄のないスポーティな演奏ですが、第2
楽章では大変叙情的で歌心あふれる演奏を展開し、終楽章のほとばしるようなエネルギーも忘れがたいものです。 |
 MSR MSR
|
|
|
「ジ・アメリカン・ストリング・プロジェクト2014」
チャイコフスキー:弦楽四重奏曲第3番変ホ短調Op.30
ハイドン:弦楽四重奏曲第61番ニ短調「五度」Op.76-2
(アンコール・ピース)
グリーグ:アリア〜組曲「ホルベアの時代より」
ブラームス:弦楽四重奏曲第3番より第3楽章
ショスタコーヴィチ:弦楽四重奏曲第3番より第3楽章 |
ジ・アメリカン・ストリング・プロジェクト |
メジャー・オケの首席級メンバーによる弦楽アンサンブルで聴く弦楽四重奏曲!
録音:2011年5月シアトル・ベナロヤ・ホール(ライヴ)
ジ・アメリカン・ストリング・プロジェクトはシカゴ響やデトロイト響、フィラデルフィア管などのメジャー・オーケストラの首席級メンバーや室内楽奏者、大学教授などが集結して毎年コンサートを行っている弦楽アンサンブル。2002
年以来毎年コンサートを行っておりましたが2011
年に一旦ピリオドを打っていますが、2014 年に活動を再開したようです。
およそ5/4/3/2/1 からなる小ぶりの弦楽アンサンブルで弦楽四重奏曲を弦楽合奏で演奏するおよそ5/4/3/2/1
からなる小ぶりの弦楽アンサンブルで弦楽四重奏曲を弦楽合奏で演奏する部がぼやけ弦楽四重奏特融の精妙さが失われてしまうことから量感と精妙なアンサンブル両方が満たされるほどよい規模の編成で演奏している。弦楽四重奏曲をゴージャスに聴きたい人におすすめ。
なおアルバム・タイトルは「2014」ですが、録音は2011
年のものです。 |
| |
|
|
「ベートーヴェン・オデッセイ第3集」
ベートーヴェン:
ピアノ・ソナタ第2番イ長調Op.2-2
ピアノ・ソナタ第17番ニ短調「テンペスト」Op.31-2
ピアノ・ソナタ第26番変ホ長調「告別」Op.81a |
ジェームズ・ブローン(Pf) |
イギリスの実力派ピアニスト、ジェームズ・ブローンの清新なベートーヴェン、ピアノ・ソナタ集第3弾!
録音:2013 年7 月22-24 日,ポットン・ホール、サフォークUK
ジェームズ・ブローンは1971 年イギリス出身で12
歳の時、オーストラリアでデビュー・リサイタルを行い、その後ニュージーランド、イギリス、オーストラリアを中心に演奏活動を行っている。MSR
ではこれまで3 枚目のアルバムを出しており、そのうち2
枚はベートーヴェン・ピアノ・ソナタ・チクルスである(第1集MS1465・第1、3、23
番「熱情」、第2集MS1466・第8番「悲愴」、第14番「月光」、第19
番、20 番、21 番「ワルトシュタイン」)。極めて堅実、清新な演奏であり、ソナタ全集完結が期待される。 |
| |
|
|
「もっとも美しいこと」〜受難節から復活祭までの音楽
パニス・アンジェリクス(フランク)
スターバト・マーテル(ペルゴレージ)
私の歌は知られていない愛(アーチャー)
もし神が私たちのためにいるのなら(ヘンデル)
トランペットの音(パーセル)
私は同様にあなたに従う(J.S.バッハ)/ほか全17曲 |
ジェーミー・ハイテル(指揮)
コネチカット州グリーンウィック・クライスト・
チャーチ聖チェチーリア少女合唱団
アリステア・レイド(Org) |
録音:2013 年
コネチカット州グリーンウィック・クライスト・チャーチは独立宣言以前の1749
年に設立されたアメリカでも最も古い教会に属する。この教会には6〜7
つの合唱団があり、教会のミサ以外にも盛んに演奏活動を行っており全米でもよく知られている。少女だけによるこのアルバムはまさに天使の歌声で癒しの効果も満点。 |
| |

MS 1463
(2CD)
\3600 |
「タペストリー/」〜ダン・ロックレア(b.1949)の合唱音楽
CD1)
ホリー・カンティクルス(1996)/アレルヤ・ダイアローグ(1990)/
インスタント・カルチャー(1985)/オン・キャッツ(1978)/
離脱せよ!(1983)/ドーナ・ノービス・パーチェム(1983)/
主を宣言する(1985)/クリスマス・キャロル(1981)/
3つのクリスマス・モテット(1993)
CD2)
吹きさらし(1992)/琥珀色の波へ(1993)/タペストリー(1982)/
短いミサ(1993)/変わってゆく認識(1987)/墓碑銘(1987) |
CD1:
デイヴィッド・ペッグ(指揮)
ベルカント・カンパニー(混声cho)
CD2:
ロバート・ラッセル(指揮)
ザ・コーラル・アート・ソサエティ(混声cho)
プロメテウス・チェンバー・プレイヤーズ
シェアリー・カリー(Pf) |
録音:1995 年・1996 年
ダン・ロックレアはアメリカの作曲家でバッファロー・フィル、カンザス・シティ・フィル、オマハ響などアメリカの地方都市のオーケストラ、アンサンブル、団体で盛んに演奏されている。作風は新ロマン主義あるいはプレ・モダン的、穏健、保守的な傾向。
ここに収められている作品は全て宗教曲で温和で敬虔な雰囲気に溢れている。 |
| |
|
|
自由でスパイスの効いたモダンなハーモニー
ウィリアム・アヴェリット(b.1948):
(1)アフロ・アメリカン断章(1991)〜
合唱と4手連弾ピアノのための
(2)青の深み(2012)〜
合唱と4手連弾ピアノのための
(3)ドリーム・キーパー(2009)〜
合唱と4手連弾ピアノのための |
ロバート・ボード(指揮)
ミズーリ・カンザス・シティ音楽院合唱団
リー・トンプソン&
メリッサ・レーニグ(Pf) |
録音:2013 年
ウィリアム・アヴェリットはアメリカの作曲家で作品はアメリカ、ヨーロッパ、アジアで盛んに演奏されているという。調性に基づきながら、自由でスパイスの効いたモダンなハーモニーが現代のロマンを感じさせる。全て混声合唱に4
手連弾のピアノ伴奏で構成されており、日本の合唱ファンにも広くアピールする内容。 |
| |
|
|
「東欧の再発見」
(1)4つのブルガリアの歌(マリア・ワイルドヘイバー編曲)
(2)ボリス・パパンドプロ(1906-91):エレジー、スケルツォ
(3)ベンジオン・エリエゼル(1920-93):ファゴット・ソナタ(1969)
(4)タデウツ・ベイルド(1928-81):4つのプレリュード(1954)
(5)ルボシュ・スルカ(b.1928) :ファゴット・ソナタ(1954/編曲971)
|
マリア・ワイルドヘイバー(Fg)
(1)スコット・プール(Fg)
(2)ミア・エレゾヴィッチ(Pf)
(3)-(5)タニア・タチコヴァ(Pf) |
録音:2012 年
マリア・(イェレツチェヴァ)・ワイルドヘイバーのMSR
へのアルバム第2弾。ワイルドヘイバーはブルガリア出身のファゴット奏者で室内楽とオーケストラの両面で活動し、これまでにブーレーズ、レヴァイン、ドゥダメルらと共演し、ルツェルン音楽祭など国際的なステージにも頻繁に立っている。このディスクは彼女の故郷ブルガリアをはじめ20
世紀東欧の作曲家の作品が集められ、いずれも民族的で親しみやすい内容。 |
| |
|
|
バーバラ・ハーバック:管弦楽作品集II
(1)管弦楽のための「ナイト・サウンディングス」
(2)ゲイトウェイ・フェスティバル交響曲
(3)ア・ステイト・ディヴァイデッド〜ミズーリ交響曲
(4)ジュビリー交響曲 |
デイヴィッド・アングス(指揮)
ロンドン・フィルハーモニック管弦楽団 |
録音:2013 年10 月ヘンリー・ウッド・ホール,ロンドン
アメリカの女流作曲家ハーバックのMSR9 枚目となる作品集で管弦楽曲集としてはこれが2
枚目となる。ここに収められた作品はいずれも3楽章形式の13分から18分の作品。
ハーバックはオペラから映画音楽まで幅広い分野の作品を発表しており、そうした経験がオーケストラ作品にも反映されている為、映画音楽を思わせる親しみやすさとドラマティックな展開で大変聴きやすい内容になっている。 |
<マイナー・レーベル歴史的録音・旧録音>
 OPUS蔵 OPUS蔵
|
|
|
フィルハーモニア管弦楽団、初期の指揮者第3弾はオットー・アッカーマン!
R.シュトラウス:
歌劇「カプリッチョ」最後の場面“明日のお昼の11時ですって?”、
4つの最後の歌
エリザベート・シュワルツコップ(ソプラノ)
録音:1953年
ワーグナー:
歌劇『さまよえるオランダ人』〜
第2幕、ダーラントのアリア「わが子よ」
歌劇『タンホイザー』〜
第2幕、領主ヘルマンのアリア「この殿堂に」
楽劇『パルジファル』〜
第3幕、聖金曜日の音楽、「これこそ聖金曜日の奇蹟」
楽劇『ローエングリン』〜
第1幕、王の挨拶「親愛なるブラバントの方々よ」、
第1幕、王の祈り「主なる神よ、この試合を」
楽劇『ワルキューレ』〜
第3幕、ヴォータンの告別と魔の火の音楽
オットー・エーデルマン(バス・バリトン)
録音:1957年 |
オットー・アッカーマン(指揮)
フィルハーモニア管弦楽団 |
原盤:UK-Columbia LP
アッカーマンは日本ではオペレッタ指揮者として知られていますが、ケルン、チューリッヒ、ウィーンと歌劇場で活躍していた指揮者です。当時のヨーロッパでは歌劇場の音楽家は多かったのですが、日本に彼らの活躍は伝わりませんでした。特にアッカーマンは50
歳という若さで亡くなったことで埋もれてしまいました。
また、エーデルマンは1950、60 年代のワーグナー歌手として一流でしたが、日本ではホッターの陰に隠れてしまいました。シュワルツコップと共演したフルトヴェングラーのバイロイトの「第9」、映像となったカラヤンとの「ばらの騎士」がありながらです。EMI
がワーグナーの全曲を録音するようになったのはエーデルマンがピークを過ぎてからのことです。実際ライブCD
が出るようになって、初めてエーデルマンのオペラでの活躍を知ることになりました。ここではアッカーマンの指揮をバックにした、シュワルツコップとエーデルマンの歌声をお聴きください。(OPUS
蔵)
「アッカーマン指揮による《メリー・ウィドウ》全曲は、前述のフランスACC
ディスク大賞「オペレッタ部門賞」に輝く成功作だったのだが、当事者のレッグ/シュワルツコップ/アッカーマンのトリオとしては、自分たちが本当に聴いて欲しい真実の芸術的自信作は、そんなオペレッタではなくて、同じ1953年の
9 月25 日と26 日、ロンドンでもいつものキングズウェイ・ホールとは別のワトフォード・タウンホールで録音したR・シュトラウスの《4
つの最後の歌》と歌劇《カプリッチョ》最後の場が、秘められた珠玉の1枚だったのである。
《メリー・ウィドウ》の「ヴィリアの歌」をあでやかに歌うシュワルツコップの円熟の名唱を伴奏しながら、いま38
歳、声と表現と魅力が絶頂期にあるこのソプラノには、もっと深い真実の芸術を歌う作品を…とアッカーマンは切望していた。スイス在住という身軽さ、一流歌劇場の主宰者でもある職業柄、アッカーマンは昨年(1952
年) 1 月のミラノ・スカラ座での《バラの騎士》公演ではじめて元帥夫人を歌い、同じくはじめてオックス男爵を歌うオットー・エーデルマンに侵すべからざる凛とした威厳の美しさを示したシュワルツコップの歌唱のすばらしさを思うと、若き元帥夫人とも想像される《カプリッチョ》の伯爵令嬢マドレーヌの独り舞台となるラスト・シーンこそ、いまの彼女のソプラノで聴きたいと考えたという。偶然だがレッグもシュワルツコップのオペラでの持ち役を決めるべき時期が来ていることを痛感していたから、かねて考えていたR・シュトラウスの《4
つの最後の歌》《カプリッチョ》最後の場をアッカーマン/フィルハーモニア管の伴奏で録るべきと確信したのだろう。
(中略)1951 年に戦後初めて再開されたバイロイト音楽祭で、あの世紀に残るフルトヴェングラーのベートーヴェン《第9》にシュワルツコップとエーデルマンの素晴らしいソロを聴いた人のすべてにこのワーグナー・プログラムを捧げたい。1916
年 2 月 5 日、ウィーンでうまれたバス・バリトンのエーデルマンは1951
年のバイロイトでは《マイスタージンガー》の主役ハンス・ザックスで、シュワルツコップのエーファと共演してデビューするが、アッカーマン/フィルハーモニア管弦楽団の伴奏での6
曲の録音が残されていたことはよろこばしい。大袈裟なハッタリや面白がらせる誇張を排したアッカーマンのワーグナー演奏、細部の自然な流れとともにアッカーマンの人間味を感じさせて爽やかな気分に誘うプログラムをを聴いていただけることと筆者は思います。」(小林利之) |

|
![]()