 NAXOS NAXOS
|


8.573283
\1100 |
ブロッホ:イスラエル交響曲・ヴィオラと管弦楽のための組曲
1-3.イスラエル交響曲(1912-1916)
<第1楽章:砂漠の祈り Lent et solennel/
第2楽章:贖罪の日 Allegro agitato/
第3楽章:仮庵の祝祭 Moderato (andante
grazioso)>/
4-7.ヴィオラと管弦楽のための組曲(1917-1919)
<第1楽章:Lento-Allegro-Moderato/
第2楽章;Allegro ironico/第3楽章:Lento/
第4楽章:Molto vivo> |
アドリアーナ・コウトコヴァ(ソプラノ)…3/
カタリナ・クラモリショーヴァ(ソプラノ)…3/
テレジア・バヤコヴァ(メゾ・ソプラノ)…3/
デニサ・ハマロヴァ(コントラルト)…3/
ミハル・マチュハ(バリトン)…3/
ユーリ・ガンデルスマン(ヴィオラ)…4-7/
スロヴァキア放送交響楽団…1-3/
アトラス・カメラータ管弦楽団…4-7/
ダリア・アトラス(指揮) |
録音 2000年10月18-22日 スロヴァキア,ブラティスラヴァ,スロヴァキア放送コンサート・スタジオ…1-3,
2001年5月10-11日…イスラエル,ハイファ,チャーチル・アウディトリアム…4-7
スイス出身のユダヤ人作曲家エルネスト・ブロッホ。彼の円熟期の中でもとりわけ重要な意味を持つのが、この「イスラエル交響曲」を始めとしたユダヤの民俗音楽、典礼音楽を元にした一連の作品です。
他にはチェロと管弦楽のための「シェロモ」や、ヴァイオリン曲「バール・シェム」、声楽のための「聖なる典礼」など多数の作品がユダヤの精神に由来してますが、この「イスラエル交響曲」はとりわけ編成も大きく、壮大な形式を持っています。
雄大な導入部を含む3楽章形式で書かれ、本来は「ユダヤの祝宴」というタイトルが付けられていましたが、ロマン・ロランの助言により現在のタイトルに改名されました。
また当初はもっと巨大な形を想定したいたのですが、完成時には整理されすっきりしたものとなっています。「組曲」はユダヤではなく、エキゾチックに憧れた彼の思いが結集した作品で、こちらも色彩豊かな管弦楽をバックにヴィオラが悠然と歌うという名作です。 |
| |


8.573273
\1100 |
ラ・ヴェッキア(指揮)&ローマ響/ブルーノ・カニーノ(ピアノ)
クレメンティ:ピアノ協奏曲&2つの交響曲集
他
1-3.ピアノ協奏曲 ハ長調 Op.33-3(1796)
4.メヌエット・パストラーレ ニ長調 WoO
36/
9-12.交響曲 ニ長調 Op.18-2(1787) |
ブルーノ・カニーノ(ピアノ)/
ローマ交響楽団/
フランチェスコ・ラ・ヴェッキア(指揮) |
録音 2012年10月28-29日 ローマ アウディトリウム・ディ・ヴィア・コンキリアツィオーネ…1-3,
2012年12月27-30日 ローマ OSRスタジオ
交響曲第1番&第2番(8.573071),交響曲第3番&第4番(8.573112)に続く、クレメンティ(1752-1832)の初期管弦楽作品のシリーズです。1780年代にいくつかの交響曲を作曲したクレメンティですが、いざ出版しようとした頃にハイドン登場。音楽界の人気を全て持って行ってしまったため、その他の作曲家たちは自作を出版することが難しくなってしまったのでした。
1796年に作曲されたピアノ協奏曲は、通常ソナタとして弾かれるOp.33-3の「原型」とされています。自筆譜はなく、1796年にヨハン・シェンクが書き写した譜面が残されていますが、本当のところ、ソナタが先で協奏曲が後なのかはわかっていません。
クレメンティの伝記作家プランティンガは、オケ・パートはシェンクによるもので、クレメンティの手によるものではないとも主張しています。Op.18の2つの交響曲は極めて古典的な様式を持つ整った美しさに満ちた作品です。変ロ長調の第1番は若干控えめですが、ニ長調の第2番は野心的な和声を持つ快活な音楽。ハイドンへの対抗意識もあったでしょうが、これはこれで素晴らしい作品になっています。 |
| |


8.571366
\1100 |
ボーエン:弦楽四重奏曲 第2番&第3番 他
1-3.弦楽四重奏曲 第2番 ニ短調 Op.41(1918頃)/
4-6.弦楽四重奏曲 第3番 ト長調 Op.46(b)(1919)/
7.バス・クラリネットと弦楽四重奏のための幻想的五重奏曲
Op.93(1932) |
ティモシー・ラインズ(バス・クラリネット)…7/
アルカェウス弦楽四重奏団
<メンバー:
アン・フーリー(第1ヴァイオリン)/
ブリジェット・デイヴィー(第2ヴァイオリン)/
エリザベス・ターンブル(ヴィオラ)/
マーティン・トーマス(チェロ)> |
録音 2001年12月16.18.20日 UK.ケント,トンブリッジ・スクール,リサイタル・ホール
ヨーク・ボーエン(ボウエン 1884-1961)はロンドン生まれの作曲家。若い頃はサン=サーンスに「イギリスの若き作曲家の中で最も注目すべき存在」と絶賛され、第1次世界大戦の前までは、ピアニスト、作曲家として素晴らしい活躍をしました。しかし、大戦後は彼のような「後期ロマン派」風の音楽を書く人は排除されてしまい、結局は忘れられてしまったのです。
最近になって再評価が進み、とりわけ「24の前奏曲」などのピアノ曲や、ヴィオラ・ソナタ(8.572580)などは、その独特の香り高い雰囲気が静かに愛されています。
このアルバムに収録された2つの弦楽四重奏曲は、どちらも比較的初期の作品で(第1番の四重奏は恐らく破棄されてしまったようです)古典的な形式に則って書かれています。第2番は「カーネギー・トラスト賞」を受賞した作品で、あのユージン・グーセンスに献呈されています。第3番も作曲時期はそれほど変わらないのですが、更に深化した表情を聴くことができます。
幻想的五重奏曲は、更に味わいのある音楽であり、バス・クラリネットを用いた点でも珍しく、輝かしいイギリス音楽の系譜に付け加えられるべき名曲と言えそうです。 |
| |

8.573314
\1100 |
金管七重奏のための音楽集
1-4.メンデルスゾーン(1809-1847):
オルガン・ソナタ ハ短調 Op.65-2(S.コックス編)/
5-8.シューマン(1810-1856):4つの二重合唱曲
Op.141(S.コックス編)/
9-13.ブラームス(1833-1897):5つのコラール前奏曲
Op.122より(S.コックス編)/
14.宗教的歌曲 Op.30(M.ナイト編)/
15-16.ブルックナー(1824-1896):2つのエクアーレ
ハ短調/
17.この場所は神が作り給う WAB23(M.ナイト編)/
18.キリストはおのれを低くして WAB11(S.コックス編)/
19.アヴェ・マリア WAB6(S.コックス編)/
20.正しき者の唇は知恵を語る WAB30(S.ヒックス編) |
セプトゥーラ
〈メンバー:
マシュー・ウィリアムス(B♭管トランペット)/
サイモン・コックス(B♭管トランペット)/
クリスティアン・バラクロウ(E♭管トランペット)/
ピーター・スミス(テューバ)/
マシュー・ギー(トロンボーン)/
マシュー・ナイト(トロンボーン)/
ダン・ウェスト(バス・トロンボーン)> |
録音 2013年11月10-12日 ロンドン ニューサウスゲート、聖ポール教会
バロック、もしくはそれ以前の時代には金管のためのアンサンブルは数多く存在していました。ガブリエリやモンテヴェルディ、バッハやヘンデル。彼らは神の声を楽器へと移し替える際に輝かしい金管楽器の音色を好んで用いたのです。しかし、ロマン派時代の作曲家たちは金管七重奏のための曲を書くことはほとんどありませんでした。
そこでアンサンブル「セプトゥーラ」はブラームス、ブルックナー、メンデルスゾーン、シューマンの合唱曲とオルガン作品を金管アンサンブル用に編曲。あたかもオリジナル作品であるかのように、自然で素晴らしい作品へ造り替えているのです。
「セプトゥーラ」のメンバーは、ロンドン交響楽団、フィルハーモニア、ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団、BBC交響楽団、バーミンガム市交響楽団、スコットランド歌劇場、オーロラ・オーケストラで活躍する若手金管奏者たちによって構成されています。この見事なアンサンブルには感嘆するほかありません。 |
| |

8.573293
\1100 |
アルベニス:ピアノ作品集 第5集
1-7.本位音を主音とする長調による7つの練習曲
T.67(1886)
<ハ長調/ト長調/ニ長調/イ長調/ホ長調/ロ長調/ヘ長調>/
8-11.四季 T.100(1892)<春/夏/秋/冬>/
12.キューバ風狂詩曲 T.46(1881)/
13-14.古風な組曲 第1番 T.62(1885頃)<ガボット/メヌエット>/
15.ピアノ・ソナタ 第1番-スケルツォ T.57(1884)/
16-17. 2つのサロン風マズルカ T.87(1888)<アマリア/リコルダーティ>/
18.秋-ワルツ T.96(1890) |
ホアン・ホセ・ムダーラ・ガミス(ピアノ) |
録音 2013年7月6-7日 スペイン マドリッド,リアル・コンセルヴァトリオ・スペリオール・デ・ムジカ
スペインの大作曲家、アルベニス(1860-1909)。彼の生涯はどうも謎が多く「数多くの冒険譚」などのエピソードはどうも存在しなかった模様で、最近新しい研究による伝記が出版されたとか…なかなか人騒がせな人物であったようです。
しかし、驚くべき神童であったことは間違いなく、4歳で最初のコンサートを行い、9歳で作品を発表するなど熟練と経験を幅広く積んでいたのです。
彼はスペインの民俗音楽を好んではいましたが、若干「時代遅れ」と感じていたようで、1889年にはロンドンに移住し、4年間生活することでこの地の文化を吸収したのです。
その後はフランスに移住。ここでもダンディやドビュッシーをはじめとした幅広い交友関係を築くことで、また新たな経験を積むことになります。このアルバムには、そんな若い時代のアルベニスの作品を聞くことができます。この頃の彼の作品の多くは、サロン風であり、印象派への憧れを含んだものであり、民俗音楽との融合はまだあまり感じさせないものばかりです。
まずは「キューバ風狂詩曲」あたりから聴いてみてください。とても活発で、気軽な音楽が、この時代のアルベニスを彷彿させます。 |
| |


8.559751
\1100 |
天才・・・カーター・パン
パン:ピアノの12のサイド 他
1-12.ピアノの12のサイド(2011/2012)
<シルエット/置き物/伝説/水の上の白い月/ル・ブランル/
クラシック・ロック/彼女は私を盗む/夕べの死の舞踏/
オリオン/子守歌/大幻想的練習曲/アイルランドの調べ>/
13-14.ビルズ
<ウィリアム・オルブライト-コンサート・ラグ/
ウィリアム・ボルコム-凝ったファンシー>/
15.チーズおろし器-2段階/
16.ユア・タッチ(ピアノ協奏曲 第1番のためのカデンツァ)
※世界初録音…1-15 |
|
ジョエル・ヘイスティング(ピアノ) |
録音 2013年8月17-20日 USA タッラハッセ,フロリダ州立大学
ルディ・ダイアモンド・コンサート・ホール
1972年生まれの若き作曲家、ピアニスト、カーター・パン(1972-)は既に数々の作品で国際的に高い評価を受けています。このピアノ曲集「12のサイド」は、彼の友人であるカナダのピアニスト、ジョエル・ヘイスティングとのコラボレーションから生まれた作品で、おのおのの曲にはタイトルと、彼に影響を与えた名ピアニストの名前が記されているという興味深いものです。
全ての曲は違った表情を持ち、ある曲は沈静し、ある曲はまるで埃のように、空気中を音符が漂います。ジャズ風な曲や大胆不敵な妙技の炸裂、そして不気味さ。捉えどころのない不思議な音楽ですが、妙に耳に残る強い存在感も有しています。
遊び心たっぷりの「ビルズ」、チーズおろし器でうっかり指を切ってしまったというアクシデントから生まれた作品、そしてピアノ協奏曲(8.559043)へのカデンツァとして書かれた「ユア・タッチ」は、アンニュイなジャズ。うーん、なかなか面白い作曲家なのです。
|
| |


8.559753
\1100 |
ケネス・フックス:落ち行く男
1-9.バリトンと管弦楽のための「落ち行く男」(2009-2010)
<序奏/アリア1/間奏曲 1/アリア 2/間奏曲
2/アリア 3/
間奏曲 3/アリア 4/コーダ(アリア 5)>/
10-16.バリトンと室内アンサンブルのための「ムーヴィー・ハウス」(2007)
<電柱/スプルースの森のカエデ/カモメ/短日/ムーヴィー・ハウス/
モディリアニのデスマスク/夏:ウエスト・サイド>/
17-20.バリトンと室内アンサンブルのための「無垢と経験の歌」(1977)
<羊/聖火曜日/春/トラ> ※世界初録音 |
ロデリック・ウィリアムズ(バリトン)/
ロンドン交響楽団/
ジョアン・ファレッタ(指揮) |
録音 2013年8月30日 UK アビー・ロード第1スタジオ…1-9/2013年8月31日
UK アビー・ロード第2スタジオ…10-16/2013年9月1日
UK アビー・ロード第2スタジオ…17-20
ここに収録された「落ち行く男」は、フックス(1956-)における重要なテーマであり、以前リリースしたピアノ曲「落ち行くカノン」や「落ち行く三重奏曲」(8.559733に収録)と密接な関連があります。
これらのテーマ、もともとは2007年に発表されたドン・デリーロの小説「Falling
Man」であり、9/11の事件の際、破壊されたワールド・トレード・センターの瓦礫に躓き、恐怖と混沌の感情に襲われた男を描いたものですが、この作品に強い感銘を受けたフックスが、この物語からこの歌を創り上げ、それを様々な作品に転用。そのどれもが衝撃的な風景を思い思いに映し出すのです。この悲しみは永遠に消えることはないでしょう。
「ムーヴィー・ハウス」はジョン・アップダイクの小説「金持ちになったウサギ」に触発された作品で、アメリカ人の完成と欲求を象徴的に描いたものです。「無垢と経験の歌」はボルコムの作品と同じく、ウィリアム・ブレイクの詩に基づいたもの。人間の存在の厳しさと牧歌的な無邪気さを併せ持つこの詩は、多くの芸術家に刺激を与えましたが、このフックス作品は独特の視点でこの詩を自らのものにしています。 |
| |


8.559759
\1100 |
ジェフスキ:4つの小品 他
1-4.4つの小品(1977)/
5-7.ハード・カッツ(2011) 〜ラルフ・ファン・ラートとルナパルクのために
<Ⅰ.-/Ⅱ.-/Ⅲ.ハチのように>/
8.主婦の嘆き(1980) |
ラルフ・ファン・ラート(ピアノ)/
ルナパルク(アンサンブル)…5-7/
アーノルド・マリニッセン(指揮)…5-7 |
録音 2011年8月10-11日 オランダ アムステルダム,スウェーリンクザール…1-4,8/2013年2月29日
オランダ ユトレヒト,ヴレデンブルク・リウエベルフ教会…5-7
最近、人気急上昇中の「不屈の民」変奏曲で知られる作曲家フレデリック・ジェフスキ(1938-)のまたもや刺激的なピアノ曲集の登場です。
「4つの小品」も、第1曲目では、難解で不気味なトレモロ音形の中に、時折親しみ易い「不屈の民」のテーマのようなメロディが埋め込まれています。もちろん気をつけていないとすぐにどこかに紛れてしまうほどの儚いものですが。
第2曲目は両手のユニゾンで始まるリズム重視の曲。彼の友人であったスティーヴ・レイシー(セロニアス・モンクの弟子であった人)の影響を受けているといます。
第3曲目はゆったりとしたアンデスの舞曲に由来するというメロディは、どことなくショスタコーヴィチの作品を想起させます。曲の終わり、破壊的な和音連打による盛り上がりの後には完全な沈黙が訪れます。
第4曲目も不可解な曲で、幾つもの層となった音が平和な耳を襲ってきます。匿名の女性作曲家の日記から題材を得たという「主婦の嘆き」はベートーヴェンの強い影響があるというものです。この曲も最初のわかり易すぎるメロディにだまされてはいけません。
そしてアンサンブルをともなう「ハード・カッツ」は抽象的な音の化合物。巧妙に仕組まれた音の乱舞が楽しくも狂おしい作品です。第3曲「Like
bees」などは、寝ている時に耳元で鳴らされたら気が変になるかも。 |
| |


8.571362
\1100 |
クック:弦楽のためのソナタ集
1-3.ヴァイオリン・ソナタ 第2番(1951)/
4-6.ヴィオラ・ソナタ(1936-1937)/
7-10.チェロ・ソナタ 第2番(1980)
※世界初録音 |
スザンヌ・スタンツェライト(ヴァイオリン)…1-3/
モーガン・ゴフ(ヴィオラ)…4-6/
ラファエル・ウォルフィッシュ(チェロ)…7−10/
ラファエル・テッローニ(ピアノ) |
録音 2005年10月2.9.16日 UK ロンドン,グィルドホール音楽演劇学校,音楽ホール
2005年に98歳でその生涯を閉じた作曲家、アーノルド・クック(1906-2005)。彼はイギリスのゴマーサルに生まれ、ケンブリッジ大学で歴史を学ぶも、音楽の道を志し、1929年からベルリン音楽アカデミーでヒンデミットに師事、ピアノと作曲を学んだという人です。
1930年代には、その作品が高く評価され、数多くの演奏会が催され、いくつかの賞も獲得しましたが、それらは主に管弦楽作品の評価であって、ここで聞けるような室内楽作品はあまり重要視されることはなく、ほとんど忘れられてしまったのでした。
この3つのソナタもそのような作品群で、1940年に出版された「ヴィオラ・ソナタ」の初々しい機動力と、その40年後の作品である「チェロ・ソナタ」の憂愁に溢れた渋さの違いを楽しむだけでも、このアルバムを聴く価値があると言えるでしょう。現代作品とは言え、聴いていてふっと安心できる音楽に満たされているところが素晴らしいの一言です。 |
| |


8.572773
\1100 |
エル=コーリー:3つの協奏曲集
1-3.ヴァイオリン協奏曲 第1番「どこからともなく国境に」Op.62/
4-6.ホルン協奏曲「暗い山」Op.74(2007-2008)/
7-9.クラリネット協奏曲「秋の絵」Op.78(2009-2010) |
サラ・ネムタヌ(ヴァイオリン)…1-3/
デヴィッド・ゲリエ(ホルン)…4-6/
パトリック・メッシーナ(クラリネット)…7-9/
フランス国立管弦楽団…1-6/
パリ室内管弦楽団…7-9/
クルト・マズア(指揮)…1-3/
ジャン=クロード・カサドシュ…4-6/
オラリー・エルツ…7-9 |
録音 2006年5月25日 パリ シャンゼリゼ劇場…1-3,
2009年9月18日 パリ ラジオ・フランス サル・オリヴィエ・メシアン
Festival ‘Presences…4-6 , 2010年11月10日
パリ シャトレ劇場 Festival ‘Les Paris de
la Musique…7-9
レバノンの作曲家、ビシャーラ・エル=コーリー(1957-)。このアルバムはNAXOSにおける第5作目の作品集です。彼は多くの場合、自然からインスピレーションを受け、その音楽の中には瞑想、回想、そして夢が含まれています。
タイトルを持つ作品が多いのですが、これは特定の何かを暗示するのではなく、どちらかというと雰囲気重視であり、この3つの協奏曲もレバノンの自然風景などを想起させるものです。とは言え、ヴァイオリン協奏曲は2002年にレバノンで開催された「フランコフォニー国際機関」サミットからの委嘱作で、メシアンが提唱した「移調の限られた旋法」に基づくモティーフが使われ、神秘的な雰囲気を醸し出しています。第2楽章はそのままカデンツァで、ソリストには超絶技巧が要求されます。
ホルン協奏曲は、彼が子供時代に経験した山の中の風景の思い出が織り込まれています。山の陰鬱さと雄大さは、人間の脆弱さをも描き出します。「秋の絵」も彼の記憶の中にある風景描写で、高い空の雲や東の空の色などが反映されているといいます。 |
| |

8.573080
\1100 |
イギリス歌曲シリーズ 第23集
ダブ:歌曲集「今宵眠る全ての人へ」他
1-6.歌曲集「冬から」(2003)/
7-9.歌曲集「わが影を棄てて」(2011)
<驚き/ギター/乾いたオレンジの樹の歌>/
10-14.歌曲集「アリエル」(1998)
<黄砂のもとに/私は王の船に乗り込んだ/
オー,オー,オー/全ての雹よ、偉大なる巨匠/
より多くの苦労はあるの?>/
15-27.歌曲集「今宵眠る全ての人へ」
<状態/電話/横切る/食事の嘆き/解釈/誤り/神の愛/
暗き道のり/ドア/夜の時計/声/間もなく/今宵眠る全ての人へ>
※15-27…世界初録音 |
クレール・ブース(ソプラノ)…10-14/
パトリシア・バルドン(メゾ・ソプラノ)…7-9,15-27/
ニッキー・スペンス(テノール)…1-6/
アンドリュー・マシューズ=オーウェン(ピアノ)…1-9,15-27 |
録音 2014年4月1-2日…1-9,15-27, 2014年5月5日…10-14
UK サリー コブハム,メニューイン・ホール
NAXOSの好評シリーズ、イギリスの歌曲集第23集は、ジョナサン・ダヴ(1959-)の歌曲です。彼は現代の英国において、最も機知に富む多彩な音楽を創り出す作曲家の一人として評価されており、中でも歌曲、合唱曲については最高の賛辞が贈られています。
このアルバムには4つの歌曲集が収録されていて、最初の「冬から」はロバート・ティアの詩によるもので、曲の雰囲気はどこかブリテンの一連の歌曲を思わせる、繊細な静けさを湛えています。
「わが影を棄てて」はガルシア・ロルカの英語訳のテキストが用いられており、乾いたリアリズムが横溢する音楽です。「アリエル」はすばらしく神秘的な歌曲で、伴奏なしのソプラノのみで歌われます。歌手は黄砂を運ぶ風の音までをも歌わなくてはなりません。エキゾチックなヴォカリーズである第3曲目は、この世のものとは思えないほどの不思議な印象を残すでしょう。
5つのセクションからなる「今宵眠る全ての人へ」はロマンティックな感情と、宗教性、心、場所、四行詩がモティーフ。歌曲はプーランクを思わせる聖と俗が入り混じった物語が描かれ、聴き疲れた人は深い眠りに誘われるのです。 |
| |


8.573164
\1100 |
パヌフニク&ルトスワフスキ:弦楽四重奏曲集
1.パヌフニク(1914-1991):弦楽四重奏曲 第1番(1976)/
2.パヌフニク:弦楽四重奏曲 第2番「メッセージ」(1980)/
3.パヌフニク:弦楽四重奏曲 第3番「ヴィチナンキ-切り絵」(1990)/
4-5.ルトスワフキ(1913-1994):弦楽四重奏曲(1964) |
ティペット四重奏団
<メンバー:
ジョン・ミルズ(第1ヴァイオリン)/
ジェレミー・アイザック(第2ヴァイオリン)/
リディア・ラウンドス=ノースコット(ヴィオラ)/
ボジダル・ヴコティッチ(チェロ)> |
録音 2013年2月4-5日…1-3, 2013年6月17日…4-5
UK ケンブリッジ大学 シドニー・サセックス・カレッジ
2014年はポーランド出身の作曲家アンジェイ・パヌフニクの生誕100周年にあたります。もちろんポーランドだけでなくワールドワイドに活躍した人であり、ウィーンで学んでいた時代には、日本の音楽家の尾高尚忠と交流があったことでも知られている人です。
彼が書いた10曲の交響曲は最近になって耳にする機会が増えていますが、この辛辣な弦楽四重奏曲も彼を知るためには外せないものです。
各々の楽器が静かに呼応する印象的な始まりの第1番、北ウェールズ音楽祭のために書かれた第2番、最晩年の作品で、抽象的な美しさを秘めた第3番と、どれも単一楽章ながら、強い印象を残します。
もう一人の偉大なるポーランドの作曲家、ルトスワフスキの弦楽四重奏曲は、彼がヨーロッパの最前線の音楽界に身を置いていた時期の作品で、強迫的なモティーフの積み重ねが興味深い音の世界を織り上げていきます。 |
| |

8.573194
\1100 |
ヒンデミット:オルガン・ソナタ 第1番-第3番
1-5.オルガン・ソナタ 第1番(1937)/
6-8.オルガン・ソナタ 第2番(1937)/
9-12.オルガン・ソナタ 第3番「古い民謡より」(1940)/
13-14.オルガンのための2つの小品(1918)/
15-25.ルードゥス・トナリスから11のインターリュード(1942)
(J.ドルフミュラーによるオルガン編)
<第1番:モデラートとエネルギー/
第2番:パストラーレ、モデラート/
第3番:スケルツァンド/第4番:はやく/
第5番:モデラート/第6番:行進曲/
第7番:とても幅広く/第8番:とてもはやく/
第9番:とても静かに/
第10番:快速に、重々しくに/第11番:ワルツ> |
キルステン・シュトルム(オルガン)…ロッテンブルク大聖堂、フーベルト・ザントナー・オルガン(1978-79) |
録音 2013年6月9日 ドイツ ネッカー,ロッテンブルク
聖マルティン大聖堂
ヒンデミット(1895-1963)は優れたヴィオラ奏者でもあり、またほとんどの楽器を演奏したという才人でしたが、オルガン音楽については専門家ではありませんでした。しかしこの3つのソナタは、オルガニストたちのレパートリーとして現在でも大切にされています。
バロック以前の時代から、オルガンという楽器は「神の声」を現すものとして、神聖化される傾向にありましたが、ヒンデミットはそんな楽器の側面に配慮することはなく、他の楽器のように、極めて実用的に鳴らすことを考えます。
彼のオルガン・ソナタには馴染みのあるコラールのメロディはどこにも使われていません。そのためバッハやレーガーの作品は純粋な教会音楽として堪能できますが、ヒンデミットの作品はあくまでもコンサート用であり、楽器の響きや性能をそのまま楽しみたい現代の人にはぴったりなのです。
「11のインターリュード」は彼がピアノのために書いた小品集。彼の理論をそのまま音にしたような多彩な表現力を必要とするもので、これをオルガンで演奏するというのは、色々な意味で面白いものです。 |
| |

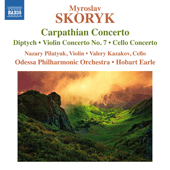
8.573333
\1100 |
泣きます・・・「メロディ」
ウクライナの作曲家ミロスラフ・スコリク
スコリク:カルパティア協奏曲 他
1.グツールの三連祭壇画-第1番 幼年時代(1965)/
2.二連祭壇画(1993)/
3.24のカプリースから第19番(M.スコリクによる管弦楽編)(2003)/
4.ヴァイオリン協奏曲 第7番(2009)/
5.メロディ(管弦楽版)(1981)/
6.チェロ協奏曲(1983)/
7.「石の客」組曲-スペイン舞曲(1973)/
8.管弦楽のための「カルパティア協奏曲」(1972)
※世界初録音…2.3.4.5.6.7 |
ナザリー・ピラチュク(ヴァイオリン)…4/
ヴァレリー・コザコフ(チェロ)…6/
オデッサ・フィルハーモニー管弦楽団/
ホーバート・アール(指揮) |
録音 2013年11月6.8日 ウクライナ オデッサ・フィルハーモニー・ホール
いつか取り上げますね。スコリクの「メロディ」。
ウクライナの作曲家ミロスラフ・スコリク(1938-)は、リヴィウに生まれるも、第二次世界大戦後に家族がシベリアに追放され、1955年まで帰国を許されなかったためその地で多感な少年時代を送ります。この地で多くの「政治犯」とされる人から音楽を学び、教師として教えるまでになりますが、ウクライナに戻ってからは、モスクワ音楽院でカバレフスキーに学ぶなどその才能を順当に伸ばし、偉大な作曲家として現在もウクライナで生活しています。
彼の音楽には聖書や哲学の精神、古典と前衛、民俗音楽とジャズのリズムなどが含まれていて、それはあまりにも多彩であるためジャンルを特定することは出来ません。
このアルバムに収録された音楽も多種多様な味わいを持つものばかりで、良く知られる「グツールの三連祭壇画」での悲しげな表情と、それに続く「二連祭壇画」のパワフルでエネルギッシュな音楽は、彼の特性を端的に表すものと言えるでしょう。
また、管弦楽のための「カルパティア協奏曲」はとても魅力的な作品で、多種多様な楽器が存分に活躍する興味深いもの。まずはここから聴いてみてはいかがでしょうか? |
| |


8.660359
(2CD)
\2200 |
マクスウェル・デイヴィス:歌劇「復活」Op.129(1987)
プロローグと1幕 |
長女,フェブス・アポロ,アンチキリスト…
デッラ・ジョーンズ(メゾ・ソプラノ)/
母,ゼウス/ヘラ…
クリストファー・ロブソン(カウンターテナー)/
校長,外科医1,白大修道院長,司教…
マーティン・ヒル(テノール)/
狂句牧師,プルート,ホット・ゴスペラー…
ネイル・ジェンキンス(テノール)/
父,外科医2,レヴの大臣,警官…
ヘンリー・ハーフォード(バリトン)/
弟,外科医3,クロス・ライト卿,裁判官…
ジェラルド・フィンリー(バリトン)/
医師,外科医4,同志セルブスキー,トレード・ユニオン・リーダー…
ジョナサン・ベスト(バス)/
ロック・バンド…Blaze/
ロック・バンドのヴォーカル、
ネコ…メアリー・カレヴェ/
エレクトロニック・ヴォーカル・カルテット
<メンバー:
レスリー・ロジャース(ソプラノ)/
デボラ・マイルス=ジョンソン(アルト)/
ジョン・ボウリー(テノール)/
マーク・ロウリンソン(バス)>/
BBCフィルハーモニック/
マクスウェル・デイヴィス(指揮) |
録音 1994年9月8日 UK マンチェスター,ロイヤル・ノーザン・カレッジ・オブ・ミュージック
Collins Classicsからの移行盤
この作品は、マクスウェル・ディヴィス(1934-)がプリンストン大学で学んでいた1960年代から着想されていたものです。しかしそれは結局1980年代まで実現することはなく、最終的に完成、上演されたのは1987年ドイツのダルムシュタットでした。
作品はさすがに彼らしく、様々な要素が内包されていて、とても一言では言い尽くせません。まさに「暴力的な多様性」を秘めた作品です。
登場人物だけを取り上げてみても異様です。何しろ、テレビ広告の声や、ロック・バンドまで登場するのですから。手術台に載せられ脳の手術を受けた英雄は、その痛みや不快感をナンセンスな歌で外科医に伝え、救世主の復活はテレビコマーシャルで伝えられます。
英雄は等身大の人形で、家族の中の母の役割ははカウンターテナーが受け持ちます。随所に猫の歌が挿入され、様々な楽器は調子はずれの曲を流し続けます。
雑多なものが詰め込まれている風を装いながら、実は社会への痛烈な批判が込められているあたりが、この作曲家のすごいところでしょう。 |
| |

8.573362
\1100 |
期待の新進演奏家シリーズ/エマヌエレ・ブオーノ
2013年 ミケーレ・ピッタールガ・ギターコンクール優勝記念
1.ダ・ミラノ(1459-1543):モン・ペル・シ・マ・マリエ/
2.ダ・ミラノ:ファンタジア第33番/
3.ダ・ミラノ:リチェルカーレ第34番 「ラ・カンパーニャ」/
4.ディオニシオ・アグアド(1784-1849):
3つの華麗なロンド Op.2-第2番アンダンテ
- ロンド・モデラート/
5-8.カステルヌオーヴォ=テデスコ(1895-1968):
ギター・ソナタ ニ長調 「ボッケリーニへのオマージュ」
Op.77/
9.ホアキン・ロドリーゴ(1901-1999):祈りと踊り
(マヌエル・デ・ファリャへのオマージュ)/
10-13.アントニオ・ホセ(1904-1936):ソナタ(1933) |
エマヌエレ・ブオーノ(ギター) |
録音 2014年1月16-18日 カナダ オンタリオ,聖ジョン・クリソストム教会
1987年トリノ生まれの若手ギタリスト、エマヌエレ・ブオーノのリサイタル・アルバムです。幼い頃からギターを学び、18歳の時にはジュゼッペ・ヴェルディ音楽院で優秀賞を獲得しています。
ミラノ音楽院に進学し、2008年のアレッサンドリア国際ギターコンクールではヤングアーティスト賞(翌年、あのパク・キュヒも同賞を受賞)に輝き、その後も数多くのコンクールで優勝していますが、やはりこのミケーレ・ピッタールガ・ギターコンクールでの優勝は、彼のキャリアに大きな転機を齎すことは間違いありません。
この受賞記念のアルバムは、彼の得意なレパートリーがふんだんに用意されていて、イタリア・ルネサンスの典雅な作品から20世紀のモダンな作品まで、その多彩な表現をたっぷり味わうことができるもの。ジャケ写の落ち着いた雰囲気そのままの「大人の演奏」をする逸材です。 |
![]()