≪第77号アリアCD新譜紹介コーナー≫
その9 8/12〜
マイナー・レーベル新譜
歴史的録音・旧録音
メジャー・レーベル
国内盤
映像 |
8/15(金)紹介新譜
マイナー・レーベル新譜
 IBS CLASSICAL IBS CLASSICAL
|
|
|
ガルシア:無限の現在 〜 合唱作品集
マチャド:Canciones del Aito Duero、Siete
Proverbios
ヒメネス:
Senor, me cansa la vida、Lo que Vos querais,
Senor、3つの抒情詩
E・M・ヴィヴァルディ:アマリージョ
ロルカ:6つのカプリース、Cien jinetes enlutados
カルバハル:Cada vez que una mano se me
ofrece、Oda la musica |
ヌーメン・アンサンブル |
| スイスの古楽総本山バーゼル・スコラ・カントルムで学んだヘクトール・E・マルケスが2011年に創設したスペインのヴォーカル・アンサンブル、ヌーメン・アンサンブルによるフアン=アルフォンソ・ガルシアの合唱作品集。アンダルシアの作家、アントニオ・マチャド、フェデリオ・ガルシア・ロルカ、E・M・ヴィヴァルディなど20世紀の現代作家の詩を、ヌーメン・アンサンブルの美しい歌声で。 |
LIR CLASSICS
|
|
|
バッハ・リサイタル 〜 J.S.バッハ:鍵盤作品、トランスクリプション集
幻想曲とフーガ ト短調 BWV.542(リスト編)
6つの小前奏曲
イタリア協奏曲ヘ長調 BWV.971
カンタータ第147番〜コラール《主よ人の望みの喜びよ》
BWV.147(ヘス編)
カンタータ第4番《イエス・キリスト、神の御子》
BWV.4(ルンメル編)
コラール《主イエス・キリストよ、われ汝に呼ばわる》BWV.639(ブゾーニ編)
カンタータ第22番《汝の善行により我らを浄めたまえ》
BWV.22(ルンメル編)
前奏曲とフーガ イ短調 BWV.543(リスト編) |
ペネロペ・スウェイツ(ピアノ) |
シャンドス(Chandos)で「ピアノ独奏作品集Vol.3〜フォスターに捧ぐ子守歌(CHAN
10205)」や「グレインジャー・エディション第17巻ピアノ独奏作品集2(CHAN
9919)」でなど多くの作品を録音している女流ベテラン・ピアニスト、ペネロペ・スウェイツによるJ.S.バッハの鍵盤作品集。1991年に国際パーシー・グレインジャー協会のメダリオンに輝くなどグレインジャーのスペシャリストとしても知られるペネロペ・スウェイツ。柔軟かつ繊細なタッチでJ.S.バッハの作品も見事に表現する。
2013年2月4日−6日の録音。 |
 STONE RECORDS STONE RECORDS
|
|
|
メンデルスゾーン:チェロとピアノのための作品全集
協奏的変奏曲ニ長調 Op.17
チェロ・ソナタ第1番変ロ長調 Op.45
無言歌ニ長調 Op.109
アッサイ・トランクィッロ
チェロ・ソナタ第2番ニ長調 Op.58 |
マリー・マクラウド(チェロ)
マッティン・ステュルフェルト(ピアノ) |
ロイヤル・ストックホルム・フィル首席によるメンデルスゾーン!伴奏はマッティン・ステュルフェルト!
2013年からスウェーデンの名門、ロイヤル・ストックホルム・フィルの首席奏者を務める女性チェリスト、マリー・マクラウドのメンデルスゾーンの「チェロとピアノのための作品全集」。
伴奏はスウェーデンの俊傑、マッティン・ステュルフェルト。11歳で定期的にリサイタルを開きキャリアをスタート。その後はソロや室内楽で活躍。2012年にはピアノ王国ハイペリオン(Hyperion)からヴィークルンドの協奏曲をリリース(CDA
67828)。
両者は2003年からデュオでの活動を始め、長きに渡り、数多くの共演を果たしている。今勢いがある名手たちによるメンデルスゾーンは、柔和な音色で味わい深い音楽を聴かせてくれる。
2009年9月9日−10日の録音。 |
| |
|
|
赤い女の心 〜 オーストラリアン・アート・ソングス
サザーランド:
4つのブレイク・ソング、6つの歌曲、
ジュディス・ライトの詩による6つの歌曲
アレン:覚えていた恋 Op.62z
グランヴィル=ヒックス:
プロフィールズ・フロム・テャイナ、
ブラックバードの13通りの見かた
ハンソン:2つの歌曲 Op.7、これは私の喜び
Op.14
フィリップス:2つのヘブライ語歌曲 |
リサ・ハーパー=ブラウン(ソプラノ)
デイヴィッド・ウィッカム(ピアノ) |
オーストラリア有数のソプラノ、リサ・ハーバー=ブラウンと、名伴奏としても知られるデイヴィッド・ウィッカムによるオーストラリアン・プログラム。知られざる作曲家の作品を聴くことが出来る貴重なアルバム。デイヴィッド・ウィッカムの解説もポイント。
2013年2月18日−19日の録音。 |
| |
|
|
コープ:失われた魂のための子守歌
流れよ、涙/魂の連鎖/
パッサカリア/他 |
マギッド・エル=ブシュラ(カウンターテナー)
ジル・カーター(フルート)
マシュー・ターナー(ヴィブラフォン)
ジュリア・デスブルスライス(チェロ) |
ジョン・ダウランド(1563−1626)のリュート作品を、ロナルド・コープ(b.1951)による独自のアレンジや、フランシス・ブースの詩によって大胆にアレンジされた「失われた魂のための子守歌」。独自の解釈で、17世紀のリュート作品に新たな響きを加え、現代曲に生まれ変わったコープの作品を、フルートやカウンターテナーの叙情的なフレージングで聴くことが出来る。
2012年9月12日−13日の録音。 |
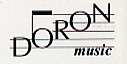 DORON DORON
|
|
|
世界初録音あり ヴェルディ、ベッリーニ、ドニゼッティ歌曲集
「ヴィヴァ・ヴェルディ!」〜歌曲・ピアノ作品集
ヴェルディ:
亡命者,墓に近づくな,孤独な部屋で,言葉のないロマンツァ(ピアノ独奏),
私は平安を失った,どうか哀れみを、おお、悲しみの聖母様,
ワルツ ヘ長調(ピアノ独奏),煙突掃除夫,乾杯
ベッリーニ:
激しい希求,フィッリデの悲しげな姿よ,優雅な月よ,
ラルゴ ヘ短調(ピアノ独奏),墓に近づくな(ピアノ独奏)
ドニゼッティ:西風の翼に乗って,糸巻き棒,愛と死,私は家を建てたい |
|
グラツィエラ・ヴァルチェヴァ・フィエロ
(メッゾソプラノ)
ヴェネツィエラ・ナイデノヴァ(ピアノ) |
録音:2013 年4 月30 日、5月6 日,ローザンヌ、DDD、56'18
ガエターノ・ドニゼッティ、ヴィンチェンツォ・ベッリーニ、ジュゼッペ・ヴェルディの歌曲およびピアノ独奏曲。数曲は世界初録音とされる。グラツィエラ・ヴァルチェヴァ・フィエロはブルガリアのメッゾソプラノ。ソフィアで学びデビューした後、スイスのローザンヌに移り、オペラ、オラトリオ、歌曲と幅広く活躍している。 |
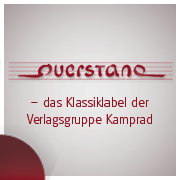 QUERSTAND QUERSTAND
|
|
|
「バッハからブロードウェイへII」
「我が魂は主をあがめ」 SWV426(シュッツ)
「主をたたえよ、すべての異教徒よ」 BWV230(J.S.バッハ)
「アレキサンダーのラグタイム・バンド」(アーヴィン・バーリン)*
「ウェスト・サイド・ストーリー」メドレー(バーンスタイン/サットン)*
「剣の舞」(ハチャトリアン)*
「ピンク・パンサー」(ヘンリー・マンシーニ)*
「パリのアメリカ人」(ガーシュイン/サットン)*
「ミスター・サンドマン」(パット・バラード)*
「プレス」(ジョゼ・ジトニク)* |
オーパス4(トロンボーン四重奏団)
コニー・ゾマー(Perc)*印 |
トロンボーン四重奏による「バッハからブロードウェイへ」第2弾!
録音:2013 年7 月
オーパス4のQUERSTAND へのアルバム第5 弾で好評の「バッハからブロードウェイへ(VKJK0420)」の第2集です。
オーパス4 はライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団のメンバーであったイェルク・リヒター、ディルク・レーマン、シュテファン・マイナー、ヴォルフラム・クーントの4
名からなるトロンボーン四重奏団で1994 年に結成、今年が結成20
周年の記念アルバムとしてバロックからブロードウェイのヒット・ナンバーをトロンボーンでオシャレに聴かせる。トロンボーン関係者は必携。 |
| |
|
|
「キューピッドと小夜啼鳥(さよなきどり)」
〜様々な楽器の伴奏によるバロック・カンタータとアリア
A.スカルラッティ:ソプラノとクラリネットと通奏低音のための2つのアリア
ヘンデル:カンタータ「ヴィーナスとアドニス」
HWV 85
テレマン:希望は私を慰める
パーセル:このように悲観的な世界が輝き始め
コレッリ:ヴァイオリンと通奏低音のためのソナタOp.5-8
ほか全12 曲26 トラック |
フリードリケ・ホルツハウゼン(Sop)
ズザンネ・エールハルト
(バロック Cl, リコーダー,シャルマイ)
ザビーネ・エルドマン(Cemb, Org) |
録音:2013 年3 月
軽やかでさわやかなバロック歌曲集。ソプラノのフリードリケ・ホルツハウゼンはライプツィヒ出身でゲバントハウス管弦楽団と多く共演、ベルリン・フィルでも多くの宗教曲のソリストを務めている。通奏低音の他にクラリネットやリコーダーが入って色彩豊かで典雅な世界が広がる。 |
| |
|
|
「小象のババール」と「動物の謝肉祭」はドイツ語による語りつき
(1)プーランク:小象のババールのお話
(2)フォーレ:ドリー〜4手連弾のための
(3)サン=サーンス:動物の謝肉祭〜4手連弾版 |
デュオ・トゥーシュ:
【アナーノ・ゴキエッリ(Pf)&
フランク=インモ・ジックナー(Pf)】
(1)(3)ミハエル・ゼンス(語り・ドイツ語) |
録音:2013 年9 月
「小象のババール」と「動物の謝肉祭」はドイツ語による語りつき。語りのミハエル・ゼンスはナレーターが必ずしも本業ではなく、ベルリンのハンス・アイスラー音楽大学でヴァイオリン、ピアノと歌を学び、その後、フリーランスのキャバレー・アーティストとして活動、作家としても活躍するマルチ・タレント。 |
 ROMEO RECORDS ROMEO RECORDS
|
|
|
「イタリアの1880年世代とその弟子たち」
ダラピッコラ:タルティーニアーナ第2番
レスピーギ:ヴァイオリン・ソナタ ロ短調
ゲディーニ:ビッザーリア
ロータ:即興曲 ニ長調 「感傷的な悪魔」
ピッツェッティ:ヴァイオリンとピアノのための3つの歌
マリピエロ:遠くからの歌,無限の歌 |
カレイドス・デュオ:
【ミロスラフ・フリストフ(Vn)
ウラディーミル・ヴァリャレヴィッチ(Pf)】 |
ダラピッコラ、レスピーギ、ロータ他、20世紀イタリアのヴァイオリン作品集
録音:2013 年5 月20-23 日、ルイジアナ
「イタリアの1880 年世代とその弟子たち」と題された興味深い内容のCD。オットリーノ・レスピーギ(1879-1936)、イルデブランド・ピッツェティ(1880-1968)、ジャン・フランチェスコ・マリピエロ(1882-1973)の三人は、20
世紀のイタリア音楽に近代の新風を送り込んだ人たちで、ジョルジョ・ゲディーニ(
1892-1965 ) 、ルイージ・ダラピッコラ( 1904-1975
) 、ニーノ・ロータ(1911-1979)はその後の世代になる。印象主義、新古典主義、モダニズム、多様な作風が見られ、非常に面白い。ミロスラフ・フリストフはブルガリア出身のヴァイオリニスト。 |
| |
|
|
「情熱と幻想」
ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第23番へ短調「熱情」Op.57
ショパン:幻想曲へ短調Op.49
ショパン:ピアノ・ソナタ第3番ロ短調Op.58 |
ソフィア・アグラノヴィッチ(Pf) |
録音:2013 年8 月
ソフィア・アグラノヴィッチはウクライナ出身のピアニストで10
歳で全ウクライナ・ヤング・アーティスト・コンペティションに入賞、その後、モスクワ音楽院、ジュリアード音楽院と異なる校風の中で研鑽を積み、ソロ、室内楽を中心に活動している他、教育者、音楽祭のオーガナイザーにも近年力を入れている。女性とは思えない強い打鍵による骨太なベートーヴェンとショパン。 |
 ZKP RTV SLOVENIJA(スロヴェニア放送) ZKP RTV SLOVENIJA(スロヴェニア放送)
|
|
|
「イザイ:無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ集
Op.27」
ソナタ第1番 ト短調 「ヨゼフ・シゲティに」
ソナタ第2番 イ短調 「ジャック・ティボーに」
ソナタ第3番 ニ短調 「ジョルジュ・エネスコに」
ソナタ第4番 ホ短調 「フリッツ・クライスラーに」
ソナタ第5番 ト長調 「マチュー・クリックボームに」
ソナタ第6番 ホ長調 「マヌエル・デ・キローガに」 |
ジガ・ブランク(ヴァイオリン) |
ジガ・ブランクの素朴で味わい深いイザイ
録音:2009 年5 月8-9 日,2011 年6 月15
日,2012 年1 月31 日,2 月28 日,11月6 日,12
月4 日、70'31
ジガ・ブランクはスロヴェニアで活発に活動するヴァイオリニスト。スロヴェニア国立劇場交響楽団のコンサートマスターを務めた後、現在はリュブヤーナ音楽・バレエ学院の教授。緊張感の高い演奏の中に、じわりと素朴な味わいが広がる演奏である。 |
| |
|
|
「フアン・ヴァスレ アリア集」
ベッリーニ:「夢遊病の女」—お前を覚えているぞ、心地よい地よ
チャイコフスキー:「エフゲニー・オネーギン」—誰でも一度は恋をして
グリンカ:「皇帝に捧げた命」—真実が気づかれそうだ
ロッシーニ:「セビリアの理髪師」—中傷はそよ風
モーツァルト:「フィガロの結婚」—もう愛の蝶も飛べない
マスネ:「ドン・キショット」—笑え、そら、笑え、哀れな理想家を
オッフェンバック:「ホフマン物語」—輝け、ダイヤモンド
ソロサーバル:「港の酒場女」—目を覚ませ、黒い奴よ
シュヴァラ:「クレオパトラ」—ああ、果てしない力と可能性の素晴らしさ
ヴェルディ:「ドン・カルロ」—彼女は私を愛していなかった
ヴェルディ:「ナブッコ」—来なさい、ああ、レビ人よ
ヴェルディ:「シチリアの晩鐘」—ああ、そなた、パレルモよ
ヴェルディ:「シモン・ボッカネグラ」—引き裂かれた心 |
フアン・ヴァスレ(バス=バリトン)
ロレンツォ・カステリオータ・
スカンデベルク(指揮)
ジガ・スタニチ(指揮)
ミリボイ・シュルベク(指揮)
ダヴィド・デ・ヴィラース(指揮)
ニコライ・ジュリチャル(指揮)
スロヴェニア放送交響楽団 |
アルゼンチン出身スロヴェニアで活躍するヴァスレのアリア集
録音:1992年1月14日,1996年1月23日,9月10日,2003年4月1-3日,2004年2月27日,2011年5月11日、62'55
フアン・ヴァスレは、1954 年、アルゼンチン、ブエノスアイレス生まれのバス=バリトン。1990
年からリュブヤーナのスロヴェニア国立オペラ・バレエ劇場の筆頭バスとして活躍、長年に渡ってリュブヤーナを拠点としているため国際的な知名度は低いが、実力の高い歌手である。20
年近くの幅のある様々な機会の録音を集めたものである。 |
<マイナー・レーベル歴史的録音・旧録音>
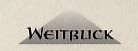 WEITBLICK WEITBLICK
|
|
|
スヴェトラーノフ 巨大で深淵なモーツァルト!!
(1)モーツァルト:交響曲第40番ト短調K.550
(2)モーツァルト:交響曲第41番ハ長調K.551「ジュピター」 |
エフゲニ・スヴェトラーノフ(指揮)
スウェーデン放送交響楽団 |
交響曲第40番、第41番「ジュピター」ライヴ
録音:(1)1988 年9 月10 日ライヴ・ステレオ (2)1993
年9 月18 日ライヴ・デジタル *ベルワルド・ホール
演奏タイミング:(1)[9:19][12:11][5:06][10:36] (2)[11:24][9:03][4:12][9:26]
巨匠スヴェトラーノフのモーツァルト!演奏スタイルがミニマムなことがトレンドの昨今、それに真っ向から逆らうような演奏と言えます。芸術家、音楽家としてモーツァルトを嫌いという人はいないでしょうが、スヴェトラーノフもまた類希なモーツァルティアンであったことは、NHK交響楽団との共演でも第34
番を大編成で演奏し、聴衆の度肝を抜いたことからも明らかでしょう。
しかし録音には恵まれておらず、第40 番の貧弱なモノラル録音が聴けるだけでした。そこに登場するのが美しい音色、高い技術で知られるスウェーデン放送響とのライヴです。
この豊饒な歌と恰幅の良さは巨匠の古典レパートリーに共通するものですが、モーツァルトの奥の院ともいえる後期交響曲ともなると、その思想や内容も広大無比であり、ロマンチスト、スヴェトラーノフにピッタリな作品と申せましょう。
※英語、日本語、ドイツ語によるライナーノート付 |
<メジャー・レーベル>
<映像>

8/14(木)紹介新譜
マイナー・レーベル新譜
 BIS BIS
|


BIS SA 2077
(SACD HYBRID)
\2700 →\2490 |
ウォルトンとヒンデミットの協奏曲を録音!
ウォルトン:
(1)チェロ協奏曲(1955-56)
(2)パッサカリア〜チェロ独奏のための(1979-80)
ヒンデミット:
(3)チェロ協奏曲(1940)
(4)無伴奏チェロ・ソナタOp.25-3(1922-23) |
クリスチャン・ポルテラ(チェロ)
(1)(3)フランク・シップウェイ(指揮)
サン・パウロ交響楽団 |
トリオ・ツィンマーマンのチェリスト、ポルテラ、ピアティゴルスキーに捧げられたウォルトンとヒンデミットの協奏曲を録音!
録音:(1)(3)2013 年7 月/サラ・サン・パウロ、(2)(4)2013
年8 月/ストックホルム音楽アカデミー(スウェーデン)/DDD、5.0
Surround Sound、69’44”
SACD ハイブリッド盤。トリオ・ツィンマーマンのチェリストとして近年目覚ましい活躍のクリスチャン・ポルテラ。BIS
レーベルでの前作、バーバーのチェロ協奏曲(BIS
SA 1827)では圧倒的な技術と豊かな表現力で作品の魅力を再発見させてくれました。期待の新録音はウォルトンとヒンデミットです。
ウォルトンとヒンデミットは親交が深く、1929
年10 月にヒンデミットがウォルトンのヴィオラ協奏曲の世界初演を行って以来良好な友人関係が続き、音楽家としてお互いに尊敬し合っていました。ここに収められたチェロ協奏曲はともにピアティゴルスキーに捧げられました。ウォルトンのチェロ協奏曲は、シャルル・ミュンシュ指揮、ボストン交響楽団の定期で行われ、その後もピアティゴルスキーによって知名度を高めた作品です。一方、ヒンデミットのチェロ協奏曲(1940)は大戦を避けてアメリカに移住した年の作品で、初演は翌1941
年2 月にセルゲイ・クーセヴィツキーの指揮で行われました。これら20
世紀を代表するチェロ協奏曲をポルテラの安定した技術と抜群の表現でお楽しみいただけます。
このアルバムには両者の無伴奏チェロ作品も収録されております。ヒンデミットのソナタはバロック時代の形式に現代音楽の響きを融和させた作品です。一方、瞑想的なウォルトンのパッサカリアは、晩年の作品の一つです。 |
| |

BIS SA 2117
(SACD HYBRID)
\2700 →\2490 |
ジョナサン・プロウライト、ブラームスの第2弾登場!
ブラームス:
(1)ピアノ・ソナタ第2番 嬰ヘ短調 Op.2
(2)創作主題による変奏曲 Op.21-1
(3)3つの間奏曲 Op.117
(4)スケルツォ 変ホ短調 Op.4 |
ジョナサン・プロウライト
(ピアノ/ Steinway D) |
イギリスの名手ジョナサン・プロウライト、ブラームスの第2弾登場!
録音:2014 年1 月/ポットン・ホール(サクスンダム)/DDD、5.0
Surround Sound、76’24”
SACD ハイブリッド盤。「優しさと力強さを兼ね備えたピアニスト」と称されるイギリスの名手、ジョナサン・プロウライト。近年は、イギリスのレーベルより珍しい編曲モノを積極的にレコーディングしておりますが、BIS
レーベルからはブラームスのピアノ独奏曲をリリースしております。プロウライトがブラームスというと意外な感じもしますが、30
歳の頃にブラームスのアルバムをリリースし、またリサイタルでも定期的にとりあげていることからブラームスは重要なレパートリーであることがわかります。第2
弾となる当アルバムにはピアノ・ソナタ第2 番、創作主題による変奏曲、3
つの間奏曲、そしてスケルツォが収録されました。1959
年生まれのプロウライトは今日稀少になりつつあるこの渋く味わい深い独特な芸風を受け継ぐ名手として貴重な存在と言え、50
代中ごろとなった今、最も充実した演奏を聴かせてくれます。とりわけブラームスの晩年の傑作3
つの間奏曲Op.117 では、プロウライトの渋みと味わいを堪能できます。好評の第1
弾(ブラームス:ピアノ・ソナタ第3 番、ヘンデルの主題による変奏曲
(BIS SA 2047))と合わせてお楽しみ下さい。 |
| |

BIS SA 2108
(SACD HYBRID)
\2700 |
トリオ・タンゴフォリア
ピアソラ:
(1)「ブエノス・アイレスの四季」 (2)「天使のミロンガ」
(3)「リベルタンゴ」(4)「デカリシモ」/
(5)「忘却」 (6)「さよなら、父さん」
(7)ファン・カルロス・コビアン:「私の隠れ家」
アニバル・トロイロ:(8)「最後の酔い」 (9)「スーロ」
(10)ルシオ・デマーレ:「マレーナ」
(11)ガルデル:「帰郷」
(12)クリスチャン・リンドベルイ:「冬至祭」
(編曲:トリオ・タンゴフォリア)
|
トリオ・タンゴフォリア
【クリスチャン・リンドベルイ(トロンボーン)、
イェンス・リンドベルイ(バンドネオン)、
ローランド・ペンティネン(ピアノ)】 |
リンドベルイ率いるトリオ・タンゴフォリアによるバンドネオンの最高傑作集!
録音:2013 年12 月/ストックホルム音楽アカデミー/DDD、5.0
Surround Sound、72’26”
SACD ハイブリッド盤。BIS レーベルを代表するクリスチャン・リンドルイが、バンドネンオンのイェンス・リンドベルイそしてピアノのローランド・ペンティネンと組んだ“トリオ・タンゴフォリア”
で録音!収録内容はその名の通りのタンゴ尽くしで、バンドネオンの神、ピアソラの「リベルタンゴ」、「ブエノス・アイレスの四季」「忘却」をはじめ、ガルデルの「帰郷」、コビアンの「私の隠れ家」など充実の選曲です。またリンドベルイ作の「冬至祭」はピアソラへのオマージュで、このトリオでの演奏のために書かれた力作です。熱い熱いタンゴの世界をご堪能ください!なお、ここに収録された作品はトリオ・タンゴフォリアによって編曲されております。 |
| |


BIS SA 1837
(SACD HYBRID)
\2700 →\2490 |
ラン・シュイによるきらめくドビュッシー
ドビュッシー:
(1)管弦楽のための映像(映像第3集)
(2)牧神の午後への前奏曲
(3)海-3つの交響的スケッチ |
ラン・シュイ(指揮)
シンガポール交響楽団 |
録音:(3)2004 年8 月、(1)2009 年7 月、(2)2013
年7 月/エスパラネード・ホール(シンガポール)/DDD、5.0
Surround Sound、76’48”
SACD ハイブリッド盤。今やBIS レーベルを代表する演奏者となったラン・シュイ(水藍)とシンガポール交響楽団の最新アルバムはドビュッシーの管弦楽曲集です。2004
年にレコーディングされた「海」は既発アルバムに収録されておりますが、2009
年録音の「映像」と2013 年録音「牧神の午後への前奏曲」は初出音源で、ともにラン・シュイの明るくきらめくようなオーケストレーションはドビュッシーの作品にもマッチしており好印象を受けます。
シンガポールを代表する国立オーケストラである当団は、1997
年、アメリカでの活動にも実績があった中国人指揮者、ラン・シュイを音楽監督に迎え、世界的に活躍するオーケストラに成長しました。レコーディングにも積極的で、チェレプニンの交響曲全集の世界初録音は特に高い評価を得ました。今後も活躍にも注目です。 |
| |
|
|
近年再評価されているレイフスの室内楽的作品集
ヨウン・レイフス(1899-1968):
(1)スケルツォ協奏曲 Op.58(1964)
(2)五重奏曲 Op.50(1960)
(3)「田園」の主題による変奏曲 Op.8(1920-30、1937)
(4)エレジー Op.35(1947) |
マルシャル・ナルドー(フルート&ピッコロ)
エイナル・ヨウハンネソン(クラリネット)
ルーナル.H.ヴィルベルグソン(バスーン)
インガ・ロウス・インゴウルスドウッティル(チェロ)
ソウルン・グヴズムンスドウッティル(メゾ・ソプラノ)
シーグルレイグ・エズヴァルスドウッティル(ヴァイオリン)
ルート・インゴウルスドウッティル(ヴァイオリン)
ソウルン・オウスク・マーリノウスドウッティル(ヴィオラ)
ベルンハルズル・ヴィルキンソン(指揮)
レイキャヴィーク室内管弦楽団、男性合唱団 |
録音:2002 年5 月、2004 年11 月、2005 年5
月/ヴィージスターザ教会、ハブナルフィヨルド、ラングホルト教会、レイキャヴィーク(アイスランド)/DDD、55’18”
BIS レーベルが力を入れているアイスランドの作曲家ヨウン・レイフスの最新盤はSmekkleysa
レーベルからのライセンス盤で、室内楽作品を中心にレイフスの中期、後期の作品が収録されました。レイフスの音楽の特徴である独特な楽器選択、強烈な音響、そして母国の伝統音楽に基づく不思議な世界がこれら室内楽作品にも表れております。
1920 年から作曲にとりかかった「田園」の主題による変奏曲
はベートーヴェンの交響曲第6 番「田園」をモティーフにしたレイフス、ライプツィヒ時代の作品です。また「エレジー」は1947
年に娘を水難事故で亡くした悲しみから作曲された作品でメゾ・ソプラノとヴァイオリンとのかけあいが非情な悲しみを表現した作品です。アイスランドの民俗音楽を取込んで作曲を行ったはじめての作曲家として言われているレイフスの独自の世界をお楽しみください。なお、当盤はBIS
レーベルによりリマスタリングされております。 |
 CLAVES CLAVES
|
|
|
バドゥラ=スコダの秘蔵っ子キオヴェッタによるハイドン
ハイドン:
(1)アンダンテと変奏曲 ヘ短調 Hob.XVII:6
(2)ピアノ・ソナタ 変イ長調 Hob.XVI:46
(3)ピアノ・ソナタ ハ短調 Hob.XVI:20
(4)ピアノ・ソナタ ホ短調 Hob.XVI:34
(5)変奏曲 変ホ長調 Hob.XVII:3 |
ファブリツィオ・キオヴェッタ
(ピアノ/ Steinway & Sons,D) |
録音:2013 年2 月9 & 10 日/サラ・マーラー(イタリア)/DDD、68’56”
1976 年ジュネーヴ生まれのファブリツィオ・キオヴェッタの新譜はハイドンです。キオヴェッタはパウル・バドゥラ=スコダ、ジョン・ペリー、ドミニク・ヴェーバーなど、世界の名だたる名教師・ピアニストに師事し、ソロはもちろんのこと室内楽、声楽の伴奏、そして即興演奏など様々な演奏形態の作品を積極的に学んできました。師のバドゥラ=スコダは「繊細にして熱い感情が伝わる演奏」と激賞し、演奏者として尊敬の念をもっています。Claves
レーベル初登場となったシューベルト(50 1213)では一音一音の粒立ちの良さと美しく光り輝くタッチ、そして絶妙なペダリングと、実に見事なまでの演奏を聴かせてくれました。新録音となるハイドンでも、キオヴェッタならではの繊細なタッチを披露しております。 |
 CONTINUO CLASSICS CONTINUO CLASSICS
|
|
|
1914 年生まれの女流ピアニスト
コルトーに師事をしたコレット・マーズによるドビュッシー
ドビュッシー:
(1)月の光
(2)版画
(3)子供の領分
(4)レントより遅く |
コレット・マーズ(ピアノ) |
録音:2003 年、パリ/DDD、日本語訳付
1914 年生まれの女流ピアニスト、コレット・マーズ。1935
年から40 年までパリ・エコール・ノルマル音楽院で、アルフレッド・コルトーに師事したマーズは、コルトーの演奏法を実践する最後の愛弟子です。マーズの演奏は珠を転がすような美しいタッチで、コルトーを思わせる独創的かつ感受性とイメージに富んだアプローチが特徴で、それぞれの声部に与えるべき色合いや響きを探求し、空気感や雰囲気抜群の演奏を聴かせてくれます。
2003 年に録音されたこのアルバムの4 曲はどれもマーズが子供時代に魅了され好んで演奏してきたもので、これら作品について「官能と感傷をひとつに混ぜ合わせ、情緒を超越して黙想に向かう」と語っております。

|
LORELEY PRODUCTION
|
|
|
チェンバロにリュートの弦を張った楽器ラウテンヴェルクで聴くバッハ
オリヴィエ・ボーモン
J.S.バッハ:
・プレリュード ハ短調 BWV 999
・リュート組曲(パルティータ) ハ短調
BWV 997
・リュート組曲 ホ短調 BWV 996
・プレリュード、フーガとアレグロ 変ホ長調
BWV 998
・半音階的幻想曲とフーガ ニ短調 BWV
903
・ポロネーズ(管弦楽組曲第2番 BWV 1067「ポロネーズ」より)(J.C.バッハ編) |
オリヴィエ・ボーモン
(ラウテンヴェルク/ Willard Martin
(1991, ペンシルヴェニア)) |
ラウテンヴェルクとは、外見はチェンバロですが、通常の金属の弦ではなく、リュートに用いられるガット弦が張られた楽器のこと。リュートのようなやわらかな音色が特徴です。18
世紀中頃のヨーロッパ、とくにドイツでは、このガット弦を張ったチェンバロは比較的多く存在していたようで、バッハもこの楽器の音色を好んでいたといいます。BWV
996 の筆写譜には、「ラウテンヴェルクのために」という記述もあります。「半音階的幻想曲とフーガ」をリュートのような音色で聴けるのも興味津々。フランスの中堅実力派、ボーモンの独白のような演奏に静かに耳を傾けたくなる1
枚です。

|
| |
|
|
フレデリック・ラロック率いる四季
ヴィヴァルディ:四季
クライスラー:プニャーニの様式による前奏曲とアレグロ
パッヘルベル:カノン |
フレデリック・ラロック(Vn ソロ、指揮)
ドリアーヌ・ギャーブル(Vn)
セドリック・ラロック(Vn)
ダニエル・ヴァグナー(Vla)
ジャン・フェリ(Vc)
アクセル・サル(Cb)
ジル・ハーレ(Cem) |
パリ・オペラ座で活躍のヴァイオリン奏者フレデリック・ラロック率いる四季
録音:2013 年5 月4,6 日(ライヴ)/サント・シャペル(パリ)
パリ・オペラ座の特別ソロヴァイオリン奏者、フレデリック・ラロック率いるアンサンブルによる、四季。ラロックは、パリ・オペラ座でのバレエ公演でヴァイオリン、指揮で活躍しています。美しいステンドグラスで有名な、世界遺産にも登録されているパリのサント・シャペルでのライヴ録音です。

|
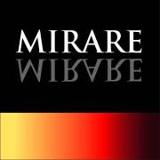 MIRARE MIRARE
|
|
|
ブラームス:クラリネットのための作品集
クラリネット三重奏曲イ短調作品114
クラリネット・ソナタ ヘ短調作品120-1
クラリネット・ソナタ 変ロ長調作品120-2 |
ラファエル・セヴェール(クラリネット)
アダム・ラルーム(ピアノ)
ヴィクトル・ジュリアン= ラファリエール(チェロ) |
20歳の若手クラリネット奏者ラファエル・セヴェール、ブラームスの晩年の珠玉のクラリネットの名作に挑む!
録音:2014 年1 月6-8 日パリ、サル・ガヴォー/71’00
名作クラリネット五重奏をはじめとした晩年のブラームスのクラリネット作品の陰には当時の名手ミュールフェルトの存在があったことは周知のこと。作曲家として引退を決意していたブラームスに再び創作への意欲を駆り立てたのがマイニンゲン宮廷管弦楽団のクラリネット奏者リヒャルト・ミュールフェルトでした。その後ブラームスは立て続けにクラリネット三重奏曲、クラリネット五重奏曲を書き上げ、その後2
つのクラリネット・ソナタを作曲しています。中でもクラリネット三重奏曲は、ブラームス自身のお気に入りの作品。冒頭から哀愁漂わせる旋律をチェロ、そしてクラリネットと奏でられ、静かに作品の世界にいざないます。2
つのクラリネット・ソナタはブラームスが残した最後の室内楽作品。クラリネットの特性を生かし、晩年のブラームスの円熟した技法で生み出された見事な表現力を発揮させた曲。また、ここに収録されている3
作品はヴィオラのレパートリーとしても親しまれています。
クラリネットを演奏するのは、1994 年生まれのラファエル・セヴェール。2010
年にフランスのヴィクトワール・ド・ラ・ミュージックに選出された注目の若手。14
歳でパリ国立音楽院に入学。これまでジェラール・コセ、アンリ・ドマルケット、エベーヌ四重奏団、チェコ・フィル、シンフォニア・ヴァルソヴィアなどと共演しています。ふくよかで美しい音を持ち、豊かな音楽性、安定したテクニックで将来が楽しみな奏者です。ピアノを担当するのは、2009
年クララ・ハスキル国際ピアノ・コンクールの優勝者アダム・ラルーム。彼の寄り添うようなピアノも光っています。チェロは、アダム・ラルームと梁美沙と共にトリオ・レゼスプリで活動しているヴィクトル・ジュリアン=
ラファリエールが務めています。 |
| |
|
|
ラ・ロック・ダンテロン国際ピアノ・フェスティヴァル2014
公式CD
〜プラタナスの木の下に佇むピアノ
1.ソレル:ソナタ ホ短調第129番R.451/ルイ・フェルナンド・ペレス
2.J.S. バッハ:前奏曲 変ロ短調BWV853/シュ・シャオメイ
3.クープラン:神秘のバリケード/イド・バル=シャイ
4.モーツァルト:ピアノ・ソナタ ハ短調K.457/アンヌ・ケフェレック
5. ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第17番ニ短調作品31-2「テンペスト」〜第3楽章/アブデル・ラーマン・エル=バシャ
6.シューマン:予言の鳥/ マタン・ポラト
7.リスト:巡礼の年第1年〜泉のほとりで/
ニコラ・アンゲリッシュ
8.シューマン:ピアノ・ソナタ第1番嬰ヘ短調作品11/アダム・ラルーム
9.ショパン:前奏曲 変ニ長調「雨だれ」作品28-15/フィリップ・ジュジアーノ
10.ラフマニノフ:前奏曲嬰ト短調作品32-12/ボリス・ベレゾフスキー
11.チャイコフスキー:中程度の12 の小品 作品40-8/ボリス・ベレゾフスキー
12.ラフマニノフ:ひなぎく 作品40-8/クレール=マリ・ルゲ
13.ビゼー:子供の遊び作品22「小さい旦那様、小さい奥様」/クレール・デゼール&エマニュエル・シュトロッセ
14.ドビュッシー:月の光/アンヌ・ケフェレック
15.ラヴェル:夜のガスパール〜オンディーヌ/ジャン=フレデリック・ヌーブルジェ
16.ヒナステラ:優雅な乙女の踊り/シャニ・デュリカ
17.ガーシュイン:3つの前奏曲/ジャン=フランソワ・エッセール
18.アーン:冬/アンヌ・ケフェレック |
MIRAREを代表するピアニストが集結したラ・ロック・ダンテロン公式アルバム
76’00
南仏プロヴァンス地方のラ・ロック・ダンテロンで、1981
年より開催されている国際ピアノ・フェスティヴァル。地元の村長ポール・オノラティニと、ラ・フォル・ジュルネ音楽祭のプロデューサーとしても知られるルネ・マルタンによって創設されました。2014
年に34 回目を迎え、世界中から集まった音楽家たちが、プラタナスの木が茂る野外ホールでコンサートを行います。このアルバムは、フェスティヴァルの常連のMIRARE
アーティストによるコンピレーションCDです。 |
 WERGO WERGO
|
|
|
原田敬子(b.1968):作品集
F-fragments(アコーディオンとピアノのための)
1. Twin Leaves/2. Speedy/3. Noise/4.
Fall Time Blues/
5. Pray for 18537? +2654?/6. Vertical/7.
Points/
8. Alert/9. BONE/10. Try to Fly/11.
(no title)/
Book I(アコーディオンのための)
12. Detour/13. Aprinkled Efforts/14.Anticipation/
15.Hen-pu/
Nach Bach(ピアノ・ソロのための)
Nach Bach(ピアノ・ソロのための)
16. XV: 廻由美子へのオマージュ/17. VI:
ル・コルビジェへのオマージュ/
18. IX: 間宮芳生へのオマージュ/19. X:
美加理(ミカリ)へのオマージュ/
20. XVIII: 三善晃へのオマージュ/
21. XXI: ブライアン・ファーニホウへのオマージュ/
22. XII: ステファン・フッソングへのオマージュ〕 |
廻由美子(ピアノ)
シュテファン・フッソング(アコーディオン) |
廻、フッソング2 人の名手が奏でる原田敬子作品集
録音:2013 年1 月10-12 日/相模湖ホール(録音:桜井卓)
日本人作曲家、原田敬子の作品集。福島が強く意識された作品が並びます。演奏するのはアコーディオンの世界的名手、フッソングに、ピアニストの廻。原田作品ならではの時間軸や緊迫感を感じさせる世界を見事に響かせています。
F.フラグメンツは、2012 年11 月3 日に世界初演された作品。原田自身「直接の面識がない人々、行ったことのない土地、そこで流れた時間を、覚醒して意識的に、この11
の断片的楽章に記憶しようと試みた」と述べていますが、福島をめぐる様々な事象や人物が刻み込まれた音を、ピアノとアコーディオンが極度の集中の中響き合わせていきます。
BOOK I(アコーディオンのための)は2010
年8 月28 日、サントリーサマーフェスティヴァルの一環の、芥川作曲賞創設20
周年記念ガラ・コンサートで委嘱世界初演されたもの。アコーディオンにはどちらかというと難しく、上手く効果が出ないと言われている表現、すなわち、囁くような音色で素早くレガートで動き回ること、垂直的で鋭い音色による多重音の速い複雑な音の連なり、気の遠くなるほどの長音を弱音で、極限の蛇腹技術でコントロールすること、そして複雑な手の動きと同時に複雑なリズムで「口」(無声音)も使うなど、名手フッソングをしても「不可能」と言わしめた非常に難しい作品。原田はこのCD
のフッソングの演奏には意にそぐわないところはない、と述べています。
Nach Bach は、田崎悦子ピアノリサイタルシリーズ〜
NACH BACH 〜のために書かれたもので、2004
年の9,11 月に初演されました。田崎が2004 年に平均律でリサイタルのプログラムを構想していた折、「平均律」に関係する作品を作ってほしい、と原田にリクエストしました。平均律の各曲のプレリュードかフーガのいずれかを任意で選び、各主題の音組織を全く自由に並び替えることで、各曲に対応する全24
曲を作曲。それぞれは、主に芸術関係者へのオマージュとなっています。本CD
には、原田の3 名の恩師、美加理(俳優)、ル・コルビジェ(建築)、そして廻とフッソングへのオマージュの7
作品が収録されています。
原田敬子は、幼少のころからピアノで即興演奏をするなどして作曲を開始。桐朋学園大学で作曲を川井學、三善晃、ブライアン・ファーニホウに、ピアノを間宮芳生、室内楽(クルターク作品)をジョルジ・クルタークに師事しました。大学では作曲を専攻すると同時に、ピアノ・室内楽・指揮法を学び、1993
年に研究科課程を修了しています。’ 90 年代半ばから「演奏家の、実際の演奏における内的状況を作曲する」というコンセプトで、演奏家の身体と脳の可能性を拡げることで実現される、独自のテンションや字管構造を特色とした作品を多く書いています。これまでに第62
回日本音楽コンクール第1 位(室内楽)をはじめ、芥川作曲賞(2001、管弦楽)、尾高賞(2008、管弦楽)ほか受賞多数。現在、東京音楽大学(芸術作曲)准教授。 |
| |
|
|
エンヨット・シュナイダー(b.1950):METAMORPHOSEN
1. 時の淵で〜モーツァルトのレクイエム K.626についての考察
2. 「私は、私自身にとっても他人にとっても、永遠に謎でありつづけたい」
(ルートヴィヒ2 世の墓碑)
〜イングリッシュ・ホルン、弦とファゴットのための協奏曲
3. 神はわがやぐら(オーケストラのための交響詩)
4. フロレスタンとオイゼビウス
(オーケストラのためのロベルト・シューマン計画) |
シンシャオ・リ(指揮)
クリストフ・ハルトマン
(イングリッシュ・ホルン/ 2)
ヨハンエス・シュトラッスル
(イングリッシュ・ホルン/ 1)
ゴットフリート・ポコーニー(ファゴット/ 2)
ニーダーエステライヒ・
トンキュンストラー管弦楽団 |
ドイツの巨匠、エンヨット・シュナイダー現代風に増幅・変容されたモーツァルト、メンデルスゾーン、シューマン
録音:2013 年10 月
エンヨット・シュナイダーは、1950 年ドイツ生まれの作曲家。哲学の博士号も取得しています。8
夜にわたるオペラ「Das Salome-Prinzip,Bahnwaerter
Thiel, Fuerst Pueckler」をはじめ、非常に多作。宗教作品も彼の作品の中で重要な地位を占め、オラトリオ、オルガン協奏曲などを作曲しています。音楽書も出版しています。また、現代ドイツにおける映画音楽の第1
人者として活躍。これまでに手掛けた映画作品は600
ほど、1993年のドイツ映画「スターリングラード」などがあります。このCD「メタモルフォーゼン」は今後WERGO
からリリースされる10 のエンヨット・シュナイダー・シリーズの第1
弾となります。
シュナイダー作品の多くは、音楽史上よく知られた作品や、作曲家の作曲スタイルの傾向を引用し、それらを「変容」させることによって、伝統に対する新しい創造的な答えを示しています。文化的に積み重ねられたものとの対話であり、現存する形式やモデルに対しての主観的な注釈です。このCD
の4つの作品も、歴史上のモデルに関連しています。1
曲目はモーツァルトのレクイエム。有名な旋律の断片がいくつも聴かれる中、レクイエムの大きな主題である「死」を思わせる作品。ルートヴィヒ2
世の没後125 年に作曲された第2 曲目は、ルートヴィヒ2
世と非常に深い関わりのあるワーグナー作品のパロディ的作品。
3 曲目の「神はわがやぐら」はメンデルスゾーンの交響曲「宗教改革」にも登場する、ルターが書いたコラール旋律ですが、それを増幅させることにより、非常に力強い作品に仕上がっています。最後の作品はシューマンの『ダヴィッド同盟』でもおなじみの、物静かなオイゼビウスと活発なフロレスタンからの。2
人のキャラクターが、シューマン作品の様々な断片を取り入れながら描かれていきます。 |
| |
|
|
THINKING OF…
セバスティアン・グラムス:
A Catena/ Macchina Basso/ Fioritura/
Spirale/
Un Vento Silenzioso/ Moto Perpetuo/ PezziDifettosi/
Sul Viaggio/ In Altre Parole/ Soffermiamoci
マーク・ドレッサー:Sostevoli Su/
ジョン・エックハルト:La Coda del Nebbio/
セバスティアン・グラムス:Voyager/
バリー・ガイ:Outside- Inside/
クリスティーヌ・フック:Rock! Nella Nebbia/
ジョエル・レアンドル:For Stefano/
ディーター・マンデルシャイト:Subito Sera/
バール・フィリップス:Tocarme/
ダニエレ・ロッカート:Breaking Glasses/
齋藤徹:Casino/ ハコン・テリン:h-Moll
ボーナス・トラック/スコダニッビオ&グラムス:Virtu |
集結したコントラバス奏者
マーク・ドレッサー(アヴァン・ギャルド・ジャズ)
ジョン・エックハルト
(クセナキスの作品の演奏を中心に活動を展開)
セバスティアン・グラムス(即興、ジャズ、現代音楽)
バリー・ガイ(即興ジャズ、オーケストラ、室内楽等)
クリスティーヌ・フック(オーケストラなど)
ジョエル・レアンドル(即興、作曲)
ディーター・マンデルシャイト(ジャズ)
バール・フィリップス(ベース・インプロヴァイザー)
ダニエレ・ロッカート(ソリスト、作曲家)
齋藤徹(コントラバス演奏、作曲)
ハコン・テリン(コントラバス演奏、作曲) |
天才コントラバス奏者、ステファノ・スコダニッビオに捧げる1枚
このアルバムは、2012 年に亡くなった天才コントラバス奏者、ステファノ・スコダニッビオへのオマージュ。世界のトップレベルのコントラバス奏者が集結しています。セバスティアン・グラムスは、プロデューサー、作曲家、そして奏者の一人としてプロジェクトに参加。自身の作品および、スコダニッビオの作品を増幅させたような作品、また、このプロジェクトのために集まった奏者たちによる作品が並ぶ、コントラバスの祭典のような1枚となっています。 |

8/13(水)紹介新譜
マイナー・レーベル新譜
 HMF HMF
|
|
|
アマンディーヌ・ベイエ(ヴァイオリン)
F.クープラン(1668-1733):讃歌集
トリオ・ソナタ「壮大なもの」(1690年頃)
リュリ讃(1725)
コレッリ讃(1724)
4声のソナタ「スルタン妃」(1695 年頃) |
アマンディーヌ・ベイエ(ヴァイオリン)
リ・インコーニティ |
魅惑のヴァイオリニスト、アマンディーヌ・ベイエ新譜はクープラン!
録音:2014 年1 月4-7 日/グラディニャン、四季劇場(ジロンド)
フランス古楽界の新世代を代表するバロック・ヴァイオリン奏者、アマンディーヌ・ベイエ。2014
年11 月にはアンサンブル・リ・インコーニティを率いての来日が予定されています。
この度、久々にハルモニアムンディからの登場となる当盤のプログラムは、F.
クープランの「リュリ讃」と「コレッリ讃」というなんとも嬉しい組み合わせ。ベイエの魅力である喜びに溢れたようなリズム、愛に満ちた明るい音色があますところなくとらえられています。
CD のプログラムは、「壮大なもの」で幕を開けます。「少しクセのある、色鮮やかな不協和音に満ちたハーモニーのキラキラとしたつむじ風にたちまち耳を奪われる」とベイエ自身述べている作品を、非常にチャーミングに響かせています。
F. クープランの「コレッリ讃」と「リュリ讃」は、両作品とも各楽章に表題が付けられており、「コレッリ讃」では音楽の神が住まうパルナッソス山にコレッリが導かれる様子が描かれ、「リュリ讃」では、コレッリに続いてパルナッソス山へ登ったリュリが、そこで出会ったコレッリと共に演奏を行う、という物語になっています。フランスでは、「トンボー」というジャンルで、先人の肖像画的な音楽を作るという伝統がありましたが、このクープランの「リュリ讃」「コレッリ讃」は、それぞれの作曲家のスタイルに厳密に従っているわけではなく、また、その規模などから、音楽史上でも特殊な作品として輝きを放っています。ベイエとアンサンブルの面々が、活き活きとしたリズムでひとつひとつのハーモニーまでも逃さず味わいつくすように演奏しています。
最後に収録されているスルタン妃は比較的初期の作品ですが、繊細なテクスチュア、柔軟な舞曲のリズム、抒情性、モティーフのキャラクターづけの巧さなどが光る秀作です。
ベイエ&アンサンブル・リ・インコーニティ2014
年来日日程
11月24日( 月・祝) 15:00 姫路 パルナソスホール【Aプロ】8/21(木)
発売予定
11月25日(火) 19:00 東京 津田ホール【Bプロ】
発売中
11月26日(水) 19:00 東京 王子ホール【Aプロ】
完売
【Aプロ】“季節の劇場~ヴィヴァルディの四季とその他の協奏曲”
ヴィヴァルディ: 歌劇「オリンピアーデ」より
シンフォニア ハ長調 RV725、チェロ協奏曲 イ短調
RV420、ヴァイオリンと鍵盤楽器のための協奏曲
ハ長調 RV808、「四季」
【Bプロ】“A.ヴィヴァルディ & J.S.
バッハ~様々な楽器による魅惑の協奏曲集”
ヴィヴァルディ: シンフォニアハ長調 RV112、チェロ協奏曲ニ長調
RV403ほか
J.S. バッハ: ヴァイオリン協奏曲 イ短調
BWV1041、チェンバロ協奏曲 ニ短調 BWV1052

|
 NAIVE NAIVE
|
|
|
ドメニコ・スカルラッティ(1685-1757):ソナタ集
(1)ニ長調 K96 (2)ホ長調 K.381 (3)ニ長調
K.119
(4)ロ短調 K.197 (5)ホ長調 K.135 (6)イ長調
K.322
(7)イ短調 K.109 (8)ニ短調 K.141 (9)ニ長調
K.492
(10)ト長調 K.146 (11)ハ短調 K.11 (12)ヘ長調
K.17
(13)ロ短調 K.27 (14)ロ短調 K.87 (15)ホ長調
K.380
(16)イ長調 K.209 (17)イ長調 K.101 (18)ニ長調
K.29 |
イーゴリ・カメンツ(P/スタインウェイ) |
チェリビダッケの教えを受けた超人ピアニスト、イーゴリ・カメンツ、スカルラッティを弾く!
録音:2013 年10 月
超人ピアニスト、カメンツがナイーブより登場します。カメンツのプロフィールは、映画にできるのではと言う人もあるくらいに超人的なもの。1968
年、ロシア東部のアムール川流域、中国との国境が近い地域に生まれました。1975
年にはノヴォシビルスク・フィルハーモニーを指揮。10
歳に満たない1977 年、ボリショイ・オーケストラを指揮して演奏会で指揮者デビューを果たします。伝説のピアニスト、ヴィタリー・マルグリス、そしてチェリビダッケに長い間師事しました。1978
年にドイツに移住してからはピアニストとして演奏活動を展開。国際的な18
のコンクールで優勝、クープランからケージまで広いレパートリーを持ちます。2014
年、モーストリー・モーツァルト・フェスティヴァルでニューヨークでリサイタル・デビューするなど、世界が注目する存在となっています。これまでにもリスト作品などのCD
をリリースしていますが、naive からは初登場となります。
カメンツは、ドメニコ・スカルラッティが遺した555
ほどもあるソナタから、18 曲を選択し、調性や曲のキャラクター、全体の流れを考えて配曲しています。完璧無比な技巧とカラリとした音色で、ユーモアや哀愁など様々な表情に富むスカルラッティの作品を一気呵成に聴かせます。
|
 REFERENCE RECORDINGS REFERENCE RECORDINGS
|
|
|
アンドレス・セゴビア・アーカイヴ〜フランスの作曲家たちの作品集
レイモン・プティ:シシリエンヌ
アンリ・マルテッリ:4 つの小品
ピエール・ド・ブレヴィル:ギターのための幻想曲
アンリ・コレ:ギターのための詩曲「ブリビエスカ」Op.67
レイモン・ムラエルト:組曲
ラウル・ラパラ:
クアドロス(スペインの風景)〜カスティーリャの村/アラゴンにて/
魔術
ピエール=オクターヴ・フェルー:スピリチュアル
イダ・プレスティ:セゴビア |
イダ・プレスティ:セゴビア
ロベルト・モロン・ペレス( ギター) |
セゴビア・アーカイヴ第2 弾!
アンジェロ・ジラルディーノ氏が校訂し、イタリアのベルベン社から出版されている「アンドレス・セゴビア・アーカイヴ」。セゴビアに献呈された作品を、作曲家の自筆譜を添えて未刊(一部既刊)の作品を出版したシリーズ第2
弾。本アルバムは、この楽譜の出版の際にも協力したスペイン出身のギタリスト、ロベルト・モロン・ペレスが、この価値ある出版物に沿った内容で収録したシリーズです。
作曲家、評論家として活躍していたレイモン・プティの美しい「シシリエンヌ」。フランスの放送局に勤務しながら作曲活動を続けていたアンリ・マルテッリの「4
つの小品」。フランク最後の弟子と言われるピエール・ド・ブレヴィルの「幻想曲」。<フランス6
人組>の名付け親としてもしられているアンリ・コレ。スペインへ留学しファリャらに学びグラナドス、アルベニスとも親交があったとされています。このギターのための詩曲「ブリビエスカ」は、ピアノ曲からのギター編曲で、スペイン風の魅力的な作品です。
ベルギーの作曲家レイモン・ムラエルトの組曲は、セゴビアには演奏されていませんが、セゴビア自身による運指が書かれた楽譜が見つかっています。パリ音楽院でフォーレやマスネに学んだラウル・ラパラの「スペインの風景」。ラパラはカンタータ「オデュッセウス」でローマ大賞を受賞。スペインの民謡などに影響を受け、スペインの語法を用いた歌劇などを多く残しています。
ピエール=オクターヴ・フェルーは、同時代の作曲家を普及させるための音楽集団「ル・トリトン」を結成し、知られざる音楽家たちの作品を紹介していました。この「スピリチュアル」は、当時の最先端の音楽を模索した革新的な音楽です。そして伝説のプレスティ=ラゴヤ・ギター二重奏団のイダ・プレスティの「セゴビア」。ギタリストならではの、ギターの特性を生かした粋な作品です。 |
| |
|
|
オースティン・ウィントリー
オフィシャル・サウンド・トラック「バナー・サーガ」
1. We Will Not Be Forgotten/2. How did
it come to This?/
3. No Tree Grows to the Sky/4.Only the
Sun has Stopped/
5.Cut with a Keen-Edged Sword/6. Huddled
in the Shadows/
7. There is no Bad Weather/8. Teach
us Luck/
9. No Life Goes Forever Unbroken/10.
Little Did They Sleep/
11. An Unblinking Eye/12. Thunder before
Lightning/
13. Embers in the Wind/14. A Long Walk
Stills Our Hearts/
15. The Egg Cracks/16. Three Days to
Cross/
17. Walls no Man has Seen/18. Strewn
Across a Bridge/
19. Weary the Weight of the Sun/20.
An Uncertain Path/
21. Into Dust/22. On the Hides of Wild
Beasts/
23. From the Table to the Axe/24. A
Sunken City/
25. Our Heels Bleed from the Bites of
Wolves/
26. Long Past that Last Sigh/27. Of
Our Bones, The Hills/
28. We are all Guests upon the Land/29.
Onward. |
ダラス・ウィンド・シンフォニー |
オースティン・ウィントリーとキース・O・ジョンソンのグラミー・コンビが創り出す壮大なRPG
の世界
壮大なファンタジーが描かれたロール・プレイング・ゲーム「バナー・サーガ(The
Banner Saga)」のオリジナル・サウンドトラック。作曲を担当したのは、あの「Journey(
風ノ旅ビト)」で第55 回グラミー賞「Best Score
Soundtrack For Visual Media」にノミネートされ、英国映画テレビ芸術アカデミー(BAFTA)
で作曲賞を受賞したオースティン・ウィントリーが手掛けています。
そしてもちろん録音を担当するのが、同じくグラミー賞受賞エンジニアであるリファレンス・レコーディングスのキース・O・ジョンソン。演奏はアメリカ最初のウィンド・オーケストラであるダラス・ウィンド・シンフォニーが壮大なゲームの世界観を存分に表現しています。 |
<国内盤>
 INDESENS! INDESENS!
|

INDE063
(国内盤)
\2800+税 |
パリのサクソフォン 〜クラシックか、それとも...?〜
ギヨーム・コヌソン(1970〜):
①テクノ・パラード(2s-sx, p)
グレアム・フィットキン(1963〜):
②ハード・フェアリー(s-sx, 録音トラック)
マウリシオ・カーゲル(1931〜2008):
③リード〜『Rrrrr…五つの小品』より(a-sx)
長生 淳(1964〜):
④パガニーニ・ロスト(2a-sx, p)
フィリップ・ガイス(1961〜):
⑤サックス・ヒーロー(a-sx)
ジョゼフ・ホロヴィッツ(1926〜):
⑥コン・ブリオ〜『ソナチネ』より(s-sx,
p)
クロード・ボリング(1930〜):
⑦よどみなく〜『ジャズ組曲』より(s-sx,
p)
ティアリー・エスケシュ(1965〜):
⑧朝闇の歌(s-sx, sx-orc)
ドィミトリ・チェスノコフ(1982〜):
⑨トッカータ〜『ソナタ』より(s-sx, p)
吉松 隆(1953〜):
⑩ラン・バード〜『ファジイバード・ソナタ』より
(a-sx, p)
ジャン・フランセ(1912〜1997):
⑪パンビッシュとメレンゲ〜
『五つのエキゾチックな舞曲』より(a-sx,
p)
クロード・ドビュッシー(1862〜1918);
⑫狂詩曲(a-sx, p)
チャーリー・パーカー(1920〜1955):
⑬マイ・リトル・スウェード・シューズ(a-sx,
p) |
ニコラ・プロスト(ソプラノ&アルト・サクソフォン)
①アンヌ・ルカプラン(s-sx2)
④ジャン=イヴ・フルモー(a-sx2)
①④⑥⑦⑨馬場みさき(p)
⑩−⑬ローラン・ワグシャル(p)
⑧エリック・オービエ指揮
パリ・サクソフォン・アンサンブル |
「管楽器の国」フランス最前線!スーパープレイヤーが奏でるソプラノ&アルトの流麗さ。
いわゆる現代音楽さえ何ら怖くない、ひたすらスタイリッシュに、センスあふれる洒脱なブロウ。
アートでもあり、そして何より「音楽」であり。
ドビュッシーに吉松 隆に...まずはご一聴を♪
フランスが世界に冠たる管楽器王国なのは今に始まったことではありませんが、こういうアルバムがひょいっと出てくるとなるとやはり「そもそも基本的なレベルが違う!」と舌を巻かずにはおれません。
そもそもこの国、どのジャンルの管楽器奏者でも世界的な名手が続々とあらわれるうえ、隣国ドイツや英国、アメリカに渡って活躍した人々も多々。フルートのランパル、ラリュー、パユ、ガロワ、リュカ、オーボエのピエルロ、ブールグ、ガテ、バソンのアラール、ファゴットでさえトレーネル...そうした活況は「アメリカの」「ジャズの」楽器としても世界で愛されているサクソフォンにおいても、まったく変わることがありません。
佐渡裕指揮コンセール・ラムルー管のサクソフォン奏者で、トゥルーズ・カピトゥール管などでも活躍するニコラ・プロストはここで、意外にもソプラノとアルトばかりを使い、ドビュッシーの傑作「狂詩曲」に始まり、フランセをへてコヌソン、エスケシュら存命中の作曲家たちにいたる、聴き手を絶対に排除しない、確実に耳になじむクラシカルな作風を忘れないフランス近代系の作曲家たちの系譜をあざやかにたどりながら、あるときはウクライナ系の作曲家チェスノコフ、あるいはアルゼンチンの名匠マウリシオ・カーゲルら注目すべき作風の異才たちの作品もさわりつつ、J.ホロヴィッツ、フィットキンなど英語圏の作曲家たちの名品、世界クラスのセンスの良さをみせる長生
淳や吉松 隆のすでに定番になりつつある名曲、そして〆には偉大なジャズのレジェンダリー、チャーリー・パーカーの素敵なメロディでアルバムを閉じる...と、実にハイセンスなフランス管楽器サウンドのひとときを演出するプログラムを提案してくれています。
ところどころ2本サックス曲があったり、無伴奏曲があったり、はたまたトランペットの巨匠エリック・オービエが振る凄腕サクソフォン・アンサンブルが登場したり…超絶技巧なパッセージをまるでこともなげに吹きこなしてしまう、そのうえでどこまで芸達者に、深みある音を「歌い」「語れる」か?! |
| |


INDE062
(国内盤)
\2800+税 |
フランス近代の傑作フルート作品集
〜ボーナストラック付・増補版〜
ガブリエル・フォーレ(1845〜1924):
①フルートとピアノのための幻想曲 作品79
クロード・ドビュッシー(1862〜1918):
②シランクス(無伴奏フルートのための)
③「牧神の午後」への前奏曲
(フルートとピアノ/ギュスターヴ・サマズイユ編)
シャルル=マリー・ヴィドール(1844〜1937):
④フルートとピアノのための組曲 作品34
フランシス・プーランク(1899〜1963):
⑤フルートとピアノのためのソナタ
フィリップ・ゴベール(1879〜1941):
⑥幻想曲 〜フルートとピアノのための
オリヴィエ・メシアン(1908〜1992):⑦黒つぐみ
アンドレ・ジョリヴェ(1905〜74):⑧リノスの歌
ジェオルジェ・エネスク(1881〜1955):
⑨フルートとピアノのためのカンタービレとプレスト* |
ヴァンサン・リュカ(fl)
エマニュエル・シュトロッセ(p)
クラウディア・バーラ(p)* |
無伴奏作品集でますます評価を高めつつあるパリ管の名手、ヴァンサン・リュカ——ピアノに稀代の俊才シュトロッセを迎えての室内楽集、無念のプレス切れから増補&新装丁で再登場!あざやかなピアニズム、玄妙かつ濃密な「管の国」最前線の妙技...
エスプリを感じる1枚です。
「管楽器の国」フランスの名門パリ管弦楽団でソロ・フルート奏者をつとめ、数々の協奏曲はもちろん、名指揮者たちが振る「『牧神の午後』
への前奏曲」の冒頭などで艶やかなソロを受け持つ俊才ヴァンサン・リュカは、おなじみIndesens!レーベルから昨今すばらしい無伴奏曲集(INDE057)をリリース、『レコード芸術』特選に輝いたのをはじめ、日本でもあらためて大好評をもって迎えられているところ。
来日経験も少なくないところ、フランス派最前線の名手ますます存在感を強めつつあります。
そんな折、残念ながらIndesens!で制作していたフランス近代作品集が、少し前にあえなくプレス切れ...これはもったいない話!と思っておりましたところ、この名盤をレーベル主宰者がいつまでも入手不可にしておくはずもなく。このたびジャケットも一新・Digipack
仕様になり(再版以降はジュエルケースになる可能性もありつつ)、さらに新たに1曲、当初収録されていなかったエネスクの充実作(エネスク作品集(INDE036)からの再録)も末尾に収録しての、より充実したヴァージョンになって戻ってきました(品番・バーコードが変更になり内容にも若干の変更があるため「新譜」としてご紹介しております)!このアルバムの素晴しいところは、それなりに録音物が出回っているようでいて、意外にフランス人の名手の演奏が見つかりにくい曲も含め、フランス近代の、巨匠たちがフルートという楽器の可能性に最も心奪われていた時代の傑作を、非常に的確に集めてくれていること——
自らフルートの巨匠だったゴベールの名曲「幻想曲」やサン=サーンス、フォーレらの同時代人ヴィドールの組曲、プーランクのソナタやメシアンの「黒つぐみ」など現代のスタンダード系、そしてきわめつけはドビュッシーの「シランクス」と、20
世紀初頭の名匠ギュスターヴ・サマズイユによってピアノ+フルート独奏(!)に編み替えられた「『牧神の午後』への前奏曲」...フランス近代音楽の新境地の幕開けを飾る象徴的なこの曲が、冒頭のあの玄妙なフルート独奏にどれほど大きく依拠した作品だったのか、この名録音を聴けばよくわかることでしょう。
解説は増補されたエネスク作品(これもかなりの充実作...オーケストレーションの達人は、たいていこのとおり管楽器の扱いに長けているものなのですね!)の部分もきちんと補い訳出。
フランスのフルート楽派というものの活躍を知るうえで、この1枚は今やまず外せない名盤といってよいと思います。
|
<映像>
 EUROARTS(映像) EUROARTS(映像)
|

20 59744
(Blu-ray)
\5000 |
「POPPEA//POPPEA」
※モンテヴェルディの傑作オペラ「ポッペアの戴冠」に触発されたプログラム |
振付:クリスチャン・シュプック
パフォーマンス:ゴーティエ・ダンス//
ダンス・カンパニー・シアターハウス・シュトゥットガルト
監督:ニコライ・ヴィアルコヴィッチ |

20 59748
(DVD)
\3000 |
クリスチャン・シュプックの画期的な振付による「ポッペア」エリック・ゴーティエの自由で独創的なダンスも必見!3D
収録で官能の世界がよりリアルに!
(Blu-ray)画面:1080i Full HD,16:9// 3D
&2D、音声:PCM ステレオ、DTS HD Master
Audio5.1、リージョン:All、原語(語り部分):独・仏、字幕:英・独・仏、78分+5分(ボーナス)
(DVD)画面:NTSC,16:9、音声:PCM ステレオ、DTS
5.1、DD5.1、リージョン:All、原語(語り部分):独・仏、字幕:英・独・仏、78分+5分(ボーナス)
シュトゥットガルト・バレエ団の振付家を経て現在チューリッヒ・バレエの芸術監督を務めているクリスチャン・シュプックと、エリック・ゴーティエが主宰するダンス・カンパニー、ゴーティエ・ダンスによる舞台「POPPEA//POPPEA」。2011
年ドイツ演劇賞「ザ・ファウスト」を受賞したプログラムです。この映像は2013
年7 月にシアターハウス・シュトゥットガルトで行われた公演で、650
人の観客が総立ちになって「ブラボー!」という歓声と、拍手が鳴りやまなかったそうです。
内容はモンテヴェルディの傑作オペラ「ポッペアの戴冠」に触発されたプログラム。皇帝ネロと愛人ポッペアをめぐり繰り広げられる「愛がすべてを許し超越する」という物語で、最後には悪が勝利するという愛憎劇。
本舞台は「こんばんは。皆様。ポッペアとネロの物語を話すことは私にとって大変名誉なことである」というフランス語の導入から開始されます。
シュプックはこの強烈なストーリーから、実験的な振付に映像と語りを組み込んだ刺激的な舞台を創り上げています。音楽は、原作というべきモンテヴェルディを主軸に、ロベルト・シューマン、イタリア・バロックの作曲家ジェミニアーニ、ドイツ・バロックの作曲家ヴェストホフ、そしてアイスランドの歌手エミリアナ・トリーニ、アメリカの歌手キャット・パワー、マーティン・ドナーらの楽曲も使用しています。
さらにブルーレイでは、3D と2D の収録になっており、暗闇に浮き上がるダンサーたちの肢体が、リアルに官能性を描き出しています。

|

8/12(火)紹介新譜
マイナー・レーベル新譜
 DELPHIAN DELPHIAN
|


DCD 34127
(3CD/特別価格)
\5100 →\4690 |
英グラモフォン賞2014Solo Vocal部門賞ノミネート・タイトル!
若き7人の逸材たちが歌うラフマニノフ!
ラフマニノフ:歌曲集
6つの歌曲 Op.4/6つの歌曲 Op.8/
12の歌曲 Op.14/しゃっくりをしたかね、ナターシャよ/
12の歌曲 Op.21/15の歌曲 Op.26/
S.ラフマニノフからK.S.スタニスラフスキーへの手紙/
14の歌曲 Op.34/6つの歌曲 Op.38 |
エヴェリーナ・ドブラチェヴァ(ソプラノ)
エカテリーナ・シウリナ(ソプラノ)
ジュスティーナ・グリンガイト(メゾ・ソプラノ)
ダニール・シュトーダ(テノール)
アンドレイ・ボンダレンコ(バリトン)
ロディオン・ポゴソフ(バリトン)
アレクサンドル・ヴィノグラードフ(バス)
イアン・バーンサイド(ピアノ) |
名手イアン・バーンサイドのピアノも光る!
デルフィアン(Delphian)のラフマニノフ歌曲集は、1890年から1916年の約25年間に出版された、若き日の傑作集。
若かりし日のラフマニノフが紡いだ優美なる旋律を歌うのは、2014年にウィグモア・ホール・デビューを果たし、ミハイル・ユロフスキやズヴェーデンとのレコーディングも高評価を得ているロシアのソプラノ、エヴェリーナ・ドブラチェヴァをはじめとする若き7人の逸材たち。
歌曲伴奏のスペシャリストとして高名なイアン・バーンサイドのピアノが、若き7人の歌い手たちのラフマニノフに華を添えている。
※録音:2012年9月、11月&2013年1月、クイーンズ・ホール(エジンバラ、スコットランド)

|
| |
|
|
シェパード:宗教合唱作品集
我らを救い給えI/タルシスの王らは/喜べ、聖母マリアよ/
サクリス・ソレムニス/キリエ、光にしてその源/
カンタータ・ミサ/とどまれ三位一体よII/
今日、われらの下に天の王が生まれ/言葉は肉となりて |
エジンバラ・セント・
メアリー大聖堂聖歌隊
ダンカン・ファーガソン(指揮) |
スコットランドの名門聖歌隊のハーモニー。イギリス・ルネサンス、シェパードの芸術。
スコットランドの名門、エジンバラ・セント・メアリー大聖堂聖歌隊が歌うイギリス・ルネサンス、ジョン・シェパード(c.1515−1558)の宗教合唱作品集。
シェパードとも縁の深いモードリン・カレッジでも学んだ経歴を持つ合唱指揮者、オルガニスト、ダンカン・ファーガソンが、セント・メアリー大聖堂の壮大な空間に、シェパードの、そしてイギリス・ルネサンスのポリフォニーを荘厳に響かせる。
このシェパードの宗教合唱作品集は、英グラモフォン誌でエディターズ・チョイスに選出されるなど、イギリスを中心に評価急上昇中。
※録音:2013年1月29日−31日&9月18日−20日、セント・メアリー大聖堂(エジンバラ、スコットランド)

|
| |

DCD 34131
(2CD/特別価格)
\4000 |
シュニトケ:ピアノ作品全集
ピアノ・ソナタ第1番/ピアノ・ソナタ第2番/
ピアノ・ソナタ第3番/変奏曲/前奏曲とフーガ/
即興とフーガ/1つの和音による変奏曲/小さなピアノ小品集/
ストラヴィンスキー、プロコフィエフ、ショスタコーヴィチへのオマージュ*/**/
5つのアフォリズム/ピアノのためのソナチナ(4手のための)*/
モーツァルトのピアノ協奏曲のためのカデンツァ
(K.39/K.467/K.491/K.503) |
サイモン・スミス(ピアノ)
リチャード・ビーチャム(ピアノ)*
ジョン・キャメロン(ピアノ)** |
イングランドの最北、ノーサンバーランドで1983年に生まれたサイモン・スミスは、スティーヴン・オズボーンの師匠でもある名教師リチャード・ビーチャムからピアノを学び、2002年にレコーディング・デビューを飾った才能豊かな若手ピアニスト。
特に20世紀以降の近現代作品を得意としているサイモン・スミスが完成させたシュニトケのピアノ作品全集は、死の淵から生還を果たした1980年代後半以降に作曲された3曲のピアノ・ソナタや、60〜70年代の作品、さらにはモーツァルトのピアノ協奏曲の"シュニトケ版カデンツァ"を収録したファン必携の好企画盤!
「オマージュ」、「ソナチナ」での師弟共演も聴きどころ。
※録音:2012年1月23日&12月4日−5日&2013年4月18日−19日、レイド・コンサート・ホール、エジンバラ大学(スコットランド) |
| |
|
|
聖コルンバを褒め讃え 〜 ケルト教会の音世界 |
ケンブリッジ・ゴンヴィル&
カイウス・カレッジ合唱団
ジェフリー・ウェッバー(指揮)
バーナビー・ブラウン(トリプルパイプ、リラ)
サイモン・オドワイアー(アイリッシュホルン)
マラキー・フレーム(アイリッシュホルン) |
ヘブリディーズ諸島のアイオナ島からの7世紀の賛歌、10世紀スイスのケルト文化からの聖歌、インチコルム島に伝わる14世紀のアンティフォン。
ジェフリー・ウェッバーとケンブリッジ・ゴンヴィル&カイウス・カレッジ合唱団が、イングランドの合唱音楽の伝統と、ケルト文化のコラボレーションによる3つの音世界を表現。バグパイプ奏者バーナビー・ブラウンと合唱の組み合わせも興味深い。
2013年7月16日−18日の録音。 |
| |
|
|
弦楽四重奏曲集は3作品が世界初録音
マクミラン:
11月の春の風景
いくぶん控えめに(世界初録音)
坊やのために(世界初録音)
弦楽四重奏曲第3番(世界初録音) |
エジンバラ弦楽四重奏団
〔トリスタン・ガーニー(ヴァイオリン)、
ゴードン・ブラッグ(ヴァイオリン)、
ジェシカ・ビーストン(ヴィオラ)、
マーク・ベイリー(チェロ)〕 |
2010年で結成50周年を迎えたスコットランドのアンサンブル、エジンバラ弦楽四重奏団。
このアンサンブルのパトロンでもあるスコットランドのリーディング・コンポーザー、ジェームズ・マクミラン(1959−)の弦楽四重奏曲集は3作品が世界初録音。アンサンブルと作曲家の結び付きの強さを証明するプログラムです。
2013年7月25日−27日&2014年1月29日−30日の録音。 |
| |
|
|
ナリチクからのポストカード
ハイドン:
弦楽四重奏曲第38番変ホ長調 Op.33-2《冗談》
(ロシア四重奏曲第2番)
プロコフィエフ:弦楽四重奏曲第2番ヘ長調
ショスタコーヴィチ:弦楽四重奏曲第8番ハ短調 |
エジンバラ弦楽四重奏団
〔トリスタン・ガーニー(ヴァイオリン)、
ゴードン・ブラッグ(ヴァイオリン)、
ジェシカ・ビーストン(ヴィオラ)、
マーク・ベイリー(チェロ)〕 |
「ナリチクからのポストカード」は、20〜21世紀の弦楽四重奏曲のスペシャリスト、エジンバラ弦楽四重奏団のロシアにまつわるプログラム。
ハイドンの「ロシア四重奏曲第2番」からプロコフィエフの「第2番」へと続く際の響きが斬新。プロコフィエフ、ショスタコーヴィチとハイドンを1つの線で結んだアイディアとアンサンブル能力の高さは見事。
2013年6月19日−21日の録音。 |
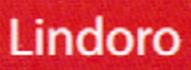 LINDORO LINDORO
|
|
|
エン・エル・ムンド 〜
世界からのクラシカル&ポピュラー・アンコール集
ムニュス/ロレンソ:エン・エル・ムンド/ラミレス:ハチドリ/
作曲者不詳(ヴェッケルラン編):ママ,
教えて/フランク:行進曲/
プーランク:村人たち第2曲 スタッカート/
ジョビン:メディテーション、ワン・ノート・サンバ/
ピアソラ:ブエノスアイレスの秋/グレイ:真珠の首飾り/
アメリカ民謡:ロンサム・ロード・ブルース/
ラウタヴァーラ:ザ・ブルー・ドリーム/
スコットランド民謡:カワガラス/
アイルランド民謡:キング・ウィリアムズ・ランブルズ/
デルシュミット:ボアリッシュ/ルール:ザイデルゼー・バラード/
アーニー:アムステルダムのチューリップ/
ハイドン:音楽時計のための小品第30番Hob.XIX-30/
ヴェルディ:歌劇《椿姫》より 「私たちはジプシー娘」/
ムソルグスキー:組曲《展覧会の絵》より
「リモージュの市場」/
中国民謡:紅豆詞(小豆の詩)/本居長世:七つの子/
滝廉太郎:荒城の月/ギリシャ民謡:ハサポセルヴィコ/
オランダ、フランドル民謡:雪のように白い鳥がいた/
ハンガリー民謡:ゲメルの男たちの踊り/
バルトーク:
《子供のために》より 「連れ合いをなくした」、
ルーマニア民俗舞曲〜第1曲「棒踊り」、
第2曲「腰帯踊り」、第3曲「足踏み踊り」、
第4曲「ブチュム人の踊り」、第5曲「ルーマニア風」、
第6曲「急速な踊り」、第7曲「急速な踊り」 |
ロイヤル・ウィンド・ミュージック
パウル・レーンフーツ(指揮) |
ルネサンス・リコーダーでめぐる世界の旅
アムステルダム・ルッキ・スターダスト・クヮルテットの元メンバー、パウル・レーンフーツが創設したリコーダー・アンサンブル、ロイヤル・ウィンド・ミュージックによる、魅惑のアンコール集!
アムステルダム音楽院で学んだ13人の奏者が、サブコントラバス・リコーダーからトイ・リコーダー(ソプラニーノの半分にも満たないサイズ!)まで、約50種のリコーダーを駆使して繰り広げるのは、アメリカ、スペイン、フランス、ブラジル、アルゼンチン、スコットランド、ロシア、ハンガリー、日本、中国など、まさに世界中をめぐるアンコール・ピース。編曲はすべてパウル・レーンフーツ。
※録音:2010年11月30日−12月4日、デ・ダウフ(アムステルダム)

|
| |
|
|
17世紀フランスのギター音楽
コルベッタ:組曲イ短調/グルヌラン:組曲ニ短調/
ル・コック:シャコンヌ/作曲者不詳:小品集ニ長調/
ド・ヴィゼー:組曲ト長調/
コルベッタ:サラバンド・ラ・ストゥアルダ、アルマンド |
イスラエル・ゴラーニ(バロックギター) |
イスラエル・ゴラーニは、イスラエルのテルアビブ大学を卒業し、ナイジェル・ノースとホプキンソン・スミスにルネサンス・リュートのマスタークラスを受け、フレッド・ヤコブスとエリザベス・ケニーに師事しテオルボのスキルを獲得。リュートとテオルボの名手として数々の古楽オーケストラやアンサンブルと共演、音楽祭などに参加しながら、2010年のユトレヒト古楽音楽祭ではバロック・ギターのソリストとしてデビューしている。
これまで、ロイヤル・ウィンド・ミュージックやオランダ・バッハ協会の録音に参加してきたゴラーニの、ソロ・デビューとなるこのアルバムは、ロベール・ド・ヴィゼー(c.1650−c.1732)を中心に、フランチェスコ・コルベッタ(1615−1681)、アンリ・グルヌラン(c.1625−1700)、フランソワ・ル・コック(fl.1685−1729)ら、17世紀フランスのバロック・ギターのための作品集。
現在は現代音楽のアンサンブルやヒップホップ・グループとのコラボレーションなど多彩な才能も発揮するイスラエル・ゴラーニ。ルイ14世を魅了したバロック・ギターの音楽を、美しく躍動的に再現する。
※録音:2012年3月14ー17日、プロテスタント教会(テルカプレ/オランダ) |
| |
|
|
ブルネッティ:弦楽三重奏のためのディヴェルティメント第4集
ディヴェルティメント第1番イ長調 L.145
ディヴェルティメント第2番変ロ長調 L.146
ディヴェルティメント第3番ハ短調 L.147
ディヴェルティメント第4番ハ長調 L.148
ディヴェルティメント第5番変ホ長調 L.149 |
カルメン・ベネリス
〔ラウル・オレリャナ(ヴァイオリン)、
パブロ・アルマサン(ヴィオラ)、
ギジェルモ・マルティン(チェロ)〕 |
前作「弦楽四重奏曲集(NL 3011)」に続く、カルメン・ベネリスによるブルネッティの作品集第2弾は、弦楽三重奏のためのディヴェルティメント。
ガエターノ・ブルネッティ(1744−1798)はイタリアに生まれ、(スカルラッティやボッケリーニなど、当時の多くのイタリア人作曲家と同じように)スペインで活躍した18世紀の作曲家。
スペインのピリオド・アンサンブル"カルメン・ベネリス"は、ヴァイオリンにチリ出身でエンリコ・ガッティに師事したヴァイオリニスト、ラウル・オレリャナ(オレジャナ)を迎え、中核メンバーであるパブロ・アルマサン、ギジェルモ・マルティンとともに、ブルネッティの知られざる音楽を聞かせてくれる。
カルメン・ベネリス/ブルネッティの第1弾 |
|
|
ガエターノ・ブルネッティ(1744-1798):弦楽四重奏曲集
イ短調 Op.2 No.4 (L.153)/ト長調 Op.3
No.6 (L.161)
変ロ長調 Serie 8 No.7 (L.196)/ニ長調
Serie 8 No.10 (L.199) |
カルメン・ベネリス
ミゲル・ロメロ・クレスポ、
ラファエル・ムニョス=トレロ・サントス(ヴァイオリン)
パブロ・アルマサン・ハエン(ヴィオラ)
ギリェルモ・マルティン・ガミス(チェロ) |
ガエターノ・ブルネッティはイタリアのファーノに生まれ、ピエトロ・ナルディーニに師事した後1762年頃スペインのマドリードに移住。1770年に国王カルロス3世の王太子(アストゥリアス公)付き音楽教師に就任。1788年、王太子がカルロス4世として即位するとともに王の私設楽団のヴァイオリニストとなり、さらに1795年に王宮楽団が創設されるにあたってその指揮者に就任しました。
450を超える作品を残したとされていますが、生前・没後とも出版された作品は少なく、演奏・録音される機会も多くありません。当盤は貴重なものと言えるでしょう。カルメン・ベネリスは2005年に創設されたスペインのピリオド楽器アンサンブル。 |
|
| |
|
|
16世紀グラナダの管楽アンサンブル
F.ゲレーロ、モラレス、P.ゲレーロ、セバリョス、
ウレデ、ラッスス、クレキヨン、ゴンベール、サンドラン、
ジョスカン・デ・プレ、マンシクール、アルカデルト、
ヴェルドロ、クレメンス・ノン・パパ、
へリンクと作曲者不詳の作品 |
アンサンブル・ラ・ダンスリー |
| マヌエル・デ・ファリャ図書館所蔵の写本を中心に、スペイン、グラナダ地方の管楽器によるアンサンブル(minstrel
ensemble)を再現。リコーダー、ツィンク(コルネット)、サックバットに、ダブルリードのチリミア、バホンシリョ、バホン、オルロ(クルムホルン)など、大小様々な古楽器を駆使した6人のアンサンブルで、宗教、大学、家庭、広場など様々な場面の音楽を奏でていく。 |
| |
|
|
デ・ラ・コンキスタ・イ・オトロス・デモニオス
ベルターリ:チャコーナ ハ長調
マリン:乙女よ、あなたの移り気に
作曲者不詳(17世紀):マリサパロス
クライン:
チェロ・ソナタ第5番イ短調 Op.4-5
(チェロと通奏低音のための6つのソナタOp.4より)
作曲者不詳(17世紀):ペルーのトルヒリョの写本より
ヴァレンテ:ナポリのガリアルダ/トルベリーノ/ハラベ・ロコ |
ロス・テンペラメントス
〔スワンティー・タムス・フライアー
(ソプラノ、リコーダー)、
アンニカ・フォーグルプ(リコーダー)、
ウゴ・ミゲル・デ・ロダス・サンチェス
(バロックギター)、
ネストル・ファビアン・コルテス・ガルソン
(バロックチェロ)、
ナディーネ・レンメルト(チェンバロ)〕 |
イタリアのアントニオ・ベルターリ(1605−1669)とアントニオ・ヴァレンテ(1530−1585)、スペインのホセ・マリン(1618−1699)、オランダのヤコプ・ヘルマン・クライン(1688−1748)。ヨーロッパの国々に侵略された中南米の音楽・文化とヨーロッパ文化の発展と融合を、歌、リコーダー、チェロ、ギターで表現。
※録音:2013年11月20日−23日、ルンセン聖コスマス&聖ダミアヌス教会(ドイツ) |
 NIMBUS(CD−R) NIMBUS(CD−R)
|


NI 2583
(CD-R)
\2100 →\1890 |
ギター&ハープシコード版!バッハの6つのトリオ・ソナタ!
J・S・バッハ:6つのトリオ・ソナタBWV.525
〜 530 |
エリオット・フィスク(ギター)
アルバート・フラー(ハープシコード) |
自身のアレンジによるギター版パガニーニの「24のカプリース」(NI
2505)がルッジェーロ・リッチからも絶賛されたセゴビア最後の弟子エリオット・フィスク。
ハープシコードはアメリカの古楽界の巨匠アルバート・フラー(1926−2007)。ギターとハープシコード版の6つのトリオ・ソナタは、耳に心地良い音色、撥弦楽器の相性の良さが際立つ。
※Nimbus、Nimbus Allianceはレーベル・オフィシャルのCD-R盤となります。
|
| |


NI 5913
(CD-R)
\2400 →\2190 |
実力者ラファエル・ウォルフィッシュ、親子共演もポイントの一つ
ブロッホ:ヘブライ狂詩曲 《シェロモ》、荒野の叫び
カプレ:エピファニ
ラヴェル:2つのヘブライの歌より第1曲 《カディッシュ》 |
ラファエル・ウォルフィッシュ(チェロ)
ベンジャミン・ウォルフィッシュ(指揮)
BBCウェールズ・ナショナル管弦楽団 |
ハイペリオン(Hyperion)、シャンドス(Chandos)、ニンバス(Nimbus)などイギリスのレーベルに数多くの録音を行ってきた実力者ラファエル・ウォルフィッシュ。
今作はラファエル自身も好きだと言う、ブロッホの「シェロモ」をメインに、輝きのある演奏を聴かせてくれる。指揮はラファエルの息子であるベンジャミン、親子共演もポイントの一つ。
2013年1月2日−4日の録音。 |
 NIMBUS ALLIANCE(CD−R) NIMBUS ALLIANCE(CD−R)
|


NI 6245/6
(2CD-R/特別価格)
\4000 →\3690 |
ベートーヴェン:ヴァイオリンとフォルテピアノのためのソナタ集
ソナタ第1番ニ長調 Op.12-1
ソナタ第2番イ長調 Op.12-2
ソナタ第3番変ホ長調 Op.12-3
ソナタ第4番イ短調 Op.23
ソナタ第5番ヘ長調Op.24 《春》 |
エリザベス・ウォルフィッシュ(ヴァイオリン)
デヴィッド・ブライトマン(フォルテピアノ) |
ハイペリオン(Hyperion)で多くの録音を残してきた、イギリスの古楽器復興時代において大きな役割を担った女流ヴァイオリニスト、エリザベス・ウォルフィッシュのベートヴェンのソナタ集。アルビノーニやコレッリ、タルティーニなど、ハイペリオンに録音を行ったイタリアン・レパートリーはいずれも名演と評されている。
2012年1月9日−14日の録音。 |
| |

NI 6253
(CD-R)
\2400 |
ヴィオラのための音楽 《リフレクションズ》
ブリテン:
リフレクション、2つの肖像’EBB’(アウトラム編)、
ラクリメ Op.48、エレジー
ブリッジ:
小川の枝垂れ柳(ブリテン編)、沈思せる人、
アレグロ・アパショナート |
マーティン・アウトラム(ヴィオラ)
ジュリアン・ロルトン(ピアノ) |
ベンジャミン・ブリテン(1913−1976)、フランク・ブリッジ(1879−1941)、2人のイギリス作曲家のヴィオラ作品集。
演奏は「スコティッシュ・ヴィオラ」(NI
6180)で共演しているマーティン・アウトラムとジュリアン・ロルトンのコンビ。
11月16日−18日の録音。 |
 MD+G MD+G
|


307 18602
\2400→\2190 |
《ライプツィヒ弦楽四重奏団〜ハイドン:弦楽四重奏曲集Vol.7》
弦楽四重奏曲第81番ト長調Op.77-1 Hob III:81
弦楽四重奏曲第82番ヘ長調Op.77-2 Hob.
III:82
弦楽四重奏曲第83番ニ短調Op.103 Hob. III:83
弦楽四重奏曲第43番ニ短調Op.42 Hob. III.43 |
ライプツィヒ弦楽四重奏団
[シュテファン・アルツベルガー(Vn)
ティルマン・ビュニング(Vn)
イーヴォ・バウアー(Va)
マティアス・モースドルフ(Vc)] |
クラシカルの弓を使用し、ハイドンの語法を見事に再現したハイドン後期の作品
世界最古のシンフォニー・オーケストラである名門ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団の首席奏者たちが1988年に結成した当団。55人の作曲家による約200曲をレパートリーに持ち、録音も30枚以上残している名門中の名門です。
そんな彼らが満を持してスタートさせたハイドン:弦楽四重奏曲録音も今回で第7弾を迎えました。81と82番は、1799年ウィーンで書かれたロプコヴィッツ伯爵に献呈されたもので、すでにシューベルトを想像させるロマン的な世界に深く入り込んだ作品。83番は、82番に続いて作曲が始められましたが、アンダンテとメヌエット楽章のみ完成され、未完となったものです。
おそらく老齢のため完成をあきらめたものと言われています。
通常ハイドンの弦楽四重奏曲はセットで書かれていますが、43番のみは唯一単独で書かれた、謎めいた作品でもあります。
このシリーズの録音ではハイドン時代の弓の忠実なコピー弓を使用し、ハイドンの語法を見事に再現しているのが特長です。 |
| |


901 18576
(SACD Hybrid)
\3100→\2790 |
ベートーヴェンの第9に匹敵する感動的な作品
メンデルスゾーン:
交響曲第2番 変ロ長調『讃歌』Op.52 |
ダグラス・ボイド(指揮)
ヴィンタートゥール・ムジークコレギウム
リサ・ラーション(Sp)
マリン・ハルテリウス(Sp)
イェルク・デュールミュラー(T)
アンサンブル・コランド(合唱) |
メンデルスゾーンの交響曲第2番「讃歌」は1840年6月5日に初演されました。
印刷技術を発明したヨハネス・グーテンベルクの生誕400年を記念する祝典がライプツィヒで開催され、このために作られたのが当作品。
歌詞は、マルティン・ルターが旧約聖書をドイツ語に翻訳したものをメンデルスゾーンが改編したものを使っています。3楽章からなる長大なシンフォニアに、合唱と独唱が高らかに「神への讃歌」を歌い上げる第4楽章が続き、ベートーヴェンの第九に匹敵する感動的な作品です。
第2番とされていますが、この曲の前に第4番「イタリア」と第5番「宗教改革」が完成されていたので、実際は彼の第4番目の交響曲ということになります。
急成長中のソプラノ、マリン・ハリテリウスとヴェテラン、リサ・ラーション、そしてテノールのイェルク・デュールミュラーという万全の歌手陣を揃え、合唱、オーケストラの全てを纏めるのは、ヨーロッパ室内管弦楽団の創設メンバーの一人、名オーボエ奏者ダグラス・ボイドです。軽やかさと壮麗さを兼ね備えた名演をお楽しみください。
ハイブリッドSACD仕様 (CD STEREO/ SACD STEREO/
SACD SURROUND)
<ダグラス・ボイド&ヴィンタートゥール・ムジークコレギウム旧譜>
チューリヒ州の工業都市ヴィンタートゥールのオーケストラ、ヴィンタートゥール・ムジークコレギウム(ヴィンタートゥール交響楽団とも)は1629年創設というスイス最古の楽団。シェルヘンがその発展向上に大きく貢献し、フルトヴェングラー、フリッツ・ブッシュ、カイルベルトなどもかかわりを持った名門。名フルート奏者ペーター=ルーカス・グラーフは若いときにここのオーケストラの首席奏者を務めていたらしい。
一時期はウェルザー=メストやハインリヒ・シフなどが首席指揮者を務めていたが、現在はダグラス・ボイドがその任に就いている。 |

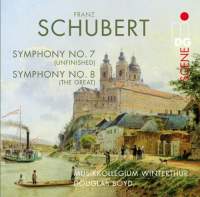
901 16366
(SACD)
\3100 →\2790 |
ダグラス・ボイド/
シューベルト:《未完成》&《ザ・グレイト》
1.交響曲第8番ロ短調D.759《未完成》
2. 同 第9番ハ長調D.944《ザ・グレイト》 |
ヴィンタートゥール・ムジークコレギウム
指揮:ダグラス・ボイド |
歯切れよく爽快な名演!
録音:2010年10月5〜8日 シュタットハウス、ヴィンタートゥール
イギリスのグラスゴー出身で、ヨーロッパ室内管の設立メンバーの一人として2002年まで首席オーボエ奏者を務め、現在は指揮者として活躍する若き名匠ダグラス・ボイド。2009−10シーズンより、スイスのヴィンタートゥール・ムジークコレギウムの首席指揮者を務める彼の最新盤は、好評を博した前作に続くシューベルト。《未完成》と《ザ・グレイト》という王道プログラムを、実に歯切れよく爽快に歌い上げています。 |
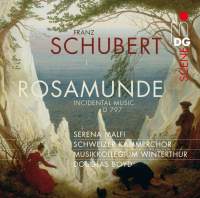
901 16336
(SACD Hybrid)
\3100 →\2790 |
ダグラス・ボイド/
シューベルト:劇付随音楽《ロザムンデ》D.797 |
セレーナ・マルフィ(アルト)
シュヴァイツァー室内合唱団
ムジークコレギウム・ヴィンタートゥーア
指揮:ダグラス・ボイド |
明快で活気に満ち溢れた音楽性を存分に活かした秀演
録音:2010年10月5〜8日 ヴィンタートゥーア
イギリスのグラスゴー出身で、ヨーロッパ室内管の設立メンバーの一人として2002年まで首席オーボエ奏者を務めていたが、現在は指揮者として活躍する若き名匠ダグラス・ボイド。マンチェスター・カメラータの音楽監督として、同団をイギリスで最も優良なオーケストラの一つに育て上げた手腕を評価され、2009-10シーズンより、スイスのヴィンタートゥーア・ムジークコレギウムの首席指揮者に就任しました。当盤に収録されたシューベルト《ロザムンデ》でも、その明快で活気に満ち溢れた音楽性を存分に活かし、強い金管の出だしも、叙情的な弦楽パートも、情感豊かに歌い上げています。 |
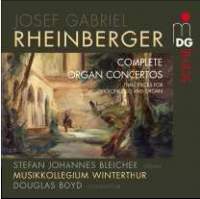
901 16436
(SACD)
\3100 →\2790 |
ラインベルガー:オルガンと管弦楽のための協奏曲集
1.協奏曲第2番ト短調Op.177
2.チェロとオルガンのための3つの小品
3.協奏曲第1番ヘ長調Op.137 |
シュテファン・ヨハネス・ブライヒャー(オルガン)
ムジークコレギウム・ヴィンタートゥーア
指揮:ダグラス・ボイド
キャシリア・クメル(チェロ:2) |
再評価が進むラインベルガーの注目の協奏曲集
録音:2010年2月 ヴィンタートゥーア
ヨーゼフ・ガブリエル・ラインベルガー(1839-1901)はリヒテンシュタインのファドゥーツに生まれ、ドイツのミュンヘンで没した作曲家&オルガン奏者。代表作のオルガン・ソナタ20曲をはじめ、オルガン作品に傑作が多いが、現在では再評価が進み、様々なCDリリースも好調になっています。古今のオルガン作品を精力的に録音し続けているブライヒャーの演奏で、彼の魅力あふれる2つのオルガン協奏曲をどうぞ!また、チェロとの美しい対話による3つの小品も聴きどころです。 |
|
|
| |

613 18582
\2400 |
シュライエルマッハーが恩師, 友人、同僚たちに敬意を払って…
フリードリッヒ・ゴールドマン(1941-2009):
4つのピアノのための小品(1973)/
ライナー・ブレデマイヤール(1929-1995):
ピアノのための小品3(1969)/
ジークフリート・ティーレ(1934-):
夕べの幻想(1988/89)/
トーマス・ミュラー(1939-):in memoriam
f.g.(2009)/
フリードリヒ・シェンカー(1942-2013):
3つのピアノのための小品(1975),
ピアノのための小品(シェーンベルクへのオマージュ)(1972)/
ヘルマン・ケラー(1945-):
カッツァー変奏曲(2004),
ハンス・ペーター・ヤンノッホのために(2002),
ライナー・ブレデマイヤールのために(2005),
クルターグ・ジェルジュのために(2002)/
クヌート・ミュラー(1963-):
Tannit (2013),
ヴォルフガング・ハイジヒ(1952-):
Absence, Happy Birthday,
Leuchtreklame,
Schade, Kein Ort Nirgends,
Sekundenweise bh/
ニコラウス・リヒター・デ・ヴロエ(1955-):
Peridotit - Steinstuck #2 (2007) |
シュテッフェン・シュライエルマッハー(P) |
シュライエルマッハーが恩師, 友人、同僚たちに敬意を払って…
現代音楽を専門とするピアノのシュテッフェン・シュライエルマッハーは、旧東ドイツのハレ出身。元々はライプツィヒ・フェリックス・メンデルスゾーン・バルトルディ音楽演劇大学やベルリン芸術大学で、ジークフリート・ティーレやフリードリヒ・ゴルトマンに作曲を師事しており、表現主義的傾向の習作を書いていました。彼の師であるティール、ゴールドマン、シェンカーらは、友人として、また同僚としてお互いに、芸術的な個性に影響を与え合ったと語っています。その後も、フランス的、アバンギャルド的、またメカニカルに作曲をする友人達と出会い、彼の音楽に新風が吹き込まれていきました。そうしたシュライエルマッハーの師,
友人、同僚たちに敬意を払って、彼らの作品を演奏しているのが当盤です。 |
| |


615 2332
\2400→\2190 |
22歳で世を去った天才作曲家シュテーレ
フーゴ・シュテーレ(1826-1848):
ピアノ四重奏曲第1番イ長調
ドヴォルザーク(1841-1904):
ピアノ四重奏曲第1番Op.23 |
モーツァルト・ピアノ四重奏団
[Klaus Schilde(P),
Karsten Heymann(Vn),
Jean Rieber(Va),
Ulrich Bode(Vc)] |
わずか22歳で世を去った天才的作曲家シュテーレの作品
フーゴ・シュテーレは、ヴァイオリンとピアノを学んだ後、シュポアの弟子となりました。
シュポアは彼を非常に高く評価し、ワーグナー、ロベルト・シューマン、クララ・シューマンらとも演奏を行い、カッセルの宮廷楽団のヴィオラ奏者も務めました。
しかしわずか22歳で髄膜炎のため惜しくも命を落とします。現在はわずかの室内楽作品、交響曲、コンサート用序曲、オペラ、詩篇が残されている程度ですが、初期のロマンチックな旋律に満ちた若々しいエネルギーあふれる音楽は、大胆なアイデアで私たちを驚かせてくれます。
シュテーレとドヴォルザークの同編成の曲をカップリングし、それぞれの相違を楽しめる興味深い企画盤です。 |
| |


605 10372
\2400→\2190
〔再発売〕 |
待望の再発売!
ラインハルト・カイザー(1674-1739):
①歌劇「クラウディウスの誘惑」より
②フルート、ヴィオラ・ダモーレと通奏低音のための3声のソナタ第1番
③歌劇「バビロンの王」より
④弦楽のための協奏曲
⑤アリア「最愛のアドニス」
⑥歌劇「美徳の力」より |
エリザベート・ショル(Sp)
ラ・リコルダンツァ(ピリオド楽器アンサンブル)
|
ドイツ・バロック歌劇の祖、カイザーによる美しいアリア
ハンブルグで活躍したバロック時代中期の作曲家ラインハルト・カイザー。オペラ、アリア、デュエット、カンタータ、セレナーデ、教会音楽とオラトリオなど、幅広い作品ジャンルで、テレマン同等の人気を誇った作曲家といわれています。
特にバッハやテレマンがあまり着手しなかったオペラのジャンルでは、「ドイツ・バロック歌劇の祖」とされています。そのカイザーのオペラからのロココ趣味を取り入れた歌にソナタや器楽合奏を組み合わせたバランスよいカップリング。
そして名バロック歌手エリザベート・ショルの透明感ある歌声によって、美しさが際立ったアルバムです。
長らく入手困難になっておりましたが、待望の再発売です!
【録音】2000年5月録音
バロック時代、音楽の中心はイタリアだった。一方ドイツは、芸術的にも文化的にも商業的にも他のヨーロッパ諸国と比べて格段に差をつけられていた。
ところが港町ハンブルグだけは違っていた。もともと「ドイツ」というひとかたまりの国などなく、幾多もの自由国家やらなんやらで構成されていた当時の「ドイツ」地方。ハンブルグはそのなかで例外的に裕福で文化的にも進んだ都市だった。
さて、オペラは基本的に貴族の宮廷のために存在していたが、ようやくヴェネツィアで一般庶民も見られる劇場が生まれた。そしてドイツでもようやくハンブルグでそうした劇場が生まれ、イタリアにも負けないようなドイツ独自のオペラが人気を博した。ご当地オペラである。そのハンブルグで一世を風靡したのが、ラインハルト・カイザー。後のハンブルク市立歌劇場の首席作曲家を
勤め、ドイツの国民オペラを隆盛に導いた。年代的にはヴィヴァルディとほぼ同時代。年下のテレマンも彼を慕ってハンブルグに来たらしい。その後いろいろ確執はあったらしいが、カイザーが繁栄させた土壌の上に、ドイツ最大の人気作曲家テレマンが生まれたことは間違いない。実際若きヘンデルもカイザーが発掘したと言われる。
さて、そんなドイツの隠れた偉人カイザーのいろいろな作品を巧みに組み合わせた秀逸なアルバム、待望の再発売。
|
BELLA GRERIT
|
アンサンブル・ベッラ・ジェリトの自主レーベル。 |
|
|
甘美な光景 フェデリーコ・ダ・モンテフェルトロの宮廷の音楽
ウルビーノ公の図書館の写本1411号所収のロンドーとバラード集(15世紀)
不詳:Bella gerit(*)
ジル・バンショワ(1400頃-1460):
Mon doulx espoir / Seulle egaree / Margarite,
fleur de valeur
Adieu, adieu
ヨハンネス・チコーニア(1373頃-1412):La
dolce vista
ギヨーム・デュファイ(1400頃-1474):Mon
cuer chant
ジル・バンショワ:Files a marier / Esclave
puist yl devenir
ギヨーム・デュファイ:Trop lonc temp
ジル・バンショワ:
Pour prison ne pour maladie / En sera
il mieux / Je ne fai tous jours
Vostre tres doulx regart
不詳:Faites de moy / Con dollia me ne
vo
ギヨーム・デュファイ:Se la face ay pale
ジル・バンショワ:Deul angoisseux
ジョン・ダンスタブル(1390頃-1453)/
ジョン・ベディンガム(1422頃-1459/1460):O
rosa bella
不詳:J'ay pris amour |
アンサンブル・ベッラ・ジェリト、
アンサンブル・ラウス・ヴェリス、
フィッファロ・コンソート
イラリア・セヴェーロ(歌)
シモーネ・ソリーニ(歌、リュート)
ダヴィド・モナッキ(歌、リュート、ビウエラ)
エネア・ソリーニ(歌、プサルテリウム、ナッカーラ、太鼓、タンバリン)
ジョルダーノ・チェッコッティ(ヴィオラ・ダ・ガンバ、リベカ、リベコーネ)
ダニエーレ・ベルナルディーニ(笛太鼓、ダブル・リコーダー、アルトバッソ、
リコーダー、ボンバルダ、クルムホルン)
アンゲリカ・モス(ポジティヴ・オルガン)
クリスティーナ・テルノヴェク(ヴィオラ・ダ・ガンバ、リベコーネ)
ニコラス・サンサルラト(リラ・ダ・ブラッチョ)
マウロ・モリーニ、ルイージ・ジェルミーニ(トロンボーン)
クリスティーナ・ベルナルディーニ(クルムホルン、リコーダー)
ジョヴァンニ・ブルニャーミ(クルムホルン、リコーダー、笛太鼓)
カッペッラ・ムジカーレ・サンティッシモ・サクラメント合唱団(*)
ピエルカルロ・フォンテマージ(合唱指揮(*)) |
録音:2005年10月10日、ドゥカーレ宮殿サーラ・カステッラーレ,2005年10月9、11、22日、聖ベルナルディーノ教会の公爵霊廟,2005年10月23-24日、ドゥカーレ宮殿宴会場,2005年11月24日、12月11日、カッペッラ・ムジカーレ・サンティッシモ・サクラメント,以上ウルビーノ、イタリア
イタリアの典型的なルネサンス君主の一人であるウルビーノ公フェデリーコ・ダ・モンテフェルトロ(フェデリーコ3世;1422-1482)の宮廷音楽を3団体合同で再現する試み。
ベッラ・ジェリトは主としてウルビーノ公国のルネサンス音楽レパートリーを演奏するために2005年イタリアのウルビーノで創設された声楽&ピリオド楽器アンサンブル。
ラウス・ヴェリスは中世・ルネサンス音楽を専門とする1999年イタリアのアッシジで創設された声楽&ピリオド楽器アンサンブル。
フィッファロ・コンソートは2002年に創設されたイタリアのルネサンス管楽器合奏団。 |
| |
|
|
カナの婚礼 ラファエロの時代のウルビーノの音楽
アドリアン・ヴィラールト(1490頃-1562):栄光の処女
[Virgo gloriosa]
アントワーヌ・ブリュメル(1460頃-1512/1513):
茨の中の百合のごとく [Sicut lilium inter
spinas]
ヨハンネス・ド・ラ・ファージュ(確認できる活躍期:1520頃):
ザカリアの妻エリザベト [Elisabeth Zachariae]
ジャン・ムトン(1459?-1522):
聖母は男を知らずして [Nesciens Mater
Virgo virum]
アンドレアス・デ・シルヴァ(1475/1480頃-1540頃):
イエスが語られていたその時 [In illo tempore
loquente Jesu]
ジョスカン・デ・プレ(1450/55頃-1521):森のニンフらよ
[Nymphes des bois]
アンドレアス・デ・シルヴァ:あなたは完璧に美しい
[Tota pulchra es]
ジャン・リシャフォール(1480頃-1547):
来たれ、キリストの花嫁 [Veni sponsa Christi]
ジャン・ムトン:
称えよ、ガリアの女王を [Exalta Regina
Galliae] /心と魂 [Corde et animo]
ルプス・ヘリンク(1493/1494-1541頃):
主よ、われらのために力の塔となりたまえ
[Esto nobis Domine, turris fortitudinis]
コンスタンツォ・フェスタ(1485/1490頃-1545):
バビロンの川のほとりで [Super flumina
Babilonis]
ジャン・ムトン:主よ、王を救いたまえ [Domine,
salvum fac regem
ピエール・ムリュ(1484?-1550頃):
あなたは私の心を奪った [Vulnerasti cor
meum]
ジャコタン(1440/1450-1529):
御身に請い願う、処女マリアよ [Rogamus
te Virgo Maria]
アドリアン・ヴィラールト:祝福されし使徒ヨハネは
[Beatus Johannes apostolus]
エリモ:カナで婚礼が行われた [Nuptiae factae
sunt]
ブリュネ:全世界に赴き [Ite in orbem universum]
ピエール・ムリュ:冷酷な死 [Fiere atropos] |
アンサンブル・ベッラ・ジェリト
シモーネ・ソリーニ(歌、リュート)
ダヴィド・モナッキ(歌、ビウエラ)
エネア・ソリーニ(歌、タンバリン)
アンゲリカ・モス(オルガン、ポジティヴ・オルガン)
アレッサンドロ・チョフィーニ、
マウロ・ボルジョーニ(歌)
ジョルダーノ・チェッコッティ(ヴィオラ・ダ・ガンバ)
ダニエーレ・ベルナルディーニ(ボンバルダ)
マッシモ・チャルフィ、
マウロ・モリーニ(トロンボーン) |
録音:2006年11月13-19日、ベネディクト会大天使聖ミカエル修道院、ラモーリ、ペルージャ県、イタリア
イタリア・ルネサンスを代表する画家ラファエロ(ラッファエッロ・サンティ;1483-1520)はウルビーノに生まれ、父も画家・詩人として仕えていたウルビーノ公の宮廷で画家としての活動を開始し、文人・芸術家たちと交流を深めました。
当盤は当時のウルビーノ公の宮廷での音楽を再現を試みたもので、古楽ファンのみならずルネサンス絵画ファンにもお勧めできます。 |
<メジャー・レーベル>
 韓国WARNER 韓国WARNER
|
 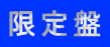
PWC15D 0012
(15CD)
\13000→\11990 |
レオニード・コーガンの芸術
CD 01
ラロ: スペイン交響曲 ニ短調 op.21 (1955
Mono recording)
レオニード・コーガン(ヴァイオリン),
シャルル・ブリュック(指揮), パリ音楽院管弦楽団
CD 02
J.S.バッハ: 2台のヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調
BWV 1043
J.S.バッハ: ヴァイオリン協奏曲 ホ長調
BWV 1042
J.S.バッハ: サラバンデ (パルティータ第1番から)
レオニード・コーガン& エリザベータ・ギレリス(ヴァイオリン),
オットー・アッカーマン(指揮),フィルハーモニア管弦楽団
CD 03
ブラームス: ヴァイオリン・ソナタ Nos.1
& 2
レオニード・コーガン(ヴァイオリン),
アンドレ・ムイトニク(ピアノ)
CD 04
モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲 第3番 ト長調
K.216 (1955 Mono recording)
プロコフィエフ: ヴァイオリン協奏曲 第2番 ト短調
op.63
レオニード・コーガン(ヴァイオリン)
オットー・アッカーマン(指揮),フィルハーモニア管弦楽団
(Mozart)
バージル・キャメロン(指揮),ロンドン交響楽団(Prokofiev)
CD 05
ブラームス: ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.77
(1955 Mono recording)
レオニード・コーガン(ヴァイオリン),
シャルル・ブリュック(指揮), パリ音楽院管弦楽団
CD 06
チャイコフスキー: ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.35
(1956 Mono recording),
ヴィヴァルディ: ヴァイオリン協奏曲第1番 ト短調
RV317
ロカテッリ:12の室内ソナタ op.6-7
レオニード・コーガン(ヴァイオリン),
アンドレ・ムイトニク(ピアノ)
アンドレ・ヴァンデルノート(指揮), パリ音楽院管弦楽団
CD 07
パガニーニ: ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調
op.6
パガニーニ:カンタービレ op.17
レオニード・コーガン(ヴァイオリン),
シャルル・ブリュック(指揮), パリ音楽院管弦楽団アンドレ・ムイトニク(ピアノ)
CD 08
ラロ: スペイン交響曲 ニ短調 op.21 (1959
Stereo recording)
チャイコフスキー: 憂鬱なセレナード op.26
レオニード・コーガン(ヴァイオリン),
キリル・コンドラシン(指揮),フィルハーモニア管弦楽団
CD 09
ブラームス: ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.77
(1959 Stereo recording)
レオニード・コーガン(ヴァイオリン),
キリル・コンドラシン(指揮),フィルハーモニア管弦楽団
CD 10
チャイコフスキー: ヴァイオリン協奏曲 ニ長調
op.35 (1959 Stereo recording)
チャイコフスキー:なつかしい土地の思い出
op.42 ニ短調〜瞑想曲
レオニード・コーガン(ヴァイオリン),
コンスタンティン・シルヴェストリ(指揮),
パリ音楽院管弦楽団
CD 11
ベートーヴェン: チャイコフスキー: ヴァイオリン協奏曲
ニ長調op.61 (1959 Stereo recording)
レオニード・コーガン(ヴァイオリン),
コンスタンティン・シルヴェストリ(指揮),
パリ音楽院管弦楽団
CD 12
モーツァルト: ヴァイオリン協奏曲 第3番 ト長調
K.216 (1959 Stereo recording)
メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲 ホ短調
op.64
レオニード・コーガン(ヴァイオリン),
コンスタンティン・シルヴェストリ(指揮),
パリ音楽院管弦楽団
CD 13
ルクレール: ソナタ 第3番 ハ長調 op.30-3,
第1番 ト長調 op.3-1
テレマン: 2台のヴァイオリンのための6つのカノン風ソナタ 第1番 ト長調
イザイ:2台のヴァイオリンのためのソナタ 第1番 ハ長調
レオニード・コーガン & エリザベート・ギレリス(ヴァイオリン)
CD 14
モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲 第3番 ト長調
K.216 (1955 Mono recording)
モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲 第5番 イ長調
K.219 'トルコ風'
レオニード・コーガン(ヴァイオリン)
オットー・アッカーマン(指揮),フィルハーモニア管弦楽団(No.3)
アンドレ・ヴァンデルノート(指揮), パリ音楽院管弦楽団(No.5)
CD 15
ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調
op.61 (1957 Mono recording)
レオニード・コーガン(ヴァイオリン),
アンドレ・ヴァンデルノート(指揮), パリ音楽院管弦楽団 |
| オリジナル・ジャケット仕様、ブックレット(英語表記)を封入。 |
<国内盤>
<映像>

|
|
![]()