AYRE CLASSICS
|
|
|
ダニエル・マトローヌ:
Rivages incertains(7つのオルガン曲;2008)
前奏曲/大天使祭のためのカリヨン/後奏曲/幻想曲「王の御旗」
フランシス・プーランクを記念するパストラーレとトッカータ
前奏曲とフーガ ハ長調/ある大西洋の礼拝堂のためのトッカータ |
ダニエル・マトローヌ(オルガン) |
|
録音:2008年11月、サン・ルイージ・デイ・フランチェージ教会、ローマ、イタリア
使用楽器:メルクリン製
ダニエル・マトローヌはアルジェリア生まれのフランス人作曲家・オルガン奏者。トゥールーズ音楽院で学んだ後パリでマリー=クレール・アラン(オルガン)、イヴォンヌ・ルフェビュール(ピアノ)、モーリス・デュリュフレ(作曲、即興演奏)を師事。
1999年以来2014年現在ローマのサン・ルイージ・デイ・フランチェージ教会(カラヴァッジョの祭壇画で有名なローマ在住フランス国民教会)のオルガン奏者を務めています。「Rivages
incertains」の直訳は「不確かな岸辺」。
|
| |
|
|
ローマのメンデルスゾーン
メンデルスゾーン(1809-1847):オルガン作品集
ソナタ第3番イ長調 Op.65 No.3(*)/ソナタ第2番ハ短調
Op.65 No.2(+)
前奏曲とフーガ ハ短調 Op.37 No.1(*)/ソナタ第5番ニ長調
Op.65 No.6(+)
ソナタ第6番ニ短調 Op.65 No.6(*) |
リヴィア・マッツァンティ(オルガン(*))
フランチェスコ・フィノッティ(オルガン(+)) |
|
録音:2009年10月20、22日、ライヴ、クリストゥス教会、ローマ、イタリア
メンデルスゾーンの生誕200年を記念してローマのルター派プロテスタント教会で行われたオルガン・コンサートのライヴ録音。
|
| |
|
|
グリーグ:夜想曲 ピアノ&歌曲集
抒情小曲集 から
アリエッタ Op.12 No.1/アルバムの綴り
Op.47 No.2/夜想曲 Op.54 No.4
ゲーゼ Op.57 No.2/ノルウェーの農民行進曲
Op.54 No.2/ワルツ Op.38 No.7
子守歌 Op.38 No.1
6つの歌曲 Op.48 から あいさつ(No.1)(*)
抒情小曲集 から 悲歌 Op.47 No.7
6つの歌曲 Op.48 から いつの日か、わが思いは(No.2)(*)
抒情小曲集 から 思い出 Op.71 No.7
6つの歌曲 Op.48 から 世の成り行き(No.3)(*)
抒情小曲集 から あなたのそばに Op.68
No.3
6つの歌曲 Op.48 から 沈黙したナイチンゲール(No.4)(*)
抒情小曲集 から 蝶 Op.43 No.1
6つの歌曲 Op.48 から 青春時代(No.5)(*)
抒情小曲集 から 夏の夕べ Op.71 No.2
6つの歌曲 Op.48 から ある夢(No.6)(*)
抒情小曲集 から
春に寄す Op.43 No.6/小人の行進 Op.54
No.3/過ぎ去った日々 Op.57 No.1
夢想 Op.62 No.5/ゆりかごの歌 Op.68
No.5/小妖精 Op.71 No.3
ノルウェー舞曲集 Op.35 から Nos.2 &
3(+)
抒情小曲集 から
家路 Op.62 No.6/森の静けさ Op.71 No.4 |
アレッサンドロ・ステッラ(ピアノ)
ジョルジャ・ミラネージ(ソプラノ(*))
ジョルジャ・トマッシ(ピアノ(+)) |
|
録音:2010年4月
スイスのルガーノで開催される「マルタ・アルゲリッチ・プロジェクト」の常連となっているローマ生まれのピアニスト、アレッサンドロ・ステッラによるグリーグ。ジョルジャ・ミラネージはローマに生まれ1999年にオペラ・デビューしたソプラノ。
|
| |
|
|
|
アレッサンドロ・ドラーゴ・プレイズ・リスト&ドビュッシー
リスト(1811-1886):ピアノ・ソナタ ロ短調
ドビュッシー(1862-1918):前奏曲集第1巻 |
アレッサンドロ・ドラーゴ(ピアノ) |
|
録音:2010年4月
アレッサンドロ・ドラーゴは1956年ローマに生まれ、グイード・アゴスティ(1901-1989、マリア・ティーポの師)に師事したピアニスト。
|
BELLA GRERIT
|
アンサンブル・ベッラ・ジェリトの自主レーベル。 |
|
|
甘美な光景 フェデリーコ・ダ・モンテフェルトロの宮廷の音楽
ウルビーノ公の図書館の写本1411号所収のロンドーとバラード集(15世紀)
不詳:Bella gerit(*)
ジル・バンショワ(1400頃-1460):
Mon doulx espoir / Seulle egaree / Margarite,
fleur de valeur
Adieu, adieu
ヨハンネス・チコーニア(1373頃-1412):La
dolce vista
ギヨーム・デュファイ(1400頃-1474):Mon
cuer chant
ジル・バンショワ:Files a marier / Esclave
puist yl devenir
ギヨーム・デュファイ:Trop lonc temp
ジル・バンショワ:
Pour prison ne pour maladie / En sera
il mieux / Je ne fai tous jours
Vostre tres doulx regart
不詳:Faites de moy / Con dollia me ne
vo
ギヨーム・デュファイ:Se la face ay pale
ジル・バンショワ:Deul angoisseux
ジョン・ダンスタブル(1390頃-1453)/
ジョン・ベディンガム(1422頃-1459/1460):O
rosa bella
不詳:J'ay pris amour |
アンサンブル・ベッラ・ジェリト、
アンサンブル・ラウス・ヴェリス、
フィッファロ・コンソート
イラリア・セヴェーロ(歌)
シモーネ・ソリーニ(歌、リュート)
ダヴィド・モナッキ(歌、リュート、ビウエラ)
エネア・ソリーニ(歌、プサルテリウム、ナッカーラ、太鼓、タンバリン)
ジョルダーノ・チェッコッティ(ヴィオラ・ダ・ガンバ、リベカ、リベコーネ)
ダニエーレ・ベルナルディーニ(笛太鼓、ダブル・リコーダー、アルトバッソ、
リコーダー、ボンバルダ、クルムホルン)
アンゲリカ・モス(ポジティヴ・オルガン)
クリスティーナ・テルノヴェク(ヴィオラ・ダ・ガンバ、リベコーネ)
ニコラス・サンサルラト(リラ・ダ・ブラッチョ)
マウロ・モリーニ、ルイージ・ジェルミーニ(トロンボーン)
クリスティーナ・ベルナルディーニ(クルムホルン、リコーダー)
ジョヴァンニ・ブルニャーミ(クルムホルン、リコーダー、笛太鼓)
カッペッラ・ムジカーレ・サンティッシモ・サクラメント合唱団(*)
ピエルカルロ・フォンテマージ(合唱指揮(*)) |
録音:2005年10月10日、ドゥカーレ宮殿サーラ・カステッラーレ,2005年10月9、11、22日、聖ベルナルディーノ教会の公爵霊廟,2005年10月23-24日、ドゥカーレ宮殿宴会場,2005年11月24日、12月11日、カッペッラ・ムジカーレ・サンティッシモ・サクラメント,以上ウルビーノ、イタリア
イタリアの典型的なルネサンス君主の一人であるウルビーノ公フェデリーコ・ダ・モンテフェルトロ(フェデリーコ3世;1422-1482)の宮廷音楽を3団体合同で再現する試み。
ベッラ・ジェリトは主としてウルビーノ公国のルネサンス音楽レパートリーを演奏するために2005年イタリアのウルビーノで創設された声楽&ピリオド楽器アンサンブル。
ラウス・ヴェリスは中世・ルネサンス音楽を専門とする1999年イタリアのアッシジで創設された声楽&ピリオド楽器アンサンブル。
フィッファロ・コンソートは2002年に創設されたイタリアのルネサンス管楽器合奏団。 |
| |
|
|
カナの婚礼 ラファエロの時代のウルビーノの音楽
アドリアン・ヴィラールト(1490頃-1562):栄光の処女
[Virgo gloriosa]
アントワーヌ・ブリュメル(1460頃-1512/1513):
茨の中の百合のごとく [Sicut lilium inter
spinas]
ヨハンネス・ド・ラ・ファージュ(確認できる活躍期:1520頃):
ザカリアの妻エリザベト [Elisabeth Zachariae]
ジャン・ムトン(1459?-1522):
聖母は男を知らずして [Nesciens Mater
Virgo virum]
アンドレアス・デ・シルヴァ(1475/1480頃-1540頃):
イエスが語られていたその時 [In illo tempore
loquente Jesu]
ジョスカン・デ・プレ(1450/55頃-1521):森のニンフらよ
[Nymphes des bois]
アンドレアス・デ・シルヴァ:あなたは完璧に美しい
[Tota pulchra es]
ジャン・リシャフォール(1480頃-1547):
来たれ、キリストの花嫁 [Veni sponsa Christi]
ジャン・ムトン:
称えよ、ガリアの女王を [Exalta Regina
Galliae] /心と魂 [Corde et animo]
ルプス・ヘリンク(1493/1494-1541頃):
主よ、われらのために力の塔となりたまえ
[Esto nobis Domine, turris fortitudinis]
コンスタンツォ・フェスタ(1485/1490頃-1545):
バビロンの川のほとりで [Super flumina
Babilonis]
ジャン・ムトン:主よ、王を救いたまえ [Domine,
salvum fac regem
ピエール・ムリュ(1484?-1550頃):
あなたは私の心を奪った [Vulnerasti cor
meum]
ジャコタン(1440/1450-1529):
御身に請い願う、処女マリアよ [Rogamus
te Virgo Maria]
アドリアン・ヴィラールト:祝福されし使徒ヨハネは
[Beatus Johannes apostolus]
エリモ:カナで婚礼が行われた [Nuptiae factae
sunt]
ブリュネ:全世界に赴き [Ite in orbem universum]
ピエール・ムリュ:冷酷な死 [Fiere atropos] |
アンサンブル・ベッラ・ジェリト
シモーネ・ソリーニ(歌、リュート)
ダヴィド・モナッキ(歌、ビウエラ)
エネア・ソリーニ(歌、タンバリン)
アンゲリカ・モス(オルガン、ポジティヴ・オルガン)
アレッサンドロ・チョフィーニ、
マウロ・ボルジョーニ(歌)
ジョルダーノ・チェッコッティ(ヴィオラ・ダ・ガンバ)
ダニエーレ・ベルナルディーニ(ボンバルダ)
マッシモ・チャルフィ、
マウロ・モリーニ(トロンボーン) |
録音:2006年11月13-19日、ベネディクト会大天使聖ミカエル修道院、ラモーリ、ペルージャ県、イタリア
イタリア・ルネサンスを代表する画家ラファエロ(ラッファエッロ・サンティ;1483-1520)はウルビーノに生まれ、父も画家・詩人として仕えていたウルビーノ公の宮廷で画家としての活動を開始し、文人・芸術家たちと交流を深めました。
当盤は当時のウルビーノ公の宮廷での音楽を再現を試みたもので、古楽ファンのみならずルネサンス絵画ファンにもお勧めできます。 |
 CARPE DIEM CARPE DIEM
|
|
|
アンネ・ヒュッタ(1974-):夢の光景
Clouds(*)/ Undrestille I(+) / Undrestille
II(+) / Undrestille III(+)
Prelude in light blue(**) / A light blue
rondo(**) / Gorr(+) / Mork Bla(*)
Ramme(#) / A Rune Tune(#) / The Blind
Door(#) / Ved arinn(++)
En Stille(**) / Den Stille Hagen(**) |
アンネ・ヒュッタ(ハリングフェレ(*/+/#)、
ヴィオラ・ダモーレ(**)、
ヴィエール(++)) |
|
録音:2013年5月13-16日、マリア教会、グラン、ノルウェー
使用楽器、チューニング:
2001年、Salve Hakedal製、E-A-D-A-E(*)/1983年、Einar
Londar製、F-C-A-E(+)
2002年、Olav Vindal製、C-E♭-C-G-D(#)/2003年、Salve
Hakedal製、F-D-A-D(**)
1999年、Sverre Jensen製、E-D-A-E-A(++)
ノルウェーのハリングフェレ(ハルダンゲル・フィドル)奏者アンネ・ヒュッタの完全自作ソロ・デビューCD。冷涼な空気感とどこか素朴な生活感が漂う音楽です。ハリングフェレはノルウェーの民族的弓奏楽器。形はヴァイオリンに似ていますが、4本の演奏弦(最近は5弦のものもあり)に加え共鳴弦を持つのが特徴です。アンネ・ヒュッタは「Slagr」「Tokso」等のノルウェー民族楽器グループに参加してきた他、中世弦楽器のスペシャリストとして古楽器アンサンブル「カレンダ・マヤ」にも参加しています。
|
| |

CARPE 16302
\2100
|
ダヴィッド・シュヴァリエ ダウランド−鏡の戯れ
伝承曲/シェークスピア作詩/ダヴィッド・シュヴァリエ編曲:
柳の歌 [The Willow song]
ジョン・ダウランド(1563-1626):晴れても曇っても
[Clear or cloudy]
ジョン・ダウランド/ダヴィッド・シュヴァリエ編曲:
流れよ、わが涙 [Flow my tears]/彼女は許すだろうか
[Can she excuse]
来たれ、いま一度 [Come again]
ぼくは愛しい人が泣くのを見た [I saw my
lady weep]
さあ、おいで [Come away]
愛と運命にそむかれた君たち [All ye whom
Love or Fortune]
いちばん低い木にも [The lowest trees]
ジョン・ダウランド:暗闇に住まわせておくれ
[In darkness let me swell] |
アンヌ・マグエ(ソプラノ)
ダヴィッド・シュヴァリエ(ギター、テオルボ)
ブルーノ・ヘルストロッファー(テオルボ) |
|
録音:2013年2月、ノワルラック修道院、ブリュエール=アリシャン、フランス
フランスのジャズ・ギタリスト、ダヴィッド・シュヴァリエのアコースティック・アレンジによるダウランド・ソングブック。情熱を内に秘めた繊細なギター・プレイにヴォーカルが軽く応える、上品に仕上がったアルバムです。
|
 CONTINUO CONTINUO
|
イタリア、ローマの音楽マネージメント会社コンテンポアルス(Contempoars)のレコード・プロダクション部門が所有するレーベルです。 |
|
|
コレッリ:ソナタとフォリア Op.5
アルカンジェロ・コレッリ(1653-1713):ソナタ集
Op.5(1700)から 第1番ヘ長調
ベルナルド・パスクイーニ(1637-1710):トッカータ第8番ニ短調
アルカンジェロ・コレッリ:ソナタ集 Op.5
から 第11番変ロ長調
ベルナルド・パスクイーニ:トッカータ第4番イ短調「フランスのために」
アルカンジェロ・コレッリ:ソナタ集 Op.5
から 第3番ハ長調,第7番ト短調
ベルナルド・パスクイーニ:トッカータ第2番ヘ長調
アルカンジェロ・コレッリ:ソナタ集 Op.5
から
第4番ヘ長調,第12番ト短調「フォリア」 |
ラ・サンフォニー・デュ・マレ
ユーゴ・レーヌ(リコーダー、ディレクター)
ジェローム・ヴィダレ(チェロ)
マルク・ヴォルフ(アートリュート)
ヤニック・ヴァルレ(チェンバロ、オルガン) |
|
録音:2012年12月15日、ライヴ、サン・ルイージ・デイ・フランチェージ教会、ローマ、イタリア
コレッリのヴァイオリン・ソナタをリコーダーの名手ユーゴ・レーヌが演奏。コレッリとパスクイーニが同僚として活躍した場である、カラヴァッジョの祭壇画でも有名なサン・ルイージ・デイ・フランチェージ教会におけるライヴ録音です。
|
| |

CONTINUO-CR 101
(2CD)
\4200 |
ソロ 無伴奏オーボエのための音楽
[CD 1]
J・S・バッハ(1685-1750):パルティータ
イ短調 BWV1013
C・P・E・バッハ(1714-1788):ソナタ
イ短調 Wq.132
マラン・マレ(1656-1728):スペインのフォリア
テレマン(1681-1767):12の幻想曲 から
第2番 TWV40:3/第6番 TWV40:7/第8番
TWV40:9/第10番 TWV40:11
[CD 2]
ブルーノ・ベッティネッリ(1913-2004):協奏的練習曲(1977)
ブリテン(1913-1976):オヴィディウスによる6つのメタモフォーゼ
Op.49(1951)
ラッセ・ヤラヴァ(1951-):Pirpana Op.23
No.1(1993)
トム・ジョンソン(1939-):タイル・ワーク「3つの交差」(2003)
ボジダル・クンツ(1903-1964):舞曲 Op.62(1950)
ジョン・ラシュビー=スミス(1929-):
モノローグ(オーボエ/オーボエ・ダモーレのための)1970)
ロバート・シッビング(1929-):
4つの楽曲(オーボエまたはサクソフォンのための1986)
オイスタイン・ソンメルフェルト(1919-1994):ディヴェルティメント
Op.41(1974) |
マリカ・ロンバルディ(オーボエ) |
|
録音:2011年4月
フルート(バッハ父子、テレマン)、ヴィオラ・ダ・ガンバ(マレ)のために書かれたバロック音楽作品をディスク1に、20世紀に書かれたオーボエのためのオリジナル作品をディスク2に収録。ベッティネッリはイタリア、ヤラヴァはフィンランド、ジョンソンとシッビングはアメリカ合衆国、クンツはクロアチア、ラシュビー=スミスはイギリス、ソンメルフェルトはノルウェーの作曲家。マリカ・ロンバルディはミラノのG・ヴェルディ音楽院で学び1988年にデビュー、さらにパリで学んだイタリアのオーボエ奏者。
|
| |
|
|
フィルム・ノワール ガック、ヘフナー:ピアノ作品集
ジェイ・アンソニー・ガック(1955-):ソナタ第4番「フィルム・ノワール」(2004)
ポール・ヘフナー:水越しの3つの遠景(2006)
万年雪が溶けて激流に、別名「タニヤのための幻想曲」
水に浮かぶ睡蓮の葉の上で休む(…の前の静けさ)/津波
5?の平易な楽曲(2008)から 四度で楽しむ,アルバンのために
ジェイ・アンソニー・ガック:ソナタ第3番(1998)
ポール・ヘフナー:チックとマッコイ(2009)(*)
ジェイ・アンソニー・ガック:
ラウンドとラウンド・ダンス集(1997-2002)(*)
から
リング=ア=ラウンド(No.3)/プロセッショナル(No.4)
ウエスタン・ラウンド(No.5)
進め!(ピアノと弦楽のためのコンチェルティーノ;2011)(+) |
エリッツァ・ハルボヴァ(ピアノ)
ティツィアーノ・レオナルディ(ピアノ(*))
ピッコラ・オルケストラ '900(+)
シモーネ・ベッチア(指揮(+)) |
|
録音:2011年6月、11月
ジェイ・アンソニー・ガック、ポール・ヘフナーはともにアメリカ合衆国の作曲家。「フィルム・ノワール」とは「虚無的・悲観的・退廃的な指向性を持つ犯罪映画」のこと(Wikipediaによる)。
エリッツァ・ハルボヴァはイタリアを本拠に活躍するブルガリアのピアニスト。
|
| |
|
|
献呈 マトローヌ、カリガリス:フルート・ソナタ集
ダニエル・マトローヌ:フルート・ソナタ(2010)
セルヒオ・カリガリス(1941-):フルート・ソナタ(2009) |
マウロ・コンティ(フルート)
アレッサンドロ・ステッラ(ピアノ) |
|
録音:2012年3月
マウロ・コンティとアレッサンドロ・ステッラのデュオ結成10周年を祝ってフランスの作曲家ダニエル・マトローヌとアルゼンチンの作曲家セルヒオ・カリガリスが献呈した2作品の世界初録音。
|
| |
|
|
回想 ジョン・ダウランド&マルコ・ポエータ
ジョン・ダウランド(1563-1626):Flow my
tears(+/*)
マルコ・ポエータ(1957-):Time within
time(*)
ジョン・ダウランド:Come again(+/#)
マルコ・ポエータ:Ninna nanna(*) / Twiri(*)
ジョン・ダウランド:Sleep wayward thoughts(#)
マルコ・ポエータ:Cistels(*)
ジョン・ダウランド:Clear or cloudy(+/*)
マルコ・ポエータ:Serenata(*)
ジョン・ダウランド:Fine knacks for ladies(+/#/*)
ロバート・ジョンソン(1583頃-1634頃):
Have you seen but a bright lily grow?(+/#/*)
マルコ・ポエータ:Alle tre fontane(*)
ジョン・ダウランド:Say, love, if ever
thou didst find(+/*) |
マルコ・ポエータ(12弦ギター(*))
アレッサンドラ・ロザッコ(歌(+))
ニュー・ヴォーカル・アンサンブル(#) |
|
録音:2012年6月
イタリアのギタリスト、マルコ・ポエータによるジョン・ダウランドのリュート歌曲をベースとしたプロジェクト。ポエータはイタリア人ながらポルトガルのファドに傾倒し、ポルトガルギターの名手としても知られています。ここでは6つの演奏弦と6つの共鳴弦を持つ12弦ギターを演奏。アレッサンドラ・ロザッコはイタリアのファド・シンガー。
|
 DUX DUX
|
|
|
ペンデレツキ(1933-):室内楽作品集 Vol.1
クラリネットとピアノのための3つの小品
ヴァイオリン独奏のためのカデンツァ
ヨハネ・パウロ2世を記念するシャコンヌ(ヴァイオリンとヴィオラのための)
スラヴァのために(チェロ独奏のための)
ラドヴァンのための奇想曲(ホルン独奏のための)
クラリネット独奏のための前奏曲
クラリネット、ホルン、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロとピアノのための六重奏曲 |
ロマン・ヴィダシェク(クラリネット)
タデウシュ・トマシェフスキ(ホルン)
マリア・マホフスカ(ヴァイオリン)
アルトゥル・ロズミスウォヴィチ(ヴィオラ)
ヤン・カリノフスキ(チェロ)
マレク・シュレゼル(ピアノ) |
| |
|
|
ルトスワフスキ(1913-1994):弦楽四重奏曲(1964)
パヴェウ・ミキェティン(1971-):弦楽四重奏曲第2番(2006) |
ルトスワフスキ弦楽四重奏団
(ヤクプ・ヤコヴィチ、
マルチン・マルコヴィチ(ヴァイオリン)
アルトゥル・ロズミスウォヴィチ(ヴィオラ)
マチェイ・ムウォダフスキ(チェロ)) |
パヴェウ・ミキェティンはワルシャワのF・ショパン音楽アカデミー(現大学)でヴオジミェシュ・コトンスキ(1925-)に師事したポーランドの作曲家・クラリネット奏者。
ルトスワフスキ弦楽四重奏団はポーランドの奏者により2007年に結成されました。 |
| |
|
|
スラヴの二重唱曲集
モニュシュコ(1819-1872)、ダルゴムイシスキー(1813-1869)、
キュイ(1835-1918)、ドヴォルジャーク(1841-1904)の作品(全20曲) |
ウルシュラ・クリゲル(メゾソプラノ)
ヤドヴィガ・ラッペ(アルト)
マリウシュ・ルトコフスキー(ピアノ) |
| |
|
|
ドイツの二重唱曲集
メンデルスゾーン(1809-1847):
私は愛を伝えたい Op.63 No.1/渡り鳥の別れの歌
Op.63 No.2
あいさつ Op.63 No.3/民謡 Op.63 No.5/すずらんと花たち
Op.63 No.6
「ルイ・ブラス」からの歌 Op.77 No.3
シューマン(1810-1856):
田舎風の歌 Op.29 No.1/私が鳥になれたら
Op.43 No.1
美しい花々 Op.43 No.3/愛の痛み Op.74
No.3/幸福 Op.79 No.15
春の歌 Op.79 No.18
ブラームス(1833-1897):
恋の道 I Op.20 No.1/海 Op.20 No.3/姉妹
Op.61 No.1
現象 Op.61 No.3/響き I Op.66 No.1/響き
II Op.66 No.2
海辺で Op.66 No.3 |
ウルシュラ・クリゲル(メゾソプラノ)
ヤドヴィガ・ラッペ(アルト)
マリウシュ・ルトコフスキー(ピアノ) |
| |
|
|
リュート、私のお気に入り
チェーザレ・ネグリ(1535頃-1605頃):白い花
ヨアヒム・ファン・デン・ホーフェ(1567?-1620):トッカータ
不詳:ジグ(パッキントンのパウンド)
ラウレンチーニ・ディ・ローマ(1550以前より活躍-1608):前奏曲
ゲオルク・レオポルト・フールマン(1578-1616):ラ・ブレ
ピエール・アテニャン(1494頃-1551/1552):パヴァーヌ
フランチェスコ・ダ・ミラノ(1497-1543):ファンタジア
ルイス・デ・ナルバエス(1500頃-1555/1560):ファンタジア
不詳:無題作品
チェーザレ・ネグリ:スパニョレット
ヴォイチェフ・ドゥーゴライ(1557/1558-1619以後):フィナーレ
エンリケス・デ・バルデラバノ(1500-1557以後):ソネット
ハンス・ノイジードラー(1508頃-1563):ヴァシャ・メサ
不詳:グリーンスリーヴズ/前奏曲/この忠告には従えない
ジャン=バティスト・ブザール(1567頃-1617/1625頃):前奏曲
ヴィンチェンツォ・カピローラ(1474-1548以後):リチェルカーレ
ロベール・バラール:(1572/1575頃-1650以後):村のブランル |
イレネウシュ・トリブレツ(リュート)
|
| イレネウシュ・トリブレツはポーランドのリュート奏者。1985年に古楽アンサンブル「カメラータ・クラコヴィア」を創設しました。 |
| |

DUX 1106/1107
(2CD)
\2800 |
パスクアーレ・アンフォッシ(1727-1797):
オラトリオ「聖フィリッポ・ネーリの死」(1796) |
アンナ・ミコワイチク、イヴォナ・ホッサ(ソプラノ)
アグニェシュカ・レフリス(メゾソプラノ)
ラファウ・バルトミンスキ(テノール)
ポズナン室内合唱団
シンフォニア・ヴィーヴァ
トマシュ・ラジヴォノヴィチ(指揮) |
| ロンドン、ヴェネツィア、ローマで活躍したイタリア・オペラ作曲家パスクアーレ・アンフォッシが晩年に書いたオラトリオ。フィリッポ・ネーリ(1515-1595)はオラトリオ会の創始者として知られるイタリアの司祭・宣教師。 |
| |
|
|
ドビュッシー(1862-1918):ピアノ作品集
映像 第1集/ベルガマスク組曲/ピアノのために |
ピオトル・マフニク(ピアノ) |
| ピオトル・マフニクはクラクフ音楽アカデミーでステファン・ヴォイタスに師事し1999年に卒業したポーランドのピアニスト。その後ユージン・インディク(Eugene
Indjic)、ルドルフ・ブーフビンダーのもとで研鑽を積み、2004年のマリア・カナルス・バルセロナ国際音楽演奏コンクール・ピアノ部門で優勝しました。来日演奏歴もあります。 |
| |
|
|
アンジェイ・シェヴィンスキ(確認できる活躍期:1725頃):作品全集
めでたし天の元后 [Ave Regina caelorum]
(8声)
聖処女マリアの無原罪の懐胎の小聖務日課
死者のためのミサ(レクイエム) [Missa
pro defunctis (Requiem)] (9声) |
ディレット(古楽アンサンブル)
スコラ・グレゴリアーナ・サンクティ・カシミリ
アンナ・モニュシュコ(指揮) |
| その生涯に関する情報がほとんど伝わっていないポーランドの作曲家アンジェイ・シェヴィンスキの現存する全作品を収録。 |
| |
|
|
ギャリック・オールソンのシューベルト
シューベルト(1797-1828):
ピアノ・ソナタ第13番イ短調 Op.120 D.664(1819)
幻想曲ハ長調「さすらい人」Op.15 D.760(1822)
ピアノ・ソナタ第16番イ短調 Op.41 D.845(1825) |
ギャリック・オールソン(ピアノ) |
|
録音:2012年8月31日-9月2日、カロル・シマノフスキ音楽アカデミー・コンサートホール、カトヴィツェ、ポーランド
使用楽器:Steinway, D 572763
第8回ショパン国際ピアノ・コンクール優勝者ギャリック・オールソン(1948年生まれ)がポーランドでシューベルトを新録音。
|
| |

DUX0803
\2400 |
The Year in Italy
ファニー・メンデルスゾーン:ピアノ曲集
12ヶ月 フォルテピアノのための12の性格的小品、
ローマへの別れ、4つの歌曲Op.2より第3曲、
4つの歌Op.6より第2番「ローマのサルタレロ」 |
ジョアンナ・スチェレツカ=オルロフスカ(pf) |
| |

DUX0946
\2400 |
ヤナーチェク:室内楽曲集
弦楽のための牧歌、
2つのヴァイオリン ヴィオラ チェロ ストリングベースのための組曲、
4つのヴァイオリンのためのソネット第1番、
弦楽四重奏曲第1番「クロイツェルソナタ」弦楽合奏版 |
エルンスト・コヴァチッチ指揮、
ワルシャワ室内管弦楽団「レオポルトディヌム」 |
| |

DUX0971
\2400 |
シェドゥルツェのヨアヒム・ヴァーグナー製オルガン第2集
ベッルナルド・ストラーチェ:バッロデッラバッターリャ/
カベソン:パヴァーヌとグロサ/
ロッシ:トッカータ第7番/
J.S.バッハ:ようこそ恵み深きイエスよBWV.768/
ラインケン:フーガ ト短調/
クリスティアン・エアバッハ:カンツォン
ハ長調/
C.P.E.バッハ:ソナタWq.70-3/
フェリーチェ・モレッティ:ソナティナ ハ長調/
ツィポーリ:アル・ポスト・コムニオ/
パスクイーニ:トッカータとかっこうのスケルツォ/
ベッリーニ:ソナタ ト長調 |
イレネウシュ・ヴィルヴァ(Org) |
| |
|
|
ポーランドのチェロ音楽
ヴィトルト・ルトスワフスキ(1913-1994):
無伴奏チェロのためのザッハー変奏曲(1975)(*)
ズビグニェフ・ブヤルスキ(1933-):2つのチェロのためのアダージョ(2013)
ヘンリク・ヤブウォンスキ(1915-1989):3つのチェロのための三部作(1967)(AA)
アレクサンデル・タンスマン(1897-1986):
4つのチェロのための2つの楽章(1935)(KJ/MM)
クシシュトフ・メイエル(1943-):内省(5つのチェロのための;1960)(AA/KJ/FP)
マチェイ・ヤブウォンスキ(1974-):
コルディッシモ!(6つのチェロのための;2012)(MM/MD/MN/MG)
オルガ・ハンス(1961-):
太陽の歌(7つのチェロのための;1999)(MM/MD/MN/MG/AL)
クシシュトフ・ペンデレツキ(1933-):ポーランド・レクイエム
から アニュスデイ
(8つのチェロのための版;2007)(AA/KJ/MM/FP/MD/MN) |
ヤン・カリノフスキ(チェロ)
ベアタ・ウルバネク=カリノフスカ(チェロ(*以外))
アンナ・アマティス=ボレッリ(チェロ(AA))
カロリナ・ヤロシェフスカ(チェロ(KJ))
マルチン・モンチンスキ(チェロ(MM))
フランチシェク・パル(チェロ(FP))
ミハウ・ドンベク(チェロ(MD))
マルタ・ナガヴィエツカ(チェロ(MN))
モニカ・ゲルノト(チェロ(MG))
アレクサンドラ・レレク(チェロ(AL)) |
| |
|
|
ホ・ウォンスク ピアノ・リサイタル
フランク(1822-1890):前奏曲、コラールとフーガ
ロ短調
イ・コニョン(1947-):夏の光に [Sulla
luce dell'estate]
ラヴェル(1875-1937):クープランの墓
ラフマニノフ(1873-1943):コレッリの主題による変奏曲
Op.42 |
ホ・ウォンスク(ピアノ) |
| |
|
|
献呈 チェロとピアノのための21世紀ポーランド音楽
ズビグニェフ・ブヤルスキ(1933-):カルシュレズ
[KalSzlez] (2010)
マチェイ・ヤブウォンスキ(1974-):残念ながら、終わった…(2006)
バルトシュ・ハイデツキ(1980-):三人のジプシー(2007)
ヤロスワフ・プウォンカ(1984-):小声で歌う(2009)
マルツェル・ヒジンスキ(1971-):別れ(2013)
ヴォイチェフ・ヴィドワク(1971-):わが怒りのすべて(2013) |
ヤン・カリノフスキ(チェロ)
マレク・シュレゼル(ピアノ) |
| |
|
|
カップ・オブ・タイム・プレイズ・ナミスウォフスキ
ズビグニェフ・ナミスウォフスキ(1939-):
バグパイプ(パイパーズ・ダンス)(*)/二人のワルツ/シュマルツ・タンゴ
シロンスク民謡/ヴィトルト・ルトスワフスキ(1913-1994)編曲/
カップ・オブ・タイム編曲:求愛のダンス
ズビグニェフ・ナミスウォフスキ:7/4拍子
グラジナ・バツェヴィチ(1909-1969):クヤヴィアク(*)
ズビグニェフ・ナミスウォフスキ:クヤヴィアク・ゴーズ・ファンキー
クシシュトフ・レンチョフスキ(1986-):必ずしも踊らないわけではないタンゴ(*)
ズビグニェフ・ナミスウォフスキ:オーラル・ペースト
シロンスク民謡/ヴィトルト・ルトスワフスキ編曲/カップ・オブ・タイム編曲:
がちょう(*)
リシャルト・ボロフスキ:マゾベル(*)
ズビグニェフ・ナミスウォフスキ:3 by 4/マズルカ・ウボルカ |
カップ・オブ・タイム
(リシャルト・ボロフスキ(フルート)
アグニェシュカ・ツィプリク(ヴァイオリン)
ラファウ・グジョンカ(アコーディオン)
クシシュトフ・レンチョフスキ(チェロ))
ズビグニェフ・ナミスウォフスキ(サクソフォン(*)) |
| |
|
|
カストルム・ドローリス(悲しみの城) ポーランドの葬送音楽
[死者の送魂]
不詳:葬送行進曲(イントラーダ)
マチェイ・ヴロノヴィチ(1645頃-1700頃):深き淵より
[De profundis]
ピョトルクフ聖歌:ミゼレーレ第4旋法
不詳:カンツォーナ I
ダミアン・スタホヴィチ(1658頃-1699):死者のためのミサ(レクイエム)から
イントロイトゥス「レクイエム・エテルナム」/キリエ
ピョトルクフ聖歌:
レクツィオ/グラドゥアーレ「レクイエム・エテルナム」第2旋法
トラクトゥス「アブソルヴェ・ドミネ」第8旋法
ダミアン・スタホヴィチ:死者のためのミサ(レクイエム)から
セクエンツィア「ディエス・イレ」
ピョトルクフ聖歌:福音書朗唱
ダミアン・スタホヴィチ:死者のためのミサ(レクイエム)から
オフェルトリウム「ドミネ・イェズ」/サンクトゥス/アニュス・デイ
ピョトルクフ聖歌:コムニオ「ルクス・エテルナ:第8旋法
不詳(ヴィエトリス写本 から):カンツォーナ
II [カストルム・ドローリス]
ピョトルクフ聖歌:
レスポンソリウム「助けたまえ」 [Subvenite]
第1旋法
レスポンソリウム「ラザロは蘇りぬ」 [Qui
Lazarum] 第4旋法
レスポンソリウム「主よ、来たもう時」
[Domine, quando veneris] 第8旋法
レスポンソリウム「覚えたもうな」 [Ne
recorderis] 第5旋法
不詳:レソポンソリウム「リベラ・メ・ドミネ」
ピョトルクフ聖歌:アンティフォナ「イン・パラディムズ」第8旋法 [埋葬の行列]
ピョトルクフ聖歌:われは復活にして命なり
[Ego sum ressurectio et vita]
伝承曲/テレマン(1681-1767):
カンツォーナ III(「善きイエス」とテレマンのカンツォーナに基づく) |
ボルヌス・コンソート
(アンナ・ミコワイチク、マルタ・チャルコフスカ(ソプラノ)
カロル・バルトシンスキ(男性アルト)
マルチン・ボルヌス=シュチチンスキ、
ロベルト・ポジャルスキ(テノール)
ミロスワフ・ボルチンスキ(バリトン)
スタニスワフ・シュチチンスキ(バス))
テンプス四重唱団
(バルバラ・トゥマノヴィチ、エヴェリカ・クシフカ(ソプラノ)
アグニェシュカ・ドロンジチク(アルト)
アンドレイ・ボジム・Jr(テノール)
レシェク・クビャク(バス))
ゴルチツキ・サルマティア合唱団
スコラ・グレゴリアーナ・シレジエンシス
コンチェルト・アンテムラーレ(古楽器アンサンブル)
レシェク・フィレク(第1ヴァイオリン)
ユスティナ・スカトゥルニク(第2ヴァイオリン)
イゴル・ツェツォホ、
ヤツェク・ユルコフスキ(トランペット)
ミハウ・サヴィツキ(ポジティヴ・オルガン))
ペストの時代のオーケストラ
(パヴェウ・イヴァシュキェヴィチ(テナー・ドゥルツィアン、グレートボック)
マチェイ・カジンスキ(バス・ドゥルツィアン、
グレートボック、
バロックドラム))
ロベルト・ポジャルスキ(カントル、総指揮) |
|
録音:2013年11月10日、ライヴ、聖バルトゥオミェイ教会、ヴロツワフ、ポーランド
「カストルム・ドローリス」という独特の構成を含むポーランド貴族の葬儀の音楽を再現する試み。ポーランドの作曲家ダミアン・スタホヴィチはトランペットを好んだと言われており、収録されたレクイエムでも所々で鳴り響いています。
|
| |
|
|
ムジカ・サクロモンターナ
ヨゼフ・シュナーベル(1767-1831):
ミサ変イ長調(1806)(*)
ギター、2つのヴァイオリン、ヴィオラとチェロのための五重奏曲(+) |
エヴァ・ビェガス(ソプラノ)
エヴァ・マルツィニェツ(メゾソプラノ)
クリスティアン・クシェショヴャク(テノール)
グジェゴシュ・ピオトル・コウォジェイ(バリトン)
ダルムシュタット・コンサート合唱団
ベートーヴェン・アカデミー管弦楽団
ヴォルフガング・セーリガー(指揮) 以上(*)
カロル・リピンスキ・アンサンブル(+)
(アンジェイ・ワドミルスキ(第1ヴァイオリン)
ヨアンナ・ワドミルスカ(第2ヴァイオリン)
ダリウシュ・ヴォウチク(ヴィオラ)
ウルシュラ・マルツィニェツ=マズル(チェロ)
ピオトル・ザレスキ(ギター)) |
| ヨゼフ・シュナーベルは現ポーランドのシロンスク(シレジア)地方に生まれ活躍した作曲家。モダーン楽器使用。 |
| |
|
|
トランペット・ソング
スワヴォミル・ツィホル(1978-):ゼファー
[Zephyr](*)
クシシュトフ・グジェシュチャク(1965-):カンティレーナ(*/#)
エリック・モラルズ(1966-):2つのトランペットのための協奏曲(+)
ジョゼフ・トゥリン(1947-):悲歌
エリック・イウェイゼン(1954-):バラード・フォー・セレモニー(#)
クシシュトフ・グジェシュチャク:トランプジャズピアノ
[Trumpjazzpiano](*)
ジェイムズ・スティーブンソン(1969-):リメンバー・フォワード
エリック・イウェイゼン(1954-):ア・ソング・フロム・ハート
スワヴォミル・ツィホル:コルヌ [Cornu](*)
(*)世界初録音。 |
スワヴォミル・ツィホル(トランペット)
リチャード・ストルゼル(トランペット(+))
マルタ・マチェジンスカ(ピアノ)
アレクサンドラ・ナヴェ(ピアノ(#)) |
| |
|
|
韓国の声
David Wikander: Kung Liljekonvalje
Jan Sandstrom: Gloria
Jaakko Mantyjarvi: Pseudo-Yoik
Vytautas Miskinis: Laudate pueri, Dominum
Cesar Alejandro Carrillo: Ave Maria
Joseph Gabriel Rheinberger: Abendlieb
Robert Schumann: Schon ist das Fest des
Lenzes
Morten Lauridsen: Sure on this Shining
Night
Thomas Jennefelt: Warning to the Rich
Heung-Yeol Lee, Jun-Bum Kim (arr.): Child
of the Island House
Hye-Young Cho: Forget Not
Korean Traditional Folk Song, arr. Byung-Hee
Oh: Koesina Ching-Ching
Korean Traditional Folk Song, arr. Hye-Young
Cho: Ongheya |
韓国国立合唱団
イ・サンフン(指揮) |
| |

DUX 1119/1120
(2CD)
\2800 |
ダリウシュ・プシビルスキ(1986-):
12声の受難曲
(ヨハネの福音書によるわれらの主イエス・キリストの受難と死;2013)
…そして死を待ち望む… [...et desiderabunt
mori...] (12声;2008)
ミゼレーレ(12声;2008) |
ゾリステンアンサンブル・フェニックス16
ティモ・クロイザー(指揮) |
| |
|
|
パトリツィア・ピェクトフスカ
ブラームス(1833-1897):ヴァイオリン・ソナタ第3番ニ短調
Op.108
フランク(1822-1890):ヴァイオリン・ソナタ
イ短調 |
パトリツィア・ピェクトフスカ(ヴァイオリン)
アンナ・ミェルニク(ピアノ) |
パトリツィア・ピェクトフスカ(1976年生まれ)はタデウシュ・ガジナ(ワルシャワのF・ショパン音楽アカデミー)、イーゴリ・オイストラフ(ブリュッセル王立音楽院)に師事したポーランドのヴァイオリニストで、当レーベルの主力アーティストの一人。

|
 ESTUDIO GLB ESTUDIO GLB
|
ヴァイオリニストのルドミラ・ヴィネツカーとチェリストのアントニオ・ゲラ・ヴィセンテが1999年ブラジルの首都ブラジリアに創設した音楽スタジオ「スタジオ(エストゥジオ)GLB」が制作するレーベル。
30を超えるCDをリリースしていますが、扱えるのは4タイトルのみ。在庫限定となります。 |
|
|
ブラジル 500
エンリケ・オズワルド(1852-1931):ピアノ五重奏曲(*)
ルイス・デ・フレイタス・ブランコ(1890-1955):弦楽四重奏曲 |
ルイス・デ・ムーラ・カストロ(ピアノ(*))
ブラジリア弦楽四重奏団
ルドミラ・ヴィネツカー(第1ヴァイオリン)
クラウディオ・コーエン(第2ヴァイオリン)
グレス・コレト(ヴィオラ)
アントニオ・ゲラ・ビセンテ(チェロ) |
|
録音:1999年1月、スタジオGLB、ブラジリア、ブラジル
おそらくポルトガル人によるブラジル発見(西暦1500年)500周年を記念したタイトル。
エンリケ・オズワルドはブラジルのリオデジャネイロに生まれた作曲家・ピアニスト・教育者・外交官。父はドイツ系スイス人、母はイタリア人。イタリア、フランスで学び、リオデジャネイロ国立音楽学校長を務めました。ルイス・デ・フレイタス・ブランコはポルトガルの作曲家。
■ブックレット、インレイカードにスレや歪みがございます。ご了承ください。(輸入元代理店)
|
| |
|
|
国民主義者
オズワルド・ラセルダ(1927-2011):弦楽四重奏曲第1番(1952)
ジョゼ・ゲラ・ヴィセンテ(1906-1976):弦楽四重奏曲「民衆の四重奏曲」(1963) |
ブラジリア弦楽四重奏団
ルドミラ・ヴィネツカー(第1ヴァイオリン)
クラウディオ・コーエン(第2ヴァイオリン)
グレス・コレト(ヴィオラ)
アントニオ・ゲラ・ビセンテ(チェロ) |
オズワルド・ラセルダはブラジルのサンパウロに生まれ、カマルゴ・グアルニエリ(1907-1993)に師事、さらにアメリカ合衆国に留学しアーロン・コープランドらに師事した作曲家・ピアニスト。サンパウロ音楽学校教授、国家教会音楽委員会顧問等を務めました。
ジョゼ・ゲラ・ヴィセンテはポルトガルに生まれ、10歳の時に家族とともにブラジルに移住、リオデジャネイロで音楽教育を受けた作曲家・チェロ奏者。リオデジャネイロ市立劇場交響楽団の創設者であり、ヴィラ=ロボスの「ブラジル風バッハ第1番」の初演にも参加しました。 |
| |
|
|
ブラジル音楽シリーズ Vol.10
ジョゼ・ゲラ・ヴィセンテ(1906-1976):室内楽&声楽作品集
カリオカの情景 [Cenas Cariocas] (チェロとピアノのための;1961)(+)
セレナード弾きのワルツ [Valsa seresteira]
カンティガ [Cantiga]/ショーロ [Choro]
悲歌 [Elegia] (チェロとピアノのための;1932)(+)
糸杉 [Ciprestes] (歌、ヴァイオリン、チェロとピアノのための;1936)(*/#/+)
ピアノ伴奏歌曲(*)
ソネット [Soneto] (1941)/すみれ
[Violeta] (1948)
ある田舎のパン屋 [Certo padeiro da roca]
(1949)
深い霧 [Brumas] (1950)/イベリアの歌
[Cantar Iberico](1951)
リンダ・イネスは… [Estavas, Linda Ines,
...](1956)
バンゾ [Banzo](1965)/ジャナイナ [Janaina](1965)
チェロ・ソナタ(1940)(+) |
ロゼ・ジ・ソザ(ソプラノ(*))
ルドミラ・ヴィネツカー(ヴァイオリン(+))
ライフ・ダンタス・バヘト(チェロ(#))
マルコス・アラゴニ(ピアノ) |
| 録音:2009年1月、スタジオGLB、ブラジリア、ブラジル |
| |
|
|
ブラジル音楽シリーズ Vol.12
ジョゼ・ゲラ・ヴィセンテ(1906-1976):ブラジリア交響曲 |
GLBフィルハーモニー交響楽団
クラウディオ・コーエン(指揮) |
録音:2009年10月14日、マルティンス・ペナ・ホール、ブラジリア、ブラジル
※収録時間34分15秒ですがフルプライスですのでご注意ください。 |
HUGO VASCO REIS
|
|
|
ウゴ・ヴァスコ・レイス ポエマ・アナクロニコ(時代遅れの詩)
アントニオ・ヴィクトリノ・ダルメイダ(1940-):
トッカータ、幻想曲とソナティナ(ポルトガルギターとピアノのための)Op.133(*)
ウゴ・ヴァスコ・レイス(1981-):ポルトガルギター独奏のための組曲
Op.4
前奏曲/ロマンス/インヴェンション/幻想曲
カルロス・セイシャス(1704-1742):
ソナタ ハ短調 K.14(+)/ソナタ ロ短調
K.80(+)/ソナタ ホ短調 K.37(+) |
ウゴ・ヴァスコ・レイス(ポルトガルギター)
カンディド・フェルナンデス(ピアノ(*))
フィリパ・メネゼス(ヴィオラ・ダ・ガンバ(+)) |
|
録音:2013年、リスボン音楽院小コンサートホール、リスボン、ポルトガル
ポルトガルギター奏者ウゴ・ヴァスコ・レイスの自主制作によるデビューCD。ウゴ・ヴァスコ・レイスは1981年リスボンに生まれ、ポルトで土木工学を修めた後ポルト・ジャズ学校でジャズ・ギターと音楽理論を学ぶと同時にポルト音楽院でカルロス・ジェズスとヌノ・ディアスにポルトガルギダーを師事、さらにペドロ・カルデイラ・カブラルとサムエル・カブラルのプライヴェート・クラスで学びました。
また、和声と対位法をジョアン・エイトル・リガウドに学び、アントニオ・ピニョ・ヴァルガスの作曲セミナーにも参加。2014年現在ポルトガル国内各地で演奏活動を行いながらリスボン音楽院で作曲を学んでいます。
彼を高く評価しているアントニオ・ヴィクトリノ・ダルメイダのオリジナル作品、自身のソロ作品、そして師ペドロ・カルデイラ・カブラル譲りのポルトガルギター版セイシャスで構成されたプログラム。収録時間こそ41分弱と短いながらその内容の充実ぶりに驚かされます。
本体・外装に規格品番表記がございませんが、弊社(代理店)では「REIS
1」として管理いたします。
|
 IBS CLASSICAL IBS CLASSICAL
|
|
|
彫刻 サクソフォンとピアノのための音楽
フランセ(1912-1997):
主題と変奏曲(原曲:クラリネットと管弦楽またはピアノのための;1974)
シューマン(1810-1856):
3つの幻想小曲集 Op.73(原曲:クラリネットと管弦楽またはピアノのための)
J・S・バッハ(1685-1750):
ソナタ ホ長調 BWV1016(原曲:ヴァイオリンとチェンバロのための)
ヒンデミット(1895-1963):ソナタ Op.11
No.4(原曲:ヴィオラとピアノのための;1919)
ドビュッシー(1862-1918):アラベスク第1番(原曲:ピアノのための)
ファリャ(1876-1946):7つのスペイン民謡(原曲:歌とピアノのための;1914) |
アニマ・デュオ
マリアノ・ガルシア(サクソフォン)
アニアナ・ハイメ・ラトレ(ピアノ) |
| 6人の作曲家の「音の彫刻」にサクソフォンで新たな彩色を施そうという趣旨のアルバム。マリアノ・ガルシアはマドリード王立音楽院で学んだサクソフォン奏者。 |
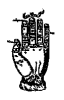 LA MA DE GUIDO LA MA DE GUIDO
|
|
|
愛の挨拶 ヴァイオリンとピアノのための名曲集
エルガー(1857-1934):愛の挨拶 Op.12
サラサーテ(1844-1908):序奏とタランテッラ
Op.43/サパテアド Op.43
ドヴォルジャーク(1841-1904)/クライスラー編曲:
スラヴ舞曲 Op.46 No.2/スラヴ舞曲 Op.72
No.2
ヘンリク・ヴィエニャフスキ(1835-1880):
スケルツォ・タランテッラ Op.16/華麗なポロネーズ
Op.21 No.2
2つのヴァイオリンのためのサルタレッロ
Op.18
グリーグ(1843-1907)/エミール・ソーレ(1852-1920)編曲:
朝露 Op.4 No.2/君を愛す Op.5 No.3/詩人の心
Op.5 No.2
森の散歩 Op.18 No.1
J・S・バッハ(1685-1750):
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第3番
BWV1006 から 前奏曲
クライスラー(1875-1962):愛の悲しみ/美しきロスマリン/愛の喜び
メンデルスゾーン(1809-1847)/ジョゼフ・アクロン(1886-1943):
歌の翼に Op.34 No.2
リムスキー=コルサコフ(1844-1908):くまばちの飛行 |
アーラ・ヴォロンコヴァ(ヴァイオリン)
ゲラシム・ヴォロンコフ(ピアノ) |
|
録音:2013年12月、スタジオ OIDO SL、バルセロナ、スペイン
アーラ・ヴォロンコヴァはウクライナのキエフに生まれ、モスクワ音楽院とグネーシン音楽大学で学んだヴァイオリニスト。ボリショイ劇場管弦楽団員を務めた後1991年にバルセロナに移住し、2014年現在バルセロナ交響楽団のソリスト兼リーダー、リセウ大劇場交響楽団のゲスト・リーダーを務めています。使用楽器は1600年イタリアのブレシアにてジオ・パオロ・マッジーニ(1580頃-1630頃)製(モダーン仕様)。
ゲラシム・ヴォロンコフはモスクワに生まれ、モスクワ音楽院で学んだ指揮者・ヴァイオリニスト・ピアニスト。1981年から1990年までボリショイ劇場管弦楽団員。1988年にボリショイ室内管弦楽団を創設。1991年にアーラ・ヴォロンコヴァと共にバルセロナに移住し、2014年現在リセウ音楽院教授および同交響楽団指揮者、リセウ大劇場交響楽団指揮者を務めています。
|
 MPMP MPMP
|
|
|
セルジオ・アヴェゼド(1968-):動物たちの謎々 児童合唱作品集
9つの易しい歌 [9 Cancoes Fraceis]
(民間の口上と早口言葉による;全8曲;2009)
ぼくの庭の歌 [Cancoes so meu Quintal]
(セルジオ・アヴェゼドのテキストによる;全12曲;2010)
動物たちの謎々 [A Charada da Bicharada]
(アリセ・ヴィエイラの詩集による;全14曲;2010)
ジョアンの眠り [O Sono do Joao]
(アントニオ・ノブレの同名の詩による2声のカンタータ;2008)(*)
怖い動物たち [Bichos de Arrepiar]
(セルジオ・アヴェゼドのテキストによる18の歌;2008)から
ティラノサウルス・レクス [Tyrannosaurus
Rex] |
ヴォクシミニ合唱団(児童合唱)
ヴォクシミクス合唱団(児童合唱(*))
ヌノ・ミゲル・フレイタス(ピアノ)
アルマンダ・パトリシオ(指揮) |
|
録音:2013年、シネ=テアトロ・アヴェニダ、カステロ・ブランコ、ポルトガル
セイシャスのシリーズをリリースしている「メログラフィア・ポルトゥゲザ・コレクション」とは別の「ベンジャミン・コレクション(coleccao
benjamin)」からの発売。セルジオ・アヴェゼドはポルトガルのコインブラに生まれ、フェルナンド・ロペス=グラサ(1906-1994)他に師事した作曲家。
|
| |
 

MPMP-HISTORIAS
(CD + BOOK)
\3800 →\3490 |
ポルトガルの音楽の歴史
ドン・ディニス[ポルトガル国王ディニス1世](1261-1325):
Pois que vos Deus, amigo, quer guisar
ゴンサロ・ピント・ゴンザルヴェス(テノール)
ヌノ・トルカ・ミランダ(リュート) マヌエル・ペドロ・フェレイラ(指揮)
原盤:MU Records / Arte das Musas /
Cesam, 2008
ドゥアルテ・ロボ(1565?-1646):Auvidi
vocem de coelo
アルス・ノヴァ(合唱) ボー・ホルテン(指揮) 原盤:Naxos,
1995
不詳(17世紀):Sa qui turo zente pleta
キングス・シンガーズ ラルペッジャータ
クリスティーナ・プルハル(指揮) 原盤:Naive,
2007
ピエトロ・ジョルジョ・アヴォンダノ(18世紀):
交響曲ヘ長調 から 第1楽章(アレグロ)
ディヴィーノ・ソスピロ エンリコ・オノフリ(指揮)
原盤:Dymanic. 2011
カルロス・セイシャス(1704-1742):
ソナタ ニ長調 K.20 から 第1楽章(アレグロ)(*)
ソナタ ニ短調 K.25 から 第2楽章(アダージョ)(+)
ジョゼ・カルロス・アラウジョ(オルガン(*)、チェンバロ(+))
原盤:MPMP, 2012
ニッコロ・ピッチンニ(1728-1800):
オペラ「迫害された匿名の女」から Pastorelle
anch'io con voi
ジョアナ・セアラ(ソプラノ) オス・ムジコス・ド・テジョ
マルコス・マガリャンイス(指揮) 原盤:Os
Musicos do Tejo, 2008
フランシスコ・アントニオ・デ・アルメイダ(1702?-1755?):
カンタータ「A quel leggiadro volto」から
Lascia per un momento
ジェンマ・ベルタニョッリ(ソプラノ) ディヴィーノ・ソスピロ
エンリコ・オノフリ(指揮) 原盤:Dymanic.
2011
マルコス・ポルトゥガル(1762-1830):オペラ「移り気な女たち」
序曲
シティ・オブ・ロンドン・シンフォニア アルヴァロ・カスト(指揮)
原盤:Marco Polo (Naxos), 2000
ジョアン・ドミンゲス・ボンテンポ(1775-1842):
レクイエム「カモンイスの記念に」Op.23
から キリエ
(旧東)ベルリン放送合唱団&交響楽団
ハインツ・レーグナー(指揮) 原盤:Portugalsom,
1982
交響曲第1番 から 第4楽章(プレスト)
アルガルヴェ管弦楽団 アルヴァロ・カスト(指揮)
原盤:Naxos, 2004
ジョアン・ギリェルメ・ダッディ(1813-1887):華麗な幻想曲(抜粋)
ドゥアルテ・ペレイラ・マルティンス(ピアノ
[Grotrian Steinweg, 1876])
原盤:MPMP, 2013 (未発売音源)
アルフレド・ケイル(1850-1907):オペラ「ア・セラナ」序曲
ポルトガル国営放送交響楽団 フェルナンド・カブラル(指揮)
原盤:ポルトガル放送 (未発売音源)
ジョゼ・ヴィアナ・ダ・モッタ(1868-1948):
交響曲「祖国」から 第4楽章(アンダンテ・ルグーブレ)(抜粋)
ハンガリー国立交響楽団 マーチャーシュ・アンタル(指揮)
原盤:Portugalsom, 1990
ルイス・デ・フレイタス・ブランコ(1890-1955):人工の楽園(抜粋)
アイルランド国営放送交響楽団 アルヴァロ・カスト(指揮)
原盤:Naxos, 2009
ルイ・コエリョ(1889-1986):バレエ「鉄の靴をはいたお姫様」(抜粋)
ポルトガル国営放送交響楽団 シルヴァ・フェレイラ(指揮)
原盤:Portugalsom. 1988/2008
フェデリコ・デ・フレイタス(1902-1980):愚かな少女の踊り(抜粋)
ロイヤル・スコティッシュ・ナショナル管弦楽団
アルヴァロ・カスト(指揮) 原盤:Naxos,
2013
ジョリ・ブガラ・サントス(1924-1988):
交響曲第5番「ヴィルトゥス・ルジタニエ」から
第4楽章(アレグロ)(抜粋)
ポルトガル交響楽団 アルヴァロ・カスト(指揮) 原盤:Naxos,
1998
フェルナンド・ロペス=グラサ(1906-1994):
Os homens que vao p'ra guerra
リスボン・カンタト室内合唱団 クララ・アルコビア・コエリョ(指揮)
原盤:MU Records / Arte das Musas /
Cesam, 2008
ジョルジェ・ペイシニョ(1940-1995):Floreal(抜粋)
リスボン現代音楽グループ ジャン=セバスティアン・ベロー(指揮)
原盤:La Ma de Guido, 2010
コンスタンサ・カプデヴィレ(1937-1992):リベラ・メ(抜粋)
グルベンキアン合唱団 オプス・アンサンブル
ジョルジェ・マッタ(指揮) 原盤:Portugalsom,
1991 |
マリオ・ジョアン・アルヴェス著・マダレナ・マトゾ画によるポルトガルの子供向けポルトガル音楽史入門絵本(もちろんポルトガル語のみ)にCDが付いたハードカバーブックCD。
本体・外装に規格品番表記がございませんが、弊社(代理店)では「MPMP-HISTORIAS」として管理いたします。 |
  MU RECORDS MU RECORDS
|
|
|
ラクリメ #1
不詳(1539、ストラスブール)/クレマン・マロ(1496-1544)詩/
ロジェ・シャパル(1912-)(詩のモダナイス;1992)/
セテ・ラグリマス(アダプテーション):
主よ、わが祈りを聴きたまえ [Seigneur,
ecoute ma priere]
ジョヴァンニ・バッティスタ・マルティーニ(1706-1784):
オリーヴ山で [In monte Oliveti]
アルカンジェロ・コレッリ(1653-1713):教会ソナタ
Op.7 No.3(1689、ローマ)
ジョヴァンニ・バッティスタ・マルティーニ:
われらは御身を拝む [Adoramus te Christe]
ハインリヒ・シュッツ(1585-1672):
聴きたまえ、われ呼ぶとき [Erhore mich,
wenn ich rufe] SWV289
不詳(1562、ジュネーヴ)/テオドール・ド・ベーズ(1519-1605)詩/
ロジェ・シャパル(詩のモダナイス;1992)/
セテ・ラグリマス(アダプテーション):
汝の山に彼は彼の王国を築いた [Sur ta
montagne il a fonde son regne]
ジョヴァンニ・バッティスタ・マルティーニ:
わが魂は悲しむ [Tristis est anima mea]
不詳(1562、ジュネーヴ)/テオドール・ド・ベーズ(1519-1605)詩/
ロジェ・シャパル(詩のモダナイス;1992)/
セテ・ラグリマス(アダプテーション):
おお!それは美しいもの [Oh! que c'est
chose belle]
ハインリヒ・シュッツ:
おお、助けたまえ、神の御子キリストよ
[O hilf, Christe Gottes Sohn] BWV295
アルカンジェロ・コレッリ:教会ソナタ Op.6
No.3(1689、ローマ)
ハインリヒ・シュッツ:
われは一つのことを主に頼む [Eins bitte
ich vom Herren] SWV294
おお、愛する主なる神よ [O lieber Herre
Gott] SWV287 |
セテ・ラグリマス
フィリペ・ファリア、
セルジオ・ペイショト(テノール、ディレクター)
イネス・モス・カルダス、
マルコ・マガリャンイス(リコーダー)
ケネス・フレイザー(ヴィオラ・ダ・ガンバ)
アンドレ・バホゾ(テオルボ) |
|
録音:2007年1月、リスボン、ポルトガル
ポルトガルのテノール歌手フィリペ・ファリアにより2000年にリスボンで創設されたアンサンブル「セテ・ラグリマス」(「7つの涙」の意)のデビューCD。16世紀終わりから17世紀の文学と音楽における「涙(Lacrimae)」をテーマとしたプログラムです。アダプテーションとは既存の旋律に歌詞をあてはめ歌曲を作り上げること。
|
| |
|
|
クライネ・ムジーク
ハインリヒ・シュッツ(1585-1672):
神よ、急ぎわれを助けたまえ [Eile mich,
Gott, zu erretten] SWV282
アイヴァン・ムーディ(1964-):師よ、われらは夜通し働きぬ
[Meister, wir haben die ganze Nacht
gearbeitet] (2007)
ハインリヒ・シュッツ:主を畏れることは
[Die Furcht des Herren] SWV318
アイヴァン・ムーディ:主よ、われは望む
[Herr, ich hoffe darauf] (2007)
ハインリヒ・シュッツ:おお、慈悲深きイエス
[O Misericordissime Jesu] SWV309
アイヴァン・ムーディ:わが魂は萎え [Anima
mea liquefacta est] (2007)
ハインリヒ・シュッツ:師よ、われらは夜通し働きぬ
[Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet]
SWV317
アイヴァン・ムーディ:
言葉は肉となり [Verbum caro factum est]
(2声のための;2007)
ハインリヒ・シュッツ:主よ、われは望む
[Herr, ich hoffe darauf] SWV312
アイヴァン・ムーディ:
神よ、急ぎわれを助けたまえ [Eile mich,
Gott, zu erretten] (2007)
ハインリヒ・シュッツ:
汝ら聖徒らよ、主をほめ歌え [Ihr Heiligen,
lobsinget dem Herren] SWV288
アイヴァン・ムーディ:おお、慈悲深きイエス
[O Misericordissime Jesu] (2007)
ハインリヒ・シュッツ:
主によりて汝の喜びをなせ [Habe deine
Lust an dem Herren] SWV311
アイヴァン・ムーディ:
主を畏れることは [Die Furcht des Herren]
(2声のための;2007)
ハインリヒ・シュッツ:言葉は肉となり [Verbum
caro factum est] SWV314
アイヴァン・ムーディ:
汝ら聖徒らよ、主をほめ歌え [Ihr Heiligen,
lobsinget dem Herren] (2007)
ハインリヒ・シュッツ:
わが魂は萎え [Anima mea liquefacta est]
SWV263
われは汝らに誓う、エルサレムの娘らよ
[Adjuro vos, filiae Hierusalem] SWV264
アイヴァン・ムーディ:
主によりて汝の喜びをなせ [Habe deine
Lust an dem Herren] (2007) |
セテ・ラグリマス
フィリペ・ファリア(テノール、ディレクター)
セルジオ・ペイショト(テノール、チェンバロ、ディレクター)
アナ・キンタンス(ソプラノ)
イネス・モス・カルダス、
ペドロ・カストロ(リコーダー)
ケネス・フレイザー(ヴィオラ・ダ・ガンバ)
ダンカン・フォクス(ヴィオローネ)
ウゴ・サンシェス(テオルボ) |
|
録音:2007年10、12月、フロンテイラ宮殿および古楽アカデミー、リスボン、ポルトガル
シュッツの「クライネ・ガイストリッヒェ・コンツェルテ」(SWV282-337)(SWV263,
264のみ「シンフォニエ・サクレ」第1巻)と、1990年以来ポルトガル在住のイギリス人作曲家アイヴァン・ムーディが同じテキストに同様の編成で作曲した楽曲で構成されたプログラム。
|
| |
|
|
ディアスポラ.pt
クロード・グディメル(1514?-1572)/不詳(16世紀ポルトガル)詩:
Triste vida vivye
(ヴィランシコ/原曲:詩篇「La terre
au Seigneur appartient」)
マカオ伝承:Bastiana
ジョアキム・アントニオ・ダ・シルヴァ(1848-1880):
Flor amorosa(ブラジルのショリーニョ)
不詳(16世紀ポルトガル):Sehnora del mundo(ヴィランシコ)
不詳(17世紀ポルトガル):Ola zente que
aqui samo(ヴィランシコ)
ティモール伝承:Mai fali e
ディエゴ・オルティス(1510-1570)/不詳(16世紀ポルトガル)詩:
Na fomte esta Lianor
(ヴィランシコ/原曲:レセルカダ第2番
[Recercada Segunda])
不詳(18/19世紀、ポルトガル/ブラジル):Menina
voce que tem(ルンドゥン)(*)
ガスパル・フェルナンデス(1565?-1629、メキシコ):Xicochi
conetzintle
インド、ゴア伝承:Farar far
ダミアン・デ・ゴイス(1502-1574、ポルトガル):苦難の日に
[In die tribulationis]
不詳(16世紀ポルトガル):Soledad tenguo
de ti(ヴィランシコ)
フアン・デ・アンチエタ(1462-1523、スペイン):Con
amores la mi madre
不詳?/エウジェニオ・タヴァレス(1867-1930、カボヴェルデ)詩:
A forca de cretcheu(モルナ)
不詳(17世紀ポルトガル):Ola plimo Baciao(黒人のヴィランシコ)
マヌエル・マシャド(1585?-1646):Es tus
brazos una noche |
セテ・ラグリマス
フィリペ・ファリア、
セルジオ・ペイショト(歌、打楽器、ディレクター)
ロザ・カルデイラ(歌)
イネス・モス・カルダス(リコーダー)
デニス・ステツェンコ(バロックヴァイオリン)
エウリコ・マシャド(ポルトガルギター)
ウゴ・サンシェス(テオルボ、リュート、ビウエラ)
ティアゴ・マティアス(バロックギター、ロマンティックギター、テオルボ)
ダンカン・フォクス(ヴィオローネ)
フェルナンド・マルコス・ゴメス(打楽器) |
|
録音:2008年4月、聖カタリナ教会、リスボン、ポルトガル
ポルトガルの「ディアスポラ」(祖国を離れ他国に住む者)、すなわちポルトガル植民地居住者たちにまつわる音楽をテーマとするアルバム。
(*)以外すべてフィリペ・ファリア&セルジオ・ペイショト編曲。南国的な雰囲気があります。
|
| |
|
|
静寂
アイヴァン・ムーディ(1964-):Genesis
I-III
アンドルー・スミス(1970-):Lamentation
I-III
ジョアン・マドゥレイラ(1971-):Passio
I-III
アイヴァン・ムーディ:
По небу гулял месяц ясный
[Po nebu gulyal mesyats yasnyi] (ロシア聖歌による)
アンドルー・スミス:
Ebi beo thu, hevene quene(18世紀イングランドのテキストによる)
ジョアン・マドゥレイラ:Porque ben Santa
Maria sabe os seus does dar
(聖母マリアのカンティガ第327番による) |
セテ・ラグリマス
フィリペ・ファリア、
セルジオ・ペイショト(テノール、ディレクター)
ジュジ・トート(ソプラノ)
ペドロ・カストロ(バロックオーボエ、オーボエ・ダ・カッチャ、リコーダー)
イネス・モス・カルダス(リコーダー)
ウゴ・サンシェス(テオルボ、リュート)
ティアゴ・マティアス(テオルボ)
ディアナ・ヴィナグレ(バロックチェロ) |
|
録音:2009年6-7月、リスボン音楽院、リスボン、ポルトガル
現代作曲家が声楽とバロック楽器のために書いた静穏なる宗教的作品集。
アイヴァン・ムーディはポルトガル在住のイギリス人。アンドルー・スミスはノルウェー在住のイギリス人。ジョアン・マドゥレイラはポルトガルの作曲家。
|
| |
|
|
いびつな石
ディオゴ・ディアス・メルガス(1638-1700):
めでたし元后 [Salve Regina]/オリーヴ山で
[In monte Oliveti]
われらを助けたまえ [Adjuva nos]/断食し涙を流し
[In jejunio et fletu]
フランシスコ・アントニオ・デ・アルメイダ(1702頃-1755?):
おお、何と甘美な [O quam suavis]
カルロス・セイシャス(1704-1742):ソナタ
20.2(*)
フランシスコ・アントニオ・デ・アルメイダ:
奇跡を求めるならば [Si quaeris miracula]
(聖アントニオの祝日のための4声コンチェルト形式のレスポンソリウム)(*)
カルロス・セイシャス:
ソナタ 20.3(*)/ソナタ 20.3(セテ・ラグリマス編曲)(*)
今日、われらに天の王が [Hodie nobis coelorum
Rex]
(クリスマスのための5声のレスポンソリウム)(*)
アントニオ・テイシェイラ(1707-1774):
かくも痛ましく [Tanta grassabatur]
(聖ヴィンセントの祝日のためのレスポンソリウム
III)(*)
カルロス・セイシャス:ソナタ 15.1(*)
カルロス・セイシャス:
杉のごとくわれは頭を高く上げ [Sicut cedrus
exaltata sum]
(聖母マリア被昇天の祝日のためのレスポンソリウム
II)(*) |
セテ・ラグリマス
フィリペ・ファリア、
セルジオ・ペイショト(テノール、ディレクター)
モニカ・モンテイロ(ソプラノ)
ペドロ・カストロ(バロックオーボエ、リコーダー)
デニス・ステツェンコ(バロックヴァイオリン)
ウゴ・サンシェス(テオルボ)
ティアゴ・マティアス(テオルボ、バロックギター)
ディアナ・ヴィナグレ(バロックチェロ)
マルタ・ヴィセンテ(バロック・コントラバス)
セルジオ・シルヴァ(ポジティヴ・オルガン) |
|
録音:2009年11月、リスボン音楽院、リスボン、ポルトガル
「バロック」という言葉は真珠の形がいびつであるという意味のポルトガル語「barroco」に由来するとも言われていますが、当盤はまさにポルトガル・バロック音楽の海から拾い上た小石を集めたような趣のアルバムです。
(*)はジョアン・ペドロ・ダルヴァレンガのクリティカル・エディションに拠る演奏。
|
| |
|
|
風
ジョアン・マドゥレイラ(1971-):聖霊降臨の主日のミサ
聖霊の風 [O vento do espirito] (アンティフォナ・アド・イオントロイトゥム)
キリエ(アクトゥム・ペニテンターリス)/グローリア
来たれ聖霊 [Veni Sancte Spiritus] (セクエンツィア)/アレルヤ
−Pega nos fios... (アンティフォナ・アド・オフェルトリウム)
サンクトゥス/アニュス・デイ/泉 [As
fontes] (ポストコムニオ)
Ama como a estrada comeca(ディミシオ) |
セテ・ラグリマス
フィリペ・ファリア、
セルジオ・ペイショト(テノール、ディレクター)
ソフィア・ディニス(ヴィオラ・ダ・ガンバ)
ウゴ・サンシェス(テオルボ) |
|
録音:2010年6月、ペニャ・ロンガ教会、リスボン、ポルトガル
ジョアン・マドゥレイラはポルトガルのリスボンに生まれ、アントニオ・ピニョ・ヴァルガスおよびクリストファー・ボッホマン(リスボン音楽院)フランコ・ドナトーニ(シエナのキジアーナ音楽アカデミー)、ヨーク・ヘラー(ケルン音楽大学)、イヴァン・フェデーレ(ストラスブール音楽院)に師事した作曲家。
セテ・ラグリマスのために書かれた「聖霊降臨の主日のミサ」は静謐で淡々とした印象の作品。
※収録時間26分ほどですがフルプライス商品ですのでご注意ください。
|
MU RECORDS
|
|
|
君の腕の中で一夜
マヌエル・マシャド(1590頃-1646):歌曲集
二つの星が太陽に従い [Dos estrellas le
siguen]
岩陰に [A la sombra de un penasco]
羊飼い娘は村の牧場に行った [Salio al
prado de su aldea]
泣くがよい、わが心よ [Bien podeis, corazon
mio](器楽)
ガラテアはどれほど感じるのか [Que bien
siente Galatea]
ぼくは君に言う、きらめく炎 [A ti digo,
ampo de fuego]
ジャシンタは泉に行った [Salio a la fuente
Jacinta] (器楽)
君の腕の中で一夜 [En tus brazos una noche]
山々は暗くなり [Oscurece las montanas]
(器楽)
ジャスミンの露を奪う小鳥よ [Avejuela
que al jazmin]
フィリスの美貌を [De la hermosura de
Filis] (器楽)
私をうんざりさせる苦痛は [Mi cansado
sufrimiento]
何と言う自惚れか [Que entonadilla que
estaba](器楽)
リサルドは谷を出た [Fuese Lisardo del
valle]
だんだんと、ぼくの不安は [Paso a paso,
empenos mios]
ぼくの恋人の瞳から [De los ojos de mi
morena]
外へ、外へ [Afuera, afuera] |
セテ・ラグリマス
フィリペ・ファリア、
セルジオ・ペイショト(テノール、ディレクター)
ペドロ・カストロ、
イネス・モス・カルダス(リコーダー)
ソフィア・ディニス(ヴィオラ・ダ・ガンバ)
ティアゴ・マティアス(ビウエラ、テオルボ、バロックギター) |
|
録音:2011年2月、リスボン高等音楽学校、リスボン、ポルトガル
マヌエル・マシャドはポルトガルのリスボンに生まれ、リスボン大聖堂併設学校でドゥアルテ・ロボ(1565頃-1646)に師事した作曲家・ハープ奏者。
1610年にスペインのマドリードに渡り王宮礼拝堂楽士、1639年には国王フェリペ4世の宮廷音楽家になりました。当盤収録曲の歌詞もすべてスペイン語です。
|
| |
|
|
陸 ディアスポラ Vol.2
ガスパル・フェルナンデス(1565頃-1629):
Tururu farara con son(4声のギネオ;メキシコ)
+16世紀ポルトガル、作者不詳のヴィランシコ「主の羊飼いは生まれた」
[Es nacido Dios pastores] の歌詞によるコントラファクタ(替え歌)
+フィリペ・ファリア(1976-)&セルジオ・ペイショト(1974-):バイレ(2声)
ブラジル民謡:もう遅い、彼女は眠っている
[E tarde, ela dorme]
セファルディムのロマンス:
モーゼはミツライムを出た [Mose salio
de Misraim] (モロッコ)
インド民謡:O Divan de Mogara
不詳:われらに告げまたえ、マリア [Dic nobis
Maria] / Dalha den cima del cielo
(16世紀ポルトガル/スペイン)
フィリペ・ファリア&セルジオ・ペイショト/ロペ・デ・ヴェガ(1562-1635)作詩:
まぐさ桶 [El pesebre] (ポルトガル/スペイン)
マヌエル・ジョゼ・ヴィグダル(確認できる活躍期:1795-1824):
冷酷なサウダーデ(モディニャ;ポルトガル)
ティモール民謡/フランシスコ・ボルジャ・ダ・コスタ(1946-1975)作詩:
Ko le le mai
フィリペ・ダ・マドレ・デ・デウス(1626-1688/1690頃):
Oiga el que ignora: Guatemala(福音史家聖ヨハネのビリャンシコ;グアテマラ)
不詳/アルナルド・タヴェイラ・アラウジョ神父(1929-)編曲:
Yamukela(南アフリカ/モザンビーク)
フィリペ・ダ・マドレ・デ・デウス:
Al mirar elevado(使徒聖ヤコブのビリャンシコ;グアテマラ)
アルトゥル・リベイロ(1924-1982):
レモン売りのロジーニャ [A Rosinha dos
limoes] (ファド;ポルトガル)
+ペドロ・カストロ(1977-)による変奏曲
ポルトガル民謡:
眠れ、眠れ、私のぼうや [Dorme, dorme,
meu menino]
ねんね、ねんね、私のぼうや [Nana, nana,
meu menino]
ああ、ああ、ぼうや、ああ [O, o, menino,
o]
ブラジル民謡:Yemanja oto / Uie ori rumba
ユダヤ歌謡:Dayenu |
セテ・ラグリマス
フィリペ・ファリア、
セルジオ・ペイショト(テノール、ディレクター)
ペドロ・カストロ(リコーダー、バロックオーボエ、オーボエ・ダ・カッチャ)
ソフィア・ディニス(ヴィオラ・ダ・ガンバ)
ウゴ・サンシェス(ビウエラ、中世リュート、テオルボ、バロック&ロマンティックギター)
マリオ・フランコ(コントラバス)
ルイシ・シルヴァ(打楽器)
ティアゴ・マティアス(ビウエラ、テオルボ、バロックギター)
ゲスト;イネス・モス・カルダス(リコーダー)
マジス合唱団 |
|
録音:2011年6月、リスボン高等音楽学校、リスボン、ポルトガル
ポルトガルの「ディアスポラ」(祖国を離れ他国に住む者)、すなわちポルトガル植民地居住者たちにまつわる音楽をテーマとするアルバム第2作。
|
| |
|
|
半島 ディアスポラ Vol.3
フィリペ・ファリア(1976-)&セルジオ・ペイショト(1974-)/
不詳(16世紀-17世紀)作詩:
悲しみと郷愁を抱いて私は去る [Parto triste
saludoso]
わが馬具は武器だ [Mis arreios son las
armas]
不詳(16世紀-17世紀):
緑色の瞳の少女 [Minina dos olhos verdes]
生きているように見えるのはぼくではない
[No soy yo quien veis vivir]
フィリペ・ファリア&セルジオ・ペイショト/不詳(16世紀-17世紀)作詩:
私の不幸のせいで私はあなたに会えないだろう
[Biem podera my desvemtura]
ルイス・デ・ミラン(1500頃-1561頃):
ぼくは生きていて気になることがひとつある
[Un cuydado que mia via ten]
不詳(16世紀-17世紀):
あなたは婚約している、レディよ [Desposastesos,
senora]
言ってくれ、泥棒女よ [Dime, robadora]
フィリペ・ファリア&セルジオ・ペイショト/不詳(16世紀-17世紀)作詩:
なぜ泣く?モーロ人よ [Porque lhoras moro]
ああ、生きているのかいないのか [Ay que
viviendo no byvo]
不詳(16世紀-17世紀):
ああ、輝く月よ [Ay luna que reluzes]
望みは潰えた [Foi-ee gastamdo a esperanca]
夜が暗いならば [Si la noche haze escura]
水浴に行くなら、フアニーリャよ [Si te
vas a banar, Juanilla]
話せ、わが目よ [Faiai, meus ollos]
私の大きな苦しみには [Em mi gram sufrimento] |
セテ・ラグリマス
フィリペ・ファリア、
セルジオ・ペイショト(テノール、ディレクター)
ペドロ・カストロ(リコーダー、バロックオーボエ、ショーム)
ソフィア・ディニス(ヴィオラ・ダ・ガンバ)
ダンカン・フォックス(ヴィオローネ)
ルイシ・シルヴァ(打楽器) |
|
録音:2012年7月、リスボン高等音楽学校、リスボン、ポルトガル
「ディアスポラ」第3作は前2作とは趣向を変え、イベリア半島の音楽における人間の内面への旅をテーマとしています。
|
| |
|
|
リングア Vol.1
Tanchao(ポルトガル語)
No piense Menguilla ya
(ホセ・マリン(1618/1619?-1699)作曲/
フィリペ・ファリア&ティアゴ・マティアス編曲;カスティリャ語)
El testament d'Amelia(カタルーニャ語)
Baila nena(ガリシア語)
Aurtxoa seaskan(バスク語)
Virgem da Consolacao(ポルトガル語)
Dime, paxarin parleru(アストゥリアス語)
Pur beilar el pingacho(ミランダ語)
Todo me cansa(作者不詳、16世紀のビリャンシコ;カスティリャ語)
El mestre(カタルーニャ語)
Agora non(アストゥリアス語)
Meu amor me deu um lenco I/II(ポルトガル語)
Pues quexar se(作者不詳、16世紀のビリャンシコ;カスティリャ語)
Mira-me Miguel(ミランダ語)
El gavinet de los talls & Canco de
pegaire(カタルーニャ語) |
ノアノア
フィリペ・ファリア(歌、アドゥフェ、バスドラム、ブルームスティック、レコ=レコ、
ゴート・ネイル、トンバク、バロックギター、コラショーネ、リコーダー、口笛、メロディカ)
ティアゴ・マティアス(バロックギター、テオルボ、ビウエラ、コラショーネ、歌、バスドラム、
ブルームスティック、口笛、ゴート・ネイル、ユダヤ・ハープ) |
|
録音:2013年6、11月、2014年1月、リスボンおよびイダニャ=ア=ノヴァ、ポルトガル
フィリペ・ファリアとティアゴ・マティアスが2012年に結成したユニット「ノアノア」のデビューCD。イベリア半島の様々な言語をテーマとしています。ミランダ語はポルトガル北東部のスペイン国境付近で話されている言語。
|
| |
|
|
カンティガ
マルティン・コダス(13世紀):恋人の歌
ああ、神よ、ご存じなら [Ai Deus, se
sab'ora meu amigo]
恋人の愛を知る人は [Quantas sabedes
amar amigo]
波よ、私はおまえに会いに来た [Ai ondas
que vim veer]
ビゴの聖所で [Eno sagrado en Vigo]
(*)
知らせが届いた [Mandad'hei comigo]
美しい妹よ、急いで [Mia irmana fremosa,
treides comigo]
ビゴの海の波 [Ondas do mar de Vigo] |
セテ・ラグリマス
フィリペ・ファリア、
セルジオ・ペイショト(テノール、ディレクター)
ペドロ・カストロ(リコーダー、バロックオーボエ、バグパイプ)
ティアゴ・マティアス(リュート、ビウエラ、サズ)
マリオ・フランコ(コントラバス)
ソフィア・ディニス(ヴィオラ・ダ・ガンバ)
ウゴ・サンシェス(ビウエラ、中世リュート、テオルボ、バロック&ロマンティックギター)
マリオ・フランコ(コントラバス)
ルイシ・シルヴァ(打楽器) |
|
録音:2013年11月、リスボン、ポルトガル
中世ガリシア語による名曲。マヌエル・ペドロ・フェレイラによるクリティカル・エディション「O
Som de Martin Codax」(1986年、ポルトガル国立印刷局刊)を基にフィリペ・ファリアとセルジオ・ペイショトが編曲((*)は楽譜が存在しないためフィリペ・ファリアとセルジオ・ペイショト新たに作曲)したヴァージョンを演奏。各曲はかなり引き延ばされ即興的に展開されます。
|
MUGUEL AMARAL
|
|
|
ミゲル・アマラル 斜めに降る雨
ミゲル・アマラル(1982-):
海辺 [A Praia] (ソフィア・デ・メロ・ブレイネル・アンドレセンの詩による)
練習曲「プロコフィエフ的暗示」(セルゲイ・プロコフィエフの記念に)Op.2
No.1
[Estudo "Sugestao Prokofiolica
(a memoria de Sergey Prokofiev)]
フェルナンド・ペソアの詩による2つの絵
[Dois Quadros Sobre Poemas de Fernando
Pessoa]
斜めに降る雨(リカルド・ロシャに)
[Chuva Obliqua (ao Ricardo Rocha)]
満月(武満徹の記念に) [Plenilunio
(a memoria de Toru Takemitsu)]
マリオ・ラジニャ(1960-):ソナタ
イゴル・C・シルヴァ(1989-):
モノローグV「半ダースの冗談」 [Monologo
V "Meia Duzia de Brincadeiras"]
ダニエル・モレイラ(1983-):迷宮 [Labirinto]
ミゲル・アマラル:永遠の帰還 [O Eterno
REgresso]
ディミトリス・アンドリコプーロス(1971-):
弔いの鐘の音(ガルシア・ロルカの詩による、
ポルトガルギターとエレクトロニクスのための)
[Clamor (sobre o poema de Garcia Lorca)] |
ミゲル・アマラル(ポルトガルギター) |
|
録音:データ記載なし
ポルトガルギター奏者ミゲル・アマラルの自主制作によるデビューCD。ミゲル・アマラルは1982年ポルトに生まれ、サムエル・カブラルとジョゼ・フォンテス・ロシャにポルトガルギターを師事、2005年にファドの伴奏者としてデビュー。しかしソリストとして活動することを決意しペドロ・カルデイラ・カブラルとリカルド・ロシャにポルトガルギターを、さらに和声と対位法をダニエル・モレイラに、作曲をディミトリス・アンドリコプーロスに師事。2009年ポルトでのソロ・リサイタルを大成功させ、以後ポルトガル国内各地で活躍しています。
本体・外装に規格品番表記がございませんが、弊社では「AMARAL
1」として管理いたします。
|
PARLOPHONE MUSIC PORTUGAL
|
|
|
レムリアの歌 現代ポルトガル歌曲集
オズヴァルド・フェルナンデス(1985-)/
ゴンサロ・M・タヴァレス(1970-)作詩:旅 [Uma
Viagem]
エドゥアルド・ルイス・パトリアルカ(1970-)/
ヴァルテル・ウゴ・マンイ(1971-)作詩:レムリアの歌
[Cancoes de Lemuria]
ヌノ・ジャシント(1985-)/パウロ・ジョゼ・ミランダ(1965-)作詩:幻影
[Ilusio]
パウロ・ペレイラ=ロペス(1964-)/
ジョゼ・ルイス・ペイショト(1974-)作詩:7つの歌
[7 Cancoes] |
マリナ・パシェコ(ソプラノ)
オルガ・アマロ(ピアノ) |
|
録音:2013年9月、ポンテ・デ・リマ音楽アカデミー・コンサートホール、ポンテ・デ・リマ、ポルトガル
作詩・作曲とも現代ポルトガルのアーティストの手になる歌曲集。「レムリア」はイギリスの動物学者フィリップ・スクレーター(1829-1913)が1874年に提唱した、インド洋に存在したとされる仮想の大陸(Wikipediaによる)。
|
 スロヴァキア音楽財団 スロヴァキア音楽財団
|
|
|
エゴン・クラーク(1958-):メモワール II
ELF交響曲 [The ELF Symphony] −マーラー没後100年記念
(大管弦楽のための;2011)(*)
スロヴァキア・フィルハーモニー管弦楽団 エルンスト・タイス(指揮)
愛の庭で [Au jardan d'amour]
(中世フランスの詩による連作歌曲、ソプラノとピアノのための版;2001)
ヤナ・パストルコヴァー(ソプラノ) エゴン・クラーク(ピアノ)
新しいハーモニー [New Harmony] (クラリネットとピアノのための;2008)
アレクサンデル・ステパノフ(クラリネット) エゴン・クラーク(ピアノ)
月光に照らされた恋人たち [Lovers in the
Moonlight] −
マルク・シャガールの記念に(フルートとピアノのための;2009)
ダニエラ・ブレサーコヴァー(フルート) マーリア・ブレサーコヴァー(ピアノ)
キャンドルライト [Candlelight] (ギターとピアノのための;2011)
アダム・マレツ(ギター) エヴァ・ツァーホヴァー(ピアノ)
パノプティコン [Panopticon] (7つのピアノ小品;1985)
エヴァ・ツァーホヴァー(ピアノ) |
|
録音:2011年9月22日、ライヴ、スロヴァキア・フィルハーモニー・ホール、ブラチスラヴァ、スロヴァキア(*)
データ記載なし(*以外)
ライセンサー:スロヴァキア・フィルハーモニーおよびスロヴァキア放送(*以外)
エゴン・クラークはブラチスラヴァ音楽演劇アカデミーで音楽理論を学び、1984年から作曲を開始しました。
チェコスロヴァキア時代の国営音楽出版社OPUSの編集者(1984-1991)後、ヴィジュアル・ステージ・プロデューサー(1991-1995)、ブラチスラヴァ音楽演劇アカデミー教員(1995-2005)、バーンスカー・ビストリツァ音楽演劇アカデミー教員(2005-2008)等を務めた後、ヤーン・アルブレヒト音楽演劇アカデミーの共同創設者となり2011の創設以来2014年現在その総長の任にあります。
|
| |
|
|
エフゲニー・イルシャイ(1951-):愛の場所で
消滅 [Uangamizi] (ヴァイオリン、チェロと管弦楽のための協奏曲;2006)(*/+)
サウンドクエイク・ゼロ [Soundquake Zero]
(管弦楽のための;2009)
引用 [Quotations] (ピアノと管弦楽のための協奏曲;2005/2006)(#)
愛の場所で [In the Space of Love]
(ヴァイオリン、ピアノと管弦楽のための協奏曲;2004/2005)(*/**) |
ミラン・パリャ(ヴァイオリン(*))
ヨゼフ・ルプターク(チェロ(+))
ラジスラフ・ファンチョヴィチ(ピアノ(#))
エフゲニー・イルシャイ(ピアノ(**))
スロヴァキア放送交響楽団
マリオ・コシク(指揮) |
|
録音:2009-2011年、スロヴァキア放送、ブラチスラヴァ、スロヴァキア
ライセンサー:スロヴァキア放送
エフゲニー(イェヴゲニー)・イルシャイはロシアのレーニングラード(現サンクトペテルブルク)に生まれたスロヴァキアの作曲家。
マリオ・コシク(1969年生まれ)はブラチスラヴァ音楽院および音楽演劇アカデミーで学んだスロヴァキアの指揮者。2007年以来2014年現在スロヴァキア放送交響楽団首席指揮者を務めています。
|
| |
|
|
スロヴァキアのヴァイオリン協奏曲集
アレクサンデル・モイゼス(1906-1984):
ヴァイオリン協奏曲 Op.53(1957-1958)
アンドレイ・オチナーシュ(1911-1995):
ヴァイオリン協奏曲 Op.47(1974-1975)
デジデル・カルドシュ(1914-1991):
ヴァイオリン協奏曲 Op.51(1980) |
ミラン・パリャ(ヴァイオリン)
スロヴァキア放送交響楽団
マリオ・コシク(指揮) |
|
録音:2009-2011年、スロヴァキア放送、ブラチスラヴァ、スロヴァキア
ライセンサー:スロヴァキア放送
20世紀後半、チェコスロヴァキア時代のスロヴァキアの作曲家によるヴァイオリン協奏曲3作品を取り上げた好企画。
スロヴァキアのヴァイオリニスト、ミラン・パリャ(1982年生まれ)はこの数年20−21世紀スロヴァキアのヴァイオリン音楽の録音を一手に引き受けている感があります。
|
| |
|
|
ベートーヴェン(1770-1827):
ピアノ・ソナタ第4番変ホ長調 Op.7
ピアノ・ソナタ第14番嬰ハ短調「月光」Op.27
No.2
ピアノ・ソナタ第23番ヘ短調「熱情」Op.57 |
ダニエラ・ヴァリーンスカ(フォルテピアノ) |
|
録音:1991年12月、ドルナー・クルパー城、トルナヴァ、スロヴァキア
使用楽器:推定1800年、プラハ、Jacob Wiemar製
ダニエラ・ヴァリーンスカはブラチスラヴァ音楽院、レーニングラード(現サンクトペテルブク)音楽院、ブラチスラヴァ音楽演劇アカデミーで学んだスロヴァキアのピアニスト。バロック(彼女はチェンバロも演奏)から現代スロヴァキア作曲家の新作に至る幅広いレパートリーを持ち、社会主義チェコスロヴァキア時代から西欧や北米に進出、1991年からは母校ブラチスラヴァ音楽演劇アカデミー教授を務めています。ヴァリーンスカは2004年から2008年にかけてモダーン楽器を弾いてベートーヴェンのピアノ・ソナタ全曲を録音しています(Diskantレーベル、DK
0118-2)が、当録音はそのプロジェクトの13年前にオリジナルのピリオド楽器を用いて行われたものです。
|
 TANIDOS TANIDOS
|
|
|
ヨハン・バプティスト(ヤン・クシチテル)・ヴァンハル(1739-1813):
クラリネットとピアノのためのソナタ集
ソナタ変ホ長調(1810)(*)/
ソナタ ハ長調(1801)(+)/
ソナタ変ロ長調(1803)(+) |
ダビド・アレナス(クラリネット)
ベレン・ゴンサレス=ドモンテ(ピアノ) |
|
録音:2014年3月30日、マドリード王立音楽院マヌエル・デ・ファリャ・ホール、マドリード、スペイン
ヴァンハルはボヘミアに生まれたウィーン古典派の作曲家。クラリネットを積極的に採り入れ、協奏曲や弦楽器との組み合わせによる室内楽作品も書いています。
ダビド・アレナス、ベレン・ゴンサレス=ドモンテはともにマドリード生まれでマドリード王立音楽院出身。(*)モダーン楽器による初録音。(+)ベーム式クラリネットによる初録音。
|
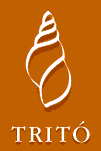 TRITO TRITO
|
|
|
シューベルト:交響曲第9番ハ長調「ザ・グレート」 |
カダケス管弦楽団
ハイメ・マルティン(指揮)
|
|
録音:2013年1月17-18日、アウディトリオ、サラゴサ、スペイン
ハイメ・マルティンは1965年スペインのサンタンデルに生まれたフルート奏者・指揮者。1992年以来ロンドンに在住しアカデミー・オブ・セント・マーティン・イン・ザ・フィールズ、ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団、ヨーロッパ室内管弦楽団のソロ・フルーティスト(首席奏者)を務めています。
2007年に指揮者としての活動を開始し、当レーベルからだけでもすでに6タイトルのCDをリリースしています。
|
| |
|
|
マルク・サンボラ/
リディア・リヌエザ台本:「探偵トム・ソーヤー」 |
マルク・アンドゥレイ(トム・ソーヤー)
マルク・ウディナ(ハックルベリー・フィン)
その他出演者、器楽奏者
マルク・サンボラ(指揮)
ミケル・アジェイ(演出) |
カタルーニャ語の子供向けミュージカル的作品。
ブックレットもカタルーニャ語のみ。収録時間37分弱ですがフルプライスです。 |
 URLICHT URLICHT
|
|
|
ピアソラ タンゴからエチュードへ
アストル・ピアソラ(1921-1992)/オクタビオ・ブルネッティ編曲:
6つのタンゴ・エチュード/天使へのイントロダクション/ナイトクラブ
1960
天使のミロンガ/バルダリート/天使の復活/革命家 |
エルミラ・ダルヴァロヴァ(ヴァイオリン)
オクタビオ・ブルネッティ(ピアノ) |
録音:2013年
アルゼンチンのピアニスト、オクタビオ・ブルネッティがヴァイオリンとピアノのために編曲したピアソラ作品集。 |
| |
|
|
デイヴィッド・アムラム(1930-):室内楽作品集 ニューヨーク室内楽祭ライヴ
ヴァイオリンとピアノのためのソナタ
エルミラ・ダルヴァロヴァ(ヴァイオリン) 金丸智子(ピアノ)
「赤い河の谷間」の主題による変奏曲(フルートと弦楽のための)
キャロル・ウィンセンス(フルート) フェイス・ザ・ミュージック・アンサンブル
フルート協奏曲「夜の巨人たち [Giants
of Night]」
エルミラ・ダルヴァロヴァ(ヴァイオリン) シン=チャオ・リャオ(ピアノ)
肖像(ピアノ四重奏のための)
ニョーヨーク・ピアノ四重奏団
リンダ・ホール(ピアノ) エルミラ・ダルヴァロヴァ(ヴァイオリン)
ロナルド・カーボーン(ヴィオラ) ウェンディ・サッター(ゲスト:ヴィオラ)
モンクのためのブルースと変奏曲(ホルンのための)
ハワード・ウォール(ホルン)
ジャック・ケルアックの「路上」からの4つの朗読
(朗読とジャズ・クアルテットのための)
イカヤニ・チェンバーリン、アディラ・アムラム、ダグラス・イーガー(朗読)
デイヴィッド・アムラム・クアルテット
デイヴィッド・アムラム(ピアノ) ケヴィン・トゥイグ(ドラムス)
リーン・ハート(ベース) アダム・アムラム(コンガ) |
|
録音:2012年9月7日、ライヴ、New York Chamber
Music Festival、シンフォニー・スペース、
ニューヨーク・シティ、アメリカ合衆国
ホルンを、ピアノをはじめ様々なクラシカル、ジャズおよび民族楽器のプレーヤーにして指揮者、作曲家(映画音楽も手がける)、さらに著作家でもあるアメリカ合衆国のマルチタレント・ミュージシャン、デイヴィッド・アムラムの室内楽プログラム・コンサートのライヴ録音。
とにかく合衆国での人気が凄いらしく早々に売り切れそうだとのことなので、お早目のオーダーをお願いいたします。(代理店)、だそうです・・・
|
 VERSO VERSO
|
|
|
ヴィオラとピアノのためのスペインのソナタ集
コンラド・デル・カンポ(1876-1953):ロマンス
フランシスコ・フレタ・ポロ(1931-):ソナタ
Op.62
ロベルト・ジェラルド[ロバート・ジェラード](1986-1970):ソナタ
ジョルディ・セルヴェリョ(1935-):ターティス・ソナタ |
アシャン・ピライ(ヴィオラ)
フアン・カルロス・コルネリェス(ピアノ) |
|
録音:2013年2月5-6日、ヘタフェ専門音楽院、ヘタフェ、マドリード県、スペイン
アシャン・ピライは1969年スリランカ生まれのイギリスのヴィオラ奏者。2014年現在、バルセロナ交響楽団首席奏者(2000-)、カタルーニャ高等音楽学校教授(2001-)、リセウ音楽院教授(2009-)を務めています。
ターティス・ソナタは伝説的ヴィオラ奏者ライオネル・ターティス(1876-1975)に捧げられた作品。
|
| |
|
|
ガブリエル・エルコレカ(1969-):
水の三重奏曲 クラリネット、ヴァイオリン、チェロ、ピアノのための作品集
水の三重奏曲 [Trio del Agua] (ヴァイオリン、チェロとピアノのための;2011)
Biribilketa(クラリネット、チェロとピアノのための;1999)
Mundaka(ピアノのための;2009)
悪魔 [Saturno] (クラリネット、バスクラリネットとチェロのための;1997)
2つのソルチコ [Dos Zortzikos] (ピアノのための;2000)
Aldakiak (ヴァイオリン、チェロとピアノのための;2003) |
アルボス三重奏団
ミゲル・ボレゴ(ヴァイオリン)
ホセ・ミゲル・ゴメス(チェロ)
フアン・カルロス・ガルバヨ(ピアノ)
ホセ・ルイス・エステリェス(クラリネット、バスクラリネット) |
|
録音:2014年1月27-29、ヘタフェ専門音楽院、ヘタフェ、マドリード県、スペイン
ガブリエル・エルコレカはスペイン・バスクのビルバオに生まれ、イギリスの王立音楽アカデミーでマイケル・フィニシーに師事した作曲家。
|
 ACOUSENCE ACOUSENCE
|


ACOCD12214
(2CD)
\2600→\2390 |
アンナ・マリコヴァ/スクリャービン:ピアノ・ソナタ全集
スクリャービン:
CD. 1
ピアノ・ソナタ第1番 ヘ短調 op.6 (24:23)
ピアノ・ソナタ第2番 嬰ト短調「幻想ソナタ」 op.19
(12:12)
ピアノ・ソナタ第3番 嬰ヘ短調 op.23 (18:33)
ピアノ・ソナタ第4番 嬰ヘ長調 op.30 (7:31)
CD. 2
ピアノ・ソナタ第5番 op.53 (12:10)
ピアノ・ソナタ第6番 op.62 (12:18)
ピアノ・ソナタ第7番「白ミサ」 op.64 (
12:11)
ピアノ・ソナタ第8番 op.66 (14:42)
ピアノ・ソナタ第9番「黒ミサ」 op.68 (8:25)
ピアノ・ソナタ第10番 op.70 (12:58)
※作品名の後ろの( )内は演奏時間 |
アンナ・マリコヴァ(ピアノ) |
2012年3月18,19日、2013年2月21,22日、2014年2月28日、3月1日録音
日本のピアノメーカーであるカワイの欧州における販売拠点 ドイツ、クレフェルトでのデジタル録音 使用ピアノ:SHIGERU
KAWAI
※2CDですが、1CDの価格にて、ご提供させて頂きます。
※デジパック仕様です。
※アンナ・マリコヴァは旧ソ連ウズベキスタン出身の女流ピアニストです。
ウズベキスタンの首都タシュケントの音楽院、モスクワ中央音楽院、チャイコフスキー音楽院で学んだ後、1993年ミュンヘン国際音楽コンクールで優勝し、現代ロシアを代表する若手ピアニストとして名声と評価を手に入れ多くの演奏会を通して活躍しています。
モアリコヴァは母国ロシアを代表する作曲家の一人であるスクリャービンによる10曲のピアノ・ソナタそれぞれに鋭く切り込み曲に潜む陰影をまばゆいほど鮮やかに描き出しています。
高い演奏技術と深い解釈に裏付けされた名演奏です。
|
 ARS MUSICI ARS MUSICI
|

233877
\2000 |
ブラームス:弦楽四重奏曲第2番
ヴェルディ:弦楽四重奏曲 |
アルテミス四重奏団 |
| 昔の出直し。 |
| |

233876
\2000 |
チロル地方のクリスマス民謡集 |
東チロル四重唱団 |
| |

233878
\2000 |
暁の星はいと麗しかな — 宗教曲集 |
フラウタンド・ケルン |
 CARUS CARUS
|


83.022
(3CD)
\4000→\3690 |
ベルニウス指揮 メンデルスゾーン:劇音楽集BOX
CD.1
劇音楽「真夏の夜の夢」 op.21 & op.61
1997年4月19日ライヴ録音
(CARUS 83.205から) |
フリーダー・ベルニウス指揮
シビラ・ルーベンス(ソプラノ)
クラウディア・シューベルト(ソプラノ)
アンネ・ベンネント(語り)
ヨアヒム・クンチュ(語り)
シュトゥツトガルト・バロック管弦楽団
シュトゥツトガルト室内合唱団 |
CD.2
劇音楽「アンティゴネー」 op.55
2004年9月5日ライヴ録音
(CARUS 83.224から) |
フリーダー・ベルニウス指揮
アンジェラ・ヴィンクラー(語り:アンティゴネー)
ヨアヒム・クンチュ(語り:クレオン)
ミヒャエル・ランスブルク(語り)
ユリア・ナクトマン(語り)
シュトゥツトガルト・クラシック・フィルハーモニー
シュトゥツトガルト室内合唱団 |
CD.3
付随音楽「コロノスのエディプス」 op.93
2004年9月5日ライヴ録音
(CARUS 83.225から) |
フリーダー・ベルニウス指揮
アンジェラ・ヴィンクラー(アンティゴネー)
ヨアヒム・クンチュ(エディプス)
ミヒャエル・ランスブルク(語り)
ユリア・ナクトマン(語り)
シュトゥツトガルト・クラシック・フィルハーモニー
シュトゥツトガルト室内合唱団 |
|
既発売のアイテムを組み合わせたお買い得なBOXセットです。
縦:130mm、横:130mm、奥行:21mmの紙BOXです。 |
 DUX DUX
|

DUX1104
\2400 |
CASTRUM DOLORIS
悲しみの城砦 古いポーランドの葬儀の歌 |
ロベルト・ポジャルスキ、
ボルヌス・コンソート、他 |
| |

DUX0600
\2400 |
バロック音楽の舞曲
ラインケン:組曲/
ルベグ:クラヴサン曲集第1巻より組曲/
デュパール:6つのクラヴサン組曲より第6番/
J.S.バッハ:フランス組曲第4番BWV815/
ダングルベール:クラヴサン曲集よりメヌエット/
クープラン:
クラヴサン曲集第1巻第1組曲より
サラバンド、
王宮のコンセールよりフォルラーヌ、
趣味の融合 または新コンセールより
シシリエンヌ/
ラモー:優雅なインドの国々 |
ウルシュラ・バルトキェヴィチ(Cemb) |
| |

DUX0806
\2400 |
ルトスワフスキ:声楽と器楽のための作品集
ラクリモーサ、アンリ・ミショーの3つの詩、
織り込まれた言葉、眠りの空間、歌の花と歌のお話 |
ダニエル・ライスキン指揮、
アルトゥール・ルービンシュタイン・
フィルハーモニー管弦楽団、合唱団
ウーツィア・シャブレフスカ=ボジコフスカ(Sop)
ラファウ・バルトミンスキ(Ten)
スタニスワフ・キェルネル(Br) |
ENZO
|

EZCD10013
\2800 |
グラナドス:12のスペイン舞曲集 Op.37
スペイン舞曲第1〜12番 |
比石 妃佐子(ピアノ) |
「アナザースカイ」(日本テレビ系全国)のゲストとして登場し、一気に注目が集まったバルセロナ在住の世界的ピアニスト、比石妃佐子(ひせきひさこ)。
比石はアリシア・デ・ラローチャの愛弟子。ラローチャと共同でアルベニス作品の楽譜校訂にも関わっているなど、スペインのピアノ音楽のスペシャリストとしてヨーロッパを中心に活躍しており、九響とアルベニスの協奏曲を本邦初演した。 |
| |

EZCD10014
\2800 |
グラナドス:組曲「ゴイエスカス」H.64
組曲「ゴイエスカス」第1〜6曲、補遺:エル・ペレレ
H.106 |
比石 妃佐子(ピアノ) |
| |

EZCD10015/16
(2CD)
\4600 |
アルベニス:組曲「イベリア」、スペイン組曲
組曲「イベリア」第1〜12曲、
スペイン組曲〜グラナダ、セビーリャ、アストゥ−リアス
Op.47-5 |
比石 妃佐子(ピアノ) |
NEWAY MUSIC
|

UM12120007
(2CD)
\4600 |
スペイン音楽の世界
グラナドス:スペイン民謡による6つの小品、ロマンティックな情景、
ショパン:バラード第4番 Op.52、
グラナドス:若き日の物語〜5月の歌、
ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第8番「悲愴」、
ファリャ:4つのスペイン小品集、
モンサルバーチェ:イヴェットのためのソナチネ、ハバネラ |
比石 妃佐子(ピアノ) |
| |

UM11120003
\2800 |
比石 妃佐子サクラダ・ファミリア大聖堂コンサート1995
ヒナステラ:ピアノ・ソナタ第1番、
トゥーリーナ:幻想的舞曲集 Op.22、
ファリャ:ピアノのための「三角帽子」から3つのダンス、
ファリャ:ベティカ(アンダルシア)幻想曲、
ファリャ:火祭りの踊り |
比石 妃佐子(ピアノ) |
| |

NM04130001
\2800 |
400年の夢、時空を超えて
モンポウ:密やかの印象、
モンサルバーチェ:左手のための3つの小品〜第2曲、
モンサルバーチェ:3つのディヴェルティメント
グラナドス:華やかな演奏家用アレグロ、
アルベニス:パバーナ・カプリーショ、
三善 昭:アン・ヴェール、
伊福部 昭:ピアノ組曲 |
比石 妃佐子(ピアノ) |
 PIANO CLASSICS PIANO CLASSICS
|

PCL 0070
\1400 |
シューベルト:ピアノソナタ第21番D.960、第13番D.664 |
クララ・ヴュルツ(pf) |
 UNITED CLASSICS UNITED CLASSICS
|

T2CD2014001
(3CD)
\3000 |
Great Cambridge Choirs
ケンブリッジの歌声宗教曲、聖歌等の作品集 |
ケンブリッジ・セント・ジョーンズ・カレッジ合唱団/
ケンブリッジ・クレア・カレッジ合唱団/
ケンブリッジ・キングス・カレッジ合唱団 |
| |

T2CD2014005
\1700 |
ヤコブス・ノゼマン:
ヴァイオリンと通奏低音のためのソナタOp.1 |
アントワネット・ローマン(Vln)
フロール・ムジクス |
| |

T2CD2014006
\1700 |
ヤコブス・ノゼマン:
ヴァイオリンと通奏低音のためのソナタOp.2 |
アントワネット・ローマン(Vln)
フロール・ムジクス |
![]()