≪第78号アリアCD新譜紹介コーナー≫
その2 8/26〜
マイナー・レーベル新譜
歴史的録音・旧録音
メジャー・レーベル
国内盤
映像 |
8/29(金)紹介新譜
マイナー・レーベル新譜
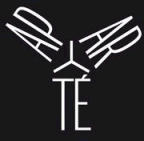 APARTE APARTE
|


AP 094
(3CD)
\5200 →\4790 |
ルセの新録音はリュリ晩期の傑作「アマディス」!
リュリ:「アマディス」 |
シリル・オヴィティ(T アマディス)
ユディト・ファン・ワンロアイ(S オリアーヌ)
イングリッド・ペリューシュ(S アルカボンヌ)
エドウィン・クロスリー=メルセル(Br アルカラウス)
ベノワ・アルヌ(Bs-Br フロレスタン)
ベネディクト・トラン(S ユルガンド)
ハスナー・ベンナニ(S コリサンド)
ピエリック・ボワソー
(Br アルキフ,アルダン・カニル,牢番,羊飼い)
レイナウト・ファン・メヘレン
(T 捕えられた者,羊飼い,勇者)
カロリーヌ・ウェイナンツ
(S ユルガンドの侍女,捕えられた者,捕虜,羊飼い)
ヴィルジニー・トマス(S 羊飼い,ユルガンドの侍女)
クリストフ・ルセ(指揮&チェンバロ)
レ・タラン・リリク,ナミュール室内合唱団 |
ルセの新録音はリュリ晩期の傑作「アマディス」!オヴィティ、ファン・ワンロアイ、ペリューシュ、クロスリー=メルセルと常連が結集これぞリュリの完成形!!!
録音:2013 年7 月4、5、6 日、ヴェルサイユ宮殿、王立オペラ劇場/164’06”
リュリを振らせたら敵なしのクリストフ・ルセ、新録音はリュリ晩期の傑作「アマディス」です!
「アマディス」は、リュリが亡くなる3 年前の作品(完成したオペラでは後ろから三つめ)。1864
年1 月に初演され大成功を収めました。台本は長年の相方、フィリップ・キノー。題材はルイ14
世自身が決めたと伝えられています。愛、魔法、嫉妬、急展開の逆転、試練、そして大団円と様々な要素に満ちた劇的変化に富んだ物語である一方、騎士道精神が色濃く反映された話には深みがあり、リュリとキノーのコンビの到達点を感じさせます。ちなみにこの台本はたいへんに人気が高く、ヘンデル(1715
年、ロンドン)やJ.C.バッハ(1779 年、パリ)をはじめ多くの翻案ものが作られています。晩年のリュリの音楽は、派手さや荘重さが控えられた代わりに深々としたじっくりした味わいが強く、それが物語と絡み合って他に類を見ない独自の高みに達しています。
ルセは「アマディス」を、2013 年7 月5 日にヴェルサイユ王宮劇場で、13
日にボーヌ音楽祭で演奏会形式で上演しています。ヴェルサイユ公演の本番とその前後に収録が行われました。ルセの指揮するリュリですからもちろん高水準、たとえば第3
幕の捕らえられた者たちの合唱の静かに広がる感動は絶品。改めてリュリの卓越した筆に目を見開かせてくれる演奏です。
ルセは、高い評価を得た「ベレロフォン」で主役を歌った二人、フランスのテノール、シリル・オヴィティとフランスのソプラノ、イングリッド・ペリューシュをここでも起用、二人は「ファエトン」でも歌っており、ルセから絶大な信頼が寄せられていることが分かります。オリアーヌのユディト・ファン・ワンロアイはオランダのソプラノ。オランダやベルギーで、バロックからモーツァルトあたりを中心に活躍しています。魔法使いアルカラウスのエドウィン・クロスリー=メルセルはフランスのまだ若いバリトンですが、広いレパートリーで既にヨーロッパ各地で活躍しています。フロレスタンのベノワ・アルヌは「ファエトン」(AP
061)でも起用されていました。
晩期のリュリの魅力はまた格別なもの、それをたっぷり堪能できる新録音です。
リュリ《アマディス》 簡単なあらすじ
プロローグ
魔法にかけられていたアルキフとユルガンドは魔法が解けて目を覚まし、アマディスの救出に向かう。
第1幕
帰還したばかりのフロレスタンに、アマディスは、オリアーヌの愛を得たと思ったのに、彼女に冷たくされていると嘆く。フロレスタンが恋人のコリサンドとの再会を喜んでいると、悲しみに沈んだオリアーヌが現れ、アマディスが心変わりしたと嘆く。
第2幕
森。ここは魔法を操るアルカラウスの牙城である。その妹アルカボンヌは、自分を助けた勇者に恋をしてしまい思い悩んでいる。兄妹の兄アルダン・カニルはアマディスに倒され、兄妹はアマディスに復讐しようとしている。そうとは知らぬアマディスが森にやって来ると、コリサンドに出会い、フロレスタンが魔法にかかり捕らえられてしまったことを知る。友を助けに行こうとするアマディスだったが、彼もまた魔法にかかって捕らえられてしまう。
第3幕
捕えられた者たちが嘆いている。処刑が始まろうとした時、墓の中から亡きアルダン・カニルが現れ、妹が裏切りを起そうとしてると告げる。アルカボンヌは捕らわれのアマディスこそが自分を助けた人だと気付き、全員を解放する。
第4幕
喜びの島。アルカボンヌは兄アルカラウスに、アマディスを愛していることを明かす。オリアーヌが島に現れ、アルカボンヌは嫉妬に燃える。アルカラウスがアマディスの「亡骸」を見せると、オリアーヌは取り乱して嘆き、兄妹はその姿にほくそ笑む。そこに大蛇の船に乗ったユルガンドと侍女たちが現れ、魔法を解いてアマディスとオリアーヌを救出。さらに大気の精霊たちがアルカラウスが呼び出した地獄の悪霊たちを打ち破り、兄妹は破滅する。
第5幕
宮殿。アマディスとオリアーヌは再会し、誤解を解く。ユルガンドはオリアーヌの父を説得することを請合う。フロレスタンとコリサンドも戻ってくる。アマディスとオリアーヌは大勢の人々から最も誠実な恋人と讃えられて幕となる。 |
 HAENSSLER HAENSSLER
|
|
|
ウェーバーを讃えて/ピアノ・デュオ作品集
ウェーバー:
CD1
(1)歌劇「アブ・ハッサン」序曲(クラインミヒェル編)
(2)8つの小品Op.60
(3)歌劇「ジルヴァーナ」序曲(クラインミヒェル編)
(4)ピアノ協奏曲第2番変ホ長調Op.32(イェーンス編による2台ピアノ版)
(5)アルマンドOp.4より第11番/第12番
CD2
(6)歌劇「魔弾の射手」序曲(デュオ・ダコール編)
(7)6つの小品Op.10
(8)6つの易しい小品Op.3
(9)ゴドフスキ:「舞踏への勧誘」による対位法的パラフレーズ(2台ピアノ版)
(10)モシェレス:ウェーバーを讃えてOp.103 |
デュオ・ダコール
【ルシア・ファン、
セバスチャン・オイラー】 |
幻の超絶難曲、ゴドフスキ編「舞踏への勧誘」を含むウェーバー・ピアノ・デュオ作品集
2013 年6 月-7 月/ SWR 室内楽スタジオ(シュトゥトガルト)/DDD、2h
18’ 55”
ドイツ人セバスチャン・オイラーと台湾人ルシア・ファンによるデュオ・ダコールは、これまでもベートーヴェンの「大フーガ」の作曲者編によるピアノ4
手版やレーガー作品集などで高い評価を受けてきました。
ヘンスラー・レーベル・デビューとなるアルバムは、ウェーバー作品集。華麗な難曲揃いのウェーバーの独奏曲と異なり、連弾曲は小曲中心で、親しみやすく、彼ならではのボルテージの高い魅力的な世界を創り上げています。録音に恵まれているとは言い難いため大歓迎と申せましょう。Op.60
の第4 曲と第7 曲、Op.10 の第2 曲はヒンデミットの「ウェーバーの主題による交響的変容」の主題に用いられていて、その原曲を聴くのも興味津々。
加えて、ウェーバーのオペラの序曲を連弾用に編曲したものと、ピアノ協奏曲第2
番を2 台のピアノで弾いているのも嬉しい限り。ドイツ・ロマン派の香りに満ちています。
さらに嬉しいのは、ゴドフスキが「舞踏への勧誘」を素材に、2
台のピアノ用編曲した珍品が収められていること。「対位法的パラフレーズ」の副題を持ち、様々なモチーフをゴドフスキならではの悪魔的ポリフォニーでからませた恐ろしく複雑な難曲となっています。
また、ウェーバーと同世代のヴィルトゥオーソ、モシェレスの連弾曲「ウェーバーを讃えて」もピアノ・デュオ・ファンが待ち望んでいた作品。こちらも演奏至難な大作ですが、このアルバムに収録されなかった「オベロン」と「オイリアンテ」のメロディを華麗なポプリとしたもので、ゾクゾクするほど演奏効果抜群です。 |
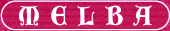 MELBA MELBA
|
|
|
世界初録音! 2台8手によるマーラーの「復活」
マーラー:交響曲第2番ハ短調「復活」
(ハインリヒ・フォン・ボックレット編・2台ピアノ8手版) |
ブライアリー・カッティング
アンジェラ・ターナー
スティーヴン・エマーソン
スチュワート・ケリー(Pf) |
78’00”
マーラーの交響曲第2 番「復活」は1894 年に完成されました。その初演に先立ち、ベーン編曲による2
台ピアノ4 手版で試演されましたが、1895年にハインリヒ・フォン・ボックレットが4
人のピアニストのための2 台ピアノ8 手用編曲を行いました。さらに4
年後の1899 年にブルーノ・ワルターが1 台ピアノ4
手版編曲をしたため、作曲者公認のものとして3
種のピアノ・デュオ編曲が知られています。ベーンの2
台版、ワルターの連弾版はすでに録音が存在しますが、2
人の独唱と合唱、オルガンやバンダまで含む大編成の原曲は4
本の手に余るため、倍の8 手による効果と表現力が強みを発揮します。
オーディオが生まれる以前、大規模なオーケストラ曲を鑑賞する手段はピアノ用編曲が一番でした。そのなかで2
台ピアノを4 人で演奏する8 手は、多くの音を再現できるだけでなく、技術的負担も軽減され、さらに演奏に加わる楽しみもあることで、今日の想像以上にポピュラーで多くの編曲が産み出されました。この「復活」もそのひとつで、19
世紀後半の愛好家の音楽需要が伺える点でも重要な資料と申せましょう。
4 人で弾くため、クライマックスの盛り上がりと音量はすさまじいのひとことに尽きますが、全体としては思いのほかすっきりしていて室内楽的なのに驚かされます。独唱や合唱の部分も工夫がなされていて思わずひきこまれる世界となっています。
演奏の4 名はいずれもオーストラリアの実力派。ブライアリー・カッティングとアンジェラ・ターナーはデュオを組んでもいて、絶妙なバランスを聴かせてくれます。
マーラーの交響曲第2 番がまったく新しいピアノ曲として眼前に姿を現します。 |
 NAIVE NAIVE
|
|
|
アレッサンドリーニ率いるコンチェルト・イタリアーノ、30周年記念アルバム!
1. モンテヴェルディ(1567-1643):『オルフェオ』よりトッカータ
2. モンテヴェルディ:『音楽の諧謔』より”Damigella
tutta bella”
3. モンテヴェルディ:
マドリガーレ集第5巻より”つれないアマリッリ(Cruda
Amarilli)”
4. モンテヴェルディ:マドリガーレ集第8巻より”Ballo
dell’Imperatore”
5. マレンツィオ(1553-1599):
マドリガーレ集第7巻より”つれないアマリッリ(Cruda
Amarilli)”
6. フィリッポ・デ・モンテ(1521-1603):
マドリガーレ集第17巻より”Di mie dogliose
note”
7. ルカ・ルッツァスキ(1545-1607):
マドリガーレ集第5巻より”Ahi, cruda sorte
mia”
8. ジェズアルド(1560-1613):Asciugate
i begl’occhi
9. A.スカルラッティ(160-1725):
アニュス・デイ(Messa per il Santissimo
Natale)
10. ベンチーニ(1675?-1755):8 声のマドリガーレ”Quia
fecit mihi magna”
11. ヘンデル:歌劇「アレッサンドロ」HWV21より序曲
12. ヘンデル:歌劇「インド王ポーロ」HWV28より
二重唱アリア”Caro! Dolce! Amico amplesso”
〔サンドリーヌ・ピオー(S)、サラ・ミンガルド(A)〕
13. ボノンチーニ:スターバト・マーテルより
14. ヴィヴァルディ:協奏曲 ハ長調 RV554aよりアレグロ
15. ヴィヴァルディ:祝されたセレナータ RV
593より
16. ヴィヴァルディ:協奏曲 ト短調 RV 156よりアレグロ
17. ヴィヴァルディ:協奏曲 ト長調 RV 160よりアレグロ
18. Frantisek Ignak Angonin Tuma(1704-1774):
シンフォニア 変ロ長調よりアンダンテ
19. J.S.バッハ:イタリア協奏曲 BWV 971よりアレグロ
20. J.S.バッハ:フーガの技法よりコントラプンクトゥス7
21. J.S.バッハ:協奏曲 ヘ長調 BWV1057よりアレグロ・アッサイ
22. J.S.バッハ:ブランデンブルク協奏曲
BWV1049よりプレスト
23. モンテヴェルディ:聖母マリアの夕べの祈りより
24. アレッサンドリーニ:シャコンヌ |
リナルド・アレッサンドリーニ
(指揮、チェンバロ)
コンチェルト・イタリアーノ |
アレッサンドリーニ率いるコンチェルト・イタリアーノ、30周年記念アルバム!バロック名曲の聴きどころ満載
アレッサンドリーニ率いる名門アンサンブル、コンチェルト・イタリアーノの結成30
周年を記念して編まれたアルバム。ルネサンスからバロック、さらにアレッサンドリーニ自身の作品までを網羅した、聴きどころ満載の1枚です! |
 SUPRAPHON SUPRAPHON
|
|
|
「ゼーリング〜バロック期プラハの教会でのクリスマスの音楽」
ゼーリング:
・「天よ、高所より露を滴らせてください」第1
・公現節のためのアリア「雷鳴と霰」
・「天よ、高所より露を滴らせてください」第2
・降誕祭モテット「恐れを捨て」
・二重唱「寵愛はおおいなる力」
・降誕祭モテット「眠れわが子よ」
フックス:
・3声のパストラーレ・ソナタKV397
ゼーリング:
・パストレラ「ああ、急ぎ行き」
・パストレラ「ああ、羊飼いが起き」
・パストレラ「流れに憩う鹿ではなく」
・全ての祝日のためのアリア「汝、明るき星」
・パストレラ「眠れ、優しく」
・3人の聖王のオッフェルトリウム「見よ、東方より博士たちが」 |
ハナ・ブラシコヴァ(ソプラノ)
マルケータ・ククロヴァー(アルト)
トマーシュ・クラール(バリトン)
ヤナ・セメラードヴァー(指揮)
コレギウム・マリアヌム |
バロック期プラハに響く敬虔な祈り色彩感豊かなクリスマスの歌
収録:2014 年7 月25、27&28 日/プラハ、鎖の下の聖母マリア教会/DDD、ステレオ、71’19”
チェコほど、クリスマスの曲のレパートリーが豊富で、色彩感あふれるものを有する国は稀でしょう。特に、バロック時代は、魅力あふれ感動を呼び起こす詩学に基づいた、畏敬の念に打たれた羊飼いが美しき幼子イエスに夢中となるテキストが使われ、伴奏付きアリアや二重唱の形式をとって、より複雑なパストラーレが増加していました。
この点で、特に注目すべき作曲家として、この録音に取り上げられた、ヨゼフ・アントニーン・ゼーリング(1710
− 1756)がいます。まだ、バロック時代にとどまり、前古典派時代には足を踏み入れていませんが、その新しい音楽様式導入の道を開いたことで知られています。彼はウィーンで学んだ後、この録音が行われた聖母教会を含むいくつかのプラハの教会のカペルマイスターを務めつつ、モルツィン伯の有名な管弦楽団の一員、聖ヴィート大聖堂の第2ヴァイオリン奏者も務めていました。
この録音は、待降節から御公顕の祝日までの期間の曲を取り上げており、彼の代表作であり、18
世紀前半のボヘミアにおけるこの分野の重要な作品と言える、降誕祭モテットやパストレラを含んでいます。その音楽は一世代前のミフナの歌曲の魅力をまだ含んでおり、同時に、次世代のリバのクリスマス・ミサとなじみのある世界に開かれています。 |
 AVIE AVIE
|
|
|
J.S.バッハ:オーボエとオーボエ・ダモーレのための協奏曲集
協奏曲ト短調 BWV.1056R
協奏曲ヘ長調 BWV.1053R
協奏曲ニ短調 BWV.1059R
オーボエ・ダモーレ協奏曲イ長調 BWV.1055R
オーボエとヴァイオリンのための協奏曲ハ短調
BWV.1060R |
モニカ・ハジェット(ディレクター)
ゴンサロ・ルイス
(オーボエ、オーボエ・ダモーレ)
ポートランド・バロック・オーケストラ
|
モニカ・ハジェット、ゴンサロ・ルイスのコンビ再び!J.S.バッハのオーボエ&オーボエ・ダモーレ協奏曲集!
バロック・ヴァイオリンの世界的パイオニア、モニカ・ハジェットが音楽監督を務めているアメリカ、オレゴン州のピリオド・オーケストラ、ポートランド・バロック・オーケストラとピリオド・オーボエの名手、ゴンサロ・ルイスによるJ.S.バッハの協奏曲集はオーボエ&オーボエ・ダモーレが主役!
J.S.バッハの管弦楽組曲(AV2171)で絶賛を博したコンビによるバッハの続編は、チェンバロ協奏曲から再構成、再構築を行い、オーボエ、オーボエ・ダモーレのための作品へと姿を変えた5つの協奏曲。バッハが思い浮かべたであろうオーボエの音色を、名手ゴンサロ・ルイスの演奏で伺うことが出来る。バッハ・ファン要注目!

|
| |
|
|
古えからの約束 〜 クリスマス・コレクション
バーニー:あめにはさかえ
ウェールズ民謡:広間を飾ろう
ナイルズ:おやすみ,小さな子
15世紀(トリニティー・ロール):かくも麗しいバラはない
ホルスト:わたしは歌う,並ぶべきものなき乙女のことを
ブリテン:「キャロルの祭典」より かくも麗しいバラはない
マクスウェル=デイヴィス:おお偉大なる神秘よ
中世の聖歌:チェスターの尼僧の歌
マクスウェル=デイヴィス:天なる父
中世の聖歌:チェスターの尼僧の歌
マクスウェル=デイヴィス:おお偉大なる神秘よ
15世紀(リトソンの写本):ルレイ,ルロウ
ナイルズ:さまよいながらわたしは不思議に思う*
民謡:スティンズのモリス・ダンス
15世紀(トリニティー・ロール):称えよ,恩寵満ちみてるマリアを
イングランド民謡:マリア様の7つの喜び
ウィアー:輝け,イェルサレムよ
アイルランド民謡:良き人々はみな,このクリスマスの季節に
ナイルズ:乙女マリア様のことを歌おう
ヴォーン・ウィリアムズ:ベツレヘムのまちに
アイルランド民謡:クリスマス・イヴ
グレゴリオ聖歌:今日,キリストは生まれ給う
ホルスト:イエスよ,乙女より生まれし方よ
ブリテン:四月の露のように
マダン:見よ!そのお方は来たる,雲に乗って |
アンドルー・パロット(指揮)
タヴァナー・コンソート&合唱団
エミリー・ヴァン・エヴェラ(ソプラノ)*
|
タヴァナー・コンソートのクリスマス・コレクション!
アンドルー・パロットと、タヴァナー・コンソート&合唱団の中世をテーマとしたクリスマス・アルバム。ブリテンやホルストと言った、中世に関連のある20世紀の作曲家の作品も収録され、7世紀の時代を越える貴重なコレクションである。
※録音:1998年5月5日−9日、セント・ジュード・オン・ザ・ヒル教会(ロンドン、イギリス) |
| |
|
AV 2318
(3CD/特別価格)
\5100
|
ベートーヴェン:中期弦楽四重奏曲集
弦楽四重奏曲第7番ヘ長調 Op.59-1 《ラズモフスキー第1番》
弦楽四重奏曲第8番ホ短調 Op.59-2 《ラズモフスキー第2番》
弦楽四重奏曲第9番ハ長調 Op.59-3 《ラズモフスキー第3番》
弦楽四重奏曲第10番変ホ長調 Op.74 《ハープ》
弦楽四重奏曲第11番ヘ短調 Op.95 《セリオーソ》 |
サイプレス弦楽四重奏団 |
ドヴォルザークの「糸杉」をアンサンブル名として、アメリカ、サンフランシスコを拠点に活躍するサイプレス弦楽四重奏団。
アンサンブルのルーツでもあるドヴォルザークの「糸杉」(AV2275)、ドヴォルザークと同世代のアメリカ人作曲家(AV2304)、19世紀王道のシューベルト(AV2307)に続くアヴィー(Avie)からのリリース第4弾では、"楽聖"ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン(1770−1827)の中期弦楽四重奏曲集。過去3作品も高く評価されており、アメリカ西海岸の実力派アンサンブルが奏でるベートーヴェンも大いに期待出来ができる。 |
 CHANDOS CHANDOS
|


CHSA 5142
(SACD HYBRID)
\2800 →\2590 |
ガードナー&ベルゲン・フィル
ヤナーチェク:管弦楽作品集 Vol.1
シンフォニエッタ JW VI/18
カプリッチョ JW VII/12
組曲 《利口な女狐の物語》 IW I/9
(2008年マッケラス最終改訂版) |
ジャン=エフラム・バヴゼ(ピアノ)
エドワード・ガードナー(指揮)
ベルゲン・フィルハーモニー管弦楽団 |
ガードナーのヤナーチェク始動!第1弾は"シンフォニエッタ"!
イングリッシュ・ナショナル・オペラの若き音楽監督、エドワード・ガードナーによるヤナーチェクのシリーズがスタート!
1765年に創設されたノルウェーの伝統あるオーケストラ、ベルゲン・フィルハーモニー管弦楽団は、現在ガードナーが首席客演指揮者に在籍、オーケストラの創立250周年を迎える2015年からは首席指揮者(Chief
Conductor)に就任が決まっており、今後の活躍もますます期待されるコンビ。
新シリーズ第1弾では、ヤナーチェクのもっとも成功した、そして人気を誇る「シンフォニエッタ」を軸に、ピアノ(左手)と管楽器のための「カプリッチョ」では、ジャン=エフラム・バヴゼがソリストを担当(バヴゼの左手といえば、ラヴェルの左手のためのピアノ協奏曲(CHSA
5084)も記憶に新しい)! そして、偉大な指揮者であり特にヤナーチェクの録音・紹介で功績を残すチャールズ・マッケラスによる最終改訂版(Final
Rivisions)の組曲「利口な女狐の物語」。
管弦楽の充実が嬉しいChandosから、また期待の新シリーズが始まります!

|
| |
|
|
ブラームス:ピアノ独奏作品集 Vol.3
ワルツ集 Op.39/主題と変奏ニ短調/
間奏曲ロ短調 Op.119-1/間奏曲ハ長調 Op.119-3/
間奏曲ホ短調 Op.116-5/
ピアノ・ソナタ第2番嬰ヘ短調 Op.2 |
バリー・ダグラス(ピアノ) |
アイルランドの名手バリー・ダグラス!クララ・シューマンに捧げられたソナタ第2番!
ルイ・ロルティ、イモジェン・クーパー、ジャン=エフラム・バヴゼと共にシャンドス(Chandos)のピアノ・ワールドを支えるアイルランドの名ピアニスト、バリー・ダグラス。1986年の第8回チャイコフスキー国際コンクールのピアノ部門で、クライバーン以来となるロシア人以外でのゴールド・メダリストに輝いた名手が弾くブラームス。
待望の第3巻は、クララ・シューマンに捧げられたブラームスの若き秀作「ピアノ・ソナタ第2番」をメインに、クララ・シューマンから求められて弦楽六重奏曲第1番の第2楽章からピアノ独奏用として編曲された「主題と変奏」、4手連弾用に作曲され独奏版としても編曲された「16のワルツ」など、ブラームスの魅力的な作品が並ぶ。
2015年初頭には来日公演も予定し、日本での活躍がますます期待されるバリー・ダグラス。武蔵野市民文化会館のリサイタルでは、この新譜に収録された「主題と変奏」を演奏予定です!
バリー・ダグラス 来日公演情報!
2015年1月26日(月) 武蔵野市民文化会館
ブラームス:主題と変奏、ピアノ・ソナタ第2番、他
2015年1月30日(金)&31日(土) 札幌コンサートホールKitara
ブラームス:ピアノ協奏曲第2番

|
| |


CHSA 5140
(2SACD HYBRID)
\5600 →\5190 |
アンドルー・デイヴィスのゲロンティアス!
エルガー:
オラトリオ 《ゲロンティアスの夢》 Op.38*
歌曲集 《海の絵》 Op.37 |
サラ・コノリー(メゾ・ソプラノ)
スチュアート・スケルトン(テノール)*
デイヴィッド・ソアー(バス)*
アンドルー・デイヴィス(指揮)
BBC交響楽団、
BBC交響合唱団* |
2014年にエルガー・メダル受賞!アンドルー・デイヴィスのゲロンティアス!
アンドルー・デイヴィス&BBC交響楽団の新録音は、故リチャード・ヒコックスより受け継いだ「英国音楽の伝道師」の名に相応しく、エルガーの大曲「ゲロンティアスの夢」!
併録されたコントラルトと管弦楽のための連作歌曲集「海の絵」では、ザ・シックスティーンやロリン・マゼール、キングズ・コンソート、ガブリエリ・コンソートなどと共演を重ねてきた世界的メゾ・ソプラノ、サラ・コノリーの歌声が響く。
また、チャールズ・マッケラスの「第九」やマイケル・ティルソン・トーマスの「大地の歌」、シアトル・オペラの「ニーベルングの指輪」などに独唱として参加してきたスチュアート・スケルトン、ウェールズ・ナショナル・オペラを中心に、数々のオペラ、オラトリオの独唱を努め、サイトウキネン・フェスティバル松本2014でも来日予定のデイヴィッド・ソアーなど、「ゲロンティアスの夢」の歌手陣も豪華。
アンドルー・デイヴィスは2014年の4月には、エルガーの音楽への貢献が評価され、エルガー協会メダルを受賞。エルガー指揮者として自他ともに認められたばかりのデイヴィスが振るゲロンティアスの夢。長い間名盤として親しまれたリチャード・ヒコックス盤「ゲロンティアスの夢(CHAN
241-46)」に続く、新たな名盤の誕生です。 |
| |

CHAN 10831
(2CD/特別価格)
\2400 |
ハイドン:弦楽四重奏曲集 Vol.1 〜 太陽四重奏曲集
Op.20
弦楽四重奏曲第31番変ホ長調 Op.20-1,Hob.III-31
弦楽四重奏曲第32番ハ長調 Op.20-2,Hob.III-32
弦楽四重奏曲第33番ト短調 Op.20-3,Hob.III-33
弦楽四重奏曲第34番ニ長調 Op.20-4,Hob.III-34
弦楽四重奏曲第35番ヘ短調 Op.20-5,Hob.III-35
弦楽四重奏曲第36番イ長調 Op.20-6,Hob.III-36 |
ドーリック弦楽四重奏団
〔アレックス・レディントン(第1ヴァイオリン)、
ジョナサン・ストーン(第2ヴァイオリン)、
エレヌ・クレモン(ヴィオラ)、
ジョン・マイヤーズコフ(チェロ)〕 |
新生ドーリックのハイドン! 太陽四重奏曲集!
英グラモフォン誌で『最も優れた若手弦楽四重奏団の1つ』と絶賛され、シャンドスが次世代のメイン・アーティストとして期待を寄せるイギリスのアンサンブル、ドーリック弦楽四重奏団。ヴィオラ奏者に新たに迎えられたのは、2012年東京国際ヴィオラ・コンクールで特別賞を受賞したフランスの若き才能、エレヌ・クレモン。新たなメンバーとなり、前作のショーソン(CHAN
10754)以来1年半ぶりに発売される新譜からは、ハイドンの弦楽四重奏シリーズがスタート!
ドーリック弦楽四重奏団のハイドン第1弾は、エステルハージ家に仕えるハイドンが生み出した数々の傑作の中の一つ、1772年に出版された「太陽四重奏曲集」。従来の楽器の役割りを覆し、新たな表現力の可能性を広げ、四重奏の範囲が万華鏡のように輝く太陽四重奏曲。これらの独創性に富んだ作品を、世界最高の若手アンサンブルのひとつ、ドーリック弦楽四重奏団が鮮烈に描いてくれることでしょう。 |
| |


CHAN 10834
(4CD/特別価格)
\7200 →\6590 |
ハルヴォルセン:管弦楽作品集
CD1:
ロシア領主たちの入場/
ヴァイオリンと管弦楽のための《アンダンテ・レリジオーソ》*/
《仮面舞踏会》からの組曲/メランコリー/交響曲第1番
CD2:
古風な組曲/3つのノルウェー舞曲*/ノルウェーの旋律*/
ベスレモイの歌*/交響曲第2番 《宿命》
CD3:
交響曲第3番ハ長調(フォスハイム校訂版)/黒鳥/
結婚行進曲Op.32-1*/カラスの森のワタリガラスの結婚/
フォッセグリムOp.21†‡/
ベルゲンシアーナ 〜 ベルゲンの古謡によるロココ変奏曲
CD4:
ノルウェー祝典序曲/ノルウェー狂詩曲第1番/
ノルウェー狂詩曲第2番/パッサカリアOp.20-2‡§/
ノルウェー結婚行進曲(原曲:グリーグ/編曲:ハルヴォルセン)/
《女王タマーラ》より 踊りの情景/交響的間奏曲/
ノルウェーのおとぎ話Op.37 |
ネーメ・ヤルヴィ(指揮)
ベルゲン・フィルハーモニー管弦楽団
マリアンネ・トゥーシェン
(ヴァイオリン)*
ラグンヒル・ヘムシング
(ハルダンゲル・フィドル)†
メリーナ・マンドッツィ
(ヴァイオリン)‡
イルゼ・クラヴァ(ヴィオラ)§ |
ヤルヴィのハルヴォルセンが4巻セットになって登場!
エストニアの音楽一族"ヤルヴィ家"のドン、ネーメ・ヤルヴィ。Chandosの北欧レパートリー充実を決定づけた、ハルヴォルセンの管弦楽作品集Vol.1〜Vol.4がセットになって登場!
ヨハン・ハルヴォルセン(1864−1935)は、ベルゲン・フィルのコンサートマスターから首席指揮者に抜擢され、1899年にはクリスチャニア国立劇場の指揮者に就任するなど、ヴァイオリニスト、指揮者としても高名な、ノルウェーの国民的作曲家。
グリーグやスヴェンセンが確立したノルウェー国民楽派の後継者であると同時に、フランスのロマン派音楽を彷彿とさせる輝かしいオーケストレーションを描くなど、その多彩な作風が持ち味であり魅力である。
ハルヴォルセンの遺した3つの交響曲から、ノルウェーの民族楽器ハルダンゲル・フィドル(ハーディングフェーレ)を使用した「フォッセグリム」など民族主義の影響の強い作品まで、ハルヴォルセンの魅力を満載したセットです。
ハルヴォルセン自身も得意だったヴァイオリンと管弦楽のための数々の作品でソリストを務める、ノルウェーのリーディング・ヴァイオリニスト、マリアンネ・トゥーシェンの好演もポイント。
※録音:2009年8月24日−9月2日、2010年8月30日−9月1日、2011年8月22日−23日グリーグホール(ベルゲン/ノルウェー) |
| |
|
|
シンフォニック・ユーフォニアム 〜 ユーフォニアム協奏曲集
ホロヴィッツ:ユーフォニアム協奏曲
ウィルビー:ユーフォニアム協奏曲
ホディノット:ユーフォニアム協奏曲
《The Sunne Rising−The King Will Ride》
ジェンキンス:ユーフォニアム協奏曲 |
デイヴィッド・チャイルズ(ユーフォニアム)
ブラムウェル・トヴェイ(指揮)
BBCウェールズ・ナショナル管弦楽団
|
デイヴィッド・チャイルズがChandosに登場!英国が誇る名手によるユーフォニアム協奏曲集!
2000年にBBCヤング・ミュージシャン・オヴ・ザ・イヤー・コンペティションのファイナリストとしてテレビ放映された際に、マーティン・ウィルビーの世界初演を成功させ、一躍世界的ユーフォニアム奏者の仲間入りを果たした、デイヴィッド・チャイルズが吹く「ユーフォニアム協奏曲集」がシャンドス(Chandos)より登場!
1972年のナショナル・ブラス・バンド・フェスティヴァルのために委嘱され、日本では日本管打楽器コンクールで常に課題曲として取り上げられ、ユーフォニアム奏者なら誰でも一度は演奏したことがあるであろうホロヴィッツのコンチェルトをはじめ、チャイルズが世界初演を成し遂げ、高速パッセージで高い技術力を要する難曲、ウィルビーのコンチェルト。ロンドン初演を成功させたホディノットの深く柔軟な音楽性が求められる知られざるコンチェルト。チャイルズのレパートリーの中でも人気が高いジェンキンスのコンチェルト。どれもユーフォニアムにとってもチャイルズにとっても重要なレパートリーを選曲。
共演は、エミリー・バイノンとのフルート協奏曲(CHAN
10718)やリチャード・ワトキンスのホルン協奏曲(CHAN
10822)で完成度の高い演奏を聴かせてくれたトヴェイ&BBCウェールズ・ナショナル管弦楽団のコンビ。普段ピアノ伴奏で聴くことが多いユーフォニアム協奏曲を、BBCウェールズ・ナショナル管弦楽団のオーケストラサウンドと、チャイルズの輝かしくも柔らかく暖かいユーフォニアムサウンドで。両者のコンチェルトに期待せずにはいられない。 |
 NAXOS NAXOS
|


8.573276J
\1100 |
細川俊夫:管弦楽作品集 第2集
1.オーケストラのための「夢を織る」(2009)/
2.室内オーケストラのための「開花 II」(2011)/
3-11.オーケストラのための「循環する海」(2005)
<Introduction-序/Silent Ocean-静かな海/
Waves from the Ocean-海の波/
Cloudscape in the Sky-空の雲模様/
Storm-嵐/Waves-波/
Breeze on the Ocean-海を渡る風/
The Water returning to the sky again-
空から再び戻る水/
Mist on the Ocean-海の上の霧>
※世界初録音…1.3-11, 3-11…8.570775に既収録 |
ロイヤル・スコティッシュ・ナショナル管弦楽団…1-2/
フランス国立リヨン管弦楽団…3-11/
準・メルクル(指揮) |
録音 2013年6月10-12日 スコットランド グラスゴー,ヘンリーウッド・ホール…1-2,
2007年7月15日 フランス,オーディトリウム・ド・リヨン…3-11
現代日本の作曲家の中でも、ワールドワイドで最も高い評価を受けている人といえば、やはり細川俊夫(1955-)であることは間違いありません。
彼の作品には、日本的な要素(音色も思考も)が極めて多く用いられているのですが、その語法の巧みさと真摯さによって、それらが言葉の壁を越えて世界中の人々へと伝播しているのですから。
ここに収録された3つの作品は、それぞれ異なる源泉から生まれています。「夢を織る」は彼自身が母の胎内にいた時の仄かな記憶とも夢とも取れるもの。永遠の揺りかごである子宮の中に聞こえてくる音は“変ロ音”。柔らかく全てを絡めとっていくようなこの音に包まれながら、彼は大いなる旅に出発するというのです。そして「開花」は彼の得意とする花がテーマとなった曲。花が開くときに必要とする莫大なエネルギーを生きる力に変換するという繊細で遠大なる作業…これについての考察です。
そして「循環する海」。こちらは水の姿の変容を音に映したものであり、「海を出発してまた海へと還る」というひたすら永遠に繰り返される現象が言葉を介さず、音だけで描かれていきます。聴き手はこのアルバムで、たくさんのことを考えることができるでしょう。
作曲者本人による詳細な解説が付いています。 |
| |


8.573170
\1100 |
プーランク:バレエ組曲(ピアノ編曲版)
1-8.バレエ組曲「模範的な動物たち」FP111(1940-1941)
(グラント・ヨハンセン編)
<第1曲:夜明け/第2曲:熊と二人の仲間/
第3曲:セミと蟻/第4曲:恋するライオン/
第5曲:中年男と二人の花嫁候補/
第6曲:死神ときこり/
第7曲:2羽の雄鳥/第8曲:昼食>/
9-14.バレエ音楽「牝鹿」FP36(1923)(ピアノ版)
<第1曲:序曲/第2曲:ロンド/
第3曲:アダージェット/第4曲:ラグ-マズルカ/
第5曲:アンダンティーノ/第6曲:フィナーレ>/
15-22.バレエ音楽「オーバード」 FP51(1929)(ピアノ版)
<トッカータ/レチタティーヴォ、ディアーヌの仲間たち/
ロンド、ディアーヌと仲間たち/
ディアーヌの化粧室/
レチタティーヴォ、「ディアーヌのヴァリアシオン」への序奏/
アンダンテ、ディアーヌのヴァリアシオン/
ディアーヌの絶望/ディアーヌの別れと出発>
※1-8…デジタルによる世界初録音,
9-22…ピアノ版による世界初録音 |
ジャン・ピエール・アルマンゴー(ピアノ) |
録音 2013年2月21-23日…15-22, 2013年3月28-29日,4月6-7日…9-14,
2013年4月11-13日,5月3日…1-8 パリ イヴリー=シュル=セーヌ,ピエール・マルボス,スタジオ「4'33”」
軽妙洒脱、そして繊細でユーモラスなプーランク(1899-1963)の作品には汲めども尽きぬ魅力があります。そのメロディの歌わせ方、ハーモニー、リズムのどれもが、いかにもフランス風であり、決して革新的ではなかったにせよ、独自の世界を築き上げたことは間違いありません。
ここで聞く事のできるピアノ版のバレエ作品は、とても珍しいものですが、彼自身はバレエ作品を書くとき、他の作曲家のようにまず「ピアノ・スコア」を作成し、それを管弦楽版に仕立てることが多く(バレエのリハーサルのために)、これらもそんなスコアに基づいて演奏されています。
パリ・オペラ座からの依頼で作曲された「模倣的な動物たち」。詩人ラ・フォンテーヌの「寓話」からテキストが取られたこの物語、ありがちなお話の中にピリリと教訓が込められた小気味のよいものなのですが、プーランクは音楽で更に創造的な世界を描きあげています。こちらのピアノ版は作曲家自身が同意した1951年のヨハンセンによるヴァージョンで演奏されています。
タイトルに「若い娘たち」の意味がある「牝鹿」も人気作品。バレエ曲でもあり、協奏曲でもある「オーバード」(夜明け)は、恋を禁じられた女神ディアーヌの失恋物語。彼の私生活の失意が反映されているとも言われています。 |
| |

8.573308
\1100 |
ロシアの回想
1-3.コンスタンティン・ヴァシリエフ(1970-):
3つの森の絵(2001)
<古い楢の樹/スノードロップ/森の亡霊の踊り>/
4.セルゲイ・ルドネフ(1955-):古い菩提樹(1978)/
5.ヴァシリエフ:白鳥の王女(2010)
(イリナ・クリコヴァに捧げる)/
6.ヴィクトル・コズロフ(1958-):ロシアの大地への献呈(1990)/
7-9.ヴァシリエフ:3つの叙情的小品(2003)
<セルゲイ・ラフマニノフの思い出へのエレジー/
アグスティン・バリオスの思い出への回想/
ヘクトル・ヴィラ=ロボスの思い出へのモギアナ>/
10.ルドネフ:切り立った岸の間に-即興(1980)/
11.コズロフ:さまよえるオランダ人(1993)/
12.コズロフ:美しきエレーナのためのバラード(1994)
※5.10…世界初録音 |
イリーナ・クリコヴァ(ギター) |
録音 2013年10月3-6日 カナダ オンタリオ,聖ジョン・クリソストム教会
すでにNAXOSから2枚のアルバム(8.572717,
8.572390)をリリースし、2013年には来日公演も行い、その才能を存分に見せつけたロシアのギタリスト、イリーナ・クリコヴァ。見た目は実に愛らしい女性ですが、実は数多くのコンクール受賞歴はもちろんのこと、25年に渡る演奏活動を続けているという、相当な実績のある人なのです。
そんな彼女の今回のアルバムは、故郷であるロシアの現代音楽集。現代と言っても前衛的な作品ではなく、どれもが詩情溢れるステキな作品です。
静けさと活気が絶妙にブレンドされたヴァシリエフの作品から、聴き手の耳をひきつけることは間違いなし。クリコヴァの深みのある音色は、郷愁と憧憬を呼び起こし、その技巧とともに深く深く心に染み込んでくることでしょう。
NAXOSの数あるギターアルバムの中でも、とりわけ強くオススメしたい1枚です。 |
| |


8.573412
\1100 |
イタリアのソプラノ・アリア集
1.レスピーギ(1879-1936):日没 P.101/
2.プッチーニ(1858-1924):歌劇「蝶々夫人」-
第2幕 ある晴れた日に/
3.ヴェルディ(1813-1901):歌劇「オテロ」-
第4幕 ご主人様のお心はずっと静まりましたでしょうか?-
私の母は一人の気の毒な女中を使っていたの(柳の歌)-
アヴェ・マリア/
4.プッチーニ:歌劇「トゥーランドット」-
第1幕 お聞きください、ご主人様/
5.プッチーニ:歌劇「ラ・ボエーム」-
第3幕 さようなら、あなたの愛の呼ぶ声に/
6.プッチーニ:歌劇「修道女アンジェリカ」-母もなしに/
7.プッチーニ:歌劇「つばめ」-
第1幕「ドレッタの美しい夢」/
8.カタラーニ:歌劇「ラ・ワリー」-
第1幕「さようなら、ふるさとの家よ」/
9.プッチーニ:歌劇「ジャンニ・スキッキ」-
第1幕「私のお父さん」 |
マリア・ルイジア・ボルシ(ソプラノ)/
ロンドン交響楽団/
イブ・アベル(指揮) |
録音 2013年12月2-3日 UK ロンドン,リンドフルスト・ホール,エア・スタジオ
恐らくこの作品は、ソプラノ歌手マリア・ルイジア・ボルシが自身の真価を問うものなのだと思うのです。
あまりにも美しくあまりにも切ない歌。本来は弦楽四重奏とメゾ・ソプラノのための作品ですが、ここではオーケストラの伴奏に載って切々と歌われます。音の一つ一つに意味があるようなこの静かな叫びの意味を知りたくて、テキストを読み込んでみたくなりました。元々は英語の詩をイタリア語に翻訳した文章…最初はよくある男女の物語だと思いました。
気の弱い男が憧れの女性に思いを告げ、嬉しい返事をもらい、そのまま夕暮れの道を歩み、一夜を共にする…なるほど、タイトルの「日没」はそこから来ているのだな。
しかし物語は一転します。その内容を知った時、この曲をもう一度繰り返して聴いてみたくなりました。そんな強い訴求力を持つ歌を歌うこの歌手。
日本にも度々来日して、聴衆を魅了している若手です。本当に素晴らしい歌い手の登場です。もちろん全ての曲が極上です。 |
| |


8.572865
\1100 |
ヨーゼフ・マルティン・クラウス:アリアと序曲集
1.歌劇「プロセルピナ」VB 19-序曲 /
2.あなたの無邪気な視線を VB 30/
3.あなたは恐れていますか?最愛の人よ VB
63/
4.あなたを愛することをやめることなど VB
59/
5.「グスタフ3世の誕生日のために」VB 41-序曲/
6.私が小さな神を見るとき VB 5/
7.「冒険家」序曲 VB 32/
8.時代の荒廃は VB 58/
9.聞いてくれ、行かないでくれ - 私の大切な人に
VB 55/
10.「グスタフ3世のための葬送カンタータ」VB
42-序曲/
11.私の痛みとため息を聞いてください VB
26
※2.3.4.6.7.11…世界初録音 |
モニカ・グループ(メゾ・ソプラノ)…2.3.1.6.8.9.11/
ヘルシンキ・バロック管弦楽団/
アーポ・ハッキネン(指揮) |
録音 2013年6月10-12日 フィンランド,エスポー、セッロ・ホール
奇しくもモーツァルトと同じ年に生まれるも、彼とは全く違う運命に翻弄されたヨーゼフ・マルティン・クラウス(1756-1792)。彼は25歳の時にストックホルムのグスタフ3世に宮廷音楽家として召抱えられ、数々の音楽経験を経て、君主が暗殺された際には「追悼音楽」を捧げ、その後まもなく彼自身も病のためこの世を去ります。それはモーツァルトが早すぎる死を迎えたほぼ1年後のことでした。
最近になって彼の作品が次々とリリースされ、その驚くべき才能に感嘆する人が増えてきましたが、まだまだ知られていない作品は多く、このアルバムの半分以上の作品も世界初録音となっています。劇音楽を得意としたクラウスらしく、序曲のどれもが溌剌とした美しさを有しており、またコンサート・アリアも素晴らしいものです。
注目すべきは、「私が小さな神を見るとき」VB5。これはクリスマスのための音楽で、牧歌的な雰囲気を湛えた木管楽器と、美しい独奏ヴァイオリンが、アルトの歌唱と絶妙な調和を見せています。モニカ・グループのつややかな美声でお楽しみください。 |
| |


8.573307
\1100 |
ジョアン・ファレッタ&バッファロー・フィル
バルトーク:交響詩「コッシュート」・2つのポートレート・組曲
1.交響詩「コッシュート」Sz.75a/
2-3. 2つのポートレート Op.5 SZ.37
<第1番:理想的なもの/第2番:みにくいもの>/
4-8.組曲 第1番 Op.3
<第1楽章:Allegro vivace/第2楽章:Poco
adagio/
第3楽章:Presto/第4楽章:Moderato/
第5楽章:Molto vivace> |
ミヒャエル・ルートヴィヒ(ヴァイオリン)…2.3/
バッファロー・フィルハーモニー管弦楽団/
ジョアン・ファレッタ(指揮) |
録音 2013年11月22.23日…1-3, 2013年10月19.20日…4-8
USA ニューヨーク,バッファロー,クレイン・ミュージック・ホール
ハンガリーの民俗音楽とクラシック音楽の融合を図り「管弦楽のための協奏曲」やミクロコスモス、弦楽四重奏曲などの素晴らしい作品を数多く書いたバルトーク(1881-1945)。しかし、そんな彼も最初からばりばりハンガリー風の音楽を書いていたわけではありません。
1898年にウィーン音楽院に入学する前の彼はブラームスの作品に影響を受けていましたが、交響詩「コッシュート」は21歳のバルトークがリヒャルト・シュトラウスの「ツァラトゥストラ」を聴いて衝撃を受け作曲したもので、題材こそはハンガリーの英雄に由来していますが、音楽はまさにシュトラウスそのもの。しかし色々な意味で世間を騒がせた上、彼も自信を持った問題作です。
「2つのポートレート」は彼が思いを寄せたヴァイオリニスト、シュテフィ・ゲイエルを意識して書かれたました。人間の2つの面を真摯に描き、彼女のモティーフを登場させることで、失恋の痛手を慰めたようです。「組曲」は彼がピアニスト、作曲家としての位置を確立させようとしていた頃の作品で、1905年に初稿が書かれましたが、後の1920年に改訂されています。壮大なオーケストラのファンファーレで始まる楽しい作品です。初演時のウィーンではセンセーショナルな話題を巻き起こした」とバルトーク自身がメモを残したとされています。 |
| |

8.572909
\1100 |
レーガー:オルガン作品集 第16集
1-4.レーガー:3つの小品 Op.7
<第1番:前奏曲とフーガ ハ長調(Track1-2)/
第2番:幻想曲「テ・デウム・ラウダムス」
イ短調/
第3番:フーガ ニ短調>/
5-19. J.S.バッハ(1685-1750):
2声のインヴェンション BWV772-786
(M.レーガー&K.シュトラウベによるオルガン編曲版)
<第1番 ハ長調 BWV 772/
第2番 ハ短調 BWV 773/
第3番 ニ長調 BWV 774/
第4番 ニ短調 BWV 775/
第5番 変ホ長調 BWV 776/
第6番 ホ長調 BWV 777/
第7番 ホ短調 BWV 778/
第8番 ヘ長調 BWV 779/
第9番 ヘ短調 BWV 780/
第10番 ト長調 BWV 781/
第11番 ト短調 BWV 782/
第12番 イ長調 BWV 783/
第13番 イ短調 BWV 784/
第14番 変ロ長調 BWV 785/
第15番 ロ短調 BWV 786>/
20-22.レーガー:52のやさしいコラール前奏曲
Op.67より
<第36番:われはわが神を歌わずにいられようか/
第37番:汝が怒りもてわれを罰したもうな/
第38番:われ汝に別れを告げん>/
23.前奏曲 ハ短調 Wo0 8-6/
24.フーガ ハ短調 Wo0 4-8/
25-26.前奏曲とフーガ ニ短調 Wo04-10/
27-28.J.S.バッハ:トッカータとフーガ ニ短調
BWV 913
(M.レーガーによるオルガン編曲版) |
クリスチャン・バルテン(オルガン) |
録音 2013年6月10-11日 ドイツ,フルラ大聖堂
リーガー・ザウアー・オルガン
レーガー(1873-1916)の偉大なるオルガン作品集もこの第16集で完結となります。このアルバムには彼の初期の作品である「3つの小品」Op.7と、「52のやさしいコラール前奏曲」の残り3曲、そして3つの遺作と、問題作「バッハの2声のインヴェンション」オルガン版が収録されています。
原曲はピアノ学習者や愛好家に良く知られているあの曲集ですが、レーガーと彼の友人シュトラウベは、この作品に基づくオルガンのためのトリオ・ソナタを作ることを考案。両手とペダルを完全に独立させ、オリジナルのメロディに新たな対旋律を組み合わせることで、全く新しい様相を持った作品が出来上がりました。
日頃聞きなれているはずの音楽が、素晴らしく荘厳に聞こえてくる様子は感動的。研究のためとは言え、ここまでするか!とため息が出てしまうほどの出来栄えです。
自らの作品を生み出すために、徹底的に先人の作品を研究するこの心意気、見習うべきところも多いのかも知れません。 |
| |


8.573108
\1100 |
リヒャルト/シュトラウス/ヴェルディ/プッチーニ:弦楽四重奏曲集
1-4.リヒャルト・シュトラウス(1864-1949):
弦楽四重奏曲 イ長調 Op.2 TrV95
<第1楽章:Allegro/
第2楽章:Scherzo: Allegro molto/
第3楽章:Andante cantabile, molto espressivo/
第4楽章:Allegro moderato>/
5.プッチーニ(1858-1924):菊/
6-8.プッチーニ:3つのメヌエット/
9-12.ヴェルディ(1813-1901):
弦楽四重奏曲 ホ短調
<第1楽章:Allegro/第2楽章:Andantino/
第3楽章:Prestissimo/
第4楽章:Scherzo Fuga: Allegro assai
mosso> |
エンソ弦楽四重奏団
<メンバー:
モーリーン・ネルソン(第1ヴァイオリン)/
ジョン・マルクス(第2ヴァイオリン)/
メリッサ・リアドン(ヴィオラ)/
リチャード・ベルチャー(チェロ)> |
録音 2012年7月30日-8月2日 カナダ オンタリオ,聖アン教会
リヒャルト・シュトラウスが16歳の時に作曲した弦楽四重奏曲は、彼の父の従兄弟であり、幼きシュトラウスにヴァイオリンを教えたベンノ・ワルター(ミュンヘン宮廷劇場のコンサート・マスター)によって初演された記念すべき作品です。
父の影響でモーツァルトやベートーヴェンを手本とするように指導されたシュトラウスの、折り目正しい作品ですが、この後彼は少しずつ父親の縛りから離れ、自らの語法を確立していくことになります。
プッチーニの「菊」は短くも感傷的で美しいエレジーです。3つのメヌエットはハイドンらしさを感じさせる短い作品です。
ヴェルディの弦楽四重奏曲は60歳の時の作品で、彼の唯一の室内楽作品です。なかなか演奏される機会に恵まれない作品群ですが、3人の作曲家の全く別の面を伺い知ることのできる名作といえるでしょう。
演奏しているエンソ弦楽四重奏団は1999年にイェール大学に設立され、2007年からニューヨークに拠点を置き活躍している団体。ルネサンスから現代までの幅広いレパートリーを持ち、中でもヒナステラの弦楽四重奏曲での名演は、他に並ぶものがありません。 |
| |
8.573176
\1100 |
ハーバート・ハウエルズ:スターバト・マーテル
他
1-7.スターバト・マーテル(1959-1965)
<悲しみの母は立っていた/嘆き、悲しみ/
涙をこぼさないものがあるだろうか/
さあ、御母よ/聖なる母よ/
私の心を燃やしてください/
キリストよ、私がこの世を去る時には/
テ・デウム(1944/1977)/
シネ・ノミネ(1922)> |
ベンジャミン・ヒューレット(テノール)…1-7.8/
アリソン・ヒル(ソプラノ)…9/
バッハ合唱団/
ボーンマス交響楽団/
デイヴィッド・ヒル(指揮) |
録音 2013年11月30日.12月1日 UK ドルセット,プール
ライトハウス
古今東西の宗教作品の中でも、高い人気を誇るのがこの「スターバト・マーテル」です。日本語にすると「悲しみの聖母」であり、歌い出しのラテン語“Stabat
mater dolorosa-悲しみの母は立っていた」がそのままタイトルに使われています。数多くの作曲家たちがこのテキストに思い思いの曲をつけています。
イギリスの作曲家、ハウエルズの「スターバト・マーテル」はドヴォルザークの作品と同様に、彼自身の9歳の息子、マイケルの突然の死が作曲の動機となりましたが、ハウエルズ(1892-1983)は曲に個人的な悲しみだけを盛り込むのではなく、1962年のキューバ危機や翌年のケネディ大統領の暗殺などの、厳しい世界情勢を危惧し、やがては核戦争への恐怖までをも内包した途方もない悲しみが含まれています。そのため曲は不安定であり、本当に悲しみに満ちていますが、時として驚くばかりの美しい響きも見てとれます。聴き手の内面の平穏を試すかのような不思議な音楽です。
打って変わって輝かしさ際立つ「テ・デウム」では開放的な明るさを体感できます。ヴォカリーズのみ(歌詞は持たない)の声とオーケストラの響きが交錯する「シネ・ノミネ」も神秘的な美しさを持っています。 |
| |


8.573204
\1100 |
イザベル・ファウスト!
ティエリー・ランシーノ:ヴァイオリン協奏曲
他
1-3.ヴァイオリン協奏曲(2005)
<第1楽章:Modere -
Accelere/Glisse-(Cadenza)-
Choral-Accelere/
第2楽章:Lent(Attacca)/第3楽章:Vif-Fugato>/
4-7.前奏曲とウェルギリウスの死
<前奏曲/間奏曲/ウェルギリウスの死/後奏曲>
※世界初録音 |
イザベル・ファウスト(ヴァイオリン)…1-3/
ルクセンブルク・フィルハーモニー管弦楽団…1-3/
アルトゥーロ・タマヨ(指揮)…2-3/
マッテオ・デ・モンティ(バリトン)…4-7/
フランス国立管弦楽団…4-7/
ジェラード・シュワルツ(指揮) |
録音 2005年11月3日 パリ,シャトレ劇場…1-3,
2000年12月2日 パリ,オーディトリウム・オリヴィエ・メシアン…4-7
あの衝撃的すぎるレクイエム(8.572771)で、その特異な作風を知らしめたフランスの作曲家ランシーノ(ランチーノ
1954-)。今回は名手イザベル・ファウストをソリストに迎えた「ヴァイオリン協奏曲」と、ローマの高名な詩人ウェルギリウスをテーマにした2つの作品を収録しました。
巨大な機械に見立てたオーケストラと、小さな木の作品(ヴァイオリン)が対峙することで生まれる様々な事象を抽象的に描くために、技術と想像力を駆使したという不思議なヴァイオリン協奏曲は、そのまま初演者であるイザベル・ファウストに捧げられています。
もうひとつの作品は、ローマの詩人ウェルギリウスが死を迎えた時の物語を描いたもの。この詩人には多くのエピソードがあり、生まれた物語も多々あります。
ランシーノは彼のエピソードをオペラ化しようと試みましたが、結局それは成就することはありませんでした。しかしこのアルバムの4曲の他、様々な管弦楽曲や声楽曲が生まれることになったというのです。この4曲からなるエピソードは激しく音がぶつかり合う前奏曲で始まり、星の煌きにも似た間奏曲、そして声楽を伴う「ウェルギリウスの死」が続き、最後は嘆くを鎮めるような後奏曲で幕を閉じます。 |
| |


8.573207
\1100 |
ボリス・チャイコフスキー:ピアノ五重奏曲・戦争組曲
1-4.ピアノ五重奏曲(1962)/
5-15.戦争組曲(1964/2011)
エレナ・アスタフィエヴァ&スタニスワフ・プロクディンによる編曲
<第1楽章:ワルツ(告別)/第2楽章:夜の突破(近道)/
第3楽章:道/
第4楽章:独奏クラリネットのためのワルツ主題(陣地)/
第5楽章:感謝/第6楽章:悲しげなワルツ(結末)/
第7楽章:邸宅/第8楽章:沼/第9楽章:分岐/
第10楽章:戦い/第11楽章:終曲(約束)>
※5-15…世界初録音 |
オルガ・ソロヴィエヴァ(ピアノ)…1-4/
マキシム・アニシモフ(クラリネット)…5.8.11.15/
ヴァンブラ四重奏団
<メンバー:グレゴリー・エリス(第1ヴァイオリン)…1-7.9-15/
キース・パスコー(第2ヴァイオリン)…5-7.9-11/
イオアナ・ペテク=コラン(第2ヴァイオリン)…1-4/
サイモン・アスペル(ヴィオラ)…1-7.9-15/
クリストファー・マルウッド(チェロ)…1-7.9-15> |
録音 2012年10月11日 モスクワ ロシア国営TV&ラジオ・カンパニー「Kultura」第1スタジオ…5-15,
2013年10月31日 モスクワ モスフィルム,トン・スタジオ…1-4
延々とピアノのユニゾンが奏され、そこに激しく切り込むヴァイオリンの不協和音。この刺激的な冒頭部分だけで耳を惹きつけられるピアノ五重奏曲。これを作曲したボリス・チャイコフスキー(1925-1996)は「ショスタコーヴィチの次の世代」における最も独創的な作曲家として高く評価されています。
1962年に書かれた「ピアノ五重奏曲」は前述の第1楽章に続く、リズミカルで旋律的な第2楽章と、変奏曲形式の第3楽章、そして表情豊かな最終楽章と、整ったフォルムを持つ作品であり、彼の最高傑作とみなされるものでもあります。
「戦争組曲」は1964年に製作されたユリ・フェイト監督による映画「前線を守りながら」のための音楽ですが、映画公開後にこのスコアは行方不明になってしまいます。
しかしボリス・チャイコフスキー協会が原稿を探索し、サンクトペテルブルクで発見、その後編集され、この形に落ち着きました。戦いに赴く若き将校ルサノフと、彼を待つ恋人カティア。友人とともに危険な任務を終え帰還したルサノフの目の前で流れ弾に当たって命を落とすカティア…最後のシーンで悲嘆に暮れ、家の外に立つルサノフ。こんなストーリーが悲しいワルツを伴いながら展開していきます。 |
| |
8.578287
\1100 |
J.シュトラウス2世:ヨハン・シュトラウス・アット・ジ・オペラ
1.ジプシー女のカドリーユ Op.24/
2.カドリーユ 「ロジェルの包囲」 Op.31/
3.マルタ・カドリーユ Op.46
(L.バビンスキによる管弦楽編曲)/
4.メロディーエン・カドリーユ Op.112/
5.インドラ・カドリーユ Op.122/
6.北極星カドリーユ Op.153/
7.カドリーユ「悪魔の分け前」(C.ポラックによる編曲)/
8.ディノーラ・カドリーユ Op.224/
9.オルフェウス・カドリーユ Op. 236/
10.新しい メロディーエン・カドリーユ Op.254/
11.カドリーユ「仮面舞踏会」 Op.272/
12.ファウスト・カドリーユ Op.277/
13.カドリーユ「アフリカの女」 Op.299/
14.こうもりカドリーユ Op.363 |
スロヴァキア国立コシツェ・フィルハーモニー管弦楽団…1.2.5.6.7.8.9.10.13.14/
スロヴァキア放送交響楽団…3.4.12/
ポーランド国立カトヴィツェ・フィルハーモニー管弦楽団…11/
アルフレード・ヴァルター(指揮)…1.2.5.8.10.13.14/
オリヴァー・ドホナーニ(指揮)…6.11/
ヨハネス・ヴィルドナー(指揮)…9.12/
ミヒャエル・ディットリヒ(指揮)…3/
アルフレッド・エシェヴェ(指揮)…4/
クリスティアン・ポラック(指揮)…7 |
J.シュトラウス全集(8.505226)より
NAXOSにおける偉大なるBOX「ヨハン・シュトラウス2世大全集」から抜粋した、楽しいカドリーユ集です。「カドリーユ」とはもともと4人の騎手が馬とともに四角い隊列を作って演じる軍事パレードでしたが、これが4組の男女が踊るダンスに転じ、18世紀に大流行したものです。
このシュトラウスの「カドリーユ」は当時流行したオペラ(自作も含め)やバレエなどの音楽を上手く貼り合せて、一連の舞曲にしたもので、元の曲は既に音楽史上から消えてしまったものもあったりと、実に興味深いものです。
現在でも残っているものをいくつか挙げると、例えば、トラック4はヴェルディの「リゴレット」から転用、トラック6はマイヤベーアの「北極星」(知られているとは言い難い?)、トラック9はオッフェンバックの「天国と地獄」、トラック11はヴェルディの「仮面舞踏会」、トラック12はグノーのファウスト、トラック12はマイヤベーアの「アフリカの女」、そして最後は自作の「こうもり」。誰もが口ずさめるメロディが軽やかに出現する、何とも楽しい曲ばかりです。
8.578787から8.578287に変更。 |
| |


8.660349
(3CD)
\3300→\2990 |
ミヨー:劇音楽「アイスキュロスのオレステイア」
<CD1>
1.アガメムノン Op.14/
2-8.コエフォール(捧げ物をする女たち) Op.24/
<CD2>
1-8.エウメニデス(慈愛の女神たち) Op.41
第1幕/
9-19.エウメニデス Op.41 第2幕/
<CD3>
1-20.エウメニデス Op.41 第3幕 |
クリネムネストラ…ロリ・フィリップス(S)/
オレステス…ダン・ケンプソン(Br)/
アポロ…シドニー・アウトロー(Br)/
女奴隷長…ソフィー・デルフィス(語り)/
アテナ/奴隷の女…ブレンダ・リー(S)/
アテナ…タマラ・マムフォード(Ms)/
アテナ…ジェニファー・レーン(C-A)/
プフィア(神託)…ジュリアンナ・ディ・ジャコモ(S)/
エレクトラ…クリスティン・エデル(Ms) 他/
UMSコーラル・ユニオン/
ミシガン大学室内合唱団/
ミシガン大学合唱団/
ミシガン大学オルフェウス・シンガーズ/
ミシガン大学パーカッション・アンサンブル/
ミシガン大学交響楽団/
ケネス・キースラー(指揮) |
録音 2013年4月4日 USA ミシガン,ミシガン大学
フランス6人組の中心的人物であり、また生涯に数多くの作品を残したダリウス・ミヨー(1892-1974)。ワーグナー的な和声を嫌い、ひたすら新古典的な響きを追求し、また古典文学や神話の世界にも興味を示した彼の作品には、複雑なリズムと多調性、そして妙に整った部分が入り混じっています。
この劇音楽は詩人ポール・クロデールがギリシャの三大詩人の一人アイスキュロスの「三部作」に台本をつけたものであり、アガメムノンと妻クリテムネストラの葛藤、娘エレクトラのクリテムネストラへの復讐、そして実際にクリテムネストラを手に掛けた息子オレステスの裁判-無罪判決までの一連の物語と通して、悲しみの連鎖の終結と、平和と調和への道筋を描くという壮大な物語です。曲は時として暴力的であり、至るところに直截的な響きが充満していますが、一度はまると癖になる音楽でもあるといえるでしょう。
まずはこれを聞く前に、一度ギリシア神話の該当箇所に目を通しておくと、一層理解が深まるかもしれません。 |
<マイナー・レーベル歴史的録音・旧録音>
 NAIVE NAIVE
|


V 5394
(4CD)
特別価格\2700 →\2490 |
マイ・フェイヴァリット・ショパン
[CD1&2](原盤:OP 30456)
グレゴリー・ソコロフ・プレイズ・ショパン
[CD1]ショパン:24の前奏曲op.28
[CD2]ショパン:ソナタ第2番変ロ短調
op.35、練習曲 op.25(全曲)
[CD3](原盤:V 5218)
ショパン:バラード(全4曲)、ピアノ協奏曲第2番
ヘ短調
[CD4](原盤:V 5229)
IMPRESSIONS ON CHOPIN〜キープ・スインギング・ショパン
(1)前奏曲op.26(遺作) (2)マズルカop.24-2
ハ長調
(3)練習曲op.10-6 (4)マズルカ op.33-2
ニ長調
(5)ノクターンop.15-1 へ長調 (6)エチュード
op.25-9 変ト長調
(7)マズルカ op.68-3 へ長調 (8)エチュード
op.25-4 イ短調
(9)マズルカ op.24-1 ト短調 (10)プレリュードop.28-7
イ長調
(11)マズルカ op.57-4 イ短調 (12)プレリュードop.28-3
ト長調
(13)ノクターンop.15-3 ト短調
(14)コントルダンス 遺作 変ト長調 (15)マズルカ
op.24-1 ト短調 |
[CD1&2]
グリゴリー・ソコロフ(ピアノ)
[CD3]
リーズ・ドゥ・ラ・サール(ピアノ)
ファビオ・ルイージ(指揮)
ドレスデン国立歌劇場管弦楽団
[CD4]
レシェック・モジジェル(ピアノ) |
naiveの名盤で編んだコンポーザー・ボックスの登場!My
favorite…マイ・フェイヴァリット・ショパン
[CD3]録音:協奏曲-2009年9月(ライヴ)/バラード-2010年2月(スタジオ録音) [CD4]録音:1999年
naive 人気アーティストたちの演奏でつづる、ショパン名盤が大変お買得ボックスとなって登場! |
<国内盤>
ミッテンヴァルト
|
ミッテンヴァルト名盤の待望の再プレス!
日本楽派シリーズ記念すべき第1弾・山田耕筰木野雅之による貴志康一のヴァイオリン作品集!
※長期欠品になっていた日本楽派シリーズの名盤2タイトルが再プレスされました。 |


MTWD 99003
【再プレス】
\2858+税 |
<日本楽派シリーズ 第1弾>
「山田耕筰:弦楽四重奏曲全曲・室内楽作品集」
弦楽四重奏曲第1番 ヘ長調(未完)
弦楽四重奏曲第2番 ト長調
弦楽四重奏曲第3番 ハ短調
弦楽四重奏のためのメヌエット ニ長調
ピアノ五重奏曲「婚姻の響き」 ハ長調
ピアノのための「からたちの花」
哀詩「荒城の月」を主題とする変奏曲
クランフォード日記
(I.「樹陰の午後」/II.「なきぬるる柳」/III.「舞踏曲」) |
YAMATO 弦楽四重奏団:
【浜野考史(1st ヴァイオリン),
石田泰尚(2nd ヴァイオリン),
榎戸崇浩(ヴィオラ),
坂田宏彰(チェロ)】
井田久美子(ピアノ) |
録音:1999 年10 月3 日、くにたち市民芸術小ホール
〜俊英YAMATO が描く日本弦楽四重奏史のあけぼの〜幸松
肇
山田耕筰は日本における近代音楽の先駆者。彼の若き日の作曲である、弦楽四重奏曲をはじめとする室内楽作品は豊かなインスピレーションに溢れ、今なお、色あせることのない魅力を湛えている。その端正で文化的資産とも呼べる作品を収録した。世界初CD
化。演奏者は日本の若手として活躍しているYAMATO
弦楽四重奏団による。 |
| |


MTWD 99013
【再プレス】
\2858+税 |
<日本楽派シリーズ IV>
「貴志康一:ヴァイオリン作品集」
月/水夫の唄/竹取物語/漁師の歌/花見/
龍/ヴァイオリン・ソナタ(世界初録音) |
木野雅之( ヴァイオリン)
木野真美(ピアノ) |
録音:2003 年5 月14 日・15 日
〜貴志と木野に共通する情感の豊かさ〜指揮者
小松一彦
貴志康一(1909〜1937)は、28 歳で夭折した日本の洋楽史上に大きな足跡を残した天才音楽家である。往年の名ヴァイオリニスト、エルマンの演奏に感動しヴァイオリンを始め、3
度のヨーロッパ留学を果たし、日本で始めてストラディバリウスを購入し話題になった。1930
年、ヒンデミット、フルトヴェングラーに師事し、作曲家・指揮者に転進。
収録のヴァイオリン・ソナタは2001 年、芦屋市の甲南学園・貴志康一記念室にて発見された幻のソナタである。演奏者は日本フィルハーモニー交響楽団のソロ・ソンサートマスター・木野雅之とパリを拠点に活躍している妹の木野真美。 |
<映像>
 ACCENTUS MUSIC(映像) ACCENTUS MUSIC(映像)
|


ACC 10299BD
(Blu-ray)
\5000 →\4590 |
シャイー&ゲヴァントハウス管によるマーラー・チクルス
マーラー:交響曲第9番ニ長調
特典映像:
「リッカルド・シャイーとアンリ=ルイ・ド・ラ・グランジュによる
マーラー交響曲第9番についての対話」 |
ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団
リッカルド・シャイー(指揮) |


ACC 20299DVD
(DVD)
\3000 →\2690 |
シャイー&ゲヴァントハウス管によるマーラー・チクルス、作品の原点に立ち返りマーラーの真髄に迫った演奏
収録:2013 年9 月6-8 日ライプツィヒ、ゲヴァントハウス(ライヴ)
(Blu-ray)画面:Full HD 16:9、音声:DTS
HD Master Audio5.1,PCM ステレオ、本編:85’
59、ボーナス:29’ 13、字幕:日本語、英仏韓(言語:独)、リージョン:All
(DVD)画面:NTSC 16:9、音声:DTS 5.1,DD5.1,PCM
ステレオ、本編:85’ 59、ボーナス:29’ 13、字幕:日本語、英仏韓(言語:独)、リージョン:All
シャイーとゲヴァントハウス管によるマーラー・チクルス。2011
年のマーラー没後100 年を記念してスタートしたシリーズで、これまでに第2
番、第4 番、第5 番、第6 番、第8 番がリリースされており、いずれも充実した演奏で高い評価を受けています。シャイーは当時音楽監督を務めていたロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団と、マーラーの交響曲全集録音を完成させています。シャイーが最初にマーラーを録音したのがベルリン放響との交響曲第10番(クック版)。シャイーは当時を振り返りこう話しています。「楽団の芸術監督に半ば強制的に言われ取り組んだ。しかしあれは私が最初にマーラーの宇宙の中に踏み込んだ貴重な体験であり素晴らしいことであった」。その後シャイーはコンセルトヘボウ管と全曲録音(第10
番を除く)を完成させますが、第9 番はコンセルトヘボウ管との首席指揮者としての最後のコンサートでまさに全曲演奏の集大成と言える気合いの入った演奏でした。それから10
年、新しい手兵ゲヴァントハウス管とのチクルスも、さらに熟考させた音楽をシャイーの明快で切れ味鋭い指揮で聴くことができます。また、世界的なマーラー研究家アンリ=ルイ・ド・ラ・グランジュとの対談も収録され、作品を深く理解することができる1
枚です。
シャイーは、研究者や指揮者たちが、この交響曲第9
番について「死」を連想させる意見を残していることに疑問を呈しています。「ベルクの「ヴォツェック」には、マーラーの交響曲第9
番によるオーケストレーションの影響がみられるし、この曲は無限の活力と精神力に満ちた作品で自身の死について考えていたとは到底思えない」。さらに「アダージョッシモのコーダは間違いなく死を予感させるものであるが、交響曲第10
番へと導く素晴らしい要素である」と語っています。シャイーは第4
番を演奏する際に、1905 年にマーラー自身がゲヴァントハウス管を最後に振ったピアノロールを聴いたといいます。そしてワルターが1945
年NY フィルを振った演奏と比べるとその演奏時間は同じだったと。シャイーは、マーラーは交響曲第1
番以降具体的な速度数値を指定していないこと、そしてマーラーとワルターの演奏時間が一致したことを受け、自分自身の責任は、自己満足にならないよう過去の原点に立ち返らなければならないと語っています。楽譜に記されたことを尊重し、さらにその奥のマーラーの真髄に迫るシャイーの指揮、マーラーを深く掘り下げることによって調和のとれた幅広い見地から音楽を表現しています。
また「ACCENTUS MUSIC」ならではの、音楽を理解した素晴らしいカメラワーク、見ごたえのある編集で、映像商品としても魅力的。
ジャケット・デザインはシリーズ通して使われているライプツィヒ出身の現代アーティスト、ネオ・ラウフによるものです。

|

.
8/28(木)紹介新譜
今日は・・・すごい・・・.
.
1年に2,3回こういう日がある。
ここまで出てこなくていいのに・・・というくらいお奨めアイテムが怒涛のようにあふれてくる日が。
今日はまさにそんな1日。どうかお気をつけて。でも目玉を見逃しませんよう・・・
. |
.
マイナー・レーベル新譜
 HMF HMF
|
 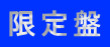
HMU 807641
(8SACD HYBRID)
特別価格\6000 →\5490 |
.
仏HMのセットものなのですぐに完売します。お早めに。
東京クヮルテット/ベートーヴェン:弦楽四重奏曲集(全曲)
・第1番ヘ長調op.18-1、第2番ト長調op.18-2、
第3番ニ長調op.18-3、第4番ハ短調op.18-4、
第5番イ長調op.18-5、第6番変ロ長調op.18-6
録音:2006 年5月、2007年2月
・「ラズモフスキー」四重奏曲集
〔第7番op.59-1、第8 番op.59-2、第9番op.59-3〕
録音:2005 年4月26 − 29日
・第10番変ホ長調 op.74「ハープ」、第11番へ短調op.95「セリオーソ」
録音:2007 年11月,場所:アカデミー・オブ・アーツ&レターズ(ニューヨーク)
・第12番op.127変ホ長調、第14番 op.131 嬰ハ短調、
第13番op.130変ロ長調&大フーガ op.133
(第5楽章カヴァティーナと、最終楽章のアレグロの間に演奏)、
第15番 op.132 イ短調、第16番 op.135 ヘ長調
録音:
op.135/2007年11月(アカデミー・オブ・アーツ&レターズ)、
opo.127, 131/2008年5月
(バード大学フィッシャー・センター・フォー・ザ・パフォーマンツ)、
opp.130, 132, 133/2008年8,9月(東京:王子ホール) |
|
東京クヮルテット
〔マーティン・ビーヴァー(Vn)
池田菊衛(Vn)
磯村和英(Vla)
クライヴ・グリーンスミス(Vc)〕 |
東京クヮルテットの芸術ベートーヴェンの弦楽四重奏全曲がSACDハイブリッドボックスで登場!
2013 年、44 年の長き活動に幕をおろした東京クヮルテット。2002
年からの最終メンバー(マーティン・ビーヴァー(Vn) 池田菊衛(Vn) 磯村和英(Vla) クライヴ・グリーンスミス(Vc)
の4 名)となってからは、ハルモニアムンディからレコーディングを発表していました。
なかでも、ベートーヴェンの弦楽四重奏曲全曲は彼らの活動のいわば最後の集大成として注目のプロジェクトとなっておりました。彼らの日本での演奏活動の中心地であった東京・王子ホールで、ハルモニアムンディ・チームがレコーディングを行ったことも話題となりました。このたび、そんなベートーヴェンの全曲がボックス化。しかも、通常盤のみでの発売だった作品18
もSACD ハイブリッドへとマスタリングが施された注目の高音質での登場です。大変お買得なこのボックス、東京クヮルテットという、音楽史上のいまや「レジェンド」的存在の集大成を聴くことができます。
|
 SIMAX SIMAX
|
|
|
バルト海(Ostsee) — ベットウシュ、タイレ、フィーアダンクの教会音楽
ヨハン・タイレ(1646-1724):
カンタータ「キリストの魂よわれを清めたまえ」
(ソプラノ、3 つのヴィオールと通奏低音のための)
ヨハン・フィーアダンク(1605-1646):
組曲(2 つのヴァイオリンと通奏低音のための)
ゲオルグ・フォン・ベットウシュ(1668-1743):
カンタータ「わたしは心を確かにします」(アルトと通奏低音のための)
トリオソナタ第13番 ハ短調(2つのヴァイオリンと通奏低音のための)
ヨハン・タイレ(1646-1724):
カンタータ「わたしは神が宣言なさるのを聞きます」
(ソプラノ、2つのヴァイオリン、3つのヴィオールと通奏低音のための)
ゲオルグ・フォン・ベットウシュ(1668-1743):
トリオソナタ第10番 イ短調(2つのヴァイオリンと通奏低音のための)
カンタータ「娘シオンよ、大いに踊れ」
(バス、2つのヴァイオリン、3つのヴィオールと通奏低音のための) |
トロンハイム・バロック
インゲボルグ・ダールハイム(ソプラノ)
マリアンネ・ベアーテ・シェラン(アルト)
ニョル・スパルボ(バス) |
北ヨーロッパの地中海、バルト海が育んだ音楽
録音:2012 年11 月15 日-18 日 ファンレム教会(トロンハイム、ノルウェー)/69’28/制作・録音:フランソワ・エケール
「北ヨーロッパの地中海」。スカンディナヴィア半島とヨーロッパ大陸に囲まれたバルト海は、何世紀にも渡り貿易と交通のルートとして栄えました。経済的に豊かなバルト海沿岸の都市では文化と芸術も育まれ、とりわけ、ハンザ同盟の盟主、北ドイツのリューベックでは裕福な商人たちの支援を受けた「夕べの演奏会」や聖マリア教会の音楽の集いが行われ、ヨーロッパ音楽の中心地のひとつとしての地位を確立しました。この地域の音楽様式の発展とその作品は、近年、注目され、その音楽遺産がさまざまな団体により演奏されるようになりました。
ノルウェーの若いアンサンブル、トロンハイム・バロックのアルバム『バルト海』では、このバルト海沿岸ゆかりの音楽家3
人の作品が演奏されます。ドイツのタイレとフィーアダンク、ドイツに生まれノルウェーで活躍したベットウシュ。ザクセンで正式の音楽教育を受けたという共通点もある3
人。アルバムの制作とエンジニアリングは、最近活躍のめざましいフランソワ・エケールが担当。トロンハイムのファンレム教会で録音セッションが行われました。楽器と声のテクスチュアと質感、録音会場となった教会の空気感、音楽の気配を大切にした、いわゆる「Simax
クオリティ」の録音です。
|
 TYX ART TYX ART
|
|
|
19歳の新星アレキサンダー・マリア・ワーグナー
J.S.バッハ:パルティータ第6番ホ短調BWV830
シューマン:蝶々Op.2
アレキサンダー・マリア・ワーグナー:インフェルノ
シューマン:謝肉祭Op.9 |
アレキサンダー・マリア・ワーグナー(ピアノ) |
作曲、演奏ともにただならぬ才能をもつ19歳の新星アレキサンダー・マリア・ワーグナー
録音:2014 年2 月/69’32
アレキサンダー・マリア・ワーグナーは1995
年生まれの19 歳。幼少期から作曲の才能を開花させ、作曲とピアノをフランツ・フンメル氏、パヴェル・ギリロフ氏に師事し研鑽を積んでいます。このアルバムは、感性豊かな瑞々しい演奏で華やかに聴かせてくれます。また3
つの小品からなる自作の「インフェルノ」も収録。得意の即興性を反映した自由な作風で今後の活躍に期待が高まります。 |
| |
|
|
「ライジングスター」シリーズに12歳の天才が登場!
モーツァルト:ピアノ・ソナタ 第9番ニ長調K311
ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ 第1番ヘ短調Op.2-1
シューベルト:ピアノ・ソナタ第13番 イ長調 op.
posth
クリストフ・プライス:
東洋風幻想曲、モーツァルトのピアノ協奏曲第23番のカデンツァ |
クリストフ・プライス(ピアノ) |
録音:2014 年/77’29
TYX art のプロデューサーが惚れ込んだ才能は12
歳のピアニストでした。この度デビューするクリストフ・プライスは、2001
年生まれ。10 歳の頃ドイツのテレビ番組にも取り上げられ「奇跡の子」として多くのメディアに登場しました。その卓越した演奏だけではなく、作曲も行い、その音楽的才能は人々を驚かせています。このアルバムには、モーツァルト、ベートーヴェン、シューベルトの初期のピアノ・ソナタに加え、クリストフ・プライスが書いた「東洋風幻想曲」とモーツァルトのピアノ協奏曲第23
番のカデンツァが収録されています。 |
 ANALEKTA ANALEKTA
|
|
|
.
ケント・ナガノの日本文化への想い
ディアナ・ダムラウが歌う"日本の唱歌"!
唱歌 〜 日本の子供の歌
—— ジャン=パスカル・バンテュス作曲&編曲
七つの子/雨降りお月さん/早春賦/青い目の人形/月見草の花/
十五夜お月さん/花かげ/夕焼け小焼け/春よ来い/隅田川/
赤とんぼ/赤い靴/朧月夜/夏は来ぬ/花嫁人形/
《ちんちん千鳥》による管弦楽幻想曲/浜千鳥/どこかで春が/
ちんちん千鳥/砂山/さくら/あの町この町 |
ディアナ・ダムラウ(ソプラノ)
ケント・ナガノ(指揮)
モントリオール交響楽団
モントリオール児童合唱団 |
2006年9月にモントリオール交響楽団(OSM)の第8代音楽監督に就任したケント・ナガノが、長きにわたり温め続けてきた日本の子供の歌「唱歌集」が遂に実現!
「唱歌集」でケント・ナガノ&OSMとコンビを組み、共に日本の心を歌うのは、ドイツが誇るコロラトゥーラ・ソプラノ、ディアナ・ダムラウ!
妻が娘に歌っていた日本の童謡、子守歌を聴き、その情緒あふれる旋律、歴史に感銘を受けたケント・ナガノ。
2010年には本拠地モントリオールで、自身のルーツである日本の文化、神秘をテーマとしたコンサート『Les
Mysteres du Japon』を実現させている。
ディアナ・ダムラウ、モントリオール児童合唱団、そしてケント・ナガノ&OSMの「唱歌集」のオーケストレーション&アレンジを担当したのは、フランス、トゥールーズ出身でグラミー賞受賞作曲家のジャン=パスカル・バンテュス(1966−)。
様々な文化が一つとなることで現実のものとなったケント・ナガノの想い。ダムラウと児童合唱の純真無垢な歌声が、日本の心を世界へと広げてゆく——。
※録音:2010年2月28日&3月2日、2011年6月28日&29日
 
|
| |
|
|
ルフェーヴルとケント・ナガノの共演!
ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第4番ト短調
Op.40(1926年原典版)
スクリャービン:プロメテウス 〜 火の詩
Op.60 |
アラン・ルフェーヴル(ピアノ)
ケント・ナガノ(指揮)
モントリオール交響楽団
モントリオール交響合唱団 |
ルフェーヴルとケント・ナガノの共演!ラフマニノフ&スクリャービンの協奏曲集!
数多くの世界的ピアニストを輩出しているカナダのコンポーザー=ピアニストであり、アナレクタ(Analekta)のメイン・アーティストの1人、アラン・ルフェーヴルとケント・ナガノ&OSMの共演盤。
ラフマニノフの「ピアノ協奏曲第4番」とスクリャービンの「プロメテウス」をカップリングしたロシアン・プログラムでは、ラフマニノフのヴァージョンが「1926年原典版」であるところも大きなポイント!
モントリオール交響楽団の新本拠地、メゾン・サンフォニーク・ド・モントリオールでのルフェーヴルとケント・ナガノの真剣勝負。ルフェーヴルのピアノが冴える!
※録音:2011年9月、メゾン・サンフォニーク・ド・モントリオール(カナダ)/当社初紹介
ケント・ナガノ&モントリオール交響楽団2014年来日公演情報!
来る10月、ケント・ナガノとモントリオール交響楽団が日本ツアーを行います!来日記念盤となる「唱歌
〜 日本の子供の歌」にご注目下さい!
2014.10.10(金)東京 東京芸術劇場 / 2014.10.11(土)福井
ハーモニーホールふくい
2014.10.12(日)京都 京都コンサートホール
/ 2014.10.13(月)神奈川 横須賀芸術劇場
2014.10.15(水)福島 郡山女子大建学記念講堂
/ 2014.10.16(木)東京 サントリーホール
2014.10.18(土)北海道 札幌コンサートホールKitara |
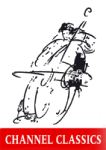 CHANNEL CLASSICS CHANNEL CLASSICS
|
 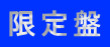

CCSBOX 6414
(8CD/特別価格)
\6400 →\5790
|
.
全集ボックス登場!これも完売必至。お早めに・・・
レイチェル・ポッジャー
モーツァルト:ヴァイオリン・ソナタ全集
CD1:
第35番ト長調K.379/第1番ハ長調K.6/
第43番ヘ長調K.547/第34番変ロ長調K.378/
CD2:
第27番ハ長調K.303/第2番ニ長調K.7/第25番ト長調K.301/
第15番ヘ長調K.30/第41番変ホ長調K.481/
CD3:
第40番変ロ長調K.454/第13番ハ長調K.28/
アンダンテとフーガ イ短調K.402/
アンダンテとアレグレット ハ長調K.404/
ヴァイオリン・ソナタ第3番変ロ長調K.8/
第36番変ホ長調K.380/
CD4:
第26番変ホ長調K.302(293b)/同第4番ト長調K.9/
同第28番ホ短調K.304(300c)/同第14番ニ長調K.29/
同第42番イ長調K.526/
CD5:
第29番イ長調K.305/同第38番ハ長調K.403(385c)/
同第16番変ロ長調K.31/同第30番ニ長調K.306/
CD6:
第32番ヘ長調K.376(374D)/第24番ハ長調K.296/
第12番ト長調K.27/第33番ヘ長調K.377(374E)/
CD7:
第31番変ロ長調K.372/
フランスの歌《ああ、私は恋人をなくした》による6つの変奏曲ト短調K.374b/
ヴァイオリン・ソナタ第11番変ホ長調K.26/幻想曲ハ短調K.396/
フランスの歌《羊飼いの娘セリメーヌ》による12の変奏曲ト長調K.374a/
CD8:ロンドン・ソナタ集*
ヴァイオリン・ソナタ
第5番変ロ長調K.10/第6番ト長調K.11/第7番イ長調K.12/
第8番ヘ長調K.13/第9番ハ長調K.14/第10番変ロ長調K.15 |
|
レイチェル・ポッジャー(ヴァイオリン)
ゲイリー・クーパー
(フォルテピアノ、チェンバロ*)
アリソン・マギリヴリー(チェロ)* |
レイチェル・ポッジャーとゲイリー・クーパー、ーツァルトのヴァイオリン・ソナタ全集BOX!
2004年に"Vol.1"(CCSSA 21804)がリリースされ、2008年発売の"Vol.7&8"(CCSSA
28109)で完結した、ポッジャーとクーパーのモーツァルトが、豪華BOXセットになって登場!
バロック・ヴァイオリンの世界的名匠として国際的な成功を収め続けてきた天女レイチェル・ポッジャーと、イギリスの名鍵盤楽器奏者ゲイリー・クーパーの素晴らしきコンビ。ペザリニウス1739年製のバロック・ヴァイオリン、デレック・アドラム1987年製アントン・ワルター1795(レプリカ)のフォルテピアノなど使用楽器にもこだわり、高音質録音盤としても高評価を獲得。5度にわたる仏ディアパソン・ドールや英グラモフォン誌のエディターズ・チョイスなど、絶大な評価を築いてきました。レイチェル・ポッジャーが、「これは私にとって、現在進行形の発見の旅である」と語った"モーツァルトのヴァイオリン・ソナタ全集"。嬉しい全集BOXの発売です!
|
 VIVAT VIVAT
|


VIVAT 107
(2CD/特別価格)
\2400 →\2190 |
J.S.バッハ:無伴奏チェロ組曲 BWV.1007−1012(全曲)
組曲第1番ト長調 BWV.1007/組曲第4番変ホ長調
BWV.1010/
組曲第5番ニ短調 BWV.1011/組曲第3番ハ長調
BWV.1009/
組曲第2番ニ短調 BWV.1008/組曲第6番ニ長調
BWV.1012
|
フィオラ・デ・ホーフ(バロック・チェロ) |
VIVAT第7弾はフィオラ・デ・ホーフ!J.S.バッハの無伴奏チェロ組曲全曲!
オランダの名チェリスト。デ・ホーフのバッハ無伴奏!
キングズ・コンソートの自主レーベル「VIVAT(ヴィヴァット)」のリリース第7弾は、オランダの名女流チェリストが奏でるチェロの聖典、J.S.バッハの無伴奏チェロ組曲全曲!
ロバート・キング、インマゼール、ガーディナーなど古楽界の巨匠たちからの信頼も厚いフィオラ・デ・ホーフは、アムステルダムでアンナー・ビルスマにチェロを学び、"バロック・チェリスト"としてはヨーロッパのピリオド・オーケストラの首席奏者として、"モダン・チェリスト"としてはシェーンベルク弦楽四重奏団のチェリストを20年にわたって務めるなど、ピリオド、モダンの両方の第一線で活躍を続けてきたオランダのトップ・チェリストの1人。
バロック・チェリストとして豊富な経験を持つデ・ホーフは、J.S.バッハの「無伴奏チェロ組曲」で、1750年製のグァダニーニと18世紀ボヘミア製の5弦チェロ(第6番)の2台の銘器を使用。
"ピリオド"、"モダン"の2つの世界で培われた経験と解釈が、バッハの無伴奏チェロ組曲で光る
——!

|
 MUSIC&ARTS MUSIC&ARTS
|
|
|
「さまよえる影/フランソワ・クープランの最後の作品集」
フランソワ・クープラン(1668-1733):
前奏曲第7番/第25オルドル(全6曲)
第24オルドル(全曲より6曲抜粋)/
第26オルドル(全6曲)/前奏曲第6番
第27オルドル(全4曲) |
キャスリーン・ロバーツ・パール(Cemb) |
ベテラン・チェンバリスト、キャスリーン・ロバーツ・パールのフランソワ・クープラン最後の作品集
録音:2013 年8 月
オルドルとはここでは一種の小品集または組曲というほどの意味でクープランの主要な仕事であるクラヴサンのための曲集の事である。
ここに収められた作品はクラヴサン作品集の最後にあたる第4
集の中のさらに最後の4 曲であり、晩年のクープランの集大成ともいえる内容。キャスリーン・ロバーツ・パールはロサンジェルス出身のチェンバリストでKOCH
からクープラン作品集、Dorian からジャック・デュフリー作品集とバッハの平均律クラヴィーア全曲とフランス組曲をそれぞれリリースしており、いずれも高い評価を得ている。 |
 STRADIVARIUS STRADIVARIUS
|
|
|
「ファブリチアーニ&プッスール/ゼウスのフルート奏者」
ロベルト・ファブリチアーニ(b.1949):
「ジジのための音」〜フルートと磁気テープのための
「A」〜ピッコロとライヴ・エレクトロニクスのための
「モーション・キャプチャー」〜
ハイパー・バス・フルートとライヴ・エレクトロニクスのための
「月の高峰」〜フルートと磁気テープのための
「ディメンション・ゲストラル」〜
ハイパー・バス・フルートとライヴ・エレクトロニクスのための
ロベルト・ファブリチアーニ&アンリ・プッスール(1929-2009):
「ゼウスのフルート奏者」〜
フルート、磁気テープとライヴ・エレクトロニクスのための |
ロベルト・ファブリチアーニ
(Fl,ピッコロ,ハイパー・バスFl)
アルヴィーゼ・ヴィドリン
(ライヴ・エレクトロニクス) |
まさに真夏の夜の夢!怪奇!幻想!サイケデリックなファブリチアーニとプッスールの世界!
録音:2012 年
これは大傑作!電子音楽ファン、サイケデリックな音響音楽の好きな人に絶対の自信を持ってお奨めできる名盤です。このイタリアのレーベルSTRADIVARIUS
はもともと現代音楽(特に電子音楽系)に強く、つい先日もリュック・フェラーリの作品集を世に問い、マニアの間では隠れた大ヒットとなったばかり。
ロベルト・ファブリチアーニはイタリアのフルート奏者、作曲家でこれまでにケージ、ベリオ、シュトックハウゼン、細川俊夫ほか多くの作曲家と共演してきましたが、自身もユニークな作品を数多く発表しています。
極めつけは独自に開発したハイパー・バス・フルートのための作品で驚異的な低音と高次倍音、特殊奏法と吐息がエレクトロニクスによって瞬時に加工、変幻自在に変容され、とても一本のフルートから作られたとは到底思えぬ幻想的でサイケデリックな音響世界が展開します。
ヨーロッパのプログレが好きな人、シュトックハウゼン・フリークにもお奨めです。空前絶後の音響の嵐があなたの耳元を吹きすぎてゆきます。快感!! |
| |
|
|
《Inviolataシリーズ》
「フルートで聴くアストル・ピアソラ」
アストル・ピアソラ(1921-1992):タンゴの歴史
(I.売春宿 1900/II.カフェ 1930/
III.ナイトクラブ1960/IV. 現代のコンサート)/
オーセンシアス(不在)/6つのタンゴ・エチュード/天使の死 |
エンリコ・ディ・フェリーチェ(Fl)
リッカルド・レオーネ(Pf) |
バロックを得意とするフルート奏者ディ・フェリーチェがピアソラを吹く!
録音:2013年8月
エンリコ・ディ・フェリーチェはイタリアを代表するフルート奏者のひとりでバッハ、ヴィヴァルディ、スカルラッティなどのバロック音楽を得意としている。
このアルバムでは普段のレパートリーとはまた違った雰囲気で肩の力の抜けた楽しい演奏を展開している。ピアノ伴奏も控えめでフルートによるピアソラを存分に楽しめる。 |
| |
|
|
「フランコ・マルゴーラ(1908-1992):室内楽作品集」
ピアノ五重奏曲第2 番/ピアノのための即興曲/
ピアノのためのソナチネ/ピアノのためのワルツ/
ピアノのための前奏曲イ長調/
ピアノのための前奏曲ハ長調/
ピアノ五重奏曲第1番 |
マルゴーラ五重奏団:
【アントニオ・デッラーカ(Vn)、
アンナ・オレリオ(Vn)、
ヤコポ・ゾンツィン(Va)、
マルゲリータ・セネス(Vc)、
クラウディア・バンツィーニ(Pf)】 |
録音:2011 年
マルゴーラは20 世紀イタリアの作曲家でアルフレード・カゼッラに師事したほか、イルデブランド・ピツェッティから影響を受けたとされる。、アルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリのためにピアノ協奏曲を作曲したことでも知られ、交響曲、各種の協奏曲などあらゆるジャンルに作品を残した。作風は後期ロマン派から新古典主義的な傾向があるが様々な様式の作品があり、一括りには出来ない。
ピアノの小品に特に味わい深いものがあり、ピアノのためのソナチネではラヴェル、モンポウや坂本龍一(ラスト・エンペラーに似た旋律が出てくる)を思わせる。 |
| |
|
|
「ラオ・シレス(1883-1953):ピアノ作品集」
歌詞のないロマンス/夜明けの夢/マドリガル/
前奏曲第1番イ短調/情熱的なセレナード/
前奏曲第12番ホ短調/主題と変奏/ワルツ第1番/
ワルツ第12番/ラメント「糸杉」/
ワルツ第1番イ短調/ワルツ第12番イ長調/
ワルツ第14番嬰ヘ長調/ワルツ第20番「心から心へ」ヘ短調 |
ロベルト・ピアーナ(Pf) |
録音:2013 年10 月
知られざる近代イタリアの抒情的な作曲家シレスのピアノ作品集。ラオ・シレスは本名スタニスラウス・シレスといい、19
世紀末から20 世紀半ばまで活躍したイタリアの軽音楽の作曲家。ミュージカル・コメディやソングを多数作曲し、その中にはカルーソーがレパートリーにしたものもあった。
ここに収められたピアノの小品はいずれも歌詞のない歌曲といってよいほどイタリアらしい伸びやかな旋律にあふれている。歌曲王トスティに通じる旋律美を持った作曲家である。
|
<マイナー・レーベル歴史的録音・旧録音>
 ALTUS ALTUS
|
|
|
.
アルゲリッチ&チェリビダッケ/伝説のシューマン:ピアノ協奏曲
(1)シューマン:ピアノ協奏曲イ短調Op.54
(2)プロコフィエフ:
『ロメオとジュリエット』組曲第2番Op.64より
モンタギュー家とキャピュレット家/少女ジュリエット/
別れの前のロメオとジュリエット/
アンティーユ諸島から来た娘たちの踊り/
ジュリエットの墓の前のロメオ/タイボルトの死 |
マルタ・アルゲリッチ(Pf)
セルジュ・チェリビダッケ(指揮)
フランス国立放送管弦楽団 |
予想以上の素晴らしさ。アルゲリッチとチェリビダッケ、空前絶後の共演が日の目を見た。
録音:1974 年5 月19 日/シャンゼリゼ劇場(ライヴ)/ADD、ステレオ、ライヴ録音
これは凄いリリース。アルゲリッチとチェリビダッケ伝説のシューマンのピアノ協奏曲が日の目を見ました。どちらのリリースでも大ニュースとなる大物の奇想天外な共演が、マスターテープからの復刻なので、冷静でいることが不可能と申せましょう。
シューマンの協奏曲はアルゲリッチの十八番で、1952
年のブエノスアイレスでのライヴから、2010
年のアルミンク&新日本フィルのライヴまで10
種類以上のディスクが存在しますが、この演奏はそのなかでも飛びぬけて凄い出来となっています。
当時アルゲリッチは33 歳、出だしのカデンツァから魔術全開で、ライヴで乗った時特有の音楽への没入ぶりに驚かされます。ことに第1
楽章半ばの「アンダンテ・エスプレッシーヴォ」でのねっとりとした音色の歌い回しは、アルゲリッチにしかできない神業。ピアノとオーケストラが穏やかに対話する第2楽章は、瞑想的なチェリビダッケと感覚的なアルゲリッチの個性の違いが面白さ満点。さらに驚くほどの生気に満ちたフィナーレなど、あまりの素晴らしさに声を失うほど。ライヴで燃える彼女の良さが最高度に発揮されていますが、おそらくチェリビダッケの要求からか、通常よりかなり抑制が利き、それがかえって多彩なニュアンスを生む結果となっています。
チェリビダッケによるオーケストラ・パートも、驚きのひと言につきます。シューマンのオーケストラ・パートがこれほど透明に聴こえるのは稀で、さらに第3
楽章の変拍子的な難所をはじめアルゲリッチにピッタリ付けて、完璧主義者の面目躍如たる指揮ぶり。あくまでもアルゲリッチを主役に立てつつも、しっかりと充実したチェリ節を味わわせてくれます。
プロコフィエフの「ロミオとジュリエット」はチェリビダッケお得意の演目。オーケストラの機能を追求した非センチメンタルな音楽はまさに彼向きですが、「ジュリエットの墓の前のロメオ」の凄みに満ちた慟哭、「タイボルトの死」の死の匂いのする疾走など、同バレエ音楽屈指の名演と呼ぶにふさわしい内容となっています。 |
| |


ALT 301 / 2
(2CD)
\4000 →\3690 |
チェリビダッケのピアニッシモをついに再現!
ラヴェル:
Disc 1
(1)スペイン狂詩曲
(2)マ・メール・ロワ(全5曲)
(3)道化師の朝の歌
Disc 2
(4)ラ・ヴァルス
(5)「ダフニスとクロエ」第1組曲
(6)「ダフニスとクロエ」第2組曲 |
セルジュ・チェリビダッケ(指揮)
フランス国立放送管弦楽団 |
チェリビダッケのピアニッシモをついに再現!人間業とは思えぬ凄さ
(1)1973年12月23日/シャンゼリゼ劇場(ライヴ) (2)1974年2月6日/シャンゼリゼ劇場(ライヴ) (3)1974年5月29日/シャンゼリゼ劇場(ライヴ) (4)1974年10月2日/シャンゼリゼ劇場(ライヴ) (5)1974年10月16日/シャンゼリゼ劇場(ライヴ) (6)1974年10月16日/シャンゼリゼ劇場(ライヴ)/ADD、ステレオ、ライヴ録音
「ついにチェリビダッケの超ピアニッシモが捉えられたか? フランスから到着したこのCD
のソースを聴いて、私は驚きに打たれた。〈ダフニスとクロエ〉の冒頭、音楽の音と呼ぶにはためらわれる、もっと微妙で、まだ形になっていない何か。空気の震えや風と呼びたくなるような何か。単にきれいとかそうでないということを超えた何か。弦楽器から漏れてくるひそやかな吐息のような、動物のうごめきみたいな何か。その生々しさや実存感にぎょっとしたのだ」(許光俊・ライナーノーツより)
この一文を読んだだけでも聴きたくてたまらなくなるチェリビダッケ最高のアルバム登場です。ラヴェルの音楽は感覚的に聴こえながらも、異常なまでに理詰めな計算に基づいているので、まさにチェリ向き。これまであまり状態の良くないライヴが多かったため、彼のピアニッシモが体感できませんでしたが、オリジナル・マスターから復刻した当アルバムはチェリビダッケのラヴェルならではの音世界を再現しました。
「マ・メール・ロワ」の幻想的な美しさも想像を絶する凄さ。人間業を超えた芸を堪能できます。
|
 HAENSSLER HAENSSLER
|
|
|
シュタルケル/20世紀のチェロ協奏曲集
(1)ヒンデミット:チェロ協奏曲(1940)
(2)プロコフィエフ:チェロと管弦楽のための交響的協奏曲
ホ短調op.125
(3)ラウタヴァーラ:チェロ協奏曲第1番op.4(1
1968) |
ヤーノシュ・シュタルケル(チェロ)
(1)アンドレアス・フォン・ルカーチ(指揮)
SWR シュトゥットガルト放送交響楽団
(2)エルネスト・ブール(指揮)
バーデン=バーデン&
フライブルクSWR 交響楽団
(3)ヘルベルト・ブロムシュテット(指揮)
バーデン=バーデン&フライブルクSWR 交響楽団 |
すべて優秀なステレオ録音!ヒンデミット、プロコフィエフ、ラウタヴァーラ、シュタルケルの弾く20世紀のチェロ協奏曲集
(1)録音:1971年1月14日/シュトゥットガルト、放送局スタジオ(放送用セッション・ステレオ)(23’50”) (2)録音:1975
年8月16日/バーデン=バーデン、ハンス・ロスバウトスタジオ(放送用セッション・ステレオ)(36’16”) (3)録音:1975
年2 月6日/バーデン=バーデン、ハンス・ロスバウトスタジオ(放送用セッション・ステレオ)(14’19”)/ADD、ステレオ、74’
46”
2013 年に88 歳で歿し、2014 年が生誕90 周年にあたるハンガリー出身の名チェリスト、ヤーノシュ・シュタルケルのお宝音源が、SWR
アーカイヴに遺されていました。このたび「haenssler
classics」のヒストリカル・シリーズより復刻される協奏曲3
曲はすべて正規盤初出の内容で、この不世出の音楽家を語るうえで外せないものとなるのはまず間違いのないところです。
シュタルケルが「20 世紀最高のチェロ協奏曲」と呼んだヒンデミットの作品は、シュタルケルにとって、1957-58
年のライナー指揮シカゴ響とのライヴ録音、1994
年のデニス・ラッセル・デイヴィス指揮バンベルク響との録音に続く3
種目の内容。レコーディングの頻度からもシュタルケルの思い入れの強さがうかがえますが、この曲についてシュタルケルは「完璧な構成、みごとな音楽素材、すばらしいオーケストレーション」で、「ショスタコーヴィチやプロコフィエフそのほかの作曲家たちよりもずっとすばらしい」とまで絶賛しており、ここでも作品を完全に掌握したその腕前を堪能できそうです。
プロコフィエフの協奏曲はシュタルケルにとって、1956
年のジュスキント指揮フィルハーモニア管とのセッション録音に次いで2
種目。おそろしく難しい独奏パートを持ち前の完璧な技巧でねじ伏せますが、決してテクニックを誇示するだけに終わらせないところに、あらためてシュタルケルの非凡さを感じさせます。
一部に熱狂的な支持を集めるラウタヴァーラの作品は、シュタルケル初のレパートリーという意味でもきわめて貴重。この多作で多面的な要素を持つ現代屈指の作曲家は、さまざまな独奏楽器のための協奏曲の創作をライフワークとしていますが、その最初にして最も広く知られている協奏曲(1968
年作曲、1969 年初演)の魅力を、シュタルケルは説得力ある演奏で引き出しています。
全3 曲とも放送用にセッションでステレオ収録されたもので、すぐれた音質で鑑賞できるのも価値あるところです。 |
SPECTRUM SOUND
|


CDSMBA 007
(2CD)
\4000 →\3690 |
シルヴェストリ&フランス国立放送管「新世界より」
ハスキル圧巻のモーツァルト第19番
Disc 1
ドヴォルザーク:交響曲第9番ホ短調 Op.95『新世界より』
ボーナストラック:
ドヴォルザーク:交響曲第9番の第3楽章と第4楽章(修正なし版)
Disc 2
モーツァルト:ピアノ協奏曲第19番ヘ長調KV.459*
ドビュッシー:牧神の午後への前奏曲
ラヴェル:ボレロ(冒頭3小節が欠けております) |
クララ・ハスキル(ピアノ)*
コンスタンティン・シルヴェストリ(指揮)
フランス国立放送管弦楽団 |
好評、スペクトラム・サウンドのコンサート・ライヴ・シリーズ、“Belle
ame(ベルアーム)”第7弾!
ステレオ録音。シルヴェストリ&フランス国立放送管によるライヴ十八番の新世界よりハスキル圧巻のモーツァルト第19
番、フランス国立視聴覚研究所音源提供 解説は平林直哉氏が担当!
ライヴ録音:1959 年2 月12 日、パリ、シャンゼリゼ劇場
(ステレオ)/フランス国立視聴覚研究所音源提供/初CD
化、日本語解説付、24bit/192kHz、Digital Restoration&24bit
Remastering
スペクトラム・サウンド・レーベルの好企画、フランス国立視聴覚研究所提供による音源を使用したコンサート・ライヴ・シリーズ“Belle
ame(ベルアーム)” の第7 弾は、コンスタンティン・シルヴェストリ指揮、フランス国立放送管弦楽団による1959
年2 月のライヴよりドヴォルザークの交響曲第9
番ホ短調 Op.95『新世界より』、クララ・ハスキルをソリストに迎えたモーツァルトのピアノ協奏曲第19
番ヘ長調KV.459、ドビュッシーの牧神の午後への前奏曲、そして、ラヴェルのボレロです。今回も平林直哉氏による日本語解説付です。なお、ボレロの冒頭3
小節が欠けております。予めご了承ください。
「指揮者、ピアニストともにルーマニアの首都ブカレスト生まれ同士の共演。原盤供給元によると当日はドヴォルザーク、モーツァルト、ドビュッシー、ラヴェルの順に演奏されたという。ハスキルは来日の実績はなかったが、モノラル時代に発売されたウエストミンスターのLP
により、すでに神格化されていた。一方、シルヴェストリは一般的な人気はそれほど高くはなかったが、一部には熱狂的な支持者を生み出した。(中略)シルヴェストリの「新世界より」は来日した際のライヴもCD
化されている(KKC 2049)が、このディスクの表現はいっそうエネルギッシュであり、かつステレオという利点もある。(中略)ハスキルはモーツァルトの第19
番と第20 番の協奏曲がことのほかお気に入りで、それぞれ生涯で約55
回、約60 回程度演奏しており、それに準じて残された録音(正規、放送録音合わせて)も多い。このシルヴェストリの明るく生き生きとした伴奏と、ハスキルの透明感溢れる音色とは抜群の相性ではなかろうか。しかも、目下のところ、この曲の唯一のステレオというのもありがたい。(中略)シルヴェストリのドビュッシー、ラヴェル(残念なことに冒頭は原テープに欠落があるが)とも、純粋にフランス的ではないが、だからこそ面白いのだ。」(平林直哉)
|
<メジャー・レーベル>
 ERATO ERATO
|


2564624055
(2CD)
\2800→\2590 |
.
エマニュエル・アイム(指揮)&ル・コンセール・ダストレ
ヘンデル:オラトリオ「メサイア」
HWV.56 |
ルーシー・クロウ(S)
ティム・ミード(C-T)
アンドルー・ステイプルズ(T)
クリストファー・パーヴス(Br)
ル・コンセール・ダストレ
エマニュエル・アイム(指揮) |
フランスのバロック界を牽引する女性指揮者アイムが創設したル・コンセール・ダストレによる「メサイア」。
女性指揮者が普通に登場するような時代になってきたが、そのなかでもこのアイムの存在は特筆すべきもの。指揮をするというより、大地から湧き上がるエネルギーを汲み取って演奏者に投げかけるような、そんな不思議な人。2008年3月にベルリン・フィルにデビューしていて、その活躍の場はどんどん広がってきた。バロック・オペラ復権が現実のものとなりつつある今、この人の活躍を知らないとちょっと恥ずかしいかも。

アイムとデセイのレコーディング風景が見られる。コチラ。
|
| |


2564623177
\2100→\1890 |
まさかのERATOから・・・
ナタリー・シュトゥッツマン/ヘンデル:アリア集
〜影のヒーロー達
「インドの王ポーロ」〜第3幕へのシンフォニア
「アリオダンテ」〜ポリネッソ「義務、正義、そして愛」
「オルランド」〜第3幕へのシンフォニア
「ガウラのアマディージ」〜ダルダーノ「荒れ狂う苦悩」
「アレッサンドロ」〜クレオーネ「私はあの風のように」
「セルセ」〜アルサメーネ「希望があるか分からない」
「パルテノペ」〜第3幕へのシンフォニア
「ラダミスト」〜ゼノビア「私は喜んで死にましょう」
「アグリッピーナ」〜
オットーネ「私の嘆きを聞いておいでの方々」
「タメルラーノ」〜
イレーネ「この胸の中に生まれたかのように」
「シピオーネ」〜第3幕へのシンフォニア
「ジュリオ・チェーザレ」〜コルネーリア「そよ吹く風」
「セルセ」〜第3幕へのシンフォニア
「ジュリオ・チェーザレ」〜
セストとコルネーリアの二重唱「涙の中に生まれて」*
「クレタのアリアンナ(クレタ島のアリアドネ)」〜
アルチェステ「私は疲れた巡礼のように」
「ロデリンダ」〜
ベルタリド「つながれた猛々しい野獣は」
「シッラ」〜
クラウディオ「聞いてくれ、わが美しき愛する人よ」
「パルテノペ」〜
ロズミーラ「私は猛々しいものを求める」
「ガウラのアマディージ」〜羊飼いの青年と娘たちの踊り |
|
ナタリー・シュトゥッツマン(コントラルト、指揮)
フィリップ・ジャルスキー(C-T)*
アンサンブル・オルフェオ55(ピリオド楽器使用) |
まさにメジャー・レーベル戦国時代。
大スターたち、次にどこのレーベルからどんなアイテムを引っさげて登場するか分からない!!
前作はドイツ・グラモフォンからのリリースだったナタリー・シュトゥッツマン、今度はERATOから。ERATOなんてもう消え去ったものだと思っていたのに!
指揮者としても天性の凄みをきかせるナタリー・シュトゥッツマン、今回もアンサンブル・オルフェオ55を従え、そしてカウンター・テナーにはフィリップ・ジャルスキーを呼び、まさに満足の出来栄え。タイトルには「影のヒーロー達」というちょっとイタい邦題がついているが、普段日の目を見ない隠れた傑作をズラリと並べた。
前作・・・DGからのバッハ |

481 0062
\2200→\1990 |
ナタリー・シュトゥッツマン
J・S・バッハによるイマジナリー・カンタータ
①『カンタータ第42番「されど同じ安息日の夕べに」BWV.42よりシンフォニア』,
②『カンタータ第30番「喜べ、贖われし群れよ」BWV.30より
アリア「来たれ アダムの 末なる 民」』,
③『カンタータ第133番「わが喜びは汝にあり」BWV.133よりアリア「喜びなさい」』,
④『管弦楽組曲第3番BWV.1068よりアリア(エア)』,
⑤『アリア「御身が共にいるならば」BWV.508』,
⑥『カンタータ第174番
「われ、いと高き者を心を尽くして愛しまつる」BWV.174よりシンフォニア』,
⑦『カンタータ第21番「わが心には憂い多かりき」BWV.21よりシンフォニア』,
⑧『カンタータ第74番「人もしわれを愛さば、わが言葉守るべし」BWV.74より
アリア「何ひとつ私を救うことのできるものはない」』,
⑨『カンタータ第33番「ただ汝にのみ、主イエス・キリストよ」BWV.33より
アリア「わが歩みは怯えよろめく」』,
⑩『カンタータ第18番「天より雨と雪の降るごとく」BWV.18よりシンフォニア』,
⑪『マタイ受難曲BWV.244よりアリア「私を憐れんで下さい」』,
⑫『カンタータ第4番「キリストは死の絆につきたまえり」BWV.4よりシンフォニア』,
⑬『カンタータ第169番「神ひとりわが心を占めたまわん」BWV.169より
アリア「さらば、わが 内なる 世の すべての
愉しみよ」』,
⑭『カンタータ第191番「いと高きところには栄光、神にあれ」BWV.191より合唱』,
⑮『カンタータ第85番「われは善き牧者なり」BWV.85より
アリア「イエスは善い羊飼い」』,
⑯『カンタータ第182番「天の王よ、よくぞ来ませり」BWV.182よりシンフォニア』,
⑰『われを忘るるなかれBWV.505』,
⑱『カンタータ第147番「心と口と行いと生きざまもて」BWV.147より
コラール「イエス わが喜び」』 |
|
ナタリー・シュトゥッツマン(コントラルト&指揮)
オルフェオ55 (ピリオド楽器アンサンブル),
ミカエリ室内合唱団 |
シュトゥッツマンによるバッハの作品で再構成した空想カンタータ
1965年パリ生まれで、当代最高のアルト歌手の一人として活躍中のナタリー・シュトゥッツマン。フランス歌曲やドイツ・ロマン派の歌曲を得意とする他、バロック・オペラや受難曲、オラトリオなどの歌唱でも評価が高い彼女が自らの理想とする形に再構成したカンタータ集。
バッハのカンタータの中から、宗教的物語の背景を基調として、美しくも情熱的なアリア、シンフォニア、コラールが選ばれ、壮大な1時間にも及ぶカンタータを作り出しました。
2009年に彼女自身が創設したアンサンブル「オルフェオ55」を指揮しつつ、持ち前の正統的な歌唱力と表現力とで見事に歌い上げています。
〔録音〕2012年4月, L’Arsenal de Metz (デジタル:セッション) |
|
| |


2564625018
\2100→\1890 |
.
まさかの共演
ルノー・カプソン&ブニアティシヴィリ
フランク:ヴァイオリン・ソナタ イ長調
グリーグ:ヴァイオリン・ソナタ第3番ハ短調
Op.45
ドヴォルザーク:4つのロマンティックな小品
Op.75 |
ルノー・カプソン(Vn)
カティア・ブニアティシヴィリ(P) |
まさにメジャー・レーベル戦国時代。
大スターたち、次にどこのレーベルからどんなアイテムを引っさげて登場するか分からない!!ほんとに。
フェスティヴァルなどでは共演している大人気スターの二人が、まさかレコーディングでも共演してくれるとは!!
ルノー・カプソンとカティア・ブニアティシヴィリ、所属レーベルはエラートとソニー・クラシカルと違えども、2009年のルガーノ・フェスティヴァル、2012年のラ・フォル・ジュルネ、2013年のプラハの春音楽祭などで共演している、若手演奏家のなかでも特に注目されている2人が、ついにレコーディング! 共演実績のある作品を中心に、ロマン派の3人の作曲家作品をピック・アップ。ヴァイオリンとピアノのための作品のなかでも、親しまれている楽曲で構成されています。
|
<国内盤>
エディション・HST
|
2014 年4 月、ヴァンハル協会東京npo(Wanhal
Gesellschaft, Tokyo npo)が設立されました。
ヴァンハル協会、ジュネーブ・ニヨンnpo(J.
B. Wanhal Association)と協力し立ち後れていたヴァンハル作品目録、全集編纂へ尽力いたします。またヴァンハルの交響全曲録音を目指している「エディションHST」レーベルは協会傘下のレーベルとなります。
今回ヴァンハル協会東京npo 設立を記念しまして、エディションHST
レーベルのCD から8 枚を選びお求めやすい価格で発売いたします(限定盤)。以前に出ていました「ヴァンハル:10
の交響曲(5 枚組)」とは重複はございません。 |

HST-903
(8CD特別価格)
\3704+税 |
ヴァンハル(1739-1813):19の交響曲集(世界初録音多数!)
CD1 (HST069)
交響曲ハ長調(パリ版)Bryan C1/交響曲へ長調(F3)/交響曲ホ長調(E3)
CD2 (HST071)
交響曲ト長調(G2)/交響曲ハ長調 (C7)/交響曲へ長調
(F6)
CD3(HST076)
交響曲へ長調 (F2)/交響曲イ長調 (A4)/交響曲へ長調
(F7)
CD4 (HST078)
交響曲ニ短調(d1a)〜第二楽章/交響曲ニ長調
(D1)/
交響曲ニ長調(D7)/交響曲ニ長調 (D18)/交響曲ト短調(g2)
CD5 (HST089)
交響曲ト長調 (G10)/交響曲ニ長調 (D9)/交響曲ハ長調
(C15)
CD6(HST088)
ピアノ協奏曲ハ長調W.II:C4/ピアノ協奏曲イ長調W.II:A1/交響曲ト長調
(G13)
CD7 (HST044)
ノッテュルノ ト長調W.IV:5/カッサシオ変ホ長調W.III:Es4/
カッサシオ変ホ長調W.deest
CD8(HST060)
三重奏W.VIa:C10-14,F7-13,G12-14/交響曲ニ長調
(D21)= Cassatio W.III:D5/
ディヴェルティメント変ロ長調W.VI:B2 ニ長調D-dur
W.VI:D2 |
ハイドン・シンフォ二エッタ トウキョウ
松井 利世子(Vn;リーダー) |
| ヴァンハル協会東京npo 設立記念、ヴァンハル交響曲集、特別限定盤8枚組! |
<映像>
 ACCENTUS MUSIC(映像) ACCENTUS MUSIC(映像)
|


ACC 20313DVD
(DVD)
\3000 →\2690 |
シュ・シャオメイのゴルトベルク2014年最新映像
J.S.バッハ:ゴルトベルク変奏曲BWV988
ドキュメンタリー:
反は道の動なり〜シュ・シャオメイとゴルトベルク変奏曲について |
シュ・シャオメイ(ピアノ) |
シュ・シャオメイのゴルトベルク2014年最新映像、ライプツィヒ・バッハ音楽祭でのライヴ
監督:ポール・スマチュニュイ/ドキュメンタリー監督:ミシェル・モラール
画面:NTSC 16:9、音声:PCM ステレオ、DD5.1、DTS5.1、85’54(本編)+52’29(ボーナス)、字幕:英仏独西、原語:中国語
フランスを拠点に活動する中国人ピアニスト、シュ・シャオメイ。文化大革命を乗り越え新たな道を切り開いてきた彼女。そのような半生からは想像もできない、心穏やかな音楽。彼女が得意とするバッハの演奏は、緻密な構成力と洗練された表現力から生み出され、ただ純粋に音楽が聴こえ聴く者の心に共鳴します。
このDVD は、2014 年ライプツィヒ・バッハ音楽祭で演奏された、彼女の代名詞とも言える作品「ゴルトベルク変奏曲」。バッハが生前活躍し、そして永眠の場所となったライプツィヒの聖トーマス教会でのライヴ収録です。音楽祭に先立って録音されたフーガの技法(ACC30308CD)と同様に様式を見事に捉えた品格ある音楽を聴かせてくれます。
シュ・シャオメイのゴルトベルク変奏曲といえば、1990
年に録音したアルバムは(現・MIR048)仏ディアパゾン誌で5
つ星を獲得した盤が真っ先に思い出されます。それから24
年後の録音となったこのDVD でも、深淵なるバッハの世界に引き込まれ、美しいバッハ像描き出しています。
グールド、レオンハルト、リヒターなど数ある名盤にも匹敵するような高い完成度の演奏を披露しています。さらに的確なカメラワークで定評のあるプロデューサー、ポール・スマチュニュイの落ち着いた映像も演奏を味わうのに一役買っています。
ボーナス映像は、老子の言葉「反は道の動なり(The
Return is the Movement of Tao)」を表題とし、シュ・シャオメイとゴルトベルク変奏曲について考察した内容となっています。
(なお本映像はDVD のみの発売となります)
|
 EURO ARTS(映像) EURO ARTS(映像)
|


20 72664
(4Blu-ray)
\8600 →\7790 |
.
ベルチャ四重奏団、コンツェルトハウスでのベートーヴェン弦楽四重奏全曲演奏会
ベートーヴェン:弦楽四重奏曲(全曲)
弦楽四重奏曲
第1番 ヘ長調 Op.18-1、第2番 ト長調 Op.18-2、
第3番 ニ長調 Op.18-3、第4番 ハ短調 Op.18-4、
第5番 イ長調 Op.18-5、第6番 変ロ長調
Op.18-6、
第7番 ヘ長調「ラズモフスキー1番」Op.59-1、
第8番 ホ短調「ラズモフスキー2番」Op.59-2、
第9番 ハ長調「ラズモフスキー3番」Op.59-3、
第10番 変ホ長調「ハープ」Op.74、
第11番 ヘ短調「セリオーソ」Op.95、
第12番 変ホ長調 Op.127、
第13番 変ロ長調 Op.130「大フーガ付」、
第14番 嬰ハ短調 Op.131、第15番 イ短調
Op.132、
第16番 ヘ長調 Op.135、
大フーガ |
|
ベルチャ四重奏団
【コリーナ・ベルチャ(ヴァイオリン)、
アクセル・シャハー(ヴァイオリン)、
クシシュトフ・ホジェルスキー(ヴィオラ)、
アントワーヌ・レデルラン(チェロ)】 |


20 72668
(5DVD)
\8600 →\7790 |
収録:2012 年コンツェルトハウス、ウィーン(ライヴ)
(4Blu-ray)画面:1080i Full HD 16:9、音声:PCM
ステレオ、DTS-HD Master Audio5.1、リージョン:All、字幕:英、独、仏、522分(+ドキュメンタリー45分)
(5DVD)画面:NTSC 16:9、音声:PCM ステレオ、DTS5.1、DD5.1、リージョン:All、字幕:英、独、仏、522分(+ドキュメンタリー45分)
この映像は、ベルチャ四重奏団がウィーンのコンツェルトハウスで2012
年に行った連続演奏会の模様。12 日間でベートーヴェンの弦楽四重奏曲を全曲演奏するというプロジェクトでした。ベルチャ四重奏団は、2008
年に解散したアルバン・ベルク四重奏団の伝統を継承する世界トップクラスの弦楽四重奏団。1994
年にロンドン王立音楽院に在学中のメンバーによって結成されました。2
度のメンバーチェンジを行い現在は第1 ヴァイオリンにコリーナ・ベルチャ(ルーマニア)、第2
ヴァイオリンにアクセル・シャッハー(スイス)、ヴィオラにはクシシュトフ・ホジェルスキー(ポーランド)、そしてチェロはアントワーヌ・ルデルラン(フランス)という国際色ゆたかなメンバーで活動を行っています。このメンバーで2011-12
年に別にセッション録音でもベートーヴェンの全集を完成させており、その切れ味鋭いダイナミックな表現力で高い評価を受けていました。この演奏会は、それを受けて実現した全曲演奏会です。
演奏は、高い技術と凄まじい集中力と緊迫感、研ぎ澄まされた感性、息の合ったアンサンブルと、まさに現代を代表するベートーヴェンの弦楽四重奏曲といってよいでしょう。さらにこの演奏会は、第13
番を、「大フーガ」を最終楽章にした初演版と、ベートーヴェンが死の直前に作曲した新たな最終楽章による出版社版の両方を弾いていることも特徴。
特典映像には、45 分間の「ベートーヴェン弦楽四重奏曲への道筋」と題されたドキュメンタリーが収録されています。

|

8/27(水)紹介新譜
マイナー・レーベル新譜
 LSO LIVE LSO LIVE
|


LSO 0765
(1SACD HYBRID +
1Blu-ray audio)
\4800 →\4390 |
.
.
ガーディナー&LSO/メンデルスゾーン・シリーズ第1弾
ピリスとのシューマン:ピアノ協奏曲
メンデルスゾーン:序曲「フィンガルの洞窟」op.26
シューマン:ピアノ協奏曲イ短調op.54
メンデルスゾーン:交響曲第3番イ短調op.56「スコットランド」
特典映像 :
メンデルスゾーン:序曲「フィンガルの洞窟」op.26
シューマン:ピアノ協奏曲イ短調op.54
メンデルスゾーン:交響曲第3番イ短調op.56「スコットランド」 |
|
マリア・ジョアン・ピリス(ピアノ)
サー・ジョン・エリオット・ガーディナー(指揮)
ロンドン交響楽団
特典映像 :
マリア・ジョアン・ピリス(ピアノ)
サー・ジョン・エリオット・ガーディナー(指揮)
ロンドン交響楽団 |
超優秀録音。ガーディナーによるメンデルスゾーン・シリーズ「スコットランド」&「フィンガルの洞窟」超強力カップリング!ピリス独奏のシューマンの協奏曲、SACDハイブリッド+ピュア・オーディオ・ブルーレイ・ディスク仕様!コンサート当日のライヴ映像も全プログラム丸ごと収録!
収録:2014 年1 月21 日/ロンドン、バービカン・ホール(ライヴ)/DSD5.1チャンネル、ステレオ、78’
DSD5.1チャンネルプロデューサー:ジェイムズ・マリンソン、エンジニアリング、ミキシング&マスタリング:Classic
Sound Ltd/[SACD : DSD5.0 surround stereo
/ 2.0 stereo][Pure Audio Blu ray : 5.0 DTS-HD
Master Audio (24bit/192kHz), 2.0 LPCM (24bit/192kHz)]
特典映像 :収録:2014 年1 月21 日/ロンドン、バービカン・ホール(ライヴ)
サー・ジョン・エリオット・ガーディナーがロンドン響を指揮して、メンデルスゾーンの交響曲第3
番「スコットランド」と序曲「フィンガルの洞窟」をレコーディング。2014
年1 月21 日に、バービカンで行われたコンサートの模様をライヴ収録したもので、当コンビによるメンデルスゾーンの交響曲全集録音シリーズ第1
弾となります。ロンドン響にとっては、アバドの指揮でメンデルスゾーンの交響曲全集を初めて完成したのが1985
年のことですので、完成すればほぼ30 年ぶりの新たな全集の登場ともなります。
よく知られるように、ガーディナーは、1996
年にウィーン・フィルを指揮して交響曲第5 番「宗教改革」をライヴ録音、1997
年にウィーン・フィルを指揮して交響曲第4 番「イタリア」“現行版”
の全曲をセッション録音しています。
しかも、交響曲第4 番「イタリア」について、ガーディナーは1998
年にウィーン・フィルを指揮して、こんどは1833
/ 34 年改訂版から、第2 楽章から第4楽章をセッション録音するというこだわりをみせてもいました。
このウィーン・フィルとの交響曲シリーズは残念ながら、全集完成には至らなかったので、16
年の時を経て、新たなシリーズにかけるガーディナーの意気込みたるや、ひとかたならぬものがありそうです。ロンドン響との顔合わせは、ガーディナーがここ毎シーズン、定期公演への客演を重ねて、親密な関係を保持しているだけに、出来ばえにはかなりの期待を持って迎えられるところです。なお、プログラム・ノートの執筆もガーディナー自らが手掛けており、ここにもシリーズに向けた気合いのほどが伺えます。
このたびは豪華なカップリングもおおきな魅力。メンデルスゾーンの2
作品と同日の演奏で、名手ピリス(ピリスとも)をソリストに迎えた、シューマンのピアノ協奏曲を収録しています。ピリスは、1997
年9 月にアバド指揮のヨーロッパ室内管と同曲をセッション録音していたので、16
年ぶりの再録音ということになります。ピリスはシューマンをキャリアの初期から取り上げて得意としていますが、美しく磨き抜かれた音色とあたたかい情感のこもった音楽に集約される、近年の進境には著しいものがあり、こちらも興味の尽きない内容といえるでしょう。
なお、当アルバムでは、従来のSACD ハイブリッド盤に加えて、同一の演奏内容を収めたピュア・オーディオ・ブルーレイ・ディスクが同梱されます。お手持ちのブルーレイ・ディスク・プレーヤーで手軽に楽しめるハイスペックのフォーマットへの対応は、かねてよりオーディオ・ファイルからの要望も高かったのでなんとも嬉しい配慮といえるでしょう。
さらにボーナス映像として、ブルーレイ・ディスクのビデオ・パートには、2014
年1 月21 日の本拠バービカンにおけるコンサート当日すべてのプログラム、序曲、協奏曲、交響曲が丸ごと収められ、まさに至れり尽くせりの仕様となっております。 |
 ECM ECM
|
ECM New Series |

481 0992
\2500 |
チェロとピアノによるジャンル無き音楽の美
《モデラート・カンタービレ》
①ゲオルギイ・グルジエフ/トーマス・ド・ハルトマン:
サイイドの歌と踊り第3番と詩篇第7番,
②フランソワ・クチュリエ:ヴォヤージュ,
③ヴァダペット・コミタス:あなたはスズカケの木,
④フェデリコ・モンポウ:歌と踊り第6番,
⑤モンポウ:ひそやかな音楽第28番と内なる印象第1番,
⑥クチュリエ:ソレイユ・ルージュ,
⑦クチュリエ:蝶々,
⑧グルジエフ:詩篇第8番とナイト・プロセッション,
⑨グルジエフ:詩篇第11番 & モンポウ:遠い祭り第3番,
⑩モンポウ:内なる印象第8番 |
アニャ・レヒナー(Vc)
フランソワ・クチュリエ(P) |
ドイツ、カッセルで生まれたチェリスト、アニャ・レヒナーはハインリッヒ・シフとヤーノシュ・シュタルケルに師事し、アムステルダム・シンフォニエッタ、アルメニア・フィル、タリン室内管弦楽団などの公演にソリストとして参加、またコンサートではアレクセイ・リュビーモフや、ジルケ・アヴェンハウス、キリル・ゲルシュタイン等、名ピアニストと共演し、古典から現代まで幅広いレパートリーを納得の演奏で聴かせる人です。
また6歳でピアノを始めたフランソワ・クチュリエはクラシック音楽だけではなく、チック・コリアやヨアヒム・キューンなどのジャズ・ピアニストからも薫陶を得た人で、即興演奏が得意であり、ジャンルを超えた表現をすることで知られています。
この2人の共演は、まさに「ジャンル無き音楽」であり、普段は真面目で晦渋ともいえるモンポウの音楽さえも、ここでは親しげで軽やかな笑みを浮かべています。ふとした心の隙間にそっと入ってくるような滑らかさが、心地よく聴き手の心に響きます。
【録音】2013年11月, ルガーノ、スイス・イタリア語放送オーディトリオ[デジタル:セッション] |
|

481 0880
\2500 |
《Tre Voci》〜武満徹, ドビュッシー, グバイドゥーリナ:作品集
武満 徹:そして、それが風であることを知った
ドビュッシー:フルート、ヴィオラ、ハープのためのソナタ
グバイドゥーリナ:喜びと悲しみの庭 |
キム・カシュカシャン(Va),
マリーナ・ピッチニーニ(Fl),
シヴァン・マゲン(Hp) |
カシュカシャンらによる、様々な相反する要素を美しく纏め上げた演奏
現在、最も高く評価されているヴィオラ奏者の一人、キム・カシュカシャンは、昨年リゲティの無伴奏ヴィオラ作品集のアルバムでグラミー賞を受賞するなど、その活躍はとどまるところを知りません。そんな彼女が今回はイタリア系アメリカ人のフルーティスト、ピッチニーニと、イスラエルのハーピスト、マゲンとともにトリオを組み、更なる新しい世界を模索します。
このアルバムはドビュッシーの晩年の作品「フルート、ヴィオラ、ハープのためのソナタ」を中心に、武満とグバイドゥーリナの同編成作品を配置。音色、質感、そして時間の流れを感じさせるプログラムとなっています。武満は明らかにドビュッシーの作品の影響を受けているように思われ、またグバイドゥーリナの作品は、オーストリアの作家タンザーの詩とモスクワの詩人オガノフの詩、この2つの東洋と西洋を描いた文学作品に触発されたもので、極めて瞑想的、かつ抒情的な世界が展開されています。
喜びと悲しみ、東洋と西洋、静けさときらめき、たくさんの相反する要素を美しく纏め上げた印象的なアルバムです。
【録音】2013年4月, ルガーノ、スイス・イタリア語放送オーディトリオ[デジタル:セッション] |
 BOTTEGA DISCANTICA BOTTEGA DISCANTICA
|
|
|
ヘンデル(1685-1759):アンセム集
神よ、起ちたまえ [Let God arise] HWV256b
主はわが光なり [The Lord is my light]
HWV255
われは主に依り頼む [In the Lord put I
my trust] HWV247 |
フランチェスカ・サルヴァトレッリ(ソプラノ)
サラ・トマジーニ(アルト)
アウレーリオ・スキアヴォーニ(男性アルト)
マッテオ・メッツァロ(テノール)
グイード・トレーボ(バリトン)
アンドレア・パッラディーノ・バロック合唱団&管弦楽団
エンリーコ・ザノヴェッロ(指揮) |
| 録音:データ未詳
イタリアの気鋭の古楽演奏家たちによるヘンデル。エンリーコ・ザノヴェッロはイタリアのヴィチェンツァに生まれ、ステファノ・インノチェンティにオルガンを、アンドレア・マルコンにチェンバロを師事した鍵盤楽器奏者・指揮者。1989年ヴィチェンツァにアンドレア・パッラディーノ・バロック管弦楽団の前進アルキチェンバロ・アンサンブルを、2009年にはアンドレア・パッラディーノ・バロック合唱団を創設。
ヘンデルの没後250年に当たる2009年、ヘンデルが独唱・合唱と管弦楽のために書いた全作品を演奏するプロジェクトを開始しました。
|
| |
|
|
J・S・バッハ(1685-1750):
インヴェンションとシンフォニア BWV772-801
4つのデュエット BWV802-805 |
ロベルト・ジョルダーノ(ピアノ) |
|
録音:2013年7月17-20日、スタジオ。カヴァッリ・ムジカ、カストレッツァート、ブレシア県、ロンバルディア州、イタリア
使用楽器:ボルガート、コンサート・グランド
L282
ロベルト・ジョルダーノは1981年生まれ。パリのエコール・ノルマル音楽院およびペーザロ(イタリア)のジョアッキーノ・ロッシーニ音楽院を卒業。2003年エリザベート王妃国際音楽コンクール第4位。
当レーベルからすでに5枚のCDをリリースしています。
|
| |
|
|
ルイージ・モルフィーノ(1916-2012):オルガン作品集
Exaltabo Deum / Ibant Magi /
Sonata in un solo tempo / Offertorio
Exultemus / Meditazione /
Tu es Petrus / Offertorio / Jesu tibi
sit gloria
Tema variato / Oremus Domine /
Improvviso / Improvvisazione / Implorazione
Concento battesimale:
Entrata solenne / Entra nel tempio
di Dio /
Io ti battezzo / Va in pace |
ロベルト・ムッチ(オルガン) |
|
録音:時期の記載なし、サンタ・マリア・マッジョーレ・バジリカ聖堂、ベルガモ、イタリア
使用楽器:1915年、ヴェジェッツィ=ボッシ製
2012年に96歳で亡くなったイタリアのオルガン奏者・作曲家・合唱指揮者ルイージ・モルフィーノ。ルガーノ(スイス)に生まれ、ミラノのジュゼッペ・ヴェルディ音楽院で学んだ彼はスカラ座管弦楽団オルガン奏者、ジェノヴァのカルロ・フェリーチェ劇場合唱指揮者、ジュゼッペ・ヴェルディ音楽院教授等を歴任しました。
|
 DIGRESSIONE MUSIC DIGRESSIONE MUSIC
|
|
|
マウロ・ジュリアーニ(1781-1829):ポプリ ギターとフルートのための作品集
オペラ「タンクレディ」によるフルートとギターのためのポプリ
Op.76(*)
フルートとギターのための変奏曲 Op.84(*)
フルートとギターのための大ポプリ Op.53(*)
「おいらはキャベツ作りの子」によるギターのための6つの変奏曲
Op.49
オペラ「愛と栄光」のロマンスによるギターのための変奏曲
Op.105
ギターのための6つの前奏曲 Op.83 から
Nos.4, 5, 6 |
アントニーノ・マッドンニ(ギター)
ジュゼッペ・ディ・リッド(フルート(*)) |
|
録音:データ記載なし
使用楽器:マリオ・ガッローネ製(ギター)/ナガハラ、フル・コンサート・14K(フルート)
「ポプリ」とはもともとフランスのごった煮鍋料理のことで、様々な香りの物を合わせた室内香の名前にもなっていますが、音楽用語としては複数の曲をつなげたメドレーを意味します。
19世紀にはひとつのオペラからいくつかの聴かせどころを選んだポプリや、当時のヒット曲をつなげたポプリ等が数多く書かれました。
アントニオ・マッドンニは1960年イタリアのバルレッタに生まれバーリのニッコロ・ピッチンニ音楽院で学んだギター奏者。ジュゼッペ・ディ・リッドは1985年生まれ、フォッジャのウンベルト・ジョルダーノ音楽院で学んだフルート奏者。
|
<マイナー・レーベル歴史的録音・旧録音>
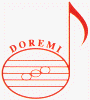 DOREMI DOREMI
|
| レジェンダリー・トレジャー・シリーズ |


DHR 8031/3
(3CD)
\7000 →\6390 |
オスカー・シュムスキー演奏集 |
オスカー・シュムスキー(ヴァイオリン) |
ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ第7番作品30-2
ナディア・ライゼンバーグ(ピアノ)
テレマン:無伴奏ヴァイオリンのための幻想曲ニ長調第10
番
録音:1972 年1月3日ニューヨーク、WQXR
スタジオ、ライヴ放送
J.S.バッハ:ヴァイオリン・ソナタ ホ長調BWV1016〜第1楽章
タルティーニ:ヴァイオリン・ソナタ「悪魔のトリル」(クライスラー編)
ラフマニノフ:歌曲「ひなぎく」作品38-(3
クライスラー編)
ヴィエニャフスキ:華麗なるポロネーズ第2番イ長調作品21
レオ・バーキン(ピアノ)/録音:1951年11月28日CBCライヴ放送
シューベルト:華麗なるロンド ロ短調作品70、D.895
J.S.バッハ:無伴奏パルティータ第2番ニ短調BWV1004
R.シュトラウス:ヴァイオリン・ソナタ変ホ長調作品18
クライスラー:レチタティーヴォとスケルツォ・カプリース作品6、ウィーン奇想曲
フランク・マウス(ピアノ)/録音:1982
年10月24日バーゼル、ライヴ
J.S.バッハ:カンタータ第132番〜アリア、アルトとヴァイオリン・ソロ
モーリン・フォレスター(アルト)
J.S.バッハ:カンタータ第120番〜アリア、ソプラノとヴァイオリン・コンチェルタンテ
ルイ・マーシャル(ソプラノ) バッハ・アリア・グループ/
録音:1962年、Deato DC7139/40(LP)
ブクステフーデ:カンタータ「主を讃えよ」
モーリン・フォレスター(アルト)/
録音:1967年7月26日スタンフォード音楽祭、カナダ、ライヴ
モーツァルト:アダージョ ホ長調 K261
ヒンデミット:ヴァイオリン・ソナタ 作品11-2
マリオ・ベルナルディ(ピアノ)/録音:1965
年ライヴ
モーツァルト:イル・レ・パストーレ(羊飼いの王様)K.208〜アリア「あの人を愛するのだ」
エルナ・ベルガー(ソプラノ)ジョージ・シック(ピアノ)/録音:1950
年
ラフマニノフ/ クライスラー編:
夜のしじまに作品4-3、子供たちに作品26-7、
乙女よ私のために歌わないで作品4-4、私の窓辺に作品26-10
ジェームズ・メルトン(テノール)キャロル・ホリスター(ピアノ)/録音:1949
年
ヴィエニャフスキ:華麗なるポロネーズ第1番ニ長調作品4
アール・ワイルド(ピアノ)
R.シュトラウス:町人貴族〜舞曲
CBC 管弦楽団/録音:1965 年CBC 放送ライヴ
シューマン:子供の情景〜トロイメライ作品15-7
アル・グッドマン管弦楽団/録音:1948
年頃
サン=サーンス:序奏とロンド・カプリチオーソ作品28
NBC 交響楽団 ミルトン・ケイティムズ(指揮)/
録音:1950 年4月22日ライヴ放送 |
伝説のヴァイオリニスト、オスカー・シュムスキーの演奏集
伝説のヴァイオリニスト、オスカー・シュムスキー。シュムスキーは、亡命ロシア人の両親のもと、1917
年にフィラデルフィアに生まれ、3 歳からヴァイオリンを学び、7
歳でフィラデルフィア管弦楽団にデビュー。あのストコフスキーに「いまだかつてない神童」と称えられました。カーティス音楽院では、名教師レオポルド・アウアーとエフレム・ジンバリストに学び、卒業後ソリストとして活動するほか、トスカニーニが率いていたNBC
交響楽団やプリムローズ弦楽四重奏団などのアンサンブル活動を行っていました。そして教育者としてジュリアード音楽院、イエール大学等で後進の指導にあたり、演奏活動の第一線から退いていました。その後80
年代初頭に演奏活動、レコーディングを行い再び表舞台に立つことになりました。
このアルバムは、シュムスキーの演奏活動の初期40
年代から80 年代の録音を集めた3 枚組アルバム。同じくカーティス音楽院でヨーゼフ・ホフマンに学び、テルミン奏者クララ・ロックモアの実姉であるピアニスト、ナディア・ライゼンバーグとのベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタ第7
番。盟友アール・ワイルドとのヴィエニャフスキの華麗なるポロネーズ第1
番。かつてクライスラーから賞賛を受けたシュムスキーによるクライスラー編によるラフマニノフの歌曲。そして目の覚めるような技巧で聴かせるサン=サーンスの序奏とロンド・カプリチオーソ、など貴重かつ素晴らしい演奏が集められています。 |
<メジャー・レーベル>
<国内盤>
<映像>

8/26(火)紹介新譜
マイナー・レーベル新譜
 PREISER PREISER
|
|
|
名バリトン、ホルツマイアーが白鳥の歌を再録音!
シューベルト:白鳥の歌 |
ヴォルフガング・ホルツマイアー(バリトン)
チャールズ・スペンサー(ピアノ)
フリードリヒ・クラインハプル(チェロ) |
録音:2011 年
オーストリアを代表するリート歌手ヴォルフガング・ホルツマイアーによるシューベルトの「白鳥の歌」。ホルツマイアーと言えばイモージェン・クーパーとのシューベルト三大歌曲集を約20
年前に録音しており、その洗練された歌声で名盤として聴き継がれています。今回はイギリス出身の優れたリート・ピアニスト、チャールズ・スペンサーをピアニストに迎え2011
年に録音されました。60 歳を迎えさらに円熟した表現力と柔らかな歌声で充実した演奏を聴かせてくれています。 |
| |
|
|
アラカルト
【ウィーン風メニュー】
L.グルーバー:母さんはウィーン娘Op.100
モーツァルト:「フィガロの結婚」〜とうとう嬉しい時が来た〜恋人よここに
アドルフ・ミュラー/ヨハン・ネストロイ:チコリ夫人の歌
【フランス風メニュー】
レイナルド・アーン:ぼくの詩に翼があったなら(ユゴー詩)
グノー:「ロメオとジュリエット」〜私は夢に生きたい
ルイギー:バラ色の人生(ピアフ詩)
【イタリア風メニュー】
ドニゼッティ:糸巻き
プッチーニ:「ラ・ボエーム」〜わたしが街を歩くと
プッチーニ:太陽と愛(朝の歌)
【オーストリア風メニュー】
ヨハン・シュトラウスII:
オペレッタ「ファニー・エルスラー」〜シーヴェリングのリラの花
ニコ・ドスタル:オペレッタ「クリビア」〜私は恋をしている
ラルフ・ベナツキー:オペレッタ「小さなカフェ」〜メールシュパイゼ |
ローラ・シェルヴィツル(ソプラノ)
ビクトリア・クロワ(ピアノ) |
| オーストリアの期待のソプラノ、ローラ・シェルヴィツル。このアルバムは、レストランのアラカルト・メニューに見立てたプロフラミングで、ウィーン、オーストリア、フランス、イタリアの各国の作曲家達の歌曲やアリアを収録しています。伸びやかでメリハリと安定感がある歌声が魅力の歌手です。 |
| |
|
|
これぞウィーンの妙!
ウィーンの新設アンサンブル、ウィーンクラング
J.S.バッハ:2つのヴァイオリンのための協奏曲BWV1043
モーツァルト:セレナーデ第6番「セレナータ・ノットゥルナ」K239
チャイコフスキー:弦楽セレナードOp.48 |
アンサンブル・ウィーンクラング
ブルグハルト・トェルケ(ヴァイオリン)
ミヒャエル・カンツィアン(ヴァイオリン)
クリスティアン・シュルツ(指揮) |
録音:バウムガルテン・カジノ
2007 年に結成されたアンサンブル・ウィーンクラングとウィーン交響楽団チェロ奏者として知られているクリスティアン・シュルツ指揮による演奏。J.S.
バッハの2 つのヴァイオリンのための協奏曲では、ザハール・ブロン氏に師事し現在ドイツ、オーストリアで活躍しているヴァイオリン奏者ブルグハルト・トェルケとミヒャエル・カンツィアンによる共演。生き生きとしたサウンドで楽曲を表現しています。 |
 COLLEGIUM COLLEGIUM
|

COLCD 137
(2CD/特別価格)
\2500 |
ダブル・セレブレーション
CD 1:ケンブリッジ・シンガーズの30年 〜
アムナー:きたれ, 賛美しよう/グレゴリオ聖歌:恵み深き救い主の母よ/
タリス:もし汝われを愛さば/ギボンズ:ダヴィデの子に栄あれ/
バード:この日こそ/
オランダのキャロル(ウッド編):この楽しい復活祭の季節/
ブルジョワ:おお喜ばしき光/
パーセル:主よ, 我らの躓きを思い出さないで下さい/
デリング:めでたし栄ある乙女よ/
ラッスス:アヴェ・ヴェルム・コルプス/
スヴェーリンク:主を崇めよ/ラフマニノフ:生神童貞女や喜べよ/
ブルックナー:アヴェ・マリア/
フォーレ:楽園にて(《レクイエム》より)/スタンフォード:青い鳥/
ウェールズ民謡(ホルスト編):ヴィーナスのような恋人/
ディーリアス:水の上の夏の夜を歌わんII/ギボンズ:銀色の白鳥/
ジョン・ベネット:ラウンド・アバウト・イン・ア・フェア・リング/
ラヴェル:楽園の3羽の美しい鳥(《3つの歌》より)/
イギリス民謡(ラッター編):大胆な手榴弾兵/
アイルランド民謡(スタンフォード編):急げ、時間がない/
ピアーサル:レイ・ア・ガーランド/
アイルランド民謡(ラッター編):アイ・ノウ・ホエア・アイム・ゴーイング/
ラッター:花がある/
コーンウォール地方の民謡(ラッター編):聖なる日のキャロル/
アパラチアのキャロル(ラッター編):さまよいながらわたしは不思議に思う/
ラッター:キャンドルライト・キャロル/
カークパトリック:飼い葉の桶で/ラッター:マリアの子守歌
CD 2:ジョン・ラッターの音楽 〜
ラッター:
美しい地球のために、ゲール人の祈り、主は我が牧者、
おお, 手を打ち鳴らせ、ビー・ザウ・マイ・ヴィジョン、汝の完璧なる愛/
アメリカのシェイカー・ソング(ラッター編):ロード・オヴ・ザ・ダンス/
ラッター:
主よ, 私をあなたの平和の道具となされよ、主よ我が目をお開きください、
ピエ・イエス(《レクイエム》より)、全ての美しく輝けるもの、
主キリストは再び、アイ・ビリーヴ・スプリング・タイム、私は私を最も愛する、
ゴッド・ビー・イン・マイ・ヘッド、コラール・アーメン/
サマセット民謡(ラッター編):流れは広く/
ラッター:
吹け, 吹けよ, 冬の風(《つららの下がる時》より)、
なぞなぞの歌(《ファンシーズ》より)/
アメリカ民謡(ラッター編):ダウン・バイ・ザ・リバーサイド/
ラッター:
フクロウと子猫ちゃん(《5つの子供の詩》より)、
素晴らしきエール(《つららの下がる時》より)/
イギリスの童謡(ラッター編):6ペンスの歌を歌っておくれ(《5つの子供の詩》より)/
イギリス民謡(ラッター編):火箸をもって走れ/
ラッター:ワルツ(《古風な組曲》より)
|
ジョン・ラッター(指揮)
ケンブリッジ・シンガーズ
シティ・オヴ・ロンドン・シンフォニア
キャロライン・アシュトン(ソプラノ)
ルース・ホルトン(ソプラノ)
マーク・パドモア(テノール)
ジェラルド・フィンリー(バリトン)
クリストファー・フッカー(オーボエ)
アンドリュー・ニコルソン(フルート)
ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団、他 |
ケンブリッジ・シンガーズの30年の歴史とジョン・ラッター70歳の誕生日を祝う!スペシャル・コンピレーション盤登場!
イギリスを代表する英国合唱の巨匠ジョン・ラッター(1945−)のダブル・セレブレーション・アルバムが登場!
ケンブリッジ大学のクレア・カレッジで教鞭を執っていたラッターが、教え子たちとともに1980年代初頭に創設したケンブリッジ・シンガーズ。
CD1では、自主レーベルCollegiumより発売されてきたケンブリッジ・シンガーズの30年に渡る軌跡を30のトラックで表現。
CD2は、2015年に迎えるジョン・ラッターの70歳の誕生日を祝い、初出となる「ダウン・バイ・ザ・リバーサイド」を含む、ラッター作編曲の名曲25曲を収録。
2014年8月には京都市交響楽団がラッターの「マニフィカト」を演奏し話題を呼ぶなど、プロ・アマ問わず根強い人気を誇るラッターの魅力が満載のスペシャル・コンピレーション・アルバムです。 |
 IBS CLASSICAL IBS CLASSICAL
|
|
|
スペインのピアノ四重奏曲集
バウティスタ:四重奏のための協奏的ソナタ第2番
Op.15
トゥリーナ:ピアノ四重奏曲 イ短調 Op.67
レマーチャ:ピアノ四重奏曲 |
トリオ・アルボース
ロシオ・ゴメス(ヴィオラ) |
2013年にスパニッシュ・ナショナル・プライズを獲得し、今注目を集める三重奏団、トリオ・アルボースのスペイン・プログラム。ジュリアン・バウティスタ(1901−1961)、ホアキン・トゥリーナ(1882−1949)、フェルナンド・レマーチャ(1898−1984)の知られざる室内楽作品を華麗なアンサンブルで。
2013年1月26日−28日の録音。 |
| |
|
|
ハワード・バス:作品集 〜 スパニッシュ・メモワーズ
ソロ・マリンバのための 《ライト・オヴ・パッセージ》
トランペットとソロ・パーカッションのための
《インカテーション》
トランペットとソロ・パーカッションのための
《スパニッシュ・メモワーズ》
トロンボーンとマリンバのための 《ナイト・タイド》
トランペット、フリューゲルホルンとソロ・パーカッションのための
《アトモスフィア》 |
チョン・ユジョン(パーカッション)
ディエゴ・アリアス(トランペット)、他 |
国際的なフェスティヴァルなどで取り上げられることが多く注目を集めている現代作曲家、ハワード・バス(b.1951−)の作品集。台湾出身のパーカッショニスト、チョン・ユジョンの叙情的なメロディーに刺激的なトランペット・サウンド。洗練された前衛音楽を聴かせてくれる。
2012年8月の録音。 |
| |

IBS-11002
(2CD)
\5000 |
ホセ・ファウス:作品全集Vol.1 1913年ー1984年 |
グラナダ・ウィンド・オーケストラ
ガルシア・ロルカ合唱団
ラウダ合唱団 |
アイ・ビー・エス・クラシカル(Ibs Classical)よりスパニッシュ・コンポーザー、ホセ・ファウスの作品全集新シリーズ始動!スペインのアルハンブラ宮殿や地中海などからインスピレーションをうけ作曲されたマーチ、賛歌、音楽の祭典など知れれざる作曲家の陽気で愉しい音楽を聴くことが出来る。
2009年10月の録音。 |
 SOMM SOMM
|
|
|
ミュージック・セラピスト、エルガー!
エルガー:ポウィック病院のための音楽
メヌエット(世界初録音)/アンダンテとアレグロ(世界初録音)/
若きコケット/ポルカ 《モード》/こん棒/ポルカ
《ネリー》/
ブルネット/ポルカ 《ブロンド》/ヴァレンタイン/
トロンボーンとコントラバスのための二重奏曲/パリ/
ポルカ 《ヘルキア》/歌うカドリーユ(世界初録音)/
オーボエとヴァイオリンのためのフーガ
ニ短調 |
イノヴェーション・チェンバー・
アンサンブル |
世界初録音を含むエルガーのミュージック・セラピーのための作品集!
エドワード・エルガー(1857−1934)の生まれ故郷ウースターの近くに位置するポウィック。そこにあるポウィック病院の患者のために行われたミュージック・セラピーを再現したアルバム。
当時のセラピーに実際に使われていた作品を含むこのアルバムは、エルガー協会のサポートも入り、より明確な130年前のミュージック・セラピーの再現を可能にした。柔らかく、美しいメロディーや軽快なポルカなどセラピーに使われていた音楽はもちろん、「メヌエット」、「アンダンテとアレグロ」、「歌うカドリーユ」は世界初録音であり、作品集としての完成度も高い。
管楽器に定評のあるバーミンガム市交響楽団のメンバーによって2002年に結成されたイノヴェーション・チェンバー・アンサンブルの表情豊かな演奏にも注目です!
☆レコード芸術2014年7月号「海外盤レヴュー!」水越健一氏によるレビュー掲載! |
SOMM(CELESTE)
|
|
|
ラフマニノフ:練習曲集 《音の絵》 Op.33&Op.39 |
マーティン・カズン(ピアノ) |
| 2005年のエットレ・ポッツォーリ国際ピアノ・コンクール(イタリア)の優勝以来、人気若手奏者として活躍するスコットランド出身のピアニスト、マーティン・カズンによるラフマニノフの「音の絵」。ラフマニノフの音の絵は、ここ数年カズンがレパートリーとして取り上げてきた曲だけに期待も大きい。 |
| |
|
|
ベートーヴェン:ピアノ三重奏曲全集 Vol.3
ピアノ三重奏曲第4番変ロ長調 Op.11 《街の歌》
カカドゥ変奏曲ト長調 Op.121a
ピアノ三重奏曲変ホ長調 Op.38(七重奏曲
Op.20 からの編曲版) |
グールド・ピアノ・トリオ
ロバート・プレーン(クラリネット) |
ヨーロッパ室内管のメンバーでもあるヴァイオリニスト、ルーシー・グールドを中心として20年以上の歴史を持つUKの室内楽団グールド・ピアノ・トリオ。現在取り組んでいるベートーヴェンの全集録音第3集には、初期作品で他の作曲家の主題を引用したとされる第4番をはじめ、カカドゥ変奏曲、七重奏曲からのアレンジの3作品を収録。BBCウェールズ交響楽団、バーミンガム市交響楽団の首席クラリネット奏者ロバート・プレーンの伸びやかなクラリネットの音色も美しい。
2012年2月29日のライヴ録音。 |
<マイナー・レーベル歴史的録音・旧録音>
GRAND SLAM
|
|
|
ワルター&コロンビア響の2トラ38シリーズ
ベートーヴェン:
(1)交響曲第4番 変ロ長調 Op.60
(2)交響曲第5番 ハ短調 Op.67「運命」 |
ブルーノ・ワルター(指揮)
コロンビア交響楽団 |
ワルター&コロンビア響の2トラ38シリーズ、ベートーヴェンの交響曲第4番&第5番「運命」!
セッション録音:(1)1958 年2 月8、10 日、ハリウッド、アメリカン・リージョン・ホール (2)1958
年1 月27、30 日、ハリウッド、アメリカン・リージョン・ホール/ADD、ステレオ
使用音源: Private archive (2トラック、38
センチ、オープンリール・テープ)
■制作者より
大好評のワルター/コロンビア交響楽団の2
トラック、38 センチのオープンリール・テープ復刻、ベートーヴェンの交響曲第6
番「田園」(GS2115)、第1 番&第2 番(GS
2116) に続き、交響曲第4 番&第5 番「運命」が登場します。音質は従来通り、原音の輝き、瑞々しさを限りなく忠実に再現します。なお、解説書にはオットー・シュトラッサーによる「ブルーノ・ワルター、謙虚なオールマイティ(その2)」を掲載しています。(「ブルーノ・ワルター、謙虚なオールマイティ(その1)」はGS-2116
に掲載しております。) 平林直哉 |
 HMF HMF
|


HMX 2908700
(10CD)
特別価格
\8000 →\7290 |
クリスティ&レザール・フロリサン
ジャン=フィリップ・ラモー(1683-1764)
没後250年記念ボックス |
ウィリアム・クリスティ(指揮、チェンバロ)
レザール・フロリサン |
[CD1-3] 「優雅なインドの国々」〔オペラ=バレエ〕 【初演:1735年】
〈ソプラノ〉クロラン・マクファーデン、イザベル・プルナール、サンドリーヌ・ピオー他
〈テノール〉ハワード・クルック、ジャン=ポール・フシェクール 〈バリトン〉ジェローム・コレア
〈バス・バリトン〉ニコラス・リヴェンク 〈バス)ベルナール・デルトレ
ウィリアム・クリスティ(指揮)レザール・フロリサン/録音:1991
年1月
オペラ作曲家としては遅咲きだったラモー。その代表作「優雅なインドの国々」は、1735
年の初演から40 年近くの間に、部分改訂がなされながらも700
回も上演されたといいます。この中から4 つの管弦楽組曲、クラヴサン編曲などが出版されています。
この「優雅なインドの国々」は、各幕に1 つの逸話があり、バレエを随所に取り入れたオペラ=バレエ。第1幕の「寛大なトルコ人」の舞台はインド洋トルコ島。海賊に囚われたプロヴァンスの娘と、そこにたまたま難破船でたどりついた彼女の恋人をめぐるひと騒動。第2
幕は火山山岳地帯の砂漠が舞台の「ペルーのインカ人たち」は、スペインとインカの娘が相思相愛だったのに、司祭が横恋慕するも、司祭は噴火火山の溶岩に呑みこまれてしまう
といった話。第3 幕では気分は一転、華やかな花々の踊りで幕を閉じます。終幕の「未開人たち」北アメリカの森林地帯が舞台。柄の長いパイプを持って踊る「平和のパイプの踊り」など見どころ満載です。オペラ=バレエといいながら、声楽曲に比べて純粋な舞曲が少なく、バレエと呼べる顕著なものは唯一、第3
幕の終幕くらいですが、この作品が舞台で大勢の踊り手によって華麗に上演された時、当時のそれまでの作品とは比較にならないほどバレエが占める重要度は増したことは確かでしょう。しかもリュリはクープランやバッハらが書いたような、様式化された舞曲ではなく、宮廷舞踊と同時に民衆の間に根付きつつあった舞踊、リゴードンやミュゼットといったものも幅広く取り入れているのもポ
イントです。物語は異国要素満載なのに、音楽には異国情緒を感じさせる打楽器なども特に用いられておりませんが、それでも当時の観客に異国趣味を満喫させてくれる作品としてもてはやされたのは疑いのない事実で、これによりラモーの名声は一気に高まっていきます。尚、このCDで使用している楽譜は基本的には1743年度改訂版となっています。
[CD4-6] 歌劇「カストールとポリュックス」(全曲) 【初演:1737年】
ハワード・クルック(カストール;T)、ジェローム・コレア(ポルクス;Br)、アニェス・メロン(テライール;S)、
ヴェロニク・ジャン(フェベ;S)、サンドリーヌ・ピオー(S)、マーク・パドモア(C-T)
ウィリアム・クリスティ(指揮)レザール・フロリサン/録音:1992年9月
「カストールとポリュックス」は、1750 年の音楽史上重要なブフォン論争(ラモーを代表とするフランス古典音楽・トラジェディ・リリックを擁護する「国王派」と、百科全書家(ルソーに代表される)の「王妃派」間の争い)のきっかけともなった作品。国王派が勝利したことにはなっていますが、フランスの古典オペラ・宮廷オペラの衰退は誰の目にも明らかでした。百科全書的啓蒙主義への流れを皮肉にも決定づけることとなった重要な作品です。あらすじは、異父兄弟カストールとポリュックスをめぐる物語。美しい太陽の娘テライールは、カストールと愛し合っている。ポリュックスもテライールを愛しているが、二人の気持ちを知り身を引く。カストールはある日戦死してしまう。嘆き悲しむテライールを見て苦悩するポリュックスは、父であるジュピター(ユピテル)に、自分の永遠の命と引き換えに、カストールを甦らせるよう懇願するが、ジュピターはこれを断る。しかしポリュックスの思いは強く、天国に行ってカストールに会う。カストールは、ポリュックスの命と引き換えに自分が甦ることはできないと断るが、ポリュックスの思いは強く、カストールは、テライールに別れを告げるため一日だけ地上に戻ることになる。テライールと再会したカストールはやはり地上にとどまりたい気持ちが大きくなるものの、ポリュックスの生命を奪うわけにはいかないと天国に戻る決意をする。これを見ていたジュピターが兄弟の思いに打たれ、カストールもポリュックスも地上で永遠に生きられるようにし、二人を十二宮の星座として祀ることを決めた(双子座を形作る星)。
[CD7] バレエ劇「ピュグマリオン」(全1幕)、「ネレとミルティス」(全1幕)
バレエ劇「ピュグマリオン」(全1幕) 【初演:1748年】
ハワード・クルック(T;ピュグマリオン) サンドリーヌ・ピオー(S;愛)
アニェス・メロン(S;セフィーズ) ドナティエンヌ・ミシェル=ダンサック(像)
「ネレとミルティス」(全1幕)
アニェス・メロン(S;ミルティス) ジェローム・コレア(Br;ネレ) フランソワーズ・スメラ(S;カロリーヌ)
ドナティエンヌ・ミシェル=ダンザック、カロリーヌ・ペロン(S;二人のアルゴス人)
ウィリアム・クリスティ(指揮)レザール・フロリサン/録音:1991年
「ピュグマリオン」はラモーの最初のバレエ劇音楽。1748年に初演された、人形師ピュグマリオンが、自分が作った人形に恋をしてしまうが、その思いの強さに次第に人形が生命を持ったものへと変化する、という物語。最後に歌われるアリエッタの超絶技巧も鮮やかな作品です。「ネレとミルティス」はラモー作品としては珍しくその自筆譜が遺されている作品のひとつで、恋人であるネレとミルティスがお互いの愛をためすためにちょっとしただましあいをするが、また元通りになる、という他愛のない若者の話。
[CD8] バレエ劇「アナクレオン」 【1757年】
ルネ・シラー(Br;アナクレオン)、アニェス・メロン(S;愛の神)、ジル・フェルドマン(S;バッカスの巫女)、
ドミニク・ヴィス(C-T;アガトクル)、ミシェル・ラプレーニー(T;宴会の客)
ウィリアム・クリスティ(指揮)レザール・フロリサン/録音:1981
年12月
「アナクレオン」は、詩人アナクレオンとその恋人に酒の神バッカスと愛の神の争いがからみ、最後には丸くおさまる、という筋。
ラモーの代表的オペラ・バレエのひとつです。洗練されたロココ芸術の美を描きだしています。
[CD9] クラヴサン曲集(1724年) (1)組曲
ホ短調 (2)組曲 ニ長調
ウィリアム・クリスティ(チェンバロ/グジョン-シュヴァーネン&リュッカース-タスキン(パリ国立高等音楽院音楽博物館))
録音:1983 年4月
[CD10] 新しいクラヴサンの組曲(1728年)
(1)組曲 イ長調 (2)組曲 ト長調
ウィリアム・クリスティ(チェンバロ/グジョン-シュヴァーネン&リュッカース-タスキン(パリ国立高等音楽院音楽博物館))
録音:1983 年4月 |
ラモー〜没後250 年 アニヴァーサリー作曲家。クリスティ&レザール・フロリサン、充実のラモー作品名録音が、お買得ボックスに!
録音:1981, 83, 91, 92 年
2014 年、没後250 年を迎えたアニヴァーサリー作曲家、ラモー。クリスティがハルモニアムンディに録音した珠玉の作品が、お買得ボックスセットになって登場します!
ラモーの生存中最大の成功作であった「優雅なインドの国々」をはじめ、音楽史的にも重要な「カストールとポリュックス」。そして、洗練されたロココ芸術の粋ともいえるバレエ劇「アナクレオン」は、約20
年ぶりのカタログ復活!見逃せません。
クリスティのチェンバロ独奏によるなつかしの知性漂う名演「クラヴサン曲集」や「新しいクラヴサンの組曲」も久々の復活。ブックレットも307
ページフルカラーで歌詞テキストも掲載された充実ぶり(英・独・仏語)、注目のボックスです!
ウィリアム・クリスティ(指揮、チェンバロ)
1944 年ニューヨーク州生まれ。13~18 歳まで、母が指揮をしていた声楽アンサンブルに所属。ハーヴァードやイェール大学で美術史や音楽学を学び、1966-1970
年ラルフ・カークパトリックやケネス・ギルバートにチェンバロを師事します。1971
年からフランスに居を移します。ルネ・ヤーコプスのアンサンブルなどで活躍した後、1979
年にレザール・フロリサンを設立。その後ハルモニアムンディなどで、フランス・バロック・オペラをメインとした100
以上の録音を残し、そのほとんどが名高い賞を受賞しています。指揮者として、オペラを中心に活動を続けるほか、若者を育成するプロジェクトも手掛けるなど、いまなお一層の活躍をしています。

|
<映像>
 C MAJOR(映像) C MAJOR(映像)
|


71 7504
(Blu-ray)
\5800 →\5290 |
巨匠ピッツィのイタリア絵画のような「ドン・ジョヴァンニ」!
モーツァルト:「ドン・ジョヴァンニ」 |
イルデブランド・ダルカンジェロ(Bs ドン・ジョヴァンニ)
アンドレア・コンチェッティ(Bs レポレッロ)
ミルト・パパタナシュ(S ドンナ・アンナ)
カルメラ・レミージョ(S ドンナ・エルヴィーラ)
マーリン・ミラー(T ドン・オッターヴィオ)
マヌエラ・ビシェリエ(S ゼルリーナ)
ウィリアム・コッロ(Bs-Br マゼット)
エンリーコ・イオーリ(Bs 騎士長)
リッカルド・フリッツァ(指揮)
マルケ地方財団管弦楽団
マルケ・ヴィンチェンツォ・ベッリーニ合唱団 |


71 7408
(2DVD)
\5000 →\4490 |
巨匠ピッツィのイタリア絵画のような「ドン・ジョヴァンニ」!逞しいダルカンジェロのジョヴァンニに、美女三人、キリリと引き締まったフリッツァの指揮!!日本語字幕付き!!
ピエール・ルイジ・ピッツィ(演出,装置,衣装)、セルジョ・ロッシ(照明)、ロベルト・マリア・ピッツート(振付)
収録:2009 年7 月23 日、マチェラータ
(Blu-ray)HD、16:9、174分、DTS-HD MA 5.1
/ PCM 2.0、字幕:伊英独仏西中韓日、リージョン:All
(2DVD)NTSC、174分、DTS 5.1 / PCM Stereo、字幕:伊英独仏西中韓日、リージョン:All
素晴らしい「ドン・ジョヴァンニ」の映像が登場!
中部イタリア、マルケ州のマチェラータは野外公演のスフェリステーリオ音楽祭が有名ですが、町には伝統的馬蹄形劇場、ラウロ・ロッシ劇場(座席数550
の中劇場)があり、ここでもオペラが上演されることがあります。2009
年は7 月23、28、30 日とモーツァルトの「ドン・ジョヴァンニ」が上演されました。ここに収録されているのはその初日の様子。
演出は巨匠ピエール・ルイジ・ピッツィ。ピッツィは2006
年から2011 年までこの音楽祭の芸術監督を務めました。ピッツィはイタリアの伝統的舞台作りを踏まえた上で、イタリア絵画のような美感を存分に生かし、さらにそこに独自の視点を盛り込んだもの。とりわけピッツィお得意の官能美は、夏の公演ということもあって肌の露出の多い歌手たち(黙役にはヌードも)によっていや増しています。
歌手は豪華。タイトルロールはイタリアの人気バス、イルデブランド・ダルカンジェロ。ドン・ジョヴァンニは彼の当り役で、ベルリン国立歌劇場、ウィーン国立歌劇場、そして2014
年夏にはザルツブルク音楽祭でも歌っているほど。堂々とした歌に逞しい体躯と大変に魅力溢れるドン・ジョヴァンニです。レポレッロのアンドレア・コンチェッティは、イタリア、マルケ州、グロッタンマーレ生まれのバス。中堅のバッソブッフォとして大活躍しており、中でもレポレッロは頻繁に歌っています。ピッツィらしく女性三役はいずれも美人歌手。
ドンナ・エルヴィーラは日本でもお馴染みのイタリアのソプラノ、カルメラ・レミージョ。モーツァルトは得意中の得意。ドンナ・アンナのミルト・パパタナシュは、ギリシャ生まれのソプラノ。ギリシャ美人で、ヴェルディ「トラヴィアータ」のヴィオレッタが当り役。モーツァルトやロッシーニでも高く評価されています。日本では2010
年10 月、新国立劇場での「フィガロの結婚」で伯爵夫人を歌っています。ドン・オッターヴィオのマーリン・ミラーは米国のテノール。非常にレパートリーの広い達者なテノールで、ここでも個性が滲むドン・オッターヴィオになっています。ゼルリーナのマヌエラ・ビシェリエは、世界遺産で知られる南イタリア、マテーラ生まれのソプラノ。小悪魔役にピッタリの美人で、ピッツィがそれを際立てています。
指揮は俊英リッカルド・フリッツァ。彼らしい引き締まったスピード感のある「ドン・ジョヴァンニ」ですが、イタリア的美感とモーツァルトらしさを両立させているのがさすがです。
鮮明映像で夏のイタリアの空気感すら伝わってくるようなきがします。
日本語字幕付きです。 |
 EURO ARTS(映像) EURO ARTS(映像)
|

20 20248
(DVD +カタログ)
\1500 →\1390 |
ユーロ・アーツ2014 カタログ付DVD
ヴェーバー:「オベロン」序曲
ショスタコーヴィチ:ヴァイオリン協奏曲第1番イ短調Op.77
J.S.バッハ:
無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ第1番ト短調BWV.1001よりプレスト
(アンコール)
ドヴォルザーク:交響曲第8番ト長調Op.88
ドヴォルザーク:スラヴ舞曲ハ長調Op.72-7(アンコール) |
ヒラリー・ハーン(ヴァイオリン)
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
マリス・ヤンソンス(指揮) |
2014 年版カタログ付お買い得DVD、ベルリン・フィル・イン・東京、ヤンソンス&ヒラリー・ハーンのショスタコ
収録:2000 年11 月26 日東京、サントリー・ホール(ライヴ)/画面:NTSC
16:9、音声:PCM ステレオ、DD5.1、DTS5.1、リージョン:All、99
分
毎年発売されるユーロアーツ・レーベルのカタログ付DVD。今年は、マリス・ヤンソンスがベルリン・フィルを率いて、2000
年に東京のサントリー・ホールでおこなった公演の模様を収めたDVD。
この映像がお買い得価格で登場するとは、なんとも驚き。ヒラリー・ハーンをソリストに迎えたショスタコーヴィチのヴァイオリン協奏曲。研ぎ澄まされた緊張感が映像からひしひしと伝わってきます。そしてメイン・プログラムは、ドヴォルザークの交響曲第8
番。オスロ・フィル、コンセルトヘボウ管とも録音しているヤンソンス得意のレパートリー。ここでは相性のよいベルリン・フィルと日本の聴衆を興奮のるつぼへ叩き込んだ圧巻の演奏を聴かせてくれます。
 
|
| |


20 59884
(Blu-ray)
\5000 →\4490 |
プレスラー90歳記念コンサート・アット・パリ
モーツァルト:
ピアノ協奏曲第23番イ長調K.488、
ロンド イ短調K.511、
ピアノ協奏曲第27番変ロ長調K.595
ドビュッシー:月の光
ボーナス:プレスラーとヤルヴィの対談
監督:セバスティアン・グラス&コランタン・ルコント |
パーヴォ・ヤルヴィ(指揮)
パリ管弦楽団
メナヘム・プレスラー(ピアノ) |


20 59888
(DVD)
\3000 →\2690 |
プレスラー90 歳記念コンサート・アット・パリ、プレスラー&ヤルヴィによるモーツァルトのピアノ協奏曲
収録:2012 年10 月17 日(K.595、ドビュッシー)、2014
年1 月29 日(K.488,K.511)、サル・プレイエル、パリ
(Blu-ray)画面:1080 60i画面:1080 60i、音声:PCM
ステレオ、DTS-HD Master Audio5.1、本編:82
分、ボーナス:13分、リージョン:All
(DVD)画面:PCM ステレオ、DD5.1、DTS5.1、本編:82分、ボーナス:13分、リージョン:All
1923 年生まれの巨匠ピアニスト、メナヘム・プレスラー。ボザール・トリオの創設メンバーとして長きに渡り活躍し、2008
年解散後から精力的にソリストとして世界各地でコンサートを行っています。2014
年に来日し、庄司紗矢香と行ったデュオ・リサイタルでは、慈悲深い演奏で静かな感動が会場に広がりました。
この映像は、2012 年と2014 年にパリのサル・プレイエルで行われた、パーヴォ・ヤルヴィ指揮パリ管弦楽団とのモーツァルトピアノ協奏曲のコンサートの模様。第27
番はまもなく89 歳を迎えようとした2012 年10
月パリ管定期演奏会での収録。モーツァルト最後の協奏曲である本作品は、崇高な美しさを持った名曲として親しまれています。プレスラーの作為的なものがまるで感じられない穏やかな演奏で、詩的で味わい深く聴かせてくれます。またアンコールのドビュッシーの月の光も、繊細さと抒情性に溢れる、聴く者の心の深淵に響く演奏です。
そして90 歳の誕生日を祝う記念コンサートで演奏された第23
番。この作品でなんといっても美しいのが第2
楽章。凛としたピアノソロではじまり、それを引き継ぐ木管群の哀愁漂う旋律。プレスラーの崇高な音楽がモーツァルト特有の天衣無縫な美しさを十二分に表現しています。プレスラーは2014年のベルリン・フィルのジルヴェスターコンサートでラトルと同曲を演奏予定です。
またプレスラーに寄り添うようなパーヴォ・ヤルヴィとパリ管の優しい演奏も好印象。なんとも心温まるライヴ映像集となっています。
旧譜
プレスラー、2012年と2013年の新録音! |

BIS SA 1999
(SACD HYBRID)
\2700 →\2490 |
まさか!メナヘム・プレスラー2012年、89歳時の最新録音!
(1)ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第31番
変イ長調Op.110[20’15]
(2)シューベルト:ピアノ・ソナタ第21番 変ロ長調D.960[45’07]
(3)ショパン:夜想曲第20番嬰 ハ短調 遺作[4’06] |
メナヘム・プレスラー(ピアノ) |
注目盤。これはすごい。室内楽界の至宝、メナヘム・プレスラー2012年、89歳時の最新録音!祈りに満ちたベートーヴェン、シューベルト、ショパン
録音:2012 年2 月、3 月/サフォーク州、ポットンホール、イギリス/5.0
Surround sound、70’33
SACD ハイブリッド盤。1923 年生まれのプレスラーが2012
年に録音した最新アルバムが登場。収録時は89
歳となり、曲はプレスラーが長年弾き続けてきたベートーヴェンのピアノ・ソナタ第31
番、シューベルトのピアノ・ソナタ第21 番、そしてショパンの夜想曲第20
番遺作です。
プレスラーは1955年より解散までの53年間、ボザール・トリオの創設メンバーとして活躍、1996年には当時72歳にしてカーネギーホールでリサイタル・デビューしたピアニストです。2008
年9 月6 日ルツェルン音楽祭でのコンサートをもってトリオは解散し、その後、現在に至るまでソリストとして世界各地でリサイタルを行っております。言わば「大器晩成」のピアニストですが、演奏は年を重ねるごとに成熟し、聴き手に音楽の本質をダイレクトに伝えてくれます。音色は明るく、また性格が滲み出ているような穏やかタッチは心を打たれます。
この収録曲を含むプログラムは、2011 年3
月23 日パリ、シテ・ド・ラ・ミュジーク(30
79668(DVD)/30 79664(Blu-ray))におけるライヴ映像が発売されており、静かなる情熱が伝わってきます。また、この公演後2011
年6 月に来日し、その時の公演は非常に話題となりました。2014
年4 月には庄司紗矢香とのデュオ・リサイタルで来日公演も予定しており、今なお進化し続ける室内楽界の至宝の音楽を間近で聴くことができそうです。 |
|
|
|
メナヘム・プレスラー、新録音!
シューベルト:ピアノ・ソナタ第18番 ト長調
D894
モーツァルト:ロンド イ短調 K511
ベートーヴェン:バガテルop.126 |
メナヘム・プレスラー
(ピアノ/スタインウェイ
(ハンブルク製、
インディアナ大学・ブルーミントン音楽学校蔵)) |
巨匠プレスラー、奇跡のシューベルト、モーツァルト、ベートーヴェン
録音:2013 年5 月22,23 日(ブルーミントン、インディアナ大学ジェイコブス・スクール)日本語ライナーノートつき
ベートーヴェン、シューベルト、ショパン作品集(BISSA
1999)も話題の奇跡の巨匠プレスラー。ラ・ドルチェ・ヴォルタレーベルからもウィーン楽派の傑作3
作品の登場となります。
シューベルトのト長調ソナタについて、プレスラーは『ある意味では、この音楽には悲劇はありません。第1楽章の「モルト・モデラート・エ・カンタービレ」は幻想曲ですが、演奏家自身がまさに「幻想曲」であることを感じ取らなければ、その性格を表現することはできません。ピアノ曲ではありますが、シューベルトはピアノを「忘れて」いると思われます。』と語っています。円熟の極みにあるからこそ成し得た奇跡的な名演がここにあります。モーツァルトのロンドに関しても、『この音楽にはあまりに多くの悲しみと喜びが、自分が体験しないと表現できないことがつまっています」「過去の幸福を思いだしているモーツァルトが思い浮かびます』と、意味深な言葉を寄せていますが、一音一音に魂がこもった神の領域の演奏といえるでしょう。ベートーヴェンも肩の力が抜けきった、天上の響き。巨匠が誘う絶美の世界です。
|
|
| |

20 45094
(Blu-ray)
\5000 |
1999年ヘルダー教会で行われたクリスマス・オラトリオ
J.S.バッハ:クリスマス・オラトリオBWV248
【ドキュメンタリー】
・「歓呼の声を放て、喜び踊れ!」〜ガーディナー、カンタータ巡礼の旅
・バッハ再訪〜ガーディナー、ザクセン=テューリンゲンを訪れる |
ジョン・エリオット・ガーディナー(指揮)
イングリッシュ・バロック・ソロイスツ
モンテヴェルディ合唱団
クラロン・マクファーデン(ソプラノ)
ベルナルダ・フィンク(アルト)
クリストフ・ゲンツ(テノール)
ディートリヒ・ヘンシェル(バス) |
|
|
ガーディナー、カンタータ巡礼の第1歩となったコンサート、1999年ヘルダー教会で行われたクリスマス・オラトリオ遂にブルーレイで登場
収録:1999 年12 月23 & 27 日ワイマール、ヘルダー教会
(Blu-ray)画面:1080 69i、音声:PCM ステレオ、DD5.1、DTS5.1、リージョン:All、字幕:英独仏韓、日本語、145分(+2×26分ドキュメンタリー)
(DVD)画面:NTSC 16:9、音声:PCM ステレオ、DD5.1、DTS5.1、リージョン:All、字幕:英独仏韓、日本語、145分(+2×26分ドキュメンタリー)
大家ガーディナーによる演奏で聴く6 曲のカンタータからなるバッハの傑作「クリスマス・オラトリオ」。この映像はDVD
では以前リリースされていましたが、ブルーレイ化は初。
ガーディナーはバッハ没後250 年企画として、ヨーロッパとアメリカの約50
都市の教会を訪れ、バッハの教会カンタータ全曲を演奏するという壮大な企画「バッハ:
カンタータ巡礼」を打ち立て見事完走しました。
この演奏は、その巡礼の旅の出発点ともなった記念碑的コンサート。収録されたワイマールにあるヘルダー教会は、バッハの子供たちが洗礼を受けた場所で、クラーナハの祭壇画で知られています。
ガーディナーの明晰な解釈と細部までコントロールされた合唱陣、深々とした祈りの音楽を完璧に表現しています。さらに巡礼の旅へかけた思いと同様、ガーディナーの情熱が聴衆を感動に導きます。
ドキュメンタリーでも、ガーディナーはこの巡礼の旅への思いを語っています。

|
| |


20 59854
(Blu-ray)
\5000 →\4490 |
ヨーロッパコンサート2014/バレンボイム
ニコライ:「ウィンザーの陽気な女房たち」序曲
エルガー:交響的習作「ファルスタッフ」
チャイコフスキー:交響曲第5番 |
ダニエル・バレンボイム(指揮)
ベルリン・フィル |

20 59858
(DVD)
\3000 →\2690 |
開場50周年を迎えた本拠地ベルリン・フィルハーモニーでバレンボイムが指揮台にあがった2014
年ヨーロッパコンサート、プログラムは生誕450
年のシェイクスピア関連作品
収録:2014 年5 月1 日ベルリン・フィルハーモニー
(Blu-ray)画面:1080i Full HD 16:9、音声:PCM
ステレオ、DTS-HD Master Audio5.1、リージョン:All、90分(+ボーナス10分)
(DVD)画面:NTSC 16:9、音声:PCM ステレオ、DTS
5.1、DD5.1、リージョン:All、90分(+ボーナス10分)
1882 年5 月1 日に創立されたベルリン・フィル。毎年記念日である5
月1 日に行われるヨーロッパコンサートは、ヨーロッパ各地の名所旧跡で行われ聴衆を楽しませています。
2014 年は、ベルリン・フィルの本拠地ベルリン・フィルハーモニー。2014
年は開場50 周年を迎えたため、地元ベルリンで開催されました。プログラムは、シェイクスピア生誕450
周年にちなむ作品を取り上げています。指揮はバレンボイム。
コンサートは、シェイクスピアの戯曲「ウィンザーの陽気な女房たち」に基づくオットー・ニコライのオペラ「ウィンザーの陽気な女房たち」の序曲で開始されます。そして英国を代表する作曲家エルガーの交響的習作「ファルスタッフ」。シェイクスピアの戯曲「ヘンリー4
世」に登場するファルスタッフを管弦楽曲で描いた作品です。R.
シュトラウスの交響詩を思わせるオーケストレーションと、エルガーらしい抒情的に歌われる穏やかなメランコリーが魅力的な曲。ベルリン・フィルの巧みな表現力とバレンボイムの的確な解釈で聴かせています。
そして最後はシェイクスピアを愛した作曲家チャイコフスキーの交響曲第5
番。この作品は近年ベルリン・フィルではあまり取り上げられていませんが、バレンボイムは、1995
年にシカゴ響と2004 年にウエスト・イースタン・ディヴァン・オーケストラと録音しています。人間の感情表現が織り込まれた作品で、音響的な盛り上がりをみせる終楽章に向けてテンポがあがっていき、バレンボイム特有の密度の濃い演出で、高い演奏効果が感じられ、公演の興奮が伝わってくる演奏です。

|

|
|
![]()