≪第78号アリアCD新譜紹介コーナー≫
その9 10/14〜
マイナー・レーベル新譜
歴史的録音・旧録音
メジャー・レーベル
国内盤
映像 |
10/17(金)紹介新譜
マイナー・レーベル新譜
 CONTINUO CONTINUO
|
|
|
ローマのサン・ルイージ・デ・フランチェージ教会のメルクリン・オルガン
フロール・ペーテルス(1903-1986):
アヴェ・マリス・ステラによるトッカータ、フーガと賛歌
Op.28
セザール・フランク(1822-1890):
コラール第1番ホ長調 FWV38/コラール第2番ロ短調
FWV39
グレープ・ニクーリン(1974-):
過ぎ越しのいけにえ [Victimae paschali
laudes] Op.22
ルイ・ヴィエルヌ(1870-1937):月の光 Op.53
No.5
マルコ・エンリコ・ボッシ(1861-1925):ラルゲット
Op.132 No.1
フロール・ペーテルス:フランドル狂詩曲
Op.37 |
ナターリア・バギンスカヤ(オルガン) |
|
録音:2013年9月23-26日、サン・ルイージ・デ・フランチェージ教会、ローマ、イタリア
使用楽器:1880年、ヨゼフ・メルクリン製
カラヴァッジョの祭壇画でも有名なローマのサン・ルイージ・デ・フランチェージ教会(ローマ在住のフランス人のために建てられた教会、1589年完成)に1880年に設置されたヨゼフ・メルクリン(1819-1905)製のオルガンを演奏。
メルクリンはドイツのオーバーハウゼンに生まれ、ブリュッセルでオルガン製作家としての活動を開始。パリ、リヨンに拠点を移動し1870年にはフランス国籍を取得、アリスティド・カヴァイエ=コル(1811-1899)のライバルとも称されました。
サン・ルイージ・デ・フランチェージ教会のオルガンはローマでは珍しいフランス式で、当録音でもこの楽器にふさわしい楽曲が選ばれています。ボッシはイタリア、ペーテルスはベルギー、ニクーリンはロシアの作曲家。
|
 DUX DUX
|
|
|
ドビュッシー、ラヴェル、ドヴォルジャーク:ピアノ三重奏曲集
ドビュッシー(1862-1818):ピアノ三重奏曲ト長調(1880)
ラヴェル(1875-1937):ピアノ三重奏曲(1914)
ドヴォルジャーク(1841-1904):ピアノ三重奏曲第4番ホ短調「ドゥムキー」Op.90 |
ダロフ三重奏団
マリア・ダロフ=クヤヴィンスカ(ピアノ)
アンナ・ダロフ(ヴァイオリン)
トマシュ・ダロフ(チェロ) |
| |
|
|
バッハvsブゾーニ
J・S・バッハ(1685-1750)/ブゾーニ編曲:シャコンヌ
ニ短調 BVB24
ブゾーニ(1866-1924):バッハによる幻想曲
BV253/対位法的幻想曲 BV256 |
ウーカシュ・クフャトコフスキ(ピアノ) |
| |
|
|
強健王アウグスト2世時代のドレスデンの音楽
ヴィヴァルディ(1678-1741):ソナタ ト短調
RV26
ヨハン・フリードリヒ・シュライフォーゲル(?-1750頃):ソナタ第1番ニ短調(*)
ヨハン・ダーヴィト・ハイニヒェン(1683-1729):ソナタ
ニ長調
ヨハン・フリードリヒ・シュライフォーゲル?:
ソナタ第4番ト短調(*)/ソナタ第3番ヘ長調(*)
フェリッポ・ベンナ(?-1750頃):ヴァイオリン・ソナタ
ヘ長調(+)
フランチェスコ・マリア・ヴェラチーニ(1690-1768):ソナタ
イ長調 Op.1 No.7
ヨハン・フリードリヒ・シュライフォーゲル?:ソナタ第2番ニ長調(+)(*) |
マルティナ・パストゥシュカ(ヴァイオリン)
クシシュトフ・フィルルス(ヴィオラ・ダ・ガンバ(*))
マルチン・シフィオントキェヴィチ(チェンバロ) |
|
録音:2013年6月13-15日、国立音楽学校コンサートホール、ビェルスコ=ビャワ、ポーランド
怪力無双にして精力絶倫、強健王と称されたポーランド・リトアニア共和国(1569-1795)国王アウグスト2世(1670-1733、在位:1697-1706、1709-1733年/ザクセン選帝侯フリードリヒ・アウグスト1世としての在位:1694-1733)。芸術を愛した彼のドレスデン宮廷楽団ではヴァイオリンの名手ヨハン・ゲオルク・ピゼンデル(1687-1755、1728年にコンサートマスターに就任)が活躍しました。
当盤の収録作品のうち、ドレスデンで出版されたヴェラチーニのソナタ以外はドレスデン州立図書館兼州立工科大学図書館が所蔵するピゼンデルの写譜に拠るものです。
(*)の4つのソナタとハイニヒェンのソナタ(第5番として配置)は一つの譜集にまとめられており、第2〜4番は作曲者表記を欠いていますが、ヴァイオリニストのマルティナ・パストゥシュカはその作風からヨハン・フリードリヒ・シュライフォーゲルの作と推定しています。シュライフォーゲルとフェリッポ・ベンナの生涯に関しては情報がほとんどありません。
マルティナ・パストゥシュカはポーランドのカトヴィツェ音楽アカデミーで現代奏法を学んだヴァイオリニスト。古楽奏法に興味を覚えピリオド楽器オーケストラであるアルテ・デイ・スオナトーリに参加。その後ポーランド国内外で様々なアンサンブルに参加、ソロ活動も行っています。
|
| |
|
|
ピオトル・モス(1949-):
静寂の…(クラリネット協奏曲)(*)
孤独(E・E・カミングズの詩によるアルトと管弦楽のための歌曲集)(+) |
ジャン=マルク・フサール(クラリネット、バスクラリネット(*))
ヤドヴィガ・ラッペ(アルト(+))
ポーランド国立放送交響楽団
ミハウ・クラウザ(指揮(*))
イェジ・マクシミュク(指揮(+)) |
| |
|
|
フランクとブラームスのヴァイオリン・ソナタをヴィオラで
フランク(1822-1890):ヴァイオリン・ソナタ
イ長調
ブラームス(1833-1897):ヴァイオリン・ソナタ第1番ト長調
Op.78(ニ長調に移調) |
エルジビェタ・ムロジェク=ロスカ(ヴィオラ)
ズビグニェフ・ラウボ(ピアノ) |
| エルジビェタ・ムロジェク=ロスカは1977年ポーランドのヤヴォジュノに生まれ、カトヴィツェ音楽アカデミーで学んだヴィオラ奏者。1998年よりAUKSO室内管弦楽団員。 |
| |
|
|
イレネウシュ・ウーカシェフスキ(1938-):
レギョノヴォの歌(無伴奏混声合唱のための)
Wojenko Wojenko / Hej Strzelcy / Marsz
Pierwszej Brygady
Kto Cie wolal Legionisto / O moj rozmarynie
Piosnka Batalionu Podhalanskiego /
Strzelcy / Kadrowka
Komendant / Warcza karabiny / Piechota
/ Roze / Leguny |
ポーランド室内合唱団
ヤン・ウーカシェフスキ(指揮) |
| |
|
|
真夏の幻想
ヘンリー・パーセル(1659-1695)/アンサンブル・コントラスト編曲:
3声のファンタジア Z.734
フランク・ブリッジ(1879-1941):ピアノ四重奏のための幻想曲嬰ヘ短調
H.94
ヘンリー・パーセル/アンサンブル・コントラスト編曲:4声のファンタジア
Z.735
オリヴィエ・ペナール(1974-):ピアノ四重奏のための幻想曲
Op.25 |
アンサンブル・コントラスト
アルノー・トレット(ヴァイオリン)
マリア・モスコーニ(ヴィオラ)
アントワーヌ・ピエルロ(チェロ)
ジョアン・ファルジョ(ピアノ) |
| |
|
|
イ・シンオ(韓国):
ピアノのためのコラール幻想曲第1番「慰めよ、慰めよ、わが民を」(2007-2009)
ピアノのためのコラール幻想曲第2番「首枷」(2013)
ピアノのためのコラール幻想曲第3番「アレルヤ」(2010/改訂:2013) |
ホ・ヒョジュン(ピアノ) |
 ENCELADE ENCELADE
|
|
|
クラヴサンのために調えられたオペラ・アリア集
クロード=ベニーニュ・バルバトル(1724-1799):
「クラヴサンのために調えられたオペラ・アリア選集」から
ピグマリオンの序曲(ラモー:「ピグマリオン」;1748)
バルバトル氏のアリア(I & II)/モンドンヴィル氏のアリア
ルベル氏のガヴォット(I & II)/エコーのアリア
スカルラッティのアリア(D・スカルラッティ:ソナタ
K.95)
ラモー氏のレ・プティ・マルトー
「遍歴の騎士」の序曲のアリア(ラモー:「遍歴の騎士」;1760)
「On ne s'avise jamais de tout」のアリア
(モンシニー:「On ne s'avise jamais
de tout」;1761)
ピグマリオンのパントマイム(ラモー:「ピグマリオン」の行進曲)
優雅なガヴォット(I & II)/ダンデルのメヌエット
ジガ(ラモー:「ピグマリオン」のパントマイム)/バルバトル氏のメヌエット
コントルダンス(ラモー:「ピグマリオン」のコントルダンス)
フェラン氏のデリーのアリア
(フェラン:「ゼリー」の“Air pour
les suivants de l'Amour”;1749)
プラテのコントルダンス(ラモー:「プラテ」のプロローグ;1745)
パルナスの謝肉祭のミュゼット(モンドンヴィル/1749)
ダルダニュスのガヴォット(I & II)(ラモー:「ダルダニュス」;1739)
ティトンと曙の女神(I & II)(モンドンヴィル:「ティトンと曙の女神」;1753)
デジャルディーノ氏のアリア/ルベル氏のロンド(I
& II)
ルベル氏のガヴォット
ティトンと曙の女神のガヴォット(I &
II)
(モンドンヴィル:「ティトンと曙の女神」のアリア)
バルバトル氏のアルマンド
ジョゼフ=ニコラ=パンクラス・ロワイエ(1705-1755):
クラヴサン曲集第1巻(1746)から
アルマンド(ロワイエ:「愛の力」の“いけにえのための行進曲”;1743)
ラ・センシブル
スキタイ人の行進(ロワイエ:「ザイード」の“トルコ人のためのロンド風アリア;1739) |
カトリーヌ・ジマー(チェンバロ) |
|
録音:2010年11月1-3日、レヴィ教会、レヴィ・サン・ノム、イヴリーヌ県、フランス
使用楽器:マルティーヌ・アルジェリース製(モデル:グジョン製)
調律:マルティーヌ・アルジェリース(D'Alembert-Rousseau,
415Hz)
フランスの作曲家・鍵盤楽器奏者クロード=ベニーニュ・バルバトルがジャン=フィリップ・ラモー(1683-1764)、ジャン=フェリ・ルベル(1666-1747)、ジャン=ジョゼフ・ド・モンドンヴィル(1711-1772)、ジョゼフ=ヤシント・フェラン(1709-1791)、ピエール=アレクサンドル・モンシニー(1729-1817)らの作品をチェンバロ(クラヴサン)用に編曲したスコアをメインとしたディスク。カトリーヌ・ジマーは知られざる・忘れられたフランス鍵盤音楽の発掘・紹介に積極的に取り組んでいるフランスのチェンバロ奏者。
|
| |
|
|
J・S・バッハ(1685-1750):フランス風序曲ロ短調
BWV831
序曲 / クラント / ガヴォット Gavotte
I & II / パスピエ I & II
サラバンド / ブーレ I & II / ジグ
/ エコー
フランソワ・クープラン(1668-1733):
クラヴサン曲集第2巻(1716頃)から 第8組曲
女流画家 / 女流詩人(アルマンド) /
クラント / 第2のクラント
風変わり(サラバンド) / ガヴォット
/ ロンドー / ジグ / パッサカリア
モラン嬢 |
ジャン=リュック・オー(チェンバロ) |
|
録音:2011年4月27-29日、レヴィ教会、レヴィ・サン・ノム、イヴリーヌ県、フランス
使用楽器:1983年、エミール・ジョバン製(モデル:1749年、グジョン製)
調律:エミール・ジョバン(406Hz)
フランスの若手チェンバロ&オルガン奏者ジャン=リュック・オー(姓をホーとする表記もあります)による流麗にして闊達なバッハとクープラン。
バッハのフランス風序曲はクープランの組曲を範として書かれたとも言われています。ジャン=リュック・オーはパリ音楽院でチェンバロをオリヴィエ・ボーモン、ブランディーヌ・ランヌに師事し2006年卒業。ブランディーヌ・ヴェルレにも教えを受け大きな影響を受けました。“Le
Choix de France Musique” および “Diapason
decouverte” 選定盤。
|
| |
|
|
トマゾ・アルビノーニ(1671-1751):ヴァイオリン・ソナタ集
ソナタ ハ短調 Op.6 No.10(1711)
ソナタ変ロ長調「ピゼンデル氏のために」(1716-1717)
ソナタ イ短調 Op.6 No.6(1711)/ソナタ
IV イ長調(1717)
ソナタ ト短調 Op.6 No.2(1711) |
ギヨーム・ルバンゲ=シュドル(ヴァイオリン)
クレール・グラットン(チェロ)
ジャン=リュック・オー(チェンバロ)
|
|
録音:2011年11月7-10日、レヴィ教会、レヴィ・サン・ノム、イヴリーヌ県、フランス
使用楽器:
ヴァイオリン:クリスチャン・ロー [Christian
Rault] 製
(モデル:1720頃、ヴェネツィア、ドメニコ・モンタニャーナ製)
チェロ:2006年、シルヴァン・ルスティコーニ製
(モデル:17世紀終盤、クレモナ、フランチェスコ・ルッジェーリ製)
チェンバロ:1998年、ギヨーム・ルバンゲ=シュドル製
(モデル:1730年頃、ハノーヴァー派の不詳作者製、ジャーマン・タイプ)
ギヨーム・ルバンゲ=シュドルはエレーヌ・シュミット、エンリーコ・ガッティに師事したフランスのヴァイオリニスト。チェンバロも弾き、その上なんとチェンバロ製作もしています。
当録音には彼が製作したチェンバロが使用されています。
|
| |
|
|
C・P・E・バッハ 遺言と約束
クラヴィーアとヴァイオリンのための作品集
カール・フィリップ・エマヌエル・バッハ(1714-1788):
ヴァイオリンを伴うクラヴィーア幻想曲
Wq.80 H.536(1787)(*)
「スペインのフォリア」による12の変奏曲
Wq.118/9 H263(1778)(*)
クラヴィーアのための幻想曲ハ短調 Wq,63/6
H.75(1753)
ヴァイオリンとクラヴィーアのためのソナタ
ハ短調 Wq.78 H.514(1763)(*)
クラヴィーアのためのソナタ イ長調 Wq.55/4
H.186(1765-1779)
チェンバロとヴァイオリンのためのアリオーソ
Wq.9 H.535(*) |
アリーヌ・ジルベライシュ(タンジェント・ピアノ)
アリス・ピエロ(ヴァイオリン(*)) |
|
録音:2012年10月4-7日、ラ・クールワ、ヴォクリューズ県、フランス
使用楽器:
タンジェント・ピアノ:1993年、ウィリアム・ユルゲンソン製
(モデル:1770年頃、レーゲンスブルク、シュペート&シュマール製)
ヴァイオリン:ジェレミー・ショー [Jeremy
Chaud] 製
(モデル:1742頃、ジュゼッペ・アントニオ・グアルネリ製「Lord
Wilton」)
C・P・E・バッハが円熟期から晩年にかけて鍵盤楽器のために書いた作品をメインに構成されたプログラム。タンジェント・ピアノ(タンゲンテンフリューゲル)はチェンバロからフォルテピアノに至る過渡期に現れた、タンジェントと呼ばれる木片で弦を叩く構造の鍵盤楽器。
アリーヌ・ジルベライシュはパリ音楽院、ボストンのニューイングランド音楽院で学んだフランスのフォルテピアノおよびチェンバロ奏者。アリス・ピエロはリヨン音楽院で学んだフランスのヴァイオリン奏者。2004年以来2014年現在ル・コンセール・スピリテュエル(エルヴェ・ニケ主宰)のファースト・ヴァイオリニストを務めています。
|
| |
|
|
あなたのそばに フランソワ1世の時代の鍵盤音楽
ピエール・アテニャン(1494頃-1552)出版:
Prelude / A mes ennuis / Pavane / Longtemps
y a / Pavane / Gaillarde
Gaillarde(+) / Tant que vivray(+) / Mon
cueur en vous / Prelude
Secourez moy / Branle commun & branle
gay / Gaillarde(*)
Dont vient cela / Gaillarde / Gaillarde
/ Branles(*) / Prelude sur chacun ton
Pavane / Gaillarde sur la pavane / Contre
raison / Aupres de vous
Pavenne / Gaillarde / Basse dance / Malgre
moy / Languir me fais(*/+)
Gaillardes |
ピエール・ガロン(クラヴィオルガヌム、ヴァージナル)
フレディ・エシェルベルジェ(クラヴィオルガヌム、ヴァージナル(*))
トマス・ダンフォード(リュート(+))
|
|
録音:2013年5月6-10日、Galerie des Affaires
Etrangeres、ヴェルサイユ市立図書館、
ヴェルサイユ、イヴリーヌ県、フランス
1531年1月から4月にかけてアテニャンが出版した7巻の鍵盤楽器用の譜集から選曲したディスク。クラヴィオルガヌム(クラヴィオルガン)は、一台の中にチェンバロまたはピアノとオルガンの発音システムを備えた鍵盤楽器で、演奏者一人で二重奏のように聴かせることも、同音を両方のシステムで重ねて鳴らしてちょっと不思議な音色を作り出すこともできます。
ピエール・ガロンはパリ音楽院でチェンバロをオリヴィエ・ボーモン、ブランディーヌ・ランヌに師事したフランスのチェンバロ奏者。
|
LABEL EURYDICE
|
フランスのパリに本拠を置く新しい古楽専門レーベル。 |
|
|
ゴセックとゲナン フランス革命混乱期の2人のヴァイオリニスト
マリー=アレクサンドル・ゲナン(1744-1835):トリオ
Op.1 No.4(1768)
フランソワ=ジョゼフ・ゴセック(1734-1829):
トリオ・ソナタ変ホ長調 Op.9 No.1(1766)
トリオ・ソナタ ヘ長調 Op.9 No.3(1766)
マリー=アレクサンドル・ゲナン:トリオ Op.1
No.6(1768) |
アンサンブル・エミオリア
ベランジェル・マヤール、
エマニュエル・レシュ(第1ヴァイオリン、ヴィオラ)
パトリツィオ・ジェルモーネ、
アルフィア・バキーエヴァ(第2ヴァイオリン)
クレール・ラムケ(チェロ)
フランソワ・ニコレ(フルート)
ジョン・オラベリア(オーボエ)
ニルス・コッパッレ(ファゴット)
エロディ・セイラニアン(チェンバロ) |
|
録音:2011年8月28-31日、サン・クレール礼拝堂、ムーラン、フランス
師弟関係にあるゴセックとゲナンのトリオ・ソナタ。アルバム・タイトルに反して革命前の作品ですが、貴重な録音と言えるでしょう。
アンサンブル・エミオリアは2008年にチェロ奏者のクレール・ラムケにより創設されたフランスのピリオド楽器アンサンブル。
|
| |
|
|
サンクトペテルブルク…パリ!
ピエール・クレモン(1784-1846):
2つのヴァイオリンとヴィオラまたはチェロのための
3つの協奏的三重奏曲 Op.13 から 第2番ニ長調(*)
2つのヴァイオリンのための3つの協奏的大二重奏曲
Op.10 から 第2番
2つのヴァイオリンとヴィオラまたはチェロのための
3つの協奏的三重奏曲 Op.13 から 第3番ト長調(*)/第1番長調(*) |
トリオ・コンコルディア
エマニュエル・レシュ、パトリツィオ・ジェルモーネ(ヴァイオリン)
クレール・ラムケ(チェロ) |
|
録音:2011年10月28-29日、2012年4月28-30日、リオー城の穀物倉、
ヴィルヌーヴ=シュル=アリエ、フランス
ピエール・クレモンはフランスのオーリアックに生まれた作曲家・ヴァイオリン奏者・指揮者。1803年、19歳にしてロシア皇帝アレクサンドル1世に招かれサンクトペテルブク宮廷楽長およびモスクワのフランス劇場監督に就任。1812年ナポレオン戦争によるフランス劇場の焼失を期に帰国、パリのオペラ・コミック座の指揮者に就任ロッシーニ、マイアベーア、ヴェーバー、ベッリーニらの作品を上演しました。
長らく忘れられた作曲家となっていましたが、1980年代中盤に作品が出版されて以降復興の機運が高まっています。Op.10は当盤が世界初録音。トリオ・コンコルディアはアンサンブル・エミオリアの弦楽器奏者から成る三重奏団。
|
| |
|
|
追放の道 ヘンデル:ドイツ語アリア&トリオ・ソナタ集
ヘンデル(1685-1759):
私の魂は見つつ聴く HWV207/快い静けさ、安らぎの泉
HWV205
暗い墓穴から来たおまえたち HWV208
トリオ・ソナタ ロ短調 Op.2 No.1 HWV386
先なる日々の思いわずらい HWV202/歌え、魂よ
HWV206
かわいい矢車草の花 HWV204
トリオ・ソナタ ト短調 Op.2 No.2 HWV387/燃えるばら
HWV210
快い茂みの中に HWV209/戯れる波のきらめく輝き
HWV203
|
アンサンブル・エミオリア
キャプシーヌ・メーンス(ソプラノ)
エマニュエル・レシュ、
アルフィア・バキーエヴァ(ヴァイオリン)
クレール・ラムケ(チェロ)
エロディ・セイラニアン(チェンバロ) |
|
録音:データ記載なし
ヘンデルの「9つのドイツ語のアリア」(HWV202-210)と2つのトリオ・ソナタを収録。
キャプシーヌ・メーンスは2007年にリール音楽院を卒業したフランスのソプラノ。古楽から現代音楽まで幅広く活動しています。
|
 MPMP MPMP
|
|
|
知られざるポルトガル・ロマン派の作曲家
アルフレド・カイルの世界初録音ピアノ作品!
ヨーロッパで活躍する日本人ピアニスト、八田智大デビューCD!
(牛田智大ではありません)
アルフレド・カイル(1850-1907):
詩的印象 Op.12
希望/思い出/追求/愛の誓い/海の歌/散歩/それは君/夢想
北国の歌/軽薄/祈り(御告げの鐘)/ボヘミアン
12のメロディー Op.9
君の笑顔!/ささやき/ギター/青春/かわいそうな花/蝶/むかしむかし
花の国/いまでも君のもの/おどけた女の子/後悔/小さなジャンヌ |
八田智大(ピアノ) |
|
録音:2013年7月30日-8月2日、リスボン国立音楽院サロン・ノブレ、リスボン、ポルトガル
使用楽器:1876年、グロトリアン=シュタインヴェーク製
|
【ピアノの画家 アルフレド・カイル】
収録作品の楽譜の再版に合わせて発売されるこのCDは、3つ−1人の作曲家、1人のピアニスト、1台のピアノ−の発見をする機会を与えてくれます。これは注目に値することであり、アルフレド・カイルの音楽を聴く機会という意味だけでも長らく待ち望まれていたと言えるでしょう。カイルのピアノ作品の録音は今までいくつかのCDに少しずつ収録されていただけで、まとまった形のCDが発売されたことがないのは信じ難いことです。そして、彼の最も重要な作品であるオペラ「セラナ」のDVDどころかCDさえ存在しないという事実に、信じ難い思いはいっそう強まります。
カイルのピアノ作品集のCDの解説を書くにあたってこの有名なオペラのことを思い出したのは別におかしな話ではないでしょう。なぜなら、「セラナ」と彼のピアノ作品との間に興味深い共通点を見出すことができるからです。
最も明らかな第一の点は、情熱あふれる、繊細で上品で快活なリリシズムです。ほとんどの作品は歌詞があれば歌うことができそうですが、それは彼のピアノ書法が語法的であるからに他なりません。もし実際に歌詞を付けてピアノ伴奏歌曲に書き換えたらむしろ漫画的に聴こえてしまうでしょう。カイルはピアノだけで歌を思わせるように極めて巧妙に書き上げているのです。実のところ、歌詞は存在するとも言えます。物語は曲集のプログラム通り、各曲のタイトルによって語られているのです。そしてまさにこの点が、八田智大がこの録音のために選ばれた楽器の「歌うピアノ」という特質をみごとに引き出すきっかけにもなっているのです。このピアノは1876年グロトリアン=シュタインヴェーク製の現在個人蔵となっている稀少品で、クララ・シューマンが所有したものに近似しています。
第二の点は、より主観的ですが、「ポルトガルらしさ」志向です。それはかすかに立ちのぼる芳香のようなものであり、タイトルに示されているわけでもそれらしい音楽素材が指摘されるわけでもありません。全体としては未だシューマン的ロマンティシズムの影響下にあり、カイル以前や同時代の数多くの作曲家たちのロマンティックな小品を思い起こさせます。しかしながら、たとえば「海の歌」を聴くと、海にまつわる叙事詩に登場するポルトガルの男の姿がどうしても思い浮かんでしまうのです。一連の力強いコントラスト、ノスタルジックなメロディー、ポルトガルギター的な装飾とカデンツァ、それらにはファドを思わせる何かが有りはしないでしょうか?
カイルのピアノ作品が持つ親密な資質は、大ホールより家庭的なサロンやプライベート・コンサートで演奏するのにふさわしいものです。つまりこれらはリスト的な技巧誇示とは対極にあるレパートリーということになります。しかしそれは必ずしもカイルの曲の演奏が容易であることを意味するわけではありません。カイルはおそらく音楽愛好家・趣味でピアノを弾く人・感性と才能ある良家の女性などが弾くことを想定して書き始めたにもかかわらず、中には難易度が高くなっているものもあるのです−純粋でときに儚げな美質がパトスを覆い隠している(たとえば「祈り」、「後悔」)、アマチュアの手には負えない鋭敏なテクニックが要求される(たとえば「蝶」、「夢想」)など。「12のメロディー」はポルトガル国王ドン・ルイス1世に、「詩的印象」はスペイン王妃ドナ・マリア・クリスティナに献呈されました。
これら2つの曲集がカイルのピアノ作品のすべてではありません。彼はこのジャンルに他にもたくさんの作品を残しています。それらのほとんどは同じく気取らないもので、カイルの絵画におけるタッチの柔らかさに通じる純粋に甘美な作品が目立ちます。しかし残念なことにそれらの大半は手稿譜の形でしか残っておらず、それらを良好なコンディションで演奏し普及させるためには音楽学的研究と校訂の作業を待たねばなりません。2つのピアノ曲集を初めて全曲収録したこのCDが、この非凡な作曲家のピアノ作品全集の最初の一巻となることを願っています。
— エドワルド・ルイス・アイレス・ダブレウ
【アルフレド・クリスティアノ・カイル】
アルフレド・クリスティアノ・カイルは1850年7月3日、ポルトガルのリスボンに生まれた。父はドイツのハノーヴァーからポルトガルに政治亡命したヨハン・クリスティアン・カイル、母はアルザス系ドイツ人ヨゼフィーナ・シュテルフルーク。ヨハン・クリスティアンは当時最も有名な仕立屋であり、国王ドン・ルイス他ポルトガル内外の貴族から注文を受けるほどであった。
ヨハン・クリスティアンは他にも様々な事業に投資を行い成功したので、カイル家はたいへん裕福であった。そのおかげでアルフレドは最高水準の教育を受けることができた。サン・アントニオ学院に入学、8歳でアントニオ・ソレル(Antonio
Soller, 1840-?)の生徒となり音楽の勉強を始め、その後リスボンの英国人学校に進学しヨーロッパを旅した。彼の作品1「Pensee
musicale」は12歳の時に書き母に捧げたピアノ曲である。18歳を前にニュルンベルク(ドイツ)の芸術アカデミーに入学。しかし1870年普仏戦争のため帰国を余儀なくされ、その後絵画をミゲル・ルピ(1826-1883)に、デッサンをジョアキム・プリエトに、音楽をアントニオ・ソアレス、エルネスト・ヴィエイラ(1848-1915)、オスカル・デ・ラ・シナ(1836-1906)に師事。画家として受賞を重ね、マドリード、パリ、リオデジャネイロで作品が展示され成功を収めた。
作曲家としては1883年トリンダーデ劇場(リスボン)で上演されたオペラ「スザンナ」でデビュー。1888年にサン・カルロス劇場で初演されたアルメイダ・ガレット(1799-1854)の叙事詩によるオペラ「ドンナ・ビアンカ」は年内上演30回を数え翌年に引き継がれ、リオデジャネイロのリリコ劇場でも成功を収めた。1890年イギリスがポルトガルに軍のアフリカからの撤退を要求する最後通告を行うと、カイルは愛国歌「A
Portuguesa」を作曲、これが後に現ポルトガル国歌に制定されることになる。1893年オペラ「イレーネ」をトリノ(イタリア)で初演、イタリア国王ウンベルトから勲章を贈られた。オペラに熱中したカイルはヴェルディ、マスネと交流し彼らから自作への称賛を得た。
カイルのオペラの中で最も有名かつ重要なのは1899年に初演された、エンリケ・ロペス・デ・メンドンサ(1856-1931)台本による「セラナ」である。初演はイタリア語で歌われたが、後に上演されたポルトガル語版はサン・カルロス劇場においてポルトガル語で歌われた最初のオペラとなった。「セラナ」はポルトガルの作曲家が書いたポルトガル語のオペラの中で20世紀に最も数多く上演された作品となっている。カイルの才能は絵画と音楽にとどまらなかった。彼は詩人でもあり楽器コレクターでもあった。没後、詩集「エニシダとローズマリー」が出版され、400を超えるたいへん貴重な楽器コレクションはポルトガル音楽博物館の所蔵品となっている。アルフレド・クリスティアノ・カイルは1907年10月4日、57歳で没した。厖大な数の絵画(2,000点以上)と音楽作品(目録には未収録)が残された。2つのオペラ「シマゥン、赤毛の男」と「インディア」が残念ながら未完に終わった。
【八田智大】(はった ともひろ)
1986年札幌市生まれ。5歳よりピアノを始め、10歳より札幌コンセルヴァトワールで学ぶ。日本国内のコンクールでは、PTNA全国決勝大会F級にて2年連続で銅賞・銀賞、洗足学園前田賞受賞をはじめ、その他数々のコンクールで上位入賞を果たす。2005年、北海道札幌平岸高等学校を学校名誉賞を受賞し卒業後、渡仏。パリ・エコール・ノールマル音楽院に入学し、ピアノ科の高等課程ディプロマ(満場一致)、最高課程ディプロマを取得。その間、フジテレビ奨学金を受ける。2008年、パリ国立地方音楽院に入学し2011年に審査員満場一致の首席でディプロマを取得し卒業。2013年、国立ジュヌヴィリエ地方音楽院室内楽科にて審査員満場一致の最高位でディプロマ取得。2010年にはそれまでの実績が認められポルトガルのカステロ・ブランコ国立芸術大学の大学卒業資格を取得し、続いて大学院へ同大学院過去最高得点の満点にて入学。現在もカステロ・ブランコ国立芸術大学音楽学部・大学院にてパウロ・アルヴァレシュ氏に師事、研鑽を積んでいる。これまでに、遠藤真紀子、宮澤功行、ビリー・エイディ、カイオ・パガノ各氏に師事。
ルドルフ・フィルクシュニー国際ピアノコンクール第3位とスメタナ賞、ララ・マリアム王女国際ピアノコンクール第3位と特別賞、アレクサンドル・スクリャービン国際コンクール第2位、そしてマリア・カンピーナ国際コンクール審査員満場一致の賞賛付での第1位を受賞。ポルトー国際ピアノコンクール最年少セミファイナリスト。ロン・ティボー国際ピアノコンクール・セミファイナリスト。
17歳でロシア・サンクトペテルブルグ・シェレメーチェフスキー宮殿にて、サンクトペテルブルグ交響楽団とコンチェルト初共演。2009年にはフランスのメザン・アカデミー・オーケストラと共演を果たした。これまでにチェコ・フィルの本拠地ルドルフィヌム・ドヴォルザーク大ホール、アンヴァリッド・グランド・サロン、パリ・ショパン協会主催・第25回パリ・ショパン・フェスティバル、パリ日仏文化センターでの日仏交流150周年記念コンサートなど演奏してきたコンサートは国内外数多く、第11回・第12回カレ・ダス若き演奏家達の音楽祭での演奏は“ラ・レプブリック”紙をはじめ各地方誌等でも取り上げられ、高い評価を得た。
2009年、ヴァイオリニストのクリストフ・ブリエール氏とフランスのパリとメザンで共演し、グリーグのヴァイオリンソナタのCDを収録。12月30日、ポルトガル国営ラジオ放送ANTENA2にて、“2010年度、ショパンの年・オープニングコンサート”を任され世界ネットで生放送され、大成功を収めた。2010年、パリ、プレイエル・ホールでの“Bon
Anniversaire Monsieur Chopin”の演奏がテレビ・フランス3にて放送されたほか、フランスのラジオRGB、ラジオAligreでも名古屋、ポルトガルでのコンサートの演奏が放送されなど、メディアからも注目されるようになった。2010年は日葡修好通商条約150周年としてポルトガル人ピアニスト、リカルド・ヴィエイラとポルトガル、日本(名古屋、札幌)、そしてフランスのパリ・ポルトガル大使館で共演を果たした。
2011年はポルトガル・リスボンにて国営ラジオで2度目のライブ録音・コンサートとサンタレンでチャリティーコンサート、パリ日本文化会館でコンサート。カーボヴェルデ共和国ではポルトガル大使館・カモンイス院の招待によりプライア、ミンデロで日本人で初めてコンサートを行った。2012年、ポルトガルでカステロ・ブランコ国際芸術フェスティバルでのオープニングコンサートとコインブラの2都市でのリサイタル。その他2012年はスロベニアでのイマゴ音楽祭、インドのニューデリーとゴアでの音楽祭等でも演奏した。
2013年トルコのイスタンブールで開催されたイスタンブール・オーケストラシオン国際ピアノコンクールで第3位を受賞した。現在、ピアノ連弾デュオ”MusicOrba”としてポルトガル人ピアニスト、リカルド・ヴィエイラとのコンサート活動も行っている。現在、クードレー・モンソー市立とヴォレアル市立音楽院ピアノ講師。
|
<メジャー・レーベル>
 SONY SONY
|

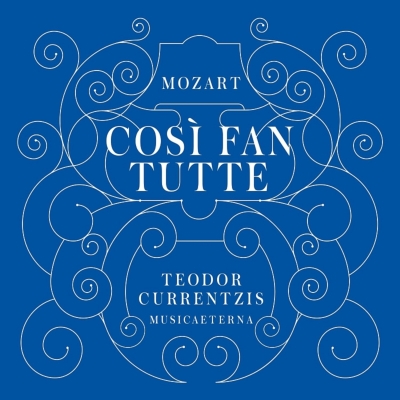
8876546616-2
(3CD)
\3600→\3390 |
鬼才天才クルレンツィス、モーツァルト・オペラ・シリーズ第2弾
モーツァルト:歌劇「コジ・ファン・トゥッテ」(全曲) |
テオドール・クルレンツィス指揮
ムジカエテルナ
ジモーネ・ケルメス(ソプラノ/フィオルディリージ)
マレーナ・エルンマン(メゾソプラノ/ドラベッラ)
クリストファー・マルトマン(バリトン/グリエルモ)
ケネス・ターヴァー(テノール/フェッランド)
アンナ・カシヤン(ソプラノ/デスピーナ)
コンスタンティン・ヴォルフ(バス/ドン・アルフォンソ) |
ギリシャからのNew Wave鬼才指揮者クルレンツィスのモーツァルト/ダ・ポンテ・オペラ第二作が早くも登場します!
これまで、パーセル「ディドーとエネアス」、モーツァルト「レクイエム」、ショスタコーヴィチ「交響曲第14番」(これは2010年度の音楽之友社レコードアカデミー賞を受賞)をリリースした後、ソニー・クラシカルとは2013年に長期契約を結び、手兵ムジカ・エテルナとモーツァルトの「ダ・ポンテ・オペラ三部作」をすべて録音する。
その第一弾「フィガロの結婚」(2014年4月日本盤発売済)に続く第二作がこの「コジ・ファン・トゥッテ」となります。
「フィガロ」の時と同様にバロック・オペラ界を牽引するソプラノ、ジモーネ・ケルメスをはじめとする歌手陣は各パートに合う歌い手をクルレンツィス自らが厳選したもので、歌唱スタイルやフレージング、ヴィブラートの使い方、そして装飾に至るまで細かく徹底させた究極の歌唱とサンサンブルを実現させています。
クルレンツィスが指向するのは自然なフレージングを重視した「最もオペラ歌手らしくない歌唱」(クルレンツィスの言葉)なのです。
録音:2013年1月9〜13日 ペルミ(セッション録音)
 
|
| |


8888379391-2
\2500→\2290 |
ノリントン(指揮)&チューリヒ室内管
モーツァルト:
『セレナード第5番ニ長調K.204/213a』
『ディヴェルティメント第10番ヘ長調K.247
「ロドロン伯爵家の夜の音楽」 |
ロジャー・ノリントン(指揮)
チューリヒ室内管弦楽団 |
ロジャー・ノリントン/モーツァルト:セレナードK.204,
ディヴェルティメントK.247
ロジャー・ノリントン&チューリッヒ室内管弦楽団とのソニー・クラシカル第2弾は、モーツァルトの作品。
これまでもノリントンは、ロンドン・クラシカル・プレーヤーズ、シュトゥットガルト放送交響楽団と数多くのモーツァルトの作品を録音してきましたが、ポストホルン・セレナード以外のセレナードやディヴェルティメントの録音は無かったので、ファンにはうれしいところ。
もちろん、ノリントンお得意のノン・ヴィヴラート奏法によるピュアトーンと、弦楽器の躍動的な旋律と管楽器の独特な絡み、リズミックな低弦などによって、今まで以上に生き生きとしたモーツァルトの音楽が展開されています。【録音】2013年6〜7月,
チューリヒ、ZKO-Haus |
| |


8888378823-2
(2CD)
\3400→\3090 |
ダニエル・ベーレ/
シューベルト:冬の旅(ピアノ・トリオ伴奏版&オリジナル版)
《CD1》
シューベルト:歌曲集『冬の旅』D.911
(D・ベーレによるピアノ・トリオ伴奏編曲版・世界初録音)
《CD2》
シューベルト:歌曲集『冬の旅』D.911(オリジナル版) |
ダニエル・ベーレ(T:CD1&2),
オリヴァー・シュニーダー(P:CD1&2),
アンドレアス・ヤンケ(Vn:CD1),
ベンヤミン・ニッフェネッガー(Vc:CD1) |
現代最高の「モーツァルト・テナー」であり、最近ではバロック〜古典派オペラ、エヴァンゲリストとして高い評価を得ているダニエル・ベーレ。また表現力豊かなリート歌手としてもリリカルな声と正確な音程、そして適度に引き締まった解釈は、このシューベルトの歌曲は最もふさわしいといえましょう。
このアルバムは、テノールのベーレ自らピアノ・トリオ伴奏用に編曲したものと、オリジナルのピアノ伴奏版も収録。オリヴァー・シュニーダー・トリオは、ピアノ三重奏曲の延長上にあるようなシューベルト後期の味わい深さを大切にし、一貫した雰囲気が醸成された編曲は、ピアノでは表現なしえなかったシューベルトの死への恐怖や、暗鬱で絶望的な心の響きを弦が表しているように感じられます。
歌い方も、オリジナル版での全曲に一貫して流れる叙情性がベーメの美声で堪能できるものとは異なり、弦を引き立たせることによって、自分の内面をネガティブに悲観的に振り返るという姿を描いたヴィルヘルム・ミュラーの詩そのものを深々と語るように歌われます。
【録音】2013年6月, チューリヒ放送スタジオ |
| |

8887503325-2
\2500 |
ティボー・コーヴァン / アルベニスへのヴォヤージュ
アルベニス:
『スペイン組曲第1集Op.47』『マヨルカOp.202』
『スペインの歌Op.232〜コルドバ』 |
ティボー・コーヴァン(G) |
フランス期待の若手クラシカル・ギタリスト、ディボー・コーヴァンによるフランス・ソニー(ヴォーグ)への2枚目のアルバムは、アルベニスのピアノ曲をギター用に編曲したアルバム。いずれもスペイン的な色彩を持つ小品で、どれもが郷愁に溢れ、ギターで演奏するにふさわしい甘美な旋律を堪能することができます。
コーヴァンは、全てのこれらの曲順を入れ替え、この1枚のアルバムを1つの組曲として演奏します。もともとピアノ曲であった完成度の高い独創的なこの作品らを、コーヴァンは、躍動感あふれるリズムとメロディで、スペイン的な情感をそのままダイレクトに伝えてくれます。
「これまで世界120カ国で1000回以上の演奏会を行なってきました。これによって私はノマドのように旅好きな人間になりました。このアルバムでは、みなさんを色彩と感情、そして美しさにあふれたスペインのアルベニスへの世界へとご招待いたします。これらの作品に相応しい、100%ピュアなサウンドを確保するために、私はクラシック音楽の録音としては全く異例の場所、世界最高のワインを生み出すワイナリー、シャトー・ラフィット・ロートシルトのホールを選びました。」——ティボー・コーヴァン
ティボー・コーヴァンは、「彼ほどカリスマ性を感じさせるギタリストはいない」と絶賛され、現在世界で最も才能のあるギタリストと高い評価を得ています。ギタリストの父親のもと6歳よりギターをはじめ、パリ高等音楽院を卒業後、20歳の時の1年間に世界中で行われた13の国際コンクール全てで優勝。2013年2月に来日した際には「テクニックはもちろん、深い響きと繊細な歌心に惹きつけられた演奏」と絶賛を浴び、ギター誌「ギター・ドリーム」の表紙にも登場しています。
【録音】2014年9月, フランス、シャトー・ラフィット・ロートシルト
 |
| |


8888378585-2
\2500→\2290 |
ドロテア・レシュマン/ポートレイト
シューベルト:
『ミニョンの歌 D 877-2』『ミニョンの歌 D
877-3』
『ただ憧れを知る者だけが D.877-4』
『ミニョンの歌 D.321』『トゥーレの王
D.367』
『糸を紡ぐグレートヒェン D.118』
『グレートヒェンの祈り D.564』/
シューマン:『メアリー・スチュアート女王の詩
Op.135』/
R.シュトラウス:
『夜 Op.10-3』『明日の朝 Op.27-4』『悪天候
Op.69-5』
『解き放たれて Op.39-4』/
ヴォルフ:『ミニョンの歌』 |
ドロテア・レシュマン(Sp),
マルコム・マルティノー(P) |
今や世界の歌劇場を席巻するドイツの名ソプラノ、ドロテア・レシュマンによるドイツ・リートのアルバムが登場。
レシュマンが世界的に注目されることになったのは1995年、ザルツブルク音楽祭におけるアーノンクールの指揮による「フィガロの結婚」のスザンナ役でした。
それからほぼ20年を経て、彼女の声はますます円熟を深め、一層の表現力を備えています。
このアルバムでは、3人の女性の「音による」肖像画が描かれています。ゲーテの名作「ヴィルヘルム・マイスター修業時代」に登場するミニョン、そして「ファウスト」の永遠の女性グレートヒェン、実在の女王メアリー・スチュアート。
彼女たちの姿が目の前に浮かぶようなレシュマンの歌唱は、彼女が実際に訪れた美術館でインスパイアされた感情を載せ、その上で入念な解釈が凝らされたものです。それだけではなく、女性心理を巧みに描くことで定評のあるリヒャルト・シュトラウスの愛らしい歌曲を何曲かを組み合わせ、アルバムに色彩感を与えているのはさすがです。
女性たちの息づかいまでが聴こえてきそうなリアルな歌唱を丁寧に支えるのは、リート伴奏の第一人者マルコム・マルティノー。2002年にボストリッジとハイペリオンにシューマンの二重唱集を録音していましたが、おそらくドイツ・リートのソロ・アルバムは初めてと思われます。真に魅力的なアルバムをお楽しみください。
【録音】2013年6月、ロンドン、オール・セインツ教会 |
| |


8884309895-2
\2500→\2290 |
イヴァン・マルティン/ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第1&2番
ベートーヴェン:
『ピアノ協奏曲第1番ハ長調Op.15』
『ピアノ協奏曲第2番変ロ長調Op.19』 |
イヴァン・マルティン(P&指揮),
ガリシア交響楽団 |
スペインのピアニスト、イヴァン・マルティンのソニー・クラシカルへのデビュー・アルバムです。
マルティンは1978年グラン.カナリアで生まれ、ラス.パルマス音楽院を卒業後、マドリードで研鑽に努めました。また現代音楽の初演を数多く行うことで評価を得るだけでなく、バッハやモーツァルトなどのプロジェクトも手がけています。
最近では「ガルドス・アンサンブル」を結成し、様々な時代の音楽を試みています。この演奏では、ガリシア交響楽団とともに自分の弾きぶりで初期ベートーヴェンに挑戦。
その演奏は、明るい開放的な音色、そしてひとつのフレーズにうねりをつけながら対話をさせ、イマジネーションに満ちた演奏が繰り広げています。
【録音】2014年5月, パラシオ・デ・ラ・オペラ・デ・ア・コルーニャ
|

10/16(木)紹介新譜
マイナー・レーベル新譜
 2L(Blu-rayオーディオ) 2L(Blu-rayオーディオ)
|

2L 103PABD
(Blu-ray Disc Audio)
\3600 |
波動と中断(Waves & Interruptions)
ビョルン・ボルスタ・シェルブレード(1970-):
・動き(Movements)(マリンバとヴィオラのための)
・底流を認める(Recognizing the Undercurrent)
(ヴィブラフォーンのための)
・静止した流れ…(Still Waters…)(マリンバとバスフルートのための)
・絡み合い、動く線(Lines in Motion,
Entwined)
(ヴィブラフォーン、クロタル、フルート群とギターのための)
・ニュクス(Nyx)(ヴィオラのための)
・波動と中断(Waves & Interruptions)(マリンバのための) |
アイリク・ラウデ(打楽器)
イーダ・ブリューン(ヴィオラ)
トム・オッタル・アンドレーアセン
(フルート群)
トマス・シェクスタ(ギター) |
マリンバ、ヴィブラフォーン、バスフルート、ヴィオラ、ギター……楽器の音が「楽器」を超え、作曲者の思い描いた「音楽」となって聴き手を包みこむ
録音:2013 年8 月 ヤール教会(ベールム、ノルウェー)/5.1
DTS-HD MA(192kHz/24bit),2.0 LPCM(192kHz/24bit),mShuttle:FLAC
96kHz + MP3 Region ABC、72’26
制作:ヴォルフガング・プラッゲ、ビョルン・ボルスタ・シェルブレード
録音:エンジニアリング ビアトリス・ヨハンネセン
ミクシング、マスタリング:ビアトリス・ヨハンネセン、モッテン・リンドベルグ[DXD(352.8kHz/24bit)録音]
ノルウェーの作曲家シェルブレードの室内楽作品がBlu-ray
Disc Audio のアルバムでリリースされます。
打楽器奏者ラウデによって演奏されることを念頭におき、「メロディ楽器」としての打楽器をクローズアップした5
曲と、ヴィオラ・ソロのための1 曲。2001 年から2013
年にかけて書かれた作品です。
ビョルン・ボルスタ・シェルブレードは1970
年生まれ。ノルウェー国立音楽アカデミーのアスビョルン・スコートゥンとビョルン・クルーセに作曲を学び、ディプロマを取得、ルチアーノ・ベリオのアシスタントを務めたルカ・フランチェスコーニに私的に師事しています。編曲者、即興演奏家、音楽教師としても活動し、ノルウェーの俳優グループ「デ・ユートヴァルグテ」(選ばれし者たち)、ヴォーカルアンサンブル「ノルディック・ヴォイセズ」、ハンガリーのバンド「ファビュラ・ラサ」、スウェーデンのアンサンブル「ペーロル・フォール・スヴィーン」(豚に真珠体験)をはじめ、さまざまなジャンルの芸術家と共同作業を行ってきました。
このアルバムで演奏される作品には、ギリシア神話の「夜の女神」を曲名とするヴィオラのための《ニュクス》をのぞき、《動き》《底流を認める》《静止した流れ…》《絡み合い、動く線》《波動と中断》と抽象的なタイトルが与えられています。作曲家からの「解説」もなく、すべてが聴き手に委ねられます。
アルバムのメイン・アーティスト、打楽器奏者のアイリク・ラウデ(1973-)は、シェルブレードがしばしば共同作業を行ってきたプレーヤーです。《動き》《静止した流れ…》《波動と中断》のマリンバ、《底流を認める》《絡み合い、動く線》のヴィブラフォーン。スコートゥンとシェルブレードの言う「静けさ」が現実の「音」に表現されます。《絡み合い、動く線》では、アンティークシンバル「クロタル」も使われています。
アルバム『波動と中断』の録音セッションは、オスロに近いベールムのヤール教会で行われました。
※Pure Audio Blu-ray ディスクのアルバムです。
Pure Audio Blu-ray ディスクにはインデックスを除き映像は収録されていません。
Pure Audio Blu-ray ディスクはCD やDVD
のプレーヤーでは再生できないので、Blu-ray
プレーヤーもしくは Blu-ray 対応のPC をお使いください。
|
 ACCENTUS MUSIC ACCENTUS MUSIC
|
|
|
クリスマス・ソング集〜グロリア・イン・エクセルシス・デオ
1. シューマン:クリスマス・トッカータ
2. いと高きところに神の栄光あれ
3. ヘンデル:シバ女王の入城
4. ヘンデル:輝かしい熾天使は列をなして燃え上がり
5. ヘンデル:シオンの娘よ、大いに喜べ
6. 高き御空よりわれは来たれり
7. マリアはいばらの森を通り
8. チャイコフスキー:組曲「くるみ割り人形」(抜粋)
9. メンデルスゾーン:クリスマス(讃美歌)
10. エサイの根よりくすしき花は
11. メンデルスゾーン:それ、主汝のためにみ使いたちに命じ
12. 聴かせて、祝福された天使たち
13. エーベル:静かに雪が降り
14. 今宵鳴りわたる
15. アイレンベルク:ペテルブルクの橇の旅
16. ロジャー・ハーヴェイ:フェスティヴ・チアー
17. ジョン・フランシス・ウェイド:神の御子は今宵しも
18. フンパーディンク:夕べの祈り
19. ジークフリート・ケラー:星降る教会
20. フランツ・グルーバー:サイレント・ナイト
21. いざ歌え、いざ祝え |
ヴェルニゲローデ青少年合唱団
ペーター・ハーベルマン(コーラスマスター)
ルート・ツィーザク(S)
アンサンブル・ソノーレ
トーマス・クラモー(指揮)
ザクセン吹奏楽団 |
伝統的なヨーロッパのクリスマスを神聖な響きで聴く
録音:2012 年12 月聖母マリア教会、マリエンベルク、ライヴ/76’00
ドイツ南部、ヴュルツブルクの丘の上にある大司教の居館マリエンベルク要塞。要塞の中には8
世紀初頭の建築物である聖母マリア教会があります。
このCD は、2012 年12 月にその教会で行われたクリスマス・コンサート(
映像はACC20227DVD として既発売)。「いと高きところに神の栄光あれ」をはじめとした讃美歌、「くるみ割り人形」、「ペテルブルクの橇の旅」、「サイレント・ナイト」などクリスマス定番の曲が演奏され、伝統的なヨーロッパのクリスマスを味わうことができます。
1951 年に創設されたヴェルニゲローデ青少年合唱団は、ドイツのザクセン=
アンハルト州立音楽高校の15 〜18 歳の選抜メンバーによって構成されています。その清楚で美しい響きは、ドイツのみならず、世界中の合唱ファンを魅了しています。また、ソリストとして登場するのはソプラノのルート・ツィーザク。透明感ある清廉な歌声は、厳かなクリスマスの雰囲気を一層盛り上げます。 |
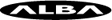 ALBA ALBA
|
|
|
トランペット協奏曲
ヨウニ・カイパイネン(1956-):トランペット協奏曲
Op.66(2003)
ヨーゼフ・ハイドン(1732-1809):トランペット協奏曲
変ホ長調 Hob.VIIe:1
アンリ・トマジ(1901-1971):トランペット協奏曲(1948) |
パシ・ピリネン(トランペット)
タンペレ・フィルハーモニー管弦楽団
ハンヌ・リントゥ(指揮) |
現代フィンランドを代表する作曲家カイパイネンのトランペット協奏曲、初演したピリネンが初録音に挑戦!
59’38
パシ・ピリネン(1969-)はフィンランドのトルニオ生まれ。シベリウス・アカデミーのジュニア・アカデミーで学んだ後、1988
年からロンドンのギルドホール音楽演劇学校のジョン・ミラー、ポール・コッシュ、スティーヴン・キーヴィの下で学びました。卒業後、クリーヴランドのマイケル・サックスとパリのアントワーヌ・キュレにも師事しています。1995
年から2005 年までフィンランド放送交響楽団の首席トランペット奏者、2005
年からはヘルシンキ・フィルハーモニー管弦楽団の首席奏者を務めています。コンセルトヘボウ管弦楽団、バーミンガム市交響楽団、オスロ・フィルハーモニック、王立ストックホルム・フィルハーモニックをはじめとするオーケストラで客演首席奏者として演奏、フィンランド・バロック管弦楽団ではピリオド楽器を演奏しています。ソロ奏者としても活動し、マックスウェル=デイヴィスの協奏曲、ヘンツェの《レクイエム》、ベリオの《セクエンツァX》を演奏、フィンランドのエーリク・ベリマンとハッリ・ヴェッスマンの協奏曲を初演しました。カイパイネンのトランペット協奏曲もピリネンが初演した作品です。
この作品は、カイパイネンが「エリート主義」的作風を離れる転機になったという1990
年のクラリネット協奏曲《今を楽しめ!》の後、オーボエ、ピアノ、サクソフォーン四重奏、ヴィオラ、ホルン、チェロ、ファゴット、ヴァイオリンとつづく、ソロ楽器と管弦楽のための作品のひとつ。フィンランド文化基金の支援を受けピリネンがカイパイネンに委嘱して作曲され、ピリネンが1997
年からメンバーを務める室内アンサンブル、アヴァンティ!の「夏の響き」フェスティヴァルで初演されました。〈アンダンテ〉〈コメ・カデンツァ:アレグロ〉〈ラルゴ・クヴィエト〉〈プレスト〉の4
楽章で構成された、演奏時間が約29 分半の作品です。初録音のカイパイネンの作品に続きハイドンとトマジ、トランペットのスタンダードレパートリーの協奏曲が2
曲演奏されます。 |
 ATMA CLASSIQUE ATMA CLASSIQUE
|
|
|
ラ・ヴェイエ・ドゥ・ノエル〜アカディアのクリスマス
1. La Veillee
2. Noel Lorrain / Noel Populaire
3. O Dieu l’ etrange chose
4. Noel de Cluny
5. Noel Dijonnais
6. Les Trois Mages
7. Noel Auxois
8. Plus on est de fous, plus on rit
9. Up and down the shouthern shore
10. Noel de Paris
11. Cantique de Noel
12. Joseph cherchant un logis
13. Les Cloches
14. Sir Symon the King / La Chandeleur
15. Escaouette
16. Plus on est de fous, plus on rit |
スージー・ルブラン(ソプラノ)
デイヴィッド・グリーンバーグ(ヴァイオリン)
アレクサンダー・ワインマン(クラヴサン)
ジャック・ゴートロー(ギター)
ニック・ハレー(打楽器)
ダニー・パーカー(ベース)
ステーヴ・ノルマンディン(アコーディオン) |
アカディア人のクリスマス・ソング集。カナダの美しきソプラノ、スージー・ルブランが歌う
録音:2014 年1 月メムラムコック、カナダ
カナダを代表する美しきソプラノ歌手スージー・ルブランが歌うクリスマス・ソング集。
このアルバムのきっかけは、2004 年に行われたクリスマス・コンサートでした。スージー・ルブランの従兄弟にあたるピウス・ルブランは、カナダのニューブランズウィック州メムラムコックのセント・ジョセフ大学で学びました。この大学は1966
年に閉鎖され、現在は北米のフランス系住民アカディアンにまつわる歴史的な文献などを集めた資料館として使用されています。大学は1864
年の設立から閉鎖までフランスから持ち込まれた歌を収集していました。主に1890
年代に刊行された「踊りと歌」という歌曲集から集められています。この歌をアカディアの人々は大切に歌い継いできており、スージー・ルブラン自身もアカディアのルーツを持ち、この度クリスマス・ソング集として録音されました。 |
 IPPNW IPPNW
|
|
|
ピアノはシフ!
IPPNW演奏会、歌曲の夕べ、名指揮者ドラティの歌曲集も!
ドラティ:歌曲集「声」(全11曲)
ムソルグスキー:歌曲集「死の歌と踊り」(全4曲) |
ハンノ・ミュラー=ブラッハマン(Bs-Br)
アンドラーシュ・シフ(P) |
ピアノはシフ!歌はミュラー=ブラッハマン!IPPNW演奏会、歌曲の夕べ、名指揮者ドラティの歌曲集も!
56’48”
IPPNW(核戦争防止国際医師会議)の慈善演奏会のCD、2013
年の演奏会の録音が登場しました。
大物演奏家が参加することで知られているこの演奏会、今回は非常に人気の高いドイツのバスバリトン、ハンノ・ミュラー=ブラッハマンの歌に、なんとアンドラーシュ・シフが伴奏ピアニストを務めています。
名指揮者アンタル・ドラティは作曲も手掛けています。「声
Die Stimmen」は、1975 年に作曲され翌年初演された歌曲集。ライナー・マリア・リルケの詩による作品で、「物乞いの歌」、「酒飲みの歌」、「自殺者の歌」、「未亡人の歌」など、全11
曲から成ります。調べがつきませんでしたが、これが初録音かもしれません。無調風の音楽は新ウィーン楽派を思わせるものです。
ミュラー=ブラッハマンは1970 年、ケルンの生まれ。バロック声楽曲から近現代歌曲まで幅広く手掛ける歌手です。ここ数年、著しく声と表現力を充実させており、ベルリンではバレンボイムの指揮でヴォータンも歌っています。ムソルグスキーの「死の歌と踊り」はもちろんロシア語での歌唱です。それにしてもシフの伴奏の素晴らしいこと!歌にピタリと寄り添い、余計に前に出ることは一切ないにも関わらず、常に強い存在感があります。ことにピアノがかなり活躍するムソルグスキーの「死の歌と踊り」の「司令官」は素晴らしいものです。
 
|
 CHRISTOPHORUS CHRISTOPHORUS
|
|
|
国際人 〜
オズヴァルト・フォン・ヴォルケンシュタインの歌 |
アンサンブル・レオネス
マルク・レヴォン
(歌、リュート、チェトラ、
ヴィオラ・ダルコ、指揮) |
国際的な中世ドイツの吟遊詩人!
「ジョスカン・デ・プレ(CHR 77348)」、「アレクサンデル・アグリコラ(CHR
77368)」らの器楽作品集といった、画期的なプログラムとクオリティの高い演奏で評判を呼んだアンサンブル・レオネス。
最新盤は、ヨーロッパから西アジア、北アフリカまで渡り歩いたという中世ドイツ語圏の詩人・作曲家、オズヴァルト・フォン・ヴォルケンシュタインの歌曲と器楽作品集。
「国際人(The Cosmopolitan)」というアルバム・タイトルのとおり、各地の文化を吸収・発展させていった、豊かで個性的な音楽が収録されており、カウ・ホルン、ハーディ・ガーディ、バグパイプ、中世フルート、ヴィエールなど、中世器楽のスペシャリスト達の演奏と歌が楽しめる。
※録音:2013年4月2日ー5日、ビニンゲン聖十字架教会(スイス)
レコード芸術2014年9月号海外盤REVIEW掲載! |
| |
|
|
マンフレディーニ:教会シンフォニア集Op.2
シンフォニア
第9番ハ長調/第8番ト長調/第3番変ロ長調/
第6番ト短調/第2番ニ短調/第11番イ長調/
第5番ロ短調/第7番ハ短調/第1番ヘ長調/
第4番ニ長調/第10番ホ短調/第12番ニ長調
※第10番、第12番を除く10曲は世界初録音 |
カプリコルヌス・コンソート・バーゼル
ペーテル・バルシ(指揮、ヴァイオリン) |
トレッリにヴァイオリンを師事し、聖フィリッポ大聖堂の音楽監督を務めたイタリア後期バロックの作曲家、フランチェスコ・マンフレディーニ(1684−1762)。作品3の中の「クリスマス協奏曲」で知られるマンフレディーニだが、それ以外の作品はほとんど録音の機会がなかっただけに、1709年にボローニャで出版された「教会シンフォニア集(Sinfonie
da chiesa)Op.2」のまとまった録音は嬉しい記録となる。
スイスのピリオド・アンサンブル、カプリコルヌス・コンソート・バーゼルは、丁寧な演奏で貴重で優雅なシンフォニアを聴かせてくれる。
※録音:2013年2月4日−7日、カトリック教会(ゼーヴェン、スイス) |
| |
|
|
モスクワ救世主ハリストス大聖堂 〜
ロシア正教会の新しい典礼の歌
ハスラー&トルカチェフ:合唱作品集 |
イリヤ・トルカチェフ(指揮)
モスクワ大司教座合唱団 |
モスクワの救世主ハリストス(キリスト)大聖堂で歌われる、モスクワ大司教座合唱団の歌声。ナタリア・ハスラー(b.1970)、イリヤ・トルカチェフ(b.1964)、二人の現代ロシアの作曲家によるロシア正教会の音楽。
2012年のラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポンでは力強い男声合唱を聴かせてくれたモスクワ大司教座合唱団だが、ここでは混声合唱で、ロシア正教会の伝統に根ざしながらも新たに拡張された現代のロシア音楽が歌われる。
※録音:2013年6月、モスクワ救世主ハリストス大聖堂(ロシア) |
| |
|
|
ピエール・ド・ラ・リューのレクイエムと聖母マリアのミサ曲
ラ・リュー:
レクイエム(死者のためのミサ)
聖母マリアのミサ |
ヴィルフリート・ロンバッハ(指揮)
アンサンブル・オフィチウム
|
数あるレクイエムのなかでも最初期に属する、ピエール・ド・ラ・リュー(c.1460−1518)のレクイエムと聖母マリアのミサ曲。
ヴィルフリート・ロンバッハによって1999年に結成された合唱アンサンブル、アンサンブル・オフィチウムは、2度のコンクール優勝歴を持つグレゴリオ聖歌とルネサンス声楽のスペシャリストで、Christophorusからも多くの録音が発売されている。
※録音:2002年2月、2003年11月、ドイツ |
| |
|
|
わが心 たたえよ主を 〜 テゼの歌 |
ノーマン・モリス(指揮)
リーディング・フェニックス・クワイア |
フランスのテゼ村から発足し世界に広がったキリスト教の修道会の1つ、「テゼ共同体」による祈りの歌。
民族や国、言語の壁を乗り越えた「和解」目指したテゼ共同体の祈りは、言語の異なる人々でも共に祈れるよう、聖書の単純な言葉を何度も繰り返して歌われるのが特徴。 |
 CORO CORO
|
|
|
スターバト・マーテル 〜 悲しみの聖母
単旋律聖歌:スターバト・マーテル
フィルソワ:スターバト・マーテル
コルヴィッツ:スターバト・マーテル
カショリーニ:スターバト・マーテル
マーティン:スターバト・マーテル
スカルラッティ:スターバト・マーテル |
ザ・シックスティーン
ハリー・クリストファーズ(指揮)
デイヴィッド・ミラー(テオルボ)
フランシス・ケリー(ハープ)
アラステア・ロス(オルガン) |
ザ・シックスティーンのスターバト・マーテル集!スターバト・マーテルの歴史に新たなページが加わる!
ザ・シックスティーン&ハリー・クリストファーズの"スターバト・マーテル集"は、単旋律聖歌(プレーンソング)、ドメニコ・スカルラッティ(1685−1757)、クラウディオ・カショリーニ(1697−1760)、そして3つの委嘱作品が並ぶ時代を超えたプログラム!
ロシア系イギリス人の若き女流コンポーザー=ピアニスト、アリッサ・フィルソワ(1986−)、母国エストニアの東南地域に伝わる民族音楽からの影響を感じさせるトヌ・コルヴィッツ(1969−)、オックスフォード・モードリン・カレッジからウェストミンスター大聖堂を経て、カンタベリー大聖堂、オックスフォード・ニュー・カレッジで活発な活動を展開する英国合唱界の次代の旗手マシュー・マーティン(1976−)。
異なる背景、文化を持つ3人の現代の音楽家たちによる新しい「スターバト・マーテル」と、単旋律聖歌、イタリアのスカルラッティ、カショリーニの「スターバト・マーテル」が、幅広いレパートリーを誇るザ・シックスティーンのハーモニーがによって、1つのストーリー、そして歴史として繋がる。

|
 SIGNUM CLASSICS SIGNUM CLASSICS
|
|
|
イギリスの近現代トランペット協奏曲集
プリチャード:スカイスペース
サックストン:詩篇 《都詣での歌》
マッケイブ:ラ・プリマヴェーラ
サックストン:シェイクスピアの場面 |
サイモン・デスブルスライス(トランペット)
ケネス・ウッズ(指揮)
デイヴィッド・カーティス(指揮)
オーケストラ・オブ・ザ・スワン |
イギリスのヴィルトゥオーゾ・トランペッター!イギリスの近現代トランペット協奏曲集!
バーミンガム・ポストに「鋼の唇」、ミュージックウェブ・インターナショナルに「説得力のある音楽性」など世界中から絶賛され、ナチュラル・トランペットによるヘルテルのトランペット協奏曲第3番の世界初録音で一躍有名になったイギリスのヴィルトゥオーゾ・トランペッター、サイモン・デスブルスライスの「イギリスの近現代トランペット協奏曲集」。
このイギリスの近現代トランペット協奏曲集のライヴが、BBC1テレビの放映と、BBCラジオ4の放送で、世界中の数百万人に視聴され反響を呼んでいる。
協奏曲や管弦楽作品のトランペット・レパートリー探求を続けるデスブルスライスによる世界初録音の協奏曲集は、トランペットの新しいレパートリーを提示します。 |
| |
|
|
オマージュ 〜 スペイン作品集
マラッツ:スペイン・セレナータ
ロドリーゴ:小麦畑にて
ソル:川岸の丘の主題と変奏
ヴィラ=ロボス:スコティッシュ − ショーロ、前奏曲第1番〜第5番
ファリャ:讃歌 《ドビュッシーの墓のために》
トゥリーナ:幻想曲
ナルバエス:皇帝の歌、牛を見張れの主題による変奏曲
リョベート:盗賊の歌、アメリアの遺言 |
クリストフ・デノート(ギター) |
1993年の第35回パリ国際ギター・コンクールなど数々の受賞歴を誇り、2012年にはウィグモア・ホール、2013年にはBBCプロムスへのデビューを果たした現在のスイスを代表するギタリスト、クリストフ・デノート。
ファリャが作曲した「讃歌《ドビュッシーの墓のために》」を軸にリョベートの「アメリアの遺言」やナルバエスの「牛を見張れの主題による変奏曲」など、バラエティ豊かだがどれも外せない名曲を、スイスの名ギタリストの妙技で聴く。 |
| |

SIGCD 401
(2CD/特別価格)
\3800 |
大戦争の歌
ベイントン/ブリス/バターワース/カプレ/
コールズ/デール/ドビュッシー/
ディーリアス/ブラウン/ファーラー/
ガーニー/ヘッド/アイヴズ/キール/ケリー/
マニャール/ミヨー/プロコフィエフ/
ルーセル/シュテファン/ヴェローヌ |
ロビン・トリッシュラー(テノール)
マルコム・マルティヌー(ピアノ) |
ロイヤル・オペラ・ハウスでデビューし、2006年2007年にウィグモア・ホール・インターナショナル・ソング・コンペティションでキャスリーン・フェリアー賞を受賞したテノール、ロビン・トリッシュラーの、名伴奏者マルコム・マルティヌーとの作品集。
敵か味方か、軍人か一般人かもわからない。世界大戦によって人生が転覆した世界にインスピレーションを受けた作品集は記念碑的録音です。 |
エンリケ・バティス/メキシコ州立交響楽団
|
 したくない・・・けど したくない・・・けど

752435 18163
(2CD)
\3400 →\3090 |
バ・・・バティスの・・・ショパン
「ピアニスト、エンリケ・バティス !!」
(1)ショパン:
夜想曲 ハ短調 Op.48-1/幻想曲 ヘ短調 Op.49/
ポロネーズ第5番 嬰ヘ短調 Op.44/
練習曲 ロ短調 Op.25-10/練習曲 イ短調
Op.25-4/
練習曲 嬰ハ短調 Op.10-4
(2)ショパン:ピアノ・ソナタ第2番 変ロ短調
Op.35 「葬送」
バッハ:6つのパルティータ
(第1番 変ロ長調 BWV.825/第2番 ハ短調
BWV.826/
第3番 イ短調 BWV.827/第4番 ニ長調
BWV.828/
第5番 ト長調 BWV.829/第6番 ホ短調
BWV.830)
(3)ショパン:幻想曲 ヘ短調 Op.49
ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第8番ハ短調Op.13「悲愴」
(4)モーツァルト:ピアノ協奏曲第23番 イ長調
K.488
|
エンリケ・バティス
(ピアノ、(4)指揮)
(4)メキシコ州立室内管弦楽団 |
爆演指揮者エンリケ・バティスまさかのピアノ演奏!ショパンやバッハのまさかの名演!
バティスのショパンなんて聴きたくない!・・・けど聴きたい。
録音:(1)1965 年、ヴァルソヴィア (2)2003
年、メキシコ・シティ、ベジャス・アルテス宮殿 (3)2009
年、ニューヨーク、カーネギー・ホール (4)2009
年、サラ・ネサウアルコヨトル/ADD、138'59
メキシコの偉大な指揮者エンリケ・バティス(1942—)がピアノを演奏した録音だが、これは決して単なる指揮者のピアノ演奏と片付けてよいものではない。バティスは1960
年代までは卓越したピアニストとして活動しており、指揮者としての名声を得てからも彼はしばしばピアノを弾いている。このCD
にはバティスの近年のピアノ演奏会のライヴ録音が収録されている。
バティスは、時に瑕も厭わず音楽に感情を激しくぶつけるが、しかしただ情熱的なだけではなく、作品全体を見通した構成はさすが大指揮者と思わせるほどよく練られたもので、幅広い表現の幅が決して独りよがりにならず、説得力が強い。
特筆すべきはショパンの葬送ソナタ。第1 楽章から思わず拍手が出るほど燃え盛っている。有名な第3
楽章の葬送行進曲では胸が破裂するような主部と夢見るような中間部の対比が極めて激しく、その壮絶さゆえ不気味に駆け抜けるフィナーレが付け足しになっていない。実に見事な演奏である。
一方でバッハのパルティータは、感情を豊かに盛り込みつつ端整さを決して失わない、ピアノ演奏バッハの理想形である。バティス・ファンはもちろん、ピアノ・マニアも外してはならないCD
だ。 |
 LYRINX LYRINX
|


LYR 2284
(2SACD HYBRID)
\5000 →\4590 |
「ショパン:夜想曲全集(全21曲)」
CD1/第1番〜第10番
CD2/第11番〜第21番 |
マリー=ジョセフ・ジュード(ピアノ) |
マリー=ジョセフ・ジュードのショパン:夜想曲全集ライヴ録音!
録音:2012 年11 月19 日国立マルセイユ劇場ラ・クリエ(ライヴ)
1968 年生まれ、フランス人の父と中華系ヴェトナム人を母にもつフランス出身の美しきピアニスト、マリー=ジョセフ・ジュード。13
歳でパリ国立高等音楽院に入学し、ピアノをアルド・チッコリーニ、その後パリ・エコール・ノルマルでジャン=クロード・ペヌティエにも師事しました。2012
年1 月からリヨン国立高等音楽舞踊学院の教授に就任。
これまでLYRINX レーベルへの録音はブラームスのシリーズなど独墺ものが中心でしたが、満を持してのショパン:夜想曲全集です。さらに、このアルバムはライヴ録音で一晩で一気に演奏さらたもの。静かな詩情に溢れたショパンの「夜想曲」をクリアなタッチで、優しく心地良く歌っています。程良くジュードの情感が込められ、ショパンの独特の陰鬱な雰囲気も包み込むように美しい。SACD
Hybrid。
旧譜
マリー=ジョセフ・ジュードのベートーヴェン! |
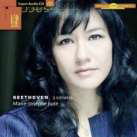
LYR 2273
(SACD HYBRID)
\2500 →\2290 |
ベートーヴェン:
ピアノ・ソナタ第8番 ハ短調 Op.13「悲愴」
ピアノ・ソナタ第23番 ヘ短調 Op.57「熱情」
ピアノ・ソナタ第26番 変ホ長調 Op.81a「告別」 |
|
マリー=ジョセフ・ジュード(ピアノ) |
ジュードのベートーヴェン「悲愴」「熱情」「告別」
録音:2010年7月1-3日、マルセイユ,DSD、59m
LYRINXへの録音がいずれも高い評価を得ているマリー=ジョセフ・ジュード。LYRINXレーベルへはブラームス、メンデルスゾーン、クララ・シューマンなどのドイツものの他、ジョリヴェ:ピアノ作品集やフォーレの歌曲の伴奏と、幅広く録音してきましたが、新譜はベートーヴェンの名曲ソナタ集です。ジュードは1968年生まれ。父はフランス人と、母は中国系ベトナム人。2012年1月からリヨン国立高等音楽舞踊学院の教授に就任している。卓越した指捌きと知性溢れる演奏が素晴らしい。
|
|
| |
|
|
「デュオ・ユモレスク〜コダーイ&ラフマニノフ」
コダーイ:チェロとピアノのためのソナチネ
コダーイ:チェロ・ソナタOp.4
ラフマニノフ:チェロ・ソナタ ト短調 Op.19
ラフマニノフ:東洋風舞曲(『2つの小品』より)Op.2-2 |
デュオ・ユモレスク:
【クララ・ザウィ(チェロ)
ゼニア・マリアレヴィチ(ピアノ)】 |
期待の若手デュオによるコダーイ&ラフマニノフ:チェロ作品集
録音:2013年2月20〜30日、67’29
パリ国立高等音楽院で学んだ2 人が2006 年に結成したデュオ・ユモレスクはいくつものコンクールで入賞経験を持つ実力派。コダーイの「ソナチネ」はもっと知られてよい名曲。エキゾチックな響きと溢れる甘美な旋律。静謐でしっとりと歌う。ハンガリーの民族音楽の素材を取り入れた「チェロ・ソナタ」は幻想的。ラフマニノフらしいほの暗い情熱を優雅に紡いでいく「チェロ・ソナタ」。流麗で温もりのある演奏です。 |
 MARQUIS MARQUIS
|
|
|
ベートーヴェン:ディアベリ変奏曲 |
スチュアート・グッドイヤー(ピアノ) |
開放的で刺激的!グッドイヤーのディアベリ変奏曲
録音:2013 年11 月2,3 日 グレン・グールド・スタジオ(トロント)、46’56
カナダのトロント出身のピアニスト兼作曲家,スチュアート・グッドイヤーはトロント音楽院で学んだあと、ジュリアード音楽院で学士号を修得。先にベートーヴェンのピアノ・ソナタ全集(MAR81513)を完成させている。
開放的で刺激的。バッハの「ゴルトベルク変奏曲」と並ぶ変奏曲の最高峰「ディアベリ変奏曲」!グッドイヤーのダイナミックな打鍵に圧倒、この豪腕っぷりは爽快にさえ感じる。飽きさせずに聴かせるインプロヴィゼーションのような個性的な変奏。揺るぎないピアニズムがディアベリ変奏曲の構造を明確に聴かせる。 |
<LP>
<マイナー・レーベル歴史的録音・旧録音>
 MUSIC&ARTS MUSIC&ARTS
|


M&ACD 1281
(15CD、8枚価格)
\18400 →\17390 |
シュナイダー四重奏団 伝説のハイドン協会録音、一挙15枚BOXセット化!
「フランツ・ヨーゼフ・ハイドン:弦楽四重奏曲選集」
CD1/
第0番 変ホ長調Op.1-0/第1番「狩」 変ロ長調Op.1-1/
第2番 変ホ長調Op.1-2/第3番 ニ長調Op.1-3
CD2/
第4番 ト長調Op.1-4/第6番 ハ長調Op.1-6/第7番
イ長調Op.2-1*
CD3/
第8番 ホ長調Op.2-2*/第9番 変ホ長調Op.2-3*/第10番
ヘ長調Op.2-4*
CD4/
第11番 ニ長調Op.2-5*/第12番 変ロ長調Op.2-6*/
第25番 ホ長調Op.17-1/第26番 ヘ長調Op/17-2
CD5/
第27番 変ホ長調Op.17-3/第28番 ハ短調Op.17-4/第29番
ト長調Op.17-5
CD6/
第30番 ニ長調Op.17-6/第31番 変ホ長調Op.20-1*/第32番
ハ長調Op.20-2*
CD7/
第33番 ト短調Op.20-3*/第34番 ニ長調Op.20-4*/第35番
ヘ短調Op.20-5*
CD8/
第36番 イ長調Op.20-6*/第37番 ロ短調Op.33-1/
第38番「冗談」 変ホ長調Op.33-2/第39番「鳥」
ハ長調Op.33-3
CD9/
第40番 変ロ長調Op.33-4/第41番 ト長調Op.33-5/
第42番 ニ長調Op.33-6/第43番 ニ短調Op.42
CD10/
第44番 変ロ長調Op.50-1/第45番 ハ長調Op.50-2/第46番
変ホ長調Op.50-3
CD11/
第47番 嬰ヘ短調 Op.50-4/第48番「夢」
ヘ長調Op.50-5/
第49番「蛙」 ニ長調Op.50-6
CD12/
十字架上のキリストの最後の7つの言葉Op.51/第63番
ハ長調Op.64-1*
CD13/
第75番 ト長調Op.76-1*/第76番「五度」ニ短調Op76-2*/
第77番 変ホ長調Op.76-3*
CD14/
第78番「日の出」変ロ長調Op.76-4*/
第79番ニ長調Op76-5*/第80番 変ホ長調Op.76-6
CD15/
第81番 ト長調Op.77-1/第82番 ヘ長調Op.77-2/第83番
ニ短調Op.103
|
シュナイダー四重奏団:
【アレクサンダー・シュナイダー(Vn)、
イシドール・コーエン(Vn)、
カレン・タトル(Va)、
マドリーヌ・フォーリー(Vc)、
ヘルマン・ブッシュ(Vc)*】 |
シュナイダー四重奏団のハイドン弦楽四重奏曲集、伝説のハイドン協会録音、一挙15枚BOXセット化!
録音:1951-1954 年ハイドン・ソサエティ、1047’16
ハイドン・ソサエティで録音されたシュナイダー四重奏団が演奏するハイドンの弦楽四重奏曲選集がお得なBOXになって復刻!
ほぼオリジナル・マスターテープから、新たにリマスターされ、音質も良好。温もりのある悠然とした演奏です。ブダペスト弦楽四重奏団の第二ヴァイオリンとして活躍したアレクサンダー・シュナイダーが創設したシュナイダー四重奏団。
ボザール・トリオのヴァイオリニスト、イシドール・コーエン、キム・カシュカシャンなど現在活躍するヴィオラ奏者を育てた名教師でもあるカレン・タトル、マールボロ音楽祭などで活躍していたチェリストのマドリーヌ・フォーリーとアドルフ・ブッシュの弟でチェリストのヘルマン・ブッシュなど、その時代の一線級の演奏家が結集した名演です。
|
<映像>
 C MAJOR(映像) C MAJOR(映像)
|

71 7704
(Blu-ray)
\5800 |
バレエ「白鳥の湖」(チャイコフスキー) |
出演:オデット/ オディール:オルガ・エシナ
ジークフリート王子:ウラジーミル・シショフ
ロットバルト:エノ・ペシ
女王:ダグマール・クロンベルガー
家庭教師:クリストフ・ヴェンツェル
執事:ガボール・オベレッガー
王子の友人たち:
橋本清香、木本全優、アリス・フィレンツェ、
グレイグ・マシューズ
大きな白鳥たちの踊り:
ガラ・ジョヴァノヴィッチ、オクサナ・キヤネンコ、
ラウラ・ニストル、プリスカ・ツァイゼル
小さな白鳥たちの踊り:
マリア・アラティ、イオアナ・アヴラム、
玉井ルイ、エステル・レダーン
スペインの踊り:
オクサナ・キヤネンコ、フラヴィア・ソアレス、
アレクサンドル・トカチェンコ、アンドレイ・テテリン
ナポリの踊り:橋本清香、リチャード・サボー
ポーランドの踊り:
アリーナ・クロシュコヴァ、アレクシス・フォラボスコ
ハンガリーの踊り:
アリス・フィレンツェ、ミハイル・ソスノフスキー
若い貴婦人たち:
マリア・アラティ、イオアナ・アヴラム、
エステル・レダーン、レイナ・サワイ、
玉井ルイ、ニーナ・トノーリ
ウィーン国立歌劇場オペラ学校の子供たち
ウィーン国立歌劇場バレエ団 |

71 7608
(DVD)
\3600 |
ヌレエフ版 祝50周年!オルガ・エシナとウラジーミル・シショフの美男美女コンビによる美しく表情豊かな「白鳥の湖」
(Blu-ray)画面:16:9 HD、音声:DTS-HD
MA 5.1,PCM ステレオ、132分
(DVD)画面:16:9 NTSC、音声:DTS-HD MA
,PCM ステレオ、132分
音楽:チャイコフスキー/芸術監督:マニュエル・ルグリ/振付&演出:ルドルフ・ヌレエフ/オリジナル振付:マリウス・プティパ&
レフ・イワーノフ
再演出:マニュエル・ルグリ、アリス・ネシェア、ルーカス・ガウデルナク、ジャン・クリストフ・ルサージュ/装置&
衣裳:ルイザ・スピナテッリ
照明:マリオン・ヒューレット/指揮:アレクサンダー・イングラム、演奏:ウィーン国立歌劇場管弦楽団
収録:2014 年3 月ウィーン国立歌劇場(ライヴ)/映像監督:ミヒャイル・ベイヤー
2010 年にウィーンでは国立歌劇場とフォルクス・オーパーのバレエ団が合併され、生まれ変わったウィーン国立バレエ団。これを率いるために初代芸術監督として招聘されたのが、パリ・オペラ座でグラン・エトワールと称賛されたマニュエル・ルグリ。
この映像は2014 年3 月にウィーン国立歌劇場で収録されたチャイコフスキーの三大バレエのひとつ「白鳥の湖」。同じく名作「くるみ割り人形」もC-major
から発売されており、世界最高水準のダンサーたち、奇才ルドルフ・ヌレエフの考え抜かれた見事な演出、美しい衣装や舞台装置は、まさに伝統と革新が融合した見ごたえのある舞台映像でした。
振付を担当したルドルフ・ヌレエフは、1877
年の初演時の台本に基づき、ヌレエフが独自に振付と演出を行っており、現代で一般的なプティバ&イワーノフ版とも構成が異なります。ヌレエフ版は、王子目線でストーリーを構築し、ジークフリート一人で溺れ死ぬ悲劇の最期が待ち受けています。ヌレエフ版は1964
年にウィーン国立歌劇場で初演され、2014 年はちょうど50
周年の年にあたります。
オデットを踊るのは現在のウィーン国立バレエ団の顔とも言えるオルガ・エシナ。ジークフリートを演じるのは、「くるみ割り人形」と同じくウラジーミル・シショフ。二人は、数々の名ダンサーを輩出したロシアの名門ワガノワ・バレエ・アカデミーの出身。美しく見栄えの良い二人による踊りは、身体の隅々まで考えられた動き、溢れ出る表現力に心奪われます。
|

10/15(水)紹介新譜
マイナー・レーベル新譜
 ONDINE ONDINE
|

ODE-1227
(SACD-Hybrid)
\2400 |
ルチアーノ・ベリオ:シンフォニア 他
1.L.ボッケリーニの「マドリードの夜警隊の行進」による4
つの変奏(1975)/
2.ベリオ:メゾ・ソプラノと22 の楽器による「カルモ」(1974/1989)/
3-7.8ベリオ: 声とオーケストラによる「シンフォニア」(1968-1969) |
ヴィルピ・レイセネン(メゾ・ソプラノ)…2/
ミリアム・ソロモン(ソプラノ)/
アンニカ・フールマン(ソプラノ)/
ユッタ・セッピネン(アルト)/
パシ・ヒヨッキ(アルト)
/サイモ・メキネン(テノール)/
パーヴォ・ヒョッキ(テノール)/
ターヴィ・オラモ(バス)/
サンポ・ハーパニエミ(バス)/
フィンランド放送交響楽団/
ハンヌ・リントゥ(指揮) |
録音 2014 年1 月 ヘルシンキ,ミュージック・センター
ONDINE レーベルで大活躍中の指揮者ハンヌ・リントゥ。彼は2013
年までタンペレ・フィルハーモニー管弦楽団の首席指揮者を務め、現在はフィンランド放送交響楽団の首席指揮者を務めています。
前作のメシアン「トゥーランガリラ交響曲」では、オーケストラの機能性と音響効果を存分に生かした素晴らしい演奏を繰り広げましたが、今回は、更に興味深いルチアーノ・ベリオの一連の作品の登場です。
ベリオ(1925-2003)については今更説明の必要もないイタリアの現代作曲家で、様々な技法を駆使した作品を書きましたが、1950
年代からは当時の妻であった歌手キャシー・バーベリアンとともに、声楽の限界を追求したことでも知られています。ボッケリーニの曲を元にした「4
つの変奏」はミラノ・スカラ座の委嘱作品で、この時の劇場のオープニングナンバーの作曲を依頼されたベリオが、そのオーケストレーションの妙技を駆使して書いた変奏曲です。
和声的には全く現代的なところのない、極めて愉快な音楽です。
「カルモ」は彼の友人の一人、ブルーノ・マデルナの死への追悼の音楽。マデルナが愛したテキストを用いた歌曲(?)です。
そして「シンフォニア」。こちらは既によく知られている作品であり、タイトルの「シンフォニア」とは交響曲の伝統ではなく、多様な声の合流という意味を持つ奇妙な作品です。一番わかりやすいのは、第3
楽章におけるマーラーをはじめとした何人かの作曲家の作品の引用でしょう。様々な音楽が断片的に浮かび上がる様子は、マーラーの原曲における魚の鱗が光を反射する様にも似ています。複雑な曲ですが、聞いていてこれほど面白い作品もないかも知れません。 |
| |


ODE-1239
\2400→\2190 |
クリスティアン・テツラフ
ショスタコーヴィチ:ヴァイオリン協奏曲集
1-4.ヴァイオリン協奏曲 第1 番 イ短調
Op.77/
5-7.ヴァイオリン協奏曲 第2 番 嬰ハ短調
Op.129 |
クリスティアン・テツラフ(ヴァイオリン)/
ヘルシンキ・フィルハーモニー管弦楽団/
ジョン・ストゥールゴールズ(指揮) |
録音 2013 年11 月27-28,30 日 フィンランド
ヘルシンキ・ミュージック・センター
ハンブルク生まれの名ヴァイオリニスト、クリスティアン・テツラフによるONDINE
レーベル5 枚目の録音は、ショスタコーヴィチ(1906-1975)の2
つの協奏曲集です。これまではモーツァルト、シューマン、メンデルスゾーンと、現代曲(ヴィトマン)の演奏で高く評価されていましたが、今回はまさに本領発揮ともいえる鬼気迫るショスタコーヴィチです。第1
番の冒頭から異様な緊張感を湛えた説得力ある演奏は、これまでに存在した他の演奏を楽々と凌駕するほどのスケール感を有しています。
ヘルシンキ・フィルハーモニーの醸し出す静謐な音にもゾクゾクさせられます。お約束の、第4
楽章での喧騒も申し分なし。第2 番がこれまた渋い雰囲気を持ち、テツラフは落ち着き払った演奏を聴かせています。 |
| |


ODE-1250
\2400→\2190 |
モーツァルト:ピアノ作品集「顧みられない宝物」
1-3.組曲 ハ長調(断章) K399/
4.ソナタの楽章 ト短調(断章) K312(189i/590d)/
5-6.前奏曲とフーガ ハ長調 K394/
7.自動オルガンのためのアンダンテ ヘ長調
K616/
8.アレグロ 変ロ長調 K400(M.シュタードラーによる補筆完成版)/
9.「われら愚かな民の思うは」による10 の変奏曲
K455/
10.「ああ、ママに聞いてよ」による12 の変奏曲(きらきら星)
K265 |
アナスタシア・インジュシナ(ピアノ) |
録音 2014 年3 月23-25 日 フィンランド クーモ・アーツ・センター
前作の「バッハ一族のピアノ協奏曲集」(ODE1224)で流麗かつ、新鮮なバッハを披露した若手ピアニスト、アナスタシア・インジュシナの2
枚目のアルバムはモーツァルト(1756-1791)の「知られざるピアノ作品集」です。
ここに収録されている作品は、最後の「きらきら星」以外は、あまり演奏会でも聞く機会のないものです。K312
のアレグロは現在の研究では、晩年の作品らしいと推測されるもの。ただし成立がはっきりしないため、成立自体は謎となっています。
K399 の組曲やK394 の「前奏曲とフーガ」はヘンデルの組曲から影響を受けているとされます。オルガンで演奏されることも多い作品です。K400
は91 小節の途中で放棄されてしまった作品です。
ピアノ・ソナタになるはずだったのかもしれません。ここではシュタードラーが補筆した版で演奏されていますが、他の人による補筆版も存在します。軽やかなフレーズが印象的な作品です。 |
| |


ODE-1265
(2CD)
\2700→\2490 |
シベリウス:管弦楽名作集と写真集
<CD1>
1-3.カレリア組曲 Op.11/
4.悲しきワルツ Op.44-1/5.ポヒョラの娘
Op.49/
6.トゥオネラの白鳥 Op.22-2/7.アンダンテ・フェスティヴォ/
8-10.付随音楽「テンペスト」から3 つの楽章
<樫の木/カリバン/ミランダ>/
11.フィランディア Op.26-7/
<CD2>
1-3.ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 Op.47/
4-7.交響曲 第2 番 ニ長調 Op.43 |
ヘルシンキ・フィルハーモニー管弦楽団/
レイフ・セーゲルスタム(指揮)/フィン
ランド放送管弦楽団…CD1:7/
ヤン・シベリウス(指揮)…CD1:7/
ペッカ・クーシスト(ヴァイオリン)…CD2:1-3 |
2015 年はシベリウス生誕150 年周年です。それを記念してONDINE
レーベルでは、彼の名管弦楽作品をセレクトし、52
ページに渡るブックレットを添付しました。
こちらにはこれまで開示されていなかった、写真家ベルティル・ダールグレンによるシベリウスの写真の何枚かが含まれているという貴重なもので、ファン垂涎のものとなることは間違いありません。
収録された作品は、レイフ・セーゲルスタムとヘルシンキ・フィルハーモニー管弦楽団の演奏によるものが中心ですが「アンダンテ・フェスティヴォ」は、現在残存する唯一のシベリウス自身の指揮によるものです。こちらはフィンランド放送管弦楽団との1939
年1 月1 日の演奏で、これは米国にも生中継された記念碑的な記録です。 |
| |

ODE-1234
(SACD-Hybrid)
\2400 |
エリッキ=スヴェン・トゥール:交響曲 第5
番 他
1-4.ビッグ・バンド,エレクトリック・ギター,
シンフォニー・オーケストラのための「交響曲
第5 番」(2004)/
5.アコーディオンとオーケストラのための「予言」(2007) |
グエン・レ(エレクトリック・ギター)…1-4/
ウモ・ジャズ・オーケストラ…1-4/
ミカ・ヴェイリネン(アコーディオ
ン)…5/ヘルシンキ・フィルハーモニー管弦楽団/
オラリー・エルツ(指揮) |
録音 2013 年6 月2-3 日…5, 2013 年10 月25.28
日…1-4 ヘルシンキ,ミュージック・センター
エストニア生まれの作曲家、スヴェン・トゥール(1959-)はタリン音楽学校でフルートと打楽器を学び、後にタリン音楽アカデミーで作曲を学んだという人。一方で1979
年から1984 年にかけて「In Spe」というロック・グループを率いて活動し、こちらはエストニアで高い人気を獲得しました。しかし作曲に専念するためにバンドを脱退したところ、作品が西側に注目され、そのまま作曲家として素晴らしい成果を挙げています。
そんな彼、自作にはしばしばビッグ・バンドやエレクトリック・ギターなどを用いることでも知られ、この交響曲第5
番でもユニークな音響に満たされています。アコーディオンを用いた「予言」でも奇妙な世界が広がります
。単なるクラシック音楽では満足できない人にオススメします。 |
| |


ODE-1238
\2400→\2190 |
ドミートリー・ホロストフスキ:夜明けの鐘
〜ロシア宗教曲と民謡を歌う
1.ドプリ・プリストフ(1875-1941):主の御名を賛美せよ/
2.パーヴェル・チェスノコフ(1877-1944):祝福された男
Op.44-2/
3.チェスノコフ:永遠の前の弁護人/
4.チェスノコフ:わが祈りを聞きたまえ/
5.チェスノコフ:わが青春時代より/
6.ミハイル・ブルマジン:賢い泥棒/
7.アレクサンドル・アルハンゲルスキー(1846-1924):信仰のシンボル/
8.アレクサンドル・ヴァルラモフ(1801-1848):吹雪/
9-13.ロシア民謡集
<彼らはマシャに行かない/森を通る道はない/孤独な鐘/
さようなら、わが喜び/霧が野原に降り注ぐ>/
14.エリザヴェータ・シャシナ(1805-1903):私は一人で小道を歩く/
15.ロシア民謡 おお、夜よ/
16.ゲオルギー・スヴィリードフ(1915-1998):夜明けの鐘 |
ドミートリー・ホロストフスキー(バリトン)/
マスターズ・オブ・コーラル・シンギング/
レフ・コントロヴィチ(指揮) |
録音 2012年6月23.25.26.29.30日,7月2日 ロシア
モスクワ,P.I.チャイコフスキー・コンセルヴァトリー
現在、最も素晴らしいバリトン歌手であるホロストフスキーの漆黒の声と、ロシアの名門合唱団、マスターズ・オブ・コーラル・シンギングのコラボレーションによる民謡と宗教曲集です。
いかにもロシアらしい、憂愁と力強さを併せ持つ歌の数々。これらをここまで完璧に歌いこなせるのは、ドミートリー・ホロストフスキーを置いて他にはいないでしょう。アルバム・タイトルになっている「夜明けの鐘」は、人気作曲家ゲオルギー・スヴィリードフの作品で、短いフレーズを繰り返す美しいソプラノと、呼応する憂鬱なバリトン、それを包み込むような深い合唱の響きが、印象的な音楽です。 |
| |


ODE-1240
\2400→\2190 |
聴きましょう、グラウプナー・・・
クリストフ・グラウプナー:トリオ・ソナタ集
1-4.ヴィオラ・ダ・ーレ、シャルモーと
ハープシコードのためのトリオ ヘ長調
GWV210/
5-7.2台のヴァイオリンと
ハープシコードのためのトリオ ハ短調
GWV203/
8-10.ファゴット、シャルモーと
ハープシコードのためのソナタ ハ長調
GWV201/
11-13.フルート、ヴィオラ・ダモーレと
ハープシコードのための三声のソナタ
ニ短調 GWV207/
14-17.2台のヴァイオリンと
ハープシコードのためのトリオ ホ長調
GWV208/
18-20.フルート,ヴィオラ・ダモーレと
ハープシコードのためのトリオ 変ロ長調
GWV217 |
<フィンランド・バロック管弦楽団のメンバー>
ペトラ・アミノフ(フルート)…11-13.18-20/
シルッカ=リサ・カーニネン=ピルク(ヴィオラ・ダモーレ)
…1-4.11-13.18-20/
ハンヌ・ヴァサラ(ヴァイオリン)
…5-7.8-10/
アスコ・ヘイスカネン(シャルモー)…1-4.8-10/
ヤニ・スンナルボルイ(ファゴット)…8-10/
マルク・ルオラヤン=ミッコラ(バロック・チェロ)…5-7,(ヴィオラ・ダ・ガンバ)…1-4.11-13.18-20/
エーロ・パルヴィアイネン(バロック・リュート)…1-13.18-20/
ペトリ・ピトゥコ(ハープシコード)…8-20,(オルガン)…5-7 |
録音 2013年10月14-16日 フィンランド ペルナヤ教会
ドイツ後期バロック音楽の作曲家、チェンバロ奏者グラウプナー(1683-1760)。彼の音楽はほとんど忘れられてしまいましたが、唯一知られるエピソードとしては、ライプツィヒの聖トーマス教会カントールのポストをバッハと競った人ということでしょうか?
そんな彼の作品も最近では少しずつ省みられており、バッハともヘンデルとも違う味わいに魅了されている人も多いようです。
多くの場合、彼の作品には珍しい楽器が使われていて、ここでもヴィオラ・ダモーレや、シャルモー(クラリネットの原型となった木管楽器)の響きをふんだんに味わうことができます。
演奏しているのは、フィンランドにおけるバロック・ヴァイオリンの第1人者カーニネン=ピルクをはじめとしたフィンランド・バロック管弦楽団のメンバー。この楽しげな響きは一度聞くとくせになります。
1722年に彼の師であったクーナウが死去すると、翌年ライプツィヒの市参事会は後任のトーマス教会カントルの候補者としてまずテレマンを指名したが、テレマンが辞退したため、次の候補者としてグラウプナーが指名された。しかし、グラウプナーの雇用主であったヘッセン=ダルムシュタット方伯エルンスト・ルートヴィヒがグラウプナーの移籍を許さなかったため、最終的にカントルの職はバッハへ舞い込むことになった。ちなみに、ヘッセン=ダルムシュタット方伯はグラウプナーをライプツィヒへ移籍させないために、グラウプナーの給料を大幅に増額することも厭わなかったという。
グラウプナーは、バッハがトーマス教会カントルの職を受諾したことを知ると、1723年5月4日にライプツィヒの市参事会に宛てて推薦の手紙を書き、バッハの優れたオルガン演奏能力と宗教曲作曲の練達した手腕を称賛し、バッハがこの職務を忠実に遂行するにふさわしい人物であると保証した(Johann
Sebastian Bach: The Learned Musician by Christoph
Wolff, W.W. Norton & Company, New York
& London, 2000, p 224) 。グラウプナーがこのようにバッハを積極的に推薦した行動を見る限り、少なくともグラウプナーがそれ以前からバッハの音楽と人柄を熟知していたことは確実であり、彼が個人的にバッハとの交流を持っていたことは間違いないようである。
「ウィキペディア」より |
|
| |


ODE-1249
\2400→\2190 |
ラフマニノフ:歌劇「モンナ・ヴァンナ」&歌曲集
1-4.歌劇「モナ・ヴァンナ」(未完…ゲンナジ・ベロフによる管弦楽補筆版)
<序奏/第1場/第2場/第3場>/
《歌曲集》
5.私の窓辺に Op.26-10/6.夜は悲しい Op.26-12/
7.リラの花 Op.21-5/8.ねずみ捕りの男
Op.38-4/
9.ヴォカリーズ Op.34-14/
10.ここはすばらしい場所 Op.21-7/11.夢
Op.38-5 |
〈モンナ・ヴァンナ〉
エブゲニア・ドゥーシナ(ソプラノ)/
ウラディーミル・アフトモノフ(バリトン)/
ドミートリー・イヴァンチェイ(テノール)/
エドヴァルド・アルチュニャン(テノール)/
ミハイル・ゴロフシキン(バス)/
モスクワ音楽院オペラ・ソロイスツ/
モスクワ音楽院学生合唱団/
モスクワ音楽院管弦楽団/
ウラディーミル・アシュケナージ(指揮)/
〈歌曲集〉
ソイレ・イソコスキ(ソプラノ)/
ウラディーミル・アシュケナージ(ピアノ) |
録音 2009年6月17日 ロシア モスクワ・チャイコフスキー音楽院…1-4/2013年9月
フィンランド イェルヴェンパー・ホール…5-11
ラフマニノフ(1873-1943)の未完のオペラ「モナ・ヴァンナ」は極めて珍しい作品です。これまでI.ブケトフによる補筆版がリリースされていましたが、こちらは英語歌唱によるもので、聴き手としては若干の不満の残るものであったことを考えると、この新しい録音は歓迎されるものとなるでしょう。
メーテルランクの戯曲に基づくこのオペラは、かの「モナ・リザ」を主人公にしたもの。もちろん彼女については、何人もの芸術家たちが音が絵画にしているものですが、ラフマニノフもこの美しい女性に魅了されたようで、このオペラを完成すべく、アメリカ亡命の際にもスコアを携えていったのです。しかし、結局完成されることはなく、そのまま忘れ去られてしまいました(このオペラが完成しなかった理由の一つは、メーテルリンクが他の作曲家、フェヴリエにオペラにする権利を与えてしまったため、ラフマニノフが作曲を続けることができなかったようです)。
結局このオペラが初演されたのは、1984年、ニューヨークで前述のブケトフ版を用いてのものでした。今回はより新しい研究に基づいたベロフによる補筆版でお楽しみください。余白にはイソコスキによるラフマニノフ歌曲を収録しています。 |
<LP>
<マイナー・レーベル歴史的録音・旧録音>
<映像>

10/14(火)紹介新譜
マイナー・レーベル新譜
 HMF HMF
|

HMU 807590
(SACD HYBRID)
\2700 →\2490 |
ザゾのバロック・オペラ・アリア集
ヘンデル:
「フラーヴィオ」—罠を砕き
「アドメート」序曲,亡霊たちのバレエ—
導入,恐ろしい亡霊,閉じよ、私の目よ,第2幕のシンフォニア
「ジューリオ・チェーザレ」—物音立てずに進む
「オットーネ」—私は裏切られた,多くの苦悩が
「ロデリンダ」—生きよ、暴君め
ボノンチーニ:
「クリスポ」−巡礼者はこのように疲れ,落ちていく急流は
「グリゼルダ」—あなたを崇める栄光のため
「ムツィオ・シェヴォラ」—傷ついた虎は
アリオスティ:
「ヴェスパシアーノ」序曲
「近くの遭難者」—波は荒れ、風は音を立て
「コリオラーノ」—
ああ、邪悪な大理石め、不吉な亡霊め,あまりにも惨めな息子の |
ローレンス・ザゾ(CT)
デイヴィッド・ベイツ(指揮)
ラ・ヌオーヴァ・ムジカ |
美声カウンター・テノール、ザゾのバロック・オペラ・アリア集。ヘンデル、ボノンチーニ、アリオスティ1720年代のロンドンっ子を熱狂させた三人組の名曲ばかり!SACD
Hybrid で登場!!!
録音:2014 年1 月、ロンドン/DSD、78 分05
秒
米国を代表するカウンターテノール、ローレンス・ザゾのバロックオペラ・アリア集です。お得意のヘンデルを中心に、ジョヴァンニ・バッティスタ・ボノンチーニ(1670—1747)、アッティーリオ・マラキア・アリオスティ(1666—1729
頃)の作品を収録しています。
この三人はいずれも同時期にロンドンで活躍しており、ここに収録されているのも1719
年から1729 年にかけてロンドンで初演されたオペラの曲ばかりです。原題のA
Royal Trio は、ロンドンでオペラ興行を行っていたロイヤル・アカデミー・オブ・ミュージックで活躍した三人組、といった意味です。ヘンデルばかりが知られていますが、ボノンチーニもアリオスティも優れた音楽を提供していたことが分かります。
ザゾは1970 年、フィラデルフィア生まれ。英国で声楽を学び、柔らかい美声で高い人気を誇っています。録音も非常に多く、特にルネ・ヤーコプスは、ヘンデル「リナルド」、「サウル」、「メサイア」、スカルラッティ「グリゼルダ」の録音でザゾを起用するほど重用しています。
なおZazzo のカナ表記はザッゾやザッツォになっている場合もありますが、この姓の多いアメリカ合衆国東海岸では、カタカナのザゾとほぼ同様に発音されています。
指揮者のデイヴィッド・ベイツも実はカウンターテノール歌手。2007
年、英国でラ・ヌオーヴァ・ムジカを創設、以来指揮者としても活躍しており、ラ・ヌオーヴァ・ムジカは数年のうちに高い評価を得ています。
SACD Hybrid での発売。録音の良さでも楽しめます。 |
.
キング・インターナショナル
|
|
|
赤松林太郎/ピアソラの天使〜ピアソラ・オン・ピアノ
アストル・ピアソラ/山本京子編曲:
(1)エスクアロ/(2)オブリビオン/
(3)アディオス・ノニーノ/(4)リベルタンゴ/
(5)ソレダード/(6)天使の死/
(7)天使のミロンガ/(8)天使の復活 |
赤松林太郎(ピアノ) |
圧倒的な存在感。ラテンの情熱とエネルギーに満ちた赤松のタンゴ
録音:2013 年12 月4 日/ベルフォーレ津山(1)、2014
年8 月14、15 日/神戸市立北神区民センター
ありまホール(2)-(8)/DDD、46’ 44”
「ふたりのドメニコ」で強烈な印象を残した赤松林太郎。圧倒的な存在感と説得力あふれる解釈が高い評価を受けました。その第2
弾はピアソラのタンゴ集。関西で活躍する山本京子の編曲によるピアノ独奏版。
演奏活動のかたわら、エッセイストとして新聞や雑誌にも連載を持ち、「美しいキモノ」ではモデルも務めるマルチ・タレントです。派手な技巧に加え、自然なフレージングと朗々とした音が非常に魅力的。
ピアソラのタンゴのなかから、ここでは天使のシリーズをメインに、人気の高い「オブリビオン」や「リベルタンゴ」ももちろん収録。民族色豊かな作品に巧いところを見せる赤松ならではの、南米そのものの空気を感じさせてくれます。
赤松林太郎、今年出たばかりの前作! |
|
|
ふたりのドメニコ/赤松林太郎
ドメニコ・スカルラッティ:
(1)ソナタ ホ長調K.531/(2)ハ長調K.159/(3)ニ長調K.178/
(4)イ長調K.322/(5)ロ短調K.87/(6)ニ長調K.430/
(7)ニ短調K.64「ガヴォット」/(8)変ロ長調K.440「メヌエット」/
(9)ヘ短調K.466/(10)ト長調K.63「カプリッチョ」
ドメニコ・チマローザ:
(11)ソナタ 変ロ長調C.27/(12)変ホ長調C.37/(13)変ロ長調C.18/
(14)イ長調C.45/(15)イ短調C.55「シチリアーナ」/(16)イ長調C.11/
(17)ニ短調C.9/(18)ニ短調C.17/(19)ニ長調C.13/(20)ト長調C.51/
(21)ト短調C.61/(22)ト長調C.82/(23)ハ短調C.66/(24)ハ長調C.14 |
赤松林太郎(ピアノ) |
「聡明かつ才能がある」(ヨアヒム・カイザー)強烈な個性とオーラあふれる音楽、天才・赤松林太郎デビュー!
録音:2013 年12 月2-4 日/ベルフォーレ津山/DDD、60’
02”
新しい才能が続々と輩出される日本ピアノ界に、強烈な個性が出現しました。赤松林太郎。何より圧倒的な存在感と説得力あふれる解釈に驚かされます。ピアノの音もたっぷりと豊かで、超絶的な指さばきもふくめ、19
世紀的ピアニズムを感じさせます。演奏のみならず音楽学的研究にも熱心で、珍しい作品の発掘にも積極的。今日の日本では珍しいタイプのピアニストと申せましょう。
演奏活動のかたわら、エッセイストとして新聞や雑誌にも連載を持ち、「美しいキモノ」ではモデルも務めるマルチ・タレントです。
このアルバムはスカルラッティとチマローザというふたりのイタリア・バロック作曲家のソナタ集をピアノで挑戦。チェンバロを意識しないピアノならではの表現力と美感を最大限に追求し、あっという間に全曲を聴かせます。
赤松 林太郎(あかまつ りんたろう)
1978 年大分生まれ、2 歳よりピアノとヴァイオリンを、6
歳よりチェロを始める。幼少より活動を始め、5
歳の時に小曽根実氏や故・芥川也寸志氏の進行でテレビ出演。10
歳の時には自作カデンツァでモーツァルトの協奏曲を演奏。1990
年に第44 回全日本学生音楽コンクールで優勝して以来、国内の主要なコンクールで優勝を重ねる。1993
年には仙台市教育委員会より平成5 年度の教育功績者に表彰される。1996
年の第1 回浜松国際ピアノアカデミーに参加、最終日のアカデミーコンクールにてファイナリストに選抜される。
神戸大学を卒業後、パリ・エコール・ノルマル音楽院にてピアノ・室内楽共に高等演奏家課程ディプロムを審査員満場一致で取得(室内楽は全審査員満点による)。ピアノを熊谷玲子、ミハイル・ヴォスクレセンスキー、フランス・クリダ、ジャン・ミコー、ジョルジュ・ナードル、ゾルターン・コチシュ、室内楽をニーナ・パタルチェツ、クリスチャン・イヴァルディ、音楽学を岡田暁生の各氏に師事。
2000 年に第3 回クララ・シューマン国際ピアノコンクール(審査員にはマルタ・アルゲリッチやネルソン・フレイレなど)で第3
位を受賞した際、Dr. ヨアヒム・カイザーより「聡明かつ才能がある」と評された。国際コンクールでの受賞は10
以上に及ぶ。
*このCDは弊社独自企画で、海外盤が存在しません。

|
|
ALICE
|
|
|
ルシエ、テニー、ケージ、ライヒ 〜
ギター、リュート、ウード作品集
ルシエ:
オン・ザ・カーペット・オヴ・リーヴス・
イルミネイテッド・バイ・ザ・ムーン
(ウード&正弦波)
テニー:クロマティック・カノン(リュート&ライヴ・エレクトロニクス)
ケージ:One7(ギター&ライヴ・エレクトロニクス)
ライヒ:ヴァイオリン・フェイズ(リュート&ライヴ・エレクトロニクス)
|
ペーテル・セーデルベリ
(アコースティック・ギター、
ウード、ルネサンス・リュート)
エリク・ペーテル
(ライヴ・エレクトロニクス) |
スウェーデンのギター&リュート奏者ペーテル・セーデルベリと、同じくスウェーデンの作曲家&ミュージシャンであるエルク・ペーテルのタッグによるアメリカン・プログラム。
スティーヴ・ライヒの「ヴァイオリン・フェイズ」に"リュートとライヴ・エレクトロニクス"で、ジョン・ケージの「One7」には"ギターとライヴ・エレクトロニクス"の組み合わせで挑むなど、その独創的なアイディアは斬新かつ見事な完成度。
2012年−2013年の録音。 |
 EUTERPE MUSICA EUTERPE MUSICA
|
|
|
チェロ&ギター
ファリャ:ナナ(子守歌)
ジナタリ:チェロとギターのためのソナタ
ストルム:夏の夜のセレナード、日時計、昼と夜、目標
レイス:もしも彼女が尋ねたら
グバイドゥーリナ:2つの前奏曲
マルティンソン:ツインズ Op.64
ヴィラ=ロボス:アリア(ブラジル風バッハ第5番より) |
グンナル・スピュート(ギター)
ヘゲ・ワルデランド(チェロ) |
スウェーデンの名ギタリスト、グンナル・スピュートと、ベンクトソン、トルトゥリエの門弟ヘゲ・ワルデランドのデュオが奏でるギターとチェロの世界。
スペインのファリャ、ブラジルのジナタリ、ヴィラ=ロボス、レイス、スウェーデンのストルム、マルティンソン、ロシアのグバイドゥーリナの音楽による多彩なプログラムでのデュオの響きが味わい深い。 |
| |
|
|
テグネール:ミュージック・フォー・ドリーマーズ |
ペーター・テグネール(ギター) |
| コンポーザー=ギタリスト、プロデューサー、ソングライターなど、様々な姿を持つスウェーデンのマルチプレーヤー、ペーター・テグネールの自作自演集。紙ケース仕様。 |
ICTUS
|
|
|
バッハ・フェイマス・アレンジメンツ
J.S.バッハ:
シンフォニア〔カンタータ第29番より〕(デュプレ編)
ソナチナ〔カンタータ第106番より〕(ギルマン編)
アリオーソ〔カンタータ第156番より〕(フォックス編)
シシリエンヌ〔フルート・ソナタより〕(ウィドール編)
目覚めよと、われらに呼ばわる物見らの声〔カンタータ第140番より〕
いざもろびと神に感謝せよ〔カンタータ第192番より〕(フォックス編)
アリア〔管弦楽組曲第3番より〕(カルク=エラート編)
羊は安らかに草をはみ〔カンタータ第208番より〕(フォックス編)
イエスは変わらざるわが喜び〔カンタータ第147番より〕(デュリュフレ編)
シンフォニア〔クリスマス・オラトリオより〕(カルク=エラート編)
甘き死よ、来たれ(フォックス編)
アダージョ・カンタービレ〔ヴァイオリン・ソナタ第2番より〕(フォックス編)
Mattheus-Final〔マタイ受難曲より〕(ウィドール編) |
ラルフ・グスタフソン(オルガン) |
デュプレやギルマン、ウィドール、デュリュフレなど、音楽史にその名を残す大オルガニストたちによるJ.S.バッハのオルガン・トランスクリプション集。
フロール・ペーテルスとジャン・ボワイエに師事したスウェーデンの名オルガニスト、ラルフ・グスタフソンが、ストックホルム、マリア・マグダレナ教会のオーケルマン&ルンド・オルガン(1927年製)を弾く。
2012年11月の録音。 |
INTIM
|
|
|
シクステンの「レクイエム」
シクステン:《レクイエム》 〜
ソプラノ、バス、混声合唱、2つのホルン、
ティンパニと弦楽のための
ウィテカー:ダヴィデが聞きしとき |
カーリン・インゲベック(ソプラノ)
アンデシュ・ラーション(バス)
ラグナル・ブーリーン(指揮)
スウェーデン放送合唱団
ノルディック室内管弦楽団 |
スウェーデンの教会音楽作曲家であり、指揮者、教会オルガニストとしても活躍するフレドリク・シクステン(1962−)。
初演者でありサンフランシスコ交響合唱団の指揮者ラグナー・ブーリンが再びタクトを執ったこのシクステンの「レクイエム」を歌うのは、北欧の名門スウェーデン放送合唱団。
スウェーデンで生まれた新たな「レクイエム」を、スウェーデン合唱界の素晴らしきコンビの演奏で。
2012年11月1日&2日、スウェーデンでのライヴ録音。 |
 NILENTO NILENTO
|
|
|
パガニーニ:24のカプリース Op.1 |
ヤン・スティグメル(ヴァイオリン) |
スウェーデンの名手スティグメルのパガニーニ!
カメラータ・ルーマン、クリスチャンサン室内管弦楽団のリーダーを務めるなど、北欧、スウェーデンを代表するヴァイオリニストの1人として活発な活動を展開しているヤン・スティグメル。
スカンジナヴィアのヴァイオリニストによる初の全曲録音となったスティグメルが奏でるパガニーニの「24のカプリース」。
その卓越したテクニックと音楽性が生み出す華麗な演奏が、「24のカプリース」が難曲中の難曲であることをしばしの間、忘れさせてくれる。
2012年2月26日−27日&3月4日の録音。 |
NOSAG RECORDS
|
|
|
ブラームス:ドイツ・レクイエム Op.45 |
ストックホルム大聖堂聖歌隊
ミカエル・ヴァルデンビ(指揮)
キャロリン・ジェントル(ソプラノ)
ヨハン・ヴァルベリ(バリトン)
マリア・ロストツスキー(ピアノ)
ヨアキム・アンデション(ピアノ) |
スウェーデン、ストックホルム大聖堂聖歌隊が歌うブラームスの「ドイツ・レクイエム」は、"ロンドン版"として知られる2台ピアノ伴奏版での演奏。
ストックホルム大聖堂に響き渡るブラームスの音楽と聖歌隊のハーモニー。2台ピアノの伴奏のシンプルな音色が、合唱を引き立てる。
2013年6月13日のライヴ録音。 |
| |

nosagCD 2212
(2CD)
\5200 →\4790 |
モーツァルト:ピアノ協奏曲集
ピアノ協奏曲第21番ハ長調 K.467
ピアノ協奏曲第22番変ホ長調 K.482
ピアノ協奏曲第17番ト長調 K.453
ピアノ協奏曲第27番変ロ長調 K.595 |
ペール・エンフロ(ピアノ)
スヴィレン・シメオノフ(指揮)
ソフィア・シンフォニエッタ |
シュナーベルの孫弟子にあたるスウェーデンのピアニスト、ペール・エンフロ(1944−)がソリストを務めるモーツァルトのピアノ協奏曲集。
第21番と第22番では、エンフロ自身のカデンツァを採用。使用ピアノはベーゼンドルファーとスタインウェイ(第17番)。
2012年−2013年の録音。 |
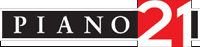 PIANO21 PIANO21
|

P21 052-N
(5CD/特別価格)
\6400 →\4990 |
シプリアン・カツァリス 111・ピアノ・ヒッツ
CD 1:
J.S.バッハ:
前奏曲第1番ハ長調 BWV.846(平均律クラヴィーア曲集第1巻より)
グノー(グノー編):アヴェ・マリア*
アディンセル(ギール/カツァリス編):ワルソー・コンチェルト*
ショパン:ポロネーズ第6番変イ長調 Op.53
《英雄》
シューマン:兵士の行進(子供のためのアルバム
Op.68より)
ブラームス(ムーア編):子守歌 Op.49-4
タレガ(ペンソン編):アルハンブラの思い出
アルビノーニ/ジャゾット:アダージョ*
ショスタコーヴィチ(ノアック編):ワルツ第2番*(ジャズ組曲第2番より)
バルトーク:ルーマニア民俗舞曲 Sz.56
シューベルト:ワルツ第10番(12の高雅なワルツ
Op.77, D.969より)
ヨハン・シュトラウスⅡ世(パラフレーズ:シュット):
ウィーンの森の物語
グルック(チェイシンズ編):
メロディー(バレエ音楽 《オルフェウス》より)*
マスネ(マスネ編):瞑想曲(歌劇 《タイス》より)
ショパン:練習曲第12番ハ短調 Op.10-12
《革命》
カツァリス:日本の歌 《さくら》 による即興曲*
エルガー(シュミッド編):行進曲 《威風堂々》
第1番Op.39-1*
ヘンデル(即興アレンジ:カツァリス):
サラバンド(組曲第11番ニ短調 HWV.437より)
C.P.E.バッハ:
行進曲ニ長調 BWV.Anh.122
(アンナ・マグダレーナ・バッハの音楽帳より)
ソルフェジエット ハ短調 H.220, Wq.117:2
ゴットシャルク(カツァリス編):
バンジョー 〜 ゴットシャルク・ファンタジー,
アメリカン・スケッチ
CD 2:
リスト:ハンガリー狂詩曲第2番
ハイドン(クレメンティ編):
第2楽章 アンダンテ(交響曲第94番ト長調
Hob.I-94 《驚愕》*
クープラン:収穫をする人たち(クラヴサン曲集第2巻より)
シューマン:
収穫の歌(子供のためのアルバム Op.68より)
楽しい農夫(子供のためのアルバム Op.68より)
トロイメライ(子供の情景 Op.15より)
シューベルト(リスト編):アヴェ・マリア
Op.52-6, D.839
ラフマニノフ:前奏曲ト短調 Op.23-5
マルチェッロ(J.S.バッハ/カツァリス編):
第2楽章 アダージョ(オーボエ協奏曲ニ短調
Op.1より)
メンデルスゾーン:春の歌 Op.62-6(無言歌集より)
シューマン:乱暴な騎手(子供のためのアルバム
Op.68より)
ショパン:前奏曲7番イ長調 Op.28-7
ビゼー(ホフマン編):ハバネラ(歌劇
《カルメン》より)*
ビゼー(編曲者不詳):ファランドール(劇音楽
《アルルの女》より)*
作曲者不詳:
メヌエット ニ短調 BWV.Anh.132
(アンナ・マグダレーナ・バッハの音楽帳より)
ブラームス:間奏曲第2番変ロ短調 Op.117
モーツァルト伝(カツァリス編):バター付きパン
シューベルト:コティヨン変ホ長調 D.976
スクリャービン:アルバムの綴り(3つの小品
Op,45より)
ベートーヴェン(リスト/カツァリス編):第4楽章
プレスト:
アレグロ・アッサイ 《歓喜の歌》(交響曲第9番ニ短調
Op.125より)
ショパン:ワルツ第7番嬰ハ短調 Op.64-2
CD 3:
マンシーニ:ピンク・パンサーのテーマ*
サン=サーンス(ゴドフスキー編):白鳥(動物の謝肉祭より)
作曲者不詳:ミュゼット ニ長調 BWV.Anh.126
(アンナ・マグダレーナ・バッハの音楽帳より)
J.S.バッハ:アリア(ゴルトベルク変奏曲
BWV.988より)
リュリ:クーラント*
スカルラッティ:ソナタ ハ長調 K.159
ファリャ:火祭りの踊り(バレエ音楽 《恋は魔術師》より)
オルフ(エリック・チュマチェンコ編):
全世界の支配者なる運命の女神〜
1.おお、運命の女神よ -
2.運命の女神に傷つけられて(カルミナ・ブラーナより)
シューベルト:
ワルツ第19番(36の独創的舞曲《最初のワルツ》
Op.9, D.365より)
ショパン:練習曲第3番ホ長調 Op.10-3 《別れの曲》
ラヴェル(シャルロ編):
眠りの森の美女のパヴァーヌ(組曲 《マ・メール・ロワ》より)*
モーツァルト:トルコ行進曲(ピアノソナタ第11番イ長調
K.331より)
ダンドリュー:小笛 - ロンドー
シューベルト:楽興の時第3番ヘ短調(6つの楽興の時
Op.94, D.780より)
ヴィヴァルディ(ファリーナ編):
第2楽章 ラルゴ(ヴァイオリン協奏曲集
《四季》 -
協奏曲第4番ヘ短調 Op.8, RV.297 《冬》より)*
ヘンデル(ツェルニー編):ハレルヤ(オラトリオ
《メサイア》より)*
J.S.バッハ(カツァリス編):
バディネリ〜バーレスク・スタイル・アレンジ
(管弦楽組曲第2番ロ短調 BWV.1067より)
シューベルト:
ワルツ第35番(36の独創的舞曲《最初のワルツ》
Op.9, D.365より)
ワイル(編曲者不詳):タンゴ・バラード(歌劇
《三文オペラ》より)*
カツァリス:
韓国の歌 《アリラン》 による即興曲*、
クリスマスの思い出(ファースト・ヴァージョン)〜
グルーバーの 《きよしこの夜》 による幻想曲*
ベートーヴェン:第1楽章 アダージョ・ソステヌート
(ピアノ・ソナタ第14番嬰ハ短調 Op.27-2
《月光》より)
ドビュッシー:月の光(ベルガマスク組曲より)
シューベルト:軍隊行進曲第1番ニ長調 Op.51-1,
D.733
(リスト:演奏会用大パラフレーズ)
ワーグナー(ブラッサン/カツァリス編):
ワルキューレの騎行(楽劇 《ワルキューレ》より)
シューマン:間奏曲(ウィーンの謝肉祭の道化より)
プロコフィエフ:第3楽章 プレチピタート
(ピアノ・ソナタ第7番変ロ長調 Op.83
《戦争ソナタ》より)
CD 4:
シフラ:演奏会用練習曲第1番
(リムスキー=コルサコフの《熊蜂の飛行》による)
モーツァルト:第2楽章 アンダンテ
(ピアノ協奏曲第21番ハ長調 K.467 《エルヴィラ・マディガン》より)†
J.S.バッハ(カツァリス編):トッカータとフーガ
ニ短調 BWV.565
チャイコフスキー:6月 舟歌(四季 Op.37aより)
ブラームス(カツァリス):ハンガリー舞曲第1番ト短調
ブラームス(レーガー編):第3楽章 ポコ・アレグレット
(交響曲第3番ヘ長調 Op.90より)*
ルビンシテイン:メロディー ヘ長調 Op.3-1
ドリーブ(ドホナーニ編):ワルツ(バレエ音楽
《コッペリア》より)
パッヘルベル(カプドヴィーユ編):カノン*
ショパン:前奏曲第16番変ロ短調 Op.28-16
ボロディン:夜想曲(小組曲より)
カツァリス:様々な主題による即興曲
(ブラームス:ハンガリー舞曲第4番、
オッフェンバック:歌劇《ホフマン物語》より
舟歌、
モーツァルト:歌劇 《魔笛》より 恋人か女房が、
サン=サーンス:歌劇《サムソンとデリラ》より
あなたの声で心は開く、
ヴェルディ:歌劇 《椿姫》より プロヴァンスの海と陸、他)*
任光(王建中編):彩雲追月
ラフマニノフ:第3楽章 フィナーレ(ピアノ協奏曲第3番ニ短調
Op.30より)‡
CD 5:
ハチャトゥリアン(ソリン/カツァリス編):
剣の舞(バレエ音楽 《ガイーヌ》より)
サティ:ジムノペディ第1番
フォーレ(コルトー編):ドリーの庭(組曲
《ドリー》 Op.56より)*
J.S.バッハ:ミュゼット ト長調(イギリス組曲第3番
BWV.808より)
ショパン(ショパン編):
第2楽章 ロマンス - ラルゲット(ピアノ協奏曲第1番ホ短調
Op.11より)
シューベルト:レントラー第5番(8つのレントラー
D.681より)
ブラームス:ワルツ第15番変イ長調 Op.39-15
ドヴォルザーク(カツァリス編):スラヴ舞曲ホ短調
Op.72-2
ベートーヴェン:バガテル第25番イ短調
WoO.59 《エリーゼのために》
マルティーニ(ビゼー編):愛の喜びは
- ロマンス*
リスト:夜想曲第3番 《愛の夢》
メンデルスゾーン(メンデルスゾーン編):
結婚行進曲(劇音楽 《夏の夜の夢》より)*
チャイコフスキー(タネーエフ編):
花のワルツ(バレエ音楽 《くるみ割り人形》
Op.71より)*
グリーグ(グリーグ編):朝の気分(ペール・ギュント組曲第1番
Op.46)
ロドリーゴ(ロドリーゴ編):
我が心のアランフエス(アランフエス協奏曲より)*
カツァリス:
マイルドレッド・J&パティ・S・ヒルの
《ハッピー・バースデー・トゥ・ユー》による幻想曲
(ファースト・ヴァージョン)*
ガーシュウィン(ガーシュウィン編):ライザ(ソングブックより)
バーンスタイン(スミット編):ジェッツ、ジャンプ、チャチャ
(ウェスト・サイド・ストーリーより3つの楽章)
ヴィラ=ロボス(グセー編):アリア 《カンティレーナ》
(ブラジル風バッハ第5番より)*
ピアソラ:ラ・ミスマ・ペーニャ*
カラスコ:アディオス |
シプリアン・カツァリス
(ピアノ)
リ・ユンク(指揮)†
ザルツブルク・
カンマーフィルハーモニー†
ルネ・ドフォッセ(指揮)‡
ベルギー国立管弦楽団‡ |
衝撃のカツァリス5枚組111曲!噂の「さくら即興曲」など、初出・秘蔵音源満載!
*=世界初録音 / ※指揮者とオーケストラの表記がある2曲を除き、すべてピアノ独奏版
齢60を超えて益々精力的な活動を繰り広げ、公演でも録音でも常に我々の度肝を抜いてくれる超絶技巧の現人神、シプリアン・カツァリス。カツァリスの音楽活動のすべてを凝縮したかのような、5枚組全111曲という超弩級のアルバムが登場!
リサイタルのアンコールなどで演奏され話題を呼んでいた「《さくら》による即興曲」や「《きよしこの夜》による幻想曲」、「《ハッピー・バースデー・トゥ・ユー》による幻想曲」など、カツァリスの優れた即興やアレンジが発揮されるオリジナル作品。
入手困難となっているバッハ・アルバムより「トッカータとフーガ
ニ短調」や「バディネリ」、リスト編曲にさらに自身の編曲も加えたベートーヴェンの第九、シフラ編「熊蜂の飛行」など、これでもかという超絶技巧曲。そして、タイスの瞑想曲、アルビノーニのアダージョ、パッヘルベルのカノン、威風堂々、剣の舞、ファランドール、ワルキューレの騎行、花のワルツ、アランフエス協奏曲などなど、超有名曲たちのピアノ・トランスクリプション版も多数収録。約30曲の世界初録音曲、初出音源、秘蔵音源を満載した、カツァリス・ファンはもとより、ピアノ・ファン、アレンジ・ファン垂涎のスペシャルBOXです! |
 CAPRICCIO CAPRICCIO
|

C5208
\2700 |
リヒャルト・シュトラウス:英雄の生涯・メタモルフォーゼン
1-6.交響詩「英雄の生涯」Op.40
<英雄/英雄の敵/英雄の伴侶/英雄の戦場/
英雄の業績/英雄の隠遁と完成>/
7.23の独奏楽器によるメタモルフォーゼン |
モレート・マックラン(ヴァイオリン・ソロ)…1-6/
ウィーン放送交響楽団/
コルネリウス・マイスター(指揮) |
2010年からウィーン放送交響楽団の首席指揮者として活躍しているコルネリウス・マイスター。現在34歳の若手ですが、度々の日本来日公演での高い評価でもわかる通り、「次世代を担う指揮者」の中でもとびきりの才能を示している人です。
彼のリヒャルト・シュトラウス(1864-1949)は既に定評があり、この手兵との演奏は、もう聴く前から期待が高まるという本当に凄いもの。元々が、若干大げさすぎる作品ではありますが、全ての音はすっきりと纏められ、伸びやかな響きが楽しめるというものです。うって変わって「メタモルフォーゼン」での憂鬱な表情と、時折見せる晴れやかな部分の対比も素晴らしいものです。 |
| |

C5213
\2700 |
ベルント・アロイス・ツィマーマン:作品集
1-5.バレエ音楽「アラゴアナ、カプリチョス・ブラジレイロス」(1940-1950頃)
<序曲/セルタネホ/サウダーテ/カボチョ/フィナーレ>/
6.1楽章の交響曲(第2稿)(1953)/
7.前奏曲「フォトプトーシス」/8.静止と反転 |
ラインランド=プファルツ州立フィルハーモニー管弦楽団/
カール=ハインツ・シュテフェンス(指揮) |
録音 2014年1月6-11日 フィルハーモニー,ルートヴィヒスハーフェン
ドイツの現代作曲家ベルント・アロイス・ツィマーマン(1918-1970)。彼は様々な音楽を書き、多くの後進を指導しましたが「自身の作品が理解されないこと」を悲しみ、ピストル自殺を遂げてしまったのです。
そんな彼の作品は、最近「兵士たち」などが注目を浴びたことでようやく聴かれる機会が増えてきました。もちろん作品の受容も深まり、CDなどのリリースも少しずつ増えてきています。
このバレエ音楽「アラゴアナ、カプリチョス・ブラジレイロス」は、彼の初期の作品。想像以上に楽しい曲で、ヴィラ=ロボスなどが好きな人にはたまらないものです。華やかなオーケストレーション、炸裂するリズムなど、全く難解ではありません。「1楽章の交響曲」も新古典派主義の音楽です。一転「フォトプトーシス」「静止と反転」は静かな音楽。「静止主義」といわれる作風で書かれています。 |
| |

C5215
\2700 |
ウィーン奇想曲
1.フリッツ・クライスラー(1875-1962):ウィーン風小行進曲/
2.クライスラー:愛の喜び/
3.クライスラー:愛の悲しみ/
4.クライスラー:ウィーン奇想曲 Op.2/
5.ヨハネス・ブラームス(1833-1897):ハンガリー舞曲
第1番/
6.モーリス・ラヴェル(1875-1937):ツィガーヌ(1924)/
7-9.ジョルジュ・エネスク(1881-1955):
ヴァイオリン・ソナタ 第3番 イ短調 Op.25(1926) |
ルカ・クストリッヒ(ヴァイオリン)/
ドラ・デリイスカ(ピアノ) |
録音 2014年6月20-23日 ウィーン,4TUNE スタジオ
1991年、ウィーン生まれのヴァイオリニスト、ルカ・クストリッヒ。芸術家の家庭に生まれた彼は幼い頃から才能を発揮し、演奏家としてだけでなく、俳優としても認められ、舞台、テレビなどで幅広く活躍しています。
しかし彼の本当の夢は偉大なる演奏家になること。ゆくゆくはヴァイオリンの教授になりたいと語り、また演奏技術も極めたいのだそうです。
2005年に初来日、その才能の片鱗を見せ付けた彼ですが、その才能は順当に成熟しているようです。このアルバムでは、難曲であるエネスクのソナタをはじめ、ラヴェルのツィガーヌで目の覚めるような名演を披露、そしてクライスラー、ブラームスの作品では柔軟な表現力を見せています。確かに将来が楽しみな若手です。 |
| |

C5217
(2枚組)
\2700 |
バロック・クリスマス 〜カンタータとモテット集
<CD1>
1-9.W.F.バッハ(1710-1784):
カンタータ「闇の衣を脱ぎ捨てて」/
10.J.C.バッハ(1642-1703):
主は、私たちを目覚めさせる/
11-13.J.C.F.バッハ(1732-1795):
クリスマス・モテット「目覚めよと呼ぶ声が聞こえ」/
14-26.C.P.E.バッハ(1714-1788):
クリスマス・カンタータ「天は御神の栄光を語り」
Wq.249/
<CD2>
1-7.J.S.バッハ(1685-1750):わが魂よ、主をほめたたえよ
BW143/
8.クリスティアン・ガイスト(1640頃-1711):
暁の星のいと美しきかな/
9.ディートリヒ・ブクステフーデ(1637-1707):
新たに生まれしみどり児 BuxWV13/
10-12.G.P.テレマン(1681-1767):神々の子等は喜びたもう
TVWV1:1020a /
13-17.マリア・ポ・デル・フィナーレ(1700頃):
「ああ、楽しき日」祝福されたクリスマスのためのモテット/
18.エステルハーツィ公(1635-1713):なぜイエスは泣くのか/
19-22.N.A.ポルポラ(1686-1768):クリスマス・モテット「明るい星」/
23-24.C.P.E.バッハ:「聖なるかな」 Wq.217 |
ライニッシェ・カントライ…CD1:1-9,11-26,CD2:23-24/
クライネ・コンツェルト…CD1:1-9,11-26,CD2:23-24/
ヘルマン・マックス(指揮)…CD1:1-9,11-26,CD2:23-24/
テルツ少年合唱団…CD1:10/
マルク・ノルドストランド(オルガン)…CD1:10/
ライプツィヒ新バッハ・コレギウム・ムジクム…CD2:1-7/
マックス・ポンマー(指揮)…CD2:1-7/
ベルリン・バロック・カンパニー…CD2:8,10-12/
カペラ・サバリア…CD2:9,18/
パール・ネメス(指揮)…CD2:9,18/
ラルテ・デル・モンド…CD2:13-17,19-22/
ヴェルナー・エールハルト…CD2:13-17,19-22 |
Capriccioレーベルが持つ膨大な作品の中から、バロック時代のクリスマス音楽を集めた2枚組。
ほとんど知られていない作品が含まれていますが、これらのなんと美しいこと!色々なスタイルの作品が含まれていますが、どれもお祝いの気分に満ちた荘厳で喜ばしい曲ばかりです。静かなクリスマスを過ごしたい人にもうってつけのアルバムです。 |
| |

C5220
\2700 |
ヨハンナ・ドーデラー:ピアノ三重奏曲集
1-4.ピアノ三重奏曲 第3番
「2010年、2011年のグスタフ・マーラー記念祭に」
DWV64(2009)/
5-7.ピアノ三重奏曲 第2番「ハイドンに捧ぐ」DWV52(2008)/
8-11.ピアノ三重奏曲 第1番 VWV31(2002)/
12-16.ピアノ三重奏曲 第4番「朝」 DWV79(2013) |
ヴィロス三重奏団
<メンバー:
ダリア・デディンスケイト(ヴァイオリン)/
グレプ・パイシュニアク(チェロ)/
オレ・クリスティアン・ハーゲンルッド(ピアノ)> |
録音 2014年6月18-20日 ウィーン,4TUNE スタジオ
1969年、オーストリアに生まれた女性作曲家ヨハンナ・ドーデラー(1969-)。名小説家や建築家などを輩出した名門の家系に生まれ、幼い頃から文化や文学に親しんできた彼女、その作品は世界的に高く評価されています。多くの芸術家たちとコラボレーションし、色々な作品を生み出してきた彼女、このピアノ三重奏曲も刺激的な音に満たされています。
彼女はピアノ三重奏曲という小さな形式を愛しているといい、このアンサンブルが生み出す音は絶対的なものだと断言しています。時にはミニマル形式を用いつつも、過去の大作曲家たちへのリスペクトを忘れない彼女の音楽は、一際美しい光を放つものです。 |
| |

C5225
(3枚組)
\3100 |
ヨハネス・ブラームス:マゲローネのロマンスをめぐって
<CD1>
美しきマゲノーネのロマンス Op.33/
<CD2-3>
「美しいマゲローネ姫とプロヴァンスの
伯爵ペーターの不思議な恋の物語」の朗読付き
美しきマゲノーネのロマンス Op.33 |
パウル・アルミン・エデルマン(バリトン)/
ユリア・シュテムベルガー(朗読)…CD2.3/
チャールズ・スペンサー(ピアノ) |
ルートヴィヒ・ティークによる「美しいマゲローネ」は、主人公ペーター伯爵と、ナポリの美しい王女マゲローネが出会ってから、苦難を乗り越え結ばれるまでを描いた長編小説です。
Capriccioレーベルでは、ダニエル・ベーレの歌う「マゲローネ」を“歌のみ”と“朗読付き”のセットでリリースし、大好評を得ていますが、今回は若きバリトン、パウル・アルミン・エデルマンの歌唱による「マゲローネ」完全版です。
テノールで歌われると若者の懊悩が際立つものですが、バリトンで歌われると、物語にまた違った陰影をもたらすものですね。こちらで朗読を担当しているのは、名女優ユリア・シュテムベルガーで、このニュアンスある語りは物語に素晴らしい余韻を残します。 |
<マイナー・レーベル歴史的録音・旧録音>
 CAPRICE CAPRICE
|
|
|
ペルガメントの大作"ユダヤ人の歌"が復活!
ペルガメント:ユダヤ人の歌 |
ビルギット・ノルディン(ソプラノ)
スヴェン・オーロフ・エリアソン(テノール)
ジェームズ・デプリースト(指揮)
ロイヤル・ストックホルム・
フィルハーモニー管弦楽団
ストックホルム・フィルハーモニー合唱団 |
近代スウェーデンの偉大なるモダニスト。ペルガメントの大作"ユダヤ人の歌"が復活!
ヘルシンキ出身のスウェーデンの音楽家であり、近代スウェーデンにおける重要なモダニストの1人と称されるモーセス・ペルガメント(1893−1977)。
ラグナー・ヨゼフソンの詩に基づき、壮大なスケールで描かれるソプラノ独唱、テノール独唱、合唱とオーケストラのための合唱交響曲「ユダヤ人の歌」(1944年)は、自らのルーツであるユダヤのテーマを用いたペルガメントの代表作である。
オレゴン交響楽団の音楽監督、東京都交響楽団の常任指揮者として活躍したジェームズ・デプリーストとストックホルム・フィルのコンビによる録音の復活は、ヘルシンキ、サンクトペテルブルク、ベルリン、パリ、そしてストックホルムで活躍し、"ユダヤ"と"北欧"の作風の融合を目指したペルガメントの音楽、功績の再評価の機運を高めてくれることだろう。
※録音(ライヴ):1974年2月3日、ストックホルム・コンサート・ホール(スウェーデン) |
GRAND SLAM
|


GS 2120/1
(2CD)
2枚組1枚価格
\2500 →¥2290 |
マーラー:交響曲第9番 ニ短調 |
ブルーノ・ワルター(指揮)
コロンビア交響楽団 |
2 枚組1枚価格!ワルター&コロンビア響、2トラ38シリーズにマーラーの交響曲第9番登場!偉大なプロデューサー、J.マックルーア追悼盤
セッション録音:1961年1月16、18、28、30日、2月2、6日、カリフォルニア、アメリカン・リージョン・ホール(ステレオ)
使用音源: Private archive (オープンリール・テープ、2トラック、38センチ)
■制作者より
ワルター指揮、コロンビア交響楽団の名盤、マーラーの交響曲第1
番「巨人」と並行して録音されたのが同じくマーラーの交響曲第9
番でした。
言うまでもなく、この曲はワルターが初演を行い、ワルター自身もこの第9
番こそマーラーの遺言であると語っています。かくして、ワルターの特別な思いがこもった作品が、2
トラック、38 センチのオープンリール・テープより蘇ります。しかも、2
枚組1 枚分価格でのご提供です!
また、初出のLP にはワルター自身がマーラーの交響曲第9
番について記した文章が掲載されていましたが、当CD
にはその全文を翻訳して掲載しています。
なお、この第9 番はジョン・マックルーアの制作ですが、その偉大なプロデューサーは2014
年6 月17 日に84 歳で他界しました。当GS シリーズにもさまざまな情報を提供してくれたマックルーアに対し、この第9
番を追悼盤として捧げたいと思います。(平林 直哉) |
IDIS
|
|
|
チェリビダッケの名伴奏も光る、グッリの至芸
(1)バルトーク:ヴァイオリン協奏曲第2番
(2)プロコフィエフ:ヴァイオリン協奏曲第1番ニ長調Op.19 |
フランコ・グッリ(Vn)
(1)マリオ・ロッシ(指揮)
イタリア国立放送管弦楽団
(2)セルジュ・チェリビダッケ(指揮)
ナポリ・アレッサンドロ・
スカルラッティ放送管弦楽団 |
(1)録音:1959 年12 月31 日ライヴ (2)録音:1957
年12 月22 日ライヴ/MONO、61’ 40”
フランコ・グッリ(1926-2001) はシゲティ門下のイタリアのヴァイオリニスト。ローマ合奏団のメンバーを務め、東京音大でも教鞭を執ったため、日本にも教え子が多くいます。
ここでは20 世紀のヴァイオリン協奏曲名作2
篇に挑戦。いずれもシゲティ譲りの辛口で深い精神性が特徴で、明るい音色に魅せられます。
さらにプロコフィエフ作品はチェリビダッケが指揮を務めているのも注目。チェリビダッケのプロコフィエフ演奏は、録音に残されたものの素晴らしさからうかがえますが、このヴァイオリン協奏曲第1
番の伴奏は驚愕の巧さ。独奏にピッタリ合わせつつ、完全にチェリの音楽となっていて面白さの極みです。
旧譜のパガニーニは入手困難。今回はお早めに・・・ |
| |
|
|
幻の名手デ・バルビエーリ、期待の第3弾
(1)レスピーギ:ヴァイオリン・ソナタ ロ短調
(2)カステルヌオーヴォ=テデスコ:ヴァイオリン協奏曲第2番「預言者たち」 |
レナート・デ・バルビエーリ(Vn)
(1)トゥリオ・マコッジ(Pf)
(2)カルロ・ファリーナ(指揮)
サンレモ管弦楽団 |
(1)録音:1962年放送録音 (2)録音:1960年代。ライヴ/MONO、56’
44”
レナート・デ・バルビエーリ(1920-1991) の第3
弾。プシホダとエルマンの門下で、決して古い人ではありませんが、録音が極めて少ないため「幻のヴァイオリニスト」の感があります。このアルバムはイタリア近代の名作2
篇を収めています。
明るい音色と超絶技巧が聴きもの。カステルヌオーヴォ=テデスコの「ヴァイオリン協奏曲第2
番」はハイフェッツの委嘱で作曲され、彼の録音で知られていますが、バルビエーリはユダヤ色よりもイタリア音楽としての表現で説得力満点。レスピーギのソナタとともの、感動させられます。
第1,2弾は早くも入手困難。第3弾もお早めに・・・ |
| |
|
|
ボリス・ゴールドシュタインの芸術II
(1)ベルトルト・フンメル:ディアローグOp.63
(2)ジョゼフ・ギブス:ヴァイオリン・ソナタニ短調
(3)ヴィタリ:シャコンヌ |
ボリス・ゴールドシュタイン(Vn)
クラウス・キューンル(Org) |
ザハール・ブロンの師・ロシア楽派の大御所ゴールドシュタインの至芸
録音:1977 / 78(スタジオ)/STEREO、41’
13”
ヴァイオリン・マニア待望のCD。ボリス・ゴリトシュテイン(1922
− 1987 姓はドイツ語風にゴルトシュタインとも、独英折衷でゴールドシュタインとも表記)は、ソ連時代のウクライナ、オデッサ生まれのヴァイオリニスト。ちなみにオデッサといえばナタン・ミルシテイン、ミッシャ・エルマン、ダヴィッド・オイストラフら多くの名ヴァイオリニストを生んだ地として知られています。ゴリトシュテインは少年期から才能を発揮し、1935
年、ワルシャワでの第1回ヴィエニャフスキ国際ヴァイオリン・コンクールで第4
位を獲得。この時は、優勝がジネット・ヌヴー、準優勝がダヴィッド・オイストラフ、第3
位がアンリ・テミアンカ、さらにゴルトシュタインより下位にイダ・ヘンデルやブロニスワフ・ギンペルが入るというとてつもない水準の高さで、まだ12
歳だったゴリトシュテインがいかに天才少年だったかを物語っています。
さらに1937 年、ブリュッセルでのイザイ・ヴァイオリン・コンクール(エリザベート王妃国際音楽コンクールの前進)
で第4 位。この時も優勝がダヴィッド・オイストラフ、準優勝がリカルド・オドノポゾフ、第7
位にローラ・ボベスコがいるという激戦の中の第4
位でした。この頃の映像が残されており、ゴリトシュテイン少年の演奏の完成度の高さに驚かされます。
そんなゴリトシュテインですが、ソ連時代には録音が極めて乏しく、幻のヴァイオリニストでした。1970
年半ばに西ドイツに亡命(弟の作曲家、ミハイル・ゴルトシュタインが先に西ドイツに亡命していた)、教職の傍ら演奏活動も行いますが、国際的な注目を浴びることはないまま1987
年に亡くなりました。
ボリス・ゴールドシュタイン(1922-1987) はザハール・ブロンの師であるため、レーピン、樫本大進、庄司紗矢香の師筋にあたるロシア楽派の大御所。
このアルバムは1977 年から翌年にかけて録音されたもので、オルガン伴奏という点がユニーク。現代作曲家ベルトルト・フンメルの「ディアローグ」は、ヴァイオリンとオルガンのためのオリジナル作品。イギリス・バロックのギブス(1699-1788)
の儚い美しさ、名作ヴィタリのシャコンヌの巨匠ぶり、いずれもヴァイオリン関係者必聴の演奏と申せましょう。
こちらも第1弾は入手困難。VENEZIAのブラームスも入手困難。下記MELODIYA盤は唯一入手可能性がある。
MELODIYA盤、入ればラッキー |
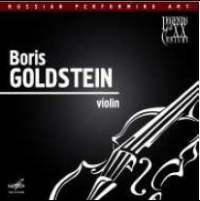
MELODIYA
MELCD 1001748
\2500 →\2290 |
20世紀の伝説 〜 ボリス・ゴールドシュタイン
メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲ニ短調(1822)*
クニュース:ヴァイオリン協奏曲ホ短調#
フェルツマン:ヴァイオリン協奏曲ホ短調** |
ボリス・ゴールドシュタイン(ヴァイオリン)
ミハイル・テリアン(指揮)*
モスクワ音楽院室内管弦楽団*
ゲンナジー・ロジェストヴェンスキー(指揮)#
モスクワ・フィルハーモニー交響楽団#
N・ラフリン(指揮)**
ソヴィエト国立交響楽団** |
オイストラフの弟子でブロンの師、ボリス・ゴールドシュタイン(1922−1987)は、1937年のウジェーヌ・イザイ・コンクールで4位入賞(第1位はオイストラフ)はロシアのヴァイオリニスト。
ドイツへの亡命の前に収録されたこの協奏曲録音では、オスカー・フェルツマン(1921−)のヴァイオリン協奏曲が初CD化となる。1962年#/**&1968年*の録音。ディジパック仕様。 |
|
<映像>
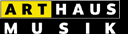 ARTHAUS(映像) ARTHAUS(映像)
|

102205
(DVD)
\4100→\3690 |
ヤンソンス&バイエルン放送響
ヴェルディ:レクイエム |
クラッシミラ・ストヤノヴァ(ソプラノ)/
マリナ・プルデンスカヤ(メゾ・ソプラノ)/
サイミール・ピルグ(テノール)/
オルリン・アナスタソフ(バス)/
バイエルン放送交響楽団&合唱団/
マリス・ヤンソンス(指揮) |


108136
(BD)
\6600→\5990 |
2013年 ウィーン・ムジークフェライン 黄金のホール
ライヴ収録/収録時間:91分/音声:イタリア語歌唱
<DVD>ステレオ2.0/DD 5.1 <BD>ステレオ2.0/dts-HDマスターオーディオ5.1字幕:英,独,仏/画面:16:9/REGION
All(Code:0)/
<DVD>片面2層ディスク <BD>単層25GB
1080i High Definition
ヴェルディ(1813-1901)のレクイエムは、もともと「マンゾーニの命日を記念するためのレクイエム」で、これは1873年に彼が青年時代から敬愛していた文豪アレッサンドロ・マンゾーニの死を悼んで構想したものです。しかし、この曲の萌芽といえるものは、1868年のジョアキーノ・ロッシーニの死去の際にヴェルディが「13人の作曲家たちによるレクイエム」の作曲を計画し(結局その発案は様々な事情で放棄されることになります)、その時に彼の担当であったリベラメであり、これは、このマンゾーニのためのレクイエムで見事リサイクルされ、若干の形を変えた上で、同じリベラメに採用されたのでした。とはいうものの、この曲で一番人気の高いのは何といっても、雪崩落ちるような迫力を持つ「ディエス・イレ(怒りの日)」であり、このメロディのおかげで、モーツァルト、フォーレ作品とともに“三大レクイエム”と称され、現在でも上演の機会が多くあるのです。数あるレクイエムの中でも、極めて劇的でドラマティックな要素を持つこの作品、オーケストラ、合唱、ソリストの全てに高い能力と緊張感が求められる曲でもあります。
さて、思わずヤンソンスの指揮姿に見入ってしまう、この「ヴェルディのレクイエム」。彼は見事に配置された合唱団を従え、揺るがないオーケストラの響きを紡ぎあげていきます。この音色は“黄金のホール”にくまなく行き渡り、美しい残響と畏敬の思念をを伴いながら聴き手の耳に届くのです。
ソリストたちの歌唱も素晴らしく、なかでも22歳の若さでクラウディオ・アバドに見出されたテノール歌手サイミール・ピルグの起用は、この演奏に素晴らしい彩りを添えていることは間違いありません。途方もない美しさを有するこのレクイエム、全ての死者と生者のためへの素晴らしい贈り物です。 |
| |
100365
(DVD)
\6600 |
ヨハン・シュトラウス2世:歌劇「ジンプリチウス」
3幕 ヴィクトール・レオン 台本
ハンス・ヤーコプ・クリストッフェル・フォン・グリンメルスハウゼン「阿呆物語」原作 |
隠者(ヴェンデリン・フォン・グルッペン)…ミヒャエル・ヴォッレ(バリトン)/
ジンプリチウス…マルティン・ツィセット(テノール)/
ヒルデガルデ…エリザーベト・マグヌソン(ソプラノ)/
アルニム・フォン・グルッペン…ピョートル・ベチャーラ(テノール)/
メルヒオール(占星術師)…オリヴァー・ヴィドマー(バス・バリトン)
他/
チューリヒ歌劇場管弦楽団&合唱団
(合唱指揮…エルンスト・ラッフェルスバーガー)/
チューリヒ歌劇場児童合唱団/
フランツ・ヴェルザー=メスト(指揮)/
デイヴィッド・ポウントニー(演出)/
ヨハネス・エンゲルス(装置)/
フィリップ・エグリ(コレオグラフィ)/
ユルゲン・ホフマン(照明)/
クザヴィエ・ツーヴァー(脚本)/
トーマス・グリム(映像ディレクター) |

108127
(BD)
\6600 |
2000年 チューリヒ歌劇場 ライヴ収録/収録時間:132分/音声:ドイツ語歌唱/<DVD>ステレオ2.0/DD
5.1/DTS5.1 <BD>ステレオ2.0/DD 5.1/DTS5.1/字幕:英,独.仏,西/画面:16:9/REGION
All(Code:0)/<DVD>片面2層ディスク
<BD>単層25GB 1080i High Definition
1887年に初演されたヨハン・シュトラウス2世(1825-1899)の非常に珍しいオペラです。同じ配役によるCDは以前発売されていましたが、現在では入手も困難であり、この映像の発売は、シュトラウス・ファンだけでなく「知られざるオペラ好き」にとっても喜ばしいものと言えるでしょう。
もともとのお話は、17世紀ドイツを代表する民衆小説で、1618年から1868年に戦われた「三十年戦争」を背景にした物語です。故郷の村を戦禍で失い、森に逃げた主人公が隠者から名前「ジンプリチウス」と学問を与えられ成長、その後は様々な職を経験しながら戦乱の世を生き抜いていくというお話で、動乱の世であるため、もちろん彼の行いは悪へ傾きがちではありましたが、どうにか狡猾に生き抜き、世界中を放浪し、最後は平和になった故郷に戻り、隠者になるというものです。
このオペラではもう少し複雑な設定が施されており、親子の愛情や男女感の愛などが巧みに盛り込まれた人情物語となっているところがシュトラウスらしいといえるでしょう。一つ一つのエピソードは確かに面白く、全体はブラックユーモアに満ちており、なかなか舞台として表現することは難しい題材ですが、演出を担当したポウントニーはこれらを難なくクリア。小粋な小道具を使い、このどぎついお話を丁寧に見せることに成功しています。歌手たちも芸達者であり、とりわけタイトル・ロールのツィセットの演技と歌は壮観です。
ウェルザー=メストはいつものようにすっきりとした味つけを施し、このオペラに清潔感を与えています。 |
| |
101670
(DVD)
\4100 |
フランシスコ・アライサ:「冬の旅」と「詩人の恋」を歌う
1.シューベルト(1797-1828):冬の旅 D911/
2.シューマン(1810-1856):詩人の恋 Op.48 |
フランシスコ・アライサ(テノール)/
ジャン・ルメール(ピアノ) |
1993年収録/収録時間:134分/音声:ドイツ語語歌唱/ステレオ2.0/字幕:なし/画面:4:3/REGION
All(Code:0)/片面2層ディスク
1950年生まれのテノール、フランシスコ・アライサ。今ではオペラの舞台から引退し、いくつかの国際声楽コンクールの審査員を務めたり、音楽大学の教授職を務めたりと後進の指導に忙しい様子ですが、彼が引退するまでは「世界最高のテノール」としてオペラ、リートの分野で華々しい活動をしていました。彼はメキシコで生まれ。1970年にベートーヴェンの歌劇「フィデリオ」の囚人役でデビュー、以降モーツァルトとロッシーニ作品で独自の個性を発揮、国際的な名声を獲得します。
1980年代にはワーグナーの歌劇もレパートリーとするなどレパートリーを広げ、その柔らかい声質と柔軟な表現力で世界中の歌劇場の聴衆を熱狂させることになります。数々の指揮者、オーケストラと共演し、素晴らしい実績を残したほか、ポピュラー音楽にも積極的に挑み、こちらはまた違った味わいを醸し出していたことでも知られています。
この2つの歌曲集は1993年に収録されたもので、円熟した歌声と深い表現力に裏打ちされた素晴らしい演奏です。ピアノを演奏しているジャン・ルメールはアライサといくつかの歌曲、フランス、スペイン、メキシコの作品を録音しており、ここでも驚くほどに、息のあったアンサンブルが聞けることでしょう。 |
| |
102198
(DVD)
\6600 |
ロメオとジュリエット(ヒップ・ホップ・ヴァージョン)
シェークスピア原作 |
ジュリエット…ジャン・ガロア/
ロメオ…ジョヴァンニ・レオカルディ/
ベンヴォーリオ…ジャン=シャルル・ザンポ/
マルキューシオ…アキム・アチョーシェ/
キャピュレット夫人…エストデ・マナス/
ジュリエットの乳母…オツアワン・ニョン/
ティボルト…ジュリアン・ロウレ/
キャピュレット…ローラン・パオリーニ/
ロレンス…チュリル・ムジー/
セバスティアン・レフランソワ(コレオグラフィ)/
ローラン・コウソン(音楽)/
マリー=ピエール・ブスケ(プロダクション)/
マガリ・デリス(脚本)/
トム・クレフスタット(照明)/
ジュリオ・リヒトナー(情景)/
マリオ・ファウンデス(衣装)/
デニス・カイオッツィ(TVディレクター) |
108123
(BD)
\6600 |
2008年 シュレンヌ ジャン・ヴィラール劇場
ライヴ収録/収録時間:79分/音声:仏 ステレオ2.0/字幕:なし/画面:16:9/REGION
All(Code:0)/<DVD>片面2層ディスク
<BD>単層25GB 1080i High Definition
誰もが知っているシェークスピアの名戯曲「ロメオとジュリエット」は、バレエ作品だけを見ても、数限りない解釈が施され、多くの作曲家が音楽を書き、様々な世界へと移されながら普遍の人気を保っています。
このフランス人コレオグラフィ、レフランソワによる解釈は、極めて現代的な視点によるもので、このバレエは「ヒップホップ」ヴァージョンと銘打たれています。
ここで最も強調されているのは、ヒップホップの要素の中でも「ブレイクダンス」の部分でしょう。踊り手はフットワークを中心に、上半身を絶えず動かしながら、腕は違った動きをしなくてはいけないという、ある意味「超絶技巧」が求められるものです。キッチュな舞台装置と奇妙な音楽、何より人物たちのダンスは滑らかな連続性を持ちながらも、一つ一つの動きは唐突で、次の動きを予測することは不可能というなかなか刺激的で興味深いものです。 |
| |
107545
(DVD 10枚組)
\20000 |
イリ・キリアン・エディション
1.イリ・キリアンのシンフォニエッタ-シンフォニー
ニ長調-スタンピング・グラウンド 1984年/
2.子供と魔法 1986年/
3.兵士の物語 1989年/
4.輝夜姫 1994年/
5.ブラック&ホワイト 1996年
<落ち行く天使たち,6つのダンス,ノー・モア・プレイ,
スウィート・ドリーム,サラバンド,小さな死>/
6.ネザーランド・ダンス・シアター・セレブレイト・イリ・キリアン
2005年
<ベッラ・フィグラ,スリープレス,バースデイ>/
7.イリ・キリアンのカーメン 2006年
<カーメン,サイレント・クリエ,沈める寺>/
8.イリ・キリアンとネザーランド・バレエ・シアター
2008年
<スヴァデブカ,詩篇交響曲,トルソ>/
9.イリ・キリアン-忘れられた思い出
2011年ドン・ケント&クリスティアン・ドゥメイ=ルヴォウスキによる映像/
《ボーナス映像》
バレエ「蝋の翼」/オランダ・ダンス・シアター/
10.コレオグラファー・イリ・キリアン 1991年
ハンス・フルシャーによる映像 |
107546
(BD 10枚組)
\20000 |
収録時間:800分/音声:<DVD>ステレオ2.0/DD
5.1(輝夜姫) <BD>ステレオ2.0/dts-HDマスターオーディオ5.1(輝夜姫)/字幕:英,独(3),仏,蘭,独(2),英,独,仏,西,伊,蘭,日(9),英,独(10)/画面:16:9/4:3/REGION
All(Code:0)/<DVD>片面2層ディスク×9,片面単層ディスク×1/<BD>単層25GB×10
1080i High Definition
イリ・キリアン(イルジ・キリアンもしくはイジー・キリアンとも)は、1947年プラハ生まれのコレオグラフィーです。1967年英国ロイヤル・バレエ学校に入学し、その翌年ソリストとしてシュトゥットガルト・バレエに所属し、名振付師ジョン・クランコに師事しながら振付を始めます。1975年にネザーランド・ダンス・シアターの副芸術監督に就任、1978年には芸術監督に昇格し、以降50以上の作品をネザーランド・ダンス・シアターのために創作しています。
2009-2010年の団創立50周年シーズンを最後に30年以上在籍したネザーランド・ダンス・シアターから退きましたが、彼の業績は永遠に称えられることでしょう。
このBOXは、そんな彼の伝説的とも言える作品の数々を収録したもので、22の作品と、ドキュメンタリーを含んでいます。 |
| |

108130
(BD)
\6600 |
ニコラウス・アーノンクール:オペラ・コレクション/
ドン・ジョヴァンニ/コジ・ファン・トゥッテ
1.モーツァルト:歌劇「ドン・ジョヴァンニ」2幕/
2.モーツァルト:歌劇「コジ・ファン・トゥッテ」2幕 |
ニコラウス・アーノンクール(指揮)/
チューリヒ歌劇場管弦楽団&合唱団
〈ドン・ジョヴァンニ〉
ドン・ジョヴァンニ…ロドニー・ギルフリー(バリトン)/
レポレッド…ラースロー・ポルガール(バス)/
ドンナ・アンナ…イザベル・レイ(ソプラノ)/
ドンナ・エルヴィラ…チェチーリア・バルトリ(メゾ・ソプラノ)/
ドン・オッターヴィオ…ローベルト・サッカ(テノール)/
騎士長…マッティ・サルミネン(バス) 他
〈コジ・ファン・トゥッテ〉
フィオルディリージ…チェチーリア・バルトリ(メゾ・ソプラノ)/
ドラベッラ…リリアナ・ニキテアヌ(ソプラノ)/
フェランド…ローベルト・サッカ(テノール)/
グリエルモ…オリヴァー・ヴィドマー(バス・バリトン)/
ドン・アルフォンソ…カルロス・ショーソン(バス)
他/
ユルゲン・フリム(演出) |
〈ドン・ジョヴァンニ〉2001年 チューリヒ歌劇場
ライヴ収録/〈コジ・ファン・トゥッテ〉2000年
チューリヒ歌劇場 ライヴ収録/収録時間:192分(コジ・ファン・トゥッテ)+187分(ドン・ジョヴァンニ)/音声:イタリア語歌唱/ステレオ2.0/字幕:英,独.仏,日/画面:16:9/REGION
All(Code:0)/二層50GB 1080i High Definition
名指揮者ニコラウス・アーノンクールの85歳の誕生日を記念して製作されたこのBlu-rayには、彼が愛してやまないモーツァルト(1756-1791)の2つの歌劇が収録されています。
ドイツのベルリンの貴族の家系に生まれたアーノンクールは、ウィーン国立音楽院(現ウィーン国立音楽大学)でチェロを専攻し、卒業後はウィーン交響楽団のチェロ奏者として活躍しました。
入団の翌年1953年には、アリス夫人とともに「ウィーン・コンツェントゥス・ムジクス」を立ち上げ、その4年後に演奏会デビューを果たしています。その後の古楽界におけるアーノンクールの活躍はご存知の通りですが、一方彼はオペラ上演にも強い意欲を示し、1970年代にはチューリヒ歌劇場を本拠にして、数々のオペラに取り組み、とりわけモーツァルト作品については、名演出家ジャン=ピエール・ポネルと組んで素晴らしい成果を挙げてきたのです。
新進歌手の起用についても素晴らしい才覚があり、デビュー間もないチェチーリア・バルトリやドロテア・レシュマン、ローベルト・サッカ等の才能を磨き上げたことなども良く知られていることでしょう。
この映像に収録されているのはもう少し後の時代の演奏で、奇才ユルゲン・フリムが演出を担った2つの作品です。極めて厳格なテンポ設定に基づいた「ドン・ジョヴァンニ」。流麗さと深刻さをうまくヴェールに包んだ「コジ・ファン・トゥッテ」。アーノンクールの信念が間違いなく透けてみえるような主張の強い演奏ですが、なんとも魅力的なモーツァルトに仕上がっています。 |
 EURO ARTS(映像) EURO ARTS(映像)
|


20 59814
(Blu-ray)
\5000 →\4590 |
鬼才天才クルレンツィス
マーラー・チェンバーと行ったクララ音楽祭ライヴ映像!
ショスタコーヴィチ:チェロ協奏曲第1番作品107
ブリテン:シンフォニエッタ作品1
ショスタコーヴィチ:交響曲第1番作品10 |
マーラー・チェンバー・オーケストラ
テオドール・クルレンツィス(指揮)
スティーヴン・イッサーリス(チェロ) |


20 59818
(DVD)
\3000 →\2690 |
注目の奇才指揮者クルレンツィスによるショスタコーヴィチ、マーラー・チェンバーと行ったクララ音楽祭ライヴ映像!イッサーリスとの共演も必見!
収録:2013 年9 月6 日ブルージュ・コンセルトヘボウ、ベルギー(クララ国際音楽祭ライヴ)/監督:ヨハン・クレテンス
(Blu-ray)画面:1080i Full-HD 16:9、音声:PCM
ステレオ、リージョン:All、82分
(DVD)画面:NTSC 16:9、音声:PCM ステレオ、リージョン:All、82分
マーラー・チェンバー・オーケストラは1997
年にクラウディオ・アバドとグスタフ・マーラー・ユーゲント管弦楽団の旧メンバーによって結成されました。1998
年にダニエル・ハーディングを首席客演指揮者として迎え以後2011
年に桂冠指揮者に就任後も緊密な関係を結んでいます。さらにエサ=ペッカ・サロネン、ピエール・ブーレーズ、ケント・ナガノ、ジョン・エリオット・ガーディナー、ロジャー・ノリントン、ウラジミール・ユロフスキ、トゥガン・ソヒエフ、ダニエレ・ガッティらとも定期的に共演し世界的に高い評価を得ています。
この映像は、毎年ユニークな音楽祭としてヨーロッパで注目を集めているベルギーのクララ国際音楽祭ライヴ。指揮はギリシャ出身の奇才として注目を集めているテオドール・クルレンツィス。クルレンツィスは1972
年アテネ生まれ。サンクト・ペテルブルク音楽院で、多くの指揮者を世に送り出したイリヤ・ムーシンに師事。その後、作曲当時の楽器と慣習による演奏を目指すために、2004
年ムジカエテルナを創設。2010 年にはペルミ国立オペラ・バレエ劇場の芸術監督に就任。マーラー・チェンバーとは、メルニコフと共演したショスタコーヴィチのピアノ協奏曲(KKC5223)でも、その比類なき才能を発揮し、今最も世界から熱い視線を寄せられている指揮者の一人です。
ショスタコーヴィチのチェロ協奏曲はイッサーリスがソリストとして登場。個性的なイッサーリスとクルレンツィスの鬼気迫る指揮、そして楽曲の持つエキセントリックな顔が一体となった快演。ブリテンのシンフォニエッタは指揮者なしの演奏ですが、多彩な楽想を鮮やかに聴かせます。
そしてショスタコーヴィチの交響曲第1 番では、ムジカエテルナの活動同様に、作曲家メッセージを丹念嗅ぎ取るクルレンツィスの音楽作りと独特の指揮姿に圧倒される、ただならぬ気迫に満ちた演奏です。
|
新書館(映像)
|

DD14 0701
(DVD)
\4600+税 |
シルヴィ・ギエム&ラッセル・マリファント「PUSH」
<収録作品>
『Solo』
振付:ラッセル・マリファント/出演:シルヴィ・ギエム
『Two』
振付:ラッセル・マリファント/出演:シルヴィ・ギエム
『Shift 』
振付:ラッセル・マリファント/出演:ラッセル・マリファント
『Push』
振付:ラッセル・マリファント/出演:シルヴィ・ギエム、ラッセル・マリファント
封入特典:豪華ブックレット、コンテンツ特典:フォトギャラリー |
バレエの女王シルヴィ・ギエムの最新DVD が登場!
画面:NTSC、カラー 16:9、音声:PCM ステレオ,DD5.1c、62分、リージョン:2(日本国内向け)
ギエムの美しい腕が千変万化の表情を見せる傑作『TWO』がついに映像化。世界的なバレエダンサーで2015
年12 月に引退することが明らかになったシルヴィ・ギエム。英国コンテンポラリーダンスのスター、マリファントとバレエの女神ギエムの出会いから生まれた、刺激的でスタイリッシュな4作品『Solo』『Two』『Shift』『Push』を収録。 |
| |

DD13 0803
(DVD)
【再発売】
\3800+税 |
ディアナ・ヴィシニョーワ サンクトペテルブルクの新星
<収録作品>
・『カルメン』より
1994年ローザンヌ国際バレエコンクール
・『コッペリア』スワニルダのヴァリエーション
1994年ローザンヌ国際バレエコンクール
・『ドン・キホーテ』第一幕より
キトリ、ドルシネアのヴァリエーション
1995 年マリインスキー・バレエ公演
・『グラン・パ・クラシック』より 女性ヴァリエーション
ローザンヌ・コンクール金賞受賞を賛える
ワガノワ・バレエ・アカデミーの特別公演
ほか、レッスン風景やインタビュー |
出演:
ディアナ・ヴィシニョーワと
ワガノワ・バレエ・アカデミーの生徒たち
教師:
リュドミラ・コワリョーワ
ワジム・デスニツキー
ピアニスト:
タチアナ・クリコーワ
インナ・リスィアク
医師:アレクサンドル・メッシェーリン |
監修:ワガノワ・バレエ・アカデミー/演出・編集:セルゲイ・ニコライエンコ/企画:新書館/アルス東京/制作:ワガノワ・バレエ・アカデミー
日本語字幕:木下 久美、鈴木 Missy(1995年映像制作)
画面:NTSC、カラー 4:3、音声:モノラル/ドルビーデジタル、56分、リージョン:2(日本国内向け)、日本語字幕
スター誕生の瞬間!マリインスキーとABT を拠点に世界で活躍するヴィシニョーワのワガノワ・バレエ・アカデミー時代を捉えた貴重なドキュメンタリー。
ローザンヌ・コンクールでグランプリを獲得し、一躍注目された彼女の姿をカメラは追います。ローザンヌでの伝説の『カルメン』、特別公演の『グラン・パ・クラシック』、マリインスキーでの『ドン・キホーテ』……美しく可憐で、強い意志の力を秘めた若き舞姫の輝きが収録されています。
※ このDVD は2003 年にリリースされた「サンクトペテルブルクの新星 ヴィシニョーワ」(DD03-0706)
と同内容のものです。 |
| |

DD13 1106
(DVD)
【再発売】
\4600+税 |
シルヴィ・ギエム パリ・オペラ座の伝説
<収録作品(部分)>
『ライモンダ』よりリハーサル・舞台
音楽:アレクサンドル・グラズノフ
振付:ルドルフ・ヌレエフ
『イン・ザ・ミドル・サムホワット・エレヴェイテッド』より
音楽:トム・ウィレムス/振付:ウィリアム・フォーサイス
『4つの最後の歌』より
音楽:リヒャルト・シュトラウス/振付:ルディ・ファン・ダンツィヒ
『ルナ』より
音楽:ヨハン・セバスチャン・バッハ/振付:モーリス・ベジャール
『シンデレラ』よりリハーサル
音楽:セルゲイ・プロコフィエフ/振付:ルドルフ・ヌレエフ |
出演:シルヴィ・ギエム
ローラン・イレール
シャルル・ジュド
ウィリアム・フォーサイス
ほか パリ・オペラ座バレエ |
製作:アラン・ブラーニュ/撮影:アンドレ・S・ラバルテ/撮影:ジャック・オードラン/クリストフ・アダ
画面:NTSC、カラー 4:3、音声:モノラル/ドルビーデジタル、53分、リージョン:2(日本国内向け)、日本語字幕
19 歳でパリ・オペラ座バレエの最年少エトワールとなった、シルヴィ・ギエム。
いまや伝説となったギエムの、オペラ座でのシーズンを追ったドキュメンタリー作品。
華やかなガルニエ宮での『ライモンダ』の舞台映像に対比するように、
フォーサイスの新作や、ヌレエフ版『シンデレラ』など、厳しいリハーサルの日々が描かれます。
つねに進化しつづける天才ダンサーの肖像が描き出されています。
※ こちらは1991 年にVHS とLD で発売されていた「美しき妖精 シルヴィ・ギエムの肖像」と同じ映像です。 |
|
|
![]()