≪第84号アリアCD新譜紹介コーナー≫
その1 2015/9/22〜
マイナー・レーベル新譜
歴史的録音・旧録音
メジャー・レーベル
国内盤
映像 |
9/25(金)紹介新譜
マイナー・レーベル新譜
.
 COLLEGIUM COLLEGIUM
|
|
|
ジョン・ラッターの新作・新録音
福島に捧げる「永遠の花」〜ギフト・オヴ・ライフ
ジョン・ラッター:
ギフト・オヴ・ライフ(生命の贈り物)/
神よ、あなたの公平を王に/永遠の花/審問/
詩篇第150篇/キリストは明けの明星/
楽園にある全ての鐘が/喜びと歌 |
ジョン・ラッター(指揮)
ケンブリッジ・シンガーズ
ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 |
☆ジョン・ラッター待望の新作! 2015年新録音!
☆福島の震災被害者に捧げる「永遠の花」も収録!
イギリスを代表する英国合唱の巨匠ジョン・ラッター(1945−)。ラッターの自主レーベル、Collegium(コレギウム)より、待望の自作新録音アルバムが登場!
子供のためのミサ(COLCD 129)以来10年ぶりとなる大作、6つのカンティクルとクリエイション
《ギフト・オヴ・ライフ(生命の贈り物)》と、7つの宗教的小品を収録。
なかでも注目は、2011年の東日本大震災、津波、そして福島原発事故の被災者のために書かれた「永遠の花(A
flower remembered)」。
「永遠の花」は2014年3月に京都で世界初演、その後楽譜も出版され、アマチュアを含む様々な合唱団で歌われています。
ジョン・ラッター自身の指揮によって響く、美しいハーモニーと印象的なメロディー。
合唱関係者必聴必携の新譜です!
※録音:2015年7月15日−16日、フェアフィールド・ホール(クロイドン、イギリス)
|
<メジャー・レーベル>
 DHM DHM
|

8887502713-2
\2700→\2490 |
ウエルガス・アンサンブル/「不幸が私を襲い」の謎
1) 作者不詳:『おお、愛の神よ、あなたは何をするのか』
2) アグリコラ:ミサ曲『不幸が私を襲い』〜サンクトゥス
3) マルクール:ミサ曲『不幸が私を襲い』〜
生まれからして、私は不幸者(2声、3声のための)
4) オブレヒト:ミサ曲『不幸が私を襲い』〜
サンクトゥス
5) 作者不詳:ミサ曲『不幸が私を襲い』〜
生まれからして、私は不幸者(3声のための)』
6) アグリコラ:ミサ曲『不幸が私を襲い』〜アニュス・デイ
7) オケゲム:『おお、愛の神よ、あなたは何をするのか』
8) カベソン:第4旋法によるティエント『不幸が私を襲い』
9) ジョスカン・デ・プレ:ミサ曲『不幸が私を襲い』〜
アニュス・デイ(2声, 4声, 5声, 6声)《演奏》 |
パウル・ファン・ネーヴェル(指揮)
ウエルガス・アンサンブル |
パウル・ファ・ネーヴェルとウエルガス・アンサンブルによる新録音です。
ルネッサンス時代、ひとつの題材を多くの作曲家が作るということは当たり前であり、基本のメロディさえ同じ場合も多数。そこで別声部に手を加え、その作曲者の独自性が発揮されていました。
今作で取り上げられている『不幸が私を襲い』のもとになったものは、1450年の頃のシャンソンと言われています。
ルネッサンス時代の名作曲が残した、『不幸が私を襲い』の題材に関連した作品が収録され、それぞれの作曲家の独創的な響きを発見しようという企画です。
バーゼル・スコラ・カントルムで学んだパウル・ファン・ネーヴェルは、調査・研究も含めてルネッサンス・ポリフォニーの権威であります。手兵のウエルガス・アンサンブルとともに、すばらしい演奏による成果を見せてくれるアルバムです。
《録音》2014年6月、フランス、エコユー
旧譜から
ファン・ネーヴェル&ウエルガス・アンサンブル
音楽芸術の第5元素
HMG 501922 \2500
クリスマス前後、こればっかりかけていた。
古楽系アルバムというのは、ちょっと聴くとどれも同じように思える。ただ、非常に微妙なニュアンスで好き嫌いが分かれる。その違いを説明するのはとても難しい。パワフルで情熱的なシクスティーンがいいときもあれば、清潔で存在感あふれるタリス・スコラーズがいいときもある。もちろんまったく無名の演奏団体のものがバッチリはまることもある。しかし指揮者やピアニスト以上に、実際に聴いてみないとわからない要素が大きい。ちょっとした強弱のアクセントがいやに鼻についたり、逆にのっぺり聴こえたりして、もう本当に申し訳ないくらい身勝手な好悪が噴出する。
今回の場合、クリスマス気分で聴くためにいくつかの宗教音楽系新譜を集めたが、バッチリはまったのはこの1枚だけだった。
ウェルガス・アンサンブルはどちらかというと「学究的」要素が強い団体で、「高度で精緻なアンサンブルによって聴く人を感動に至らしめる」というタイプの団体ではない。
それよりは作曲家やその周辺の雰囲気をリアルに再現して、極めて繊細に聴く人の心に忍び込んでくる。
「歌」よりも「空気」を感じさせて聴く人の心を虜にしてくれるのである。
このアルバムもとっても慎み深く控えめな音楽。・・・でもたまにはクリスマスくらい敬虔な気分で迎えたいと思う心境には、なんとなくそれがはまった。
|

仏HM
HMG 501922
\2500
海外在庫限り |
ネーヴェル&ウエルガス・アンサンブル
音楽芸術の第5元素〜The quintessence of
a musical art~
(1)ラッスス(1532-1594):ミサ曲「すべての悲しみよ」
(2)トマス・アシュウェル(1478頃-1513以降):ミサ「アヴェ・マリア」
(3)パレストリーナ(1525頃-1594):ミサ「ウト・レ・ミ・ファ・ソ・ラ」 |
パウル・ファン・ネーヴェル(指)
ウエルガス・アンサンブル |
ウエルガス・アンサンブルによる声の饗宴
録音:2005 年11 月
このCDのタイトルは、録音が行われた、リスボンにある水の博物館に由来している。
第五の元素とは、気・火・地・水の4要素のほかにあると考えられた元素のこと。この場所自体がもつただならぬ雰囲気、そしてその音響は、これらの作品が普遍的で時空を超えた内容(=「第五の」要素)をもっているということを私たちに示している。
厳格な対位法を用いて書かれたパレストリーナのミサ曲、イングランドが生んだ後期ゴシック様式の作品をのこしたアシュウェルのミサ曲、そして多声音楽爛熟期のラッススのミサ曲。これらの作品が、生きたものとして聴く者にせまってくる。
|
|
|
| |

8887514103-2
\2700→\2490 |
カペラ・デ・ラ・トーレ/チャコーナ
1) トロンボンチーノ:『辛抱強くあなたに従う』,
2) モンテヴェルディ:『西風がもどり』,
3) ファルコニエーリ:『チャコーナ』,
4) ミシェル・ゴダール:『Dreaming Dancers』,
5) オルティス:『Recercada Passamezzo』,
6) 作者不詳:『Passacaglia della vita』,
7) 作者不詳:『Un sarao de la ciaconna』
,
8)マネッリ:『Accesso mi cuore』,
9) カロサ:『Alta regina』,
10) フォークト:『Follia leggera』,
11) パラッシオ:『Non quiero ser monja』,
12) ミシェル・ゴダール:『Folie de 1000
lumieres』,
13) 作者不詳:『Guardame las vacas』,
14) オルティス:『Recercada Romanesca』,
15) パラッシオ:『Muchos van deamor heridos』,
16) ミシェル・ゴダール:『Song for Urte』,
17) ファルコニエーリ:『Folia echa para
mi Senora Dona Tarolilla de Carallenos』,
18) ファルコニエーリ:『Aria sopra la Ciaconna』,
19) パラッシオ:『Rodrigo Martinez』,
20) ステフィン・メリット:『The Book of
Love』 |
カペラ・デ・ラ・トーレ
(ルネッサンス・アンサンブル) |
『カペラ・デ・ラ・トーレ』は、ドイツを中心に今、宗教音楽のから世俗的作品まで「最も優れた解釈」と高い評価を受けているルネッサンス・アンサンブル。メンバーそれぞれが、その時代の演奏のスペシャリスト、独奏者でもあります。
当アルバムでは、イタリア・ルネッサンス時代のチャコーナ(シャコンヌ)の作品を収録。定型のバスの音型の上に変奏曲のように変化していく音楽を、実践的に研究し、演奏していきます。
途中には名セルパン奏者ミシェル・ゴダールの書いた作品や、最後にはポップ・ミュジーシャンのステフィン・メリットの曲も入れてしまうのも、決して枠にはまらないこのグループの粋なところでしょう。
《録音》2014年11月、ドイツ。バーデン=バーデン、南西ドイツ放送、ハンス=ロスバウト・スタジオ

ここで彼らの演奏をいくつか試聴できます!
http://www.capella-de-la-torre.de/de/cds.html
カペラ・デ・ラ・トーレ前作
なぜか代理店からの案内では記載されないソプラノのセシル・ケンペナースの歌声が天国的 |
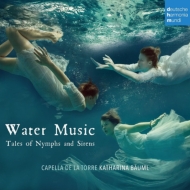
8887506200-2
\2700→\2490 |
カペラ・デ・ラ・トーレ / 水の音楽〜妖精とセイレーンの物語
1) M・プレトリウス:Philou,
2) A・ヴィラールト:Passa la nave,
3) F・カローゾ:Laura suave,
4) ビクトリア:Ave maris stella,
5) ジョスカン・デ・プレ:In exitu Israel,
6) T・モーリー:Besides a Fountain,
7) A・ホルボーン:The Fruit of Love,
8) L・マレンツィオ:Ad una fresca riva,
9) A・ホルボーン:The Funerals,
10) ジョスカン・デ・プレ:Nymphes nappes
/ Circumdederunt me,
11) L・アレグリ:Quinto ballo detto le
ninfe di Senna,
12) B・モスキーニ:Ecco, signor il Tebro,
13) O・ヴェッキ:Gitene ninfe,
14) オルランド・ディ・ラッソ:Super flumina
Babylonis,
15) G・ギッツォーロ:Canto di Sirene,
16) G・ギッツォーロ:Riposta di Nettuno,
17) 作者不詳:Les nymphes de la Grenouillere,
18) R・ジョンソン:Full Fathom Five Thy
Father Lies,
19) ビクトリア:Versa est in luctum,
20) J・アルカデルト:l bianco e dolce cigno,
21) J・フォクト:Canto,
22) O・ギボンズ:The Silver Swan,
23) L・マレンツィオ:Chi dal delfino, |
カペラ・デ・ラ・トーレ(ルネッサンス・アンサンブル)
セシル・ケンペナース(So) |
『カペラ・デ・ラ・トーレ』は、ドイツを中心に今、宗教音楽のから世俗的作品まで「最も優れた解釈」と高い評価を受けているルネッサンス・アンサンブル。メンバーそれぞれが、その時代の演奏のスペシャリスト、独奏者でもあります。
ドイツ・ハルモニア・ムンディからの第3弾となる当アルバムでは、様々なヨーロッパのルネッサンス作品の中から、水、妖精、ギリシャ神話のセイレーン(美しい歌声で近くを通る船人を誘い寄せて難破させたという半女半鳥の海の精)に関したものが選ばれています。民族的要素、厳かな宮廷音楽が織り交ぜられた、ルネッサンス時代の音楽に引き込まれるはずです。
【録音】2014年9月, ドイツ、アウハウゼン修道院教会(デジタル:
セッション)
|
|
<国内盤>
<映像>

9/24(木)紹介新譜
マイナー・レーベル新譜
 ECM ECM
|

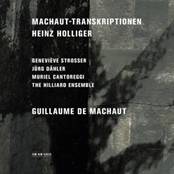
476 5121
\2500→\2290 |
ヒリヤード・アンサンブル
《ハインツ・ホリガー:マショー・トランスクリプション》
4人歌手と3台のヴィオラのためのユニークな編曲版
マショー(ハンツ・ホリガー編;4人歌手と3台のヴィオラのための):
1) バラードIV(Biaute qui toutes autre
pere),
2) バラードIV(3台のヴァイオラのための),
3) バラードXXVI(Donnez, Seigneur),
4) バラードXXXVI(3台のヴァイオラのための),
5) 二重ホケット(ダヴィデのホケトゥス),
6) 二重ホケット(ダヴィデのホケトゥスの後に),
7) レイVII(4人の歌手のための),
8) 3声のインヴェンティオと、3台のヴァイオラのためのPlor-/Prol-/Oratio,
9) 哀歌(「運命の癒薬」による)と、
4人歌手と3台のヴィオラのためのエピローグ |
ヒリヤード・アンサンブル,
ジュヌヴィエーヴ・シュトロッセ(ヴィオラ),
イェルク・デーラー(ヴィオラ),
ミュリエル・カントレッギ(ヴィオラ) |
10年を越える年月をかけて、ハインツ・ホリガーが創り上げた「マショー・トランスクリプション」は、14世紀に生きたギョーム・ド・マショーの複雑で神秘的な音楽を、3台のヴィオラ、4人の歌手、もしくはその両方が演奏するというものです。
この試みは極めて有意義なものであり、半音階的な主題をヴィオラで演奏することで、この時代の音楽がどれほど先進的なものであったか(現代においても)を再認識することになるのです。
ホリガーは2001年にマショーの作品をヴィオラ用に編曲してから、このユニークな世界に魅せられ、様々な試みを施しつつ編曲法を拡大してきたと語っており、原曲を忠実に移し替えたもの、自由な即興を加えたものなど、原曲のテクスチャーを残しながらも、ホリガー独自の音も聴きとれるものとなっています。
惜しまれつつ解散したヒリヤード・アンサンブルの比類なき演奏です。
《録音》2010年11月, チューリヒ、DRSスタジオ(デジタル:セッション) |
| . |

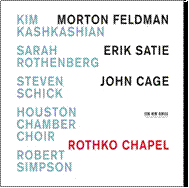
481 1796
\2500→\2290 |
モートン・フェルドマン、サティ、ケージによる作品の相互作用
アメリカ、ヒューストンの超教派の礼拝堂《ロスコ・チャペル》
1) モートン・フェルドマン:ロスコ・チャペル,
2) エリック・サティ:グノシェンヌ第4番,
3) ジョン・ケージ:Four,
4) サティ:オジーヴ第1番,
5) ケージ:イヤー・フォー・イヤー,
6) サティ:オジーヴ第2番,
7) サティ:グノシェンヌ第1番,
8) ケージ:ファイヴ,
9) サティ:グノシェンヌ第3番,
10) ケージ:ある風景の中で |
キム・カシュカシャン(ヴィオラ:1),
サラ・ローゼンバーグ(ピアノ, チェレスタ:1,2,4,6,7,9,10),
スティーヴン・シック(パーカッション:1),
ソンヤ・ブルザウスカス(メゾ・ソプラノ:1),
ローレン・スノウファー(ソプラノ:1),
ヒューストン室内合唱団
ロバート・シンプソン(指揮:1,3,5,8) |
1971年、アメリカ、ヒューストンに完成した「ロスコ・チャペル」。ここは超教派の礼拝堂で、あらゆる人々の瞑想と礼拝の場として開かれています。
この壁面にはアメリカの抽象表現主義の画家、マーク・ロスコの大きな壁画が飾られ「静けさ、静寂、熟考」の雰囲気をかもし出しています。
このアルバムは、その「ロスコ・チャペル」の存在自体を音楽で描くものであり、ロスコの親友であったモートン・フェルドマン(彼の音楽も、ロスコの絵画と同じように瞑想にふさわしい要素を備えている)の作品を冒頭に置き、音が自由に飛躍するジョン・ケージの作品と、「音と瞑想」の関係性を示すには最もふさわしいエリック・サティの一連の作品を組み合わせ、相互に影響を与え合った芸術家たちが創り上げた世界を再構築しています。
キム・カシュカシャンの深いヴィオラの音色に導かれ、永遠の音の迷宮の旅が始まります。
《録音》2012年5月, 2013年2月, ヒューストン
  
|
| |

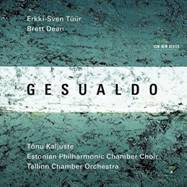
481 1800
\2500→\2290 |
ジェズアルドに魅せられた3人の現代作曲家たちによるオマージュ
《ジェズアルド》
1) ジェズアルド:悲しや、我は死す(カリユステによる弦楽合奏版),
2) ブレット・ディーン(1961-):カルロ,
3) ジェズアルド:ああ 祝福された 十字架よ
(エリッキ=スヴェン・トゥールによる弦楽合奏版),
4) エリッキ=スヴェン・トゥール(1959-):
L’ombra della croce(マンフレート・アイヒャーに献呈),
5) エリッキ=スヴェン・トゥール:プサルムディー |
トヌ・カリユステ(指揮)
エストニア・フィルハーモニー室内合唱団,
タリン室内管弦楽団 |
あまりにも罪深く、また波乱万丈の生涯を送った作曲家カルロ・ジェズアルド。その作風もまた当時の音楽とは全く乖離したものであり、彼が死して400年を経た今でも、謎めいた音楽は聴き手の思考を混乱させるとともに、芸術家たちに強い影響を及ぼしています。
このアルバムも、そんなジェズアルドに魅せられた3人の現代作曲家たちによるオマージュであり、ジェズアルドのある意味歪んだ「愛と死」の概念を丹念に写し取りながら、現代的な音楽へと変貌させた作品が収録されています。
もともとのマドリガルから引用されたフレーズが、拡大、変容され、新たな命を得ていく過程には、確かに多くの喜びと絶望が垣間見えます。
トゥールの作品の一つは、レーベルの創設者にしてプロデューサーであるマンフレート・アイヒャーに献呈されていることからもわかるとおり、時代とジャンルの超越を試みるECMらしい1枚です。
《録音》2014年2月, タリン・メソジスト教会 |
 MD+G MD+G
|


901 19136
(SACD Hybrid)
\3100→\2790 |
切迫した雰囲気と神秘さを小編成ながら再現
《小オーケストラ編曲によるベルク作品集》
ベルク:
1) 3つの管弦楽曲
(ジョン・リアによる、小オーケストラのための編曲版)
2)「ヴォツェック」から3つの断章
(ジョン・リアによる、小オーケストラのための編曲版)
3) ヴァイオリン協奏曲
(アンドレアス・N・タルクマンによる、
独奏ヴァイオリンと室内アンサンブルのための編曲版) |
ベネディクト・トラン(ソプラノ)、
ラヘル・クンツ(ヴァイオリン)
ピエール=アラン・モノ(指揮)
ヴィンタートゥール・ムジークコレギウム |
カナダのアレンジャー、作曲家ジョン・リア(1944-)は、このベルクの「ヴォツェック」の室内楽版の編曲でセンセーショナルな成功を収めました。
これは複雑に入り組んだ原曲のスコアを、すっきりと纏め上げながらも、微妙な響きの陰影は損なわれることのないというもので、「ヴィンタートゥール・ムジークコレギウム」の妙技が緊張感に満ちた音楽を詳細に描いていきます。
この緊迫した雰囲気は「3つの管弦楽曲」でも変わることなく神秘的で、時には崩壊寸前の響きを丁寧になぞっていきます。
タルクマンの編曲による「ヴァイオリン協奏曲」も特色ある響きが面白く、あのシェーンベルクの「私的演奏協会」で演奏された際、ハーモニウムに置き換えられた管のパートはアコーディオンに委ねられるなど、様々な工夫がなされています。凝縮した世界を垣間見ることができるアルバムです。
Hybrid-SACD仕様(SACD-Stereo, SACD-Surround,
CD-Stereo) |
| |

903 19146
(SACD Hybrid)
\3100 |
《バスーン・アンサンブルによるゴルトベルク》
J.S.バッハ:ゴルトベルク変奏曲 BWV.998
(ヘンリク・ラビエンによる、9人のバスーン奏者のための編曲版) |
バスーン・コンソート・フランクフルト
[Henrik Rabien,
Lena Nagai,
Felix Eberle,
Charlotte Sutthoff,
Thomas Gkesios,
Leon Kranich,
Merve Selcuk,
Kathrin Mayer,
Stephan Krings] |
ゴルトベルクの編曲版はここまで来た!
J.S.バッハの最高傑作「ゴルトベルク変奏曲」は、もともとは鍵盤楽器のための作品であり、基本的にはチェンバロもしくはモダン・ピアノで演奏されます。しかしあまりにも魅力的な作品であるため、これまでにも弦楽三重奏版やギターソロ、もしくは二重奏版、2台ピアノ版、オルガン版、木管四重奏版など多彩な編曲が施され、奏者、聴き手の双方を楽しませていることはご存知の通りでしょう。
そんな「ゴルトベルク」に今回挑むのは、ファゴット8本とコントラファゴット1本という面白い編成です。
ここで演奏しているバスーン・コンソートのメンバーであるヘンリク・ラビエンの編曲は、全体を1オクターブ低くすることで、原曲の調性(ト長調/ト短調)を保つことができ、またコントラファゴットを用いることで、一層深淵な響きを投入した上で、数々の華麗な変奏部分を完璧に演奏するというもの。
完璧なアンサンブルとテクニックが原曲を越えた楽しさを感じさせてくれます。ファゴットのつややかな響きを余すことなく伝えるSACDハイブリッド盤による優秀録音です。
Hybrid-SACD仕様(SACD-Stereo, SACD-Surround,
CD-Stereo) |
| |

905 19156
(SACD Hybrid)
\3100 |
《フェデリコ・モレノ・トローバ:ギター作品集》
フェデリコ・モレノ・トローバ:
1) プレリュード, 2) マドロノス, 3) ノットゥルノ,
4) 性格的小品, 5) スペイン城,
6) 7つのマドリードの門 |
フランク・ブンガルテン(ギター) |
ギタリスト、ブンガルテンの洞察力に溢れた演奏
スペインの指揮者、作曲家モレノ・トローバは現在ギター音楽の作曲家として知られていますが、本来はサルスエラの普及に尽力した「オペラ作曲家」でした。
もともと彼自身はギターが演奏できたわけではなかったようで、彼がギターの作品を書くようになったのは、1912年に偉大なるギタリスト、アンドレス・セゴビアと出会ったことがきっかけでした。
そのセゴビアの依頼により(もちろん技巧的な手助けも含めて)いくつものギター作品が生まれたことは、あまり知られていません。
彼のギター曲のほとんどは短いもので、調性なども逸脱していませんが、その作品は情熱的なスペインのリズムに裏打ちされた多彩なものであり、ギタリストのテクニックも存分に披露できるという見事なものばかり。
ここではフランク・ブンガルテンの洞察力に溢れた演奏が、これらの作品の魅力を余すことなく引き出しています。
Hybrid-SACD仕様(SACD-Stereo, SACD-Surround,
CD-Stereo) |
| |

949 19196
(SACD Hybrid)
\3100 |
《レーガー:オルガン作品集》
マックス・レーガー:
『われらが神は堅き砦』によるコラール幻想曲Op.27/
『30の小コラール前奏曲 Op.135a』より
「暁の星のいかに美しきかな」
「最愛のイエスよ 我らここに集いて」
「ほめよ主を 強き栄えの君を」
「深き困窮より,われ汝に呼ばわる」
「主イエス・キリストよ われらをかえりみたまえ」
「目覚めよと、われらに呼ばわる物見らの声」
「喜べ、わが魂よ」「ああ、汝の恩寵もて」
「私に千の舌があったなら」
「エルサレムよ、かたく建てられし町よ」
「おお、血と涙にまみれた御頭よ」
「こぞりて主を頌め」/
『序奏、パッサカリアとフーガ ホ短調 Op.
127』 |
クリストフ・シェーナー(ハンブルク、聖ミヒャエル教会のオルガン) |
レーガーにも縁のあるハンブルク、聖ミヒャエル教会のオルガンで奏でる
2016年に没後100周年を迎えるマックス・レーガーの代表的なオルガン作品集です。
バッハ、ベートーヴェン、ブラームスと言ったドイツ音楽の伝統を継承しつつ、ロマン派特有の拡大された和声法と、厳格な対位法を用いた彼の作品には、リストのオルガン曲のような派手な響きはないものの、深淵なる思索と宗教的法悦に満ち溢れています。
このアルバムには名コラール「われらが神は堅き砦」をモティーフにした初期の大作「コラール幻想曲」を中心に、晩年の名作「序奏、パッサカリアとフーガ」、シンプルで短い曲の中に限りない可能性が秘められた「30の小コラール前奏曲」の3作品が収録されていて、これらはレーガーの宗教的指向を知るにはうってつけの1枚となっています。
この演奏で用いられたのは、レーガーにも縁のある、北ドイツで「最も美しいバロック建築」と言われるミヒャエル教会の壮麗なオルガンで、美しい響きを存分に捉えた高音質の録音も特筆すべきでしょう。
Hybrid-SACD仕様(SACD-Stereo, SACD-Surround,
CD-Stereo) |
| |

301 3142
\2400 |
《ハイドン、モーツァルト:オーボエ四重奏曲》
ハイドン(フランツ・ヨーゼフ・ロジナック編):
オーボエ四重奏曲ヘ長調
(原曲:弦楽四重奏曲第48番ヘ長調Op.50-5)
オーボエ四重奏曲ハ長調
(原曲:弦楽四重奏曲第63番ハ長調Op.65-1)
モーツァルト:オーボエ四重奏曲ヘ長調K.370(368b) |
コンソルティウム・クラシクム
[Gernot Schmalfu, (Ob),
Kurt Guntner(Vn),
Helmut Nicolai(Va),
Helmar Stiehler(Vc)] |
18世紀のオーボエ奏者ロジナックによる編曲版
フルステンベルク管弦楽団のオーボエ奏者として活躍したフランツ・ヨーゼフ・ロジナック(1748-1823)は、作曲家としても多くの作品を宮廷のために書いていました。
当時の宮廷では音楽を演奏する機会が数多く、彼は自作だけでなく他の音楽家たちの作品を、自らが演奏するための「オーボエ四重奏」に編曲し、原曲とは違った魅力のある作品へと生まれ変わらせたのです。
もちろん第1ヴァイオリンのパートをそのままオーボエに移し替えるのではなく、第2ヴァイオリンのパートも含めて考慮し、オーボエが最も効果的に聞こえる形となっているのが興味深いところです。
このアルバムでは、モーツァルトによる「オーボエ四重奏曲」をカップリングすることで、ロジナックの編曲の素晴らしさが一層伝わるものとなっています。コンソルティウム・クラシクムの名演奏の中からの再発売となります。 |
<メジャー・レーベル>
 イタリアDECCA イタリアDECCA
|


PO 482 3130
(21CD)
\9600→\8990 |
アンドラーシュ・シフ〜プレイズ・モーツァルト
モーツァルト:
ピアノ協奏曲全集、
ピアノソナタ全集、
ロンド K.382,386,485,511、
幻想曲 K.475、3台のピアノの協奏曲
ピアノ5重奏曲 K.452、
静けさがほほえみながら K.152、
どうしてあなたを忘れられようか K.505、
きらきら星変奏曲 K.265、アダージョ K.356,K.540、
我が愚かなペーベル`主題による10の変奏曲
、
メヌエット K.355
小さなジーグ K.574、
ヴァイオリン.・ソナタ K.379,304,454、K.521,497、
ロンドK.485,511、ピアノ4重奏曲 K.478,493、
自動オルガンのためのアンダンテ ヘ長調
K.616、
メヌエット K.355、アンダンテと5つの変奏曲 K.501、
アダージョとアレグロ K.594、幻想曲 K.475,608、
ピアノ・ソナタ K.304,379,454,545,571、
ヴァイオリンとピアノの6つの変奏曲
|
アンドラーシュ・シフ(p)、
チェチーリア・バルトリ、
ペーター・シュライヤー、
ダニエル・バレンボイム、
エーリヒ・ホーバルト、
ハインツ・ホリガー、
イギリス室内管弦楽団、
ウィーン室内管弦楽団、
シャンドール・ヴェーグ |
 SONY SONY
|

8887512973-2
\2700→\2490 |
ヴェラール・サバドゥス/
カルダーラ:カストラートのためのアリア集
アントニオ・カルダーラ:
歌劇『Osminda e Fileno』よりシンフォニア,
歌劇『Le Lodi d'Augusto』より「Num che
sei」「Merta il propizio」,
歌劇『セデーチア』より
「O eletto delsignor」「Ahi! Come quella
un tempo citta」,
カンタータ『Il giuoco del quadriglio』より
「(Introduzione)・・・Ah se toccasse
a me」,
カンタータ『ニゲッラとティルシ』より
「(Introduzione)・・・Questo e il prato」,
歌劇『Le profezie evangeliche di Isaia』より
「Reggimi, o tu, che sola」,
歌劇『Il nome piu glorioso』より
「Giunse appena quel bel nome」,
『チェロのための室内協奏曲』,
歌劇『セデーチア』より
「Ti sento, Iddioio, ti sento」「Esca
da L'Aquilon」,
歌劇『LeLodi d'Augusto』より「Vive l'immagine
vostra」,
歌劇『David Umiliato』より「ti daro laude,
iddio」《演奏》 |
ヴェラール・サバドゥス(カウンター・テナー),
ヌオーヴォ・アスペット・ブレーメン(ピリオド楽器アンサンブル) |
そのルックスと驚異のヴォイスは世界中を席巻している、1986年ルーマニア生まれの若手カウンター・テナー、ヴェラール・バルナ=サバドゥス。
昨年のグルックとサッキーニのカストラート・アリア集に続き、ソニー・クラシカルへの2枚目のソロ・アルバムが早くも登場です。
今回のアルバムでは、ヴィヴァルディとほぼ同時期に活躍したアントニオ・カルダーラ(1670-1736)が作曲したアリア集。
カルダーラの書いたカストラートのためのアリアには、難関なコロラトゥーラがちりばめられていますが、サバドゥスは見事なテクニックと美声、多彩な表情を表現しており、この至難なアリアを個性豊かに歌い上げています。
《録音》2015年7月, ケルン、オーケストラ・リハーサル・センター
|
| |
8887511574-2
\2700 |
ブレッヒシャーデン/金管アンサンブル「ブレッヒシャーデン」のクリスマス
「Sleigh Ride」「Last Christmas」「O Tannenbaum」
「Stille Nacht」「Let it Snow」
「Es wird schon glei dumpa」「Winter Wonderland」
「Das OrffscheKonzert」「Irish Blessing」
「Feliz Navidad」「The Christmas Song」
「Rudolph the Red-Nosed Reindeer」
「Muttertag」「Andachtsjodler」「Jingle
Bells」
「White Christmas」「Silent Night」 |
ブレッヒシャーデン(金管アンサンブル) |
金管アンサンブル「ブレッヒシャーデン」は、ミュンヘン・フィルの金管メンバーを中心として1985年に結成されました。
伝統的なルネッサンスから現代までのクラシック音楽だけでなく、ポピュラー、ロックまで演奏してしまう器用さが大ウケ。1999年と2002年には、ドイツのグラミー賞といわれるエコー賞を受賞。さらにバイエルン文化賞も受賞している名誉あるブラス・アンサンブルです。
創立30周年を迎えた彼らのソニー・クラシカルへの最新録音は、クリスマスの名曲ばかりを厳選。彼らの厳かなものからポップな編曲まで、すばらしいテクニックによって様々に楽しませてくれます。
《録音》2015年、ドイツ、アイヒェナウ、ドリアン・グレイ・スタジオ |
 DHM DHM
|
8887505144-2
\2700 |
ムジカ・フィアータ/ヨハン・ヘルマン・シャイン:聖歌集『シオンのシンバル』
ヨハン・ヘルマン・シャイン:
聖歌集『シオンのシンバル』より
「来たりて主を喜び歌わん」
「いと高きにある神にのみ栄光あれ」
「言葉は肉体となり」「羊飼い達よ、汝ら見たものを語れ」
「神よ、その慈しみをもってわたしを憐れんでください」
「エフライムは私の大切な息子なのだろうか」
「おお、主イエス・キリストよ」
「行きます、最後までおこなうことを」
「アレルヤ!主をおそれ、その道を歩むものは」
「アレルヤ!主に感謝せよ」
「いったいどこにあなたの恋人は行ってしまったのか?」
「わたしはうれしかった」「天主はその御一人子を」
「誰を探しているのですか、マグダラのマリアよ」/
「5声のカンツォン イ短調 :コロラリウム」 |
ローランド・ウィルソン(指揮)、
ムジカ・フィアータ・ケルン,
ラ・シャペル・デュカーレ |
ヨハン・ヘルマン・シャイン(1586.1630)は、ドレスデン宮廷礼拝堂少年聖歌隊員として音楽教育を受け、1607年からライプツィヒ大学で学びました。
1615年からヴァイマール宮廷楽長、1616〜1630年には聖トマス教会カントールを務めています。シュッツとも親交が深く、宗教的及び世俗的声楽曲の領域で本領を発揮し、イタリア様式をルター派の教会音楽に伝統的な要素を融合させた重要な作曲家です。
シャインの重要な作品で「音楽の宴」「イスラエルの泉」がありますが、この「シオンのシンバル」は、降誕、葬礼、婚礼、復活祭など様々な場面での聖歌を集めた作品です。
近年ではこのドイツ宗教的作品の研究と録音を集中的におこなっているローランド・ウィルソンとムジカ・フィアータとラ・シャペル・ドゥカーレによる演奏で、演奏法や解釈をくまなく研究し、当時の質素で敬虔な祈りを反映し、感情を抑えながらも、気品に満ちた演奏となっています。《録音》2014年11月、ライプツィヒ、ベタニエン教会 |
| |

8887515882-2
\2700→\2490 |
ラウテン・カンパニー/マルコ・ポーロの歩んだ道
ピエール・ファレーズ:
『フェッラレーゼのパヴァーヌとガリアルド』
『サルタレッロ』,
カッチーニ:『天にもかほどの星はなく』,
ロッシ:『Das vereiste Paar』,
ヨアン・アンブロシオ・ダルツァ:『Kalata
alla spagnola』,
Trad:『Schlacht - Schach / Horse Race』,
マッツォッキ:『おろかな心よ』,
メールラ:『Cin / No,no ch'io non mi fido』,
Trad:『中国のランタン』,
フランチェスコ・トゥリーニ:『カンツォン』,
Trad:『瑶族の舞曲』,
モンテヴェルディ:『かくも甘い苦悩を』,
カステッロ:『ソナタ』,
モンテヴェルディ:『何と快い今日のそよ風』『ただあなたを見つめ』,
Trad:『龍の舞』,
カール・ヴァレンティン:『中国のカプレット』 |
ラウテン・カンパニー(ピリオド楽器アンサンブル),
ウー・ウェイ(中国笙),
エヴァ・マッテス(語り、歌) |
「東方見聞録」で有名なマルコ・ポーロ。彼は24年間にわたってアジア各地を訪れましたが、その途中、中国に17年間滞在しました。「東方見聞録」には中国の音楽についてもその中に書かれており、その後ヨーロッパに伝えられました。
ラウテン・カンパニー率いるリュート奏者ヴォルフガング・カチュナーは、このアルバムで中国の音楽と初期バロック音楽を融合させています。
これまでフィリップ・グラスなどの現代音楽との共演や、ポピュラーを古楽器で演奏するような取り組みにも積極的な彼らは、中国の現代笙の名手ウー・ウェイと共演し、東と西の文化の間を経験することができる画期的なアルバムに仕上げています。《録音》2015年5月,
ベルリン、ハウス・デス・ルントフンクス
ラウテン・カンパニー/創立30年記念ベスト |
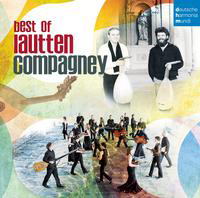
8887501631-2
\2700→\2490 |
ラウテン・カンパニー/創立30年記念ベスト
1) ジョアン・アンブロジオ・ダルツァ:『フェッラーラ風のピーヴァ』,
2) タルクィニオ・メールラ:『センティーレ=カンツォネッタ』,
3) ニコラ・マテイス:『チャコネッタ』,
4) ニコラ・マテイス:『ラ・ディア・スパニョーラ』、
5) イギリス舞曲:『カプリッチョ・デット・スヴェリアトーイオ』,
6) J.S.バッハ:『ヴァージン・クイーン』,
7) J.S.バッハ:『Bobbing Joe』,
8) J.S.バッハ:『モテット「主に向かって新しき歌をうたえ」BWV.225〜第1曲』,
9) J.S.バッハ:『コラール「はかなく むなしき」』,
10) J.S.バッハ:『カンタータ「はかなく
むなしき」〜コラール』,
11) ブクステフーデ:『強めたまえ』,
12) ブクステフーデ:『主よ、あなたさえこの世にあれば』,
13) ヘンデル:『オラトリオ「メサイア」〜ハレルヤ』(ドイツ語版),
14) パーセル:『歌劇「アセンスのターモン」〜グラウンドによるカーテンチューン』,
15) パーセル:『歌劇「妖精の女王」〜One
Charming Night』,
16) ヘンデル:『歌劇「リチャード1世」〜死よ、来てください』,
17) ヘンデル:『歌劇「リナルド」〜私を泣かせてください』,
18) フィリップ・グラス:『The Windcatcher
Part I』,
19) モンテヴェルディ:『歌劇「オルフェオ」〜ViRicorda
Boschi Ombrosio』,
20) パーセル:『グラウンド ハ長調』,
21) ヨハン・フィリップ・クリーガー:『暗がりは悪事に好都合』,
22) トマス・ロビンソン:『プレインソング』,
23) ダウランド:『わが過ちを許してくれようか』,
24) ウィリアム・バード:『深い緑の森よ』,
25) パーセル:『Bedlam Boys』,
26) ヨハン・タイレ:『Nun ich singe, Gott
ich knie』 |
ウォルフガング・カチュナー(指揮&リュート)、
ラウテン・カンパニー |
| ヴォルフガング・カチュナー指揮するベルリンの古楽器アンサンブル「ラウテン・カンパニー」。1984年設立当初はカチュナーとハンス=ヴェルナー・アペルとのリュート・デュオから始まりました。10月18日にはベルリンで30周年を祝う記念コンサートが行われますが、それに合わせて発売されるのが当アルバムです。ラウテン・カンパニーは、いわゆるピリオド楽器演奏とは一味違い、当時の音楽を現代に蘇えらせることに主眼を置いていて、様々なソリストたちを取り込み、多様な編成で演奏活動を行なうのが特徴。例えば演奏会では、管弦楽だけによる歌無し版オペラ・アリアや、フィリップ・グラスなどの現代音楽やポピュラーを古楽器で演奏するような取り組みにも積極的です。このアルバムはそうした彼らの演奏活動の30年の積み重ねをバロック音楽の分野の録音で辿ってゆくもの。DHMの音源だけでなく彼らが録音してきた様々な音源から選曲されています。 |
|
<国内盤>

9/23(水)紹介新譜
マイナー・レーベル新譜
 STRADIVARIUS STRADIVARIUS
|
|
|
モーツァルト 偽りのパリジャン
ドメニコ・チマローザ(1749-1801):
オペラ「古代ローマの狂信者」から Sposate
che
ジョヴァンニ・パイジェッロ(1740-1816):
オペラ「水車屋の娘」から Ah, che nel
petto io sento
ガブリエーレ・レオーネ(確認できる活躍期:1725-1790):
マンドリンと通奏低音のためのソナタ ト短調
Op.5 No.2
エジーディオ・ロムアルド・ドゥーニ(1708-1775):L'avez
vous vu mon bien aime
ガブリエーレ・レオーネ:「L'avez vous vu
mon bien aime」による変奏曲
ジュゼッペ・サルティ(1729-1802):
オペラ「デモフォーンテ」から Chere idole
de mon ame
アンドレ=エルネスト=モデスト・グレトリ(1741-1813):
オペラ「獅子心王リチャード」から Je crains
de lui par
ヤン・クシチテル・クルンプホルツ(1747-1790):Purisque
mon espoir Op.10
グルック(1714-1787):オペラ「タウリスのイフィゲニア」から
D'une images
モーツァルト(1756-1791):
満足 K.349/おいで、愛しのツィターよ
K.351(367b)
ヴァイオリン・ソナタ第15番ヘ長調 K.30(マンドリンとハープによる)
オペラ「フィガロの結婚」K.492 から L'ho
perduta / Mon coeur soupire
カンツォネッタ I, II, III, VII |
マリネッラ・ペンニッキ(ソプラノ)
マウロ・スクイッランテ(マンドリン)
マーラ・ガラッシ(ハープ) |
チマローザ、パイジェッロ、グルック、モーツァルトはもちろん、ジュゼッペ・サルティ、アンドレ=エルネスト=モデスト・グレトリ、クルンプホルツ、みなフランス以外の国からパリに惹かれてやってきた作曲家。
パリという巨大な背徳と芸術の町が彼らにどんな影響を及ぼしたか・・・そういうアルバムか。
|
| |
|
|
マイケル・チャンス(カウンタテナー)
ジョン・ダウランド(1563-1626):暗闇に リュート歌曲集
Praeludium / In darkness let me dwell
/ Lord Viscount Lisle's galliard
Sweet stay a while / Fancy / In this
trembling shadow cast
Sir Henry Guilford his Almaine / Shall
I strive with words to move?
A fancy by Mr. Dowlande / Farre from
triumphing court
Coranto by Doctor Dowland / Stay time
a while thy flying
An almand by Mr. John Dowland / Lady
if you so spight me / Pavan
Tell me true love / Galliard to 'Lacrimae'
/ Thou mighty god |
マイケル・チャンス(カウンタテナー)
ポール・ベイアー(リュート) |
| |
|
|
ロカテッリ、ヴィヴァルディ、レーオ:弦楽器のための協奏曲集
ピエトロ・アントニオ・ロカテッリ(1695-1764):
ヴァイオリンの技法 Op.3 から ヴァイオリンと弦楽のための協奏曲ニ長調(No.1)
ヴィヴァルディ(1678-1741):
2つのチェロ、弦楽と通奏低音のための協奏曲ト短調
RV531
4つのヴァイオリン、弦楽と通奏低音のための協奏曲ロ短調
Op.3 No.10 RV580
レオナルド・レーオ(1694-1744):
4つのヴァイオリンのオブリガートと通奏低音のための協奏曲ニ長調 |
リ・アルキ・ディ・ジナイーダ
マリア・カテリーナ・カルリーニ(コンサートマスター)
|
| リ・アルキ・ディ・ジナイーダはイタリアのジナイーダ・ギレリス・ヴァイオリン学校の生徒たちから成る弦楽合奏団。 |
| |
|
|
マルシャン、クレランボー:チェンバロ作品全集
ルイ・マルシャン(1669-1732):
組曲ニ短調/組曲ト短調/ヴェネツィア風/ひょうきん者/ガヴォット
ルイ=ニコラ・クレランボー(1676-1749):組曲ハ長調/組曲ハ短調 |
ルーカ・オベルティ(チェンバロ) |
|
フランス・バロックの作曲家・鍵盤楽器奏者マルシャンとクレランボー。マルシャンは自作の出版に興味がなく、クレランボーは主にフランス語カンタータや教会音楽であったため、出版された二人のチェンバロ作品は当盤収録のものがすべてです。
これらの作品に魅了されたと言うルーカ・オベルティによる演奏。ルーカ・オベルティはエミーリア・ファディーニ、クリストフ・ルセ、ピエール・アンタイに師事したイタリアのチェンバロおよびフォルテピアノ奏者・指揮者。
プロモーション・ビデオクリップ
|
| |
|
|
J・S・バッハ(1685-1750):トッカータ集
トッカータ嬰ヘ短調 BWV910/トッカータ
ト短調 BWV915
トッカータ ト長調 BWV916/トッカータ
ハ短調 BWV911
トッカータ ホ短調 BWV914/トッカータ
ニ短調 BWV913
トッカータ ニ長調 BWV912 |
ステファノ・インノチェンティ(チェンバロ) |
| ステファノ・インノチェンティはイタリアのフィレンツェに生まれ、ハールレム音楽アカデミーでアントン・ハイラー、ルイージ・フェルディナンド・タリアヴィーニ、マリー=クレール・アラン、ケネス・ギルバートに師事したオルガンおよびチェンバロ奏者。 |
| |
|
|
エマヌエーレ・カザーレ(1974-):
11(アンサンブルとエレクトロニクスのための;2008)
Questo e un gruppo e pace(2014)
Esistere lago, nulla e un tempo(2006)
7(弦楽四重奏のための;2005)
5(フルート、クラリネットとエレクトロニクスのための;2003) |
mdiアンサンブル
杉山洋一(指揮) |
| |
|
|
ルイス・デ・パブロ(1930-):フルートのために
独白 [Soliloquio]
(一人の奏者によるC管フルート、G管フルートと
オッタヴィーノのための;1997/1998)
メリスマ・フリオーソ [Melisma furioso]
(フルート独奏のための;1990)
フルートのために [Per flauto]
(一人の奏者によるC管フルート、G管フルートと
オッタヴィーノのための;2010)
「KIU」の4つの断章 [Cuatro fragmentos
de "KIU"]
(一人の奏者による様々なフルートとピアノのための;1986)(*) |
ロベルト・ファッブリチアーニ(各種フルート)
マッシミリアーノ・ダメリーニ(ピアノ) |
<マイナー・レーベル歴史的録音・旧録音>
 VISTA VERA VISTA VERA
|
|
|
マリア・ユーディナの遺産 Vol.18
J・S・バッハ(1685-1750):
トッカータ ハ短調 BWV911(*)
平均律クラヴィーア曲集第2巻 から 前奏曲嬰ヘ短調
BWV883(*)
ユーリー・シャポーリン(1887-1966):ピアノ・ソナタ第2番ロ短調
Op.7(#)
カジミェシュ・セロツキ(1922-1981):前奏曲組曲(1952)(+)
マルチヌー(1890-1959):2つの小品(1948)(+)
マラケ河岸の古本屋/陰暦五月五日
バルトーク(1881-1945):2台のピアノと打楽器のためのソナタ(++) |
マリア・ユーディナ(ピアノ)
ヴィクトル・デレヴャンコ(ピアノ(**))
ヴァレンチン・スネギリョフ、
ルシアン・ニクーリン(打楽器(**)) |
|
録音:1936年(*)/1953年(+)/1959年(#)/1963年(**)
バッハやベートーヴェンに加え、親友ショスタコーヴィチ他20世紀の作曲家の音楽にも積極的に取り組んだロシアのピアニスト、マリア・ユーディナ(1899-1970)。当シリーズ久々のリリースです。
|
| |
|
|
ピョートル・メシチャニノフ
ヒンデミット(1895-1963):
ピアノ、金管楽器と2つのハープのための協奏音楽(演奏会用音楽)Op.49
メシアン(1908-1992):異国の鳥(ピアノと小管弦楽のための)
サン=サーンス(1835-1921):
カプリス=ワルツ「ウェディング・ケーキ」(ピアノと弦楽合奏のための)Op.76
スクリャービン(1872-1915):プロメテウス(交響曲第5番「火の詩」)Op.60(*) |
ピョートル・メシチャニノフ(ピアノ)
ソヴィエト国立交響楽団ソリスト・アンサンブル(*以外)
ゲンナジー・ロジェストヴェンスキー(指揮(*以外))
ソヴィエト国立交響楽団(*)
エフゲニー・スヴェトラーノフ(指揮(*)) |
|
録音:1975-1977年、場所の記載なし(*以外)
1978年12月26日、ライヴ、モスクワ音楽院大ホール、モスクワ、ロシア、ソヴィエト
ピョートル・メシチャニノフ(1944-2006)はロシアのピアニスト・指揮者・音楽理論家。作曲家ソフィア・グバイドゥーリナの三番目の夫で、現代音楽にも積極的に取り組みました。
|
<メジャー・レーベル>
.
 オーストラリアELOQUECNE オーストラリアELOQUECNE
|


480 8895
(6CD)
\6000→\5490 |
《ピエール・モントゥー/ベートーヴェン:交響曲全集》
ベートーヴェン:交響曲第1〜9番
(3番は2種類の録音、第9番はリハーサル付),
「フィデリオ」序曲, 「エグモント」序曲,
「シュテファン王」序曲,
ド・リール:「ラ・マルセイエーズ」 |
ピエール・モントゥー(指揮)/
交響曲第1, 3, 6, 8番〜
ウィーン・フィル
交響曲第2, 4, 5, 7番&序曲〜
ロンドン交響楽団
交響曲第9番(+リハーサル付)&ラ・マルセイエーズ〜
エリーザベト・ゼーダーシュトレーム(ソプラノ),
レジーナ・レズニック(メゾソプラノ),
ジョン・ヴィッカーズ(テノール),
デイヴィット・ワード(バス),
ロンドン・バッハ合唱団,
ロンドン交響楽団/
交響曲第3番〜
ロイヤル・コンセルヘボウ管 |
燃焼度の高きモントゥーのベートーヴェン名演
80歳を越えてもなお精力的に活躍していたモントゥー。その彼が2つのオーケストラを操り演奏したベートーヴェンの交響曲全曲は、第9番のみレーベルが異なっていたため、全集としてまとめられたのは後年になってからのことでした。スコアを丁寧に読み取り、燃焼度の高い凄まじい演奏を繰り広げるモントゥーのベートーヴェンは普遍の価値があるものです。
リハーサル、序曲も含んだその全集に、今回はロイヤル・コンセルトヘボウとの第3番の録音も加え、最強のBOXセットが完成しました。
第1, 3, 6, 8番〜(1957〜1960年:ゾフィエンザール)/
第2, 4, 5, 7番&序曲〜(1959〜1961年:キングズウェイ・ホール)/
第9番(+リハーサル付)&ラ・マルセイエーズ〜(1962年6月:ウォルサムストウ、アセンブリー・ホール)/
第3番〜(1962年6月、アムステルダム・コンセルヘボウ)
|
| |


482 1993
\1200 |
《エルガー:エニグマ変奏曲, 威風堂々》
エルガー:エニグマ変奏曲, 威風堂々第1〜5番 |
ノーマン・デル・マー(指揮)
ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 |
ノーマン・デル・マーの洗練された解釈
ロンドンで生まれ、活動の初期はホルン奏者としてロイヤル・フィルに入団。ビーチャムの助手を経て、1947年に指揮者としてデビューしたノーマン・デル・マー。シェーンベルクやR・シュトラウスなどの録音も残っていますが、何と言っても彼の本領はイギリス音楽にあります。エルガー作品では、とりわけ小品集での評価が高い人ですが、この「エニグマ変奏曲」と「威風堂々」でも洗練された解釈を聴く事ができます。
ギルフォード大聖堂の素晴らしい音響に心を奪われるアルバムです。
《録音》1975年1月, ギルフォード大聖堂 |
| |


482 0288
\1200 |
フェルナンド・コレーナ
《モーツァルト:バスのためのアリア集》
モーツァルト:
1) 歌劇『フィガロの結婚』K.492〜
「すべて準備は整った・・・時は —少しばかりその目を開け」,
2) 歌劇『フィガロの結婚』K.492〜「もう飛ぶまいぞ
この蝶々」,
3) 歌劇『魔笛』K.620〜「この聖なる殿堂では」,
4) 歌劇『コシ・ファン・トゥッテ』K.588〜
「多くのご婦人方、あなた方は」,
5) 歌劇『ドン・ジョヴァンニ』K.527〜「カタログの歌」,
6) 歌劇『ドン・ジョヴァンニ』K.527〜「ああ、お情けを、おふたり様」,
7) 歌劇『フィガロの結婚』K.492〜
「踊りになられたければ、伯爵さま」,
8) 歌劇『フィガロの結婚』K.492〜
「仇を討つまことに愉快じゃ」,
9) 「この美しい手と瞳のために」K.612,
10) 「彼に眼を向けなさい」K.584,
11) 「「かくて汝は裏切りぬ・・・激しく堪えがたき苛責」K.432,
12) 「どこから来るのか私は知らない」K.512,
13) 「御手に口づけ」K.541,
14) 「おお、娘よ、お前と別れる今」K.513 |
フェルナンド・コレーナ(バス)/
アルベルト・エレーデ(指揮)
ローマ・サンタ・チェチーリア国立管弦楽団(1-4)/
ペーター・マーク(指揮)
スイス・ロマンド管弦楽団(5-8)/
アルジェオ・クァドリ(指揮)
コヴェント・ガーデン王立歌劇場管弦楽団(9-14) |
名バス歌手フェルナンド・コレーナの気品あふれる歌唱
スイス出身のバス歌手、コレーナは神学を志していた大学時代、地元の声楽コンテストで優勝したことをきっかけに声楽に転向し、ジュネーブ音楽院で学び、1940年に歌手デビューを飾ります。
張りのある低音と巧みな表現力は様々な歌劇の道化役として重用され、アメリカの評論家ハロルド・C・ショーンバーグからも高く評価されています。このモーツァルトでもコミカルさの中に溢れる気品を感じさせる素晴らしい歌唱をお楽しみいただけます。
《録音》1952年8月、ローマ(1-4)/1952年4月、ジュネーブ(5-8)/1960年6月、ロンドン(9-14) |
| |

480 7059
(2CD)
\1800 |
《ギルバート&サリヴァン:ペンザンスの海賊,
コックスとボックス》
ギルバート&サリヴァン:
1) 喜歌劇「ペンザンスの海賊」,
2) 喜歌劇「コックスとボックス」 |
イサイドア・ゴッドフリー(指揮)
ドイリー・カート・オペラ・カンパニー,
ロンドン新交響楽団(1)/
ロイストン・ナッシュ(指揮)
ドイリー・カート・オペラ・カンパニー,
ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団(2) |
波乱万丈の荒唐無稽なオペレッタ
ギルバート&サリヴァンの作品の中でも知名度の高い「ペンザンスの海賊」。物語は彼らの他のオペラと同じくかなり荒唐無稽であり、この主人公も本来は水先案内人(pilot)の修行に出るはずが、ちょっとした間違いで海賊(pirate)になってしまったというもの。波乱万丈のやりとりの末、全て丸くおさまるというお話です。
「コックスとボックス」はすれ違いの2人という意味のあるタイトルで、日本で初めて上演された作品であるともされています。
《録音》1957年11月、キングズウェイ・ホール(1)/1978年2月、ロンドン、デッカ第3スタジオ(2) |
| |


482 2566
\1200 |
《グノー:歌劇「ファウスト」(ハイライト)》
グノー:歌劇「ファウスト」(ハイライト) |
フランコ・コレッリ(ファウスト),
ジョーン・サザーランド(マルグリート),
ニコライ・ギャウロフ(メフィストフェレス),
他、
リチャード・ボニング(指揮)
ロンドン交響楽団,
アンブロジアン・オペラ・コーラス, |
恐ろしいまでに迫力のあるギャウロフのメフィストフェレス
1966年に録音された「ファウスト」の名録音からのハイライト盤。恐ろしいまでに迫力のあるギャウロフのメフィストフェレス、甘美なる高音が聴きもののコレッリのファウスト、そして気品あるサザーランドのマルグリートと配役は完璧。ボニングの指揮は、歌にぴったりと寄り添うことで、声高な主張をせずとも、この流麗な音楽を存分に楽しませてくれます。
《録音》1966年6〜7月, ロンドン、キングズウェイ・ホール |
| |


482 0268
\1200 |
《ヴェルディ:歌劇「ファルスタッフ」より場面とアリア》
ヴェルディ:歌劇「ファルスタッフ」より場面とアリア
《録音》1963年6&7月, ウォルサムストウ、アセンブリー・ホール |
ファルナンド・コレナ(ファルスタッフ),
レナート・カペッキ(フォード),
イルヴァ・リガブーエ(アリーチェ・フォード),
リディア・マリンピエトリ(ナンネッタ),
フェルナンダ・カドーニ(メグ・ペイジ),
レジーナ・レズニック(クイックリー夫人)、他
エドワード・ダウンズ(指揮)
ロンドン新交響楽団 |
ロッシーニ:
歌劇『セビリャの理髪師』より「わしのような医者に向かって」,
歌劇『どろぼうかささぎ』より「Il mio pianto
? preparato」,
ドニゼッティ:
歌劇『愛の妙薬』より「お聴きあれ、村の衆」,
歌劇『ドン・パスクヮーレ』より
「ああ!あられもない炎がわしの体中を焼き尽くす」
《録音》1950&1952年、ジュネーブ |
ファルナンド・コレナ(バス),
アルベルト・エレーデ(指揮)
スイス・ロマンド管弦楽団 |
ファルナンド・コレーナ当たり役の円熟の歌唱
スイスからイタリアに帰化したブッフォ・バス、コレーナを知りたければ、やはり「ファルスタッフ」を聴かないわけにはいきません。1955年のエディンバラ音楽祭で絶賛されて以来、この役にかけては右に出るものがいないほどの彼にとっての当たり役。この1963年録音では円熟の歌唱を聴く事ができます。また、マリンピエトリを始めとした女声の充実も忘れがたい印象を残す録音です。
余白にはコレーナの珍しい50年代録音のロッシーニ、ドニゼッティのアリアも収録されています。 |
| |


482 0727
\1200 |
《ヴォルフガング・シュナイダーハン, ティボール・ビストリチュキー/
ヴィルトゥーゾ・ヴァイオリン》
バルトーク:6つのルーマニア民俗舞曲(バルトーク/セーケイ編),
ストラヴィンスキー:ロシアの乙女の歌(歌劇「マヴラ」より),
ストラヴィンスキー(ドゥシュキン&ストラヴィンスキー編):
ロシア舞曲(バレエ「ペトルーシュカ」より,
サン=サーンス:白鳥,
クライスラー:ウィーン奇想曲, 愛の悲しみ,
愛の喜び,
レーガー:子守歌,
シューバート:蜜蜂,
ブラームス(ヨアヒム編):ハンガリー舞曲第5番,
エルガー:気まぐれな女,
リース:常動曲,
ムソルグスキー(ハルトマン編):ゴパーク,
ヘブライの歌,
ファリャ(クライスラー編):スペイン舞曲,
ショパン(サラサーテ編):夜想曲Op.9-2,
マルティヌー(ハルトマン編):アラベスク
《録音》1957年7月、ザルツブルク、クレスハイム城 |
ヴォルフガング・シュナイダーハン(ヴァイオリン)
アルベルト・ヒルシュ(ピアノ) |
チャイコフスキー:感傷的なワルツ,
フバイ:ゼフィール,
コダーイ:小ワルツ,
ゾルト:とんぼ,
ドヴォルザーク:スラヴ舞曲Op.72-2,
シャミナード:スペインのセレナード,
ラフマニノフ:エレジーOp.3-1,
ドビュッシー:小さな黒人,
リスト:忘れられワルツ第1番,
《録音》1958年11月, ベルリン |
ティボール・ビストリチュキー(ヴァイオリン)
フェリックス・シュレーダー(ピアノ), |
二人の名ヴァイオリニストによる名小品集
1900年代の初頭に生まれた2人のヴィルトゥオーゾ・ヴァイオリニストの録音集。
1915年ウィーン生まれのシュナイダーハンは録音も比較的多く、その活動も広く知られています。2015年は生誕100年の記念年でもあり、その録音が大量に復刻されファンを狂気乱舞させましたが、1908年生まれのビストリチュキーについては、ほとんど知られていないのが現状です。
ハンガリー領のアラドに生まれ、フランツ・リスト音楽院で学び、1946年まで母校の教授を務めたあと、ソリストとして活動します。
優れた才能を持っていた人ですが、当時のハンガリーはヴァイオリニストの激戦区であったため、存分に個性を発揮できぬまま忘れられてしまったのです。そんな2人の演奏を併せて収録。 |
<映像>
 OPUS ARTE(映像) OPUS ARTE(映像)
|

OA1195D
(DVD)
\4000 |
バレエ《ナポリ,あるいは漁師とその花嫁》
オーギュスト・ブルノンヴィル(1805-1879):原振付
ソレッラ・エングルンド&ニコライ・ヒュッベ:振付 |
【ダンサー】
ジェンナロ:若い猟師…アルバン・レンドルフ/
テレシーナ:ジェンナロの恋人…アレクサンドラ・ロ・サルド/
ゴルフォ:海の王…ベンジャミン・ブーザ/
ヴェロニカ:テレシーナの母…リス・イェペッセン/
ジョヴァンニーナ…アルバ・ネダル/
フローラ…メッテ・ボッチャー/
ペッポ…ジーン=ルーシェン・マソット/
ジャコモ…フェルナンド・モーラ/
パスカリッロ…ポール・エリク・ハッセルキルデ/
【音楽】
エドヴァルド・ヘルステッド/
ホルガー・シモン・パウリ/
H・C・ロンビ/ルイス・アレヌス/
【演奏】
デンマーク王立管弦楽団/
グラハム・ボンド(指揮)/
マヤ・レイヴン(装置&衣装)/
ミッキ・クントゥ(照明)/
カミラ・ヒュッベ(ドラマトゥルギー)/
ウッフェ・ボルクヴァルト&
ペテル・ボルクヴァルト(スクリーン・ディレクター)/
ジェンス・ランゲ(プロデューサー) |
OABD7185D
(BD)
\4800 |
2014年2月 コペンハーゲン デンマーク・ロイヤル・バレエ
ライヴ収録/収録時間:105分/音声:<DVD>ステレオ2.0/DTS5.1
<BD>ステレオ2.0/DTS5.0/画面:16:9/REGION
All(Code:0)/<DVD>片面2層ディスク <BD>ニ層
50GB 1080i High Definition
恋人同士のジェンナロとテレシーナはある日海で遭難してしまい、ジェンナロだけが港に戻ってきます。死んだと思われていたテレシーナは、実は海の王ゴルフォに気に入られ、今は海の精となって青の洞窟に囚われています。彼女を探しに来たジェンナロですが、ゴルフォに記憶を奪われてしまったテレシーナには、ジェンナロのことがわかりません。さて、一体2人はどうなるのでしょうか?
デンマーク王立バレエ団のために50以上のバレエ作品を作り、その活気漲る美しい舞台が世界中から絶賛された振付家、オーギュスト・ブルノンヴィル。彼の代表作の一つがこのバレエ《ナポリ》です。
これは1841年、国王の怒りに触れた彼が6ヶ月間の国外追放になった時に、旅先のイタリアで着想を得た物語で、有名な「青の洞窟」も舞台として登場するというイタリア風味満載のものです。
この上演では、1950年代のフェデリコ・フェリーニの初期映画からインスピレーションを受けたという演出が用いられており、ソレッラ・エングルンドとニコライ・ヒュッベの2人が新しい振付を施し、第2幕には新しい音楽を導入。
またマヤ・レイヴンの精巧な装置と衣装も、1842年の初演時の古典的な雰囲気を壊すことなく、極めて現代的な作品として生まれ変らせることに成功しています。 |
| |

OA1198BD
(DVD 6枚組)
\5400 |
ベンジャミン・ブリテン:コレクション
①歌劇《ピーター・グライムズ》(2012)
特典映像:キャスト・ギャラリー/キャストたちへのインタビュー
収録 2012年6月 ミラノ・スカラ座 ライヴ |
ピーター・グライムズ(漁師):ジョン・グレアム=ホール/
エレン・オーフォード(未亡人で村の教師):スーザン・グリットン/
ボルストロード船長:クリストファー・パーヴェス
他/
ミラノ・スカラ座管弦楽団&合唱団/
ロビン・ティチアーティ(指揮)/
リチャード・ジョーンズ(演出) |
2005年にすでに最年少でミラノ・スカラ座デビューを果たしたロビン・ティチアーティ。1983年生まれのイギリスの若き指揮者(当時まだ20代!)が、イギリス人キャストたちを率いてスカラ座で披露したブリテンの代表作《ピーター・グライムズ》。スカラ座でようやく3度目の上演となったこの演目。1830年代のイギリスの小さな漁村で起きるピーター・グライムズと村人たちをめぐる音の心理劇は、演出家リチャード・ジョーンズの手により20世紀後半のイギリスへと舞台を移します。
ヴィヴィッドな舞台造詣により一層鮮明に浮かび上がってくるリアリティ、グライムズの恐怖や孤独感に戦慄。 |
②歌劇《ルクレツィアの陵辱》(2001)
特典映像:キャスト・ギャラリー/ディレクターからのコメント
収録 2001年 オールドバラ音楽祭 ライヴ |
ルクレツィア(コッラティヌスの妻):サラ・コノリー/
ターキニアス(エトルリアの王子タルクィニウス):クリストファー・マルトマン/
男性のコーラス役:ジョン・マーク・エインズリー/
女性のコーラス役:オルラ・ボイラン 他/
イングリッシュ・ナショナル・オペラ管弦楽団/
ポール・ダニエル(指揮)/
デイヴィッド・マクヴィカー(演出) |
ローマの王政が終わりを告げる端緒となったとされる紀元前6世紀の事件《ルクレツィアの陵辱》を描いたブリテン(1913-1976)のオペラ。
ローマの陣営でコラティナス、ターキニアス(タルクィニウス・セクストゥス)、ユニウスが妻の貞淑を競い合います。するとその貞淑さを讃えられたコラティナスの妻ルクレツィアに横恋慕したエトルリアの王子ターキニアスは、夜中、夫の留守を襲ってルクレツィアを陵辱する。ルクレツィアは陣営より夫を呼び戻し、自分の受けた恥辱を告白し、自らを剣で刺して自害するという救いのない物語です。
デイヴィッド・マクヴィカーがイングリッシュ・ナショナル・オペラのために演出したこのプロダクションでは、「どの時代、どんな場所にも存在しうる普通の女性ルクレツィア」を物語の中核に据えて描き出します。その役をサラ・コノリーがしっかりと引き受け、引き締まった舞台を作り上げています。 |
③歌劇《ビリー・バッド》(2010)
特典映像:キャスト・ギャラリー/オペラへのイントロダクション/デザイン
収録 2010年6月 グラインドボーン音楽祭
ライヴ |
ヴィア艦長:ジョン・マーク・エインズリー/
ビリー・バッド:ジャック・インブライロ/
クラッガート:フィリップ・エンス 他/
グラインドボーン音楽祭合唱団/
ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団/
マーク・エルダー(指揮)/
マイケル・グランデージ(演出) |
かつて《ルクレティアの陵辱》や《アルバート・ヘリング》のブリテンのオペラを初演するなど、ブリテンのオペラとの結びつきにおいて誇らしい実績を有するグラインドボーン音楽祭で、『ビリー・バッド』が初めて舞台にかけられた2010年の公演。
英国の軍艦インドミタブル号で起こる善と悪、純真と堕落とのせめぎ合いをスリリングに語る、男性ばかりで演じられるこのオペラを、英国きっての演出家、トミー賞受賞のマイケル・グランデージが手がけ、若き水夫ビリー・バッド、思慮深いヴィア艦長、邪な憲兵曹長クラッガートの間に生ずる抜き差しならない緊張感を丹念に描き出します。
ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団を指揮するのはマーク・エルダー。英国オペラ界に絶大なる影響力を誇る巨匠がタクトをとった、記念すべき100回目のオペラ・プロダクションは、音楽を深く掘り下げ、圧倒的な力で感動のクライマックスを形作る、迫真の演奏を生みました。 |
OABD7189BD
(BD 5枚組)
\6600 |
④歌劇《グロリアーナ》(2013)
特典映像:
キャスト・ギャラリー/オペラへのイントロダクション/
ブリテンのオールドバラ
収録 2013年6月 ロンドン,ロイヤル・オペラ・ハウス
ライヴ |
エリザベス1世:スーザン・ブロック/
エセックス伯ロバート・デヴァルー:トビー・スペンス/
エセックス伯夫人フランシス:パトリシア・バードン/
マウントジョイ卿:マーク・ストーン 他/
コヴェント・ガーデン王立歌劇場管弦楽団&合唱団/
ポール・ダニエル(指揮)/
リチャード・ジョーンズ(演出) |
ベンジャミン・ブリテンの生誕100周年を迎えた2013年に、英国ロイヤル・オペラがその記念イヤーのハイライトとして舞台に上げたのは、ロイヤル・オペラの委嘱により、エリザベス2世の戴冠を祝して、その女王に捧げるために作曲されたブリテンのオペラ《グロリアーナ》でした。
英国を代表する演出家であるリチャード・ジョーンズが手がけたニュー・プロダクションでは、そのウィットに溢れ洞察力に富んだ舞台造詣と人物描写が、このオペラの魅力を十二分に浮かび上がらせます。エリザベス1世の晩年を、女王が寵愛するエセックス伯との複雑な関係性に焦点を当てながら描写するこのオペラ。
本上演では情熱的ながらどこか信頼の置けないエセックス伯を、トビー・スペンスが魅力的に演じ、貫禄溢れるスーザン・ブロックとの掛け合いの中で、栄光にあったエリザベスの晩年の悲哀を際立たせます。 |
⑤歌劇《ヴェニスに死す》(2013)
特典映像:キャスト・ギャラリー
収録 2013年6月 ロンドン・コロシアム
ライヴ |
グスタフ・フォン・アッシェンバッハ:ジョン・グラハム=ハール/
旅人/老いた伊達男/ゴンドラこぎ/
床屋/ホテル支配人/旅芸人/
ディオニュソスの声:アンドリュー・ショア
アポロの声:ティム・ミード/
タジオ:サム・ツァルドヴァー(ダンサー)他/
イングリッシュ・ナショナル・オペラ管弦楽団/
エドワード・ガードナー(指揮)/
デボラ・ワーナー(演出) |
舞台が幻想的であればあるほどに、人間の持つ「美への憧れ」と、それに比例した「現実の醜い部分」が際立つというこの物語。
演出を担当したデボラ・ワーナーは、装置も衣装もシンプルな物を用い、儚い夢にのたうつ芸術家の苦悩を突き放すことを試みるかのようです。
主人公を歌うジョン・グラハム=ハールはケンブリッジ王立音楽大学で学び、2012年にはイタリアの権威ある「フランコ・アッヴィアーティ賞」を受賞するなど注目のテノール歌手。力強く、リリカルな声は将来を期待させる才能です。
様々な役を歌い分けるアンドリュー・ショアはイギリスのベテラン。イングリッシュ・ナショナル・オペラの顔とも言える存在です。 |
収録時間:①154分+14分/②120分/③200分/④163分+13分/⑤153分/音声:英語歌唱
<DVD>ステレオ2.0/DTS5.1 <BD>ステレオ2.0/dts-HDマスターオーディオ5.0/字幕:①英,
仏, 独, 韓, 日 ②英, 仏, 独, 韓, 日 ③英,
仏, 独, 西 ④英, 仏, 独, 韓, 日 ⑤英, 仏,
独, 韓/画面16:9/REGION All(Code:0)/<DVD>片面2層ディスク<BD>ニ層
50GB 1080i High Definition
卓越した歌手、指揮者、そしてディレクターを揃えたブリテンの5つのオペラ集。霧深い風景の中、屈折した人々の思いが反映されたそれぞれの作品は、どれもが深い闇と、はっとするような美しさを備えています。
確かにどの作品も、手放しで楽しむような娯楽的な雰囲気はありませんが一度引き込まれると抜け出すことができなくなるのが、ブリテン作品の特徴なのです。 |

9/22(火)紹介新譜
マイナー・レーベル新譜
 DELPHIAN DELPHIAN
|
|
|
使徒らは口々に 〜 ボールドウィン・パートブックからの音楽
ロバート・パーソンズ:歌はラッパを招き/
トマス・タリス:使徒らは口々に/ウィリアム・マンディ:われは若く/
ウィリアム・バード:6声の単純カノン/
ウィリアム・バード:おお、救い主なるいけにえよ/
ヒュー・アストン:ヒュー・アストンのマスク/
デリック・ヘラルト:傷付きし/エルウェイ・ベヴィン:ブラウニング/
アルフォンソ・フェッラボスコI世:主よ、我らが日々に平和を与えたまえ/
オルランド・デ・ラッスス:アベルはいずこに/
クリスティアン・ホランダー:安息日が過ぎて/
トマス・タリス:聞き入れたまえ、我は願う/
ジョン・タヴァナー:慕いこがるるごとく/
ウィリアム・マンディ:わが魂はちりについています/
ジョン・ボールドウィン:カッコウ/ジョン・シェパード:めでたし、海の星 |
マリアン・コンソート
ロリー・マクリーリー(ディレクター)
ローズ・コンソート・オヴ・ヴィオールズ |
マリアン・コンソートが歌うポリフォニー!ボールドウィン・パートブックからの音楽!
"聖母マリア"の名を冠し、イギリスの声楽、古楽界に彗星の如く現れた若きヴォーカル・アンサンブル、マリアン・コンソート!
エジンバラ・セント・メアリー大聖堂の少年聖歌隊員としてキャリアをスタートさせた若きカウンターテナー、ロリー・マクリーリーによって、2007年にオックスフォード大学で結成されたマリアン・コンソート。
音楽学者でもあるリーダー、ロリー・マクリーリーの研究、時代考証に基づき、15世紀〜17世紀を中心に、全ての時代の教会音楽に取り組み続けている。
またメンバーのエマ・ウォルシュも、2015年6月のタリス・スコラーズの来日公演にも参加した注目の若手ソプラノである。
マリアン・コンソートが歌うのは、1575年の時点でウィンザー城セント・ジョージ・チャペルの聖歌隊員として活躍していたイングランドのテノール、ジョン・ボールドウィン(c.1560−1615)が編慕したパートブックからの秀作たち。
イギリスとヨーロッパ大陸のポリフォニーの魅力が凝縮された見事なプログラム。マリアン・コンソートの輝かしく伸びやかな歌声、ローズ・コンソート・ヴィオールズの音色の相性も特筆もの。
※録音:2015年1月8日−11日、マートン・カレッジ・チャペル(オックスフォード、イギリス)
|
| |
|
|
清廉なるトレブルのハーモニー!
モーツァルトの戴冠式ミサ曲&ヴェスペレ!
モーツァルト:
戴冠式ミサ曲ハ長調 K.317
アヴェ・ヴェルム・コルプス K.618
ヴェスペレ K.339 |
テュークスベリー寺院スコラ・カントルム
シャリヴァリ・アグレアブル
ベンジャミン・ニコラス(指揮)
ローレンス・キルスビー(トレブル)
ジェレミー・ケニオン(アルト)
クリストファー・ワトソン(テール)
クリストファー・ボレット(バス) |
清廉なるトレブルのハーモニー。少年合唱、男声合唱とソリストが創り上げたモーツァルトの宗教合唱作品集。
英国有数の合唱指揮者ベンジャミン・ニコラスの優れた手腕が、テュークスベリー寺院スコラ・カントルムの清らかなるハーモニーでモーツァルトを感動的に表現する。
※録音:2011年7月12日−13日、マートン・カレッジ・チャペル(オックスフォード、イギリス) |
| |
|
|
ソリチュード 〜 バルティック・リフレクションズ
オリ・ムストネン:トッカータ
ジータ・ブルザイテ:ピアノ独奏のための《波》
アウリス・サッリネン:前奏曲とタンゴ序曲
エルッキ=スヴェン・トゥール:チェロとピアノのための《献呈》
カレヴィ・アホ:2つのヴィオラのための《哀歌》
ペトリス・ヴァスクス:小さな夏の音楽
アルヴォ・ペルト:ピアノ独奏のための《アリーナのために》
トイヴォ・カルキ(ロバート・マクフォール編):満月
ジャン・シベリウス(ロバート・マクフォール編):孤独の歌
ウント・モノネン(ロバート・マクフォール編):おとぎの国
ジャン・シベリウス(ロバート・マクフォール編):フィンランディア賛歌 |
ミスター・マクフォールズ・チェンバー
〔シリル・ガラク(ヴァイオリン)、
ロバート・マクフォール(ヴァイオリン)、
ブライアン・シーレ(ヴィオラ)、
ス=ア・リー(チェロ)、
リック・スタッドリー(コントラバス)、
マリア・マルティノワ(ピアノ)〕 |
スコットランド発。5つの弦楽器とピアノが奏でる、ペルト、トゥール、アホ、ヴァスクス、そしてムストネンやシベリウスなど、「バルト海」東部の国々の音楽家たちによる美しくメランコリックな旋律の数々。
1996年に結成されたミスター・マクフォールズ・チェンバーは、タンゴからジャズ、ロック、コンテンポラリーなど膨大なジャンルをカバーするスコットランドのマルチ・アンサンブル。バルト海東部の国々の音楽から浮かび上がる風景と魅力をじっくりと。
※録音:2014年12月8日−9日、セント・メアリー・パリッシュ教会(ホワイトカーク、イギリス) |
| |
|
|
ウィアー:合唱作品集
詩篇第148番/私の守護天使/ヴェルチェ/
天国への昇天/小さな木/ワイルド・モジー・マウンテン/
青い空の真の夢/マドリガル/2つの人間賛歌/
光を放て、エルサレム/天よ、露をしたたらせ/
愛は私を喜んで招き入れた/エトリック・バンクス |
ケンブリッジ・ゴンヴィル&
キーズ・カレッジ合唱団
ジェフリー・ウェッバー(指揮)
マシュー・フレッチャー(オルガン)
アニー・リドフォード(オルガン) |
女流作曲家として初めて「女王の音楽師範(Master
of Queen's Music)」に任命されたジュディス・ウィアー(1954−)の合唱作品集。
ルネサンス、バロックから現代、さらにはブラジルやケルトなど膨大なレパートリーを誇るケンブリッジの実力派カレッジ合唱団が、イギリス合唱界の名女流の合唱作品を歌う。
2010年7月8日−10日の録音。 |
| |
|
|
ブダペスト国際音楽コンクール優勝から50年
デイヴィッド・ワイルド・プレイズ・ベートーヴェン
ピアノ・ソナタ第21番ハ長調 Op.53《ワルトシュタイン》
ピアノ・ソナタ第17番ニ短調 Op.31-2《テンペスト》
ピアノ・ソナタ第31番変イ長調 Op.110 |
デイヴィッド・ワイルド(ピアノ) |
イギリス、マンチェスター出身で、ソロモンとライゼンシュタイン、ナディア・ブーランジェからピアノを学んだベテラン・ピアニスト、デイヴィッド・ワイルド(1935−)。
ブーランジェに師事する転機となった1961年のリスト=バルトーク国際ピアノ・コンクール(ブダペスト国際音楽コンクール)の優勝から約50年。長き経験が光るいぶし銀のベートーヴェンを聴かせてくれている。
2009年−2010年の録音。
|
| |
|
|
シェイベル:弦楽四重奏曲集
弦楽四重奏曲第1番
弦楽四重奏曲第2番
クヮルテット・リリコ(弦楽四重奏曲第3番) |
エジンバラ弦楽四重奏団 |
|
スコットランド、エジンバラを拠点とする近現代作品のスペシャリストたち、エジンバラ弦楽四重奏団。
コダーイに作曲を学び、イギリスを活躍の場としたハンガリー人、マーチャーシュ・シェイベル(1905−60)の弦楽四重奏曲集は、初期から後期にかけての3曲を収録。
|
| |
|
|
ピアノ・チューナー 〜 スコットランドのピアノ三重奏曲集
ビーミッシュ:海の旅人
ウィアー:ピアノ・トリオ・ツー
オズボーン:ピアノ・チューナー |
フィデリオ・トリオ
アレクサンドル・マッコール・スミス
(ナレーター) |
| スコットランドのリーディング・コンポーザーたち、サリー・ビーミッシュ、ジュディス・ウィアー、ナイジェル・オズボーンのピアノ三重奏曲。全曲世界初録音。 |
 BMC BMC
|
|
|
「バルトーク&フォーク」〜バルトーク:
民族音楽にインスパイアされた男声合唱曲全集
ベラ・バルトーク(1881-1945):
4つの古いハンガリー民謡BB60(1910-12)/
夕べ BB30(1903)/スロヴァキア民謡BB77(1917)/
セーケイ民謡BB106(1932)/過ぎ去った時よりBB112(1935)/
4つの古いハンガリー民謡BB60(1910-12,改訂1926) |
タマーシュ・ブブノー(指揮)
聖エフレム男声合唱団
バラス・ソコライ・ドンゴー
(フルート、バグパイプ、タロガトー)
マルク・ブブノ
(ガードン[パーカッシヴ・チェロ]) |
バルトークの民謡に影響された男声合唱曲集
録音:2014 年12 月ベラ・バルトーク・ウニタリアン・パリッシュ教会,ブダペスト
[62:25]
バルトークのアカペラ男声合唱のための作品を全て収録。既発売の「バルトーク合唱曲全集」(BMC186)と比べてこのディスクが特筆に値するのはハンガリーの様々な民族楽器が合唱に花を添えていること。
クラリネットの一種でサックスに似た音色のタロガトー、吹き歌いする奇妙なフルート、バグパイプなどバルトークが民謡を採集した時に実際に聴いたであろう、活き活きとした姿がよみがえります。 |
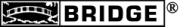 BRIDGE BRIDGE
|
|
|
ボトスタインのヒンデミット「長いクリスマスの晩餐」
オリジナルの英語版初録音!
ヒンデミット:歌劇「長いクリスマスの晩餐」(オリジナル版) |
カミーユ・サモラ(S,ルチア/ルチア2世)
サラ・マーフィー
(MS,マザー・ベイヤード/アーメンガード)
ジャレット・オット(Br,ロドリック/サム)
ジョシュ・クィン(B,ブランドン)
グレン・セヴン(T,チャールズ)
キャスリーン・マーティン(MS,ジュヌヴィエーヴ)
キャスリン・ガスリー(S,レノーラ)
スコット・マーフリー(T,ロドリック2世)
レオン・ボトスタイン(指揮)
アメリカ交響楽団 |
録音:2014年12月19日、ニューヨーク、DDD、48'49
パウル・ヒンデミットの「長いクリスマスの晩餐(ロング・クリスマス・ディナー)」オリジナル英語版の初録音。「長いクリスマスの晩餐」はヒンデミット晩年のオペラ。1
幕仕立てで1 時間にも満たない短さ、小編成のオーケストラと小振りなオペラだが、晩年のヒンデミットの熟達した筆が楽しめる作品である。
1960 年から翌年にかけて作曲、1961 年12
月にマンハイムでドイツ語訳により初演、オリジナルの英語版は1963
年3 月にジュリアード音楽院で初演された。舞台は米国の田舎町のベイヤード家。クリスマスの夜、ベイヤード家の人々が集まりディナーが始まるが、時代が徐々に進み、古い世代が亡くなり新しい世代が生まれながら、90
年ほどの時が過ぎていく。
「長いクリスマスの晩餐」には既にCDがあるが、オリジナルの英語を用いた録音はこれが初となる。珍しい作品を積極的に取り上げることで知られるレオン・ボトスタインが、長年の手兵アメリカ交響楽団を指揮して2014
年12 月19 日にリンカーン・センターのアリス・タリー・ホールで行った上演のライヴ録音。米国の優秀な若手歌手が多く起用されている。 |
| |
|
|
ロジャー・セッションズ(1896-1985):
ヴァイオリンとピアノのための作品集
(1)デュオ(1942)
(2)アダージョ(1947)
(3)ブレンダのためのワルツ(1936)
(4)ヴァイオリン・ソナタ(1953)
(5)ピアノ・ソナタ第2番(1946) |
(1)-(5)デイヴィッド・ホルツマン(Pf)
(1)(4)デイヴィッド・ボウリン(Vn) |
ロジャー・セッションズの1930〜50年代の作品集
録音:2009-2012 年 [62:17]
アメリカ作曲界の重鎮セッションズが1930
から50 年代までに書かれたピアノ、ヴァイオリンのための作品を収録。いずれも無調による厳しい音楽で新ウィーン楽派との強い親和性が見られる。 |
 GEGA NEW GEGA NEW
|
|
|
日本語解説付き!ブルガリアの作曲家ヴォデニチャロフ作品集
ヤッセン・ヴォデニチャロフ(b.1964):
(1)異教徒の歌
(2)シルバー・ドロップス
(3)蝶のメタモルフォーゼ
(4)キネティック・コンポジション
(5)5つの不思議な作品 |
(1)パスカル・ロフェ(指揮)
アンサンブル・イティネレール
(2)クワザー・サキソフォン四重奏団
(3)ロビン・ファロ(ヴィオラ・ダ・ガンバ)
(4)アンサンブル・イティネレールの独奏者達:
【フロリアン・ロリドン(チェロ)、
ナタリー・フォルジェ(オンド・マルトノ)、
棚田文紀(ピアノ)】
(5)ピエール=イブ・アルトー(オクトバスFl)、
アンヘル・ケミン(S)、
マキシヌ・エカドール(Perc)、
アントワーヌ・アレリーニ(Pf)、
ヤッセン・ヴォデニチャロフ(エレクトロニクス)、
ジャヴィエ・ゴンザレス(指揮)
フランス・フルート・オーケストラ |
※日本語解説付き 69:07
ヤセン・ヴォデニチャロフはブルガリア出身の気鋭の作曲家でソフィア国立高等音楽院で学んだ後、パリ国立高等音楽院でポール・メファノに師事した。数々のコンクールで受賞し国際的評価を得ている。
現代音楽の様々な技法を駆使しジョージ・クラムにも通じる神秘的でイマジナリーな世界が拡がる。
ブックレットには日本語解説のページもあります。 |
| |

GR 26
(2CD)
\4200 |
マルタの作曲コンクール優勝作品と特別賞作品
(1)スティーヴン=ジョセフ・サイラ(b.1984):イムディーナのカトリン
(2)パウル・ポルテッリ(b.不詳):
5つのドゥム・カルム・サイラの詩(室内オーケストラのための組曲) |
クリストファー・ムスカート(指揮)
マルタ・フィルハーモニー管弦楽団 |
録音:2014 年11 月、35:42/36:49
2012 年に開催されたAPS 銀行国際作曲コンクールの優勝作品と特別賞の受賞作品の二つを収録。このコンクールはマルタ共和国の銀行が主催するもので課題は地中海に浮かぶ島マルタ共和国を題材にした管弦楽組曲を作曲する、というものであった。ジョセフ・サイラが優勝、ポルテッリが特別賞を受賞した。
作品はどちらも現代音楽とは無縁で古典派、ロマン派を思わせる親しみ易い作風。 |
<マイナー・レーベル歴史的録音・旧録音>
.
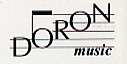 DORON DORON
|
|
|
ルビンシテインのピアノ協奏曲第4番を聴け!
マイケル・ポンティの珍しいピアノ協奏曲復刻第2弾
〜Legendary Artists シリーズ〜
(1)アントン・ルビンシテイン(1829-94):
ピアノ協奏曲第4番ニ短調Op.70
(2)シャルル=アンリ・アルカン(1813-88):
ピアノ協奏曲第2番嬰ハ短調
(3)シギスモント・タールベルク(1812-71):
ピアノ協奏曲ヘ短調Op.5 |
マイケル・ポンティ(Pf)
(1)オトマール・マーガ(指揮)
フィルハーモニア・フンガリカ
(2)パウル・アンゲラー(指揮)
プフォルツハイム南西ドイツ室内管弦楽団
(3)フォルカー・シュミット=ガーテンバッハ指揮
ベルリン交響楽団 |
録音:(1)1968 年(2)1979 年(3)1973 年 オリジナル:VOX
Turnabout、60:09
VOX レーベルに多数録音されたマイケル(ミヒャエル)ポンティの復刻第2
弾(第1集はモシェレス、ヒラー、リトルフの協奏曲集、DRC4024)。ポンティはドイツ出身のアメリカ人で渡米後にゴドフスキー門下のギルマー・マクドナルドに師事、1964
年にはブゾーニ国際コンクールに優勝。VOX レコードに知られざるロマン派作曲家のピアノ曲、ピアノ協奏曲を多数録音しました。
ここではルビンシテイン、タールベルクのほかアルカンの極めて珍しいピアノ協奏曲を収録。
アントン・ルビンシテインのピアノ協奏曲第4番。
アントン・ルビンシテインは1829年生まれのロシアの作曲家。ロシア最初の専門的な音楽教育機関を設立した人で、チャイコフスキーの師匠でもあります。
ロシアにドイツ・ロマン派の音楽を本格導入した偉人ですが、そのために民族主義的なロシア5人組と対立して、音楽史的には敗者的な位置づけになってしまってます。
でもこの人の、「前」チャイコフスキーともいうべきロシアとヨーロッパの折衷的ロマンはもっと注目されていいと思います。
このピアノ協奏曲第4番もチャイコフスキーを髣髴とさせる、いえ、それを凌駕するような美しい瞬間が何度も訪れる歴史的傑作。胸をかきむしらせる哀愁と情熱がないまぜになった激しい曲です。
これほどの傑作なのになかなか名演が現れないのが哀しいですが、超絶技巧テクニシャン、マイケル・ポンティ
の貴族的な演奏があれば満足でしょう。
でもどうでもいい話ですが、レコード製作者は経費節減のためにポンティを酷使して、寝るときも毛布一枚しか渡さなかったそうです・・・。(「どっこいクラシックは死なない!」より)
.
旧譜/第1弾 |
|
|
〜Legendary Artistsシリーズ〜
マイケル・ポンティの復刻!
(1)イグナツ・モシェレス(1794-1870):ピアノ協奏曲
ト短調Op.58
(2)フェルディナンド・ヒラー(1811-85):ピアノ協奏曲嬰ヘ短調Op.69
(3)ヘンリー・リトルフ(1818-91):交響的協奏曲第3番
変ホ長調Op.45 |
マイケル(ミハエル)・ポンティ(Pf)、
(1)オトマール・マーガ(指揮)
フィルハーモニア・フンガリカ
(2)ルイ・ド・フロマン(指揮)
ルクセンブルク放送管弦楽団
(3)フォルカー・シュミット=ゲルテンバッハ(指揮)
ベルリン交響楽団 |
VOXレーベルの看板アーティスト、マイケル・ポンティの復刻!
録音:(1)1968年ドイツ (2)1974年ルクセンブルク
(3)1978年ベルリンVox Turnabout音源よリ2013年リマスタリング
マイケル(ミハエル)・ポンティの名前を聞いて懐かしいと思う人はかなりのピアノ・マニアか、さもなくば廉価レーベルのVox
を愛好されていた方に違いない(Vox レーベルは有名楽曲から珍しい作品や現代曲までを安く、しかも全集、選集の形で出してくれたので大変ありがたかったものである)。
さてポンティはドイツ出身のアメリカのピアニストでゴドフスキーの弟子ギルマー・マクドナルドらに師事し、19
世紀型のヴルトゥオーゾを身につける。そしてVox
レコードが知られざるロマン派のピアノ曲を録音するプロジェクトに抜擢され広く知られるようになった。ここに収められたモシェレスは彼の得意のレパートリーのひとつであり、19
世紀の華麗なピアニズムを堪能できる。共演するマーガやフロマンやゲルテンバッハなどの絶妙のサポートも聴きどころ。 |
|
| |
|
|
ブリギッテ・マイヤー&アイオナ・ブラウンの端正なモーツァルト
W.A.モーツァルト(1756-1791):
ピアノ協奏曲第9番変ホ長調KV271
ピアノ協奏曲第23番イ長調KV488 |
ブリギッテ・マイヤー(Pf)
アイオナ・ブラウン(指揮)
ノルウェー室内管弦楽団 |
録音:1987 年2 月、57:49
ブリギッテ・マイヤーはスイス出身のベテラン。ウィーンの音楽アカデミーでブルーノ・ザイドルホーファーに師事、クララ・ハスキル・コンクールでは第2
位を受賞しています。モーツァルト弾きとして定評があり、これまでモントルー音楽祭、ルツェルン音楽祭、ミケランジェリ・ピアノ・フェスティヴァルなどに招待され精力的に活動しています。派手さはないものの、芯のしっかりしたタッチにイチゴの種がプチプチとはじけるような繊細な味わいがあり、バッハあたりからモーツァルト、古典派全般に適した演奏様式と言えるでしょう。よく考え抜かれた端正な音楽作りはさすがハスキル・コンクールのファイナリストと思わせます。共演のアイオナ・ブラウン&ノルウェー室内管弦楽団は少なめの弦楽でピアノの細やかな動きにも機敏に反応し好感が持てます。 |
<国内盤>
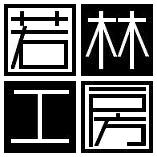 若林工房 若林工房
|

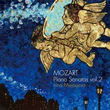
WAKA 4189-90
(2CD)
\3700(税込) |
メジューエワ/モーツァルト ピアノ・ソナタ集
vol.2
●disc-1
ピアノ・ソナタ 第8(9)番 ニ長調 K.311
(284c)
幻想曲 ハ短調 K.475
ピアノ・ソナタ 第14番 ハ短調 K.457
ピアノ・ソナタ 第16(15)番 ハ長調 K.545
●disc-2
ピアノ・ソナタ 第10番 ハ長調 K.330 (300h)
幻想曲 ハ短調 K.396 (385f)
ピアノ・ソナタ 第12番 ヘ長調 K.332 (300k)
ピアノ・ソナタ 第17(16)番 変ロ長調
K.570 |
イリーナ・メジューエワ(ピアノ) |
馥郁たる生命力 〜 天才モーツァルトの愉悦と哀しみをうたう。モーツァルト:ピアノ・ソナタ集
Vol.2 イリーナ・メジューエワ
録音: 2014〜2015 年、新川文化ホール(富山県魚津市)/STEREO
/ DSD 録音、発売元:若林工房
ロシア・ピアニズムの伝統を受け継ぐ名手、メジューエワによる好評のモーツァルト・シリーズ第二弾の登場です。
今回は1777 年にマンハイムで書かれたとされる名作ソナタK.311
と、ウィーン時代の傑作ソナタ5 曲を中心に、ソナタK.457
とセットで演奏される幻想曲(ハ短調)K.475、マクシミリアン・シュタットラーが補筆完成させた幻想曲K.396
を併録した充実のプログラム。モダン・ピアノならではの多彩な音色を駆使しながら、モーツァルトの思い描いた響きを現代に甦らせた演奏は、重ねて聴くほどに味わいが深まります。
繊細なタッチが織りなす天才作曲家の微笑とメランコリー。18
世紀ロココの理性と、それを突き破る「デモーニッシュなもの」が、不可分に、絶妙のバランスで結びついた表現には、ただ脱帽するばかり。愉悦と哀しみが一瞬のうちに入れ替わるモーツァルト音楽の陰影を濃やかに描き出した、詩情あふれるピアノ。さらなる深化をみせる至高のピアニズムをお楽しみください。
ライナーノートより
「イリーナさんの演奏には、バロック期や古典派のスタイルには不可欠の、テンポの柱が鮮やかに立っている。厳然たるイン・テンポであることは言うに及ばず、アクセントやブレス感覚の筆舌に尽くし難い見事さ、またフレージングの自然さによって、音楽が馥郁たる生命力をもって十全に息衝いているのだ。」 (真嶋雄大/ライナーノートより)
|

|
|
![]()