≪第84号アリアCD新譜紹介コーナー≫
その2 2015/9/29~
マイナー・レーベル新譜
歴史的録音・旧録音
メジャー・レーベル
国内盤
映像 |
10/2(金)紹介新譜
マイナー・レーベル新譜
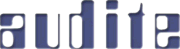 AUDITE AUDITE
|
AU 92684
(SACD HYBRID)
\2700
|
ベートーヴェン:弦楽四重奏曲全集 Vol.5
(1)弦楽五重奏曲 ハ長調 Op.29(35’ 06”)
(2)弦楽四重奏曲第15番 イ短調 Op.132(45’
24”) |
クレモナ四重奏団
【クリスティアーノ・グアルコ
(第1ヴァイオリン;ニコラ・アマティ(1640)、
パオロ・アンドレオーニ
(第2ヴァイオリン;アントニオ・テストーレ(1750)、
シモーネ・グラマーリャ
(ヴィオラ;ジョアキーノ・トラッツィ(1680-1720)、
ジョヴァンニ・スカリオーネ
(チェロ;ニコラ・アマティ(1712)】
(2)ローレンス・ダットン
(第2ヴィオラ;サミュエル・ジグムントヴィッツ(2003)) |
艶やかな美音!イタリアのクレモナ四重奏団によるベートーヴェン第5
弾は第15 番、そして、エマーソン弦楽四重奏団のヴィオラ奏者、ダットンを迎えた五重奏曲
ハ長調!
セッション録音:2014年11月24-27日/ポイリーノ(イタリア)/80’47”、ディジパック仕様
SACD ハイブリッド盤。
今やイタリアを代表するクァルテット、クレモナ四重奏団。audite
レーベルからリリースを続けているベートーヴェンの弦楽四重奏曲全曲録音の第5
集は、弦楽四重奏曲第15 番 イ短調 Op.132 そして、エマーソン弦楽四重奏団のローレンス・ダットンを迎えて弦楽四重奏曲
ハ長調 Op.29 が収録されました。
イタリア四重奏団のファルーリ、アルバン・ベルク四重奏団のバイエルレの両氏に師事した2000
年結成のクレモナ四重奏団は、イタリアの伝統受け継ぐ若手実力派で世界が注目しています。イタリアらしい明るく非常にクリアな発音が魅力の一つで、個々の音色が見事に溶け合った驚くべきアンサンブルとして現代最高の呼び声高い四重奏団といえます。
なお、当全集では曲に合わせて使用楽器を変えているところにも注目で、音色の違いを楽しむこともでき、現代の楽器も歴史的な楽器と調和し、魂のこもった演奏を聴くことができます。
ベートーヴェンのシリーズはこれまでに第1集(第16番、第11番『セリオーソ』、第6番
/ AU 92680)、第2集(第12番、第8番『ラズモフスキー第2番』
/ AU 92681)、第3集(「大フーガ」、第 4 番、第7番『ラズモフスキー第1番』
/ AU 92682)、第4集(第1番、第14番 / AU92683)がリリースされております。 |
| . |
|
|
名手ハインツマンによる20世紀のフルートとピアノによる作品集
(1)シュルホフ:フルートとフォルテピアノによるソナタ(11’57”)
(2)スミット:フルートとピアノのためのソナタ(12’
37”)
(3)ガル:3 つの間奏曲(14’35”)
(4)ラファエル:フルートとピアノのためのソナタ
ホ短調(15’23”)
(5)タンスマン:フルートとピアノのためのソナチネ(10’35”) |
アンネ=カテリーネ・ハインツマン(フルート)
トーマス・ホッペ(ピアノ) |
セッション録音:2014年9月24-26日/イエス・キリスト教会(ベルリン)/65’16”、ディジパック仕様
ドイツのフルート界の中堅を担う名手アンネ=カテリーネ・ハインツマンのaudite
レーベルからの第2 弾は20 世紀に活躍した5
人の作曲家(E. シュルホフ、L. スミット、H.
ガル、G. ラファエル、A. タンスマン)によるフルートとピアノのための作品集です。
シュルホフやタンスマンはドビュッシーなどのフランス音楽からインスピレーションを得た作品です。
ラファエルは古典的な明快さとロマンティックなメロディが魅力の作品です。
スミットはアムステルダム音楽院で学んだのち1927
年にパリに出てラヴェルとストラビンスキーから大きな影響を受けた作曲家です。1937
年にアムステルダムに戻りましたが、1943 年2
月にフルートとピアノのためのソナタを完成させましたが、同年4
月27 日にナチス・ドイツによって強制収容所に送られ、4
月30 日殺害されました。このソナタはスミットの最後の作品となりました。
アンネ=カテリーネ・ハインツマンは1999
年にフランクフルト歌劇場管弦楽団の副主席奏者に抜擢されて以来、世界的躍進を続けている女流フルート奏者。ニコレやマイゼンなど、独仏双方の匠に師事し、粋を継いだ実力派です。
トーマス・ホッペはパールマンをはじめ世界の著名な演奏者からも信頼の厚いピアニスト。近年はハインツマンとデュオを組んで演奏活動を共にしており、アンサンブルの息もぴったりです。フルート・ピアノ双方に高い演奏技術と表現力を求められる難曲尽くしのプログラムですが、常にも増す絶妙なアンサンブルで聴かせてくれます。
プーランク、ヒンデミット、デュティユー、ムチンスキ、マルタンの作品を収録したアルバム(AU
92667)と合わせてご堪能ください。
アンネ=カテリーネ・ハインツマン
前作 |

AU 92667
(SACD HYBRID)
\2600 →\2390 |
アンネ=カテリーネ・ハインツマン(Fl)
フルート・ソナタ集
(1)プーランク:フルート・ソナタ
(2)ヒンデミット:フルート・ソナタ 変ロ調
(3)デュティユー:ソナチネ
(4)ムチンスキ:フルート・ソナタop.14
(5)マルタン:フルートとピアノのためのバラード |
|
アンネ=カテリーネ・ハインツマン(Fl)
トーマス・ホッペ(Pf) |
ドイツの中堅、ハインツマンによる20 世紀フルート・ソナタ集
録音:2012 年6 月26-28 日、イエス・キリスト教会(ベルリン)/59’46”
ドイツのフルート界の中堅を担う名手アンネ=カテリーネ・ハインツマンが、AUDITE
レーベルより初となるソナタ・アルバムをリリースしました!プーランク、ヒンデミットといった20
世紀の作品を中心としたプログラムとなっています。
ハインツマンは1999 年にフランクフルト歌劇場管弦楽団の副主席奏者に抜擢されて以来、世界的躍進を続けている女流フルート奏者。A.
ニコレやP. マイゼンなど、独仏双方の匠に師事し、粋を継いだ実力派だけに期待もひとしおと言ったところでしょう。
4 曲目には、2010 年に惜しまれながらも逝去したアメリカの現代作曲家ムチンスキのソナタを収録。ジャズの要素を取り入れた独特のリズム感が魅力的で、ピアノとフルートが息を呑むほどの勢いでリズムの応酬を繰り広げます。激しい掛け合いの中にも垣間見える、民族的なメロディも聴き所。
ピアノ伴奏を務めるのはI. パールマンやJ.
ベルらとも共演経験のあるベテラン、トーマス・ホッペ。ハインツマンとはデュオを組んで演奏活動を共にしており、アンサンブルの息もぴったりです。フルート・ピアノ双方に高い演奏技術と表現力を求められる難曲尽くしのプログラムですが、常にも増す絶妙なアンサンブルで聴かせてくれます。
録音場所はお馴染みのイエス・キリスト教会。高音質SACD
Hybrid 盤ということで、多くの名演を生んだ教会の素晴らしい音響と共に、ハインツマンの澄んだフルートの音色を存分に堪能できます。 |

|
.
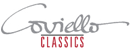 COVIELLO COVIELLO
|
|
|
プリマドンナ~ベルリン放送響首席オーボエ奏者クララ・デント
オーボエによるオペラ・アリア編曲集(タルクマン編)
ヴェルディ:歌劇「シチリア島の夕べの祈り」~ありがとう、愛する友よ
プッチーニ:愛の短い物語
ロッシーニ:歌劇「アルミーダ」~甘き愛の帝国では
ヴェルディ:歌劇「椿姫」~さようなら、過ぎ去った日よ
プッチーニ:歌劇「ラ・ボエーム」~太陽と愛(朝の歌)
ヴェルディ:歌劇「アイーダ」~おお、わが故郷
グルック:歌劇「パリーデとエレーナ」~ああ、私のやさしい熱情が
モーツァルト:歌劇「フィガロの結婚」~幸せな日々はどこへ
ウェーバー:歌劇「魔弾の射手」~コンチェルティーノ
ロッシーニ:歌劇「チェネレントラ」~悲しみと涙のうちに生まれ
ワーグナー:ヴェーゼンドンク歌曲集~夢
タルクマン:インテルメッツォ~アレグロ |
クララ・デント(オーボエ)
ペーター・ブルンス(指揮)
ライプツィヒ・メンデルスゾーン・
カンマーオーケストラ |
新たな歌姫の登場!オーボエが奏でるオペラ・アリア集
録音:2014年6月15-17日 ライプツィヒ、MDRスタジオ/61’48
ベルリン放送交響楽団の首席オーボエ奏者クララ・デントが吹く、オーボエによるオペラ・アリア編曲集。オーボエのためのレパートリーは比較的豊富ではありますが、彼女は特別なレパートリーを模索していました。ドイツで活躍中の作曲家であり編曲家のアンドレアス・N・タルクマンに、オーボエ用にオペラ・アリアを編曲することをお願いしました。オーボエの音色は女性の歌声に近いとも言われており、タルクマンの編曲ははじめからオーボエのために作曲されたのでは?と思わせる自然な流れで、新たな歌姫を誕生させています。
クララ・デントは、1973 年生まれ、父親はオーボエ奏者のサイモン・デント。ザルツブルク・モーツァルテウム、ミュンヘン音楽大学で学び、1991年にはギリシャのテッサロニキの劇場でソリスト・デビューを飾ります。その後はミュンヘン交響楽団、バイエルン放送交響楽団などと共演し、国際的なコンクールでも受賞歴が数多くある実力者。1999
年からベルリン放送響の首席を務めるほか、ベルリン・フィル、バイエルン国立歌劇場管といった一流のオケの客演もこなし、メータ、ケント・ナガノら著名な指揮者とも共演しています。現在はニュルンベルクの音楽大学で教鞭をとり、後進の指導にもあたっています。
|
 EVIL PENGUIN RECORDS EVIL PENGUIN RECORDS
|
|
|
Lignes claires ~光の線
ラヴェル:高貴で感傷的なワルツ、クープランの墓
リパッティ(1917-1950):夜想曲、左手のためのソナチネ |
ジュリアン・リベール(ピアノ) |
ベルギーが生んだ俊英にしてピリスの秘蔵っ子ジュリアン・リベール、ソロ・デビューアルバム!
録音:2013年8月&2015年8月
ベルギーが生んだ俊英ピアニスト、ジュリアン・リベール。ピリスの秘蔵っ子でもあります。「完璧な音楽家。いかなる音楽の瞬間にも、作品への真の理解、微細なものに対しての知的なアプローチと間違いない本能を統合することができる」とピリスが絶賛するリベールは1987
年生まれ。リベールは6 歳でピアノを始め、ピリスとの出会いをきっかけに、世界的に活躍の場を広げることとなりました。
このアルバムでは、ラヴェルとリパッティの作品を収録。二人の天才は完璧主義で非常に自己に対して厳しかったという共通点(光の線)で結ばれているとリベールは語っています。リベールの真摯な音楽性が光る1
枚です。
ジュリアン・リベール 演奏会予定
10/27(火)すみだトリフォニーホール[19:00開演]
パルティトゥーラ・プロジェクト「ベートーヴェン ピアノ協奏曲全曲演奏会」第1回
デュメイ(指揮)新日本フィル (リベール:第1番を演奏)
11/10(火)松本 ザ・ハーモニーホール[19:00開演]
マリア・ジョアン・ピリス&ジュリアン・リベール ピアノ・デュオ<開館30周年記念/
パルティトゥーラ・プロジェクト>
シューベルト: 4手のためのアレグロ「人生の嵐」,
4手のための幻想曲D.940ほか
|
LIGIA DIGITAL
|
|
|
C.P.E.バッハ:オルガン作品全集
[CD1]
(1)ソナタ ニ長調 Wq 70/5-H86
(2)フーガ ニ短調 Wq 119/2-H99
(3)フーガ ヘ長調 Wq 119/3-H100(アレグロ)
(4)ソナタト短調 Wq 70/6-H87
(5)フーガ ト短調 Wq 119/5-H101/5(アレグロ・ディ・モルト)
(6)フーガ イ長調 Wq 119/4-H101(アレグレット)
(7)主イエスキリスト、われ汝に呼ばわる
BWV Anh. II73
[CD2]
(1)ソナタ 変ロ長調 Wq 70/2-H134
(2)フーガ 変ホ長調 Wq 119/6-H102(アラ・ブレーヴェ・モデラート)
(3)おお神よ、何時まことなる神よ H336/1
(4)主よわれは汝の御力のままに H336/2
(5)イエス、わが信頼 H336/3
(6)ただ愛する神の御旨に従うものは H336/4
(7)来たれ、聖霊、主なる神 H 336/4
(8)深き淵より BWV Anh.745
(9)コンチェルト ト長調 Wq34-H444
(10)前奏曲 ニ長調 Wq 70/7-H107
(11)アダージョ ニ短調 H352
(12)ファンタジーとフーガ ハ短調 Wq 119/7-H75/5
(13)コンチェルト 変ホ長調 Wq 35-H446 |
オリヴィエ・ヴェルネ(オルガン)
オーヴェルニュ室内オーケストラ
アリ・ヴァン・ベーク(指揮) |
C.P.E.バッハのオルガン作品全集
録音:1998年&2014年
C.P.E. バッハのオルガン作品全集。独奏曲のほか、協奏曲も含む充実の内容を、ヴェルネの確かな演奏で味わうことができます。 |
.
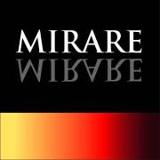 MIRARE MIRARE
|
|
|
シャニ・ディリュカ
シューベルト:ピアノ作品集~星のかけら
感傷的なワルツD.779 ~第13番
16のドイツ舞曲 D.783 ~第5番、第14番、第15番、第10番
12のワルツD.145 ~第2番、第8番
12のドイツ舞曲D.790 ~第5番、第11番、第3番
高貴なワルツD.969 ~第10番
オリジナル舞曲集D.365 ~第1番
ハンガリー風のメロディ D.817
ピアノ・ソナタ第21番変ロ長調D.960 |
シャニ・ディリュカ(ピアノ) |
シャニ・ディリュカによる魅力的なシューベルト舞曲
録音:2013年9月 フランス、ナンテール芸術文化センター/58’00
毎年ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポンにも参加している才能溢れるピアニスト、シャニ・ディリュカによるシューベルト。スリランカ出身の両親のもと、モナコで生まれ育ち、グレース王妃に見出され英才教育を受け、次世代のピアノ界を牽引する若手として成長を遂げています。
今回MIRARE レーベルより発売される新譜は、シューベルトのピアノ舞曲を中心に選曲した内容。
シューベルトは2 手および4 手のための作品をあわせると600
以上のピアノ舞曲を作曲しています。それらはすべて踊ることを目的としており、その多くが友人たちの集うシューベルティアーデで生まれた実用的な作品でありました。ちょうどシューベルトが舞曲を書き上げた時期は、貴族的な舞踏から民衆・中産階級の人々が親しむものへと変化した時代でもあり、そうした背景もあり多くの作品が生み出されました。一つ一つは短い曲ですが、次々とテンポや調性が変化する即興性があり、“星のかけら”
をひとつずつ集めて行くような楽しさがある選曲です。
アルバムの最後には、シューベルト最後のピアノ・ソナタ第21
番が収録されており、シャニ・ディリュカは、晩年の崇高で穏やかなシューベルトの世界が果てしなく広がるような雄大さを感じる演奏を聴かせてくれます。
旧譜
グレース王妃に見いだされた逸材シャニ・ディリュカ

指揮者クワメ・ライアンのベートーヴェンに期待して
MIRARE MIR 126のベートーヴェンのピアノ協奏曲集を聴いた。
ライアンはさすが懐の深いオケ伴奏を聴かせてくれて、主役のピアノが出てくるまでにたっぷりこちらを酔わせてくれる。ときどきあまりに冒頭のオーケストラがすばらしすぎてその曲が何の曲だったか分からなくなる協奏曲録音があるが、まさにこれがそういうアルバム。
ライアン、本当にいい指揮者。
ところがまったく期待していなかったピアノのシャニ・ディリュカがよかった。
モデル系のルックスから勝手にギスギスの痩せた演奏を想像していたが、いやいや、なかなかふくよかで温かい。だからライアンの大スケールのオーケストラともぴったり。しかもピアノの音色を慈しむようなソロの場面でのていねいな語り口。感性も豊かだが、この人相当頭もいいとみた。
|
|
ベートーヴェン:
ピアノ協奏曲第 2 番変ロ長調 作品 19
ピアノ協奏曲第 1 番ハ長調 作品 15 |
シャニ・ディリュカ (P)
クワメ・ライアン(指)
ボルドー・アキテーヌ国立管弦楽団 |
MIRARE レーベル 3 枚目のアルバムはベートーヴェンのピアノ協奏曲第
1 & 2 番。
演奏に関するこだわりは非常に強く、カンデンツァはヴィルヘルム・ケンプの自作を使用し、繊細でクリアな響きに魅せられた名器ベヒシュタインで演奏しています。ディリュカは繊細なタッチの変化や大胆で説得力のある音楽、そして卓越したテクニックを兼ね備えています。
指揮は、店主注目、若手有望株の指揮者クワメ・ライアン。そしてオケはもちろんボルドー・アキテーヌ国立管。注目の若手音楽家の共演で聴く瑞々しい演奏です。
録音:2010 年 4 月/64’00 |
さてそのシャニ・ディリュカはスリランカ国籍の両親のもとモナコで生まれ、幼少の頃からその才能を開花させた。
モナコといえば・・・グレース王妃。彼女、そのグレース王妃に見いだされて世界各国で英才教育を受けたらしい。まさに現代のシンデレラ・ガール。またラ・フォル・ジュルネ音楽祭などでも来日したのでご存知の方も多いと思う。これからいろいろな形でその名を聞くことになると思う。
ということで、ディリュカの映像を少し観てみますか?
まずドビュッシーのプロモーション・ビデオ。ふくよかな演奏です。
http://www.youtube.com/watch?v=9tQQUKHgBfg
.
個人的にはこのショパンが好きです。
http://www.youtube.com/watch?v=ewLmCETf1HU
.
フランス語なので何を言っているかは分からないですが、才能がほとばしり出る瞬間を味わえる。
http://www.youtube.com/watch?v=k5GsKceZRLM
で、そんなシャニ・ディリュカの最新盤が・・・どういうわけか「アメリカ音楽ピアノ作品集」。
うーん・・・これでは売れんなあ・・・とかブツブツ言いながら聴いてみたら・・・・これが絶品!あのベートーヴェンを聴かせてくれた人だけのことはある、ポップでロマンティックで洗練されていてかっこいい素敵なアルバム!!ケルアックの「路上」にインスパイアされて選曲したらしい。だからキース・ジャレットやビル・エヴァンスもいい感じで登場する。
やはりこの人、なかなかの才女。
|
|
ルート66~アメリカ音楽ピアノ作品集
・ジョン・アダムズ:中国の門
・キース・ジャレット:マイ・ワイルド・アイリッシュ・ローズ
・グレインジャー:子守唄
・バーバー:パ・ドゥ・ドゥ
・エイミー・ビーチ:ヤング・バーチズ
・ビル・エヴァンス:ワルツ・フォー・デビイ
・フィリップ・グラス:エチュード第9番
・バーンスタイン:フェリシア・モンテアレグレのために
・ジョン・ケージ:イン・ア・ランドスケープ
・ガーシュウィン(キース・ジャレット編):愛するポーギー
・バーンスタイン:間奏曲
・ヒャン-キ・ジュー:シャンデルアーズ
・ヒナステラ:優雅な乙女の踊り
・バーンスタイン:アーロン・コープランドのために
・コープランド:ピアノ・ブルース第1番「レオ・スミットのために」
・ビル・エヴァンス:ピース・ピース
・ガーシュウィン(グレインジャー編):愛が訪れた時
・コール・ポーター(ラファエル・メルラン編):恋とはなんでしょう* |
シャニ・ディリュカ(P)
ナタリー・デセイ* |
シャニ・ディリュカが選曲したアメリカ・ピアノ作品集
録音:2013 年11 月/70’00
モナコ出身のピアニスト、シャニ・ディリュカ。アメリカのビート・ジェネレーションを代表する作家ジャック・ケルアックの著書「路上(オン・ザ・ロード)」にインスパイアされて彼女自身が選曲したアメリカ・ピアノ音楽集。アルバムのタイトルにもなっている「ルート66」は、ケルアックの「路上」にも登場するシカゴとサンタモニカを結んでいた国道66
号線。今は廃線になっていますが、20 世紀中頃のポップ・カルチャーの中で度々題材とされ愛され、今なおその名が残っています。
アルバムは、ミニマル音楽のジョン・アダムズ「中国の門」にはじまり、キース・ジャレットの名曲「マイ・ワイルド・アイリッシュ・ローズ」、ジャズ・ピアニストのビル・エヴァンスの愛らしい作品「ワルツ・フォー・デビイ」、バーンスタインの奥さんフェリシア・モンテアレグレに捧げられたピアノ曲、ガーシュウィンの傑作<ポーギーとベス>からキース・ジャレット編曲の「愛するポーギー」など多彩な内容で、若い男女の青春と苦悩を描いた「路上」と同じく、喜びや切なさ、孤独感、渇望、さまざまな感情が入り混じったピアノ作品が収録されています。
さらにアルバムの最後にはコール・ポーターがミュージカル「ウェイク・アップ・アンド・ドリーム」のために作曲した「恋とはなんでしょう」をフランスの歌姫ナタリー・デセイが歌っています。穏やかな美しいデセイの歌声で響く極上の一曲となっています。
|
. それではシャニ・ディリュカのMIRAREのアルバム、あと2枚ご紹介しておきましょうね。
どちらもディリュカの資質に合ったアルバムです。メンデルスゾーンの「スコットランド・ソナタ」は知る人ぞ知る名曲。ディリュカの劇的で、しかも温かなピアノがはまってます。
|
|
|
.
 PROFIL PROFIL
|
|
|
シャラー指揮フィルハーモニー・フェスティヴァ、
2015年3月最新録音ブルックナーの交響曲第0番
ブルックナー:交響曲第0番ニ短調WAB 100
(1869) |
フィルハーモニー・フェスティヴァ
ゲルト・シャラー(指揮) |
2015年3月最新録音シャラー指揮フィルハーモニー・フェスティヴァ、ブルックナーの交響曲第0番
録音:2015 年3 月/レゲンテンバウ・バート・キッシンゲン(ライヴ)、
バイエルン放送―シュトゥーディオ・フランケン[バイエルン放送との共同製作]/DDD、ステレオ、43’29”
バンベルクに生まれたドイツの指揮者ゲルト・シャラーが進めるブルックナーの交響曲シリーズに第0
番が登場。
ブルックナー40 代半ばに書かれ、時期的に第1
番のあとの作と考えられる交響曲第0 番は、一旦楽譜冒頭に表記されていた「第2
番」の数字を、最晩年のブルックナー自らが斜線で消して“無効”
を意味するドイツ語annulirt と書き添えたことから、一連の交響曲から除外されてきました。けれども、1960
年代にハイティンク、1970 年代後半には朝比奈、バレンボイムの録音が登場し、さらにシャイー、インバル、スクロヴァチェフスキら、最近ではヤング、ボッシュのように全集録音に加える指揮者が増えつつある状況にあって、受容が進んでいるようです。
交響曲ニ短調は、すでにブルックナーの交響曲に慣れ親しんだ耳には、第1
番や第2 番に通じるブルックナー風のひびきのなかにも、かえって未知の魅力を発見する楽しみに満ちた作品といえるのかもしれません。
これまでのシリーズで高水準の演奏内容を示してきたシャラーとフィルハーモニア・フェスティヴァの顔合わせということで、この作品のさらなる認知の拡大も期待されるところです。
=シャラーによるブルックナー交響曲第0 番トラックタイム=
I.15’33 +II.11’30 +III.6’29 +IV.9’53
= TT.43’29
旧譜
シャラー/ブルックナー交響曲
▼フィルハーモニー・フェスティヴァ
フィルハーモニー・フェスティヴァは、ミュンヘンの主要なオーケストラ、すなわちミュンヘン・フィル、バイエルン放送響、バイエルン州立歌劇場管のメンバーと首席奏者たちで構成されるオーケストラ。もともとはカール・リヒターが1953
年に創設した世界的アンサンブル、ミュンヘン・バッハ管をその母体とし、偉大な伝統を振り返ることが可能ですが、レパートリーを拡大し古典派とロマン派時代の傑作群を網羅しようとして、“フィルハーモニー・フェスティヴァ”
の名称のもと、幅広い楽器編成で演奏をおこなっています。
▼ゲルト・シャラー
1965 年バンベルクに生まれたゲルト・シャラーは、1993
年にハノーファー州立歌劇場で指揮者としてのキャリアをスタートさせ、ほかにも1998
年にブラウンシュヴァイク州立歌劇場、2003
年から2006 年までマグデブルク劇場の総音楽監督を務めている実績が示すように、劇場たたき上げのマエストロ。
とりわけワーグナー、シュトラウス、ヴェルディのオペラを得意として評価も高く、そのいっぽうで、あたらしいレパートリーの開拓にも前向きなシャラーは、最近ではProfil
よりリリースされたゴルトマルクの「メルリン」のレコーディングでも注目を集めています。これまではおもに舞台作品のアルバムを発表してきたシャラーですが、ブルックナーのシンフォニーを一挙に3
曲、しかもフィナーレ補筆完成版つきの第9 番を取り上げているということで、ブルックナー・ファンにもおおいに話題を提供するのはまず間違いないなさそうです。
|
|

PH 12022
(3CD)
\5000 →\4590 |
ゲルト・シャラーによるブルックナー交響曲集ライヴ
第1,2,3番
[CD 1] 51’34”
・ブルックナー:交響曲第1番ハ短調(1866/キャラガン校訂版)
[CD 2] 70’21”
・ブルックナー:交響曲第2番ハ短調(1872/キャラガン校訂版)
[CD 3] 70’24”
・ブルックナー:交響曲第3番ニ短調(1874/キャラガン校訂版) |
|
ゲルト・シャラー(指揮)
フィルハーモニー・フェスティヴァ |
世界初録音! キャラガン校訂版によるブルックナーの交響曲集ライヴ
キャラガン校訂譜による『交響曲第3 番』1874
年版
*世界初録音/DDD、ステレオ
ブルックナー好きから快哉をもって迎えられたゲルト・シャラーによるブルックナー・シリーズに続篇が登場します。
前作に引き続き、フィルハーモニー・フェスティヴァを指揮して、すべてキャラガン校訂譜を使用した演奏内容は、2011
年7 月末に一挙にライヴ収録されたもので、交響曲第1
番から第3 番まで、初期の番号付きの3 曲を収めています。
●キャラガン校訂譜による『交響曲第3 番』1874
年版の世界初録音
ブルックナーの交響曲第3 番には、大別すると作曲時期の異なる3
つの版が存在します。作曲者が崇拝するワーグナー作品の引用をふんだんに留め、インバルを皮切りに近年、ノリントン、ナガノ、ヤング、ボッシュ、ブロムシュテットら多くの指揮者が選択する傾向にある、1872
年から1873 年にかけての第1 稿。1874 年、1876
年から1877 年にかけての、別名エーザー版ともいわれる第2
稿。そして、交響曲第8 番の初稿校了後、1888
年から1889 年にかけての第3 稿は、後期の交響曲への接近を随所に感じさせるもので、もっぱらヴァントやチェリビダッケ、ザンデルリングなどが取り上げたのもこの版でした。
ここでブルックナー研究の第一人者ウィリアム・キャラガンによると「1874
年版は、ワーグナーに献呈された1873 年初稿とは対をなす片方の複製スコア、それはブルックナーが取っておいて、1874
年におもに第1 楽章でテクスチャーにかなりの追加を書き込むことになったスコアに完全にもとづくものであり、剥き出しの1873
年初稿よりもいくぶん、カノン風の導入部は増強され、細部のリズムはより複雑に、そして全体の響きがよりあたたかく、洗練されている」とのことなので、その1873
年初稿との相違にもおおいに着目したいところです。
●キャラガン校訂譜による交響曲第1 番1866
年版、交響曲第2 番1872 年初稿版
このシャラー&シンフォニー・フェスティヴァによるライヴ盤がキャラガン校訂譜による『交響曲第3
番』1874 年版の初録音であるのに対して、キャラガン校訂譜による交響曲第1
番には、ティントナー指揮ロイヤル・スコティッシュ・ナショナル管とのセッション録音(1998
年) があり、また、キャラガン校訂譜による交響曲第2
番には、アイヒホルン指揮リンツ・ブルックナー管(1991
年)、ティントナー指揮アイルランド国立響(1996
年) によるセッション録音、シモーネ・ヤング指揮ハンブルク・フィル(2006
年)、ボッシュ指揮アーヘン響(2010 年) によるライヴ録音などがあり、いずれもブルックナー・ファンのあいだでは話題を呼んでいました。
前作のすぐれた出来ばえを踏まえると、やはりシャラー&シンフォニー・フェスティヴァの新録音には大きく期待も膨らみます。
|
|
|
|
シャラー指揮フィルハーモニー・フェスティヴァ、
ブルックナー:交響曲第4番変ホ長調「ロマンティック」
(1878年版“村の祭り” フィナーレつき/キャラガン校訂) |
フィルハーモニー・フェスティヴァ
ゲルト・シャラー(指揮) |
録音:2013年1月/レゲンテンバウ・バート・キッシンゲン、バイエルン放送―シュトゥーディオ・フランケン(ライヴ)/DDD、ステレオ、60’
11”
シャラー指揮フィルハーモニー・フェスティヴァによるブルックナーの交響曲シリーズは、アメリカの音楽学者でブルックナー研究の第一人者ウィリアム・キャラガン校訂譜に拠るすぐれた演奏内容で注目を集めており、第1
番、第2 番、第3 番、第4 番、第7 番、第8 番、第9
番がリリース済み。
2013 年にあらたにライヴ収録された第4 番は、2007
年収録の「1878 / 80 年稿、ノーヴァク版」がすでにあるため、シリーズ初の“ナンバー重複”となりますが、ここでは「村の祭り」と名付けられた、“まぼろし”
のフィナーレを採用している点が新機軸。
ブルックナー自身が「Volksfest(村の祭り、あるいは民衆の祭りとも)」と呼んだフィナーレは、第1
稿の改訂作業中の1878 年8 月1 日から9 月30
日までのあいだに作曲されたもので、通常、ブルックナーの第4
番とされる形態、すなわち、1878 年に書かれた第1、2、3
楽章の第2 稿が活かされ、1879 年から1880 年にかけて書き上げられた第4
楽章の第3 稿とを合わせたことにより、取り外されました。
このフィナーレは、ハースによって1936 年に旧全集の付録として出版され、わずかなミス・プリントを訂正した形で1980
年にノーヴァク版が再出版されていますが、演奏されることはまれ。ところどころで現行版と共通する音型があらわれるものの、全体ではずいぶんと趣きの異なる味わいで、楽章全体の長さが短い替わりに、そのぶんキャッチでユニークな内容ともなっています。
録音もこれまでにティントナー盤やロジェストヴェンスキー盤などがあったのみという状況でしたので、ノーヴァク版を念頭にキャラガンが校訂した最新録音によるすぐれた演奏の登場は、広く歓迎されるところです。
=シャラーによるブルックナー「ロマンティック」トラックタイム比較=
[2013年録音「1878年・“村の祭り”フィナーレつき・キャラガン校訂版」]
I. 19:10 + III. 14:30+ III. 10:48+
IV. 15:42= TT. 60:11
[2007年録音「1878/80年・ノーヴァク版」]
I. 17:41+ II. 14:08+ III. 11:02+
IV. 20:13= TT. 65:43
|
|
|
|
シャラー指揮フィルハーモニー・フェスティヴァ
ブルックナー:交響曲第5番変ロ長調 |
フィルハーモニー・フェスティヴァ
ゲルト・シャラー(指揮) |
注目のシリーズ最新盤、シャラー指揮フィルハーモニー・フェスティヴァ、ブルックナーの交響曲第5番
録音:2013 年7 月/エーブラハ、大修道院附属教会(ライヴ)/DDD、72’52”、ステレオ
=シャラーによるブルックナー交響曲第5 番トラックタイム=
I.19:41+II.16:27+III.13:01+IV.23:40=
TT.72:52
バンベルクに生まれたドイツの指揮者ゲルト・シャラーが進めるブルックナーの交響曲シリーズに第5
番が登場。2013 年7 月にエーブラハの大修道院附属教会で、手兵フィルハーモニー・フェスティヴァを指揮したコンサートの模様をライヴ収録したものです。
ブルックナー中期の傑作第5 番は、ヴァントやチェリビダッケら名だたるブルックナー指揮者たちがよく取り上げたことでも知られ、効果的な対位法処理、崇高なコラール、圧倒的な感銘を与えるフィナーレという具合に、内容の充実ぶりと聞きごたえでは後期の作品に並ぶ人気作でもあります。
アメリカの音楽学者でブルックナー研究の第一人者ウィリアム・キャラガン校訂譜に拠るすぐれた演奏内容で注目を集めてきた当シリーズはすでに第1
番、第2 番、第3 番、第4 番(フィナーレ異稿2
種)、第7 番、第8 番、第9 番がリリース済み。
このたびの第5 番については、キャラガン校訂譜使用との記載はなく、原典版に拠る演奏とおもわれますが、これまでの演奏がみごとなものだっただけに、やはりブルックナー好きには聞き逃せない内容といえるでしょう。
なお、2013 年9 月にライヴ収録された第6
番も近々リリースが予定されています。
|
|
|
|
シャラー指揮フィルハーモニー・フェスティヴァ、
ブルックナーの交響曲第6番
ブルックナー:交響曲第6番イ長調WAB.106 |
フィルハーモニー・フェスティヴァ
ゲルト・シャラー(指揮) |
録音:2013 年8 月/エーブラハ、大修道院附属教会(ライヴ) バイエルン放送との共同製作/DDD、ステレオ、57’30”
バンベルクに生まれたドイツの指揮者ゲルト・シャラーが進めるブルックナーの交響曲シリーズに第6
番が登場。第5 番が演奏された翌月、2013 年8
月にエーブラハ大修道院附属教会で、手兵フィルハーモニー・フェスティヴァを指揮したコンサートの模様をライヴ収録したものです。
当シリーズは、アメリカの音楽学者でブルックナー研究の第一人者ウィリアム・キャラガン校訂譜に拠るナンバーを含むことでも注目を集めてきましたが、このたびの第6
番で通常全集とされる番号付きの9 曲が揃うことになります。
中期の傑作第5 番と後期の3 曲に挟まれる第6
番は、ごつごつとした武骨なテーマで開始される第1
楽章と、対照的に哀感のこもった第2 楽章に抗しがたい魅力があり、ブルックナー演奏の第一人者ヴァントが実演でよく取り上げていたこともなるほどと思わせる作品。
このたびの第6 番については、例外的に作曲者による改訂を経ていないこともあり、キャラガン校訂譜使用との記載もありませんが、シリーズを通じてのすぐれた成果を踏まえると、ブルックナー好きにはおおきな期待を持って迎えられるものとおもわれます。
=シャラーによるブルックナー交響曲第6番トラックタイム=
I.16:38 +II.17:50+III.8:34+IV.14:25=TT.57:30 |
|

PH 13027
(2CD)
\5000 →\4590 |
キャラガン校訂1888年異版による世界初録音
ブルックナー:交響曲第8番ハ短調(1888年異版/キャラガン校訂)
オットー・キツラー父子:葬送音楽-アントン・ブルックナーの思い出に
(ゲルト・シャラーによるオーケストレーション復元) |
フィルハーモニー・フェスティヴァ
ゲルト・シャラー(指揮) |
シャラー指揮フィルハーモニー・フェスティヴァ、ブルックナーの交響曲第8
番、キャラガン校訂1888年異版による世界初録音
録音:2012 年7 月/エーブラハ、大修道院附属教会(ライヴ)/DDD、ステレオ、61’14”、38’15”
シャラー指揮フィルハーモニー・フェスティヴァによるブルックナーの交響曲シリーズは、第1
番、第2 番、第3 番、第4 番、第7 番、第9 番がリリース済みで、キャラガン校訂譜を採用していることでも注目を集めていますが、あらたに登場する第8
番もまた、キャラガンが校訂した1888 年異版にもとづく演奏内容がおおいに話題を呼びそうです。
第8 交響曲の「1888 年異版」といえば、Dermot
Gault と川?高伸の校訂によるアダージョ異版が、熱心なブルックナー好きのあいだでは知られています。これは、いわゆる第1
稿と第2 稿とのあいだの時期の1888 年頃に書かれたと考えられていて、ウィーン国立図書館所蔵の筆写譜をもとにしたものです。
アダージョ異版の録音には内藤彰の指揮で
東京ニュー・シティ・フィル演奏によるライヴ盤もありましたが、このたびのシャラーの演奏ではアダージョ異版をそのまま使用しているほかにも、前半2
楽章についても、オーストリア国立図書館収蔵のスコアに鉛筆書きで遺されていた数多くの細かい変更点も盛り込んでいるとのことですので、より徹底した「1888
年異版」としてのユニークな仕上がりが期待されるところです。
アルバムのフィルアップは、オットー・キツラー作曲の葬送音楽。ドレスデンに生まれ、リンツ大聖堂のオルガニストとリンツ劇場の楽長を務めたキツラー(1834-1915)は、ブルックナーが楽式論と管弦楽法を師事したことで知られる人物で、キツラーはまた「タンホイザー」リンツ初演を指揮して、ブルックナーがワーグナーに傾倒するきっかけを与えてもいます。
現在ではキツラー父子の共作という扱いの葬送音楽は「アントン・ブルックナーの思い出に」という副題からもわかるように、自らよりも先に逝った弟子ブルックナーに捧げたとされるオーケストラ曲。
ここでの演奏に際して、オリジナルの管弦楽版総譜とパート譜が一度も出版されず、1906
年に出版されたピアノ・デュオ版のスコアより管弦楽版の復元がなされましたが、後期ロマン派の様式を念頭に、ブルックナーの音楽語法に精通したシャラーが手掛けているのもおおいに気になるところです。
|
|

PH 11028
(4CD)
\5400 →¥4990 |
シャラー指揮ブルックナー交響曲集ライヴ 第4,7,9番
世界初録音!
フィナーレ補筆完成、2010 年キャラガン改訂版
第9 番
[CD 1]
ブルックナー:交響曲第4番変ホ長調「ロマンティック」(1878/80年版) |
[CD 2]
ブルックナー:交響曲第7番ホ長調 |
[CD 3、4]
ブルックナー:交響曲第9番ニ短調
(ウィリアム・キャラガンによるフィナーレ補筆完成2010
年改訂版による世界初録音) |
|
ゲルト・シャラー(指揮)
フィルハーモニー・フェスティヴァ |
[バイエルン放送収録による共同制作]ステレオ
[CD 1]65’43” 録音:2007 年7 月29日エーブラハ、大修道院附属教会(ライヴ)/
[CD 2]64’52” 録音:2008 年7 月29日エーブラハ、大修道院附属教会(ライヴ)
[CD 3] 36’54”/ [CD 4] 46’47” 録音:2010
年8 月1 日エーブラハ、大修道院附属教会(ライヴ)
/ バイエルン放送-シュトゥーディオ・フランケン
ブルックナー研究の第一人者ウィリアム・キャラガンが2010
年にフィナーレを復元した最新改訂版による第9
交響曲を収めた、ファン注目のアルバム。
▼キャラガン校訂2010 年改訂版フィナーレつき第9
番の世界初録音
ブルックナーの第9 交響曲は、1887 年から1894
年にかけて第1 楽章から第3 楽章までが完成されたものの、1896
年の作曲者の死によって、未完の交響曲として残されています。
遺されたスケッチの数々をもとに、フィナーレを補筆して全曲を完成する試みにはいくつもの版が存在し、キャラガン校訂によるもののほかにも主だったものとして、以下のようなものがあります。
・「サマーレ& マツーカによる1984 年フィナーレ復元版」-インバル、ロジェストヴェンスキー
・「サマーレ、フィリップス、コールス、マツーカによる1992
年フィナーレ復元版( サマーレ& コールスによる2005
年改訂)」-ボッシュ
1981 年から83 年にかけてフィナーレの復元作業を手掛けた権威ウィリアム・キャラガンによるものとしては、すでにオリジナル版、2003
年改訂版、2006 年改訂版のレコーディングがそれぞれありますが、このたび登場するのは2010
年に行われた最新改訂版。どのような内容かは聴いてのお楽しみですが、トラックタイム22
分12 秒にも及ぶ聴きごたえ十分のボリュームを有しているのはなんとも見逃せないところです。
|
|
|
|
.
 NAXOS NAXOS
|

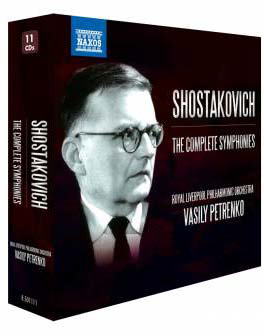
8.501111
(11CD)
\7700→\6990 |
ヴァシリーだってすごい。
ヴァシリー・ペトレンコ&ロイヤル・リヴァプール・フィル/
ショスタコーヴィチ:交響曲全集
《CD1…8.572396》
1-4.交響曲 第1番 ヘ短調 Op.10(1924-1925)/
5-10.交響曲 第3番 変ホ長調「メーデー」Op.20(1929)/
《CD2…8.572708》
1-3.交響曲 第2番 ロ長調「十月革命に捧ぐ」Op.14/
4-7.交響曲 第15番 イ長調 Op.141/
《CD3…8.573188》
1-3.交響曲 第4番 ハ短調 Op.43/
《CD4…8.572167》
1-4.交響曲 第5番 ニ短調 Op.47/
5-9.交響曲 第9番 変ホ長調 Op.70/
《CD5…8.572658》
1-3.交響曲 第6番 ロ短調 Op.54/
4-7.交響曲 第12番 ニ短調「1917年」Op.112/
《CD6…8.573057》
1-4.交響曲 第7番 ハ長調「レニングラード」Op.60/
《CD7…8.572392》
1-5.交響曲 第8番 ハ短調 Op.65/
《CD8…8.572461》
1-4.交響曲 第10番 ホ短調 Op.93/
《CD9…8.572082》
1-4.交響曲 第11番 ト短調「1905年」Op.103/
《CD10…8.573218》
1-5.交響曲 第13番 変ロ短調「バビ・ヤール」Op.113/
《CD11…8.573132》
1-11.交響曲 第14番 ト短調「死者の歌」Op.135 |
アレクサンドル・ヴィノグラードフ(バス)…CD10.11/
ガル・ジェイムズ(ソプラノ)…CD11/
ロイヤル・リヴァプール・フィルハーモニー合唱団…CD2.1-3/
ロイヤル・リヴァプール・フィルハーモニー合唱団男声セクション…CD10/
ハダースフィールド合唱協会…CD10/
ロイヤル・リヴァプール・フィルハーモニー管/
ヴァシリー・ペトレンコ(指揮) |
すっかり「もうひとりのペトレンコ」になってしまったワシーリーだが、みなさんもご存知のように3ヶ月前まではペトレンコといえばこの人だった。
そしてこのNAXOSのショスタコーヴィチで名を成したのである。
録音 2009年7月28-29日…CD1.1-4, 2008年6月22-23日…CD1.5-10,
2011年6月14日…CD2.1-3, 2010年10月26-27日…CD2.4-7,
2013年2月9-10日…CD3, 2008年7月7-8日…CD4.1-4,
2008年7月29-30日…CD4.5-9, 2010年6月23-24日…CD5.1-3,
2009年7月28-29日…CD5.4-7, 2012年6月1-3日…CD6,
2009年4月6-7日…CD7, 2009年9月11-12日…CD8,
2008年4月22-23日…CD9, 2013年9月27-29日…CD10,
2013年5月4-5日…CD11 UK リヴァプール フィルハーモニック・ホール
1976年、サンクトペテルブルクに生まれたヴァシリー・ペトレンコは、その地の音楽院でイリヤ・ムーシンをはじめ、ヤンソンス、テミルカーノフ、サロネンら錚々たる指揮者たちに指導を受け、その才能を伸び伸びと開花させました。
もちろんいくつものコンクール受賞歴を持ち、世界中のオーケストラを指揮し、喝采を浴びています。
そのペトレンコによるショスタコーヴィチ(1906-1975)の交響曲全集の登場です。
分売時から「多くの人がこれまで抱いていたショスタコーヴィチのイメージを覆す革新的な演奏」として高く評価されていた。
ワシーリー・ペトレンコ、旧譜から |
最近注目の若手指揮者の中でも、とりわけ有望株の一人であるヴァシリー・ペトレンコ。チャイコフスキーの「マンフレッド交響曲」(NAXOS
8.570568)は2009 年のグラモフォン・アウォードも受賞した。
ただ店主的にはそれほど注目してなかった。
ロイヤル・リヴァプール・フィルは面白いオケだが、それほど個性的というワケでもない。ペトレンコも、聴いたことはないが、中庸な優等生的指揮者と思っていたので。
でもこのオケがペトレンコを手放したがらず契約を延長し、さらに2013年にはオスロ・フィルハーモニー管弦楽団の首席指揮者にも就任している。そのあたりから気にはなっていたし、NAXOSからのショスタコーヴィチは評判も悪くない。
そうしたらある日ショシュタコーヴィチ・マニアのお客さんが「ペトレンコのショスタコの11番がすごい!」と言ってきた。さらに追い討ちをかけるように第10番は2011年のグラモフォン・アウォーズの交響曲部門を受賞してしまった。こうなるともうホンモノである。
NAXOSのショスタコーヴィチは正統派でしっかりした演奏だし、AVIEの2作はチャイコフスキーとラフマニノフは躍動感あふれた傑作。パワーも色彩感も兼ね備えたかなりの名演である。
今度はAVIEが彼を放したがらないかも。
|
|
|
<メジャー・レーベル>
.
 DECCA DECCA
|

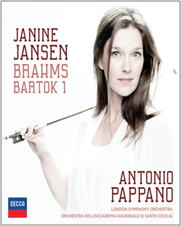
478 8412
\2300→\2090 |
ジャニーヌ・ヤンセン/ブラームス&バルトーク:ヴァイオリン協奏曲
ブラームス:①ヴァイオリン協奏曲 ニ長調
作品77
バルトーク:②ヴァイオリン協奏曲 第1番
Sz.36 |
ジャニーヌ・ヤンセン(ヴァイオリン)
ローマ・サンタ・チェチーリア音楽院管弦楽団(①)、
ロンドン交響楽団(②)
指揮:アントニオ・パッパーノ |
実力派ヴァイオリニスト、ヤンセンが艶やかに歌い上げる待望の協奏曲録音
美しき俊英、ジャニーヌ・ヤンセンがブラームス協奏曲とバルトークの協奏曲第1番の2曲を収録。
共演はアントニオ・パッパーノ、ロンドン交響楽団&ローマ・サンタ・チェチーリア音楽院管弦楽団。
オランダ生まれ(1978年7月7日)の女流ヴァイオリニスト、ジャニーヌ・ヤンセンは所謂3大ヴァイオリン協奏曲集(ベートーヴェン・ブラームス・メンデルスゾーン)と呼ばれる作品のうち、ベートーヴェン(2009年)とメンデルスゾーン(2006年)を既に録音していますので、当盤はその完結編とも呼べるもの。パッパーノの的確なサポートを得て、2曲それぞれに込められた濃密な抒情をみずみずしく描き上げています。
常に進化し続けるヤンセンの現在が美しく刻印された一枚です。
録音:2015年2月21-24日 ローマ、サンタ・チェチーリア(①) 2014年8月26日 ウォルサムストウ、アセンブリー・ホール(②)
ジャニーヌ・ヤンセンの旧譜ならこの1枚でしょうか
史上最小編成「四季」
DECCA 475 6293 1CD¥2300→¥1990
ヤンセンのアルバムならなんでもいいというわけではないが、そのなかでもこれは反則。
今までたくさんの美貌の演奏家が出てきたが、ここまでいくともう誉め文句も出てこない。
ジャケットに映るその容姿は女優並みというより、明らかにそれ以上。それでアイドルではなく本格派なのだからたまらない。アンナ・ゴウラリ、パトリシア・プティボン、村治佳織、フジ子・ヘミング(そりゃ違うか)らを次々担ぎ出し、実力派かわいこちゃん路線を推進するDECCAがそんな彼女を放っておくはずがない。
ジャニーヌ・ヤンセン。1978年オランダ生まれ。
97年コンセルトヘボウの演奏会でデビュー。あれよあれよといううちに人気アーティストの仲間入りし、1999年にはカーネギー・ホール・デビュー。2000年にゲルギエフ&キーロフと初共演、直後にオケをロッテルダム・フィルに代えて日本デビュー。2002年のロンドン・デビューで大絶賛を浴びついにデッカ・レーベルから声を掛けられることになる。さらに自ら故郷のユトレヒトで室内楽の音楽祭も主宰しマイスキーら超一流アーティストを招き共演しているという。
なんだか宇宙人のような人。
前作のDECCAデビュー・アルバムはアイドル的作品だったが、にもかかわらず批評家の評価も高く(そりゃ甘くなるわなー)、オランダ国内でも大ヒットを記録した。
そのヤンセンの第2弾が「四季」。ははあ、またアイドル路線第2弾かと思いきや、これが史上最小編成8人による演奏というのだから、ついつい食指が動いてしまう。案外女傑で指揮りたがりでぐいぐい自分の感性で音楽作りをしているかもしれない。なんたって20代で音楽祭を創設しちゃうんだから。しかも若手とはいえ大先輩の天才ラクリンをヴィオラに据えている。よほどすごいパトロンがいるか、よほど厚顔無恥か、よほど人間的に魅力があるか、よほど音楽的に優れていないとこんなアルバムを第2弾にはもってこられない。・・・聴いてみましょう。
ということで聴きました。
きっとその美貌に惑わされているに違いない・・・。こんなぽっとでのアイドル系ヴァイオリニストの演奏に惹かれるはずがない・・・。しかしなんとなく高貴で気品ある正統派音楽作りと、小編成演奏による斬新な演奏に、ヤンセンであることを忘れて何回も聴いてしまった。悪くないんです。ほんとに。(「やっぱりクラシックは死なない!」)
|
|
|
| . |
 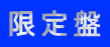
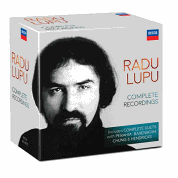
478 8772
(28CD)
\14000→\12990 |
《ラドゥ・ルプー~1970~92年録音全集》
【CD1】
モーツァルト:
ピアノ協奏曲第21番ハ長調K.467,
ピアノ協奏曲第12番イ長調K.414~
ウリ・セガル(指揮)イギリス室内管弦楽団[1974年録音],
モーツァルト:ピアノと管楽のための五重奏曲変ホ長調K.452~
ハン・デ・フリース(オーボエ)ゲオルク・ピーターソン(クラリネット)
ヴィセンテ・サルソ(ホルン)ブライアン・ポラード(ファゴット)[1984年録音]/
【CD2】
ベートーヴェン:
ピアノ協奏曲第1番ハ長調Op.15,
ピアノ協奏曲第2番変ロ長調Op.19~
ズービン・メータ(指揮)イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団[1979年録音]/
【CD3】
ベートーヴェン:
ピアノ協奏曲第3番ハ短調Op.37,
ピアノ協奏曲第4番ト長調Op.58~
ズービン・メータ(指揮)イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団
[1979&1977年録音]/
【CD4】
ベートーヴェン:
ピアノ協奏曲第5盤変ホ長調Op.73「皇帝」~
ズービン・メータ(指揮)イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団[1979年録音],
ベートーヴェン:ピアノと管楽のための五重奏曲変ホ長調Op.16~
ハン・デ・フリース(オーボエ)
ゲオルク・ピーターソン(クラリネット)ヴィセンテ・サルソ(ホルン)
ブライアン・ポラード(ファゴット)[1984年録音]/
【CD5】
ベートーヴェン:
ロンドOp.51, 創作主題による32の変奏曲ハ長調
WoO.80,
ピアノ・ソナタ第19番ト短調Op.49-1,
ピアノ・ソナタ第20番ト長調Op.49-2[1979&1977年録音],
ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第3番ハ短調Op.37~
ローレンス・フォスター(指揮)ロンドン交響楽団[1970年録音]/
【CD6】
ベートーヴェン:
ピアノ・ソナタ第14番嬰ハ短調 Op.27-2「月光」,
ピアノ・ソナタ第8番ハ短調 Op.13「悲愴」,
ピアノ・ソナタ第21番ハ長調 Op.53「ワルトシュタイン」[1972年録音]/
【CD7】
シューベルト:
ピアノ・ソナタ第16番イ短調 D.845,
ピアノ・ソナタ第18番ト長調 D.894「幻想」[1979&1974年録音]/
【CD8】
シューベルト:
ピアノ・ソナタ第5番変イ長調, 2つのスケルツォ
D.593,
楽興の時 D.780, ピアノ・ソナタ第19番ハ短調
D.958[1974&1981年録音]/
【CD9】
シューベルト:
ピアノ・ソナタ第20番イ長調 D.959,
ピアノ・ソナタ第14番イ短調 D.784,
ピアノ・ソナタ第1番ホ長調 D.157[1976,
1970, 1979年録音]/
【CD10】
シューベルト:
ピアノ・ソナタ第13番イ長調 D.664,
ピアノ・ソナタ第21番変ロ長調 D.960[1991年録音]/
【CD11】
シューベルト:
4つの即興曲 D.899, 4つの即興曲 D.935[1982年録音]/
【CD12】
シューマン:
フモレスケ変ロ長調 Op.20, 子供の情景
Op.15,
クライスレリアーナ Op.16[1993年録音]/
【CD13】
シューマン:ピアノ協奏曲イ短調Op.54,
グリーグ:ピアノ協奏曲イ短調Op.16~
アンドレ・プレヴィン(指揮)ロンドン交響楽団[1973年録音]/
【CD14】
ブラームス:ピアノ協奏曲第1番ニ短調Op.15~
エド・デ・ワールト(指揮)ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団[1974年録音]/
【CD15】
ブラームス:
ピアノ・ソナタ第3番へ短調 Op.5,
主題と変奏曲ニ短調(原曲:弦楽六重奏曲第1番~第2楽章)[1981年録音]/
【CD16】
ブラームス:
2つのラプソディ Op.79, 3つの間奏曲 Op.117,
6つのピアノ小品 Op.118, 4つのピアノ小品
Op.119[1970&1976年録音]/
【CD17】
モーツァルト:
ヴァイオリン・ソナタ第25番 ト長調 K.301,
ヴァイオリン・ソナタ第26番 変ホ長調 K.302,
ヴァイオリン・ソナタ第27番ハ長調 K.303,
ヴァイオリン・ソナタ第28番ホ短調 K.304,
ヴァイオリン・ソナタ第30番ニ長調 K.306~
シモン・ゴールドベルク(ヴァイオリン)[1974年録音]/
【CD18】
モーツァルト:
ヴァイオリン・ソナタ第24番ハ長調 K.296,
ヴァイオリン・ソナタ第32番ヘ長調 K.376,
ヴァイオリン・ソナタ第33番ヘ長調 K.377,
ヴァイオリン・ソナタ第34番変ロ長調 K.378~
シモン・ゴールドベルク(ヴァイオリン)[1974年録音]/
【CD19】
モーツァルト:
ヴァイオリン・ソナタ第29番イ長調 K.305,
ヴァイオリン・ソナタ第35番ト長調 K.379,
ヴァイオリン・ソナタ第36番変ホ長調 K.380,
ヴァイオリン・ソナタ第40番変ロ長調 K.454~
シモン・ゴールドベルク(ヴァイオリン)[1974年録音]/
【CD20】
モーツァルト:
ヴァイオリン・ソナタ第41番変ホ長調 K.481,
ヴァイオリン・ソナタ第42番イ長調 K.526,
ヴァイオリン・ソナタ第43番ヘ長調 K.547~
シモン・ゴールドベルク(ヴァイオリン)[1974年録音]/
【CD21】
モーツァルト:
2台のピアノのための協奏曲変ホ長調K.365,
2台のピアノのための協奏曲ヘ長調K.242(2台用版)~
マレイ・ペライア(指揮&ピアノ)イギリス室内管弦楽団[1988年録音],
モーツァルト:
幻想曲ヘ短調 K.608,
4手のためのアンダンテと5つの変奏曲ト長調K.501[1990年録音]/
【CD22】
モーツァルト:2台のピアノのためのソナタ
ニ長調K.448,
シューベルト:幻想曲へ短調 D.940~マレイ・ペライア(ピアノ)[1984年録音]/
【CD23】
シューベルト:
ヴァイオリンとピアノのためのソナチネ
ニ長調 D.384,
ヴァイオリンとピアノのためのソナチネ
ト短調 D.408,
ヴァイオリンとピアノのためのソナチネ
イ短調 D.385,
ヴァイオリンとピアノのためのソナチネ
イ長調 D.574~
シモン・ゴールドベルク(ヴァイオリン)[1978&1979年録音]/
【CD24】
シューベルト:
ヴァイオリンとピアノのための幻想曲 ハ長調
D.934~
シモン・ゴールドベルク(ヴァイオリン)[1979年録音]/
【CD25】
シューベルト:
3つの軍隊行進曲Op.51, D.733,
創作主題による8つの変奏曲変イ短調Op.35,
D.813,
グラン・デュオ・ソナタ ハ長調Op.140,
D.812~
ダニエル・バレンボイム(ピアノ)[1996年録音]/
【CD26】
シューベルト:
月に寄せるさすらいの歌 D.870, 盲目の少年
D.833,
独りずまい D.800, 夜と夢 D.827, ズライカ1
D.720,
ガニメード D.544, 憩いなき恋 D.138, 旅人の夜の歌
D.768,
ます D.550, ズライカ2 D.717, ミューズの子
D.764,
ミニヨンの歌 D.877, トゥーレの王 D.367,
糸を紡ぐグレートヒェン D.118, 君はわが憩い
D.776,
春に D.882, シルヴィアに D.891~バーバラ・ヘンドリックス(ソプラノ)[1985年録音]/
【CD27】
シューベルト:
愛の便り D.957-1, セレナード D.957-4,
笑いと涙 D.777,
男は人が悪い D.866-3, 流れの上で D.943,
あこがれ D.879,
月に寄す D.193, 遊びにおぼれて D.715,
岩上の羊飼 D.965,
汝はわれを愛さず D.756, 愛は裏切られ
D.751, 若い尼僧 D.828,
嘆きの歌 D.23, エレンの歌 III(アヴェ・マリア)
D.839,
デルフィーヌの歌 D.857-1, 野ばら D.257~
バーバラ・ヘンドリックス(ソプラノ)[1992年録音]/
【CD28】
フランク:ヴァイオリン・ソナタ イ長調,
ドビュッシー:ヴァイオリン・ソナタ ト短調~
チョン・キョンファ(ヴァイオリン)[1977年録音] |
ラドゥ・ルプー(ピアノ) |
鍵盤を超越するピアノ界のコロンブス
「千人に一人のリリシスト」が残したピアノの至芸
リパッティの再来と称せられ「千人に一人のリリシスト」と謳われたピアニスト、ラドゥ・ルプー。彼の70歳を記念して、1970~92年に残した録音を集めた28枚組です。
ベートーヴェン、ブラームス、シューベルト、シューマン、いずれの名曲も、透明な音色で美しく紡ぎ出した珠玉の名録音。メータ、デ・ワールト、プレヴィンら、錚々たる巨匠たちの巧みなサポートも光る珠玉の協奏曲。
シモン・ゴールドベルクとのモーツァルトとシューベルトのヴァイオリン・ソナタ、チョン・キョンファとのフランスのヴァイオリン・ソナタ。
Deccaへの録音以外にも、Teldecへのバレンボイムとのデュエット,
Sonyへのペライアとのデュエット、旧EMIへのバーバラ・ヘンドリックスとのシューベルトの歌曲集なども含む。
なお、購入者が日本語解説をダウンロードできるサイトを開設する予定です。
2010年の記事から・・・
先日プラハに行った。
「プラハの春」に合わせて、コンサートもいくつか行ってきた。目玉はペライア弾き振りのモーツァルトだったが、それは、まあ、普通だった。
一方、ちょうどめぐり合わせが良くてたまたま聴くことになったのがルプーのシューマンのピアノ協奏曲。
ラドゥ・ルプー。
一時期DECCAから大量の録音が出ていたことはみなさんご存知だと思うが、1990年代初めにシューマンがリリースされて以降新録音はまったく出ていない。おまけに日本でのコンサートも10年近く開かれていないから、店主のように「あら、ルプーってまだいたの」と思われた方も多いと思う。
なので今回も、「千人に一人のリリシスト」というちょっと恥ずかしいようなコピーでレコード・ショップを賑わしていたころを懐かしむように、そのシューマンを聴きに行った。
ルプー、まだ元気かな?と。
そうしたら・・・!
本当にごくごくたまにあるのだが、ステージ上にその人が現れただけで会場全体の雰囲気がガラリと変わってしまうことがある。
このときのルプーがまさにそれ。
現れたルプーは、かつてCDジャケットで見たような、若いのか年寄りなのか分からない髭の青年などではもちろんなく、どこからどう見ても老哲学者。いや、仙人に近い。いま山から下りて来ました、というような風貌。
そのまま天に向かって両手を挙げて何か叫び始めても全然おかしくない・・・そんな雰囲気。
そんな姿でよろりステージに現れたルプー、ピアノにたどり着くまでに客席を一度軽く見据えた。途端、会場全体が「しん」と静まり返った。みながゴクリと息を呑んでたじろいでいるのが空気で分かる。というより、店主が何より一番凍っていた。・・・とにかくただならぬ気配なのである。
で、それはシューマンの冒頭の「ジャランジャランジャラン」から、客席にご威光が投げかけられる感じで始まった。
・・・そう、これはルプーの祈祷コンサートだったのである。
ピアノのひとつひとつの旋律はまさに呪文のごとく響き、オーケストラはまるで取り巻き信者のように、その呪文を守り増長させるために歌う。
素敵なピアニストの演奏に出会うと店主は、「ひとつひとつの旋律に、歌が、意味が、心がある。」、なんてことをよく言う。だがルプーの場合そんなものじゃない。初めに何か途方もない確信・信念のようなものがあって、そこから音楽が滲み出てくる感じなのである。あたかも山の巨大な岩石の裂け目から泉が沁みだしてくるように。音楽の解釈だとか、演奏上のなんだとかかんだとかは、この人の前ではほとんど意味がない。だから変なことを言うようだが、ここで音楽は主役ではなく、ひとつの手段に過ぎない。重要なのはルプーがどう生きていて、何を考えて、何を思っているか。そしてそれを投げかけられた我々が、どう思い、どう考え、どう生きるか。
ルプーがあの日ステージ上から放ったのは、そうした、人間の原存在的なものを露わにしてしまうような、「音楽」を超えたものだった。
日本に帰って、今年(2010年)ルプーの来日公演があることを知った。
さっきも書いたが、来日は9年ぶり。現在は一切の録音を断っているから、今のルプーを聴くのはコンサートしかない。さらにインタビューのたぐいも一切拒否しているというから、ルプーという人が今音楽に何を求めているかはおのずと分かってくる。もしタイミングが合う人は行っておいたほうがいい。
さて、そんなルプーのCD。
先ほども言ったようにルプーは90年代初頭までにDECCAから多くの録音を出していた。・・・が、おそらく当時から商業用録音や商業用パフォーマンスに何らかの嫌悪感を抱いていたのだろう。なので、いずれも素敵な演奏ではあるが、現在の超越的なルプーを知るのにそれらのCDは有効な手立てとはならないかもしれない。
だが、1枚だけ、紹介したいCDがある。
67年のベートーヴェンのピアノ協奏曲第3番。
ルーマニアELECT RECORDS。この曲を3回録音しているルプーの最初のもの。
全部で41分という異常演奏。3回目のメータとの演奏が36分(まあ、これが普通)ということを考えると、この1回目の録音がどんなに遅いかわかると思う。
同曲録音のおそらく最長記録となるのではないか。
ブゲーヌの指揮がのっけから遅いから、両者によって画策された確信犯的な演奏と思われるが、聴いていただければおわかりのとおり、その後のDECCA録音で聴ける端正で抒情的な演奏とは一味も二味も違う。確かに美しくなまめかしいが、明らかに劇薬。
このときルプー、22歳。
クライバーン・コンクール、エネスコ・コンクール優勝直後。これは、師ネイガウスによってその野心的な個性をはばたかせた天才青年が残した、純粋且つ自由な録音なわけである。
そしてルプーはこの録音の2年後、リーズ国際コンクールの最終審査でもこの第3番を演奏。審査員の度肝を抜いて、もちろん優勝を果たした。そうしてDECCAでメジャー・デビュー。その後20年間、第一線で「知性派、兼、抒情派」ピアニストの第一人者として大衆的人気を勝ち得て、がんばったわけである。
・・・そう、おそらく、がんばったのだ。ちょっと無理して。
で、無理があったから・・・リタイアしてしまったのだ。
DECCAの録音、とっても素敵で、店主も良く聴いていたが、間違っても毒はない。ギラギラした野心もない。このベートーヴェンの3番の劇薬のような個性はない。言ってみれば良薬である。
しかし、今回プラハで聴かせてくれたルプーの音楽は、そうした良薬の延長上にはないような気がする。・・・どちらかというと、この67年のベートーヴェンの第3番のほうが、匂いは近い。とくに第1楽章終盤3分の異様な圧迫感は、あの日のコンサートを思い出させる。
あの日ステージ上からルプーが放っていた、聴く人の息を止め、心臓を抜き取るような強烈なオーラは、DECCA録音よりこの22歳の録音のほうに強く感じることができるのだ。
|
これだけ宣伝しておいて入らなかったほんとにごめんなさい!
というか、入らない可能性高い・・・
|
|
| . |
 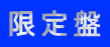
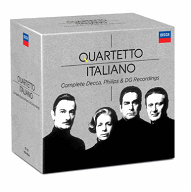
478 8824
(37CD)
\15000→\13990 |
《イタリア弦楽四重奏団~フィリップス&デッカ録音全集》
【CD1】
ベートーヴェン:
弦楽四重奏曲第7番ヘ長調Op.59-1「ラズモフスキー第1番」,
弦楽四重奏曲第9番ハ長調Op.59-3「ラズモフスキー第3番」
[1952&1949年録音]/
【CD2】
モーツァルト:
弦楽四重奏曲第2番ニ長調K.155,
クラリネット五重奏曲イ長調K.581~
アントワーヌ・ド・バヴィエ(クラリネット)[1952年録音]/
【CD3】
ハイドン:弦楽四重奏曲第81番ト長調Op.77-1,
ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第6番変ロ長調Op.18-6[1952年録音]/
【CD4】
モーツァルト:
弦楽四重奏曲第19番ハ長調K.465「不協和音」,
アダージョとフーガ ハ短調K.546,
弦楽四重奏曲第23番 ヘ長調K.590「プロシャ王第3番」[1952年録音]/
【CD5】
ハイドン:弦楽四重奏曲第68番変ホ長調Op.64-6,
ボッケリーニ:弦楽四重奏曲ニ長調Op.6-1,
シューマン:弦楽四重奏曲第2番ヘ長調Op.41-2,
ヴェルディ:弦楽四重奏曲ホ短調[1948&1950年録音]/
【CD6】
シューベルト:
弦楽四重奏曲第13番イ短調D.804「ロザムンデ」,
弦楽四重奏曲第8番変ロ長調D.112,
弦楽四重奏曲第12番ハ短調D.703「四重奏断章」[1952&1949年録音]/
【CD7】
モーツァルト:
弦楽四重奏曲第1番ト長調 K.80,
弦楽四重奏曲第2番 ニ長調 K.155,
弦楽四重奏曲第3番ト長調 K.156,
弦楽四重奏曲第4番ハ長調 K.157,
弦楽四重奏曲第5番 ヘ長調 K.158[1970&1971年録音]/
【CD8】
モーツァルト:
弦楽四重奏曲第6番変ロ長調 K.159,
弦楽四重奏曲第7番変ホ長調 K.160,
弦楽四重奏曲第8番ヘ長調 K.168,
弦楽四重奏曲第9番イ長調 K.169[1971&1973年録音]/
【CD9】
モーツァルト:
弦楽四重奏曲第10番 ハ長調 K.170,
弦楽四重奏曲第11番変ホ長調 K.171,
弦楽四重奏曲第12番変ロ長調 K.172,
弦楽四重奏曲第13番ニ短調 K.173[1973年録音]/
【CD10】
モーツァルト:
弦楽四重奏曲第14番ト長調K.387,
弦楽四重奏曲第15番ニ短調K.421[1966年録音]/
【CD11】
モーツァルト:
弦楽四重奏曲第16番変ホ長調K.428,
弦楽四重奏曲第17番変ロ長調K.458「狩」[1966年録音]/
【CD12】
モーツァルト:
弦楽四重奏曲第18番イ長調K.464,
弦楽四重奏曲第19番ハ長調K.465「不協和音」[1966年録音]/
【CD13】
モーツァルト:
弦楽四重奏曲第20番ニ長調K.499「ホフマイスター」,
弦楽四重奏曲第21番ニ長調K.575「プロシャ王第1番」[1971年録音]/
【CD14】
モーツァルト:
弦楽四重奏曲第22番変ロ長調K.589「プロシャ王第2番」,
弦楽四重奏曲第23番ヘ長調K.590「プロシャ王第3番」[1972年録音]/
【CD15】
モーツァルト:
ディヴェルティメント ニ長調K.136,
ディヴェルティメント 変ロ長調K.137,
ディヴェルティメント ヘ長調K.138,
アダージョとフーガ ハ短調K.546[1972年録音]/
【CD16】
ハイドン:
弦楽四重奏曲第67番ニ長調Op.64-5「ひばり」,
弦楽四重奏曲第17番ヘ長調Op.3-5「セレナード」,
弦楽四重奏曲第76番ニ短調Op.76-2「五度」[1965年録音]/
【CD17】
ハイドン:
弦楽四重奏曲第77番ハ長調Op.76-3「皇帝」,
弦楽四重奏曲第78番変ロ長調Op.76-4「日の出」[1976年録音]/
【CD18】
ボッケリーニ:
弦楽四重奏曲ニ長調Op.6-1,
弦楽四重奏曲変ホ長調Op.6-3,
弦楽四重奏曲変ホ長調Op.58-2[1976年録音]/
【CD19】
ベートーヴェン:
弦楽四重奏曲第1番ヘ長調Op..18-1,
弦楽四重奏曲第2番ト長調Op.18-2[1972&1975年録音]/
【CD20】
ベートーヴェン:
弦楽四重奏曲第3番ニ長調Op.18-3,
弦楽四重奏曲第4番ハ短調Op.18-4[1972&1975年録音]/
【CD21】
ベートーヴェン:
弦楽四重奏曲第5番イ長調Op.18-5,
弦楽四重奏曲第6番変ロ長調Op.18-6[1973年録音]/
【CD22】
ベートーヴェン:
弦楽四重奏曲第7番ヘ長調Op..59-1「ラズモフスキー第1番」[1973年録音]/
【CD23】
ベートーヴェン:
弦楽四重奏曲第8番ホ短調Op.59-2「ラズモフスキー第2番」,
弦楽四重奏曲第11番ヘ短調Op.95「セリオーソ」[1973&1971年録音]/
【CD24】
ベートーヴェン:
弦楽四重奏曲第9番ハ長調Op.59-3「ラズモフスキー第3番」,
弦楽四重奏曲第10番変ホ長調Op.74「ハープ」[1973&1971年録音]/
【CD25】
ベートーヴェン:
弦楽四重奏曲第12番変ホ長調Op.127,
弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調Op.131[1968&1969年録音]/
【CD26】
ベートーヴェン:
弦楽四重奏曲第13番変ロ長調Op.130,
弦楽四重奏曲第16番ヘ長調Op.135[1969&1968年録音]/
【CD27】
ベートーヴェン:
弦楽四重奏曲第15番イ短調Op.132, 大フーガOp.133[1967&1969年録音]/
【CD28】
シューベルト:
弦楽四重奏曲第14番ニ短調D.810「死と乙女」,
弦楽四重奏曲第13番イ短調D.804「ロザムンデ」[1965&1976年録音]/
【CD29】
シューベルト:
弦楽四重奏曲第15番ト長調D.887,
弦楽四重奏曲第12番ハ短調D.703「四重奏断章」[1977&1965年録音]/
【CD30】
シューベルト:
弦楽四重奏曲第10番変ホ長調D.87,
弦楽四重奏曲第14番ニ短調D.810「死と乙女」,
弦楽四重奏曲第12番 ハ短調「四重奏断章」[1976,
1979, 1979年録音]/
【CD31】
ブラームス:
弦楽四重奏曲第1番ハ短調Op.51-1,
弦楽四重奏曲第3番変ロ長調Op.67[1967&1971年録音]/
【CD32】
ブラームス:弦楽四重奏曲第2番イ短調Op.51-2
[1970年録音]/
【CD33】
シューマン:
弦楽四重奏曲第1番イ短調Op.41-1,
弦楽四重奏曲第2番ヘ長調Op.41-2,
弦楽四重奏曲第3番イ長調Op.41-3[1967,
1971, 1970年録音]/
【CD34】
ドヴォルザーク:弦楽四重奏曲第12 番ヘ長調Op.96「アメリカ」,
ボロディン:弦楽四重奏曲第2 番ニ長調[1968年録音]/
【CD35】
ドビュッシー:弦楽四重奏曲ト短調Op.10,
ラヴェル:弦楽四重奏曲ヘ長調M.35[1965年録音]/
【CD36】
ウェーベルン:
弦楽四重奏のための緩徐楽章, 弦楽四重奏曲,
弦楽四重奏のための5つの断章Op.5,
弦楽四重奏のための6つのバガテルOp.9,
弦楽四重奏曲Op.28[1970年録音]/
【CD37】
ブラームス:ピアノ五重奏曲ヘ短調Op.34~
マウリツィオ・ポリーニ(ピアノ)[1979年録音] |
イタリア弦楽四重奏団 |
叙情的で艶やかな格調高き音色 ◆結成70周年記念!◆
イタリア弦楽四重奏団は、1945年に作曲家マリピエロの提唱で、北イタリアのレッジョで結成された弦楽四重奏団。1980年代初頭まで活躍し、流麗で明快な響き、緊密に絡み合う絶妙なアンサンブルで、様々な弦楽四重奏曲の名作の魅力を生き生きと表出してきました。
当セットは彼らの結成70年を記念して、フィリップスとデッカに録音されたものを全て収録。そのうち10枚は初CD化となるものが含まれ、37枚目にはマウリツィオ・ポリーニとの共演によるブラームスのピアノ五重奏曲が収められています。
室内楽ファン必携のBOXといえましょう。
初CD化⇒CD1,2,3,4,15,17,18,30,33,34 |

10/1(木)紹介新譜
<国内盤>
.
ベルリン・フィル自主製作盤
BERLINER PHILHARMONIKER
ラトル&ベルリン・フィル/シベリウス交響曲全集
|


KKC 9137
(4CD+2Blu-ray)
\13000+税 |
シベリウス:交響曲全集
CD1
1-4. 交響曲第1番(37’39)/5-8. 交響曲第2番(43’12)
CD2
1-3. 交響曲第3番(28’17)/4-7. 交響曲第4番(36’50)
CD3
1-3. 交響曲第5番(30’32)
CD4
1-4. 交響曲第6番(29’13)/5-8. 交響曲第7番(21’48)
|
サー・サイモン・ラトル(指揮)
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 |
Disc1
ブルーレイ・ディスク・オーディオ
交響曲第1 - 7 番(24bit/96kHz)
● ボーナス・ビデオ
サー・サイモン・ラトル、シベリウスを語る(ドイツ語字幕のみ)
Disc2
ブルーレイ・ディスク・ビデオ
交響曲第1 - 7 番(HD Video)
● ボーナス・ビデオ
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の
デジタル・コンサート・ホールについて
特典
(1)スタジオ・マスター・クオリティーの音源(24bit/192kHz)を
ダウンロードできる、クーポンコードを封入
(2)ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の
デジタル・コンサート・ホールの7日間無料視聴コードを封入 |
注目盤。シベリウス・イヤーに真打登場!ベルリンの聴衆をも魅了したラトルの新しいシベリウス全集が完成!
[録音日]CD & BDA:2014 年12月18-20日(5番)、2015
年1月28日~2月6日(1~4番)、2015 年2月7~9日(5~7
番)
VIDEO:2015 年2月6日(1、2番)、2015 年2月7日(3、4番)、2015
年2月8日(5~7番)
録音場所:フィルハーモニー、ベルリン/[24bit/192kHz録音]/日本語帯・解説付
Disc1:2.0 PCM Stereo 24bit/96kHz、5.0
DTS-HD MA 24bit/96kHz、227分/ボーナス・ビデオ58分
Disc2:画面:Full HD 1080/60i 16:9、音声:2.0
PCM Stereo、5.0 DTS-HD MA、リージョン:All、297分
「ベルリン・フィル・レコーディングス」からサー・サイモン・ラトル指揮ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団によるシベリウス交響曲全集が発売されます。
CD4 枚とブルーレイ・ディスク2 枚がセットになった豪華パッケージ。
CD4 枚に交響曲全曲を収録、2 枚のブルーレイ・ディスクには、1
枚目に96kHz/24bit のステレオ音声とサラウンド音声で交響曲全曲とボーナス映像を収録、2
枚目はHD ビデオで交響曲全曲が収録されています。
また、192kHz/24bit ハイレゾ音源をダウンロードできるコード、さらに、デジタル・コンサート・ホールの7
日間チケットも封入されています。
ラトルは1981 ~ 1987 年にかけてバーミンガム市交響楽団とシベリウスの全集をレコーディングしており、今回が2
度目の全集録音となります。
ラトルは子供の頃からイギリス人としてシベリウスに愛着があり、リバプール・フィルで指揮者としてデビューした際も、シベリウスの交響曲第5
番を振っており、ラトルにとってシベリウスは特に思い入れのある作曲家のひとりであることがわかります。
今回のベルリン・フィルとのシベリウス・チクルスは、2002年の首席指揮者就任からの希望であり、2015
年シベリウス・イヤーを飾るにもっとも相応しい交響曲全集といえるでしょう。
[ボーナス・ビデオ~ラトル、シベリウスを語るから]
マーラーの音楽では、人間と自然、とりわけ彼自身がテーマとなっています。しかしシベリウスでは、「人がそこにいる」とは感じられません。もし人間がいるとすれば、自分自身の「不安の藪」に入り込み、捕らわれた人がいる、という意味においてでしょう。つまり、そこに足を踏み入れる者は、もう二度と帰って来られないかもしれないのです。私はシベリウスの音楽の本質は、最終的にはそこにあるような気がします。

|
マイナー・レーベル新譜
.
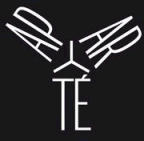 APARTE APARTE
|
|
|
吉野直子、フランスAparteレーベルから待望の新譜
ハープ協奏曲集
ロドリーゴ(1901-1999):アランフェス協奏曲(ハープ版)
カステルヌオーヴォ=テデスコ(1895-1968):小協奏曲
ドビュッシー(1862-1918):神聖な舞曲と世俗的な舞曲
トゥリーナ(1882-1949):主題と変奏 |
吉野直子(ハープ)
ロベルト・フォレス・ヴェセス(指揮)
オーヴェルニュ室内オーケストラ |
吉野直子、理想的なパートナーを得てフランスAparteレーベルから待望の新譜発売!日本語解説・帯つき仕様
録音:2015年6 月/クレルモン=フェラン(フランス)/日本語解説・帯付仕様
世界的ハープ奏者、吉野直子の待望の新譜が登場します。ハープの名協奏曲を集めた注目プログラムです。
ソロでの素晴らしさはもちろん、クレーメル、パユ・・・様々な世界的アーティストと共演しても、一寸の隙もないアンサンブルで絶大な信頼を得ている吉野が、ヴェセス指揮オーヴェルニュ室内オーケストラには「赤い糸で結ばれたような出会いは、今まで経験したことのない本当に特別なもの」を感じたというほど、オーケストラとの素晴らしいアンサンブルにも注目です。
アランフェス協奏曲の有名な第2 楽章などは曲の世界に深く引きずり込まれるようです。もともとギター曲ではありますが、ハープのために書かれたのではと思うほど。
他の作品でも管弦楽の繊細なアンサンブルと吉野のハープの絶妙なバランスと絡み合いは見事。吉野直子の世界がますます深まっていることに感じ入るとともに、スペイン出身の俊英指揮者ヴェセスの今後にも大いに期待できる新譜の登場となりました。
吉野直子
ロンドン生まれ。6 歳よりロサンゼルスでスーザン・マクドナルド女史のもとでハープを学び始める。1981
年に第1 回ローマ国際ハープ・コンクール第2
位入賞。1985 年には第9 回イスラエル国際ハープ・コンクールに参加者中最年少で優勝し、国際的キャリアの第一歩を踏み出した。これまでにベルリン・フィルハーモニー管弦楽団、イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団、チューリヒ・トーンハレ管弦楽団、フィルハーモニア管弦楽団、フィラデルフィア管弦楽団、ウィーン・コンツェントゥス・ムジクスなど、欧米の一流オーケストラおよび日本国内の主要なオーケストラと共演を重ねている。また、ザルツブルク、ロッケンハウス、ルツェルン、グシュタード、シュレスヴィヒ・ホルシュタイン、サイトウ・キネン・フェスティバル松本、マールボロ、モーストリー・モーツァルト・フェスティバルなどの世界の主要音楽祭にも度々招かれ、常に好評を博している。1985
年アリオン賞、1987 年村松賞、1988 年芸術祭賞、1989
年モービル音楽賞奨励賞、1991 年文化庁芸術選奨文部大臣新人賞、エイボン女性芸術賞をそれぞれ受賞している。国際基督教大学卒業。上野学園大学特任教授。
ロベルト・フォレス・ヴェセス
2012 年よりオーヴェルニュ室内オーケストラの首席指揮者兼芸術監督。ヴァレンシア(スペイン)出身。オーケストラとの活動は、リヨン国立管弦楽団、ルクセンブルク・フィル、プラハ・フィルハーモニアなどと共演。2015
年のラ・フォル・ジュルネ音楽祭でオーヴェルニュ室内管弦楽団と共に来日、バッハの協奏曲などを演奏、絶賛を博した。
オーヴェルニュ室内オーケストラ - Orchestre
d'Auvergne
1981 年に創設された「ヨーロッパ屈指の室内管弦楽団」(ラ・モンターニュ紙)。歴代の音楽監督にはジャン=ジャック・カントロフ、アリ・ヴァン・ベークが、現在はスペイン出身のロベルト・フォレス・ヴェセスが首席指揮者兼芸術監督を務めている。今日ではそのレパートリーをバロック音楽から現代音楽の初演にまで広げ、多方面で活躍。E.クリヴィヌ、L.ハーガー、F.ビオンディ等の客演指揮者、J=P.ランパル、M.アンドレ、A.デュメイ、M.ダルベルト、Y.バシュメットら世界的ソリストたちと共演。ニューヨーク、フィラデルフィア、ボルティモア、ミュンヘン、ジュネーヴ、ミラノ、東京、大阪等の主要なホールでたびたび演奏し、プラド、ラ・ロック・ダンテロン国際ピアノ、オーヴェル・シュル・オワーズなど著名な音楽祭から招かれている。日本各地で開催されているラ・フォル・ジュルネでも常連で、人気オーケストラのひとつである。
ロベルト・フォレス・ヴェセス来日情報
●兵庫芸術文化センター管弦楽団 第33回名曲コンサート
<オール・ベートーヴェン・プログラム>
2015年10月17日(土)15時開演/兵庫県立芸術文化センター
ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第5番「皇帝」&交響曲第6番「田園」
シプリアン・カツァリス(ピアノ)
吉野直子&ヴェセス演奏会情報
●クリスマス・コンサート~オーヴェルニュ室内管弦楽団オーケストラ&吉野直子
2015 年
12月2日(水)18:45開演/三井住友海上しらかわホール
12月3日(木)19:00 開演/東京オペラシティ
12月5日(土)17:00開演/フィリアホール
12月7日(月)19:00 開演/ザ・シンフォニーホール
ヘンデル:ハープ協奏曲/J.S. バッハ:G
線上のアリア/パッヘルベル:カノン/
マーラー:アダージェット~交響曲第5番から/チャイコフスキー:弦楽セレナード
ハ長調 op.48/
ドビュッシー:神聖な舞曲と世俗的な舞曲
ロベルト・フォレス・ヴェセス(指揮)
2016 年2月6日(土) サントリーホールブルーローズにて吉野直子リサイタル開催
|
 LSO LIVE LSO LIVE
|

LSO 0696
(SACD-HYBRID
+ DVD[PAL])
\2500 |
ゲルギエフのラヴェル・アルバムにDVDが付いて・・・
「ボレロ」全曲演奏収録の「DVD 同梱仕様版」が登場
= SACD =
ラヴェル:
(1)バレエ「ダフニスとクロエ」(全曲)
*
(2)ボレロ
(3)亡き王女のためのパヴァーヌ
=ボーナスDVD[PAL]=
・ラヴェル:ボレロ(全曲) |
ロンドン交響楽団
ワレリー・ゲルギエフ(指揮)
ロンドン・シンフォニー・コーラス* |
録音:
(1)2009年9月20 & 24日/ロンドン、バービカンホール(ライヴ)、(2)2009年12月13
& 18日/ロンドン、バービカンホール(ライヴ)、(3)2009年12月13
& 18日/ロンドン、バービカンホール(ライヴ)、
(ボーナスDVD)2009年12月18日/ロンドン、バービカンホール(ライヴ)
DSD 5.1、マルチチャンネルステレオ
SACD :78’ 36
ボーナスDVD[PAL]:リージョン:All、16 :
9、2.0 & Dolby Surround、17’33
首席指揮者ゲルギエフがロンドン響を指揮して、初めてラヴェルの作品をレコーディングしたアルバムは、当代きってのカリスマが持ち前のバレエへの適性を示したみごとな内容によりすでに高評価を得ています。
すぐれた録音でも注目され、ベストセラーを続けているこのアルバムに、あらたに「ボレロ」全曲演奏を収めたDVD(PAL
仕様)同梱仕様版が登場します。
いままでありそうでなかったゲルギエフの「ボレロ」は、映像で観るとインパクトも絶大。ニール・パーシーのスネアドラムに始まり、順々にソロを取る腕っ扱き揃いのメンバーの表情はもちろん、絵になるゲルギエフの指揮姿をバッチリと捉えたカメラワークも効果的。演奏終了後に立ちあがって割れんばかりの拍手を送る聴衆の熱狂ぶりも納得の出来栄えとなっています。
※DVDはPAL方式のため、日本国内で販売されている機器では再生できない場合があります。 |
 WERGO WERGO
|
|
|
ファン・カルロス・パス(1901 ~ 1972):作品集
(1)edalus
(2)invencion(世界初録音)
(3)Nucleos
(4)Concrecion (世界初録音) |
アンサンブル・アバンチュール
アキコ・オカベ
(ピアノ(1)、(3))、
アレクサンダー・オット(指揮(1)(4)) |
西洋音楽多国籍化の夜明け20世紀アルゼンチン作曲家、ファン・カルロス・パスの作品集
録音:2014年9月26日-28日、11月30日
20 世紀アルゼンチンの作曲家、ファン・カルロス・パスの作品集。世界初録音も2
曲含まれます。
当時、ラテンアメリカの音楽界では民族音楽をベースにした創作が主流でしたが、パスはその風潮とは一線を画し、当時の西洋音楽の動向を吸収しつつそれらを統合させるような作品を発表しました。当時ヨーロッパで盛んに使用された音楽語法の一つ、「12
音技法」を初めて南米で使用した作曲家とも言われています。
後期ロマン派、新ウィーン楽派の12 音技法、ジャズや新古典主義など、20
世紀前半にヨーロッパで起こっていた、または持ち込まれた様々な同時代音楽の影響を受けた彼が、20
世紀半ばのうちに遠く海を隔てた国でこのような作品を書いていたことは、現代に続く「西洋音楽の多国籍化」の始まりといえるでしょう。文化の国境が徐々になくなっていく、世界で同じ文化を共有する、そんな新しい時代の文化のあり方を感じる一枚です。 |
| |
|
|
クラウス・オスパルト(1956 ~ ): レオパルディ・チクルスより
(1)Cosi dell’ uomo ignara…
(室内アンサンブルとライブエレクトロニクスのための)
(2)Sovente in queste rive…(大オーケストラのための)
(3)Sopra un basso rilievo antico seppolcrale…
(混声合唱、バステューバ、打楽器四重奏、ライブエレクトロニクスのための) |
(1)コレギウム・ノヴム・チューリッヒ
ペーター・ヒルシュ(指揮)
SWR実験スタジオ
(2)ケルンWDR交響楽団
ルペルト・フーバー(指揮)
(3)ケルンWDR放送合唱団
ハンス・ニッケル(バステューバ)
ケルン打楽器四重奏団
ルペルト・フーバー(指揮) |
200年前の抒情詩人、レオパルディの世界がオスパルトの手で今世紀の音楽となって甦る
録音:(1)2009 年11 月19 日、(2)2011 年12
月16 日、(3)2012 年4 月25 日-27 日
ドイツの作曲家、クラウス・オスパルトが2005
~ 2011 年に書いた一連の作品「レオパルディ・チクルス」。18
世紀後半~ 19 世紀前半のイタリアの詩人ジャコモ・レオパルディによる詩「砂漠に咲く花」を題材にした全6
作の作品のうち、このCD には3 作品目、5 作品目、4
作品目がおさめられています。200 年近く前に書かれたレオパルディの厭世的、抒情的な世界が、現代に通じる普遍的なテーマとして音楽の中に息づいているこれらの作品群は、不気味な低音や、エレクトロニクスによる音色の歪み、各楽器や合唱が作り出す滲むような響きによって独特な世界を形作っています。重々しい曲調ながらカタルシスを味わえる作品です。 |
| . |
|
|
アロンドラ・デ・ラ・パーラ
エンヨット・シュナイダー(1950 ~ ):オーケストラ作品集
・交響曲7番「闇の世界 ウンタースベルグ山」
・自然の響き~セルジュ・チェリビダッケへのオマージュ
・秋のミルク
・Die Flucht |
ウィーン・トーンキュンストラー管弦楽団
アロンドラ・デ・ラ・パーラ(指揮) |
ドイツの映画音楽作曲家エンヨット・シュナイダーの情感あふれる世界
録音:2015 年3 月4 日-7 日
ドイツの映画音楽作曲家、エンヨット・シュナイダーの伸びやかでエモーショナルな魅力が詰まった一枚。
多くの伝説が眠るウィーンのウンタースベルグ山を描いた「交響曲7
番」と、自然への讃歌、そして失われゆく自然への哀歌である「自然の響き」(チェリビダッケ生誕100
周年、およびドビュッシー没後150 周年にあたる2012
年に書かれたもの)、そして彼が音楽を手掛けた2
つの映画「秋のミルク」と「Die Flucht」の音楽がおさめられています。
前半ではシュナイダーの大自然への愛と畏怖の念がオーケストラのパレットで雄大に語られ、後半2
曲では映画音楽が組曲にまとめられています。
シュナイダーの音が描く壮大な景色や情感たっぷりのメロディに身を委ねることができるCD
です。
 アロンドラ・デ・ラ・パーラ アロンドラ・デ・ラ・パーラ

|
.
 LAWO LAWO
|
|
|
ワシリー・ペトレンコ!オスロ・フィル!LAWO!
スクリャービン・サイクルがスタート!
スクリャービン:
交響曲第3番ハ長調 Op.43《神聖な詩》
交響曲第4番 Op.54《法悦の詩》 |
ワシリー・ペトレンコ(指揮)
オスロ・フィルハーモニー管弦楽団 |
SACDからCDに変更
ノルウェーの名門オーケストラ、オスロ・フィルハーモニック管弦楽団と、同じくノルウェーの高音質レーベル「ラウォ(LAWO)」とのコレボレーションがスタート!
待望の第1弾となるのは、オスロ・フィルの現首席指揮者、ワシリー・ペトレンコが振るスクリャービンの交響曲第3番と第4番!
ペトレンコとオスロ・フィルは、スクリャービンの交響曲全曲録音を予定しており、シリーズの幕開けとなる今回の「第3番」と「第4番」へ懸かる期待は非常に大きい。
古くはハルヴォルセン、そしてブロムシュテット、カム、ヤンソンスなどの名指揮者たちが築き上げてきたオスロ・フィルの伝統を受け継ぐペトレンコ。大注目必至!
※録音:2015年2月、オスロ(ノルウェー) |
<マイナー・レーベル歴史的録音・旧録音>
.
CUGATE CLASSICS
|

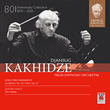
CGC 001
(2CD)
\4000 →\3690 |
ジャンスク・カヒーゼの遺産Vol.1
CD1
ラフマニノフ:交響曲第2番ホ短調Op.27
CD2
ホルスト:惑星 |
ジャンスク・カヒーゼ(指揮)
トビリシ交響楽団 |
音の洪水に酔わされるカヒーゼのラフマニノフとホルスト
24bit / 96kHz/111’ 27”
グルジア(ジョージア)出身の指揮者ジャンスク・カヒーゼ(1936-2002)。ロジェストヴェンスキー、フェドセーエフらと同世代のソ連型指揮者としてカルト的人気を誇っていました。
その遺産が24bit / 96kHz の新リマスタリングを経て体系的に発売されることとなりました。
第1 弾となるラフマニノフの交響曲第2 番、実は超お宝で、何故かリリースされないままファンの間で伝説化していたものが待望の登場となります。
さらに嬉しいのがホルストの「惑星」。イギリス系のオーケストラとは異なるリムスキー=コルサコフのような世界が興味津々。
トビリシ交響楽団は1993 年にカヒーゼが設立したオーケストラ。カヒーゼは「グルジアのカラヤン」と称されていましたが、アンサンブルの精度を追求しつつも、場合によっては破天荒な爆演になるところがさすがです。
どういうわけかカヒッツェ(カヒーゼ)のアイテムというのはすぐに廃盤になることが多い。
それだけマイナーなレーベルからしかCDが出ないということなのかもしれないが、なんとなくこのレーベルも同じような運命にあるような匂いがプンプンする。
もちろんそうならないことを願うけれど・・・
さらに追記としてお客様からご指摘を。引用させていただくと、
今回発売されるこの2枚組の音源は初出の様に書かれているが、おそらく間違い。
正確には「カヒーゼの演奏として発売される」のが初めてということ。音源としてはいずれもかつてJahni
Mardjani指揮Georgian Festival Orchestraの演奏として米SONYの廉価レーベルINFINITY
DIGITALで発売されたものと同じようだ。
ラフマニノフはQK64559、ホルストはQK57258というカタログ番号で発売されていた。
このSONYのシリーズはメジャー・レーベルとは思えない怪しいシリーズで、このシリーズのMardjani指揮のチャイコフスキーの4-6番もかつて独HDCレーベルから出ていたカヒーゼの録音と同じ音源だった。
おそらくMardjaniという指揮者はいわゆる『幽霊指揮者』ではないかと思う。
とのことで、SONYのINFINITY DIGITALシリーズは基本的に日本には入ってきていないのでお持ちの方は少ないと思うが、気になる方はCD棚を見てみてください。
このSONYのINFINITY DIGITAL レーベルは HDCのボルクヴァゼなどの演奏も出していたのでどこかでHDCとつながっていたのだろう。なぜMardjani名で出していたのは不可解だが・・・。
. |
| |

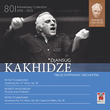
CGC 002
(2CD)
\4000 →\3690 |
ジャンスク・カヒーゼの遺産Vol.2
CD1
(1)チャイコフスキー:交響曲第4番ヘ短調Op.36
(2)ムソルグスキー(ラヴェル編):展覧会の絵
CD2
チャイコフスキー:交響曲第5番ホ短調Op.64 |
ジャンスク・カヒーゼ(指揮)
トビリシ交響楽団 |
ムラヴィンスキーも認めたカヒーゼのチャイコフスキーを満喫
24bit / 96kHz/140’ 27”
カルト的な人気を誇る指揮者ジャンスク・カヒーゼ(1936-2002)。彼のチャイコフスキー演奏は、かのムラヴィンスキーが高く評価したと伝えられています。その4
番と5 番を堪能できるアルバムが登場。さすがムラヴィンスキーが認めただけある端正かつ底力を秘めた名演で、旧ソ連系演奏のファンの方々に超オススメです。
もうひとつの注目が「展覧会の絵」。これも西側の演奏団体にはみられない独特の解釈に驚かされます。 |
| |
|
|
公的なプロコフィエフ
プロコフィエフ:
(1)十月革命20周年のためのカンタータOp.74
(詞:マルクス、レーニン、スターリン)
(2)偉大なる十月革命30周年カンタータ「栄えよ、強い国土」Op.114
(3)乾杯Op.85 |
アレクサンドル・チトーフ(指揮)
ニュー・フィルハーモニー管弦楽団、
ペテルブルグ・フィル合唱団
アレクセイ・エメリャノフ(語り) |
録音:1997年/ペテルブルグ/24bit / 96kHz/65’
14”
スターリンの恐怖政治時代、彼の偉大さやソ連の優位性を自己宣伝するため、大芸術家たちが提灯持ち作品を強要されました。
プロコフィエフも例外でなく、生き延びるためにここに収められたような作品を作りました。ソ連邦が崩壊した後、反動でこうした芸術は忌み嫌われ演奏されなくなっていますが、プロコフィエフとスターリンが亡くなった翌1954
年に生まれた指揮者アレクサンドル・チトーフが挑戦。今日の目からすると呆れてしまう作品ながら、プロコフィエフの音楽は超一級の素晴らしさなうえ、オリジナルのロシア語詩も実は大作家たちが匿名で書かされたらしく、形式やリズムも計算され、真に感動的な芸術作品となっています。
アルバム・タイトルは「バック・インUSSR」ですが、反語としてプロコフィエフの真意をあますことなく描いています。 |
| |
|
|
恐ろしいまでに真摯な集中力。
サンクトペテルブルグSQ 入魂のショスタコーヴィチ
ショスタコーヴィチ:
(1)弦楽四重奏曲第3番ヘ長調Op.73
(2)同第5番変ロ長調Op.92
(3)同第7番嬰ヘ短調Op.108 |
サンクトペテルブルグSQ |
24bit / 96kHz/73’ 37”
1985 年、当時レニングラード音楽院教授で、タネーエフSQ
の第1 ヴァイオリンを務めていたウラジーミル・オフチャレクが結成したサンクトペテルブルグSQ。旧ソ連最良の教育を受けた最後の世代で、ここに収められたショスタコーヴィチもまったく隙のない完成度。交響曲を聴くような充実したひとときを味わえます。 |
| |
|
|
ビゼー(シチェドリン& ポノマレンコ編):
ビゼーのカルメン組曲の再生 |
ダブル・デュエット「MA.GR.IG.AL」
アレクサンドル・チェルノバエフ(Perc) |
まるでパンク・ロック。ロシア民族楽器によるビゼーのカルメン
24bit / 96kHz/49’ 24”
シチェドリンが愛妻で大バレリーナのプリセツカヤのために、ビゼーの名作「カルメン」を弦と打楽器のために編曲。それを、バラライカ、バヤン、ドムラなどロシアの民族楽器で披露。
4人組でダブル・デュエットと称する「MA.GR.IG.AL」は、まだソ連時代の1980
年代に結成。グループ名は、マクシム・トルスティ(バラリカ)、グリゴーリー・ヴォスコボイニク(ダブルベース)、イーゴリ・ポノマレンコ(ドムラ)、アレクサンドル・マトロソフ(バヤン)の名の頭文字に由来します。ソ連、民族音楽という語から想像できないようなちょい悪風集団で、ほとんどパンク・バンド風。演奏も過激で、ビゼーのスペイン色が濃厚なロシア音楽に様変わり。ロックのように爽快な演奏に釘付けとなります。

|
IDIS
|
|
|
カラヤン・スペクタキュラー vol.4
ブラームス:
(1)交響曲第1番ハ短調Op.68
(2)悲劇的序曲Op.81
(3)ハイドンの主題による変奏曲Op.56a * |
ヘルベルト・フォン・カラヤン(指揮)
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
フィルハーモニア管弦楽団* |
録音:(1)1960年(1959年?スタジオ)/(2)1964年(1961年?スタジオ)/(3)1955年(スタジオ)/77’16
録音年表記間違い?
ブラームス交響曲第1番は下記のアリア・レーベルと同じ録音と思われるのだが・・・
|
| . |
|
|
サラサーテ/フアン・マネン/マヌエル・キロガ!
サラサーテ:
(1)ツィゴイネルワイゼンOp.20 モデラート (2)バスク奇想曲Op.24
(3)序奏とカプリース ホタOp.41 (4)序奏とタランテッラ
Op.43
(5)ミラマールOp.42 (6)ハバネラ
(7)スペイン舞曲集 Op. 23 - サパテアード
ショパン:(8)夜想曲第2番変ホ長調 Op. 9
バッハ:(9)無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第3番
ホ長調 プレリュード |
(1)-(9)パブロ・デ・サラサーテ(ヴァイオリン) |
ベートーヴェン:(10)ヴァイオリン協奏曲ニ長調
Op. 61 第2楽章 ラルゲット
サラサーテ:(11)ホタ・アラゴネーサ Op.
27 |
(10)(11)フアン・マネン(ヴァイオリン) |
サラサーテ:(12)ミラマールOp.42
ヴィエニャフスキ:(13)モスクワの思い出
Op. 6
バッツィー二:(14)妖精の踊り Op.25
サラサーテ:
(15)スペイン舞曲集 Op. 22 第2番 ホタ・ナバーラ
(16)スペイン舞曲集 Op. 22 第1番 アンダルシアのロマンス
ウェーバー:
(17)ヴァイオリンソナタ第1番へ長調 Op.
10 第2楽章 ロマンツァ ラルゲット
シューマン:(18)12のピアノ小品 Op. 85 第12曲
夕べの歌
サラサーテ:
(19)序奏とタランテッラ Op. 43 (20)ホタ・アラゴネーサ
Op. 27 |
(12)-(20)マヌエル・キロガ(ヴァイオリン) |
|
録音:(1)-(9)1904年/(10)(11)1922年/(12)-(15)1912年/(16)-(20)1928年/73’34
サラサーテ本人の自作自演による「ツィゴイネルワイゼン」ほか、スペインの名ヴァイオリニスト、フアン・マネンとマヌエル・キロガによる個性的で貴重な演奏集。 |
| |
|
|
ナルバエス/サンス/ソル/モレノ・トローバ:ギター作品集
ナルバエス:(1)「牛を見張れ」によるディファレンシア
サンス:(2)組曲
ソル:
(3)メヌエットニ長調 (4)モーツァルトの「魔笛」の主題による変奏曲Op.9
(5)エチュード第17番ホ短調
モレノ・トローバ:(6)マドロノス
サインス・デ・ラ・マーサ:(7)ハバネラ
タルレガ:(8)タンゴ「マリア」 (9)4つのマズルカ (10)アルボラーダ
アルベニス:
(11)スペイン組曲Op.47 (12)12の性格的小品Op.92
第12曲朱色の塔
ムニョス・モリエダ:(13)ファルーカ
トゥリーナ:
(14)タルレガへのオマージュOp.69 (15)疾風Op.53
(16)ファンダンギーリョOp.36 |
ナルシソ・イエペス(ギター) |
録音:1960 年/1963年(スタジオ)/68’07
名ギタリスト、ナルシソ・イエペスの30 代前半の録音集。スペイン情緒溢れる演奏で、生き生きとした豊かな音楽を聴かせてくれます。 |
.
RELIEF
|
|
|
フェドセーエフ&モスクワ放送響
生誕百年記念、スヴィリドフ傑作集
スヴィリドフ:
(1)悲愴オラトリオ
(2)「時よ前進」組曲
(3)小トリプティーク
(4)春のカンタータ
(5)「吹雪」~ワルツのエコー |
ウラジーミル・フェドセーエフ(指揮)
チャイコフスキー記念モスクワ放送交響楽団 |
録音:1959-1974年/76’ 00”
今年が生誕100 年にあたる作曲家ゲオルギー・スヴィリドフ。ショスタコーヴィチ門下のソ連作曲家で、「時よ前進」の景気良いマーチが長年モスクワ放送のニュース番組のテーマ曲として使われていて、日本でもロシア関係者の顔が輝く懐かしのメロディとなっています。
フェドセーエフはスヴィリドフの音楽を好み、日本でも「吹雪」などを頻繁に演奏して普及に努めてきました。ここではフェドセーエフがメロディに録音した古い音源を集めてCD
化。スヴィリドフの代表作がすべて収められていて、まず1
枚としてコレクションするにも最適。モスクワ放送響最盛期の神業的名演を楽しむことができます。
|
<国内盤>

9/30(水)紹介新譜(1)
マイナー・レーベル新譜
 2L 2L
|

2L 113SABD
(Blu-ray Disc Audio +
SACD HYBRID
[5.1 surround/stereo])
\4300 |
初期ロマンティシズムのホルンソナタ
フェルディナント・リース(1784-1838):
大ソナタ ヘ長調 Op.34(1811)
フランツ・ダンツィ(1763-1826):ソナタ
変ホ長調 Op.28(1804)
ニコラウス・フォン・クルフト(1779-1818):ソナタ
ホ長調(1812) |
スタイナル・グランモ・ニルセン
(ナチュラルホルン)
クリスティン・フォスハイム
(フォルテピアノ) |
名手スタイナル・グランモ・ニルセン教会に響き渡るナチュラルホルンの柔らかな響き、空間をまるごと録音する2Lの高音質ディスクで登場
楽器:アンドレーアス・ユングヴィルト(2000)(ボヘミアのラウスマン1800年頃の複製/ナチュラルホルン)、
ケネス・ベイクマン(1983)(ウィーンのヴァルター1805
年モデル の複製/フォルテピアノ)
録音:2014年6月 ヤール教会(ベールム、ノルウェー)
制作&バランスエンジニアリング:モッテン・リンドベルグ
録音:ビアトリス・ヨハンネセン
[DXD(24bit/352.8kHz)録音]
[Blu-ray: 5.1 DTS-HD MA(24bit/192kHz),
2.0 LPCM (24bit/192kHz), mShuttle: FLAC
96kHz + MP3 Region ABC]
[SACD hybrid(5.1 surround DSD/2.0 stereo
DSD)
67’38
絶対主義が崩壊したその余波と戦って手に入れた「新しい自由」の時代に居合わせた音楽家たち、フェルディナント・リース、フランツ・ダンツィ、ニコラウス・フォン・クルフトのホルンソナタを集めたアルバム。
ヨーゼフ・アントン・コッホが1805 年に描いた『虹のある英雄的な景色』をジャケットのアートワークに使われています。
ブックレットのノーツを書いたアネッテ・ナウマンは、その意味を「細部に至るまで正確に組み立てられ、統一感された世界……自然と文化の領域の調和……コッホの絵は、ネオクラシカルな規律の構造をもちながら、自然に対する新しい、ロマンティックな意識を示唆する……時代は、新しい自由へと芸術を導いていく」と述べています。
フェルディナント・リース(1784-1838)は、ボン生まれ。ベートーヴェンにピアノを学び、1801
年10 月、ウィーンに行き、ベートーヴェンの庇護の下、作曲を行い、交響曲、オペラ、オラトリオ、管弦楽曲、室内楽曲、ピアノ曲を含む、180
近い作品を残しています。
シュヴェツィンゲン生まれのフランツ・ダンツィ(1763-1826)は、イタリア家系のドイツ人音楽家ではもっとも重要な作曲家とみなされています。交響曲、協奏曲、オペラ、教会音楽、歌曲と、広い分野に多くの曲を作り、室内楽のための音楽、とりわけ木管アンサンブルのための作品が知られています。
ニコラウス・フォン・クルフト(1779-1818)は、ウィーン生まれ。ウィーン大学で哲学と法律を修め、アルブレヒツベルガーの下で作曲を学びました。外相メッテルニヒに仕え、公務のかたわら作曲したホルンソナタ、ファゴットソナタ、歌曲が、彼の遺産です。
ノルウェーのスタイナル・グランモ・ニルセンは、ナチュラルホルンの名手の一人に挙げられるプレーヤーです。トロンハイム音楽院のスタイン・ヴィランゲル、フライブルク州立大学のアイフォー・ジェイムズ、オスロのノルウェー音楽アカデミーでフロイディス・レー・ヴェクレに学びました。1999
年からノルウェー軍音楽隊のホルン奏者を務め、現在はノルウェー・ウィンドアンサンブルに所属しています。コントロールのむずかしいナチュラルホルンを巧みに操り、楽譜を正しく音にするとともに、ロマンティシズムが芽生え育ちゆく時代の作品を瑞々しい、活き活きした音楽に表現していきます。
録音セッションは、制作を担当したモッテン・リンドベルグが響きの良さを気に入っている録音場所のひとつ、アーケシュフース県ベールムのヤール教会で行われました。DXD(352.8kHz/24bit)録音。教会の空間に響くナチュラルホルンの音が程よい距離感で捉えられ、リアルなテクスチュアを感じさせるフォルテピアノとともに美しい音楽を作り上げています。
Pure Audio Blu-ray と SACD hybrid のディスクを収めた「コンボ」仕様のアルバムです。
[Pure Audio Blu-ray ディスクと SACD ハイブリッドディスクをセットにしたアルバムです。Pure
Audio Blu-ray ディスクにはインデックスを除き映像は収録されていません。
SACD ハイブリッドディスクはSACD ブレーヤーとCD
プレーヤーで再生できますが、Pure Audio Blu-ray
ディスクはCD やDVDのプレーヤーでは再生できないので、Blu-ray
プレーヤーもしくは Blu-ray 対応のPC をお使いください]

|
| |

2L114SACD
(SACD HYBRID)
\2600 |
指の黄金~主の聖血の祝日
聖血の聖務日課 |
スコラ・サンクテ・スンニヴェ
アンネ・クライヴセット(指揮) |
キリストの聖血を巡るミサ曲
録音:2014年5月 リングサーケル教会(ヘードマルク、ノルウェー)/5.0
surround/stereo、78’17
制作:エウゲーン・リヴェン・ダベラルド/バランスエンジニアリング:ビアトリス・ヨハンネセン/ミクシング・マスタリング:モッテン・リンドベルグ
[DXD (24bit/352.8kHz) 録音]
[SACD DXD (5.0 surround 2.8224 Mbit/s/ch,
2.0 stereo 2.8224 Mbit/s/ch)/CD 2.0 stereo
(16 bit/44.1 kHz)]
「われらが主イエス・キリストの御血がニーダロスに届く」。アイスランドの『王室年代記』は、1165
年の項にそう記し、聖十字架、聖釘、聖槍、聖骸布、聖杯とならぶキリストの聖遺物のひとつ「キリストの血の一滴(聖血)」が、ノルウェーのニーダロス、今日のトロンハイムに届いたことを記録に残しました。この記載を裏付けるように、トロンハイムのニーダロス大聖堂は毎年9
月12 日を「主の聖血の祝日」と定め、聖務日課を行っています。
大聖堂では、この日、キリストの血が黄金の指輪に納められたことから、13
世紀に作られた祝日表に「指の黄金のミサ」と記載されたミサが行われ、1250年から1275
年の間にニーダロス大聖堂のために書かれたと推測される聖歌が歌われます。
「第一の晩課」「朝課」「第一の夕べの祈り」「第二の夕べの祈り」「第三の夕べの祈り」「讃歌」「第二の晩課」。アンティフォナ、レスポンソリウムなど、36
の聖歌は、二つ折りの羊皮紙10 枚からなる一巻の写本に書かれ、ニーダロス大聖堂が度重なる大火に見舞われたこともあって、この聖務日課のための聖歌として現存する唯一の書とされています。
スコラ・サンクテ・スンニヴェは、1992 年、トロンハイムに創設された女声ヴォーカルアンサンブルです。中世ノルウェーから伝わる聖歌を研究し保存する活動を行い、『聖母マリアの生誕』(2L69SACD)をはじめとするアルバムにその成果を残してきました。
スコラ・サンクテ・スンニヴェは、創設者のアンネ・クライヴセットとともに「聖血の聖務日課」の資料と長年にわたり取り組み、12
世紀中期に建立されノルウェーの守護聖人、聖オラヴに捧げられたリングサーケル教会で2014
年5 月に録音セッションを行い、最初の全曲録音を完成させました。 |
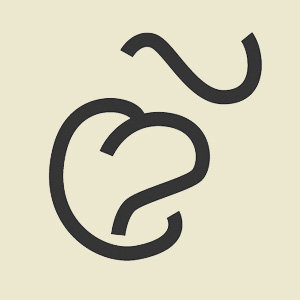 GLOSSA GLOSSA
|
|
|
カンティカ・シンフォニアが歌うミサ曲&モテット!
イザーク:
ミサ曲《主の憐れみを》(世界初録音)
めでたし天の女王(世界初録音)
三位一体の哲学をたたえよ(世界初録音)
けがれなく、完全で、貞節な方、マリア(世界初録音)
御身が庇護の下に
御身に請い願う、処女マリアよ
彼女は誰なのか?(世界初録音)
おお、栄光の母なる教会よ |
カンティカ・シンフォニア
〔ラウラ・ファブリス(ソプラノ)、
フランチェスカ・カッシナーリ(ソプラノ)、
ジュゼッペ・マレット(テノール&ディレクター)、
ジャンルカ・フェッラリーニ(テノール)、
ファビオ・フルナーリ(テノール)、
マルコ・スカヴァッツァ(バリトン)、
グイド・マニャーノ(オルガン)、
スヴェトラーナ・フォミーナ(フィドル)、
エフィクス・プレオ(フィドル)、
ダニエラ・ゴディオ(フィドル)、
エルメス・ジュッサーニ
(サックバット&スライド・トランペット)、
マウロ・モリーニ(サックバット)、
ダヴィド・ヤクス
(サックバット&スライド・トランペット)〕 |
ハインリヒ・イザーク没後500周年記念!カンティカ・シンフォニアが歌うミサ曲&モテット!
「デュファイ・トリロジー(三部作)」やビュノワの「ミサ・ロム・アルメ」など、数多くの名唱を生み出してきたジュゼッペ・マレットが率いるイタリアのヴォーカル・アンサンブル、カンティカ・シンフォニア。
2017年に没後500周年を迎えるハインリヒ・イザーク(c.1450-1517)のミサ曲とモテットを次なるプログラムに選んだカンティカ・シンフォニアは、メイン・プログラムの「ミサ曲《主の憐みを》」を筆頭に、世界初録音となる貴重な作品を収録。
カンティカ・シンフォニアの定評あるハーモニーと、共演の実力派器楽奏者たちのサウンドのブレンドは古楽ファン必聴。早くもイザーク・イヤーの大本命誕生の予感が漂う要注目新譜です!

|
| |

GCD 922410
(6CD/特別価格)
\8900 →\7990 |
スヴェーリンク:鍵盤作品全集 |
ボブ・ファン・アスペレン
(ハープシコード&ヴァージナル)
ピーター=ヤン・ベルダー
(ハープシコード&ヴァージナル)
ピーター・ファン・ダイク(オルガン)
ピーター・ダークセン
(ハープシコード&ヴァージナル)
レオ・ファン・ドゥセラール(オルガン)
グスタフ・レオンハルト
(ハープシコード)
ライツェ・スミッツ(オルガン)
マリーケ・スパーンス
(ハープシコード&ヴァージナル)
ハラルド・フォーゲル(オルガン)
アレクサンダー・ヴァイマン
(ハープシコード)
ベルナール・ヴィンセミウス(オルガン)
ジェズアルド・コンソート・アムステルダム
〔ネーレ・グラムス(ソプラノ)、
マルニクス・ド・カート(アルト)、
ハリー・ファン・ベルヌ(テノール)、
ハリー・ファン・デル・カンプ(バス)〕 |
●CD1
◆シュヴェルベンネスト・オルガン(聖母マリア教会、レムゴー、ドイツ)
4声のファンタジアa1, B.A.C.H SwWV.273〔ベルナール・ヴィンセミウス〕
主よ、わたしたちの日々に平安を与えて下さい
SwWV.302
〔マルニクス・ド・カート(アルト)、ハリー・ファン・ベルヌ(テノール)、
ハリー・ファン・デル・カンプ(バス)、ベルナール・ヴィンセミウス〕
ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラによる4声のファンタジアF1,
SwWV.263
〔ベルナール・ヴィンセミウス〕
おお、主なる神よ、わたしを憐れんでください
SwWV.303
〔ネーレ・グラムス(ソプラノ)、マルニクス・ド・カート(アルト)、
ハリー・ファン・ベルヌ(テノール)、
ハリー・ファン・デル・カンプ(バス)、レオ・ファン・ドゥセラール〕
ファンタジアC5, SwWV.257〔レオ・ファン・ドゥセラール〕
おお、我らが父なる神よ SwWV.308
〔ネーレ・グラムス(ソプラノ)、マルニクス・ド・カート(アルト)、
ハリー・ファン・ベルヌ(テノール)、
ハリー・ファン・デル・カンプ(バス)、レオ・ファン・ドゥセラール〕
◆16~17世紀のオルガン(改革派教会、ウットゥム、ドイツ)
今ぞ喜べ、汝ら愛するキリストのともがらよ
SwWV.307
〔ネーレ・グラムス(ソプラノ)、マルニクス・ド・カート(アルト)、
ハリー・ファン・ベルヌ(テノール)、
ハリー・ファン・デル・カンプ(バス)、ベルナール・ヴィンセミウス〕
第一旋法によるトッカータd3, SwWV.287、
4声のファンタジアF2, SwWV.264、3声のファンタジアg2,
SwWV.271
〔ハラルド・フォーゲル〕
●CD2
◆ハンス・ルッカースのヴァージナル(1604年製作、ドルトレヒト、オランダ)
トッカータg4, SwWV.295〔ピーター・ダークセン〕
わが青春は既に過ぎ去り SwWV.324
〔ネーレ・グラムス(ソプラノ)、マルニクス・ド・カート(アルト)、
ハリー・ファン・ベルヌ(テノール)、
ハリー・ファン・デル・カンプ(バス)、ピーター・ダークセン〕
アルマンド・グラティエ SwWV.318、2声のトッカータ(前奏曲)SwWV.297
〔ピーター・ダークセン〕
みどりごがわたしたちのために生まれ SwWV.315
〔ネーレ・グラムス(ソプラノ)、ボブ・ファン・アスペレン〕
涙のパヴァーヌ SwWV.328〔ボブ・ファン・アスペレン〕
◆ヨアネス・ルッカースのハープシコード
(1639年製、リンゲンベルク宮殿、ハンミンケルン、ドイツ)
トッカータC1, SwWV.282〔ボブ・ファン・アスペレン〕
イギリスの定め SwWV.320
〔ネーレ・グラムス(ソプラノ)、マルニクス・ド・カート(アルト)、
ハリー・ファン・ベルヌ(テノール)、
ハリー・ファン・デル・カンプ(バス)、ボブ・ファン・アスペレン〕
トッカータa1, SwWV.296、スペインのパヴァーヌ
SwWV.327、
4声のファンタジアd2, SwWV.259〔ボブ・ファン・アスペレン〕
フィリップスのパヴァーヌ SwWV.329、半音階的ファンタジアd1,
SwWV.259
〔ピーター=ヤン・ベルダー〕
●CD3
◆ヤン・ファン・コフェレンス・オルガン
(聖ラウレンス教会、アルクマール、オランダ)
3声のトッカータC3, SwWV.284、
2・3・4声のためのファンタジアG2, SwWV.267、
3声のエコー・ファンタジア SwWV.275、
詩篇36番と68番の旋律によるカノン SwWV.196〔ピーター・ダークセン〕
キリストよ、光にして日なるかた SwWV.301
〔マルニクス・ド・カート(アルト)、ハリー・ファン・ベルヌ(テノール)、
ハリー・ファン・デル・カンプ(バス)、ピーター・ファン・ダイク〕
2声のファンタジアg3, SwWV.272、4声のファンタジアg1,
SwWV.270
〔ピーター・ファン・ダイク〕
◆エド・エファース(ワルンフリート教会、オステル、ドイツ)
3声のトッカータG2, SwWV.289、ファンタジアd5,
SwWV.262
〔ライツェ・スミッツ〕
主イエス・キリストよ、わたしはあなたを呼ぶ
SwWV.305
〔ネーレ・グラムス(ソプラノ)、マルニクス・ド・カート(アルト)、
ハリー・ファン・ベルヌ(テノール)、
ハリー・ファン・デル・カンプ(バス)、ライツェ・スミッツ〕
フーガ・ファンタジアG3, SwWV.268〔ピーター・ダークセン〕
ただあなたにのみ、主イエス・キリストよ
SwWV.309
〔ネーレ・グラムス(ソプラノ)、マルニクス・ド・カート(アルト)、
ハリー・ファン・ベルヌ(テノール)、
ハリー・ファン・デル・カンプ(バス)、ピーター・ダークセン〕
●CD4
◆アルトゥス・ヘールディンクのヴァージナル
(1605年製作、ゲルマン国立博物館、ニュルンベルク、ドイツ)
トッカータG1, SwWV.288、礼拝堂のアルマンド
SwWV.317、
トッカータC2, SwWV.283、おかしなシモン
SwWV.323
〔マリーケ・スパーンス〕
トッカータg1, SwWV.292、我はライン川に漕ぎ出し
SwWV.322、
トッカータg3, SwWV.294〔ピーター=ヤン・ベルダー〕
◆アンドレアス・ルッカースのハープシコード
(1637年製作、ゲルマン国立博物館、ニュルンベルク、ドイツ)
それはマルスの神 SwWV.321
〔ネーレ・グラムス(ソプラノ)、マルニクス・ド・カート(アルト)、
ハリー・ファン・ベルヌ(テノール)、
ハリー・ファン・デル・カンプ(バス)、マリーケ・スパーンス〕
トッカータG4, SwWV.291、4声のファンタジアC2,
SwWV.254、
飛び回る妖精 SwWV.331、エコー・ファンタジアC3,
SwWV.255
〔マリーケ・スパーンス〕
ポーランドのアルマンド SwWV.330、トッカータd2,
SwWV.286、
緑なす菩提樹のもとで SwWV.325、エコー・ファンタジアG1,
SwWV.253、
トッカータg2, SwWV.293〔アレクサンダー・ヴァイマン〕
●CD5
◆ヘンドリック&ヨハネス・ハウス・オルガン
(聖アントニウス教会、カンテンス、オランダ)
高きところの神にのみ栄光あれ SwWV.299
〔ネーレ・グラムス(ソプラノ)、マルニクス・ド・カート(アルト)、
ハリー・ファン・ベルヌ(テノール)、
ハリー・ファン・デル・カンプ(バス)、ライツェ・スミッツ〕
トッカータd1, SwWV.285、4声のエコー・ファンタジアd3,
SwWV.260
〔ライツェ・スミッツ〕
リチェルカーレa1, SwWV.280、ファンタジアF3,
SwWV.265
〔ピーター=ヤン・ベルダー〕
◆ガルトゥス&ゲルマー・ファン・ハーゲルベール・オルガン
(聖ピータース教会、ライデン、オランダ)
我らは皆唯一の神を信ず SwWV.316
〔ネーレ・グラムス(ソプラノ)、マルニクス・ド・カート(アルト)、
ハリー・ファン・ベルヌ(テノール)、
ハリー・ファン・デル・カンプ(バス)、レオ・ファン・ドゥセラール〕
4声のトッカータa3, SwWV.298、
4声のエコー・ファンタジアd4, SwWV.261〔レオ・ファン・ドゥセラール〕
われらの救い主なるイエス・キリスト
SwWV.306
〔ネーレ・グラムス(ソプラノ)、マルニクス・ド・カート(アルト)、
ハリー・ファン・ベルヌ(テノール)、
ハリー・ファン・デル・カンプ(バス)、ハラルド・フォーゲル〕
2声のファンタジア SwWV.274〔ハラルド・フォーゲル〕
●CD6
◆トランセプト・オルガン(旧教会、アムステルダム、オランダ)
詩篇第36番 SwWV.311、詩篇第23番 SwWV.310、詩篇第140番
SwWV.314、
詩篇第60番 SwWV.312、詩篇第116番 SwWV.313
〔ベルナール・ヴィンセミウス〕
詩篇第9番/ヴァースII ~ クロード・ル・ジュヌの主題による二重フーガ
〔ネーレ・グラムス(ソプラノ)、マルニクス・ド・カート(アルト)、
ハリー・ファン・ベルヌ(テノール)、
ハリー・ファン・デル・カンプ(バス)〕
◆アンドレアス・ルッカースのハープシコード
(1637年製、ゲルマン国立博物館、ニュルンベルク、ドイツ)
4声のファンタジアG1, SwWV.266〔ピーター・ダークセン〕
喜ばしい五月(クレメンス・ノン・パパ)
〔ネーレ・グラムス(ソプラノ)、マルニクス・ド・カート(アルト)、
ハリー・ファン・ベルヌ(テノール)、
ハリー・ファン・デル・カンプ(バス)、ピーター・ダークセン〕
ヤン・ピーテルス氏のフーガによる幻想曲(ジョン・ブル)
〔アレクサンダー・ヴァイマン〕
◆ライナー・シュッツェのハープシコード
(1961年製作、アムステルダム、オランダ)
それはマルスの神 SwWV.321〔グスタフ・レオンハルト〕
涙のパヴァーヌ SwWV.328〔グスタフ・レオンハルト〕 |
Glossaが送り出すスヴェーリンクBOX!豪華演奏者、銘器による"鍵盤作品全集"!
ルネサンス時代の末期からバロック時代の初期にかけて多大な足跡を残し、北ドイツ・オルガン楽派の始祖として、当時の鍵盤楽器のための音楽を発展へと導いたオランダの巨匠ヤン・ピーテルスゾーン・スヴェーリンク(1562-1621)。
スペインのグロッサ(Glossa)が完成させたスヴェーリンクの「鍵盤作品全集」は、レオンハルトやアスペレン、ダークセンなど、歴史にその名を刻む名鍵盤奏者たちの起用、貴重なヒストリカル楽器の使用、さらにはジェズアルド・コンソート・アムステルダムが歌う4声のコラールの収録など、その完成度の高さは圧巻。
まさに北ドイツ・オルガン楽派の巨匠が遺した至芸、「鍵盤作品」の決定盤となる全集の登場です!
※録音:2012年6月-2014年2月、オランダ&ドイツ、1971年10月(レオンハルト)、2009年7月(ベルナール・ヴィンセミウス) |
ARTE DELL’ARCO JAPAN
|
|
|
有名・無名の作曲家/作品からこぼれる古典派の愉悦!
(1)モーツァルト:交響曲ニ長調K.196+121
(2)ファン・マルデレ:交響曲変ロ長調Op.4-3
(3)ハイドン:チェロ協奏曲第2番ニ長調 Hob.VIIb-2
(4)ハイドン:交響曲第71番変ロ長調Hob.I-71 |
鈴木秀美(指揮、(3)チェロ)
オーケストラ・リベラ・クラシカ |
有名・無名の作曲家/作品からこぼれる古典派の愉悦!鈴木秀美3度目となるハイドンの協奏曲第2番も収録
ライヴ録音:2014 年6 月15 日/石橋メモリアルホール/DDD、ライヴ
このアルバムはオーケストラ・リベラ・クラシカ(OLC)第33
回公演のライヴ録音で、今回のプログラムはモーツァルトの交響曲ニ長調
K.196 +121、マルデレの交響曲 Op.4-3、ハイドンのチェロ協奏曲第2
番、そしてハイドンの交響曲第71 番です。
モーツァルト:交響曲ニ長調K.196+121はオペラ「偽りの女庭師」序曲に基づく交響曲。あまり演奏されることのない作品だが、ザルツブルグで書かれた表情豊かな作品。
ハイドンのチェロ協奏曲第2 番はOLC 第6 回公演以来の演奏で、録音としては3
度目となります。また、ファン・マルデレの交響曲はプログラムで取り上げたことはありませんが、OLC
第1 回のアンコールに一つの楽章を演奏した思い出の作品です。
最後のハイドンの交響曲第71 番はパリ・セット辺りと比べると規模はやや小さめかもしれませんが、充実した中身を持っております。有名・無名の作曲家、作品からこぼれる古典派の作品をご堪能ください。
オーケストラ・リベラ・クラシカ第36回定期演奏会情報
2015 年10 月17 日(土)15:00 開演 上野学園石橋メモリアルホール
ハイドン: 交響曲第90番ハ長調Hob.I:90/ベートーヴェン:
交響曲第7番イ長調 Op.92
鈴木秀美(指揮)、オーケストラ・リベラ・クラシカ

|
AURORA
|
|
|
オイヴィン・トルヴンの音楽を演奏する
オイヴィン・トルヴン(1976-):
・ヴィリバルト・モーター・ランドスケープ(2012)
・ネオン・フォレスト・スペース(2009)
・狼の研究(2006/2014)
・プラスティックの波(2013) |
クリスティーネ・チョーゲシェン
(クラリネット、ハーモニカ、口笛)
アンデシュ・フォリスダール
(エレクトリックギター、アクースティックギター)
ホーコン・ステーネ(打楽器)
エレン・ウゲルヴィーク(ピアノ、キーボード)
ターニャ・オルニング(チェロ)
トリル・G・ベルグ(トロンボーン)
カーリン・ヘルクヴィスト(ヴァイオリン)
オイヴィン・トルヴン
(ノイズ・ジェネレーター、フィードバック・カセットプレーヤー) |
録音:レインボースタジオ(オスロ)/制作:ヤン・マッティン・スモルダール
録音:ヤン・エーリク・コングスハウグ、ペール・エスペン・ウーシュフィヨルド/ミクシング:インガル・フンスコール
58’26
オイヴィン・トルヴンは、オスロ・シンフォニエッタのコンポーザー・イン・レジデンス。フォーク、パンク、あるいはバロックのスタイルによるメロディのテーマとアクースティックの室内音楽を、フィールド・レコーディングや手製の楽器による「ローファイ」音と組み合わせた、独自性のある作品を手がけてきました。
ドナウエッシンゲン、サンフランシスコの「Other
Minds」、オスロのウルティマ Ultima をはじめとするコンテンポラリー・ミュージックのフェスティヴァルで作品が取り上げられ、2012
年にはアルネ・ヌールハイム作曲家賞を受賞しました。
ノルウェー作曲家協会のレーベル Aurora が制作した『Neon
Forest Space』は、「前衛音楽とその歴史への情熱と興味を共有する」音楽家が集まり2002
年に結成したアンサンブル「asamisimasa」とのコラボレートによるトルヴンのポートレートアルバムです。
オスロの街を行き交う車、レーシングカー、ピンボール・マシンの音を収めた録音を交え、クラリネット/
バスクラリネット、エレクトリックギター、キーボード、打楽器、チェロとテープのための《WillibaldMotor
Landscape》。
クラリネット、エレクトリックギター、打楽器、チェロがフィールド・レコーディングに合わせ、森から聞こえる太古のメロディを模す《Neon
Forest Space》。
クラリネット/ バスクラリネット、トロンボーン、アクースティックギター、2
組の打楽器、ヴァイオリン、チェロが、スウェーデンの森で録音された狼の遠吠えとベルリンのアーカイヴの録音と共演する《Wolf
Studies(狼の研究)》。
ピアノ・ソロ、クラリネット/ バスクラリネット、エレクトリックギター、打楽器、チェロのアンサンブルがとノイズ・ジェネレーター(雑音発生器)とともに、岸に打ちつける「波」を表現する《PlasticWaves(プラスティックの波)》。
電気ドリルやおもちゃのレーザーガンといった「楽器」は打楽器のホーコン・ステーネが担当しています。 |
.
 CHANDOS CHANDOS
|


CHSA 5160
(SACD HYBRID)
\2800 →\2590 |
ネーメ・ヤルヴィ・コンダクツ・オッフェンバック
~
オッフェンバック:管弦楽作品集
《天国と地獄》 序曲/《美しきエレーヌ》
序曲/
《月世界旅行》 序曲とバレエ/《鼓手長の娘》
序曲/
《ホフマン物語》 間奏曲と舟歌/《青ひげ》
序曲/
《ランタン灯りでの結婚式》 序曲/
《ジェロルスタン大公妃殿下》 序曲/
《ヴェル=ヴェル》 序曲/《パリの生活》
序曲 |
ネーメ・ヤルヴィ(指揮)
スイス・ロマンド管弦楽団 |
ヤルヴィ節全開! オッフェンバック!
サン=サーンス(CHSA 5122)、マスネ(CHSA
5137)に続く、スイス・ロマンド管弦楽団とネーメ・ヤルヴィのコンビによるフランス作品集。
最新巻は、ドイツ生まれ、フランスで活躍したオペレッタ王、ジャック・オッフェンバック(1819-1880)!
代表作「天国と地獄(地獄のオルフェ)」を始めとするオペレッタからの序曲、そして歌劇「ホフマン物語」から「ホフマンの舟歌」など、オッフェンバックの魅力を余すところ無く伝えるプログラム。大ヤルヴィの華やかなタクト、スイス・ロマンド管の鮮やかな管弦楽で聴く、珠玉のオッフェンバックをどうぞ。
※録音:2015年6月23日-24日、ヴィクトリア・ホール(ジュネーヴ、スイス)

どうもヤルヴィ、最近冴えてる。
スイス・ロマンド管とのフランス系アルバム2つ、そしてロイヤル・スコティッシュ・ナショナル管とのスッペ、フチークと快進撃が続いている。
全然息子に負けてない。 |

CHSA 5137
(SACD HYBRID)
\2800 →\2590 |
ネーメ・ヤルヴィ・コンダクツ・マスネ ~ マスネ:管弦楽作品集
歌劇 《ル・シッド》 より バレエ組曲/
オラトリオ 《聖処女》 より 聖処女の最後の眠り*/
歌劇 《ラオールの王》への序曲/チェロと管弦楽のための幻想曲*/
序曲 《フェードル》/劇音楽 《復讐の三女神》
より 宗教的な場面*/
歌劇 《バザンのドン・セザール》 より セビリャーナ/絵のような風景
|
トルルス・モルク(チェロ)*
ネーメ・ヤルヴィ(指揮)
スイス・ロマンド管弦楽団 |
ヤルヴィの新たなるフレンチ・プログラムジュール・マスネの管弦楽作品!
スイス・ロマンド管弦楽団、ロイヤル・スコティッシュ・ナショナル管弦楽団、ヨーテボリ交響楽団、ベルゲン・フィルハーモニー管弦楽団を振り、世界でも類を見ない驚異的なペースで新録音を世に送り出しているエストニアの巨人ネーメ・ヤルヴィ。サン=サーンス(CHSA
5104)、シャブリエ(CHSA 5122)と続く「フレンチ・レパートリー」シリーズの最新作は、19世紀フランスのオペラ作家、ジュール・マスネ(1842-1912)の管弦楽作品集!
「タイスの瞑想曲」で知られる歌劇「タイス」や「マノン」、「ウェルテル」など、数多くのオペラを作曲したことで知られるマスネは、オペラ以外にも管弦楽曲、歌曲など、多くの作品を残している。
オペラ以外にスポットの当たることの少ないマスネの知られざる管弦楽作品を、ネーメ・ヤルヴィの鋭いタクトで紹介する。ヤルヴィが2012年に音楽監督に就任したスイスの名門、スイス・ロマンド管弦楽団、スヴェンセンのチェロ協奏曲で好演を聴かせてくれたノルウェーの名チェリスト、トルルス・モルクの組み合わせにも期待。
※録音:2013年7月11日-12日、ヴィクトリア・ホール(ジュネーヴ、スイス) |
|

CHSA 5122
(SACD HYBRID)
\2800 →\2590 |
ネーメ・ヤルヴィ・コンダクツ・シャブリエ
シャブリエ:
楽しい行進曲/歌劇《グヴァンドリーヌ》序曲/
ハバネラ/狂詩曲《スペイン》/ラメント/
気まぐれなブーレ(モットル編)/田園組曲/
喜歌劇《エトワール》より 3つの楽章/
喜歌劇《いやいやながらの王様》より 2つの楽章 |
ネーメ・ヤルヴィ(指揮)
スイス・ロマンド管弦楽団 |
ネーメ・ヤルヴィが振る熱き"シャブリエ"!スイス・ロマンドとのフレンチ・シリーズ!
ロイヤル・スコティッシュ・ナショナル管弦楽団、エーテボリ交響楽団、ベルゲン・フィルハーモニー管弦楽団を振り、世界でも類を見ない驚異的なペースで新録音を世に送り出しているエストニアの巨人ネーメ・ヤルヴィ。
ヤルヴィが2012年に音楽監督に就任したスイスの名門、スイス・ロマンド管弦楽団と贈る新シリーズ「フレンチ・レパートリー」からエマニュエル・シャブリエ(1841-1894)の管弦楽作品集が登場!
法律を学び、内務省に勤務し、公務員として働きながら作曲を独学で学んだシャブリエ。
1880年(39~40歳)で内務省を退職、公務員という肩書を捨て、作曲家の道を歩むことを選んだ男、シャブリエの管弦楽作品を、ネーメ・ヤルヴィのタクトが熱く、力強く、勢い豊かに盛り上げる!
スペインでの印象を題材とした狂詩曲「スペイン」や、自身の手で管弦楽版へと編曲を行った「楽しい行進曲」、モットルのオーケストレーションによる「気まぐれなブーレ」など、シャブリエの管弦楽作品集は、スッペの「序曲&行進曲集」(CHSA
5110)に続く大ヒットの予感!
※録音:2012年6月27日-29日、ヴィクトリア・ホール(ジュネーヴ、スイス)
|
|
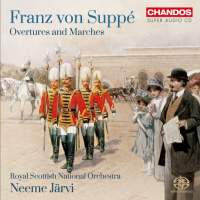
CHSA 5110
(SACD HYBRID)
\2800 →\2590 |
ネーメ・ヤルヴィの快進撃は続く!新作はウィーンのオペレッタ王「スッペ」!
スッペ:序曲&行進曲集
喜歌劇《軽騎兵》序曲/喜歌劇《ボッカッチオ》序曲/
ボッカッチオ行進曲/喜歌劇《スペードの女王》序曲/
愉快な変奏曲/喜歌劇《詩人と農夫》序曲/
喜歌劇《ファティニッツァ》のモチーフによる行進曲/
喜歌劇《モデル》序曲/
演奏会用行進曲《丘を上り谷を下って(いたるところに)》/
喜歌劇《イサベラ》序曲/喜歌劇《美しきガラテア》序曲/
行進曲《フアニータ》/
喜歌劇《ウィーンの朝・昼・晩》序曲 |
|
ネーメ・ヤルヴィ(指揮)
ロイヤル・スコティッシュ・ナショナル管弦楽団 |
全5巻の「オーケストラ版ワーグナー」を完成させ、前作の「サン=サーンス」(CHSA
5104)では、フランス音楽との予想以上の相性の良さを披露してくれたネーメ・ヤルヴィとロイヤル・スコティッシュ・ナショナル管弦楽団(RSNO)。
快進撃を続けるヤルヴィ一族の長老が次に送り出してきたのは、フランチェスコ・エゼキエーレ・エルメネジルド・スッペ=デメッリ。またの名をフランツ・フォン・スッペ(1819-1895)の「序曲」と「行進曲」!
アドリア海、ダルマチア地方のスプリト(現在のクロアチアの都市)で生を受けたスッペ。
オーストリアの首都ウィーンで本格的に「オペレッタ」を流行させた19世紀最大のオペレッタ作曲家の1人であり、その作風から「ウィーンのオッフェンバック」という異名を得ていたという。
華やかで劇的、オーケストラがダイナミックに鳴るスッペの「序曲」と「行進曲」は、ネーメ・ヤルヴィとRSNOのコンビにとって実は理想的とも言えるプログラムなのである。
ヤルヴィとスッペ。改めてそのレパートリーの広さに脱帽です。
|

CHSA 5158
(SACD HYBRID)
\2800 →\2590 |
またまた大ヒットなるか!?
ヤルヴィ(指揮)&ロイヤル・スコティッシュ
フチークの祝祭 「マーチ・アルバム」!
ユリウス・フチーク:
演奏会用序曲 《マリナレッラ》 Op.215
絵画的行進曲 《叔父テディ》 Op.236
演奏会用ワルツ 《ドナウ伝説》 Op.233
行進曲 《メリー・ブラックスミス》 Op.218
おどけたポルカ 《小言親父》 Op.210*
大管弦楽のための演奏会用行進曲 《剣闘士の入場》
Op.68
演奏会用序曲 《ミラマーレ》 Op.247
イタリアの大行進曲 《フローレンティナー》
Op.214
演奏会用ワルツ 《冬の嵐》 Op.184
行進曲 《ヘルツェゴヴィナ》 Op.235
行進曲 《連隊の子供たち》 Op.169
ワルツ 《小さなバレリーナ》 Op.226
アメリカの行進曲 《ミシシッピ川》 Op.160(161)
演奏会用行進曲 《将官旗の下に》 Op.82 |
|
ネーメ・ヤルヴィ(指揮)
ロイヤル・スコティッシュ・ナショナル管
デイヴィッド・ハバード(ファゴット)* |
「スッペ」に続く、「マーチ・アルバム」!熱きネーメ・ヤルヴィのフチーク登場!
その大迫力の演奏でヒットしたフランツ・フォン・スッペの「序曲&行進曲集(CHSA
5110)」に続くネーネ・ヤルヴィのマーチ・アルバムは、代表作「剣闘士の入場」で知られるチェコの作曲家、ユリウス・アルノシュト・ヴィレーム・フチーク(1872-1916)の管弦楽作品集!
オーストリア=ハンガリー帝国下のボヘミアに生まれ、ドヴォルザークに作曲を師事、軍楽隊の指揮者を務めながら、400曲以上の行進曲、ワルツ、ポルカを作曲。特に「剣闘士の入場(雷鳴と稲光)」は、サーカスにおけるピエロのテーマとして世界中で親しまれている。
ネーメ・ヤルヴィの鋭いタクトで祝祭的に彩る、ボヘミアのリズムとエネルギッシュな金管、メロディックな旋律。「スッペ」以上の大ヒット間違いなし!
※録音:2015年2月16日-17日、ロイヤル・コンサート・ホール(グラスゴー)
|
|
| |
|
|
ルイ・ロルティ(ピアノ)&エレーヌ・メルシエ(ピアノ)
ラフマニノフ:ピアノ・デュエット集
2台のピアノのための組曲第1番 Op.5 《幻想的絵画》
2台のピアノのための組曲第2番 Op.17
交響的舞曲 Op.45(作曲者自身の編曲による2台ピアノ版) |
ルイ・ロルティ(ピアノ)
エレーヌ・メルシエ(ピアノ) |
ルイ・ロルティ&エレーヌ・メルシエ、ラフマニノフの2台ピアノ作品集!
プーランクの作品集(CHAN 10875)で、久しぶりの登場となったルイ・ロルティ、エレーヌ・メルシエのコンビ。本格的なデュオ・アルバムとして、ラフマニノフの2台ピアノのための作品集が登場!
ラフマニノフ最後の作品となった交響的舞曲の2台ピアノ版、そしてデュオ・ピアノのために書かれた2つの組曲。モーツァルトやラヴェル、ベートーヴェンのアルバムでも見事なデュオを披露してきた名コンビが、2台のファツィオーリ・ピアノで弾く美麗なるラフマニノフです。
※録音:2014年12月5日-7日、ポットン・ホール(サフォーク) |
| . |
|
|
ノセダの大人気シリーズ/カゼッラ第4弾
カゼッラ:管弦楽作品集 Vol.4
交響的断片 《水上の修道院》 Op.19*
大管弦楽のための 《英雄的悲歌》 Op.29
交響曲第1番ロ短調 Op.5 |
ジャナンドレア・ノセダ(指揮)
BBCフィルハーモニック
ジリアン・キース(ソプラノ)* |
イタリアの知られざる作品を紹介するジャナンドレア・ノセダの人気シリーズ「ムジカ・イタリアーナ」。中でも、来日公演などで大きな反響を得てきたのが、アルフレード・カゼッラ(1883-1947)の管弦楽作品集。ついに「交響曲第1番」を収録した第4巻が登場!
オペラが絶大な存在感を放っていた20世紀初期のイタリアにおいて、管弦楽曲の作曲家として成功を収めたカゼッラ。初期の作品である交響曲第1番から、第1次世界対戦の犠牲者に捧げた「英雄的悲歌」まで。
ジャナンドレア・ノセダという最良の理解者を得て復権される、カゼッラの管弦楽作品にご期待ください!
※録音:2013年9月12日-13日、2015年2月11日-12日、メディア・シティUK(サルフォード)

ひそかにベストセラー
ノセダ&BBCフィル
カゼッラ:管弦楽作品集Vol.1~3
|
|
|
ノセダ&BBCフィル
カゼッラ:管弦楽作品集Vol.1
カゼッラ:
交響曲第2番ハ短調Op.12(世界初録音)
スカルラッティアーナOp.44
|
マーティン・ロスコー(ピアノ)
ジャナンドレア・ノセダ(指揮)
BBCフィルハーモニック
|
|
秘曲の伝道師ジャナンドレア・ノセダが燃える!ムジカ・イタリアーナ最新作はカゼッラ!
灼熱のマエストロ、ジャナンドレア・ノセダが母国イタリアの知られざる音楽を発掘、紹介する"ムジカ・イタリアーナ"シリーズ。
レスピーギ、ヴォルフ=フェラーリ、ダラピッコラが登場してきた"ムジカ・イタリアーナ"に新たに加わるのは、両大戦間のイタリア音楽界で大きな影響力を誇ったアルフレード・カゼッラ(1883-1947)!
オペラが隆盛を誇っていた19世紀~20世紀イタリアの中で、交響曲や管弦楽曲の作曲に取り組んだカゼッラ。
パリ音楽院への留学時代にはフォーレに作曲を師事し、ラヴェルやエネスコと親交を深め、さらにはドビュッシー、ロシア国民楽派、マーラー、R・シュトラウス、バルトーク、シェーンベルク、ストラヴィンスキーといった作曲家たちの作品からも影響を受けるなど、オペラに偏っていた当時のイタリア以外の音楽と積極的に接した作曲家なのである。
エネスコに捧げられたマーラーからの影響を思わせる約50分の大作「交響曲第2番」は、このノセダ&BBCフィルの演奏が世界初録音。
また母国イタリアの先人スカルラッティの音楽をベースとしたピアノと管弦楽のための「スカルラッティアーナ」には、英国の名手マーティン・ロスコーがソリストとして参戦するなど、カゼッラの管弦楽作品集に好奇心をくすぐられること必至!
知られざる名曲秘曲の伝道師ノセダの熱きタクトが、プッチーニ後のイタリアを支えたカゼッラの音楽を現代に解き放ちます!
|
|
|
|
ノセダ&BBCフィルのカゼッラ第2弾!
カゼッラ:管弦楽作品集Vol.2
管弦楽のための協奏曲Op.61(世界初録音)
深夜にてOp.30*
《蛇女》Op.50より 交響的断章 |
ジャナンドレア・ノセダ(指揮)
BBCフィルハーモニック
マーティン・ロスコー(ピアノ)* |
世界初録音!管弦楽のための協奏曲!
灼熱のマエストロ、ジャナンドレア・ノセダとBBCフィルハーモニックの「ムジカ・イタリアーナ」シリーズ最新作は、アルフレード・カゼッラ(1883-1947)の「管弦楽作品集Vol.2」!
来日公演でも大反響を呼んだ「交響曲第2番」(CHAN
10605)に続く第2集では、「管弦楽のための協奏曲」が世界初録音!オペラが隆盛を誇る両大戦間のイタリアで器楽音楽の再興に力を注ぎ、ヴィヴァルディの音楽の復権においても重要な役割を果たしたカゼッラ。
ノセダ&BBCフィルは、後に妻となるイヴォンヌ・ミュラーに捧げられた初期の作品で唯一の標題音楽「深夜にてOp.30」、カルロ・ゴッツィの寓話劇「蛇女」を題材とした同名のオペラからの「交響的断章」、そしてコンセルトヘボウ管の創立50周年を記念して献呈された大作「管弦楽のための協奏曲」を収録。オペラの陰に隠れた20世紀イタリアの巨匠、カゼッラの音楽、管弦楽作品の完全復権へ
――!ノセダ&BBCフィルの破竹の快進撃が続きます!!
|
|
|
|
ノセダ&BBCフィル
カゼッラ:管弦楽作品集Vol.3
交響的狂詩曲《イタリア》 Op.11
序奏、コラールと行進曲 Op.57
シンフォニア Op.63(交響曲第3番) |
ジャナンドレア・ノセダ(指揮)
BBCフィルハーモニック |
ノセダ&BBCフィルのムジカ・イタリアーナ!最新作はカゼッラ後期の大作"交響曲第3番"!
タリアの灼熱のマエストロ、知られざる名作の伝道師ジャナンドレア・ノセダとBBCフィルハーモニック。
同コンビの代名詞「ムジカ・イタリアーナ」シリーズ最新作は、アルフレード・カゼッラ(1883-1947)の管弦楽作品集第3巻!「シンフォニア
Op.56(交響曲第3番)」を収録!
オペラの専制政治時代と呼んでも過言ではないほどに、オペラが絶大な存在感を放っていた20世紀初期のイタリアにおいて、管弦楽曲の作曲家として成功を収めたカゼッラ。
イタリアにおける"スペインのアルベニス"を目指して作曲された「イタリア
Op.11」、1935年に完成した木管、金管、打楽器、ピアノとコントラバスのための作品でストラヴィンスキーの影響が見られる「序奏、コラールと行進曲
Op.57」、そしてシカゴ交響楽団の創立50周年のために作曲され、1941年3月に初演が行われたカゼッラ後期の大作「シンフォニア(交響曲第3番)」。
マルトゥッチの薦めによりフランス、パリ音楽院でラヴェルやエネスコと共に作曲を学んだカゼッラの管弦楽作品。 ジャナンドレア・ノセダという最良の理解者を得て、本格的な復権の時が来た
――!
|
|
| . |
|
|
タスミン・リトル(ヴァイオリン)
イギリスのヴァイオリン協奏曲集
コールリッジ=テイラー:ヴァイオリン協奏曲ト短調
Op.80
ディーリアス:ヴァイオリンと管弦楽のための組曲
ウッド:ヴァイオリン協奏曲イ短調 |
タスミン・リトル(ヴァイオリン)
アンドルー・デイヴィス(指揮)
BBCフィルハーモニック |
タスミン・リトル&A・デイヴィス!ディーリアス&コールリッジ=テイラー!
知られざる作品の探求、そしてイギリス音楽の伝導者として長いキャリアを歩む女流ヴァイオリニスト、タスミン・リトル。同じくイギリス音楽のスペシャリストでありディーリアン仲間であるアンドルー・デイヴィスと共に描く、イギリスのヴァイオリン協奏曲集が登場!
タスミン・リトル&アンドルー・デイヴィスのディーリアスと言えば、ヴァイオリン協奏曲とチェロ協奏曲、二重協奏曲を収録したCHSA
5094の大ヒットも記憶に新しいが、ここではディーリアスの「組曲」と、サミュエル・コールリッジ=テイラー(1875-1912)、ハイドン・ウッド(1882-1934)のヴァイオリン協奏曲といった知られざる作品を収録。
ディーリアスの他、エルガーやモーランなどのヴァイオリン協奏曲でも名録音を生み出してきたタスミン・リトルとアンドルー・デイヴィス。イギリス音楽ファン、ヴァイオリン協奏曲ファン要チェックのプログラムです!
※録音:2015年5月1日-3日、メディア・シティUK(サルフォード)

|
| |
|
|
ポール・ワトキンス(チェロ)
アメリカのチェロ作品集
バーバー:チェロ・ソナタ ハ短調 Op.6
バーンスタイン:《ミサ曲》 より 3つの瞑想曲
(作曲者自身の編曲によるチェロとピアノ版)
カーター:チェロ・ソナタ
クラム:無伴奏チェロ・ソナタ
コープランド:《ビリー・ザ・キッド》
より ワルツとセレブレーション
(作曲者自身の編曲によるチェロとピアノ版) |
ポール・ワトキンス(チェロ)
ヒュー・ワトキンス(ピアノ) |
ワトキンス兄弟の新たな旅はアメリカへ!
19世紀末から20世紀後半まで、近代イギリスのチェロ作品を時系列に沿って辿るという意義深い作品集(全4巻)を完成させたポール・ワトキンス、ヒュー・ワトキンスの兄弟デュオ。新たな旅立ちは、アメリカのチェロ作品へと向かう。
サミュエル・バーバー、レナード・バーンスタイン、エリオット・カーター、ジョージ・クラム、そしてアーロン・コープランドといった、アメリカを代表する作曲家たちが書いた多彩なチェロ・ソナタとチェロ・トランスクリプションを、二人の名手が濃密に描きます。
※録音:2015年5月25日-27日、ポットン・ホール(サフォーク)

|
<マイナー・レーベル歴史的録音・旧録音>
GRAND SLAM
|
|
|
ハイフェッツの2トラック、38センチ、オープンリール・テープ復刻
第4弾はブラームスとブルッフ!
(1)ブラームス:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調
Op.77
(2)ブルッフ:スコットランド幻想曲 Op.16 |
ヤッシャ・ハイフェッツ(ヴァイオリン)
(1)フリッツ・ライナー(指揮)
シカゴ交響楽団
(2)サー・マルコム・サージェント(指揮)
ロンドン新交響楽団
オシアン・エリス(ハープ) |
セッション録音:(1)1955 年2 月21、22 日/オーケストラ・ホール(シカゴ)、(2)1961
年5 月15、22 日/ウォルサムストウ・タウン・ホール(ロンドン)
使用音源:Private archive (2 トラック、38
センチ、オープンリール・テープ)/録音方式:ステレオ(アナログ)
■制作者より
ハイフェッツの2 トラック、38 センチ、オープンリール・テープ復刻第4
弾です。
ブラームスはGS 2050(2011 年8 月、2 トラック、19
センチのオープンリール・テープ使用。廃盤)以来の復刻ですが、ブルッフは当シリーズ初復刻です。音質については、従来通りと申し上げれば、それで十分かと思います。
解説書にはかつてRCA のRED SEAL 部門の部長を務め、ハイフェッツの録音を多数手がけたチャールズ・オコーネルの手記「ヤッシャ・ハイフェッツ〈その2〉」を掲載します。(「ヤッシャ・ハイフェッツ〈その1〉」はメンデルスゾーン&ベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲、GS
2137 に掲載しています。非常に興味深い内容なので、併せてどうぞ) (平林直哉) |
<国内盤>
<映像>

9/29(火)紹介新譜
マイナー・レーベル新譜
 ODRADEK RECORDS ODRADEK RECORDS
|

ODRCD 321
(ボーナスDVD付き
※PAL方式)
\2400 |
「カリオン」~ニールセンの足跡
カール・ニールセン(1865-1931):木管五重奏曲
op.43 (1922)
カイ・ヘルマー・センティウス(1889-1966):木管五重奏曲
op. 16 (1934)
イェンス・レーシェン・エンボルグ(1876-1957):木管五重奏曲
op. 74 (1935)
スヴェンド・シモン・シュルツ(1913-98):
木管五重奏のための小セレナーデ「アムレット」
(1943) |
カリオン(木管五重奏団):
【ドーラ・シェレシュ(Fl)
エギルス・ウパトニエクス(Ob)
エギルス・シェーフェルス(Cl)
ダヴィド・M.A.パルムクヴィスト(Hr)
ニルス・アンデルス・ヴェドステン・ラーセン
(Fg)】 |
ニールセン生誕150 年記念!ニールセンの木管五重奏曲とそれに影響された作品集!
このディスクには生誕150 周年を迎えるデンマーク人作曲家カール・ニールセンの木管五重奏曲とニールセンに影響を受けた3
人の作曲家による世界初録音の作品が収録されている。
ニールセンの木管五重奏曲は彼の作品の中でも最も革新的で洗練されたものの一つで、旋律と伴奏といった従来の構造を捨て去り、よりバランスの取れた実験的なスタイルを探るため、様々な楽器を組み合わせることで、豊かな響きを創造した。
デンマークのアンサンブル「カリオン」の生演奏は、空間的な位置が作り出す音響を利用して作品を具象化している。すなわち、目立った旋律を演奏する場合には一歩前に出て緻密なサウンドを作り出し、それ以外の楽器は一歩後ろに下がったり一列に並んだりすることでまとまりのあるコラールを形成するのだ。この作品における興味深く非常にユニークな解釈である。
3 曲の世界初録音はシュルツの一種独特であるが叙情的な「アムレット」、カラフルで多彩なエンボルグ、空想的で親しみやすいセンティウスの作品により構成されている。
※ご注意!特典DVDはPAL方式のため通常の日本のDVDプレイヤーでは見ることはできません。 |
| |
|
|
「ゴーン・イントゥ・ナイト・アー・オール・ジ・アイズ」
トーマス・コチェフ(b.1988):
gone into night are all theeyes (2013、世界初録音)
エリック・モー(b.1954):We Happy Few
レオン・キルヒナー(1919-2009):ピアノ三重奏曲
チャールズ・アイヴズ(1874-1954):ピアノ三重奏曲 |
トリオ・アパッショナータ:
【リディア・チェルニコフ(Vn)
アンドレア・カサルビオス(Vc)
ロナルド・ロリム(Pf)】 |
4世代に渡るアメリカのピアノ三重奏曲作品集
録音:2013 年8 月7-10 日、オクタヴィアン・オーディオ,75’36 ※日本語解説つき
ブラジル、スペイン、アメリカ出身のアーティストで構成されるトリオ・アパッショナータは、ピーボディ音楽院(アメリカ)の学生時代に結成された。アメリカ音楽の遺産に敬意を表して、4
世代に亘るアメリカ人作曲家のアンサンブル作品を1
枚のディスクに収めた。
コチェフのこの作品はこのアルバムのために委嘱したもので、タイトルはホルヘ・ルイス・ボルヘスの詩集Poems
of the Night の冒頭の一節から引用されている。エリック・モー(b.1954)のWeHappy
Few は作曲家自身の持論を反映したタイトルである。「室内楽における逆説的経済的アート。減らすと増える。」と言うものだ。
シェーンベルクの弟子として最初のアメリカ人であるレオン・キルヒナー(またはカーシュナー)のピアノ三重奏曲(1954)は、それまでのロマン派的表現の仕方を最もよく踏襲している。
アイヴズ作品の第1 楽章は哲学の父が語りかけてくるような非常に意識の高い真面目な印象。対して第2
楽章のタイトル「TSIAJ」は'This Scherzo Is
A Joke(このスケルツォはジョークです)’の頭文字をとったものである。
最終楽章ではまたシリアスなトーンに立ち返り、最後はミュージカル『ロック・オブ・エイジズ』に登場する賛美歌で閉じている。予期していた解決和音は寸止めされ、夜想的な空間が戻ってくる。 |
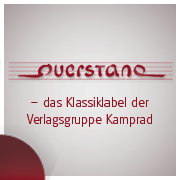 QUERSTAND QUERSTAND
|
|
|
「ライ(プ)ツィンガー・アレルライ」
~ファゴット四重奏編曲集(ドミニク・シュルツ編)
ワーグナー:「ローエングリン」第3幕への前奏曲
ベートーヴェン:交響曲第5番 ハ短調 Op.67
メンデルスゾーン:弦楽のための交響曲第7番ニ短調
MWV N7 |
ライツィンガー・バスーン四重奏団:
【ダーヴィト・ペーターゼン(Fg)
テオドール・ナウモフ(Fg)
ドミニク・シュルツ(Fg,コントラFg)
カール・フェンツレット(Fg)】 |
ファゴット四重奏によるローエングリンに運命?!
録音:2015 年1 月31 日、2 月1 日、DDD、54'40
曲目だけ見るとオーケストラのCD だが、すべてファゴット四重奏による演奏。どこか紳士然とした落ち着きのある曲調になっており、ファゴット好きでなくても面白く聞けるだろう。
アンサンブル名のライツィンガーとは、ドイツの高名なファゴット製作者シュテファン・ライツィンガーが作る楽器のこと。 |
| |
|
|
「夢と忘我」~ウテ・プルッグマイヤー=フィリップ即興集
ラヴェルとスクリャービンの間
メシアンによるミニマリスト風な連想
夜の歌についての騒乱
エヴァンスの面影のあるオスティナート
混沌とした対話、引用、対比 |
ウテ・プルッグマイヤー=フィリップ(ピアノ) |
録音:2013 年5 月 ドレスデン、DDD、67'43
いずれも即興演奏。ウテ・プルッグマイヤー=フィリップは1962
年生まれのドイツのピアニスト。1986 年からドレスデン音楽大学で即興演奏を指導し、1993
年からは同大学のピアノ専攻およびピアノ即興演奏専攻の教授を務めている。 |
| |
|
|
「ルター」~有名コラール集
バッハ:私たちの神は堅固な砦 BWV720/ヴルピウス:私たちの神は堅固な砦/
クレプス:高みにおられる神だけに栄光があるように/
ブクステフーデ:さあ来てください、異教徒の救い主よ/
バッハ:天の高みから BWV248/シャイン:天の高みから/
バッハ:これらは聖なる十戒 BWV 635/
シャイン:賛美を受けてください、イエス・キリストよ/
バッハ:私たちは唯一の神を信じます BWV680/
バッハ:私たちは唯一の神を信じます BWV681/
ヴルピウス:私たちに恵み深く平安を与えてください/
バッハ:私たちの主であるキリストがヨルダン川に来た
BWV684/
バッハ:私たちの主であるキリストがヨルダン川に来た
BWV685/
バッハ:深い苦しみから私はあなたに呼びかける
BWV687/
クレプス:天におられる私たちの神よ/クレプス:キリストは死の縄に縛られて/
パッヘルベル:キリストは死の縄に縛られて/
ヴァルター:私たちは人生の真っ只中で/クレプス:私たちは人生の真っ只中で/
ヴァルター:平和と喜びのうちに私は発ちます/
バッハ:私たちの救い主、イエス・キリストは死の縄に縛られて
BWV626/
コルトカンプ:主である神よ、私たちはあなたを讃えます/
バッハ:私たちは唯一の神を信じます BWV680 |
フェリックス・フリードリヒ(Org)
ゲルト・フリッシムート(指揮)
ヴァイマール・フランツ・リスト音楽院室内合唱団
ゼバスティアン・ゲリング(指揮)
ミヒャエルシュタイン室内合唱団
クリスティアン・スコボフスキー(指揮)
フライベルク大聖堂少年聖歌隊
オーパス4(トロンボーン四重奏)
ライナー・ゲーデ(Org)
ジャン・フェラール(Org)
ウルリヒ・ベーメ(Org)
クリストフ・クルマッハー(Org)
ライプツィヒ愛好・教会合唱団、
ライプツィヒ金管コレギウム |
DDD、60'47
VKJK9602 、VKJK0106 、VKJK0719 、VKJK0516
、VKJK1427 、VKJK0219 、VKJK9506 、VKJK0202、VKJK0603、VKJK0007
からの寄せ集め。オルガンもしくは合唱によるコラール集。 |
 ACTE PREALABLE ACTE PREALABLE
|
|
|
ヨアンナ・ブルズドヴィチ(1943-):
サルバドール・ダリ展の16の絵画(ピアノのための)(*)
アメリカの春(ヴァイオリンとピアノのためのソナタ)(+)
希望と愛の歌(チェロとピアノのためのソナタ)(#) |
トマシュ・ヨチ(ピアノ)
カロリナ・ピョントコフスカ=ノヴィツカ(ヴァイオリン(+))
クシシュトフ・パヴウォフスキ(チェロ(#)) |
|
録音:2014年4月(*/+)、2015年5月、スタニスワフ・モニュシュコ音楽アカデミー・コンサートホール、
グダンスク、ポーランド
ヨアンナ・ブルズドヴィチはポーランドのワルシャワに生まれた作曲家。6歳で作曲を始め、ワルシャワのフリデリク・ショパン音楽アカデミーを卒業後、1968年フランス国費留学生としてパリに移りナディア・ブーランジェ、オリヴィエ・メシアン、ピエール・シェフェールに師事。
4つのオペラをはじめオリジナリティ豊かな作品を書き上げています。
|
| . |

|
ノクターン ヴィオラのピアノのための音楽
ベートーヴェン(1770-1827):ノットゥルノ
Op.42(プリムローズ版)
ショパン(1810-1849):
夜想曲第2番変ホ長調 Op.9 No.2/夜想曲第13番ハ短調
Op.48 No.1
夜想曲第18番ホ長調 Op.62 No.2
ヤン・クシチテル・ヴァーツラフ・カリヴォダ
(ヨハン・バプティスト・ヴェンツェル・カリヴォダ)(1801-1866):6つの夜想曲
Op.186 |
マルチン・ムラフスキ(ヴィオラ)
アンナ・スタジェツ・マカンダシス(ピアノ) |
|
録音:2015年6月21-23日、I・J・パデレフスキ音楽アカデミー新講堂(アウラ・ノヴァ)、
ポズナン、ポーランド
マルチン・ムラフスキは「マイケル・キンバー:ヴィオラのための音楽」シリーズでおなじみのポーランドのヴィオラ奏者。
|
.
 BOMBA-PITER BOMBA-PITER
|
|
|
ラフマニノフ、ヴァシレンコ、ブーニン:ヴィオラとピアノのための音楽
ラフマニノフ(1873-1943):幻想小曲集 Op.3
から セレナード(No.5)
セルゲイ・ヴァシレンコ(1872-1956):ヴィオラ・ソナタ
ニ短調 Op.46(1923)
ラフマニノフ:幻想小曲集 Op.3 から メロディ(No.3)
レヴォリ・ブーニン(1924-1976):ヴィオラ・ソナタ
ニ短調 Op.26(1955)
ラフマニノフ:ヴォカリーズ Op.34 No.14 |
オレク・ラリオーノフ(ヴィオラ)
マリア・カムーチリナ=ラリオーノヴァ(ピアノ) |
|
録音:データ記載なし
セルゲイ・ヴァシレンコはモスクワに生まれモスクワ音楽院でタネーエフ他に師事した作曲家・指揮者・音楽教師。ヴィオラ・ソナタはロシアの名ヴィオラ奏者ヴァジム・ボリソフスキー(1900-1972)に献呈されました。
レヴォリ・ブーニンはモスクワに生まれ、モスクワ音楽院でシェバーリン、ショスタコーヴィチに師事した作曲家。ヴィオラ・ソナタはショスタコーヴィチに献呈されました。
オレク・ラリオーノフは2004年から2014年までマリインスキー劇場管弦楽団の副首席奏者を務め、2015年現在フォンランドのトゥルク・フィルハーモニー管弦楽団に在籍しているロシアのヴィオラ奏者。
|
| . |

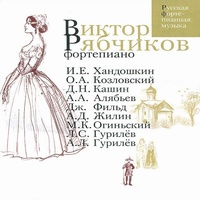
CDMAN 572-14
(2CD)
\3600 →\3290 |
注目されることの少ないロシア・ピアノ音楽アルバム
ハンドキシンからグリリョーフまで ピアノ作品集
[CD 1]
イヴァン・ハンドシキン(1747-1804):ロシア民謡「私は川へ行こう」による変奏曲
オシプ・コズロフスキー(1757-1831):ポロネーズ=パストラーレ/ポロネース
ニ短調
ダニール・カーシン(1769-1841):ロシア民謡「私は通りを行く」による変奏曲
アレクサンドル・アリャビエフ(1787-1851):
カドリーユ/マズルカ/マズルカ/コントルダンス/「ナイチンゲール」への別れ
ワルツ
ジョン・フィールド(1782-1837):
夜想曲第2番ハ短調/夜想曲第14番ハ長調/夜想曲第13番ニ短調
夜想曲第5番変ロ長調/夜想曲第10番ホ短調
アレクセイ・ジーリン(1766-1848):ワルツ変イ長調
ミハウ・クレオファス・オギンスキ(1765-1833):
ポロネーズ「別れ」/ポロネーズ「祖国への別れ」
[CD 2]
レフ・グリリョーフ(1770-1844):
ポロネーズ ホ短調/前奏曲ハ短調/前奏曲嬰ヘ長調/前奏曲嬰ヘ短調
ポロネーズ ト短調/前奏曲ニ長調/前奏曲ト短調/ポロネーズ
ホ短調
アレクサンドル・グリリョーフ(1803-1858):
ポルカ=マズルカ ト長調
ヴァルラーモフの歌曲「夜明けに彼女を起こさないで」による変奏曲
ポルカ=マズルカ イ短調
グリンカのオペラ「皇帝に捧げた命(イヴァン・スサーニン)」の三重唱による変奏曲
レフ・グリリョーフ:ロシア民謡「私は人々に非難された」による変奏曲 |
ヴィクトル・リャプチコフ(ピアノ) |
|
録音:2012年7月、V・S・ポポフ記念合唱アカデミー・コンサートホール、モスクワ、ロシア
ロシア・ピアノ音楽史上で注目されることの少ない作曲家たちの作品を取り上げたアルバム。外装およびブックレットはキリル文字表記のみです。
|
| |
|
|
春の六日間 オリガ・グラーゾヴァ(グースリ)
オリガ・グラーゾヴァ:
Best wishes for summer / With you / Waltz
/ Irish wind
Cool track / Cloud (Faniar) / Six days
of spring
Sigurd / Where sweet disappeared / With
you (remix by tembr69) |
オリガ・グラーゾヴァ(グースリ、歌、ピアノ) |
|
録音:データ記載なし
ロシアの民族撥弦楽器グースリを操るユニークなミュージシャン、オリガ・グラーゾヴァ(オルガ・グラゾワ)のセカンド・アルバム。
|
| |
|
|
エク=スタシス
プロコフィエフ(1891-1953):ピアノ・ソナタ第8番変ロ長調
Op.84
ジオ・ジャニアシヴィリ:インヴォケーション/エク=スタシス |
マリア・ネムツォヴァ(ピアノ) |
|
録音:2014年、場所の記載なし
ジオ・ジャニアシヴィリはグルシアの首都トビリシに生まれ、アメリカ合衆国に移住して活躍している若手作曲家。収録2作品はいずれも2012年から2013年にかけてマリア・ネムツォヴァとコラボレーションしたもので、声や口笛もパファーマンスに加わります。
マリア・ネムツォヴァは1984年モスクワに生まれのピアニスト。モスクワ音楽院でユーリー・スレサーレフに、ロンドンの王立音楽カレッジでドミトリー・アレクセーエフに、イーモラ(イタリア)のピアノ・アカデミーでレオニード・マルガリウスに師事。
|
| |

] BP 14-15
\2200 |
20世紀サックス アドルフ・サックス生誕200年
ドビュッシー(1862-1918):
サクソフォンと管弦楽のための狂詩曲 L.98(アルトサクソフォンとピアノのための版)
ヒンデミット(1895-1963):アルトサクソフォンとピアノのためのソナタ
ピエール・サンカン(1916-2008):ラメントとロンド
フェルナンド・デクリュック(1896-1954):サクソフォン・ソナタ嬰ハ長調 |
ヴィタリー・ヴァトゥーリャ(サクソフォン)
マリア・ネムツォヴァ(ピアノ) |
|
録音:データ記載なし
映画会社「20世紀フォックス」のパロディのようなタイトルとジャケット・デザイン。サクソフォンの考案者アドルフ・サックス(1814-1894)の生誕100年にあたる2014年に合わせて企画されたアルバムです。
ヴィタリー・ヴァトゥーリャは1987年モスクワに生まれ、A・シニートケ音楽カレッジでユーリー・ヴォロンツォフに、グネーシン音楽アカデミーでマルガリータ・シャポシニコヴァに師事したロシアの若手で今最も注目を集めているサクソフォン奏者。
|
| |

CDMAN 395-09
\2200
【未案内旧譜】 |
ラフマニノフ、チェスノコフ、チャイコフスキー、スヴィリードフ:合唱作品集
ラフマニノフ(1873-1943):来たれ、伏し拝まん
チェスノコフ(1877-1944):幸いなり
ラフマニノフ:生神女よ、喜びたまえ/6つの詩篇
チェスノコフ:優しき光
チャイコフスキー(1840-1893):われらの父/共與の聖句
スヴィリドフ(1915-1998):ばらはいずこに
ロシア民謡/オシプ・コズロフスキー(1757-1831)編曲:トロイカ
スヴィリードフ:
「プーシキンの花輪」から 冬の朝,こだま
カンタータ「ユヴェナリスの鞭」から 第1曲,第6曲
「プーシキンの花輪」から
樟脳とムスク,起床ラッパが鳴り響く,ナターシャ,立て、臆病者
左に草原、右に草原 |
スモーリヌイ大聖堂室内合唱団
ヴラディーミル・ベグレツォフ(指揮) |
| 録音:2005年4月17日、5月25日、11月19日、2006年2月25日、ライヴ、スモーリヌイ大聖堂、サンクトペテルブルク、ロシア |
| |

CDMAN 469-11
\2200
【未案内旧譜】 |
フランクのヴァイオリン・ソナタをコントラバスで
グリンカ(1804-1857):ヴィオラ・ソナタ
ニ短調(1828)
シューベルト(1797-1828):アルペッジョーネ・ソナタ
ト短調 D.821(1824)
フランク(1822-1890):ヴァイオリン・ソナタ
イ長調(1886) |
セルゲイ・アコポフ(コントラバス)
ナターリア・アルズマノヴァ(ピアノ)
|
|
録音:2004年5月、場所の記載なし
ヴァイオリン、ヴィオラ、アルペッジョーネのために書かれたソナタをコントラバスで演奏した興味深いアルバム。
セルゲイ・アコポフはレニングラード音楽院在学中にチェロからコントラバスに転向し1967年に卒業したロシアのコントラバス奏者。当録音前より2015年現在マリインスキー劇場管弦楽団員。
※現時点で品薄となっている可能性がございますので、お早目のオーダーをお願いいたします。
|
<マイナー・レーベル歴史的録音・旧録音>
.
 MARSTON MARSTON
|

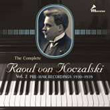
53016-2
(3CD)
\7500 →¥6990 |
「ラウル・フォン・コチャルスキ 全録音集 第2集
1930-1939 年」 |
ラウル・フォン・コチャルスキ(ピアノ) |
○Homocord 社録音 1930 年9 月頃、ミラノ
バッハ:イギリス組曲第3番 BWV 808~ガヴォット
ト短調/
モーツァルト:ドイツ舞曲 変ロ長調 K.600-3/
モーツァルト:ドイツ舞曲 ヘ長調 K. 602-2/
ショパン:
前奏曲 イ長調 Op.28-7/ワルツ 変ニ長調
Op.64-1 「小犬のワルツ」/前奏曲 変ニ長調
Op.28-15 「雨だれ」/
子守歌 変ニ長調 Op.57/練習曲 変ト長調Op.10-5
「黒鍵」/練習曲 変ト長調 Op.25-9 「蝶々」/
練習曲 ヘ短調 Op.25-2/練習曲 ヘ長調
Op.25-3/ピアノ・ソナタ第2番 変ロ短調 Op.35
「葬送」~第3楽章
○Electrola/His Master's Voice 社録音 1937
年3 月17 日、ベルリン
ショパン:
3つのエコセーズ Op.72-3(ニ長調,ト長調,ニ長調)/マズルカ
ヘ長調 Op.68-3/
夜想曲 嬰ヘ長調 Op.15-2/ポロネーズ 変イ長調
Op.53 「英雄ポロネーズ」/スケルツォ 変ロ短調
Op.31
○Deutsche Grammophon/Polydor 社録音 1938
年6 月28、29 日、ベルリン
ショパン:
子守歌 変ニ長調 Op.57/即興曲 嬰ヘ長調
Op.36/幻想即興曲 嬰ハ短調Op.66/夜想曲 変ホ長調
Op.9-2/
12の練習曲 Op.10/12 の練習曲 Op.25/練習曲
変イ長調/練習曲 変ニ長調/練習曲 ヘ短調/
ワルツ 変イ長調 Op.34-1/ワルツ 変イ長調
Op.69-1 「別れのワルツ」
○Deutsche Grammophon/Polydor 社録音 1939
年6 月10、12、19 日、ベルリン
ショパン:
ワルツ 変ホ長調 Op.18 「華麗なる大円舞曲」/ワルツ
イ短調 Op.34-2/ワルツヘ長調 Op.34-3/
ワルツ 変ニ長調 Op.64-1 「小犬のワルツ」/ワルツ
変イ長調Op.64-3/ワルツ 変ト長調 Op.70-1/
24 の前奏曲 Op.28/前奏曲 変イ長調/前奏曲
嬰ハ短調 Op.45/バラード ヘ長調 Op.38/
バラード 変イ長調 Op.47/バラードヘ短調
Op.52
○Deutsche Grammophon/Polydor 社録音 1939
年11 月17 日、ベルリン
ショパン:バラード ト短調 Op.23/夜想曲
ロ長調 Op.32-1/夜想曲 ハ短調 Op.48-1 |
好評のコチャルスキ全集待望の第2集発売!
ADD、232'49
第1 集 52063-2(2CD)に続くポーランドのピアニスト、ラウル・フォン・コチャルスキの第2
集。
今回は1930 年代のミラノとベルリンの録音。ラウル・フォン・コチャルスキ(1885-1948)は、ショパンの愛弟子カロル・ミクリの高弟で、つまりショパンの孫弟子。しかし直系ということを抜きにしても、柔らかな音色で豊かな香りを振りまく彼のショパンはたいへん優美で魅力に溢れている。いつもながらMarston
の丁寧な復刻は見事なもので、全盛期のコチャルスキの美感が伝わってくる。 |
<メジャー・レーベル>
<国内盤>
 アクースティカ アクースティカ
|
|
|
「杉目奈央子 ピアノ・リサイタル ライブ III」
~園田高弘没後10年を偲んで
J.S.バッハ:
フランス組曲 第5番 ト長調 BWV.816
半音階的幻想曲とフーガ ニ短調 BWV.903
ベートーヴェン:ピアノソナタ第31番 変イ長調
Op.110
バッハ=ブゾーニ:シャコンヌ ニ短調 BWV.1004 |
杉目奈央子(ピアノ) |
杉目奈央子の園田高弘没後10 年を偲ぶリサイタル!
録音:2014年11月3日、トッパン・ホール(ライヴ収録)/67:13
「演奏会に寄せて」 杉目奈央子
ピアノの巨匠・園田高弘先生がご逝去され早10年が経ってしまいました・・。
まず「ピアニスト園田高弘没後10年を偲んで」に出演させていただきましたこと、そしてCD制作まで、これまでお世話になりました皆様に厚くお礼申しあげます。
私が地元・大分県の「園田高弘賞ピアノコンクール」に出場して以来、先生は私の恩師であり、指針であり、憧れでもありました。ピアノの真髄までチャレンジされている先生のおそばで勉強させていただけたことで私はピアノに対していつも真剣に、そして真っ向から向き合う心構えが出来ました。「そこはそうじゃないだろう」と横で弾いて下さった先生。大舞台でお弾きになる先生が田舎から出てきた一生徒である私のためにレッスンで真剣に弾いて下さるそのお姿に、いつも感謝と尊敬と畏敬の念を感じていました。そして志を高く持つことを教えられました。
「『杉目流』という自分のスタイルを創りなさい。そして先生はいなくなるんだから自立しなさい」と仰ったお姿がついこの前のことのように想い出されます。この10年、ポッカリ穴が開いたようでしたが奥様の春子先生が先生のご遺志を受け継がれ、若いピアニスト達に演奏会を開く機会をお与え下さいました。そして園田先生のピアニズムは生き続けています。
今回の演奏会での曲目は、園田先生が生前弾かれた曲(先生はバッハから現代まで物凄いレパートリーの数でしたが)、CDに残された曲からバッハを中心に弾かせていただきました。改めて勉強し直すと色々とまた違う面が見えてくるものです。組曲なら当時のダンスを、半音階的幻想曲とフーガならキリスト教を、ベートーヴェンのソナタならベートーヴェンの人生を、バッハ=ブゾーニならばバイオリン独奏のシャコンヌをと研究しました。
ピアノという楽器は一筋縄ではいかない大変な楽器ですがやはり園田先生と同様、私もピアノが大好きです。そしてピアノのお陰で色々な方とご縁が出来ました。このCDをお聴きいただけますご縁にも感謝しつつ・・・。(杉目奈央子ブックレットから抜粋) |
| |

PPCA-607
【未案内旧譜】
\2667+税 |
「杉目奈央子 リサイタル ライブ II」
J.S.バッハ:パルティータ第1番変ロ長調BWV.825
ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第23番ヘ短調Op.57「熱情」
シューマン:幻想曲ハ長調Op.17
シューマン=リスト:献呈 |
杉目奈央子(ピアノ) |
杉目奈央子のリサイタル・ライヴ第2集!
録音:2007年4月14日、トッパン・ホール(ライヴ収録)
杉目奈央子は桐朋学園大学を終了後、ミュンヘン国立音楽大学に留学。ドイツ国家演奏家資格を取得。1986
年第2 回園田高弘賞ピアノコンクール優勝、1996
年第8回ブゾーニ国際ピアノコンクール第6位入賞などを受賞。既に「ピアノ・リサイタル
ライブI」(PPCA-605)でリリースしている。 |
| |
|
|
「田山正之のラフマニノフIII」
ラフマニノフ:
ショパンの主題による変奏曲Op.22
コレルリの主題による変奏曲Op.42
幻想小曲集 Op.3 より(No.3 メロディ ホ長調、No.5セレナード変ロ短調) |
田山正之(ピアノ) |
ロンドンを中心に演奏活動を続ける田山正之、得意とするラフマニノフ作品集第3弾!
録音:2012年12月26日-28日、三重県津市 三重総合文化センタ大ホール(セッション収録)
田山正之は幼少時代をロンドンで育つ。桐朋学園大学ソリストディプロコースで学び、更に渡英して王立音楽大学、更にギルドホール音楽院の双方で演奏家ディプロマとともに特別賞を受賞。第16回園田高弘賞ピアノコンクールにて大山平一郎指揮、九州交響楽団とラフマニノフピアノ協奏曲第2番を共演し、園田高弘賞受賞(第一位)。他、ロンドン国際ピアノコンクールにて、ヨーロッパ
ベートーベンピアノ協会より特別賞受賞、英国ブラントバーミンガム国際ピアノコンクール
第1位など、数多くの受賞歴を持つ。
現在ロンドンを中心に演奏活動を展開している。ラフマニノフ全曲録音を目指し、既に「ソナタ第1
番。第2 番」(EvicaHTCA-6003)、「エチュード集」(PPCA-611)を発売している。 |
| |

PPCA-611
【未案内旧譜】
\2667+税 |
「田山正之のラフマニノフII」
ラフマニノフ:
練習曲集「音の絵」Op.33(全8曲)
5つの幻想小曲集 Op.3
練習曲集「音の絵」Op.39(全9曲) |
田山正之(ピアノ) |
田山正之のラフマニノフ第2弾!音の絵全曲!
録音:2007年12月7日-9日、2008年4月4日、三重県津市
三重総合文化センタ大ホール(セッション収録)
私はここ数年、ラフマニノフのソナタ、ピアノ協奏曲を含め「大曲」と言われる作品を多く演奏してきたが、今回、一曲一曲それぞれが独特の情熱に溢れ宝石のように粒ぞろいで固有の輝きを持った「小曲」集に取り組んだ事は大きな挑戦であり、たいへん実になる経験となった。
ラフマニノフ自身、生涯に渡りオペラ、交響曲、ピアノ協奏曲など大曲を中心に力を注いできた中で必要と感じた商品における表現への挑戦、その賜物である「音の絵」。ピアニストとして、また作曲家として歩み始めた初期の小品集と合わせて彼の作品の魅力を噛みしめつつ、ラフマニノフの音を追求していきたいと思う。(田山正之、ライナー・ノートより) |
イプシロン・インターナショナル
|
|
|
「ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン」
ベートーヴェン:
(1)ピアノ・ソナタ第8番 ハ短調 作品13「悲愴」
(9’43/5’02/4’34)
(2)ピアノ・ソナタ第13番 変ホ長調 作品27-1
「幻想曲風ソナタ」
(5’06/2’05/3’10/6’08)
(3)ピアノ・ソナタ第26番 変ホ長調 作品81a
「告別」
(7’21/3’48/6’12)
(4)ピアノ・ソナタ第31番 変イ長調 作品110
(6’15/2’33/3’15/6’59) |
吉川隆弘(ピアノ) |
イタリアで高い評価を得ているピアニスト吉川隆弘による渾身のベートーヴェン!
録音:2014~2015 年、 東京Studio Pianoforte
芸大大学院修了後ミラノを拠点に活動する吉川はこれまでペトルーシュカや夜のガスパールを始め、技巧的なピアニストとしての一面が強調されてきましたが、今回満を持してベートーヴェンのピアノ・ソナタ4
曲のアルバムを録音しました。
2008 年以降、ミラノのレコード会社LIMEN
からソロ2 枚、室内楽2 枚、そして今年3 月には室内楽でドイツ・グラモフォンからもCD
をリリースしてきましたが、今回は初めて東京のスタジオでの録音、日本での制作となり、最高音質のHR
カッティングを採用しました。
深い楽譜の読みに裏付けられた細部まで磨き上げられた演奏を支える、倍音までコントロールされている「吉川の音」が再現されています。このCD
は今後イタリアをはじめ海外でもリリースされる予定です。
※放送予定
10 月26 日NHKFM『ベスト・オブ・クラシック』にて『吉川隆弘&F.メローニ
デュオ・コンサート』が放送されます。
2015 年7 月4 日 サントリーホール・ブルーローズで開催された吉川隆弘とミラノ・スカラ座首席クラリネット奏者ファブリツィオ・メローニのデュオ・コンサートはNHK
に収録されました。
9 月4 日にはNHKBS プレミアム『クラシック倶楽部』にて放映されました。10
月26 日NHKFM『ベスト・オブ・クラシック』にて放送されます。
※2015 年 秋公演「吉川隆弘 ピアノ リサイタル」
主催・お問合せ:イプシロン・インターナショナル株式会社
TEL: 03-6421-8131 / E-mail: tokyo@ypsilon-i.com
□ 東京公演 日時:11 月8 日(日)14:30
開演 会場:サントリーホール・ブルーローズ
□ 関西公演 日時:11 月11 日(水)19:00
開演 会場:兵庫県立芸術文化センター神戸女学院小ホール |

|
|
![]()