 BMC BMC
|
|
|
「バルトーク&フォーク」〜バルトーク:
民族音楽にインスパイアされた男声合唱曲全集
ベラ・バルトーク(1881-1945):
4つの古いハンガリー民謡BB60(1910-12)/
夕べ BB30(1903)/スロヴァキア民謡BB77(1917)/
セーケイ民謡BB106(1932)/過ぎ去った時よりBB112(1935)/
4つの古いハンガリー民謡BB60(1910-12,改訂1926) |
タマーシュ・ブブノー(指揮)
聖エフレム男声合唱団
バラス・ソコライ・ドンゴー
(フルート、バグパイプ、タロガトー)
マルク・ブブノ
(ガードン[パーカッシヴ・チェロ]) |
バルトークの民謡に影響された男声合唱曲集
録音:2014 年12 月ベラ・バルトーク・ウニタリアン・パリッシュ教会,ブダペスト
[62:25]
バルトークのアカペラ男声合唱のための作品を全て収録。既発売の「バルトーク合唱曲全集」(BMC186)と比べてこのディスクが特筆に値するのはハンガリーの様々な民族楽器が合唱に花を添えていること。
クラリネットの一種でサックスに似た音色のタロガトー、吹き歌いする奇妙なフルート、バグパイプなどバルトークが民謡を採集した時に実際に聴いたであろう、活き活きとした姿がよみがえります。 |
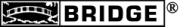 BRIDGE BRIDGE
|
|
|
ボトスタインのヒンデミット「長いクリスマスの晩餐」
オリジナルの英語版初録音!
ヒンデミット:歌劇「長いクリスマスの晩餐」(オリジナル版) |
カミーユ・サモラ(S,ルチア/ルチア2世)
サラ・マーフィー
(MS,マザー・ベイヤード/アーメンガード)
ジャレット・オット(Br,ロドリック/サム)
ジョシュ・クィン(B,ブランドン)
グレン・セヴン(T,チャールズ)
キャスリーン・マーティン(MS,ジュヌヴィエーヴ)
キャスリン・ガスリー(S,レノーラ)
スコット・マーフリー(T,ロドリック2世)
レオン・ボトスタイン(指揮)
アメリカ交響楽団 |
録音:2014年12月19日、ニューヨーク、DDD、48'49
パウル・ヒンデミットの「長いクリスマスの晩餐(ロング・クリスマス・ディナー)」オリジナル英語版の初録音。「長いクリスマスの晩餐」はヒンデミット晩年のオペラ。1
幕仕立てで1 時間にも満たない短さ、小編成のオーケストラと小振りなオペラだが、晩年のヒンデミットの熟達した筆が楽しめる作品である。
1960 年から翌年にかけて作曲、1961
年12
月にマンハイムでドイツ語訳により初演、オリジナルの英語版は1963
年3 月にジュリアード音楽院で初演された。舞台は米国の田舎町のベイヤード家。クリスマスの夜、ベイヤード家の人々が集まりディナーが始まるが、時代が徐々に進み、古い世代が亡くなり新しい世代が生まれながら、90
年ほどの時が過ぎていく。
「長いクリスマスの晩餐」には既にCDがあるが、オリジナルの英語を用いた録音はこれが初となる。珍しい作品を積極的に取り上げることで知られるレオン・ボトスタインが、長年の手兵アメリカ交響楽団を指揮して2014
年12 月19 日にリンカーン・センターのアリス・タリー・ホールで行った上演のライヴ録音。米国の優秀な若手歌手が多く起用されている。 |
| |
|
|
ロジャー・セッションズ(1896-1985):
ヴァイオリンとピアノのための作品集
(1)デュオ(1942)
(2)アダージョ(1947)
(3)ブレンダのためのワルツ(1936)
(4)ヴァイオリン・ソナタ(1953)
(5)ピアノ・ソナタ第2番(1946) |
(1)-(5)デイヴィッド・ホルツマン(Pf)
(1)(4)デイヴィッド・ボウリン(Vn) |
ロジャー・セッションズの1930〜50年代の作品集
録音:2009-2012 年 [62:17]
アメリカ作曲界の重鎮セッションズが1930
から50 年代までに書かれたピアノ、ヴァイオリンのための作品を収録。いずれも無調による厳しい音楽で新ウィーン楽派との強い親和性が見られる。 |
 ELECT RECORD ELECT RECORD
|
|
|
「20世紀の木管五重奏曲集」
イルジー・パウエル(1919-2007):木管五重奏曲
テレサ・プロカッチーニ(1934-):
「道化師の音楽」〜木管五重奏のための4つの小品
ポール・パターソン(1947-):5つの管楽器のためのコメディ
ウォルター・ピストン(1894-1976):木管五重奏曲
ジェルジュ・リゲティ(1923-2006):木管五重奏のための6つのバガテル
クロード・ドビュッシー(1862-1918):小さな黒んぼ
フリドリン・ダリンジャー(1933-):ポルカ |
木管五重奏団「コンコルディア」 |
ルーマニアの木管楽器奏者達!
72’29
ルーマニアの木管五重奏団、コンコルディアによる20
世紀に作曲された木管五重奏作品集。
チェコ、イタリア、イギリス、アメリカ、ハンガリー、フランス、オーストリアの作曲家と、多彩な色を持つ作品を選曲しています。 |
| |
|
|
「ヴィヴァルディ:ファゴット協奏曲集」
(1)ファゴット協奏曲 ハ長調
RV472
(2)ファゴット協奏曲 イ短調
RV497
(3)ファゴット協奏曲 変ロ短調「夜」RV501
(4)オーボエ(ファゴット)協奏曲
ヘ長調 RV457
(5)ファゴット協奏曲 ニ短調
RV481
(6)ファゴット協奏曲 イ短調
RV498 |
ミルティアーデ・ネノイウ(Fg)
(1)-(4)イラリオン・ヨネスク=ガラーツィ(指揮)
ヤシ・モルドヴァ・フィルハーモニー室内管弦楽団
(5)(6)クリスチャン・ブランクーシ(指揮)
室内合奏団 |
70’48
ルーマニア国立放送交響楽団のファゴット奏者として1956
年から2003 年まで、47 年間と長期に渡り在籍していた、ネノイウによるヴィヴァルディのファゴット協奏曲集。 |
 GEGA NEW GEGA NEW
|
|
|
日本語解説付き!ブルガリアの作曲家ヴォデニチャロフ作品集
ヤッセン・ヴォデニチャロフ(b.1964):
(1)異教徒の歌
(2)シルバー・ドロップス
(3)蝶のメタモルフォーゼ
(4)キネティック・コンポジション
(5)5つの不思議な作品 |
(1)パスカル・ロフェ(指揮)
アンサンブル・イティネレール
(2)クワザー・サキソフォン四重奏団
(3)ロビン・ファロ(ヴィオラ・ダ・ガンバ)
(4)アンサンブル・イティネレールの独奏者達:
【フロリアン・ロリドン(チェロ)、
ナタリー・フォルジェ(オンド・マルトノ)、
棚田文紀(ピアノ)】
(5)ピエール=イブ・アルトー(オクトバスFl)、
アンヘル・ケミン(S)、
マキシヌ・エカドール(Perc)、
アントワーヌ・アレリーニ(Pf)、
ヤッセン・ヴォデニチャロフ(エレクトロニクス)、
ジャヴィエ・ゴンザレス(指揮)
フランス・フルート・オーケストラ |
※日本語解説付き 69:07
ヤセン・ヴォデニチャロフはブルガリア出身の気鋭の作曲家でソフィア国立高等音楽院で学んだ後、パリ国立高等音楽院でポール・メファノに師事した。数々のコンクールで受賞し国際的評価を得ている。
現代音楽の様々な技法を駆使しジョージ・クラムにも通じる神秘的でイマジナリーな世界が拡がる。
ブックレットには日本語解説のページもあります。 |
| |

GR 26
(2CD)
\4200 |
マルタの作曲コンクール優勝作品と特別賞作品
(1)スティーヴン=ジョセフ・サイラ(b.1984):イムディーナのカトリン
(2)パウル・ポルテッリ(b.不詳):
5つのドゥム・カルム・サイラの詩(室内オーケストラのための組曲) |
クリストファー・ムスカート(指揮)
マルタ・フィルハーモニー管弦楽団 |
録音:2014 年11 月、35:42/36:49
2012 年に開催されたAPS 銀行国際作曲コンクールの優勝作品と特別賞の受賞作品の二つを収録。このコンクールはマルタ共和国の銀行が主催するもので課題は地中海に浮かぶ島マルタ共和国を題材にした管弦楽組曲を作曲する、というものであった。ジョセフ・サイラが優勝、ポルテッリが特別賞を受賞した。
作品はどちらも現代音楽とは無縁で古典派、ロマン派を思わせる親しみ易い作風。 |
.
 GENUIN GENUIN
|
|
|
「ヴェッセリーナ・カサロヴァGENUIN初登場!
ロシア・アリア集」
(1)ムソルグスキー:《ホヴァーンシチナ》〜神秘的な力、大きな力が
(2)ダルゴムイシスキー:《石の客》〜グラナダは神秘のヴェールに包まれ
(3)チャイコフスキー:《エフゲニー・オネーギン》〜ああ、ターニャ、ターニャ!
(4)リムスキー=コルサコフ:《皇帝の花嫁》〜大好きなお母さん
(5)チャイコフスキー:《スペードの女王》前奏曲*
(6)チャイコフスキー:《スペードの女王》〜リーザの好きなロマンスを歌います
(7)チャイコフスキー:《スペードの女王》〜ああ、今の世にはうんざりする
(8)グリンカ:《イヴァン・スサーニン》〜
かわいそうな馬は野で倒れ/泣くな、泣くな、小さな孤児よ
(9)チャイコフスキー:《オルレアンの乙女》〜
そう、時は来た/許しておくれ、故郷の野や丘よ
(10)ボロディン:《イーゴリ公》〜陽の光が消えていく
(11)ムソルグスキー:《ボリス・ゴドゥノフ》〜なんともどかしくだらだらと
(12)リムスキー=コルサコフ:《雪娘》〜スコモローフたちの踊り*
*はオーケストラのみ |
|
ヴェッセリーナ・カサロヴァ(Ms)
パヴェル・バレフ(指揮)
バーデン=バーデン・フィルハーモニー |
人気・実力兼ね備えたメゾのヴェッセリーナ・カサロヴァ、GENUIN初登場!新レパートリーのロシア・アリア集!
録音:2014 年10 月24 日、59'20
ヴェッセリーナ・カサロヴァも栄光あるブルガリア人歌手の一人である。1965
年、ブルガリア中部のスターラ・ザゴラの生まれ。ソフィアで学んだ後、1989
年に西欧に出るやたちまち評判となり、僅か数年のうちに国際的な人気歌手になった。
当時のカサロヴァは主にモーツァルトやロッシーニのメッゾソプラノ役を歌っており、その後ヘンデルなどのバロックオペラの男装メッゾソプラノ役でも名を馳せる。その一方で、メッゾソプラノを代表する役であるビゼー《カルメン》のタイトルロールを歌ったのはやっと2008
年のこと。
サン=サーンスの《サムソンとデリラ》のデリラはようやく2011
年に初めて歌っている。カサロヴァが役選びに慎重なことが分かるだろう。
2014 年に録音されたこのロシア・アリア集は、カサロヴァがロシアオペラに取り組もうとする意気込みが強く感じられる内容になっている。
ブルガリア人歌手に共通した低音域の力強さはロシアオペラでは大きな武器になっている一方で、四半世紀に渡る西欧での活動で磨き上げられた洗練された美感がまたとても良く映えている。
|
| |
|
|
〜ドイツ音楽コンクール 2013年度優勝者〜
「Playtime!」〜サブリナ・マ(パーカッション)
(1)マルクス・ボンガルツ(1963-):ポートレート
※
(2)スティーヴ・ライヒ(1936-):ナゴヤ・マリンバ
(3)リリ・ウィロウ:…azz
e hamechir…
(4)ブライアン・ファーニホウ(1943-):ボーン・アルファベット
(5)ヤン・ショワー(1977-):プラトー
※
(6)ホセ・M.ロペス・ロペス(1956-):カルキュオ・セクレト
(7)リリ・ウィロウ:ハヴァナ
※
(8)マルクス・ボンガルツ:ポエム
※
※世界初録音 |
サブリナ・マ(Perc)
(3)(7)リリ・ウィロウ(Vo)
(1)オルガ・ツェルティコヴァ(Cemb)
(2)(7)(8)アレキサンドロス・ジョヴァノス
(マリンバ、ドラムス)
(5)(7)ヤン・ショワー(エレキ・ギター) |
録音:2014 年10 月、56’12
イギリス生まれ、香港育ちのパーカッショニスト、サブリナ・マ。2013
年のドイツ音楽コンクールの優勝者は、マイケル・ユドゥー、デイヴィッド・フリードマン、中村功に師事。
パーカッションにおけるダイナミックで多彩な表現に満ちた楽曲をセレクトしたこのアルバムは世界初録音曲を4
曲収録しています。
ロペス・ロペスの“カルキュオ・セレクト”は、神秘的で幻想の世界へと誘うヴィブラフォンの音色。音に身を委ねたくなる癒しのパワーがすごい!
スティーヴ・ライヒの“ナゴヤ・マリンバ”は、しらかわホールの柿落としのために委嘱された作品。2
つのマリンバが絡み合いながら、音型を少しずつ変えていきます。 |
| |
|
|
「テルミン・ソナタ」
〜クリストファー・タルノフ:テルミン・オリジナル作品集
クリストファー・タルノフ(1984-):
テルミン・ソナタ第1番
テルミンとピアノのための間奏曲第1番
テルミン・ソナタ第2番
テルミンとピアノのための間奏曲第2番 |
カロリーナ・エイク(テルミン)
クリストファー・タルノフ(ピアノ) |
録音:2014 年10 月、56’41
世界初録音!前代未聞!?テルミン・ソナタ誕生!
若き人気テルミン奏者カロリーナ・エイク。オーボエ奏者ハインツ・ホリガーとの共演や、フィンランドの現代音楽作曲家カラレヴィ・アホが彼女のために作曲した「テルミン協奏曲」、ハンブルク・バレエ団「人魚姫」(音楽:レーラ・アウエルバッハ)での演奏や、ファジル・サイの「交響曲第2
番“メソポタミア”」の録音に参加するなど、活動の場を広げている注目のテルミン奏者です。
このアルバムもエイクのために書かれたもの。別世界へと誘う神秘的な音色のテルミンですが、とても明快で力強さを感じる音色、音程の確かさ、ピアノとの自然な融合はさすがの一言です。
テルミンのためのソナタ…これからのテルミン作品の代表作になりそうです。 |
| |
|
|
「チェロ・エフェクト」
〜チェロ四重奏編曲集(編曲:S.ドラブキン)
プロコフィエフ:バレエ「ロミオとジュリエット」より
(少女ジュリエット/マーキュシオ/百合の花を持った娘たちの踊り/
仮面/騎士たちの踊り)
プッチーニ:「トスカ」より“星は光りぬ”/
ラフマニノフ:ヴォカリーズ/
アントニ・カルロス・ジョビン:デサフィナード/
ウィリアム・クリストファー・ハンディ:セントルイス・ブルース/
デイヴ・ブルーベック:トルコ風ブルー・ロンド/
ルロイ・アンダーソン:シンコペーテッド・クロック/
アントニ・カルロス・ジョビン:ワン・ノート・サンバ/
作曲者不詳:ブーブリキ/
ボビー・ティモンズ:モーニン/
ポール・デズモンド:テイク・ファイブ/
チャイコフスキー:感傷的なワルツ |
ラストレッリ・チェロ四重奏団:
【セルジオ・ドラブキン、
キラ・クラフツォフ、
キリル・ティモフェーエフ、
ミシャ・デグチャレフ】 |
録音: 2014 年6 月、53’45
「誰も聴いたことのないチェロ四重奏を演奏しよう」と、ロシア出身のクラフツォフとベラルーシ出身のドラブキンを中心に2002
年に結成されたラストレッリ・チェロ四重奏団。
クラシック、ジャズ、ラテン、ブルースなど、ジャンルを限定せずにとにかく楽しくチェロ四重奏曲を親しんでもらおうと選曲されています。
メンバーの一人、ドラブキンがすべて編曲。携帯電話のCM
で有名になったプロコフィエフの「ロミオとジュリエット」のあのメロディや、抜け感のあるリズムが心地よいカルロス・ジョビンの「デサフィナード」、ユーモアあふれるアンダーソンの「シンコペーテッド・クロック」、ジャズの名曲「テイク・ファイブ」も変拍子の難曲を息の合ったアンサンブルで演奏しています。 |
| |
|
|
「Blue」〜ドビュッシー、リン・ヤン、ラヴェルの弦楽四重奏曲集
ドビュッシー:弦楽四重奏曲ト短調Op.10
リン・ヤン(1982-):弦楽四重奏曲第1番「この瞬間に」
ラヴェル:弦楽四重奏曲ヘ長調 |
アマリリス四重奏団:
【グスタフ・フリーリングハウス(Vn)
レナ・サンドゥ(Vn)、
レナ・エッケルス(Va)、
イヴ・サンドゥ(Vc)】 |
録音:2013〜2015 年、72’24
アルバム「White(GEN 11218,ハイドン&ウェーベルン)」はドイツの権威ある音楽賞「エコー・クラシック・アワード」を受賞しました。
次に「Red」「Green」と続いたこのシリーズの最新作がこの「Blue」。印象派のドビュッシー、ラヴェル、そしてアマリリス四重奏団のために作曲され、今回が世界初録音となるリン・ヤンの“弦楽四重奏曲第1
番「この瞬間に」”。中国伝統音楽を取り入れ、ほぼピチカートとグリッサンドで奏されるという難曲です。
ドビュッシーの作品はジャワのガムランからの影響を受けたとされる響き、そのドビュッシーに絶賛されたラヴェルの作品は3
作品とも、作曲家の持つ個性的なスタイルを取り入れた作風のもの。洗練されたモダンな響きが広がっています。 |
| |
|
|
「バッハ・ウィズアウト・ワーズ」〜
J.S.バッハのコラールとコラール前奏曲の編曲集 |
アンナ・クリスティアーヌ・ノイマン(ピアノ)
アンヤ・クラインミヒェル(ピアノ[連弾]) |
(1)クルターク編:四手連弾カンタータ「神の時こそいと良きときBWV106」より“ソナティーナ”
(2)「いざ来たれ、異教徒の救い主よ」※
(3)ブゾーニ編:コラール前奏曲「いざ来たれ、異教徒の救い主よBWV659」
(4)ノイマン編:四声のコラール「主よ、人の望みの喜びよ」
(5)ノイマン編:「主よ、人の望みの喜びよ」
(6)「かくも喜びに満てる日」※
(7)ランバート編:コラール前奏曲「かくも喜びに満てる日BWV605」
(8)「甘き喜びのうちに」※
(9)ケンプ編:コラール前奏曲「甘き喜びのうちにBWV751」
(10)ロード・バーナーズ編:コラール前奏曲「甘き喜びのうちにBWV729」
(11)「ひとよ、汝がつみの」※
(12)ハウエルズ編:コラール前奏曲「ひとよ、汝がつみのBWV622」
(13)「わが心の切なる願い」※
(14)ウォルトン編:コラール前奏曲「わが心の切なる願いBWV727」
(15)「おお、穢れなき神の子羊」※
(16)クルターク編:四手連弾のためのコラール「おお、穢れなき神の子羊」
(17)ウィルナー編:「マタイ受難曲BWV244」より最終合唱「我らは涙流してひざまずき」
(18)ヴォーン=ウィリアムズ編:コラール「ああ、われらと共に留まりたまえ、主イエス・キリストよBWV.253」
(19)ヴォーン=ウィリアムズ編:コラール前奏曲「ああ、われらと共に留まりたまえ、主イエス・キリストよBWV.649」
(20)「最愛のイエス、われらここにあり」※
(21)コーエン編:コラール前奏曲「最愛のイエス、われらここにありBWV731」
(22)「主イエス・キリストよ、われ汝に呼ばわる」※
(23)コラール前奏曲「主イエス・キリストよ、われ汝に呼ばわるBWV639」
(24)「深き困窮より,われ汝に呼ばわる」※
(25)クルターク編:四手連弾のためのコラール「深き困窮より,われ汝に呼ばわるBWV687」
(26)「いと高きところにいます神にのみ栄光あれ」※
(27)クルターク編:四手連弾のためのコラール「いと高きところにいます神にのみ栄光あれBWV711」
(28)ケンプ編:コラール「審判の日は来れりBWV307」
(29)ケンプ編:コラール「今ぞ喜べ、愛するキリスト者の仲間たちよBWV734」
(30)ブリッジ編:宗教歌曲「甘き死よ来たれ
BWV478」
(31)「目覚めよと、われらに呼ばわる物見らの声」※
(32)ヘス編:シュープラー・コラール「目覚めよと、われらに呼ばわる物見らの声BWV645」※
(33)レーガー編:四手連弾のための「G
線上のアリア」BWV1068
※印:アルバート・リーメンシュナイダー校訂「J.S.バッハ:371の和声的コラールと69
の通奏低音付き旋律コラール」より |
録音:2014 年9 月、69’33
J.S.バッハのコラール、コラール前奏曲、宗教曲などをピアノに編曲した作品を収録。
J.S.バッハの偉大な作品は、時代を超えて様々な編曲が多数存在します。バッハへの深い愛情や尊敬の念が詰まった現代音楽作曲家のクルタークによる四手連弾や、名ピアニスト、ヴィルヘルム・ケンプによるアレンジは、原曲をさらに魅力的で刺激的に、聴き手に新鮮な感情を与えてくれます。 |
| |
|
|
「デュオ・フォー・ワン」
ストラヴィンスキー:イタリア組曲
ヴィラ=ロボス:赤ちゃんの一族
第一組曲
セルヴェ:サンクトペテルブルクの思い出Op.15
パガニーニ:弦楽独奏のためのモーセの主題による変奏曲
ストラヴィンスキー:ペトルーシュカからの3章 |
エレナ・ガポネンコ
(チェロ&ピアノ多重録音) |
録音:2014 年7 月、8 月、11 月、68’06
4 歳からチェロとピアノをはじめ、遂には大学で両方を学んだ才媛ガポネンコのデビュー・アルバム。真似出来る人は少ないであろう、チェロとピアノ、どちらもガポネンコ自身の演奏という興味深いもの。
彼女が望む作品表現が完璧に収められています。 |
| |
|
|
「休みなさい、我が魂よ」〜R.シュトラウス:歌曲集
休みなさい、我が魂よOp.27-1/夜Op.10-3/冬の夜Op.15-2/
赤いバラ/バラのリボンOp.36-1/時なし花Op.10-7/なにもOp.10-2/
乙女の花Op.22 [矢車菊、ポピー、木づた、睡蓮]/
森のしあわせOp.49-1/若い魔女の歌Op.39-2/子守歌Op.41-1/
解き放たれてOp.39-4/ひそやかな歌Op.41-5/
詩人の夕暮れの散策Op.47-2/万霊節Op.10-8/明日!Op.27-4 |
カタリーナ・ペルジケ(ソプラノ)
ニコラス・リンマー(ピアノ) |
録音:2015 年3 月、57’02
シューベルト国際リート・コンクール、ノルウェーのソニヤ王妃国際音楽コンクールに優勝するなど、ドイツの注目のソプラノ、カテレーナ・ペルジケ。
ドレスデンのゼンパーオーパーでの喜歌劇「愉快なニーベルンゲン」のジゼルヘーマ役、フライブルク歌劇場とオルテンブルク州立歌劇場での歌劇「愛の妙薬」のジャンネッタ役など、世界各地で活躍しています。
このリヒャルト・シュトラウスの歌曲では、滑らかな美声で、甘美な歌の世界を繰り広げています。 |
| |

GEN 15380
(2CD)
\4600 →\4190 |
レオニード・サバネーエフ(1881-1968):ピアノ作品全集Vol.1
CD1)
4つの前奏曲Op.1/4つの前奏曲Op.2/2つの前奏曲Op.3/
2つの小品Op.5/2つの小品Op.6/3つの小品Op.7/
2つの小品Op.8/4つの小品Op.9
CD2)
8つの前奏曲Op.10/6つの詩Op.11/
3つの小品Op.12/4つの断片Op.13 |
ミヒャエル・シェーファー(ピアノ) |
録音:2014〜2015 年59’34/48’58
忘れられたロシアの作曲家、音楽学者、評論家サバネーエフ。タネーエフ、リムスキー=コルサコフに師事しました。
スクリャービンの友人としても知られ、スクリャービンの回想録「晩年に明かされた創作秘話」が有名です。今作はまさに貴重といえるピアノ・ソロ作品をまとめたアルバム第1弾!
埋もれたままにするのはもったいない程の小品ばかり。抒情が溢れ出る美しいメロディ。ちょっぴりの切なさも入り混じる。どこかスクリャービンのような神秘的な雰囲気も感じられます。ピアノ好きの方にオススメです。 |
 KAIROS KAIROS
|

13292KAI
(2CD)
\5000 |
「リスト・インスペクションズ(リスト検証)」
フランツ・リスト/ジョン・アダムズ/ルチアーノ・ベリオ/
フリードリヒ・チェルハ/モートン・フェルドマン/
ジェルジ・クルターク/ジェルジ・リゲティ/
トリスタン・ミュライユ/ゲラルド・ペッソン/
ヴォルフガング・リーム/サルヴァトーレ・シャリーノ/
カールハインツ・シュトックハウゼン/
ガリーナ・ウストヴォルスカヤ
のピアノ作品(全19曲) |
マリーノ・フォルメンティ(Pf) |
これは驚き!リストと20、21世紀の作曲家たちの意外な共通点に光を当てたユニークなディスクの登場!
録音:2012 年2 月20-26 日,ドイツランド・ラジオ/71:21/59:07
現代作品を中心に世界的に活躍するピアニスト、マリーノ・フォルメンティがフランツ・リストの音楽の中でこれまで見過ごされてきた音楽言語のある側面に光を当て、それと現代音楽の作曲家のピアノ作品とを比較対照させることでリストの音楽の時代を越えた先進性に光を当てる極めて特異なプログラム。
フォルメンティはこの企画の推敲におよそ6年の歳月をかけたという。ディスクではリストと現代作曲家の作品が交互に配置され、百年以上の時を越えた両者の間に不思議な共振現象を聴き手は体験することになる。
すなわちCDを聴き進むうちにリストがベリオ、シュトックハウゼン、アダムズやフェルドマン、ミュライユらと同時代の作曲家に感じられ、逆にシュトックハウゼン、リゲティ、チェルハがリストの作品のように聴こえてくる、という驚くべきプログラム。
マリーノ・フェルメンティは極めて精緻、繊細なピアノを聴かせ、彼のこれまでの全仕事の中でも最上に位置するであろう仕上がりとなっている。全体に静かで瞑想的な曲が選ばれているのでイーノやハロルド・バッドのようにアンビエントとして楽しむことも出来る。必聴です。 |
 K&K K&K
|
|
|
「キャッスル・コンサート・シリーズ」〜ルービン四重奏団
ハイドン:弦楽四重奏曲第63番(第78番)
変ロ長調Op.76-4Hob:III78「日の出」
モーツァルト:弦楽四重奏曲第14番
ト短調K.387「春」
ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第8番
ホ短調Op.59-2「ラズモフスキー第2番」 |
ルービン四重奏団 |
ルービン四重奏団のライヴによる古典派弦楽四重奏曲集
録音:2014 年11 月9 日バートホンブルク城教会(ライヴ),80min
「キャッスル・コンサート・シリーズ」より、ドイツ、フランクフルトの北にある、かつて世界の王族、貴族がこぞって訪れる温泉保養地として栄えていたバートホンブルクにあるバートホンブルクの教会で行われたコンサート。
荘厳で、その時代への想像力が掻き立てられる古城の中で、さらに時代の雰囲気を味わえる弦楽四重奏作品。
1992 年女性4 人によって結成されたルービン四重奏団。古典から現代音楽まで幅広いレパートリーを持つ実力派弦楽四重奏団です。
ハイドンの弦楽四重奏曲のなかでも傑作と称される「日の出」はロマンティックで軽快に「喜び」が音楽から聴こえてきます。そしてハイドンに献呈されたモーツァルトの「春」。ベートーヴェンの弦楽四重奏曲の傑作「ラズモフスキー第2
番」を収録。 |
 MARQUIS MARQUIS
|
|
|
「メンデルスゾーン&マクドナルド:二重協奏曲集」
メンデルスゾーン:ヴァイオリンとピアノのための二重協奏曲
ニ短調
アンドリュー・ポール・マクドナルド:
ヴァイオリンとピアノのための二重協奏曲
Op.51 |
デュオ・コンチェルタンテ:
【ナンシー・ダーン(Vn)、
ティモシー・スティーヴズ(Pf)】
マーク・デイヴィッド(指揮)
ニューファンドランド交響楽団 |
メンデルスゾーンと当コンビ委嘱作マクドナルドの二重協奏曲集
録音:2014年9月26日、27日,64’43
1997 年に結成されたヴァイオリンとピアノのデュオ「デュオ・コンチェルタンテ」による二重協奏曲集。
早熟の天才メンデルスゾーン、14
歳の時の作品「ヴァイオリンとピアノのための二重協奏曲ニ短調」はバロック風の対位法が用いられた作品で、ヴァイオリンとピアノが瑞々しく対話し、純粋な抒情が横溢した演奏です。
カナダの作曲家アンドリュー・ポール・マクドナルドの「ヴァイオリンとピアノのための協奏曲」は、デュオ・コンチェルタンテからの委嘱作。多数のソロ、デュオのカデンツァを含む超絶技巧協奏曲。シンフォニックで情熱的な作品です。 |
 MERIDIAN MERIDIAN
|
|
|
モーツァルト(モルデカイ・レヒトマン編曲):
ファゴット四重奏曲集 (原曲:フルート四重奏曲)
ファゴット四重奏曲第1番ト長調K.285
ファゴット四重奏曲第2番ハ長調K.285a
ファゴット四重奏曲第3番ヘ長調K.285b
ファゴット四重奏曲第4番変ロ長調K.298 |
ウジィ・シャレフ(Fg)
シャロン・コーエン(Vn)
ロテム・ベイデル(Va)
ヨータム・バルーク(Vc) |
モーツァルト:フルート四重奏曲のファゴット編曲版!
録音:2013 年4 月テル・アヴィヴ,55’20
イスラエル出身で、イスラエル・フィルの元首席ファゴット奏者、指揮者、指導者として大きな足跡を残しているモルデカイ・レヒトマン(1926-)。ファゴットを知り尽くした彼がモーツァルトの“フルート四重奏曲”を“ファゴット四重奏曲”に編曲。
とても暖かな音色で、ファゴットの演奏がしやすいように転調された作品は、原曲とは別の作品のような趣です。
演奏者のウジィ・シャレフは、編曲者でもあるレヒトマンに師事していました。1987年からイスラエル・フィルのファゴット奏者で現在は副首席ファゴット奏者として活躍しています。 |
| |
|
|
「タンゴ:ボディ&ソウル」
エンリケ・フランチーニ(1916-78)/ヴェルナー・トーマス=ミフネ編:
やってきた女
フリオ・デ・カロ(1899-1980)/ヴェルナー・トーマス=ミフネ編:
グアルディア・ビエハ
エドゥアルド・アロンソ=クレスポ(1956-):トリオOp.30
フアン・マリア・ソラレ(1966-):テンゴ・アン・タンゴ
ルイス・ホルヘ・ゴンザレス(1936-):希望のモンタージュ
アストル・ピアソラ(1921-92)/ホセ・ブラガート編:ブエノスアイレスの四季 |
トリオ・コルディレラス:
【エリザベス・キッパー(Vn)、
トーマス・ハインリッヒ(Vc)、
アレハンドロ・クレマスキ(Pf)】 |
録音:2014 年3 月、63’03
ヴァイオリン、チェロ、ピアノの編成でタンゴの名曲から、現代音楽作曲家が“タンゴ”からインスパイアされた作品を収録。
アルゼンチンの作曲家兼指揮者として活躍しているアロンソ=クレスポの“トリオ”はトリオ・コルディレラスが委嘱した作品。クラシックの要素とタンゴのリズムやメロディが融合。ロマンティックでありながら、ひんやりとした哀愁が美しい作品。
ジャジーな“テンゴ・アン・タンゴ”、そしてピアノ・トリオに編曲されたピアソラの傑作「ブエノスアイレスの四季」は抒情豊かで優雅に生まれ変わりました。 |
| |
|
|
「ガブリエル・フォーレ:ピアノ作品集」
舟歌第1番イ短調Op.26/バラード嬰ヘ短調Op.19/
3つの無言歌Op.17 より第3番変イ短調/夜想曲第4番変ホ長調Op.36/
ヴァルス・カプリス第2番変ニ長調Op.38舟歌第3番変ト長調Op.42/
8つの小品より第4曲、第5曲/夜想曲第6番変ニ長調Op.63/
夢のあとに(グレインジャー編) |
クリスティーヌ・クロショウ(Pf) |
録音:2014 年8 月、65’13
イギリスのピアニスト、トリニティ・ラバン・コンセルヴァトワール音楽大学の教授を務めているクリスティーヌ・クロショウによるフォーレのピアノ作品集。
ロンドンの王立音楽アカデミーにて、ヴィヴィアン・ラングリッシュ、ゴードン・グリーンに師事。ソロのほかに、室内楽にも力を入れており、ミルシテイン、ヤニグロ、デボスト、ジャック・ズーンなど数多くの共演を重ねています。
このアルバムではファツィオリのピアノで演奏しており、「舟歌第1
番」では、もの静かでセンチメンタルに奏で、小川から雄大な大河を思わせます。
「3 つの無言歌より第3 番」では、右手で歌う「メロディ」が子守歌のように語りかけてくるようです。 |
.
NEOS
|
|
|
レブエルタス没後75 年記念
シルベストレ・レブエルタス(1899-1940):アンサンブル作品集
(1)カミナンド(1937)〜器楽アンサンブル版
(2)ラジオ向きの八重奏曲(1933)
(3)プラーノス(1934)〜大アンサンブルのための
(4)真面目な小品第1番&第2番(1940)〜管楽アンサンブルのための
(5)トッカータ(1933)
〜ピッコロ、3つのクラリネット、ホルン、トランペット、
ティンパニとヴァイオリンのための
(6)3つのソネット(1938)
〜語りと管楽アンサンブル、ピアノと打楽器のための
(7)「あなたが考える理由がわかりません」(1937)
〜バリトンとアンサンブルのための
(8)フェデリコ・ガルシア・ロルカへの讃歌(1936)〜大アンサンブルのための
(9)センセマヤ(1937)〜室内アンサンブルのための
|
ローランド・クルティヒ(指揮)
アンサンブルKNMベルリン
ガブリエル・ウルティア(Br/語り) |
没後75年!これがホントの反乱(レブエルタス)!
ヨーロッパ前衛音楽の殿堂NEOSからまさかのレブエルタス作品集リリース!
録音:2008年、50:02
メキシコの作曲家兼ヴァイオリニスト、レブエルタスの没後75
年を記念したアルバム。ガルシア・ロルカへの讃歌、センセマヤなど彼の主要作品も収録され、初めてレブエルタスを聴く人にもお薦め。メキシコ先住民の音楽や当時の世俗音楽、街の喧騒をも複調、多調、ポリリズムを駆使して取り込みラテンの血が爆発する色彩豊かで生命力に満ちたすばらしい音楽。死後70
年余りを経て西洋前衛派が衰退した今、あらためてレブエルタスが注目されています。
アンサンブルKNMベルリンの演奏はレブエルタスの作品の先見性、実験性に光をあて、さながらブーレーズが演奏するストラヴィンスキーを思わせる切れ味の鋭いアンサンブルを聴かせます。お店の試聴機に入れれば大きなセールスが期待できます。
作曲家特集
シルヴェストレ・レブエルタス
SILVESTRE REVUELTAS 1899年(サンティアゴ近郊パパスキアロ)〜1940年(メキシコ・シティ)
ASVの中南米シリーズや、BMGの現代音楽レーベルCATALISTから出た真っ黒いガイコツのジャケットCDでお聞きになった方もおられるだろう。
シルヴェストレ・レブエルタス。
今から100年ほど前、1899年にメキシコで生まれた。
メキシコの作曲家といえばチャベスやポンセがそこそこ有名だし良い曲も書いているが、民族主義とクラシック音楽の素敵な融合という枠を超えることはない。
それに比べて、このレブエルタスという男の作品は荒唐無稽、大胆というか、気が狂ってるんじゃないかと思われるような曲まである。
35歳くらいまでは、メキシコ・シティやシカゴで作曲やヴァイオリンを学んだり、チャベスに招かれてメキシコSOの副指揮者を務めたりするなど、まともな音楽家の生き方を歩んでいた。それが37歳のとき、突然内戦中のスペインに渡り人民戦線側に立って戦う。そのへんからどうも普通の人間ではなくなってくる・・・。
実際、帰国してからの彼の作品は異常な作品が多い。
それらの作品を「原始的」とか「エネルギッシュ」とかいう言葉で表現している評論家もいるが、そんな生易しいものではない。ストラヴィンスキーやコダーイなど問題外。何かに取り憑かれたような、呪術的な魔力を秘めた曲。たたきつけるようなクレッシェンド、襲い掛かってくるようなフォルテッシモ。劇画的でドス黒い華やかさと冷笑的でニヒルな視線。
一体あの内乱で何が彼に起こったのか。
・・・しかしそんな作品がいくつも書けるわけがない。
帰国して2年後にアル中の末、無残な病死。
わずか40歳であった。
聴いて欲しいのは「センセマヤ(1938年)」と「マヤ族の夜(1939年)」。
廉価なバリオス盤で2曲を聴くか、20年前なら考えられなかったメジャー・レーベル・リリースによるサロネン盤で聴くか。
あるいはほかのメキシコ音楽の傑作も楽しみながらバティスの「センセマヤ」1曲を贅沢に聴くか。
どうぞお好みに合わせて。
|
 左右の顔が違う人になってます・・・。コワイです。 左右の顔が違う人になってます・・・。コワイです。
|
|
| |
|
|
マルクス・シュタンゲのジョージ・クラム:マクロコスモス第1集・第2集
ジョージ・クラム(b.1929):
マクロコスモスI(1972)
〜黄道十二宮による増幅されたピアノのための
マクロコスモスII(1973)
〜黄道十二宮による増幅されたピアノのための |
マルクス・シュタンゲ(Pf) |
録音:2007年12月(I)、2008年2月(II)、72:25
クラムの代名詞ともいえる「マクロコスモス」全4
集のうち、一人のピアニストで演奏される第1、2
集を収録。ドビュッシー、メシアン、武満に通底する美を持ちながら通常奏法の他にプリペアド・ピアノ、内部奏法そしてピアニストは時に歌ったり叫んだり口笛を吹いたりと、独自の神秘的世界が展開する。
既に多くのピアニストによって取り上げられている名作をドイツのベテラン、マルクス・シュタンゲが冴えたリアリゼーションで聴き手を惹きつける。スタンゲはアロイス・コンタルスキーに師事し20
年に渡ってシュトゥットガルト・ピアノ・デュオのメンバーを勤め、現在は内藤祐紀子&マルクス・シュタンゲ・ピアノ・デュオ、アンサンブル・フォルミンクスのメンバーとして活動している。 |
| |
|
|
イリーナ・エメリアンツェワ(b.1973)ピアノ作品集
前奏曲(1991)/ロシア風フーガ(1991-1992/2009)/
子供のための小品集(1991-1992)/
循環するファンタジー(1996)/7つの小品(1998-1999)/
ヴィーパースドルファー前奏曲(2003)/影・光(2003)
断章(2003)/オズボーン・レクイエム(2007) |
イリーナ・エメリアンツェワ(Pf) |
ロシアの女流作曲家エメリアンツェワの自作自演ピアノ作品集
録音:2009年、70:17
ロスラヴェッツ作品集(NEOS
10902)に続くエメリアンツェワのアルバム。エメリアンツェワはロシア出身。サンクト・ペテルブルクのR.コルサコフ音楽院でセルゲイ・スロムニスキに師事、後にドイツでハンスペーター・キーブルツの指導を受けている。
このCD では彼女の20代から30
代にかけての作品が収められているが、作風はバルトーク、ドビュッシーがやや進化したような曲から無調音楽まで多種多様。自らピアノを弾き生気あふれる音楽を聴かせる。 |
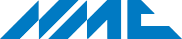 NMC NMC
|


NMC D210
(2CD)
\4600 →\4190 |
《スティーヴ・マートランド没後2年追悼企画》
スティーヴ・マートランド(1954-2013):作品集
CD1)
教訓をたれる馬たち/アンダーソン氏のパヴァーヌ/
永遠の喜び/パトロール(*)
CD2)
ビート・ザ・リトリート/肩から肩へ/
アメリカン・インヴェンション/
クロッシング・ザ・ボーダー(越境) |
スティーヴ・マートランド(指揮)
スティーヴ・マートランド・バンド
*スミス・クァルテット |
マイケル・ナイマン、グラハム・フィットキンの好きな人にはお薦め!イギリスのポスト・ミニマリズムの旗手マートランドの主要作品集!
録音:1991-2000年,CD1[68:32]/CD2[65:17]
スティーヴ・マートランドは日本の西村朗や吉松隆らと同世代のイギリスの作曲家でオランダのミニマリスト、ルイ・アンドリーセンに師事。バロック音楽、ストラヴィンスキー、ミニマリズム、ジャズ、ロック、ストリート・ミュージックなどありとあらゆる音楽の影響を受け個性的なスタイルを確立しました。
イギリスでは同じ傾向のマーク・アンソニー・タネジの双璧と目されており、大音響と激しいビートにはパンクやブリティッシュ・プログレの影響も感じさせます。特にディスク2
の「ビート・ザ・リトリート」はアンドリーセン譲りのホケトゥスとマイケル・ナイマン流のテカテカしたサウンドが合体した魅力的な作品。2013
年に惜しくも59 歳の若さで急逝したマートランドの音楽を俯瞰する上で最適のこのセット、貴重です。
Steve Martland Crossing The Border
(1990)
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=s5GJsfk7mNU
|
| |
|
|
「エコーとナルシス」〜ライアン・ウィッグル
スワース(b.1979):作品集
(1)瞳の歌(2009)
(2)インヴェンション第1巻(2010)
(3)劇的カンタータ「エコーとナルシス」(2013-14)
(4)ヴァイオリン協奏曲(2011/13)
(5)ロックの劇場(2013) |
ライアン・ウィッグルスワース(指揮)
(1)(2)(4)(5)ハレ管弦楽団
(3)クレア・ブース(S)
RSVP ヴォイシズ
パメラ・ヘレン・スティーヴン(MS)
マーク・パドモア
(4)バルナバス・ケレメン(Vn) |
録音:2014〜15 年、63’03
指揮者・ピアニストでもある作曲家ライアン・ウィッグルスワース(b.1979)初の作品集(ちなみに指揮者のマーク・ウィッグルスワースとは別人)。
指揮者としては現在ハレ管弦楽団の首席客演指揮者を勤め現代音楽を中心に録音も多い。基本的に自由な無調〜調性感があるもの作品が多い。暗い色調で色彩的なオーケストレーションを駆使したダイナミックな作風です。暗く激しいヴァイオリン協奏曲や「ロックの劇場」など聴きものです。 |
| |
|
|
「科学にインスパイアされた音楽」
セア・マスグレイヴ:パワー・プレイ [6:35]
クリストファー・マヨ:スーパーマリーン [12:08]
クラウディア・モリター:2TwoLO [11:42]
デイヴィッド・ソーアーザワー:コーチマン・クロノス [9:14]
ジェラルド・バリー:片腕のピアニスト [6:49]
バリー・ガイ:バベージ氏は夕食に来ている [9:10] |
ニコラス・コロン(指揮)
オーロラ管弦楽団 |
録音:2015 年5 月10-14 日、55’43
科学、機械、テクノロジーにインスパイアされて作曲された作品を収録。作曲者たちはロンドンのサイエンス・ミュージアムを見てそこで得たインスピレーションに基づき作曲を行ったという。一口に科学といっても作曲家によってテーマは抽象的な科学思想を作品に反映させたものからSL
や初期の電話などノスタルジックでアナログな機械を礼賛するものまで捉え方も様々。その中でもジャズ畑出身の作曲家バリー・ガイによる「バベージ氏は夕食に来ている」のウェーベルンを思わせる抽象性の高い、繊細優美な音楽が聴きもの。 |
 ODRADEK RECORDS ODRADEK RECORDS
|

ODRCD 321
(ボーナスDVD付き
※PAL方式)
\2400 |
「カリオン」〜ニールセンの足跡
カール・ニールセン(1865-1931):木管五重奏曲
op.43 (1922)
カイ・ヘルマー・センティウス(1889-1966):木管五重奏曲
op. 16 (1934)
イェンス・レーシェン・エンボルグ(1876-1957):木管五重奏曲
op. 74 (1935)
スヴェンド・シモン・シュルツ(1913-98):
木管五重奏のための小セレナーデ「アムレット」
(1943) |
カリオン(木管五重奏団):
【ドーラ・シェレシュ(Fl)
エギルス・ウパトニエクス(Ob)
エギルス・シェーフェルス(Cl)
ダヴィド・M.A.パルムクヴィスト(Hr)
ニルス・アンデルス・ヴェドステン・ラーセン
(Fg)】 |
ニールセン生誕150 年記念!ニールセンの木管五重奏曲とそれに影響された作品集!
このディスクには生誕150 周年を迎えるデンマーク人作曲家カール・ニールセンの木管五重奏曲とニールセンに影響を受けた3
人の作曲家による世界初録音の作品が収録されている。
ニールセンの木管五重奏曲は彼の作品の中でも最も革新的で洗練されたものの一つで、旋律と伴奏といった従来の構造を捨て去り、よりバランスの取れた実験的なスタイルを探るため、様々な楽器を組み合わせることで、豊かな響きを創造した。
デンマークのアンサンブル「カリオン」の生演奏は、空間的な位置が作り出す音響を利用して作品を具象化している。すなわち、目立った旋律を演奏する場合には一歩前に出て緻密なサウンドを作り出し、それ以外の楽器は一歩後ろに下がったり一列に並んだりすることでまとまりのあるコラールを形成するのだ。この作品における興味深く非常にユニークな解釈である。
3 曲の世界初録音はシュルツの一種独特であるが叙情的な「アムレット」、カラフルで多彩なエンボルグ、空想的で親しみやすいセンティウスの作品により構成されている。
※ご注意!特典DVDはPAL方式のため通常の日本のDVDプレイヤーでは見ることはできません。 |
| |
|
|
「ゴーン・イントゥ・ナイト・アー・オール・ジ・アイズ」
トーマス・コチェフ(b.1988):
gone into night are all theeyes
(2013、世界初録音)
エリック・モー(b.1954):We
Happy Few
レオン・キルヒナー(1919-2009):ピアノ三重奏曲
チャールズ・アイヴズ(1874-1954):ピアノ三重奏曲 |
トリオ・アパッショナータ:
【リディア・チェルニコフ(Vn)
アンドレア・カサルビオス(Vc)
ロナルド・ロリム(Pf)】 |
4世代に渡るアメリカのピアノ三重奏曲作品集
録音:2013 年8 月7-10 日、オクタヴィアン・オーディオ,75’36 ※日本語解説つき
ブラジル、スペイン、アメリカ出身のアーティストで構成されるトリオ・アパッショナータは、ピーボディ音楽院(アメリカ)の学生時代に結成された。アメリカ音楽の遺産に敬意を表して、4
世代に亘るアメリカ人作曲家のアンサンブル作品を1
枚のディスクに収めた。
コチェフのこの作品はこのアルバムのために委嘱したもので、タイトルはホルヘ・ルイス・ボルヘスの詩集Poems
of the Night の冒頭の一節から引用されている。エリック・モー(b.1954)のWeHappy
Few は作曲家自身の持論を反映したタイトルである。「室内楽における逆説的経済的アート。減らすと増える。」と言うものだ。
シェーンベルクの弟子として最初のアメリカ人であるレオン・キルヒナー(またはカーシュナー)のピアノ三重奏曲(1954)は、それまでのロマン派的表現の仕方を最もよく踏襲している。
アイヴズ作品の第1 楽章は哲学の父が語りかけてくるような非常に意識の高い真面目な印象。対して第2
楽章のタイトル「TSIAJ」は'This
Scherzo Is
A Joke(このスケルツォはジョークです)’の頭文字をとったものである。
最終楽章ではまたシリアスなトーンに立ち返り、最後はミュージカル『ロック・オブ・エイジズ』に登場する賛美歌で閉じている。予期していた解決和音は寸止めされ、夜想的な空間が戻ってくる。 |
.
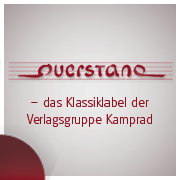 QUERSTAND QUERSTAND
|
|
|
アンネ・シューマン
「ビーバー(1644-1704):ロザリオのソナタ
第2集」
ハインリヒ・イグナツ・フランツ・フォン・ビーバー:
ロザリオのソナタ 第2集 (第6番〜第10番)
パッヘルベル:シャコンヌ ニ短調 |
アンネ・シューマン(バロックVn)
セバスチャン・クネーベル(Org) |
鄙びた味わい!ベテラン・ピリオド楽器奏者アンネ・シューマンのビーバー:ロザリオのソナタ第2集・第3集
録音:2007 年8 月 カルテンレングスフェルト教会、45’10
ビーバーの名作「ロザリオのソナタ(ローゼンクランツ・ソナタ)」第2集。17世紀の偉大なヴァイオリニストであり作曲家だったビーバーの最高傑作。聖母マリアへの祈りを表した15のソナタに無伴奏の“パッサカリア”からなる大作。“スコルダトゥーラ”と呼ばれる調弦を変えて演奏する技法の難曲です。
この第2集は『受難』。
ヴァイオリンのアンネ・シューマンはヴァイマールとドレスデンで学び、1989
年にライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団のヴァイオリン奏者として活動を始めます。その後ピリオド楽器奏者に転向し、イングリッシュ・バロック・ソロイスツや、クールザクセン・カペレ・ライプツィヒなどで活躍しています。 |
| |
|
|
「ビーバー(1644-1704):ロザリオのソナタ 第3集」
ハインリヒ・イグナツ・フランツ・フォン・ビーバー:
ロザリオのソナタ 第3集 (第11番〜第15番、パッサカリア)
ブクステフーデ:シャコンヌ
ホ短調 BuxWV
160 |
アンネ・シューマン(バロックVn)
セバスチャン・クネーベル(Org) |
録音:2007 年8 月 カルテンレングスフェルト教会、63’09
ビーバーの名作「ロザリオのソナタ(ローゼンクランツ・ソナタ)」第3集。この第3集は『復活』。
そのあとに秘密の名曲「ブクステフーデ:シャコンヌ」
が収録されているのも魅力です。
第1集 |
|
|
「ビーバー:ロザリオのソナタ(ローゼンクランツ・ソナタ)集第1集」
(1)フリーデルハウゼン教会の鐘の音
(2)ビーバー(1644-1704):ロザリオのソナタ第1集(ソナタ第1番〜第5番)
(3)ブクステフーデ:オルガンのためのパッサカリア
ニ短調BuxWV.161 |
アンネ・シューマン(バロックVn)
ゼバスチャン・クネーベル(Org) |
鄙びた味わい!ベテラン・ピリオド楽器奏者アンネ・シューマンのビーバー:ロザリオのソナタ第1集
録音:2007 年8 月フリーデルスハウゼン、40:24
ビーバーの名作「ロザリオのソナタ(ローゼンクランツ・ソナタ)」全3集から第1集を収録しています。
ビーバーの前に教会の鐘の音、後にはオルガン独奏作品を収録するなど雰囲気豊かな味わい深い1枚になっております。
ヴァイオリンのアンネ・シューマンはヴァイマールとドレスデンで音楽を学び、1989
年にゲヴァントハウス管弦楽団の奏者としてキャリアをスタートしました。その後古楽に魅せられピリオド楽器奏者に転向しています。
このアルバムでも鄙びた哀愁のあるバロック・ヴァイオリンが味わい深いです。

|
|
| |
|
|
詩集「子供の不思議な角笛」の歌曲〜マーラー、ヴァイスマン |
フラウケ・メイ(メゾ・ソプラノ)
ベルンハルド・レンツィコフスキー(ピアノ) |
CD1
1.マーラー:三人の天使がやさしい歌を歌ってた
(「子供の不思議な角笛」より)/
2.ヴァイスマン:Das Rautenstrauchelein
Op.53-2/
3.マーラー:死んだ少年鼓手
(「子供の不思議な角笛」より)/
4.マーラー:少年鼓手 (「子供の不思議な角笛」より)/
5.マーラー:シュトラスブルクの砦に
(「若き日の歌」より)/
6.ヴァイスマン:シュトラスブルクの女の子Op.41-2/
7.マーラー:歩哨の夜の歌 (「子供の不思議な角笛」より)/
8.マーラー:この歌を作ったのは誰?(「子供の不思議な角笛」より)/
9.ヴァイスマン:小さなフクロウOp.41-5/10.マーラー:別離(「若き日の歌」より)/
11.マーラー:天上の暮らし/12.ヴァイスマン:警告Op.29-1/
13.ヴァイスマン:夕べの歌Op.29-4/14.ヴァイスマン:横たわる吟遊詩人を埋葬するOp.41-1/
15.マーラー:魚に説教するパドゥアの聖アントニウス(「子供の不思議な角笛」より)/
16.マーラー:悪い子を良い子にするには(「若き日の歌」より)/
17.マーラー:不幸中の慰め(「子供の不思議な角笛」より)/
18.マーラー:むだな骨折り(「子供の不思議な角笛」より)/
19.マーラー:たくましい想像力(「若き日の歌」より)/20.ヴァイスマン:遅延Op.23-4
CD2
1.マーラー:この世の生活(「子供の不思議な角笛」より)/
2.マーラー:原光(「子供の不思議な角笛」より)/3.ヴァイスマン:秘密Op.29-8/
4.マーラー:ラインの伝説(「子供の不思議な角笛」より)/5.ヴァイスマン:亡命Op.29-1/
6.ヴァイスマン:Soldatengluck
Op.41-4/7.マーラー:それ行け!(「若き日の歌」より)/
8.マーラー:高い知性を賛える(「子供の不思議な角笛」より)/
9.マーラー:うぬぼれ(「若き日の歌」より)/10.ヴァイスマン:Sauberliches
Magdlein Op.41-3/
11.マーラー:もう会えない!(「若き日の歌」より)/12.ヴァイスマン:アイ!アイ!/
13.マーラー:塔の中で迫害されている者の歌(「子供の不思議な角笛」より)/
14.マーラー:私は緑の森を楽しく歩いた(「若き日の歌」より)/
15.マーラー:夏に小鳥はかわり(「若き日の歌」より)/
16.マーラー:美しいラッパが鳴りひびくところ(「子供の不思議な角笛」より)/
17.ヴァイスマン:聖なる子守歌Op.29-7/18.ヴァイスマン:せむしのこびとさんOp.29-5/
19.ヴァイスマン:野外の子守歌Op.53-3/20.ヴァイスマン:ある老いた女中の子守歌Op.53-1/
21.ヴァイスマン:子守の時計Op.29-3/22.ヴァイスマン:朝の歌Op.54-1/
23.ヴァイスマン:太陽の歌Op.53-4 |
マーラーとヴァイスマンの子供の不思議な角笛からの歌曲
録音:2007年〜2014年 CD1:73’56/CD2:68’43
ドイツのマザーグースと呼ばれる「子供の不思議な角笛」はドイツの民衆歌謡の詩集で、アルニムとブレンターノによって約600
編の民謡が収集され、1806〜08
年に3 巻出版されました。この詩集は、多くの作曲家が取り上げ、その中でも有名なのはマーラーの12
曲からなる歌曲集「子供の不思議な角笛」。マーラーは、歌曲集「若き日の歌」でもこの詩集から作品を残しています。他にもメンデルスゾーン、シューマン、ブラームスなども取り上げています。このアルバムは、詩集を用いた歌曲を集めたもので、マーラーとドイツの作曲家ユリウス・ヴァイスマン(1879-1950)の作品を収録。ヴァイスマンはラインベルガー、ヘルツォーゲンベルク、トゥイレなどに作曲を師事。ドイツ・ロマン派の影響を受けながら、その当時の音楽性も反映された作品を数多く生み出しています。ヴァイスマンの作品はほぼ世界初録音です。注目。 |
| . |

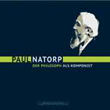
VKJK 1519
(2CD)
\4000 →\3690 |
科学の認識論的基礎付け、プラトン的イデア論に基く哲学、意志とイデアの陶冶による社会的教育学を説いた・・・らしい
「哲学者にして作曲家〜パウル・ナトルプ(1854-1924)作品集」
CD1
(1)ヴァイオリン・ソナタ 嬰ヘ短調
(2)チェロ・ソナタ ニ長調
CD2
(3)ピアノのための2つの幻想小曲集
(4)3つのプレリュードとフーガ
(5)ピアノ三重奏曲 ホ短調 |
(1)フローリアン・マイアロット(Vn)
(2)アレクサンドル・ヒュルスホフ(Vc)
(1)(2)ステファン・パーム(Pf)
(5)リュドミラ・フラヨノヴァ(Vn)
(5)ニコライ・シュガエフ(Vc)
(3)-(5)ユーリ・ファヴォリン(Pf) |
哲学者パウル・ナトルプの室内楽作品集
録音:2010 年、2011 年、CD1:75’48、CD2:71’39
「社会的教育学」の提唱者、ドイツの偉大なる哲学者であり教育者として有名なパウル・ナトルプ。なんと青年時代、作曲も学んでおり、その貴重な作品を録音したアルバムです。
ストラスブールでヤーコプスタールに師事。ブラームスに手紙でアドバイスをもらうなど本格的に学びました。ドイツ・ロマン派の、ロマンティックで情熱的な作風。
“2つの幻想小曲集”は、ユニークなメロディで独創的な作品です。ロマン派の“プレリュードとフーガ”といった趣の楽曲など、まさに知られざる作品ばかり!ドイツ・ロマン派がお好きな人はオススメです。
パウル・ナトルプ(Paul Gerhard
Natorp,
1854年1月24日 - 1924年8月17日
)は、ドイツの哲学者。
デュッセルドルフ生まれ。マールブルク大学の教授を務めた。
コーエンとともに、新カント派のマールブルク学派を形成。
科学の認識論的基礎付け、プラトン的イデア論に基く哲学、意志とイデアの陶冶による社会的教育学を説いた。
弟子にガダマー、ハルトマン、パステルナーク
またブランシュヴィックはナトルプの科学の認識論基礎付けに影響を受けた。
 ナトルプの言葉:「人間は、人間的社会によってのみ人間になる」 ナトルプの言葉:「人間は、人間的社会によってのみ人間になる」
. |
|
|
|
「ライ(プ)ツィンガー・アレルライ」
〜ファゴット四重奏編曲集(ドミニク・シュルツ編)
ワーグナー:「ローエングリン」第3幕への前奏曲
ベートーヴェン:交響曲第5番
ハ短調 Op.67
メンデルスゾーン:弦楽のための交響曲第7番ニ短調
MWV N7 |
ライツィンガー・バスーン四重奏団:
【ダーヴィト・ペーターゼン(Fg)
テオドール・ナウモフ(Fg)
ドミニク・シュルツ(Fg,コントラFg)
カール・フェンツレット(Fg)】 |
ファゴット四重奏によるローエングリンに運命?!
録音:2015 年1 月31 日、2 月1
日、DDD、54'40
曲目だけ見るとオーケストラのCD
だが、すべてファゴット四重奏による演奏。どこか紳士然とした落ち着きのある曲調になっており、ファゴット好きでなくても面白く聞けるだろう。
アンサンブル名のライツィンガーとは、ドイツの高名なファゴット製作者シュテファン・ライツィンガーが作る楽器のこと。 |
| |
|
|
「夢と忘我」〜ウテ・プルッグマイヤー=フィリップ即興集
ラヴェルとスクリャービンの間
メシアンによるミニマリスト風な連想
夜の歌についての騒乱
エヴァンスの面影のあるオスティナート
混沌とした対話、引用、対比 |
ウテ・プルッグマイヤー=フィリップ(ピアノ) |
録音:2013 年5 月 ドレスデン、DDD、67'43
いずれも即興演奏。ウテ・プルッグマイヤー=フィリップは1962
年生まれのドイツのピアニスト。1986
年からドレスデン音楽大学で即興演奏を指導し、1993
年からは同大学のピアノ専攻およびピアノ即興演奏専攻の教授を務めている。 |
| |
|
|
「ルター」〜有名コラール集
バッハ:私たちの神は堅固な砦
BWV720/ヴルピウス:私たちの神は堅固な砦/
クレプス:高みにおられる神だけに栄光があるように/
ブクステフーデ:さあ来てください、異教徒の救い主よ/
バッハ:天の高みから BWV248/シャイン:天の高みから/
バッハ:これらは聖なる十戒
BWV 635/
シャイン:賛美を受けてください、イエス・キリストよ/
バッハ:私たちは唯一の神を信じます
BWV680/
バッハ:私たちは唯一の神を信じます
BWV681/
ヴルピウス:私たちに恵み深く平安を与えてください/
バッハ:私たちの主であるキリストがヨルダン川に来た
BWV684/
バッハ:私たちの主であるキリストがヨルダン川に来た
BWV685/
バッハ:深い苦しみから私はあなたに呼びかける
BWV687/
クレプス:天におられる私たちの神よ/クレプス:キリストは死の縄に縛られて/
パッヘルベル:キリストは死の縄に縛られて/
ヴァルター:私たちは人生の真っ只中で/クレプス:私たちは人生の真っ只中で/
ヴァルター:平和と喜びのうちに私は発ちます/
バッハ:私たちの救い主、イエス・キリストは死の縄に縛られて
BWV626/
コルトカンプ:主である神よ、私たちはあなたを讃えます/
バッハ:私たちは唯一の神を信じます
BWV680 |
フェリックス・フリードリヒ(Org)
ゲルト・フリッシムート(指揮)
ヴァイマール・フランツ・リスト音楽院室内合唱団
ゼバスティアン・ゲリング(指揮)
ミヒャエルシュタイン室内合唱団
クリスティアン・スコボフスキー(指揮)
フライベルク大聖堂少年聖歌隊
オーパス4(トロンボーン四重奏)
ライナー・ゲーデ(Org)
ジャン・フェラール(Org)
ウルリヒ・ベーメ(Org)
クリストフ・クルマッハー(Org)
ライプツィヒ愛好・教会合唱団、
ライプツィヒ金管コレギウム |
DDD、60'47
VKJK9602 、VKJK0106 、VKJK0719
、VKJK0516
、VKJK1427 、VKJK0219 、VKJK9506
、VKJK0202、VKJK0603、VKJK0007
からの寄せ集め。オルガンもしくは合唱によるコラール集。 |
 STRADIVARIUS STRADIVARIUS
|
|
|
「ほとんど矢筒」〜マルコ・モミ(b.1978)作品集
イコニカII(2008)〜2Vn,Va,Db,Sax,2Perc,Prepared
pf
イコニカIV(2010)〜弦楽三重奏,Fl,Cl,Prepared
pf,Elec
2つのヌード(2013)〜無伴奏Va
ホックス・オン・ベケット(2003)〜Vn,Va,Ob,B.Cl
E.P.のための「ほとんど矢筒」(2011)
〜Fl,Ob,Cl,
弦楽三重奏,Perc,Pf
ルディカIII(2012)〜弦楽三重奏,Fl,Pf,3群の子供グループ,Elec |
サンドロ・ゴルリ(指揮)
ディヴェルティンメント・アンサンブル |
これはお薦め!清冽で美しい音楽はまさに新時代のフェルドマン!
録音:2013 年5 月12 日ミラノ,68:19
マルコ・モミは作曲をファビオ・チファリエロ・チャルディ、イヴァン・フェデーレに師事した後、パリのIRCAM
でコンピュータ音楽の研究を積みました。
作品は既にアンサンブル・モデルン、アンサンブル・アンテルコンタンポラン、バング・オン・ナ・カンなど多くの団体によって取り上げられており、いずれも静けさの中にぽつりぽつり、ぴゅ・ぴゅ・ぴゅ、ころころ、ひょろひょろ、と雨粒が落ちるような点描的で繊細な音響がこれといったクライマックスもなく延々と続くもの。しかし、ひんやりとした硬質の響きが耳元で涼しげに響いて心地よく、さながら水琴窟を聴いているようです。ルディカIII
は可愛らしい子供たちの語りと歌が時々入るチャーミングな作品。アンビエントとしても楽しめるのでお店の試聴機に入れたらセールスが期待できます。 |
| |
|
|
「シモーネ・ザンキーニ・ジャズ・カルテット」
〜ライヴ・イン・ラヴェンナ音楽祭
幸運、オリーブの木の下で、
ロマーニャとサンジョヴェーゼ、
マリエッタ、私の家で、ロマーニャ・ミア |
シモーネ・ザンキーニ
(アコーディオン、エレクトロニクス)
ステファーノ・ベネディッティ
(テナー&ソプラノsax)
ステファーノ・センニ(ベース)
デノ・デ・ロッシ(ドラムス) |
録音:2013 年7 月1 日ラヴェンナ(ライヴ)
72:58
シモーネ・ザンキーニはイタリアのアコーディオン奏者でジャンルとしてはジャズに分類されるが現代音楽とのコラボレーションも多い。
ここに収められた作品は古色蒼然とした昔風のダンス音楽からファンク、フリー・ミュージック、ライヴ・エレクトロニクスを使用した実験的な作品まで作風は多種多様。なお本年12
月5 日、大阪で行われるイタリア芸術フェスティバルにタンゴ・イ・アルゴ・マス・トリオの一員として出演のため来日しバルトーク、ピアソラ、ジスモンチのほか自作を演奏する予定。 |
 TUDOR TUDOR
|
|
|
「ブリリアント・ブラス」
トーマス・ガンシュ:5つの艦隊
ヴィクトル・エヴァルド:金管五重奏曲第1番
変ロ短調
ヨーゼフ・ランナー(マリアンヌ・ブルックナー編):シュタイアー風舞曲
マルコム・アーノルド:金管五重奏曲Op.73
ヴェルナー・ピルヒナー:金槌をポケットに持った男
|
ウィーン=ベルリン・ブラス・クインテット:
【ガボール・タルコヴィ
(トランペット/ベルリン・フィル首席)、
ギョーム・ジェル(トランペット/ベルリン・フィル)
トーマス・イェプストル(ホルン/ウィーン・フィル)、
ディートマル・キューブルベック
(トロンボーン/ウィーン・フィル首席)、
アレクサンダー・フォン・プットカマー
(テューバ/ベルリン・フィル)】
|
12月に来日決定!ウィーン=ベルリン・ブラス・クインテット、定番のエワルド、アーノルド収録!
録音:2014年5月 シンフォニア・スタジオ(ウィーン)、56’42
管楽器ファン、大注目のアルバムがリリース。世界的ソリストとしても活躍する5
人が、オーケストラという枠を超えて結成した「ウィーン=ベルリン・ブラス・クインテット」。ベルリン・フィル、ウィーン・フィルのメンバーによる世界最高峰の響きを堪能できます!
コンクールの定番“エヴァルドの金管五重奏曲第1番”や、“アーノルドの金管五重奏曲”など、最高の演奏で聴く金管五重奏曲はまさに極上の時間。2015
年12月に来日公演を予定しています。 |
| |
|
|
腕っこき集団シャロウン・アンサンブル
「ドヴォルザーク:室内楽作品集」
バガテルOp.47 B.79
テルツェット(三重奏曲) Op.74
B.148
弦楽五重奏曲第2番 Op.77 B.49 |
シャロウン・アンサンブル・ベルリン
【ヴォルフラム・ブランドル(ヴァイオリン)、
レイチェル・シュミット(ヴァイオリン)、
ミシャ・アフカム(ヴィオラ)、
リチャード・デュヴェン(チェロ)、
ペーター・リーゲルバウアー(コントラバス)、
ヴォルフガング・キューン(ハーモニウム)】 |
腕っこき集団シャロウン・アンサンブルによるドヴォルザークのレアな室内楽曲集!
録音:2013年5月〜6月、69’35
1983 年ベルリン・フィルのメンバーによって設立されたシャロウン・アンサンブル・ベルリン。現在はドイツの主要なオーケストラに在籍するメンバーで構成されています。
ヴァイオリンのブランドルは10
年間ベルリン・フィルで活躍。現在ベルリン国立歌劇場管弦楽団のコンサート・マスターを務めている実力派です。
ドヴォルザークのユニークな編成の室内楽作品を収録。「バガテル」は2
本のヴァイオリン、チェロとピアノの代わりにリードを用いたオルガン“ハーモニウム”を用いた作品。
「テルツェット(三重奏曲)」はヴァイオリン2
本とヴィオラ。「弦楽五重奏曲第2
番」は弦楽四重奏+コントラバスの編成。シャロウン・アンサンブル・ベルリンはドヴォルザークの民俗色を洗練された演奏で楽しませてくれます。
「シャロウン・アンサンブル」
★ベートーヴェン:七重奏曲、管楽六重奏曲
★シューベルト:八重奏曲
TUDOR 各1SACD¥2400→¥2190
シャロウン・アンサンブル・ベルリンはベルリン・フィルハーモニーの首席奏者が集まって1983年に結成された。レパートリーは古典から現代まで幅広く、アバド、バレンボイム、ラトルとも共演している。
ヴァイオリンのブランドルは現在ベルリン国立歌劇場管弦楽団のコンサート・マスターを務めている |

TUDOR 7146
(SACD HYBRID)
\2190 |
ベートーヴェン(1770-1827):
(1)七重奏曲 変ホ長調Op.20
(2)管楽六重奏曲
変ホ長調Op.71 |
シャロウン・アンサンブル・ベルリン:
【(1)W.ブランドル(Vn)、(1)M.アフカム(Va)、
(1)R.デュヴェン(Vc)、
(1)P.リーゲルバウアー(Cb)、
(1)(2)A.バーダー(Cl)、
(1)(2)M.ヴァイトマン(Fg)、
(1)(2)S.d.L.
イェツィエルスキ(Hrn) 】
(2)G.V.ブオノマーノ(C
lII)、
(2)S.ウィリス(Hrn
II)、(2)H.トロック(Fg II) |
| 録音:(1)2008年10月,(2)2009年5月,ベルリン |

TUDOR 7114
(SACD HYBRID)
\2190 |
シューベルト(1797-1828):
八重奏曲 ヘ長調Op.166,D803(1824) |
シャロウン・アンサンブル・ベルリン:
【P.ガイスラー(Cl)、K.トゥーネマン(Fg)、
S.d.L.イェツィエルスキ(Hrn)、
A.カッポーネ(Vn)、A.イヴィッチ(Vn)、
U.クネルツァー(Va)、R.デュヴェン(Vc)、
P.リーゲルバウアー(Cb)】 |
録音:2001年6月
音質の向上により、より声部間の細やかなやり取りが鮮明に聴き取れるように。 |
|
|
| |

TUDOR 7601
(2枚組 1枚価格)
\2400 |
「シューベルト:ピアノ三重奏曲全集」
CD1)
ピアノ三重奏曲第1番変ロ長調
作品99 D898
ピアノ三重奏曲変ロ長調 D28
CD2)
ピアノ三重奏曲第2番変ホ長調
作品100 D929
ピアノ三重奏曲変ホ長調「ノットゥルノ」作品148
D897 |
モスクワ・ラフマニノフ三重奏団:
【ミハイル・ツィンマン(Vn)、
ナタリア・サヴィノヴァ(Vc)、
ヴィクトール・ヤンポルスキー(Pf)】 |
モスクワ・ラフマニノフ三重奏団円熟のシューベルト!
録音:2013年8月モスクワ/CD1:52’33/CD2:56’25
シューベルトはピアノ三重奏曲を生涯で4
曲残しました。D.28
は15 歳の時の作品。残りの3曲は晩年に作曲しています。「第1
番」と「第2 番」は長大で晩年の傑作として名高いもの。美しいメロディの中から訪れる絶望の影。シューベルトの深淵な音楽がここにある。
モスクワ・ラフマニノフ・トリオはロマンティックで喜びに溢れ、穏やかな気分を存分に表現した演奏を繰り広げています。 |
 ZKP RTV SLOVENIJA ZKP RTV SLOVENIJA
|
|
|
サショ・カラン(b.1974):バレエ《トリスタンとイゾルデ》 |
マルコ・ガシュペルシッチ(指揮)
スロヴェニア国立歌劇場管弦楽団
サショ・カラン(エレクトロニクス) |
トリスタンとイゾルデですがワーグナーではありません
録音:2014 年7 月8-10 日(オーケストラ録音)、2014
年10 月30 日初演、71:16
作曲者のサショ・カランはカナダ、モントリオール出身で後にスロヴェニアの首都リュブリャーナに移住し創作活動を続けている。サウンド・エンジニアリングの研究を修めた彼は電子音楽によるバレエやフィルムのための作品が多い。2014
年にスロヴェニア国立劇場で初演された「トリスタンとイゾルデ」は全編アンビエントもしくはミニマルといった雰囲気でフィリップ・グラス、ハロルド・バッドあるいはブライアン・イーノを思わせる。
アヴァン・ポップ、エレクトロニカの好きな人におすすめ。 |
![]()